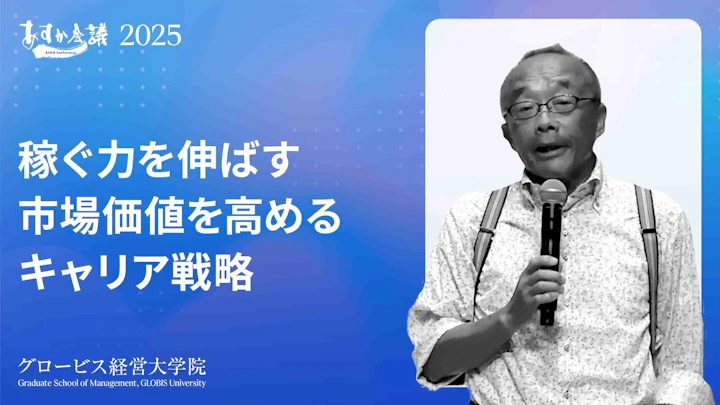木村:本セッションは「企業再生の要諦と落とし穴」というテーマで進めていきます。
昨今は100年に1度の経済危機ということで、「再生」という言葉がクローズアップされています。ニュースなどで取り上げられる、GMやクライスラーのような世界的な大企業だけではなく、国内のごく小さな会社での再生もたくさん行われているはずです。今日は、実際にそうした企業再生の現場に長年携わってきたお三方に集まっていただきました。一言に再生といっても、関わるステージや関わり方は様々です。そこで自己紹介を含め、まずはどういった立ち位置で再生に携わってきたのかからお聞かせください。
再生の成功確率は、決して高くない(尾関)
尾関:私は今、グロービスで「ストラテジック・リオーガニゼーション」というクラスを担当しています。中には既に私のクラスを受講して、同じような話を聞いている方もいるかもしれませんが、そのあたりはご容赦ください。
再生に関して私の立ち位置は3つに収斂されます。1つは、経営の本質は、それが再生の局面であろうが、そうでなかろうが、そんなには変わらないということ。経営に携わっていく中で、自分のやり方、考え方、哲学が出来上がってくるので、それをもう少し知恵を使って実行する。そういうスタンスが大切ではないかと思います。そして2つ目は覚悟。経営者としての覚悟が特に再生の場面においては重要です。最後は、何をもって成功とするかを最初に自分で見定めておくこと。再生の成功確率は、決して高くはありません。ですから、これを決めておくのが肝要なんです。
永沢:まず、本セッションの「企業再生の要諦と落とし穴」というタイトルですが、私は正直言って違和感があります。再生するべきは、「事業」であって「企業」ではないのではないか。企業を甦らせるのが我々の仕事ではなく、その中にある事業を立ち直らせるのが我々のミッションです。私は弁護士なので法律的な仕事をしていると思われがちですが、弁護士の資格は管財人になるために取りました。仕事の半分以上はおよそ法廷とは縁のない、事業再生の現場にあります。
私は栃木県足利市の材木屋の倅として育ちました。高校は、東京の私立校に進学したのですが、同級生のお父さんが勤めていた興人というパルプ会社が、忘れもしない1975年8月29日に倒産したのです。負債額は約2000億円。戦後最大の倒産と言われました。
「倒産」というと、私の育ってきた環境からすると、即ち「夜逃げ」というようなイメージがあったので、「2学期にはその同級生はもういないだろう」「私立高校に通うのはもう難しいだろう」と思っていたら、夏休み明け初日の9月1日から彼は学校に登校してきたんですね。しかも割と元気がいい。そこで、どうも会社更生法という法律があって、都心の社宅もそのまま住み続けられるらしい。若い弁護士が来て采配を振るっているなんていう話を、小耳に挟みました。会社更生法という法律があることも、管財人という仕事があることも、そのとき初めて知ったのです。そうであれば法学部に進んで、弁護士になるのも悪くないな、と思いました。
その後これまで、保険会社やゼネコン、ホテル、ゴルフ場などの再生をしてきました。最近では例えば、突然に破産した、あるアパレル上場会社の破産管財人を務めています。破産したのだからもう企業再生はあり得ないわけですが、ブランドとしてはまだ残っているものがあって、それを別な会社に事業譲渡する仕事に取り組んでいるところです。また例えば、ゼネコンの上場会社に会社更生法を適用し、DIP型手続きと言って、債務者となる経営者がそのまま残って経営再生をするやり方の法的なアドバイザーもしています。あるいは食品会社の民事再生の申し立てもしています。事案によって様々なステージがありますが、基本的には「瀕死期」から「止血期」の中で法的な対応をして、「再成長期」にバトンタッチをしていくというのが、私の立ち位置です(下図を参照)。
木村:「企業の再生ではなく事業の再生」という、非常に良い言葉をいただきました。私自身も自分の仕事を通じあくまでも事業を守るための再生が重要だと常々感じています。では林さん、お願いします。
林:私は、プライベートエクイティの仕事を始めて、今年で11年になります。
プライベートエクイティは間口の広い経営の考え方をするんですけれども、最初の数年間、特に2003年ぐらいまでは、「企業再生」ないし「事業再生」が大きなテーマになってきました。その後、世の中の状況は良くなってきていたので、どうしたら投資ファンドとして「成長」をサポートできるのかを問われることが多くなりました。ところが昨年の後半からまた、「再生」がテーマになりました。
プライベートエクイティというのは、基本的に会社の経営権を人に渡して、そしてゴーイングコンサーンの危機を乗り切ることだと考えています。それから企業再生に対する関わり方という意味では、例えば尾関さんのように、再生企業のCFO(最高財務責任者)として現場で活躍するマネージャーの立場ではなく、企業再生のためのストーリーを描いて、そのために必要な経営リソースを集め、そこにお金をつけて、全体を進行させる。映画制作で言えば、プロデューサー的な仕事です。したがってこのセッションでは、経営への関与という意味では一歩引いた立場で、同じトピックについても異なる観点からの意見が出せればと思います。
木村:ありがとうございました。それぞれいろいろな角度から再生に携わっているパネリストの方々です。再生のフェーズとして、まず「混迷期」のところでP/L(損益計算書)、C/F(キャッシュフロー計算書)が落ちてきます。大方の会社では、こういうフェーズがあるでしょう。ここで苦境から脱することができなければ、その先にB/S(貸借対照表)まで痛んで、瀕死の重傷になって何がしかの手術をしなければならなくなると思います。それでは最初の質問です。こういった「瀕死期」に入って再生を要する企業の特徴をお伺いします。
破綻企業には必ず「大理石の法則」が当てはまる(永沢)
永沢:私が関与するのは破綻企業です。破綻企業の特徴的なものが何かあるかという点は、いつも考えています。私はこれを「大理石の法則」と呼んでいます。破産だろうが会社更生だろうが民事再生だろうが、破綻した会社には共通していることがあります。
それは、なぜか社長室が大理石でできているということ。大理石は象徴なのですが、いわゆる“ベンチャー崩れ”の若い社長であればフェラーリであったり、あるいは海外の保養所であったり、ホテル経営であったり、ゴルフ場であったり…。要は見栄だけのために役に立たないものに、お金を使っているということです。
たとえば、某破綻デパートの会長室も、大理石でできていました。私は縁があって、その地域店舗子会社の再生案件に携わりました。その店舗は開業以来大変な赤字続きですが、その中にも立派な大理石の会長室がありました。年に数回かしか来ない会長のために、大理石の部屋があるわけです。有価証券報告書の虚偽記載で上場廃止になった某鉄道グループの会長室も、大理石づくりでした。某生命保険会社も、某ゼネコンも、私が関与した限り、本当に社長室・会長室が立派なことこのうえないものばかりです。
これは従業員の目には、どのように映るでしょうか。社長がフェラーリに乗っていることが誇らしく思えるかというと、断じて誇りにはできないわけでして、「大理石」に金をかけるよりは、きちんとした生産設備に投資してほしいとか、従業員の処遇を改善して欲しいとか、経営資源の有効配分ができていないことの象徴が、「大理石」に他ならないと思っています。破綻企業には必ず「大理石の法則」が当てはまるというのが、私の持論です。
最大の特徴は危機感の欠如(尾関)
尾関:社内と社外で状況の認識にギャップがあります。社内の人たちは、状況を衰退期と捉えているが、客観的には既に瀕死期であるということが、往々にしてあります。まずは、これを見極めないといけません。社外からのほうが、実情がよく見えるということはあるんです。外から入っていくと、それまでの情報がないわけですから、かえっていろいろなものが見えてくる。
一つは大きな括りでいうと、産業再生機構のCOO(業務執行最高責任者)を務め、現在は経営共創基盤の代表取締役CEOの冨山和彦さんが本に書かれている言葉で、「合理と情理」というものがあります。別に新しい言葉ではありませんが、組み合わせが非常に面白いんです。言うなれば肉体と精神のうち、精神がかなり病んでいる。つまり人、ソフトの部分がかなり傷んでいるということが、まず原因です。
数字的なところでいうと、B/Sが汚い。また、仕事のオペレーションでいうと、人が辞めていくのでプロセスが歯抜けになっている。一応は誰かが仕事を引き継いでいるけど、引き継ぎがしっかりできていなくて、不完全で非効率的な仕事の進め方をしている。もう一つは、企業の経営が立ち行かなくなってくると、自分が可愛いので保身を考える。そうすると、仕事が個人個人で完結するようになる。つまり自分がいなくても回っていく状況を、わざと作らなくなってくる。そしてコミュニケーションが取られなくなって、情報も共有されず、さらに非効率になる。
そして何をおいても最大の特徴は、危機感の欠如です。人々は成功体験によって、仕事をしている。日本という国全体がそうかもしれませんが、老害がはびこっています。これが私の見る破綻企業の特徴です。
木村:「大理石の法則」とかいろいろ面白い話がありましたが、私の視点からすると、中小企業を含めたオーナー系の企業のパターンと、カネボウのような大企業で創業者一族はいなくなっているというパターンがあると思います。そのあたりの違いも含めて、どこが再生を要する企業の特徴でしょうか?
ガバナンスが構造的に崩れる(林)
林:まず「大理石の法則」はまさしくその通りですね。私の経験でもヘリコプター、ピカソの絵画、東山魁夷の絵画とか、事業に役立たない高価なものが必ずありました。
私は、プライベートエクイティの仕事には、企業に対する適切なガバナンスを設計して提供するという機能があると思っています。その観点からすると、再生状況に陥る企業は、長期にわたって構造的かつ継続的にガバナンスが崩れています。その結果として、判断を見誤るわけです。
オーナー企業については、以前、このあすか会議に(ユニゾン・キャピタルから、東ハト再生のために執行役員として同社に行った)後藤(英恒)さんが来て、東ハトでの事例をお話ししたかと思います。この会社は正真正銘のオーナー企業です。絶対的なオーナー経営者ですから、名君であるうちは素晴らしい。確かに創業者は素晴らしい人だったらしいんですが、代が替わって、安定的であまり労力をかけないでも儲かるような本業だけやっていても面白くないということで、趣味が高じてゴルフ場を作ってレディーストーナメントなどを開催し始めた(会場笑)。そういったことを始めたときに、社内に止める機能がないんですね。異議を唱えると、実際にクビになってしまうというような独裁的な環境が生じていた。組織の問題点を抽出するプロセスが破綻していたわけです。これが顕著な例ですね。
一方の同族経営ではない大企業では、支配株主がいない中で上場しているわけですが、きちんとした体制で企業経営が成されているのかというと、必ずしもそうではありません。上場している会社で、しかもオーナーが経営しているのではなくても、破綻危機に瀕するような会社は、支配株主がいないことによって、逆にガバナンスが機能しなくなり、事実上経営者が好き勝手できてしまう。それを止める役割を担う人が、これもまた社内にいなくなってくるし、主要株主の上位10に挙がってくる人たちというのは、基本的には取引銀行ないし取引先であったりするので、なかなか経営者の暴走を止められないわけなんです。
そういう意味で、上場していようがいまいが、あるいはサラリーマン経営者であろうがオーナー経営者であろうが、ガバナンスが構造的に崩れるとういうのが、実は普遍的に存在する危機なのだろうと思います。
木村:お三方の話に共通する点として、正しいことが正しく判断できなくなる、ということがありました。尾関さんの話にもあったように、大概においては、混迷期から気づかないうちに瀕死期に至ってしまい、皆さんが入っていかれるわけですが、再生するうえでのポイント、もしくはその裏返しになりますが、こうすると失敗するというところに話を移していきたいと思います。
従業員に背中を見せて、巻き込む(尾関)
尾関:再生の場面であろうと日常的な経営であろうと、経営の本質は変わらないという話を冒頭にしましたよね。再生にもプランニング、設計することが大切で、そのときのキーポイントは何かというと5Wです。
誰がといえば、当然まずは自分です。何をやるかというのは、いくつか出てきます。何をやるかを決めるときに大切なのは、再生戦略ではなくて戦術です。これを自分がやることもあれば、チームを作ってリーダーがやることもある。ただし、自分がやることも必ずないといけない。要するに従業員に背中を見せる。背中を見せることによって、周りの人を巻き込むことができる。人の心が病んでいるわけですから、それを元気にさせるためには、自分がやらなければならない。
私は、コロムビアというレコード会社の再生をしたことがありますが、その際に、私が、どうやって背中を見せたかというと、とにかく脇目も振らず、朝早くから夜遅くまで一所懸命仕事をしました。そうすると、誰かが気づいてくれるわけです。私の場合、誰が気づいたかというと、自社ビルの通用口にいる守衛さんたちでした。定年退職した元社員の守衛さんなので、よく会社のことが分かっている。その彼らが「今度の役員はよく仕事をする」と言ってくれたんです。それから「今度の役員はちょっと違う」と社員たちが気付いてくれて、それなりに我々のほうを向いてくれるようになった。背中を見せるというのは、そういうことなんです。
いつ、誰が、何をやるか。そこから大切なのがいつまでにやるか。そういうことを決めていく。
後はこれも経営の本質ですが、シンプルにやる。分かりやすくすることが大切です。2:8の法則というのは、こういう局面でも働くもので、10あるうちで重要な2は何かを考え、その2を優先して実行すれば全体が変わります。だからプランニングが重要なわけです。それから、どちらかというとライフル銃ではなく散弾銃なんです。散弾銃の弾は小さいので、当たってもそれぞれの影響力は小さいけれど、目に見えるようなヒットが社員の中に浸透していくと、段々と結果が見えてくるわけです。
木村:どんな立ち位置でも、再生される側の人間にとっては、お三方は「外部の人間」でしかないわけで、この壁を乗り越えなければいけないという部分もあると思います。その先入観や、現場の嫌悪感みたいなものを、いかにして乗り越えていくのか。それからもう一つは、今のお話で出てきた「クイックヒット」を、具体的にはどのようにして出すのか。この2点をお聞かせください。
あばたこそえくぼ(永沢)
永沢:管財人の仕事をするにあたって、ある先輩から教えていただいたことがあります。その先輩とは、三宅省三弁護士という、会社更生の世界では神様みたいな存在の人だったのですが、教えていただいたのは、保全管理人や管財人としていきなり会社に乗り込んでいくわけですが、「そのときに最初に近づいてくる奴には気をつけろ」ということでした。決して信用してはいけないということなんですね。これは今まで外れたことがないんです。
つまり我々が乗り込んだとき、玄関で出迎えていろいろと世話をしてくれる人。LAN回線の手配や机の手配をしてくれて、面倒を見てくれるそこそこ偉い人がいますが、そういう人は現場で信用されていないと見てほぼ間違いありません。
というのは会社が潰れたという一大事ですから、それぞれ現場の持ち場で、お客様に説明したり、あるいは債権者に対していろいろお願いをしたり、従業員をまとめたりというような、本当に大変な修羅場になっているはずなんです。なのに、自分の持ち場を放って、真っ先に管財人を迎えに行くという行為は、従業員からしたらいかにも優先順位が分かってない人にしか見えないわけです。
ですから、彼らを重用すると「やっぱり管財人も似たようなものなのか」と見られてしまいます。彼らは前経営者のときにもイエスマンで、処世術だけには長けていた人であることが多いので、ファーストコンタクトに気をつけることは、仕事を進めるうえで非常に役立っています。
それからクイックヒットという点では、「あばたもえくぼ」という諺がありますが、私は「あばたこそえくぼ」と言っています。この会社の悪い点が分かるんだったら、そこを直せば確実に良くなるんじゃないかということです。財務体質が悪かったのなら、会社更生により無借金になることで、それは改善されたということになります。あるいは役員が悪かったのなら、今回この手続きを取ることによって役員がいなくなったのだから、やはり良くなるはずです。
そして、これまでの経験から、現場から必ず良い人材が出てくるということを確信しています。そういった人が中心となって、それまで淀んでいた情報がクリアに伝わるようになれば、意思決定も早くなる。そこで何か小さいヒットが生まれれば、次のステップに進めるのではないかと思っています。
そういう意味では、東ハトの民事再生手続きをする中で、「暴君ハバネロ」という劇辛スナック菓子の新製品をヒットさせたのは、すごい成功事例ですね。それによって社員の士気も高まり、山崎製パンへの売却額が上がったと私は思っていますが、林さん、いかがでしょうか(会場笑)。
「共通敵」を作って内部に入っていく(林)
林:確かに、そうですね(笑)。
ただ、あれは特異な例だったと思います。事業の中で(暴君ハバネロのヒットのような)分かりやすい成功事例を出せれば、それは確かに理想的ですが、通常はそんなにうまくいかないですよね。企業再生ないし事業再生の初期の段階では、会社内部のことを優先して取り組む。経営管理の体制がまったくできなないところから、いかにしてお金の流れや情報の流れを見えるようにするかを考えて、設計し直します。ですから、なかなか新商品のヒットが出せるまでいかないことも多いのです。
一番大きい変化として顕在化できることがあるとすれば、情報の共有だと思います。再生のストーリーを従業員の末端にまで共有し、進捗を報告する。どんな再生案件であっても四半期ごとの進捗報告会を実施するようにしているのですが、ある会社で、「自分の会社の四半期の業績を入社来、初めて共有してもらえた」「自分の会社の利益が黒字化したのを初めてみた」と感激する声が上がっていました。やると言ったことが、きちんと行われていることを見せるだけでも、現場の雰囲気は変わります。情報共有はタダですから、情報資源が限られている中でこれを利用しない手はないですよね。
「外部の人間」として入っていって徐々に「内部の人間」となっていく過程では、こうした情報共有のプロセスを強力に進めていくことが一つ、非常に有効な手段として使えます。このほか単純ではありますが、「共通敵」を作るというのも戦術としては有用です。
我々がスポンサーになるとき、通常は新しい銀行借入のパッケージと併せてファイナンスをするので、その際には当然のことながら財務制限条項が課されます。したがって、事業の現場で行われているオペレーションとファイナンスをつないで、「銀行にはこう約束しているから、これは頑張ってやらなきゃいけない」と、ずるいんですが、我々の後ろにはもっと怖い銀行の人たちがいて、「銀行には迷惑をかけたでしょ。今度は迷惑をかけないようにするために、ここで頑張らなきゃいけない」というような打ち出し方をすることは、初期の段階で外部の人間が内部化するうえでは有効だと思います。
木村:皆さんはいかにして中に入っていくかということで、苦労されていると思います。企業の外部から内部に入っていて再生を果たす役割を担っていますが、こういった状況に陥ったとき、企業の内部の人間としてできることはどんなことがあるのでしょうか?
抵抗勢力になるな(尾関)
尾関:一言で言うと、自分が抵抗勢力にならないようにすることではないでしょうか。心理的にそうなりがちなことは否めませんが、グロービスで学んで経営に携わる志がある限り、抵抗勢力にならないように努力をしなければならないですね。
人は必ず何かいいところを持っているし、仕事を長年続けていれば自分に出来ることが会社の中で必ずあるわけです。だから、外から入っていったときには、そんな目で人を観察しています。
それから、もちろん再生はタイムリーに行わなければなりません。3カ月や半年という短いタームの中でやっていくわけですが、その一方で拙速であってはならないんです。特に人に対して、拙速にならないこと。冒頭で老害の話をしましたが、老害というものは肉体的な年齢ばかりではなく、精神面での老害もあって、私の経験からいうと、30代が老害になっていることが非常に多い。逆に定年間際の50代半ばに差し掛かった寡黙で真面目な人が、数は少ないですけど、貴重な情報をたくさん持っていることもあります。そういう発見があるので、人に対して拙速にならないようにしています。
現場からの声をどれだけ集められるか(永沢)
永沢:現場の方からの提案をどう扱うかということも大きなポイントになります。現場の提案というのは必ずしも正解ではありません。そして、「それはもう検討済み」だとか、論理的に打ち負かすことも難しくない。けれど、あえて受け入れて、試してみることも大切です。
私が、とあるホテルの管財人を務めたとき、客室の白熱電球を蛍光灯に替えたほうが経費の節減になるのではないか、という現場からの提案がありました。しかし、白熱球型の蛍光灯は長い間つけていれば同じ照度になるとしても、つけてからしばらくは暗いんですね。でも、そう言ってしまうともう提案が来なくなると思ったので、ある客室だけ蛍光灯に替えたところ、やはりお客さんから「入った瞬間に暗い」という苦情があったということで、結果的には白熱電球に戻したんです。
ただ、「現場からの提案をすぐに実行に移してくれた」ということで、その後、他の提案が来るようになりました。面白い提案がいろいろあって、奥深いものだと思いました。提案を積極的に出させる風土を作るためには、下からの現場の声をどれだけ潰さずにやらせてみるか、ということではないかと思っています。
再生といっても特別のことをするわけではなく、当たり前のことを当たり前にやるということ。これまでできていなかったことが問題なので、それを一つ一つクリアしていくことが大切です。自分がスーパーマンのように、「自分のプラン通りにやれば、必ず会社は良くなる」と押し付けるのでは事業再生は難しいのではないでしょうか。むしろ、現場で持っている情報をいかに集めて、改善していくか。こうした戦術を積み重ねが、とても大きいと思います。
内部化のプロセスをあえて演出する(林)
林:誰が考えても正しいということが行われないというのは、ガバナンスが崩れている状況なんですよね。内部の人間として再生に携わるという場合は、いかに最初に自分を外部の人間として登場させて、そこから意図的に内部化のプロセスを演出するかということが、ポイントではなかろうかと思います。
永沢さんのお話にもあった通り、話を聞くというプロセスは、不安がある中でのマネジメントとして非常に重要でしょう。そういう意味では、外部の人間が来るのはとても不安なわけですが、そこからやりとりを進めていく中で、同一化していくということです。外部の人間なら否応なくこれをやらざるを得ませんが、内部の人間としてそういう状況に置かれるのであれば、むしろ「自分は全然分からないから、どうしてこうなっているのか教えてくれ」というように質問を発しながら、まずは外部の人間としてそこに登場し、そこから同一化していくことを意図的にやることが、とても有効ではないかと思います。
尾関:内部の立場からということで、一つ付け加えたいことがあります。それは、女性の方は自分の能力に自信を持ってそういう場面で立ち上がる。男性はそういう場面では、女性の力を利用するべきだということです。女性の幹部の比率を高めることが、強い力になってくると思いますね。
そういう意味では、日本の女性が自信を持っていないことが、非常に気になります。もっと自信を持っていいと思っています。クラスでよくやることは、議論が詰まってくると女性にあてるんですね。そうすると女性から意見が出てきて、また議論が盛り上がってくることがあります。女性は発言しないけどいろいろ考えていて、きちっとした意見を持っていることが多いし、本質的に男性より女性のほうが真面目です(会場笑)。
木村:逆に落とし穴みたいなところがあって、私の経験から言えば、債権者としての金融機関は長期的な目線から将来的な成長の芽を育むことよりも、現在のキャッシュの方に目が向くものだと思います。会社側として、例えば設備投資を抑制するとか、経費を削減するのは当然なのですが、将来に向けた芽まで摘んでしまってはいけない。そのあたりの落とし穴についてはいかがですか。
「手術は成功しても、患者は死亡」では難しい(永沢)
永沢:それを、よく我々は「手術は成功したけど、患者は死んじゃった」という言い方で表現します。つまり、財務は改善し、従業員は削減して、後は売上を上げれば健全な会社に戻れる。でも何の夢、理念もないような会社に、優秀な社員が目標を共有してくれるかといえば、なかなか難しい。
かつて「Hoxy」というティッシュペーパーを作っていたホクシーという企業がありました(現在は合併により王子ネピアに。Hoxyブランドの製品は今も販売されている)。大手に伍していたこの企業は、会社更生を経て、設備投資を削って、古い設備でチマチマとやって、結果的には二番手グループから脱落してしまいました。
一方で同じような会社更生を経ても、「エリエール」ブランドの大王製紙は、設備投資をどんどんやり続けて、今ではクリネックスやネピアに堂々と伍しています。エリエールとHoxyを比較すると、エリエールの方がはるかに上ですよね。
我々の役割を考えたとき、臨床医として手術を成功させることは、もちろんとても大事なんですけれども、同時に活力を削いでしまってはいけません。そういう点では、何かシードを残しておくことが重要なことです。
ニセの自己満足、ニセの危機感が一番怖い(尾関)
林:また東ハトの話に戻りますが、私たちが再生で入っていくまでは、お菓子の事業から出てきたキャッシュフローを、すべてゴルフ場建設につぎ込むという、安定したサイクル(笑)が社内に確立していました。同時に、私たちが最初に工場を見学したときは、消防法違反や衛生上の問題が生じていました。ゴルフ場建設などにキャッシュが回る反面、本業の工場などへの設備投資は、最小限に抑えられていたわけです。そこを何とか、現場の人たちのマンパワーと気合で、大きな事故が起こらないようにしている状況でした。
我々が関わって以降は、想定外の相当なお金をつぎ込んで、工場として安全で安心できる操業環境を作りました。これは直接的な利益を生むわけではなく、キャッシュが出て行くだけの話なのですが、山崎製パンの社長が買収の際、開口一番「この工場は素晴らしい」と言ってくれました。我々が初めて工場を見に行ってから、3年後のことです。
見た目のEBITDAは同じなんですが、キャッシュフローのクオリティが、格段に高いものに変わっていた。そういうところが、価値を生むのだろうということです。まったく利益を生まないことでも、投資はしなければいけないと思います。次のオーナーに渡すまで「ファイナンシャルモデル的には無駄だから」と何もしなかったら、結局は企業再生というプロセス自体もうまく回らなかったと思います。
尾関:先ほど危機感が大切と申し上げましたが、ニセの危機感はダメですね。例えば、まず再生で最初にやることはコスト削減ですよね。コストの中で一番高いのは人件費です。ところが、ニセの危機感に基づいて活動をし始めると、交通費・接待費を削減することになります。でも皆さんご承知のとおり、全経費のうち交通費・接待費の割合を考えれば、大してインパクトのある削減にはなりません。
これをやっていれば、何となく努力しているようにな気になる、という自己満足、ニセの危機感が再生では一番怖いですね。だから経営者は常に先を見る視点が必要だし、これをやると決めたことは必ずやり遂げなければなりません。
木村:やはり最初にやることは引き算なんですよね。その後に来る足し算を見越したうえで、引いてはいけないことを引かない。残すべきものがあるはずです。それから足し算という意味で将来的な絵を描く。そして、安心しないでやり続ける、ということが重要ではないかと認識させられました。では、会場の皆様方からの質問をお受けしたいと思います。
配牌が悪ければ上がれなくても仕方がない(永沢)
会場:再生の局面で案件が来て、完璧にうまく出来る自信はないまでも、何となくうまくいきそうだとスタートしても、途中でうまくいかなかったというケースもあろうかと思います。そのうまくいかなかった理由は、どういうものが大きいのか、当初との見込み違いはどこにあるのか、実体験からお聞かせ願えますか。
永沢:まず我々は案件を選べません。裁判所から頼まれるものなので、それについてこの案件は遠慮したい、ということはないんです。その反面、「案件を選んだ責任は私にはない」と言えます。
麻雀に喩えれば、配牌が悪ければ上がれなくても仕方がないということです(会場笑)。所与の条件の中でベストを尽くすことが我々の役割であって、その中で出す結論は、私としてはベストを尽くした結論だから、失敗ではないと自分に言い聞かせながら仕事に取り組んでいます。
最終的にかなりの人数の従業員が転職したとしても、ベストを尽くしていくつかの事業部門が残せて、そこが社会的に認められるものになればいいし、あるいは再生を通していろいろな方々と触れ合って、いわば一緒に戦友として戦ったことがその人の価値になっていると確信しています。MBAで理論的に学ぶことも必要ですが、臨床の場面で苦楽を共にするというのは、こんな楽しい経験は他にないと思っています。だから、失敗ではありません。
林:案件が選べる立場の私から申し上げます(会場笑)。選べるはずなんですが、当初から想定していた前提条件が、そのまま実現するということは絶対にありません。
いかにタイムラグなく修正できるか。あるいは修正のためのフィードバックのメカニズムとして、対象企業の内部から上がってくる情報とスポンサーとの間のルールをいかにして作っていくかが、非常に大きな課題となります。それを初期段階で形にできれば、その後は大概のことには対処していけるということです。
ところが、初期段階でフィードバックが十分に機能するような関係が作れなかったような場合には、どうしてプランから外れていっているのか、ということも分からない。また外部のコンサルにそこから入ってもらって、分析してもらうようなことをすると、どんどん時間が経っていくわけです。再生の局面では、きついところを乗り切って、全体の時間をいかに短くするかが大事なので、そういうことは致命的になりかねません。だから先程お話しした外部の人間の内部化は、こういう場面でも効いてきます。
シミュレーションを提示してマネジメントに危機感を持たせる(木村)
会場:我が社では大理石の法則があり、ガバナンスの崩壊もあり、身も心もボロボロです。まさにぶつからんとする前で、きちっと外部の方にお願いするべきか、ぶつかってから選択肢がなくなって再生に入るのかは、大きな違いがあると思います。ぶつかる前に勇気を持って、自発的に白旗を上げさせるにはどうしたらいいのか、事例があれば教えていただきたいと思います。
尾関:白旗が上がっていても、受けられる案件かどうかという問題があります。先程の永沢さんのお話に出てきた、配牌がとんでもないというときには、流したほうがいいのではないかといった見極めは大切です。仕事だから結果を出さないといけない。
オーナーあるいは経営者と、何をもって成功とするかを決めることが、再生に携わるときの基本原則だろうと思います。失敗というのは結果なんですよ。失敗と決めたときに失敗になる。再生をやるときには、自分で考えられる限り、あるいは周りの知恵も使って、でき得ることをすべてやる。やったことに対する後悔は少ない。やらなかったことに対する後悔は大きい。そこが原理原則ではないでしょうか。
永沢:私はよく「神風は絶対に吹かない」と申し上げています。治療するのなら一日も早いほうがいい。内科的な投薬よりも、外科的な手術をした方がいいということを、いつも助言しています。それでも、なかなかすぐに申請をしようということにはならず、悪あがきしてしまうことが常だと思います。
そういうときには、本体の再生にかかるのは勇気がいるし大変だろうけれども、「シミュレーションをしてみませんか?」と言います。ある子会社もしくはある部門を、こういう形でプリパッケージ型で再生できれば、同じようなことが本体にも通じるはずではないかと。この部署は誰が見てもどうしようもない。であればここにまずここを治療して、うまくいけば次のステップで本体の大手術をしてみませんか、というようなアプローチをします。
結果的に本体についても、無事に再生案件に取りかかれたということもあります。なかなか手術に踏み切れずに、心肺停止になることもありますが、それは最終的には経営者の判断です。我々の役割としては、経営者に情報をきちんと提供して、選択肢を与えることしかありません。
林:非常に重要なご質問ですね。いま思い出したんですが、2005年頃にも経済産業省の審議会で、同じようなことを議論しました。どうすれば破綻してしまう、もしくは危機に瀕するもっと前の段階で、再生のプロセスはできるのか。そういうことをいろんな方々が集まって議論をしたんですが、どうも妙案はないようです。
先程のお話では大変おつらい状況にいらっしゃるようですけど、こうすればもっと早く白旗が上がるという案は、実のこところなさそうなんです。そういう意味では、シンプルな回答で心苦しいのですが、やはり社内にいる一人ひとりが、勇気を持って問題提起していくしかないと思います。
木村:私からも答えさせていただきます。一つは、問題を先送りしてしまうというところがあるように思います。決めるべきことを決め切れずに、そういう状況に陥ってしまうのではないでしょうか。
意識しているのは、このまま行くと将来どうなるか、を出来るだけ臨場感込めて伝えていくか、ということです。マネジメントの方に対して、このままいったらキャッシュが回るのか回らないのか、そして回らなくなることを想定した場合には、どんな打ち手を予め考えておかなければならないのか、ということをしっかりシミュレーションして見せてさしあげる。
仮に私的整理や法的整理ということを選択肢の一つとして考える、というケースがあったとしても、すぐに出来るわけではないですから、事前に準備しなくてはいけない。そのためには、何カ月前から何をすべきか、というストーリーを組み立てる。その場合には、会社として、マネジメントとして、従業員にとって、というなるべく詳細化した形で現実論を直視できるようにしてあげることが「カギ」と思います。
永沢:是非、補足したいのですが、よく「法的整理は最後の手段」というイメージを持たれるのですが、実は法的整理で企業価値が棄損するというのは、私は幻想ではないかと思っています。もしかすると会社更生とか民事再生というのは、むしろもっと早い段階で取るべき手段かもしれません。
これまでは会社更生の申し立てをすると、経営陣が全員辞めさせられて、株主責任も取るという流れで、突然面識もない弁護士が入ってくるようなストーリーだったんですが、今はDIP型の会社更生を申し立てることで、経営陣がそのまま残って手続きを行うこともできます。また、取引債権を保護する形で、金融債権だけを棄損させて、今までの取引関係を維持することも可能です。
また、100%減資しなくてもいい。つまり会社更生を申し立てたからといって、上場廃止する必然性もない。もう十分に株価が下がっているのだから、株主責任は取っている。そういう形で更生手続きができるとすれば、随分合理的な法的整理になるのではないでしょうか。
それは破綻処理ではなく、再生処理とも言えます。現にそういった形での試みがされていて、「是非、良い案件が来ないかな」と、裁判所も待ち構えているくらいです。しっかりとした会社が準備を整えて、良い形で会社再生をやれば、一つのエポックメイキングになるのではないかと思っています。
社会的価値のある、例えばソーラー発電の設備を製造する電気メーカーなどが、法的手続きを選択するというのも、あってもいいと期待しています。しかし、そういった会社は大概、ホワイトナイトが現われてしまいますが。万策尽きて法的手続きをするものではないということを、我々も啓蒙していきたいと思っています。
木村:最後にMBAを学ばれている皆さんへ、コメントをいただければと思います。
環境が整っていなくとも成果を出せるプレイヤーになれ(林)
尾関:再生現場で直面したり、新聞などで企業再生の話が出たときに思うのは、どうしてこんな状態になるまで放っておいたのか、ということなんですね。日本独特の経営の問題が存在することを、我々は認識しなければなりません。双日の前社長・西村英俊氏の著書に、『会社は毎日つぶれている』があります。すなわち、会社は毎日、潰れる理由を作っている、それが何かのきっかけで現実化するということです。潰さないよう経営することが、基本中の基本です。我々のロールモデルは、京セラの稲盛和夫氏だと思います。稲盛さんが作ったあの組織は、日本が誇れる素晴らしい企業です。
最後に付け加えると、お金がポイントですよね。お金についてもっと勉強してください。キャッスフロー計算書がきちっと読めるように、日夜努力してください。
永沢:この「リゾナーレ」という場所で企業再生の話をするのは、非常に意義があると思っています。ここは旧ニチイグループ(その後マイカル)が立ち上げたリゾート施設で、同グループがいわば“大理石”として作ったものであります。
その施設を、再建請負人である星野リゾートが見事に再生させた。マイカルという企業は残念ながら破綻したけれども、その器を引き継いで志がある人が再生させると、ここまで蘇るのかなというのが、実感として伝わってきます。客単価もおそらく、マイカルが経営していたときの倍以上になっているはずです。
やはり、企業は人次第です。人という経営資源を、いかにうまく配分するかにかかっています。他の人にとっての“大理石”が、ピカピカの設備に生まれ変わったのが、この現場です。この音楽の森ホールも、まさに「こんな施設を作って、どう考えても割に合わないな」と思われるようなものが、このようなシンポジウムに使われるということは、大変意義のあることだと思います。
林:私はこの会議に参加は、今回が初めてですが、大変熱いですね。そういう意味でエネルギーが集積していると、「場」の力を感じます。
私は必ずしも再生案件ばかりに携わっているわけではないのですが、いまだプライベートエクイティの市場自体が日本においては、きれいにできあがっているわけではないんですね。そういう中で、日々もがいている立場から申し上げると、ビジネスをするにせよ、経営をするにせよ、整った環境で仕事ができるのはむしろまれなことだと思います。
「社会が悪い」とか「制度が悪い」とか、人のせいにするのは、例えばサッカーで、きちんと整地されていないから、芝の状態が整っていないから、とパフォーマンスが上げられない言い訳をするのと同じことです。しかし、サッカーをする喜びは、凸凹のグラウンドであっても、ネットがなくても、きちんとしたグラウンドでするのと同じように存在するはずです。
我々が今後、しなければいけないことは、環境が整っていないところでも成果を出せるプレイヤーとして、成長していくことだと思います。環境が整うかどうかに問題意識を向けたところで、すぐには変わりようがありませんから、言い訳をし過ぎることにもなりかねません。
そういう意味で「創造と変革」は、実はどんな環境であっても、いま自分がすぐにでも取り組めるものだということを、私自身がこの会議に参加して感じているので、皆さんにも共有させていただければと思います。
木村:“事業”そのものを再生すること、当たり前のことを当たり前にやること、日々できることをコツコツとやる、ということが、大きなメッセージだったと思います。どうもありがとうございました。