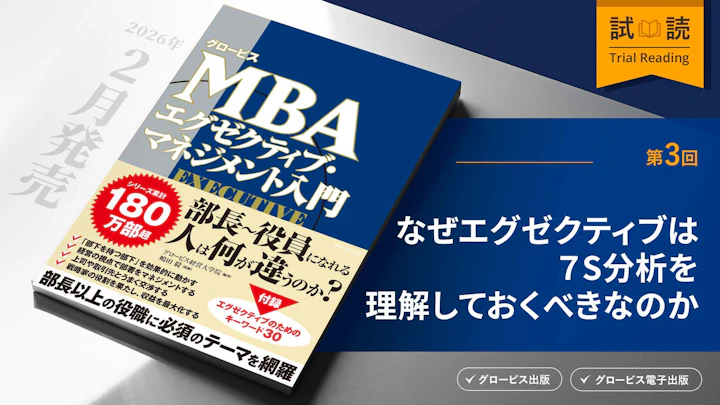加藤:今日は農業界気鋭の起業家お2人にご登壇頂きます。私はビジネス誌の記者として様々な食の現場を取材してきましたが、日本の農業を語るとき、取扱高5兆円という規模で流通を抑えている全農(JA)の存在に触れないわけにはいきません。高島さんはJAさんとは別の土俵で、新たな流通を作ろうとしている。松本さんはJAさんの仕組みを生かしながら、生産の現場を変革しようとしている。いわばJAの中と外から農業を変えようとしているお2人の議論から、日本の農業が抱える課題、可能性が浮かび上がればと思います。まずは自己紹介をいただきたいと思います。では高島さん、お願いします。
作った人が自分の子供に食べさせられるものを売る(高島)
高島:おはようございます。オイシックスの高島です。よろしくお願いします。
オイシックスは、減農薬野菜、無添加食品を中心とした自然食品の宅配サービス会社です。2000年に創業しまして、現在売上高62億円、契約農家約1000戸、定期購入者3万4000人を持っています。今日どういう立ち位置でお話をするかということを最初に申し上げておきます。私の行っている事業は農業ではないんですね。食品小売業ということで、インターネットで食材を一般消費者の方に売るという、宅配の仕事をする会社です。
会社のコンセプトの一つとして、「作った人が自分の子供に食べさせられることのできるものを売る」というものがあります。私は元々と外資系経営コンサルティング会社マッキンゼーでコンサルタントをしていたので、食品業界の経験はありませんでした。「作った人や輸入した人が食べないものがこんなに多いのか」と、驚きました。
「作った人が食べられるものだけに絞り込んで売る」ということを考えると、従来の流通の買い方ではできない。特に野菜・青果物に関しては、かなり川上、農家さんのところまで遡らないと、そういう物を買えない。あるいは生産者に流通業として働きかけをしていかないと、なかなか規模の拡大が出来ないということを感じながら事業をしています。
今日は農業ビジネスをどうするかというよりは、流通業・売り手、あるいは使い手のユーザーさんの視点から見て、農業にはこういう課題があって、こういうチャンスがあるということを、私の立ち位置として話していきたいと思います。よろしくお願いします。
松本:おはようございます。日本アグリマネジメントの松本です。よろしくお願いします。
日本アグリマネジメントは傘下に農業生産法人を持ち、現在、北海道、大分、佐賀の3カ所に、合計50ha弱(東京ドーム10個分)の農地を持っています。トマト、ピーマン、さつまいも、玉ねぎ、じゃがいも、スイートコーンなど8品目の生産をしています。元々は銀行マンをやっていて、グロービスでは大学院でアカウンティング基礎とファイナンス基礎のクラスを、マネジメント・スクールではアカウンティングのクラスを教えてもいます。
東京三菱銀行(現三菱東京UFJ銀行)を辞めたのが1999年でして、辞めるときから農林水産業が頭の中にありました。会社を立ち上げたのは3年前になります。グループビジョンの中に、まさに高島さんが今おっしゃったことと同じことをうたっています。「私たちが自分たちの子供に食べさせたいと思うお野菜を皆さんにお届けします」。生産現場でこの考えを軸としながら、取り組んでいるところです。今日は私の立ち位置として、皆さんと一緒に日本で農業をやる意味を考えていきたいと思います。よろしくお願いします。
加藤:日本の食、とりわけ農業の現場で今何が起きていて、どのような問題意識を抱えてえているのか。それに対してどのような取り組みをなされているのかをお話しいただきたい。では先に松本さんからお願いします。松本さんは金融のご出身ですよね。なんでこの世界に飛び込んだんですか。どのような問題意識があったのでしょうか?
安全、安心なものを、安く広く供給する(松本)
松本:そうですね。僕はもしかすると、意外と農業に対して熱い想いがないのかもしれないんですけど、銀行を辞めた当時、世の中に必要な産業の中で、お金が回りにくいと思った分野がいくつかあって、それが医療と教育と農林水産業だったんですね。こういうところにお金が回る仕組みを何とか作りたいと思ったのですが、既存の金融機関の中でやるのは難しいなと思い、銀行を飛び出しました。それが一つですね。
それともう一つは、人そのものが価値を生み出すビジネスはとても面白いと思っていて、それが医療であったり、教育であったり、農林水産業だったりします。
だから「美味しい野菜を食べたい」とか「日本の農業を守りたい」とか、そういう熱い想いで銀行を辞めたわけではないんです。銀行員の立場から見たときに、今挙げたような産業は、どの国、地域に行こうが必要なインフラであるにもかかわらず、なかなかお金が借りられない。「貸す側にも借りる側にも問題があるな」と思いながら、色々見ていったところ、農業は特に借りる側に問題がありそうだということで、やってみたというのがきっかけです。
日本でこのビジネスをしている意味合いについてお話します。大きく二つ。食料安全保障と、地域の活性化です。
野菜などの食糧は、社会や国家にとって必要な資源だと私は思っています。自給率はカロリーベースで40%。これだけ低いと、将来我々が「食える」ことを担保できるのだろうか。食べ物を確保できるんだろうか。そういう懸念があるわけです。農業の生産の現場である程度、食べられる量をきちんと確保しなければいけないのではないか。
また日本は国土が狭いですが、農村に行くと過疎の地域が山ほどあります。我々が農場をやっている大分県臼杵市野津町というところは、過疎の地域です。非常に良い場所で、そこに行けば土地も結構あるんです。そういう土地をやはり守っていくべきだという想いもある。そこで、地域の方々の技術をいただき、地域の方々を雇用し、地域に都会に住む人々を呼んでくる。この3本を軸に農業を展開しています。
「安全な食品を」という話は、当たり前なんですけど、基準がよく分からない。色々な基準があってどれが正しく、信頼できるか分からないんです。だから、先ほど言ったように、本当に子供たちに安心して食べさせられるんだろうかということをキーワードにしながら、実際に農業に取り組んでみて、皆さんに情報発信していこうと考えています。
我々は「有機無農薬」といういま流行りのキャッチーなものを掲げていないんです。有機肥料はたっぷり使います。化学肥料は極力減らします。農薬も基本的には使いたくない。でも、使ったりすることもあります。例えば、トマトは慣行栽培比を5割削減していますが、我々は特別栽培品の認定を受けようとは思っていません。
あえて言えばそこがオイシックスさんとの違いかなと思います。私たちは高付加価値のものをそれなりの値段で売るのではなくて、安全、安心でそれなりに美味しいものを、出来るだけ安く広く供給したい。
例えばトマト。1個2000円の高級トマトを売るつもりはない。普段食べるトマトで、必ず水に沈むもの。これはある程度、糖度も栄養価も高いということの証左なんですが。こういったものをきちんと供給できるようになりたい、というのが私たちの願いです。
ところが世間では、水に浮くトマトが市場に出回っている。信じられないです。ウチのトマト、どれをもいでいただいても結構ですが、全部沈みます。浮いてしまうトマトを売っている人の感覚が分からない。しかし、そういうものが流通して、店舗に並んでいるわけですよね。そこを駆逐すれば、私たちには勝機が十分あると思っています。
加藤:ありがとうございます。参入される際に、マクロ環境や、日本の農家の現状を調べる機会があったかと思いますが、何か課題で見えてきたものはありますか?
松本:農家の戸数と規模の関係を見てみると、小さい農家は恐ろしい勢いで減ってきています。一方で、政策的な後押しがあったにもかかわらず、大規模な農家はほとんど増えていない。農業就業人口を見ても、農業者人口が確実に減ってきました。1959年に1700万人だったのが、2002年では850万人です。半減しました。今後さらに急激に減ることが予想されています。
高齢化で辞めていく方が多くいらっしゃる一方で、新規就農者数は少ないままだと、技術が継承されていきません。農業技術を持った人材を確保できないというのは、農業ビジネスを考える上で、非常に大きな問題です。
加藤:技術を受け継ぐ人がいない。売るべき生産物自体が減っていく。日本の農業はまさに大変な時期に差し掛かっているわけですね。高島さんは流通を変えていく取り組みをしているわけですけれども、この農業の現状をどう考えていらっしゃいますか。
作り手側にプライシングの自由を取り戻す(高島)
高島:もともと私はネット事業に携わっていて、「ネットで何かをやりたい」という想いから入ったので、まさか農業とこんなに深い関わりを持つことになるとはまったく想像もしませんでした。最初の農家との出会は最悪で、適当に市場にある段ボールに書かれた電話番号でアポを取って、農家さんのところに行きました。「インターネットで有機野菜を売るので、おたくのトマトを買いたいんですけど」という話をしたら、「何を言っているのか分からないから帰ってくれ」と追い返されました。それぐらい農業のことを何にも知らなかったわけです。
その中で手探りでやってきたんですが、今は農業に対して深刻な問題意識を持ち始めています。日本の食というもの自体の国際的競争力は、潜在的には非常に高いと思っています。『ミシュランガイド』(日本ミシュランタイヤ株式会社)に載る飲食店の星の数も、東京は多いですよね。非常に日本の食文化は素晴らしい。
でも日本の食を支える素材を作っている人たちが減っている。農業人口が減っているし、漁業人口も10年で10万人ぐらい減っていて、あと20年もすると漁業をやっている人が全然いなくなってしまうのでなないでしょうか。それぐらい急激です。
なぜ減っているのかというと、経営資源をヒト・モノ・カネに分けるとすると、特にカネの問題が大きくて、農業をやっていくにしても、事業を継承する経済合理性のある理由がない。まあ、儲からないということが、大きな要因でしょう。
儲からないのはなぜか。JAさんでは、「何がいい野菜か」という基準ははっきりしています。きれいで重いものがいい野菜ということです。値段が重量で決まってくる。そうすると、美味しいものとか安全なものを作っていることが、自己満足になってしまいますよね。経済的になかなかリターンが得られにくい。
「とりあえず生活のためにやっていこうか」という人たちは、ある程度重いものを作れれば評価されます。しかし、もっと美味しいものにこだわってやっていこう、安全なものにこだわってやっていこうとしても、今の仕組みでは自分がかけた努力に対して、経済的なリターンが得られる機会が少ないというのが、大きな問題です。
生産者側にプライシングの自由がまったくない。他の農家さんより美味しいものを作ろうと思って、1年間一生懸命やった結果いくらになるのかは、市場に持って行くまで分からない。やはりプライシングの自由度を作り手側が取り戻さないと、良いものを作っている人たちが続けられない。私が抱えている一つの問題意識です。
ここで私たちが「良いもの」と言っているものは、従来JAさんなどが言っていた「きれいで重いもの」ではなくて、安全で美味しいものです。良いものの軸を変えたうえで、それに対して高いお金で買って、高いお金で売ります。高いと言っても、ものすごく高いというよりは、ちゃんと付加価値を考えた価格にしていくということです。
良い事例が一つあります。オイシックスには何人かのカリスマ農家がいます。当社の場合はすべての商品に関して、生産者がどこの誰なのか、情報開示して売っているんです。
三竹さんという愛知県の農家なんですが、この人はウチでものすごく人気です。スーパーでも「顔が見える野菜」と銘打って売っていますが、あれを見ても基本的に同じようなおじさんが、同じような畑をバックに、同じような商品を持って笑っているだけなので、全然よく分からないと思います。しかしこの三竹さんは、ブランドが立っています。「早く三竹さんの野菜が買いたい」と、毎年冬が近づくとお客様からメールが来ます。
三竹さんは、夏は働かないんです。夏には、海外行ったり、実験をしたりと野菜の開発をしています。チャレンジをするための研究期間なんですね。取扱高も毎年増えていますし。我々にとってもこの方の商品が、お客様をグリップするうえで非常に重要なアイテムになっています。生産者と流通業者が有意義な関係を築いている事例の一つですね。
生産者がヒーローになるインフラを作る(高島)
加藤:そうは言ってもJAさんが果たしてきた役割というのはあると思っています。特に国民全員がきちんと食べられなければいけないという時期には、大きさや重さによって計り、市場に安定的な供給をする役割をJAさんは担ってきました。そのあたりはいかがでしょうか。
高島:もちろんJAさんに役割、機能がないなどとはみじんも思っていません。非常に重要な機能を、今でも果たしていると思っています。基本的にはJAさんの仕組みは、力の弱い農家さんも含めてしっかりと底上げをしていく機能を持っています。農業はどうしても天候など不安定な要因が多い商材なので、生産者が持っているリスクを分散、吸収しているという面もあります。また、農家に対する様々な支援もしている。
ただし、JAさんというインフラは、力の強い生産者がなかなかヒーローになりにくいシステムでもあるわけです。私たちとしては、「スターになりたい」「競争したい」「自分の力を分かってほしい」と考える方々に、私たちのインフラの上でどんどん競っていただいて、勝ち負けもはっきりさせる。三竹さんのように大成功する方もいれば、消費者の賛成をまったく得られずに退場されていく方もいます。オイシックスはそういうインフラであろうとしている。そういう意味ではJAさんとオイシックスは、異なった重要な機能を持っていると思います。
加藤:ありがとうございます。では、松本さんの会社がどういう生産者になろうとしているのか。ここまで話してきたような課題を踏まえて、ビジネスモデルをお話ください。
ウチにはトマト部長、ピーマン部長、甘藷部長がいます(松本)
松本:私たちは、JAさんと協働で事業を展開しています。主に優良な農地と生産技術の確保が狙いです。例えば、大分県に参入したときは、県庁の方と話をすると、県の南のほうが空いているようだという情報が得られたんですね。南の臼杵市に行くと、集落の名前が出てきた。そしてその地域のJAさんに行くと、今度は表札になるんです。「あそこは次男坊が帰ってきた」とか、「子供がいる」とか、とにかく詳しいわけです。地域の誰が技術を持っていて、どこに担い手がいて、働き手になりそうな人がいるのか、しっかりと把握している。
例えば秋の収穫が終わる時期に、誰が種を注文しなかったのか、JAさんなら分かる。種を注文していなかったら、次の年は土地が空いてしまいますよね。またどこの誰がどういう産品に強いのか、全部把握している。JAさんとタッグを組みながらやっていると、土地や技術に関して、地元の細かい情報が得られるというメリットがあります。
例えば、ウチには、トマト部長、ピーマン部長、甘藷部長がいます。実際に名刺にもこういう肩書きが載っています(会場笑)。地元の作り手で上手だと言われているトマト部長に最初に出会って、最初は技術指導料を払いながら面倒を見てもらったんですが、2年目からうちのトマト部長になっていただいて、全面的に支援していただいています。ピーマン部長は元JAの営農部長だった人です。甘藷部長は地元で1番の作り手で、10haを栽培している最大の農家さんですが、この方にもご参画いただいています。
しかし経営は絶対渡さないんです。よく経営を一緒に組みましょうという話があるんですが、経営は私がやる。生産技術に関してどう逆立ちしても勝てませんから、こういう方々にご参画いただいて技術を移転する。職員は21歳から83歳までいます。お爺さんお婆さんの技術を、我々企業が触媒となって、フィルターを通して、マニュアル化する。そして地元の若い人、都会から就農を目指す若者を雇い、技術を伝承していく。これが我々のビジネスモデルです。こういう活動であれば、色眼鏡で見られがちな企業も、地元の方々に受け入れられやすいと感じています。
ポートフォリオによるリスク分散を徹底する(松本)
加藤:なるほど。松本さんは金融畑のご出身で、グロービスでも教鞭をとってらっしゃる。そのあたりの知識、ご経験はどう生かされているのですか。
松本:私は全国で8カ所、当面は350haまで農場を増やしていこうと考えています。農業で一番のリスク要因は、天候不順と市況の変動です。これに対して、おっしゃるとおり金融業界出身でグロービスでも教鞭をとっているわけですから、当然リスク分散を考えたわけです。
まずはエリアの分散です。北と南に振っているのは、周年栽培(=1年を通じて同じ作物を栽培すること)をするためでもあります。例えば、冬〜春のトマトは大分県で作っているんですが、夏〜秋のトマトは北海道で作る。いま北海道ではジャガイモをやっていますが、第2番目の産地は九州・長崎なんですね。九州では特に台風のリスクがあるので、並行栽培もしようとしています。大分がダメでも、もう1カ所の産地があるという形で、天候不順というリスクを分散していく。
次は作物分散、アセットミックスですね。大きく3つのグループに分けています。C&T(Cucumber&Tomato)グループはキュウリ&トマトの栽培で、これはあまり収量にブレがなくて、単価にもブレがありません。投資の世界でいうとFixed Income投資のようなものです。
次に収穫量にブレがないけれども値段にばらつきがある積乱雲グループ。これは言ってみれば株式投資、あるいはヘッジファンド投資のように考えています。最後に値段にはブレがないけれど、収穫量にばらつきがある横長グループ。この3つのグループのポートフォリオを組み合わせることによって、農業経営体として強い経営体を作っていこうと考えているわけです。例えばいま大分で作っているのは、C&Tグループにあるトマトと積乱雲グループにあるピーマンとを組み合わせてやっているところです。
各作物の相関係数をとった表があります。過去20年間の各作物のプライスの動きの相関をとって、できれば相関のないものを組み合わせようということです。例えば、ジャガイモとブロッコリーはほとんど相関関係がない。では、北海道でジャガイモと組み合わせる作物として、ブロッコリーをやってみようかということにある。農家さんですと、うちはトマト農家とか葉物農家とか様々ですが、我々は企業であるがゆえに、こういうポートフォリオが組めるわけです。
農地法が参入障壁になっている(松本)
加藤:「経営は渡さない」というお話が出ました。そもそも農業生産法人として企業が参入しようとすると、いろいろ制約要件があると聞いていますが、そこをご説明いただいてよろしいですか。
松本:今回の農地法改正で企業が土地が持てるようにはなりましたが、事実上の変化はありません。大きな問題はいまだ解決していません。借りるとしたら年間1万円の土地が、買おうとすると60万円で売られているんですよ。ファイナンスを勉強されている方はお分かりになると思いますが、これはまったく割に合いません。そう考えると、基本的に借りるしかない。
もう一つ問題があります。農地法では、役員要件が定まっていて、取締役の過半数以上が年間150日以上農業に従事し、さらにその過半数が、年間60日以上農作業に従事しなければならない。私が60日以上農作業しなければならないんです。北海道と九州に農業生産法人持っているので、年間120日です。あすか会議の直前まで北海道で草刈りしていて、これが終わると家に帰らずにそのまま大分に行くんですけども、60日ずつの農作業っていうのは結構ハードルが高い。企業が参入する際に、ここを農家さんに任せようとなれば、結局は経営の分断が起きて、喧嘩別れになるか、乗っ取られるか、捨て去るかということになる。そうしたくなかったので、60日の農作業を含めてやっています。これは農業参入する上での大きな参入障壁になっています。
加藤:ずいぶん日に焼けてらっしゃいますよね。ちなみに、先ほど8カ所でポートフォリオを組むというお話があったかと思うのですが、8カ所丸々持ってしまうと60×8=480日、1年間で就業できないことになろうかと思うのですが。
松本:この日焼けはゴルフ焼けではないですからね。それもあって、どっかでクローンとかできないのかなと思うんですけども(会場笑)。現状は苦肉の策で、農業生産法人の支店を開設することで3番目の農場を開拓したりしています。さすがにもうこれ以上、私自身が作業するのは無理ですね。
加藤:ありがとうございます。松本さんの話では、そんなにものすごく高いものではなく、きちっとみんなが安心して食べられるものをあるリーズナブルな価格で提供していくということでした。一方高島さんは、JAさんが決めた軸とはちょっと違う方向でものを作っている農家さんを発掘し、それを流通に載せていくということでした。では、今度はJAを通さないで、どのようにして物を流通させるのかという話になってくるかと思うのですが、例えばマーケティングなどの工夫をどのようになさっているのか、お話いただけますでしょうか。
作り手が食べているのに流通に乗らない商品がたくさんある(高島)
高島:我々の場合は流通業なので、作り方というよりは売り方のほうを工夫する場面が多いです。日本では食品流通のサプライチェーンが長いんですよね。食べる人と作る人との間に、実に様々な人が介在するんですよ。そのためビジネス的に効率が悪いところが多々あって、情報が断絶している。そこが逆にチャンスになる場合が多いので、我々が産地に行くときにはその情報のギャップを探します。
例えば、ウチには生で食べられるトウモロコシがあります。5年ぐらい前からやっていて、非常に売れています。今は色々なところで生で食べられるものが出てきていますが、当時はほとんどありませんでした。どのようにして始めたかと言うと、ウチのバイヤーが産地に入って、トウモロコシ農家を訪問したところ、そこの子供が生でトウモロコシをおやつで食べていたんです。ウチのバイヤーがビックリして、「生で食べるんですか?」と聞いたら、逆に農家の方がびっくりして「生で食べないの?」という話になったんですね。
こういうときにビジネスチャンスがある。食べる側の常識と作る側の常識が違うんです。早速都会でも届いた日と翌日は生で食べられる、というような管理をして売ったところ、大ヒットしたわけです。
加藤:私もこのトウモロコシの大ファンです。とっても美味しいんです。でも中々買えなくて…・・・。特別に分けてください(会場笑)。
高島:有難うございます。規格外の野菜もかなり前から扱っています。実際に産地に行くと、形が悪い野菜が大量にあるんですよ。そこで「これはどうするのですか」と聞くと、「売れないから自分の家で食べて、あとは放っておく」というので、試しにシリーズ化して販売したらやはり非常に売れました。
私たちは味が良くて安全性があれば、形が悪くてもそれは十分に価値のある商品だと認識しています。お客様も今までよりも安い価格で安全な美味しい有機野菜を買えるようになり、生産者もこれまで捨てていた不揃いの野菜を売ることができるようになりました。
当初は生産者からかなり激しい反対を受けました。「絶対に恥をかくからやめておけ」と言われたんですが、実際にやってみると消費者が急増して喜んでもらえた。そうすると、生産者のほうから「実はこんな規格外の野菜もあるんだけど」という感じで、どんどん紹介をいただけるようになりました。
マッシュルームやえのきの軸が大人気(高島)
加藤:JA的なピラミッドの三角形の上の方でなくても、消費者から見たときには付加価値の高いものがまだまだあるということでしょうか。
高島:そうですね。まあ、上か下かというの難しいんですけど、そのピラミッドの軸が見た目なのか、安全性や味なのかという問題です。我々の場合は安全性や味の軸でのピラミッドを作っているんです。その分調達できる野菜がいっぱいあります。
最近非常にヒットしているのが、「もったいない」コーナーです。例えばキノコの軸。マッシュルームの軸を食べないのは日本人だけらしく、日本人でも生産者は食べているんです。しかもダシも濃く出て、美味しい。我々のほうでこれを「マッシュルン」と名付けて販売したところ、非常に評判が良い。ほかに「えのき貝柱(えのきの軸)」などを販売しています。「作り手は食べているのに、今までは商品化していなかった」というものを、商品化して販売することによって、消費者にも喜んでもらえるし、生産者にも喜んでいただいています。
「リバイバル・ベジタブル」というものがあるんですが、絶滅品種の販売も行っています。日本の中に滅び行く野菜というのが結構あって、赤根ほうれん草(山形県)、ひろっこ(福島県)、にが菜(沖縄県)など、日本に生産者が2、3人しかいないケースが多いんです。なぜ滅び行くかというと、作るのがちょっと難しいので、品種改良して栽培の成功確率の高いものに、どんどんシフトしてきてしまったんですね。こういったタイプの食べ物は、原種に近いので味に力がある場合が多い。私たちは生産者と提携して、いくつかを復活させようということでやっています。
なぜこういうことやっているかと言うと、これらの商品は一体いくらが適正価格か分からないので、かなりプライシングの自由度があるんです。それは流通業者である我々にとってもそうですし、生産者にとっても同じですが、作るのが難しい分だけリスクが高いんですが、一方でリターンを結構取れるというタイプの商品になる。我々は流通業者としてはこういう力のある、でもほとんど流通していないものを何とか、消費者の生活の中に浸透させていきたい。
加藤:今はオイシックスさんのブランド力があるからこそ、農家さんに行っても、「じゃあ取引をしましょう」と安心していただけるでしょうが、ブランドがまだない時期には、「JAさんのほうが安心」というようなことも言われて取引につながりにくかったのではないかと思います。そういう場合、どのように口説いてきたのでしょうか。
「農家・オブ・ザ・イヤー」授賞式で涙する生産者がいる(高島)
高島:どう口説いたかって言っても、大した話ではありません。20代だった私がスーツを着て、「インターネットで野菜売りたい」とお願いしても何を言っているのか理解してもらえない。仕方がないので生産者さんと一緒にお酒を飲んで、いかにインターネットの未来がすごいかということを話しました。それでもあまり分かってくれませんでしたが、段々同情されて、「お前ら可哀想だな」という感じになって、「端っこのやつ持って行っていいよ」という具合に始まりました。同情買いですね。
加藤:同情買いから始まったんですね。でも、そうこうするうちに三竹さんのようなカリスマ農家が出てきたら、「俺たちも」となるわけですよね。
高島:「俺たちも」となります。非常に大きいのは、消費者の生の声が大量に来ることです。「美味しかった」「不味かった」という反響をフィードバックしていきました。
今「農家・オブ・ザ・イヤー」というイベントを開催しています。元々これは農家さんの新年会の二次会の余興でやったら非常にウケが良かったので、今はしっかりと年に1回やっています。全国から300人ぐらい農家さんが集まって、純粋に消費者の方の投票の数で、その年1番評価の高かった農家さんを表彰する。優勝した方は涙を流して喜んでいただける。
美味しいものを作るために何十年も努力してきた方が評価される場は、今まで全くなかったんです。「自分のものが認められた」という達成感が湧くし、それを目の当たりにした生産者の方も、非常に高いモチベーションを持って帰っていただいている。「絶対、来年は自分が獲る」ということを、皆さんが口々に言っています。
「農家・オブ・ザ・イヤー」を獲ると、自分のプライドが満たされるということもあるし、それから私たちのインターネットサイトの中で、「農家・オブ・ザ・イヤー」受賞のワッペンが付くのですが、それで売上がかなり伸びるんですね。経済的なリターンもあるわけです。
加藤:非常に魅力的ですよね。先程生産人口が減っているという話があったと思いますが、こういうやり方だったら、「農業に参入してみたい」という若手も出てくるんじゃないですか。
高島:どちらかと言うと、私たちは元々、後継者のいる生産者を選ぶようにしています。後継者の中には、非常に志の高い人もいるんですが、「とりあえず継いでみた」という人たちもいるので、そういう人たちのマインドをお父さんたちと同じように、「いいものを作って消費者に喜んでもらう」というものに変えていきたいですね。
加藤:松本さんが参入されて課題に感じてらっしゃることを伺いたいと思います。
普通の企業がやっていることを農業の世界に落とし込む(松本)
松本:実はこれまでも、各市場に、全国から旨いものを見つけてくる人がいたわけですよ。ところが生産の現場には、消費者がどう言っているかという声が通らなかったんですよね。私たちは月1回の簡単な会報を5000部ぐらい刷って配っているんですが、消費者の方々と直接コンタクトするためのツールとして使っています。これを農場で働いている若い人たちにフィードバックすると、非常にモチベートされて頑張っていただけるということです。
高島さんが「生産者側にはプライシングの自由がない」とおっしゃっていました。その通りなんです。しかも農家さんでは、そもそも原価がどれぐらいか把握されていない。だから、適正な価格が、「生活できるだけの価格」になってしまう。変ですよね。一般の事業会社であれば、努力して原価を下げなければいけないものもあります。100で売るためには、120のコストを80にしなければならないというのが、日々の皆さんの企業活動の源泉なんだと思うんですけど、農家ではそもそもいくら掛かっているのかがよく分からないんです。
僕は実のところ、農業をやるんだったら海外でやりたいんです。元々銀行の出身で海外志向が強くて、今でもカンボジアに畑を作りたいとか、海外で野菜を売りたいという想いが強いんですね。でも、海外の安い人件費でペイするとか、JAを通さなかったらペイするというのは、僕は本質的な解決にはならないと思うんですね。
カンボジアでやったら儲かるんだけど、日本の人件費だったら儲からないというんだったら、ではブレークイーブンのポイントはどこにあるのか。そこまでコストを切り詰めることが出来れば、日本で間に合うのではないか。あるいはJAさんのコストはどうですかと。JAの中で影響力を持つことによって、プライシングについても、「もっと適正な価格をつけよう」と、発言していきたいと思っています。
加藤:ありがとうございます。コストというお話だと、JAさんが間にいらっしゃらないことで、オイシックスさんは、選別などの工程を挟まないで済むような流通が実現できるとお聞きしましたが。
高島:そうですね。私たちの今の課題は、先程とちょっと矛盾したことを申し上げますが、価格なんですね。価格が高過ぎるということです。私どもの行っているビジネスはリッチビジネスで、特定の人だけしか買えないプライシングになっている。本来プライシングに自由度を持たせなければならないし、その自由度の水準をもう少し下げていかなければいけないと思っています。
プライシングの水準を下げつつ、生産者が今より儲かって、私どもも儲かる方法がないかと考えているんですが、その中でいま私たちが直面しているのは、まさに松本さんがおっしゃった農業のエコノミクスを農業者自体があまり把握していないということなんです。
皆さん自分の人件費がタダなので、そのへんを把握されていない。かなりカットできる部分が多いと感じています。それはJAさんが間にいらっしゃることもあるかもしれませんが、そこの部分だけではなく、生産工程そのものに改善の余地が多々あると思っています。
特に生産した後、収穫したり、洗ったり、袋詰めしたり、サイズによって仕分けをしたり、こういうことに掛かっているコストが結構多い。あと大量に獲れて余ってしまった場合のコストも結構大きいですね。流通業と生産者が一体となることが重要かなと思っています。例えば「私たちのジャガイモはサイズによって区分けをしていませんが、その工程を省いたからこのぐらいのプライスに下げられます」ということが可能になります。
あるいは、「ナスが獲れすぎた」という情報がきたら、我々が売り切ることによって、廃棄を見込んでプライシングされていたものを、もっとリーズナブルな価格にできる。生産ともっと緊密に連携できれば、コストダウンにつながることがたくさんあるんです。
松本:生産現場の効率化という観点でいうと、私たちはトラクターなどの重機材をどれだけ効率的に使うか、ということも考えています。例えば、大型のトラクター1台1000万円します。フルに稼働しないともったいない。ですから1台のトラクターでどれだけ作付できるかという作業量の数字を基に、最適作付面積をはじき出します。
トマトの出荷は、10aの畑でだいたい200kgぐらい獲れるんですけど、普通免許で運転できるのは、4t車までです。4t車までなら職員誰でも、出荷ができる。ところが、5t獲れると、10t車とか大型の免許持たなければならない。職員は36人いますけど、大型の免許を持っているのは2人しかいません。しかも10t車は高い。4t車2回で行くとすごい効率悪い。そんなことも考えながら、作付面積を考えていきます。
作業の平準化も行っています。毎月の作業量を同じようにすることによって、通年雇用をしようとしています。私たちがピーマン農家になってしまうと、夏の間2カ月だけの採用になってしまう。でも農業は「経験と勘」が必要で、長期に渡って働かないと身に付かない。また地元は季節的な雇用ではなく、通年で安定した雇用を望んでいます。だから一人ひとりにノウハウが蓄積されるよう、1年を通じて雇用できる体系を作っている。冬〜春のトマトと夏〜秋のピーマンを組み合わせるわけですね。
こういう形での作業の平準化や効率化、ナレッジの積み上げということは、たぶん一般企業にお勤めの皆さんには当たり前のことなんですが、農業の世界ではまだまだなんです。
加藤:ありがとうございました。食べることが生きがいの私は、高島さんのトウモロコシも、松本さんのトマトも頂いたことがあるのですが、本当に美味しいのです。今日のお話の内容が、実際に食べてみると、より理解していただけるかと思います。では会場からご質問をお受けします。
35歳で年収1000万稼げる農家を育成する(松本)
会場:事業規模をどこまで持っていこうとされているのか、お伺いしたいと思います。
松本:8カ所350haということはお話しましたが、やるからにはメインの5品種、6品種については、日本の1%のシェアまで持っていきたいと思っています。500haぐらいまではやりたいですね。ただ、ウチには3年間限定の期間雇用で独立前提の社員も入って来ているので、将来的にはFC化のような形になると思います。自前でやるのは350ha〜500haです。
会場:魅力ある産業づくりという観点から、お二方のご意見をお聞かせください。
高島:私としては、やはりスターになれるということが大事だと思っています。大成功できるかもしれない希望があるほうが、何となく平均して安定的というよりはいいのではないでしょうか。我々はそのあたりを意識して、スターづくりを進めています。
松本:農業と一口に言っても、皆が一様に同じ農作業するわけではありません。皆さんの会社でも、係長、課長と昇進していきますよね。ウチは契約社員から入って、正社員にするのを一つのインセンティブプランにしているんですが、その上にマネージャー、次長という一般の会社のような組織をつくろうと思っているんです。
今20代の社員たちに言っているのは、「35歳で年収1000万取るにはどういうふうに働いたらいいのか考えろ」ということです。例えば、10aのトマト畑で15t収穫獲して、キロ300円だとすると、450万円の売上にしかならないです。それでは年収1000万円貰うのは無理だということですね。
また農家の作り手として、どのぐらいの面積を管理しなければいけないのか。そうすると自ずとそれを管理する人と、作業する人がそれぞれいるはずなんですよね。そしてそういう方々をパーツパーツで必要なだけ使っていくことによって、儲かる仕組みをつくっていこうとしているわけです。
だから、みんな一様に一人前の農家になるということは、私の会社ではやらないつもりなんです。そういう意味では控えめなスターですが、うちの会社の中でトマトのスター、ピーマンのスターを、つくっていこうというふうには考えているところです。
会場:自分なりに既存の農業が儲からない理由を勉強したところ、10個の理由があったんですけども、そのうち8個は松本さんに明確にお答えいただいたので、残りの2個を質問します。一つはJAさんを通すということで、規格外品のロスに関して問題があると思いますが、これどうされるのか。あとは大規模化されるということなので、資金調達をどのようにされるのか。この2点をお願いします。
松本:規格外品のキャッシュ化は、本当に悩ましいところなんですね。取り組みとして行っているのは、加工と地産地消ですね。
今は埼玉県で加工品を作っているんですが、ぜひ大分県内でやりたいということで、今マッチングを県にお願いしているところです。生鮮の賞味期限は1週間ですが、トマトジュースやケチャップにすると延びるわけです。例えばサツマイモは芋焼酎の原料になりますがで、これは洗わなくて済みます。洗いの手間がない分コストが非常に安くなるので、お互いWin-Winの関係を築けます。
規格外の野菜は、事務所の前でも売っているんです。普通に月間の売上が100万円ぐらいになります。2日に1回しか売らないんですけど、味にまったく問題ないということで、ベンツでわざわざ買いに来られる方もいらっしゃいます。
大規模化の資金調達について。私がなぜ農業をやったかと言うと、農業って春に植えて、秋に必ず回収できるからです。しっかり運営さえすれば、キャッシュが回るんですよ、そこのところについては、基本的に自分で回せる限り回したい。
会場:松本さんに質問です。地域活性など過疎化対策にもいいという話だったんですが、都会から人を呼ぶ場合、どのようにしているのか。もし何か具体的にアイデアがあるのであれば教えて下さい。
松本:そうですね。これも試行錯誤ですが、北海道農場体験ツアーを今年の夏にやるんですけども、実際に来ていただく機会というのを、そういった形でつくっていこうと思っています。収穫体験は多いですよね。でもジャガイモは実は、今の時期が一番綺麗なんですよ。白い花もあれば紫の花もあって、綺麗なんですね。いろんな旅行系の方々とお話させていただいているのは、年に4回ぐらい見に来るツアーが組めないかということ。
地元の農家さんがある程度管理をお手伝いしながら、都会から年に何日以上か来ていただいて、交流の場をつくっていきたいと思っているんですよね。そして、物作りの現場の悩みを知っていただきたいんです。害虫が出るんです。できれば殺虫剤を使いたくなので、摘んで回ってみる。それでも、ウジャウジャいるので、泣く泣く殺虫剤を振ろうかどうしようかと悩んでいる。そんな日々の農家の悩みも含めて、皆さんとキャッチボールしながらやっていきたい。単なる収穫体験に終わらせないで、田植えから稲刈りまで、皆さんに追っかけていただくようなイベントをやっていきたいと思っています。
会場:高島さんのご経歴だと、完全に異分野からの参入となりますね。その意義や課題に感じている点があればお聞かせいただけますか。
高島:常識に捉われない点が良かったですね。私は「安全な食」という言葉自体に、ものすごく違和感があったんです。「安全な食」は何かといえば、食べていい食べ物のことですが、そうすると、「食べてはいけない食べ物があるのか」ということになります。普通なら、「このペン書けます」とか、「この車走ります」とかわざわざ言わないですよね。でも食品業界においては、「この食べ物は安全に食べられます」とわざわざ言わなければなりません。食品業界にずっといると、それが変だということになかなか気づかない。その他にもおかしな業界常識があって、異分野から入ることで気づくことはたくさんあります。
それから農業は事業というより家業になっているところがほとんどなので、事業的な視点の入る余地がすごくたくさんあります。オペレーションもそうだし、マーケティングもそうだし、すごくいっぱいあると思うので、そのあたりがチャンスですね。

























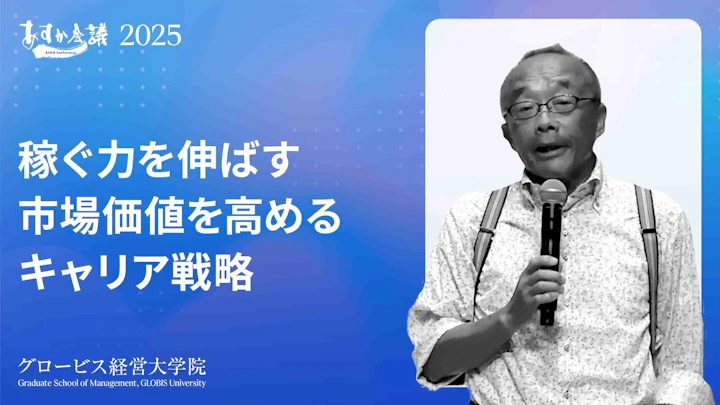














.png?fm=webp&fit=clip&w=720)
.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)