
サービス業の海外展開は、製造業と比べてハードルが高いと言われる。SILC 2007 autumn2日目の分科会「国境を越えるサービス」では、3社の代表が、この壁を打ち破る要諦を議論した。(文中敬称略・肩書きは講演時のもの)。
「創業者が息子のために作った教材が公文式の基礎に」(石川氏)

岡島:日本人の購買力低下が懸念される昨今、業種・業態に関わらず海外市場への進出を喫緊の課題と捉えている企業は多いのではないでしょうか。しかし自動車・家電といった製造業と比べ、サービス業の国際展開は難しいと伝統的に考えられてきているような気がします。本日は、この理由を掘り下げ、海外市場で日本のサービス業を成功させる要諦について議論したいと思います。まず、お三方に自己紹介いただきます。
日本発のサービスを海外に定着させた公文教育研究会(以下、公文)から石川さん、これとは逆に海外のサービスを日本に移転しているリヴァンプから浜田さん。そして日本発の製品を海外に定着させたサンヨー食品の井田さん、逆に海外製品を日本に持ち込まれた(デル・コンピュータ日本法人の代表取締役社長を務めた)浜田さんというお立場から、お話を伺います。まず石川さんからお願いします。
石川:現在、公文は国内外45の国と地域でビジネスを展開しています。教室は、海外だからといって特別なことはなく、日本と同じような雰囲気でやっています。
社員数は国内2400人、海外700人。教室数は国内1万7600、海外7800。学習者は国内147万人、海外262万人という構成です。教室数に対し、海外の学習者数が多いのは、韓国におけるビジネスの内容によるものです。
韓国では「集会」が禁止されていたため、地区ごとに学習者が集まるスタイルではなく、教材を宅配する方式をとっています。この学習者が180万人おり、現地では「学習紙」と呼ばれる業界の大手と業務提携する形で教材を提供しています。提携先の企業は、当初4番手だったのですが、今年中に1番手を抜く勢いとなりました。
教材は、数学は全世界で同じものを使っています。これに加えて、国ごとの母国語教材と外国語教材。「読み・書き・計算」を中心に置いています。
公文をご理解いただくために、私たちの最初の教材について少し、お話しさせてください。
創業者の公文公(くもんとおる)は、高校の数学教師だったのですが、息子が小学校2年生のとき、算数のテストで芳しくない点数をとり、「数学教師の子どもが算数でつまずくのはいかがなものか」と考えたそうです。彼はそこで、「自分が手取り足取り教えるのではなく、自身できちんと勉強できる子どもに育てたい」と、自学自習のための教材を作りました。
その際、学校で教えることと家庭教育でできることを切り分けて、教材に盛り込むのは家庭でできる範囲のこと。そして、数学を学んでいくうえで何よりのポイントとなる代数計算力の強化に内容を絞りました。
B5版のルーズリーフに計算問題を毎日1枚。裏表を使って、最初は足し算・引き算から始めて、徐々に微分・積分にいくもので、息子は小学校2年生から開始し、5年生で微積分まで終了したそうです。この教材が、今の公文式の基礎となりました。
この話から理解できるのは、公文の教材が完全な個人別の教材だということです。元々が自分の息子のためだけに作った教材ですから、究極の個人別・能力別の教材です。そこが公文式の肝であり、また、私たちが今でも一番大切にしている発想になっています。
つまり、どれほど教室が多くなっても、先生と生徒が1対1の関係で学習を進めること。それを根幹に置いています。
海外展開は1974年から。米国ニューヨークに開いた教室が第1号です。その後、ヨーロッパ、アジアほか、世界各国に拡げてきました。常に学ぶ集団であり続けようと、私たち社員も先生方も含め、学びの場を持つようにしています。
「造り酒屋から多角化して即席麺の市場に」(井田氏)

井田:サンヨー食品グループのコアビジネスは即席麺です。このほか飲料、菓子、ゴルフ場などを、日本以外に米国、中国、ベトナムなどでも展開し、全世界の総売上高は約20億USドルであります。グループの中心であるサンヨー食品は株式を上場しておらず、同族会社です。
設立は1953年です。井田家は元々、群馬県で何百年にもわたり造り酒屋を営んでいたのですが、私の祖父である井田文夫が事業の多角化を図り、加工食品である即席麺という未知の分野に参入しました。今でいうところのベンチャーです。その後、1966年に「サッポロ一番」が大ヒットし、現在につながる事業基盤ができました。
その基盤を私の父である井田毅が継承拡大いたしました。1978年に米国に現地法人を立ち上げ、海外での即席麺の製造販売を開始しました。また、1981年に大手即席麺会社であるエースコックに資本参加しました。その後、1994年には会社更生法を適用した大手米菓会社、日東あられを買収しました。
私が社長に就任したのは今から10年前となる1998年です。大学卒業後に富士銀行(当時、現在みずほ銀行)に約8年務めた後に、サンヨー食品に戻り、父の後を継ぎ社長に就任しました。1999年には中国最大級の食品会社である康師傳(カンシーフ)に資本参加しました。
また、私の公職としては、社団法人日本即席食品工業協会理事長、社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン理事、立教大学講師などを務めています。
海外事業としては、米国に現地法人のSanyo Foods America、中国に33%の株式を所有している康師傳、ベトナムにエースコックの子会社Vina-Acecookがあります。
このほか米国に4カ所、日本に3カ所のゴルフ場を所有しています。
日本におけるビジネスをご説明します。まず即席麺事業ですが、即席袋麺分野でトップシェアのサンヨー食品「サッポロ一番」、大盛カップ麺分野でトップシェアのエースコック「スーパーカップ」、春雨カップ麺分野でトップシェアのエースコック「スープはるさめ」、などのブランドを有しています。
即席麺市場全体におけるシェアは、サンヨー食品とエースコック合計で約20%です。このほか日東あられは鏡餅で高いシェアを有しています。
一方、海外のビジネスでは、中国で即席麺、飲料、菓子を手がけており、米国とベトナムでは即席麺を手がけております。中国では、即席麺のシェアが40%、茶飲料が50%、ミネラルウォーターのシェアが20%、といずれもトップシェアです。中国では現在、ペットボトルの茶飲料やミネラルウォーターが人気を博しており、飲料ビジネスが急拡大しております。ベトナムでは、即席麺シェアが約70%とトップシェアを有しており、Vina-Acecookはベトナム第2位の食品会社となっています。
康師傳の売上高は約3000億円。康師傳は香港株式市場に上場していますが、株式の時価総額は1兆円近くです。Vina-Acecookの売上高は約200億円です。
「企業を芯から活性化(revamp)させていく」(浜田氏)

浜田:リヴァンプは経営支援を主業務とする会社で、2005年10月に設立しました。私はサービス業の専門家ではないのですが、幼い頃から「世界を股にかける仕事をしたい」と考え、実際、米国、中国、韓国など様々な国でビジネス経験を積んできましたので、そこから何かご参考になる話ができればと思っています。
まず、リヴァンプについて簡単にご紹介します。私たちが掲げる使命は、「企業を芯から活性化(revamp)し、中長期の企業価値向上を主体的に実現する」こと。企業を進化させることを目指しています。
表層的・短期的な再生ではなく、従業員を元気にすることから始まり、会社を仕組みから変革し、長期的に永続する体制を構築することで企業価値を向上させていきます。現在、20社近い企業の支援に携わっていますが、全ての会社に多いときには5名程度の経営執行チームを送り込み、彼らが24時間365日、当事者意識を持って経営に参画します。その期間は長く、3年、5年、もしかしたら、もっと長期に及ぶ覚悟を持っています。
ヒトだけではなく、資本参加するのもリヴァンプの経営支援の特徴です。身銭を切るということは、自分たちもリスクを負うという決意の表れです。ただ、私たちはファンドではないため潤沢な資金を持っているわけではありません。プロジェクトごとに共同出資を募ることはありますが、いずれにせよ大規模な資本投下はできません。株式の保有シェアでいうと小さなものなのですが、経営責任を負い、支援先と共に成長する覚悟から必ずオーナーシップを共有する体制をとっています。
代表パートナーは、ファーストリテイリングの副社長を務めた澤田貴司、同社長を務めた玉塚元一、そして私の3名です。設立から2年を経て、社員数が53名になりました。大変に気持ちのいい人たちが集まってくれたと思います。3分の1が(現在、社長をしている人も含め)社長経験者。
3分の1がコンサルタント出身などの、いわゆるプロフェッショナル。そして残りの3分の1が事業会社の出身で、例えば「ファーストフード店で、○○については誰よりも優れていた」というように、特定職種のプロが多いです。
リヴァンプの提供する経営支援は3種類に大別できます。
一つは、ベンチャー企業の「スタートアップ支援」。経営人材が揃わず、体制構築に苦慮している会社に経験者をご紹介するなどして、成長を加速します。
二つめが「ブレークスルー(再活性化・成長)支援」。成長鈍化のフェーズに入った企業を再成長のフェーズに導きます。
そして「ターンアラウンド支援」これが最も大変です。業績が悪化した企業をV字回復させるお手伝いをします。
業種でいうと、私たちの支援先は流通業、小売業、外食業が多いです。外食は、「コールド・ストーン・クリーマリー」、「クリスピー・クリーム・ドーナツ」、「バーガーキング」など、海外発のサービス業に近い業態を日本に紹介したりしています。
「クリスピー・クリーム・ドーナツ」は、2時間の待ち行列ができるドーナツ店として話題になりましたから、ご存じの方も多いのではないでしょうか。東京・新宿の1号店に続き、先日、有楽町にも出店しました。
1号店のオープン前日は大嵐。けれど夜8時半から徹夜で並んでくださったお客様が大勢いて、とても感激しました。今でも短いときで45分、長いときには1時間半の行列ができます。金額は言えませんが、大手ハンバーガー店の1カ月〜1カ月半の売り上げを1日で稼ぎ出してしまうほどの人気です。
ただ、こうした行列は、いつかはなくなります。ブームが収まり、山手線の駅ごとに店舗ができれば並ぶ必要はなくなります。そこからが本当の勝負と気を引き締めています。
「コールド・ストーン・クリーマリー」も、真夏には45分〜1時間の行列ができるお店です。スタッフが歌いながら石の上でアイスクリームをこねることで話題になっているお店です。アルバイトのスタッフが数百人いますが、全員オーディションで採用しています。即興で歌や踊りを披露してもらい、エンターテインメント性と、「楽しさ」を全面に押し出すというコンセプトへの共感を重視して採っています。
「バーガーキング」は、日本再上陸。今回は私たちが日本法人の経営をしています。まだ始めたばかりですが、とてもおいしいので食べてみてください。
このほか、メーカーもやっています。例えば「プラマイゼロ」はデザイン家電の会社。工業デザイナーの深澤直人さんと二人三脚を組んで、日本発のデザイン家電を欧州から展開し、世界に拡げていきたいと考えています。また、不動産会社もあります。
「自学自習力を構築する、そのコンセプトは万国共通」(石川氏)

岡島:ありがとうございました。では、ここからパネルディスカッションに入ります。最初に申し上げたとおり、それぞれグローバル化に対する立ち位置は違われるのですが、今までの業務のなかで、グローバル化に際してご苦労されたことと、それを、いかにして克服したかを、お話しください。
石川:私たちのビジネスは、学習者が「ボクも、ワタシも、勉強したい」とやってきて、教室が満杯になると、「もう一つ、教室を作りましょうか」というような形で拡大してきました。「この教材を使って是非、指導してみたい」という方がいらして、それに応えて教室を開いていきました。最初から会社を作ろうとしていたわけではなく、教室が13カ所になり、学習者が300人を超えたあたりで、必要に迫られ組織を立ち上げた、というような感じでした。
海外展開も、これと同じような形で進みました。それまで日本で教室を運営していた方が「夫がニューヨークに赴任することになったのだが、自分の子どもに公文式の学習を続けさせたい」と申し出て来られたのをきっかけに、米国に教室を作ったのです。最初は、その方の知り合いの日本人駐在員の子弟。次第に韓国や中国など、勤勉な国民性をもった東洋系の方の子弟へと拡がり、「私も教室を運営したい」という方が増えるのに応え、現地法人を立ち上げました。ドイツやブラジルでも同じことが起こりました。
つまり、やりたい人がいて、学習効果があるので評判になって、増えていった。それが気づいたときには、予想を上回る規模になった。最初から「海外展開する」という綿密な計画があったわけではありません。
岡島:拠点ごとに経営を現地化してフランチャイズ展開していったのですね。日本で一元管理するのではなく、現地法人を立てられた理由は何ですか。
石川:一つは文化の違いです。教室がある程度の数に達したところで現地法人を作り、日本から派遣した社員が創業者の考え方について伝えていきました。
例えば米国では、勉強というのは学校でするもので、なぜ家に帰ってまで勉強をしなければならないのか?という考えをする人が大半です。ただ、東洋系の米国人が公文式の学習で成績が上がったと評判になり、徐々に「自分の子どもにも公文を」という人が出てきました。またフィリピンでは、夏休みだけ(家庭でも)勉強する習慣があります。いろいろな文化があります。
岡島:実は私は、ハーバード・ビジネス・スクールで公文の米国法人のケースを読みました。そこには、米国人の親は夏休みなどではない時期にも、学校を休ませてでも親の休暇に子どもを同行する。この結果、子どもが公文も休んでしまい、習慣的に続けていくモチベーションを失ってしまうことが多い。こうした文化の差異を、いかにして乗り越えるべきか?という問題提起がされていました。実際には、どのようにして乗り越えて来たのでしょうか。教育と文化は密接な関係にあり、親の価値観を変えるほどのビジネスモデルを構築するには様々な困難があったのではないですか。
石川:明確な戦略を持って臨んだわけではありません。先に申し上げたように、評判に下支えされて、ここまで来ました。教育と文化の関係についてはおっしゃるとおりで、発展途上国では国策にも直結しています。国の繁栄のために、どんな人材を育成したいか、という明確な意図のあるところに、真正面から海外の日本という国で確立した教育法を持ち込んでも、受け入れがたいというところは往々にしてあります。
岡島:先生方への啓蒙、価値観の共有は、どのようにされたのですか。
石川:国内外に関わらず、ブームが起きて教室数が急増した際に、価値観を共有できない先生が増え、結果として辞めていただいた経験があります。
ブームになると、どうしても「これはカネ儲けができるのではないか」という感覚で寄ってくる人も出てきます。例えば海外では、過去に香港やブラジルでそうした状況が見られました。
学習者数を増やすことに主眼を置いた時期も確かにありましたが、一つひとつの教室の品質が公文式全体への信頼につながることを、現在では最重要視しています。
岡島:先生方に共有する価値観とは具体的に、どのようなことですか。
石川:公文式学習法は、その方法論のユニークさに目を留められがちですが、創業者の公文公が目指したのは、子どもたちが自分自身で学ぶ力を身に着ける、その手助けをすることでした。極端に言えば、数学や国語を学ぶことは、あくまで子どもに自信を持たせる、自学自習力を構築するための手段なのです。その基礎として、読み・書き・計算を位置づけているのだということは、万国共通で伝え続けました。
岡島:先ほど、公文式は生徒と先生が1対1の関係で学習を行うという話がありました。先生が子どもの親のように接することができなければ、目指す教育スタイルにはならないのでしょうね。
石川:おっしゃるとおりです。父親(創業者)と息子の関係が、教室の先生と生徒の関係に発展したわけですから、そこには愛情がなければいけない。私たちは、人間には無限の可能性があり、どんな子どもも伸びると信じています。教える側が、「この子はできない」と思った途端に、その子どもの可能性は制限されてしまいます。
岡島:もう1点、お聞きしたいのですが、1995年に創業者の公文公さんが亡くなり、1997年には後を継いだ2代目の公文毅さんも他界されました。この苦境を組織としてどう乗り越えたのですか。この時期、海外展開も進めていらっしゃいます。
石川:創業者はカリスマ的存在でしたから、彼が大号令をかけると会社全体が無条件に舵を切りました。その結果、当時は、実行力は高いが、自ら問題意識を持って考える社員の少ない組織だったように思います。
創業者が亡くなったとき、(1983年に社長を継いだ2代目の)公文毅は既にガンにおかされ入院していました。彼は公文の将来について非常に悩んでいたようです。そして、(公文への入社前に務めた)野村證券で知り合った杏中保夫に「次期社長になってもらえないか」と頼みました。杏中は、若くして野村證券の取締役になり、その後、三洋証券の専務に就任していました。
杏中は当初、この申し出を断り続けていたそうです。ところが、最終的な断りを入れようと公文毅の病室を訪ねた際に、思わず「Yes」と言ってしまった。それがなぜだったか、自分でも分からないと後日、話していました。
1996年1月、創業者の亡くなった翌年に杏中が、まず副社長に就任し、そこから公文の改革が始まりました。翌1997年1月に公文毅が亡くなった後、杏中が旗振り役をして、「公文の本質とは何か」「自分たちは何のために仕事をしているのか」「世の中にどんな貢献をしているのか」と社内に繰り返し問いかけました。2000人の社員を東京、大阪に隔月で全員集合させて、杏中がメッセージを伝えた後に、「自分たちは何のために存在するのか」という議論を徹底的に行ったのです。そこから「The Kumon Way」というバリュー(価値観)を作り上げました。
「私たちが一番大切にするもの、それは『子どもたち一人ひとり』です」という一文から始まるのですが、とにかく私たちは子どもたち、即ち学習者を一番大切に考える。そして二番目が指導者である先生方。そうしたことを明確にした社内の行動規範です。
この「The Kumon Way」をはじめ、企業理念(ミッション・ビジョン・バリュー)は、海外法人でも共通です。徹底に苦労はありますが、国内外の社員交流などにより、浸透に力を注いでいます。
岡島:カリスマ創業者が亡くなり、地域も多様化するなかで、理念や共通価値観を言語化する、また言語化するプロセスそのものも全社を巻き込んで創り上げる、というのは、非常に強いよりどころとなりますよね。
石川:はい。 「The Kumon Way」を打ち出す前は、ある種の大企業病にかかって大切なことを見失っていたようなところがありました。例えば学習者の「数」だけを追い求めてしまう社員もいたのですが、物事を考え、行動するための基準が軸に座ったことで、組織全体としてブレがなくなってきたと思います。
所得水準や人口増減を定点観測して進出タイミングを計る」(井田氏)

岡島:井田さんからは、製品を海外展開されていったご苦労という観点で、中国とベトナムでのご経験をお話しいただけますか。
井田:先ずは即席麺という商品について説明させてください。
日ごろ、何気なく食べられている即席麺ですが、実は極めて国際競争力の高い商品なのです。安価で美味しくて保存が効く。そして高エネルギーです。即席麺はだいたい100gですが、成人の1食分にあたる約400kcalのエネルギーを含有しています。かつ、蛋白質・炭水化物・脂質のバランスが良い。
即席麺の主原料は小麦粉と油でありますが、どちらも世界的に流通しており調達が楽です。また、生産効率も非常に良く製造時間は約30分と短く、製造ロスも少ないです。
味さえ現地化すれば、どんな食文化にも溶け込ませられることも特徴です。日本では醤油味、塩味、味噌味というオーソドックスな味ですが、中国では麻婆豆腐味や担々麺味、ロシアではボルシチ味、タイのトムヤムクン味、インドのカレー味といった具合です。また、宗教の教義に合わせてウシやブタを原材料に使用しない即席麺も可能です。
即席麺は、日本で生まれ、日本で育った商品ですが、1970年頃から世界中の食品会社がそのポテンシャルに目を向け始めました。
そこでまず、日本の即席麺会社が海外進出を始めました。これに競合する形で、現地の食品会社が即席麺の生産に乗り出したほか、国際的に事業展開している欧米系食品会社も参入してきました。結果として、全世界で即席麺が普及しました。
続きまして中国の話に移ります。全世界で即席麺が普及する中、中国だけは1990年ごろまで即席麺の普及が進みませんでした。なぜなら生活水準が低かったためです。また、1989年の天安門事件により海外企業の進出も遅れました。
その結果として、人口13億人の巨大市場が1990年までは手付かずで残りました。サンヨー食品は中国の市場状況を検討したうえで、1993年に中国進出しました。ほぼ同時期に、他の日系即席麺企業も一斉に参入を始めました。しかしながら、サンヨー食品を始め全ての日系即席麺企業が成功を収めることが出来ませんでした。
その理由は、手付かずと思われた中国の即席麺市場でしたが、実は1990年頃に中国進出した台湾系食品会社が、わずか数年で即席麺市場を制覇してしまったからです。
その後、日本メーカーが取った対応は各社各様でありました。苦戦しながらも経営を継続した企業もありましたが、一方、サンヨー食品はすぐに撤退を決めました。その理由は台湾系即席麺会社があまりに強大であり、またブランドも確立していることから、真正面から立ち向かっても勝算が立たないと判断して、戦略を変えるべきとの結論に至ったからです。
岡島:撤退の意思決定は難しいですよね。「もう少し頑張ればブレークスルーするかもしれない」とするのではなく、まずは撤退との見極めはどのようにしてされたのですか。
井田:当社では昔から「見切り千両」という格言をよく引用します。株式取引の世界で、早めに損を確定させることで、その後の損失を防ぐ。それは千両の価値にも相当するという、古くからある言葉です。サンヨー食品は、この言葉を常に念頭に置いている会社で、壁にぶちあたったときに真っ先に検討するのが、撤退・撤収です。そういう経営スタイルをとっています。
大きく戦略を変えられるのは、当社が未上場会社であり、迅速かつ大胆な意思決定をしやすいからです。
岡島:一度、撤退し、次に出る機会を窺っていた、ということですね。
井田:はい。撤退はしたものの、13億人の市場を見逃す手はない。そこで、先発のメーカーがあまりに強いのであれば、いっそ資本提携や業務提携で手を結んでしまおうと、戦略転換したわけです。サンヨー食品は過去もM&A(企業の合併や買収)を積極的に行ってきています。エースコックや日東あられはM&Aでグループ化しており、7カ所所有するゴルフ場のうち5カ所は買収です。自社でゼロから事業を興すことは最も重要ですが、M&Aも有効な戦略の一つと捉えています。中国戦略も、真正面から戦っても負ける相手なら、取り込んでしまおうと決めたわけです。
岡島:一方、エースコックのベトナム進出は正面突破に近いですね。
井田:海外市場への展開というのは非常に難しく、成功確率は10%にも満たないと思うのですが、エースコックのベトナム事業は大成功した数少ない事例と捉えています。成功要因は幾つか挙げられますが、まず、現地の優良企業と良いパートナーシップを結べて合弁会社が始動をしたこと。また進出した時期が最適でした。国際展開においては進出するタイミングは極めて重要な要素です。
例を挙げましょう。食品会社が海外進出する際のポイントとして、進出する国の国民消費力がどのレベルかが重要になります。だいたい現地の平均的な月収が50USドルを超えると、消費者とみなせます。月収が50USドル以下ですと加工食品などを購入することは難しいですが、月収が50USドルを超えるあたりから、ある程度の生活の余裕が生まれ、スーパーマーケットで買い物を始めます。国民がこの生活水準に近づいてきた国に進出し、巨額のマーケティング投資をすると、成功する確率が高まるのです。エースコックのベトナム展開は、まさにその好例と言えます。
サービス産業の場合は、もう少し所得水準が上がってからでないと需要が生まれないかもしれません。ただ、当社が扱うような低価格の消費財は、時期を見極め、かなり早い段階で進出しない限り成功しません。
岡島:世界中で、そうしたタイミングを見つけるための調査をしているわけですね。
井田: そのとおりです。例えばインド。富裕層は別として、平均的な国民の月収は50USドルに満たない状況なので、これからの市場です。
また即席麺事業において、人口も重要なポイントです。現在、中国が13億人、インドが11億人、米国が3億人。米国も移民による人口増が続いており、長期的には人口が4億人に達すると予想されています。
これに、インドネシア(2億人)、ブラジル(2億人)、パキスタン(1億5000万人)、ロシア(1億6000万人)、バングラデシュ(1億4000万人)、ナイジェリア(1億3000万人)などが、成長を期待される市場として控えています。
私どもで成長市場として注目している某国は、現在、外務省から渡航危険情報が発令されており、市場調査すらできない状況です。しかしながら、ある程度の危険やリスクと直面しながら、防弾チョッキとヘルメットを持って市場調査に行くぐらいの覚悟でないと海外では成功できないと思います。
岡島:以前、井田さんから「ヒトは先に進出した食品会社の味に慣れてしまう傾向がある」と伺ったのが印象に残っています。
井田:そうですね。例えば「サッポロ一番みそラーメン」は、味噌味の即席袋麺の中で約70%のシェアを取っています。これは、「サッポロ一番みそラーメン」が美味しいのは勿論ですが、お客様が「その味に慣れた」ために他製品への切り替えが起こらないと思います。
この点では公文教育研究所さんのビジネスとも共通項があると思います。公文式に慣れると、それが標準となり、他社が同じようなビジネスをした場合、二番煎じのようになってしまうのではないでしょうか。
石川:実は公文も中国からは一度、撤退しています。制度上の問題などがあり、独自の教室を開くことは諦めて、上海で学校導入と呼ぶ、契約校の生徒に放課後、公文式の教材で学習するスタイルだけを、続けました。
現在は再進出しているのですが、著作権の保護に頭を悩ませています。ご承知のとおり、中国は法治国家というより、人知国家。ヒトによって法解釈が全く異なるので、一筋縄にはいきません。最初に進出した際の教材がコピーされて、「日本の公文公が作った歴史ある」とか「画期的な」といったうたい文句で、インターネットなどで堂々と販売されている現状があります。
現地の企業とパートナーシップを組んで・・・という話も出ましたが、当社はここでも一度、痛い目に遭っています。インドネシアでは合弁会社を設立して事業展開したのですが、フランチャイザー(パートナー)のフランチャイジーの締め付けや利益優先主義的な考え方、それは当社の考え方とは相反するため、現在は解消し、どの国に進出する際も基本的には100%自己資本で子会社を作ることにしています。
「製品やサービスではなく、『経営品質』のグローバル化が課題」(浜田氏)

岡島:合弁か自己資本かというのは皆さん、悩まれるところと思います。関連して浜田さんに2点、ご質問させてください。一つは、「コールド・ストーン・クリーマリー」ほか、海外のサービス業の日本のパートナーとして展開されていますが、そこにどのような苦労があるか、ということ。もう一つは、パートナーとして組む際の相手先選びの基準があれば、お聞かせください。
浜田:リヴァンプと、かつて仕事をしたデル・コンピュータでは全く異なります。
リヴァンプでは、(コールド・ストーン・クリーマリーや・クリーム・ドーナツから)フランチャイズ権をもらってロッテとの共同投資で運営しています。いずれも日が浅いので、正直に言って、まだそれほどの苦労が出てきているとはいえません。ブームになって売れていますので。
では何に気を配ったか、最初からうまく立ち上がったのか、ということですが、いずれもコンセプトもサービスも味も何も変えず、そのまま持ってきました。これは、何も変えなくても、国境を越えた日本でも充分な人気が得られるだろうという“目利き”をしたからです。
岡島:全て(米国での)「標準」スタイルに順じており、「現地化」はされていない、ということですか。
浜田:そのとおりです。逆にいうと、適切なマーケティングをして日本でヒトを集められるか、経営陣が本国で作られたオリジナルの製品やコンセプトを本気で愛せるか、自分のものとできるか、といったところがポイントとなります。
そのため、立ち上げ前にはスタッフ合宿などをして、企業理念(バリューやミッション)を読み込み、皆でその内容を議論するなど、理解のためのプロセスをしっかりと取りました。
岡島:先ほどの公文のお話同様、理念の浸透が最も重要ということですね。
浜田:はい。クリスピー・クリーム・ドーナツは、開店から11カ月しか経っていませんから、まだ、得意気にはできません。ただ、(日本から)他の国に行くときも、文化や言語の壁を越え、普遍的な価値観として共有できるサービスや製品であれば成功の確率は高いのではないでしょうか。
デル・コンピュータの話もしましょう。デルの製品はパソコンですから国ごとに仕様は変えず、売り上げ規模が3兆〜4兆円まで規模化し、余裕がでてきたところで国別の製品を用意し始めました。
デルの立ち上げは非常に苦労しました。私は当時、米国でグローバル企業のコンサルティングをしていたのですが、その過程でデル・コンピュータの幹部と出会い、「日本進出で苦戦しているので手を貸してくれ」と言われ、(最初はコンサルタントとして)立ち上げから関与しました。
このとき何が一番の問題だったかというと文化の衝突でした。デルの本拠地は米国テキサス州ですが、ここはテキサス中心主義が浸透しています。テキサスこそが世界の中心だ、という考え方です。
日本では、IT関連企業からヒトを集めてきて組織化したのですが、このテキサス中心主義に代表されるようなモノの考え方が全く理解されませんでした。働き方も違うし、ビジネスモデルや企業理念も、まるで浸透せず、次第に日米双方で疑心暗鬼になるという非常に良くない状況でした。
そこでまず、合宿を行いました。私は、実は合宿が大好きな男でして。
岡島:グロービスも合宿カルチャーです。
浜田:三浦半島の先のほうに、全員バスに乗せていきました。
岡島:理念を壁に飾ったお題目としておくのではなく、理念が作られた背景や作った人たちの想い、理念の解釈方法のようなものは、合宿の形を使うと、とても伝わりやすいですよね。
浜田:欧米の企業は日本と比べて海外進出が得意ですが、これは元々、多様性のうえに成り立っていて、(日本のように、単一の言語や文化に下支えされ、多少、言葉足らずでも行間を読んで理解されるようなことはなく)きちんと説明したり、文化や習慣の壁を超える普遍的な価値を作り上げない限り、他者には理解してもらえないという前提があるからではないでしょうか。世界中どこでも通用するマネジメントシステムを高い完成度で用意する、或いは進出しながら作っていく。それがとても上手いように感じます。
例えば私は、中国の大連で千数百人規模のサポートセンターを作ったのですが、この際、日本企業から雪崩のように人材を奪い取り、短期間で立ち上げることができました。
岡島:日本企業では皆、働きたがらない?
浜田:中国では全く人気がありません。中国に進出している日本企業では、経営陣ほか管理者クラスは大半が日本人で、日本語だけでやりとりをしています。現地社員との処遇の差があまりに明白で、中国人は「日本企業にいても出世できる可能性はない」と感じます。ですから、機会さえあれば欧米の企業に転職したいと考えているわけです。従って、良い人材は日本企業には集まらないし、残らない。これが決定的な弱みで、早く乗り越えて欲しいと願っています。
岡島:国際展開するうえで、普遍的なバリューを徹底的に浸透させることは、どの企業にとっても重要な課題ですね。
井田:冒頭で岡島さんが、製造業と比べてサービス業は国際展開が難しいと“伝統的に”捉えられてきた、という話をされました。その理由を考えてみました。
メーカーの場合は商品力が大切ですから、それを全面に押し出せばいいと思います。商品力こそが、“普遍的なバリュー”となります。商品以外のオペレーション等は現地法人に任せればいい。トヨタ自動車などが好例でしょう。
当社も同じです。成功しているベトナムでも、日本から派遣された社員はマネジメントに徹して、セールスや代金回収、マーケティングなどのオペレーションは現地採用の社員に任せています。
ところがサービス業の場合、オペレーションにこそ付加価値があり、結果的にオペレーションを現地社員になかなか任せられないのではないでしょうか?
オペレーションに関して、製造業とサービス業の本質的な差異があるように思います。
石川:やはり先ほどからの議論のとおり、理念を現地法人に浸透させる必要があるのでしょうね。そしてその理念は普遍的で各国でも共有できるものでなくてはならない。そうでなければ、おっしゃるとおり日本で提供するのと同等の品質を海外では提供できなくなってしまう。
公文の場合には、「子どもは宝である」ということ。それが万国共通の価値です。とりわけ発展途上国では、先生方が、この子どもたちが国を変革してくれるはずという意識で指導してくれています。
価値観の浸透によって、公文の海外法人の(現地採用の)社員の定着率は高まってきました。今後の課題は、「社長は結局、日本人が務めるのでしょう?」ということにせず、現地採用の社員からも経営者が出てくるような、そういう人材教育、キャリアパスを設けることと認識しています。
岡島:それが、浜田さんがよくおっしゃっている、経営のグローバル視点ということでしょうか。
浜田:皆さんが言われるように、日本の製品やサービスは、ものすごく質が高い。コンセプトも普遍的に受け入れられているものがたくさんあります。
となると日本企業に足りないものは、個人的な意見ですが、やはり「経営」だと思います。経営者。
英語は世界の共通語になっているので、英語がある程度できるというのは当然ですが、成功したグローバル企業を見ていると、人事制度も全世界共通です。報酬体系も共通です。国ごとに消費者価格の水準が違いますから、その意味での調整はありますが、基本的にはすべて共通です。
デル・コンピュータでは様々な国籍の社員が入り乱れ、世界があたかも一つの国であるようにして動き回っていました。誰も、「現地社員」というような呼び方はしないし、最初から分け隔てがありません。ですから日本人の私が、「おまえ、中国の社長をやれ」とか、「韓国の社長も兼任しろ」などと言われることが、何の違和感もなく受け止められ、大連のサポートセンター立ち上げ時も、最初の社長は日本人、次に中国人。中国人社長は業績を上げられなかったので、マレーシア人を異動させてきて、と、人材が世界で遍在していました。日本法人も1900人が働いていましたが、ここにも16カ国の人がいました。
これはある種の理想郷に過ぎないかもしれません。けれど、多様性を一つの経営システムの下に統合するということを、本気でやっており、その結果として世界中から良い人材が集まってきていたのは厳然たる事実です。
世界を一つの市場と考え、ビジネスを展開しようと考えるのであれば、そこまでのことをやろうという気概が必要なように私は思います。
岡島:普遍的なバリューの浸透があって、従業員の満足度が向上し、それが顧客満足度につながる。そうした、サービス・プロフィット・チェーンの構築が、海外展開においても不可欠ということなのでしょう。
石川:そうですね。先ほども言いましたが、根本にあるのは、子どもたちが生き生きと伸びていくこと。自信のなかった子どもがどんどん自信を付けていくこと。そういうプロセスを可視化することで、みんなが元気になる。その循環だと思いますね。
「処方箋は百社百様だが、先駆者の取り組みが大きなヒントになる」(岡島氏)

岡島:まだまだ伺いたいことはたくさんあるのですが、会場からもご質問をいただきたいと思いますので、最後にひと言ずつ、お願いします。会社の宣伝でも結構です(会場笑)。
ドーナツとアイスクリームをたくさん買っていただき、風邪が流行っていますので、(プラマイゼロのヒット商品である)加湿器を買ってください。
今日は率直に考えを述べさせていただきました。皆さん、世界に出て行くのでしたら、どうぞ「世界は一つ」という思いを持ってください。私も、「“現地社員”などと言っていたらダメだ」などと吠えていますけど、実際には自分も(そうした表現を)たまに使ってしまうんです。本当に情けないことですけれども。「あの国は格下」というように見ていたら、相手は全部お見通しです。結果として良い人材は集まりません。
井田:私からは、ガバナンスに関してお話いたします。
昨今、食品業界では多くの不祥事が発覚しております。コンプライアンス、即ち倫理観を持ってルールを守ることは当たり前の話ですから、法律を犯した企業に厳罰が下ることは当然であります。ただ、法令遵守を貫くにはガバナンスが必要で、当社のような同族会社は特に注意が必要です。同族企業の中には、役員の大部分を同族が占めて、結果的にガバナンスに問題がある企業が多いと思いますし、最近、不祥事を起こした企業の多くがこのようなケースです。
サンヨー食品には現在13名の役員がいますが、井田家出身の役員は私一人だけです。残りの12名はプロパーの社員や銀行の出身者です。同族企業にありがちな甘えを排除して、コンプライアンスを守れる体制を敷いているわけです。
先ほど、上場企業と比べて意思決定が早いという話をしましたが、「リスクを取って海外展開したい」と考えたら、リスクの範囲を限定し、きちんと説明をして役員を説得しない限り、社長であっても独断で前に進むことはできません。同族企業においては、ガバナンスを徹底することが、不祥事を食い止める重要な要素であると思っています。
石川:公文はグローバル企業として緒に就いたばかりで、まだまだ日本中心的な考え方があります。先ほどリヴァンプの浜田さんがおっしゃったような、全世界共通の人事制度は、今年から取りかかりました。IT関連でも共通のプラットフォームを持つための議論が、やっとスタートしたという状況です。
我々が、誇れるのは、公文の歴史は教材改訂の歴史だということです。つまり、常に教材をより良いものにしていく。どんな子どもも伸びる、という考え方が源泉にあるので、子どもがつまずくとしたら、それは子どものせいではなく、教材が悪いのではないかと考え、改良を重ねてきました。
岡島:ありがとうございます。では会場から、ご質問をどうぞ。
会場:製品やサービスをローカライズ(現地化)する際、大企業であれば大規模なマーケティングが行えますが、ベンチャー企業には難しい。どのようにしてストライクゾーンを見つけていければいいのでしょうか
井田:とにかく先ずは進出してみるしかないと思います。日本にいて考えていても何も始まりません。海外に出てみるとよく分かるのですが、日本にいては“米国以外の海外の情報”はほとんど入ってきません。日本に入ってくる海外情報の大部分は米国の情報なのです。アジア、中東、アフリカなどの情報は実際に現地に行ってみないと把握できません。小さい投資でもいいから、まず現地で事業を始めてみるより他ないと思います。
先ほど、中国から一度、撤退したという話をしましたが、なぜ速やかに撤退できたかというと、非常に小さい投資額だったからです。「この投資に社運を賭ける」ということではなく、撤退しやすい小さい投資から進出して、その後は機動的に対応するのです。もちろん進出に先立っての市場調査は重要です。サンヨー食品では進出予定の国に市場調査スタッフを派遣していますが、派遣する期間は数カ月です。そのくらいの期間は現地に張りついて、正確な現地情報を理解したうえで迅速に進出することです。
石川:公文の場合には、数学教材は全世界で同じですし、言語系の教材も、例えばポルトガル語の国語は、ポルトガル語圏では全部同じものを使っています。現地化というより、標準化したものを横展開している形です。
浜田:日本でそれなりの評価を得た製品やサービスというのは、その時点でかなりのグローバルスタンダード(世界標準)になっていると思います。ポイントは先にも申し上げたように、経営の品質がグローバルスタンダードになっていないことでしょう。年功序列に代表される人事制度や意志決定のプロセス、男女差別など、そこが磨かれていない。磨かれていないから外には持っていけない。持っていけないということは、現地化もできない。そこが問題なんです。
ちなみに海外の大企業の場合、新しい国に討って出る際には、まず第一陣として「交渉チーム」のような部隊が行きます。まず国や地域と交渉して、税制免除など可能な限りの優遇措置を引き出してから一旦、引き上げる。その後、「オペレーションチーム」が入ります。ヘッドハンターを使って採用を進めたり、オフィスビルを探して契約したりします。そして、(敢えてこの表現を使いますが)現地採用の社員によってヒトや組織のローカライゼーションをすすめていくわけです。
このように、現地法人立ち上げのプロセスを仕組みとして持っていて、過去の成功や失敗の事例が形式知化されている。ですから、立ち上げチームは徐々に専門チーム化していきます。
岡島:もう1つだけ、ご質問をどうぞ。
会場:企業の国際化が進展するということは、人材の国際競争が進むということでもあると認識しています。そこで浜田さんに質問ですが、先ほど日本の経営や経営者が弱いというお話がありましたが、日本人自身、特にリーダーをどう強くしていくべきか、お考えを聞かせてください。
浜田:私自身も明確な回答は持っていません。私は現在、経済同友会の教育問題委員会で副委員長を務めているのですが、今年のテーマがまさに「国際的なリーダーをどうやって育てるか」ということで、毎月、議論しています。
その過程で今、考えているのが、教育も小学校ぐらいまで遡らなければダメなのではないか、ということです。
明らかに我々、日本人に欠けているのは、人生観というか、人生に対するダイナミズムの欠如です。
こういう喩えは失礼にあたるかもしれないのですが、リストラされて自殺してしまうヒトがいます。それって日本人だけではないかと思うのです。精神的に追い込まれ、鬱状態になってしまっているのでしょうけれど、そんなことで命を失うなんて、この国の外ではあり得ません。例えば、ニューヨークで職を失ったのならば、もっと物価の安いアトランタやアリゾナに移って仕事を探す。日本で言えば、伊豆とか下田を車で走っていれば、「従業員募集」の張り紙がたくさん目につきます。
ダイナミズム、自分の人生をどう楽しく生きるかということについて自ら選択肢を狭めてしまっているように思うのです。そして、その根を探ると、(偏差値など限られた軸だけでヒトの優劣を評価する)学校教育に行き着いてしまうのです。
世界のどこに行っても活躍できるダイナミックなヒトを作るには、「大企業の名刺を持っているのが誇らしい」とか「三菱がいい、住友がいい、いやいや三井だ」とか、そうした価値観から変えていかなければならない。左遷されて悔しかったら辞めればいいじゃないですか、辞めてもっと良い職を探せばいいじゃないですか。
「あいつはすげぇな」と思えるヒトっていますよね。たとえば最近では、スポーツの世界に沢山います。ああいうヒトが、経済界からは誰も出てこないことに危機感を持たなければならないと考えています。自戒も込めて。
経済界と政界だけがグローバルプレイヤーがいない。今の日本の上場企業の社長で例えばイタリアの国営会社の社長をやれる人がいるかというと1人もいない。ロシアに行って社長になれる人がいるかというと1人もいない。私だってできない。情けないと思います。その根源は一つは教育制度だと考え、教育問題に焦点を当てています。50年ぐらいかかるかもしれませんね。残念ですが。でも、やらなければいけないと思っています。
岡島:サービス業が国境を越えるためには、どうしればいいのか、というテーマでパネルディスカッションをしてまいりました。「これをすれば」という唯一の処方箋というのはないのだと思いますが、パネリストの皆様の具体的な体験から、多くの現実的なヒントをいただく議論になったと思っております。
3人のパネリストの皆様、そして会場の皆様、ありがとうございました。最後に3人のパネリストの方に盛大な拍手をお送りください。ありがとうございました。

























.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)
.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)
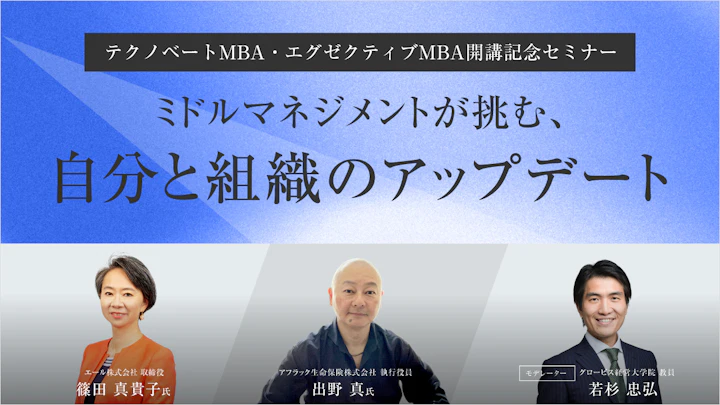
.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)


.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)














.png?fm=webp&fit=clip&w=720)
.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)




