
これまでのコラムで、イノベーションを起こすためには、その“種”となる豊かな発想が必要であること。それには組織や個々人のクリエイティビティを妨げる「3つの罠」を乗り越える必要があることを述べてきました。そして、「未開発能力の存在」「末端化の落とし穴」「短期目線の圧力」という3つの罠を越えるためには、「(固定概念に囚われない)ルールブレイクシンキングの力を高める」、「組織の垣根を越え、“クリエイティブ・フリクション”を迎え撃つ姿勢を持つ」、「自社の理念をベースに、個人のLike to(やりたい想い)を見つけ、育む」ことが求められると、前3回のコラムの中で提示しました。
(前回のコラム「時間軸の罠—短期目線の圧力を越える」はこちら)
ただ、そうは言っても、いずれもそう簡単に実現できるものではないこともまた事実と認識しています。様々な会社の経営陣やミドルマネジャーとの対話する中でも「既存の常識や前提に囚われていて新しいビジネスモデルが描けない」「部門間での衝突を避け穏便に済ませようとし結果として大胆な発想が生まれない」「会社のタスク(=やらねばならないこと)以上のことに取り組む志を失ってしまっている」といった実態はよく耳にするところです。
「自由に発想していい」「組織横断的にモノを考えろ」と号令するだけではヒトも組織も変わらず、動かないのは自明のこと。組織の構成員を動機づけるHRM(人的資源管理)の施策や、お金や設備などのリソースを割り当てる戦略的判断など、様々な取り組みが、そうした理想に整合する形でシステマチックに導入され、機動的に回り、一定以上の成果が出て初めてヒトの行動変容がもたらされ、また、組織文化として定着するものだからです。
では、継続的にイノベーティブな製品やサービスを生み出している企業は、どのようなシステムを作り、クリエイティビティを引き出すことを実現しているのか——。参考事例の一つとして、IT業界で気を吐き続けている「サイバーエージェント」を取り上げ、その一端を明らかにしてみたいと思います。
上場後、成功事業が出てこない。社員間には次第に“しらけ”のムードが蔓延し・・・
サイバーエージェントは1998年に藤田晋代表取締役社長によって設立。インターネットを事業領域に急成長を遂げてきました。2000年マザーズ上場。直近2012年の連結決算で社員数2500名、売上1411億円、営業利益174億円の規模となっています。提供する商品・サービスも、当初の広告代理事業から今や、ブログ、アプリ、ゲーム等、多種多様におよび、読者の皆さんも日本のインターネット産業をけん引する一社として認識されていると思います。
ただ、その成長への軌跡は、業績数値から見て取れる以上に困難なものだったようです。創業期のがむしゃらなエネルギーや社員間の創発的な仕事ぶりが鈍化していく中、いかに新規事業を生み出し、絶え間ない成長を続ける今現在の組織風土を作り上げてきたか。同社取締役人事本部長・曽山哲人さんへのインタビューから浮き彫りにしていきます。
井上:2000年3月24日のマザーズ上場以降の経緯からお聞かせください。上場後、赤字を解消できず、社員のモチベーションが上がらず、退職率も30%を超える状態に陥ったと聞いています。上場で得た資金で様々な領域に投資するも新たな事業の柱はなかなか生まれない・・・今から振り返ると社内はどのような空気感だったのでしょうか?
曽山:私は1999年の入社以来、2004年まではずっと広告営業をやっていました。マネジャー、シニアマネジャーという役割で、シニアマネジャーのときで15人ぐらいのメンバーを抱えていたと思います。インターネット広告事業本部統括を経て、2005年に新設された人事本部の本部長として異動しました。
上場後のサイバーエージェントですが、調達した資金でメディア事業を立ち上げようとトップダウンで次から次へと新規事業を立ち上げていました。ただ、経営陣の誰かが考え、「これでいいんじゃないか」ということになると事業が生まれるので、作った人たち以外の社員にとっては唐突感がある。しかも、特に明確な基準が示されることなくメンバーの抜擢が行われるため、選ばれなかった側からすると「死ぬほど頑張っているのに何で僕じゃないんだろう?」という疑問が生じてしまう。
「そんなに新規事業に関わりたいなら手を挙げればいいじゃん」と思われるかもしれないですが、公式に意見を言える場もないので、その気持ちをうまく消化できないんですね。全般的にそんな“しらけ”のムードが蔓延していました。
おっしゃるところの、退職率30%程度だったのはこの時期です。全員が不幸なわけではなく、新規事業に抜擢された“ご機嫌”な人と、それを面白く思わない“不機嫌”な人が同居している。ただ、抜擢されるのは少数なので、ご機嫌な人のほうがマイノリティという状況。私は日々の仕事自体は楽しく感じており、組織へのロイヤリティはそれでも高いほうだったと思うのですが、「中途採用だと抜擢もされないよな」という“しらけ”の気持ちは自分の中にもあったような気がします。
井上:しらけ、ですか。
曽山:はい。今でも私たちがよく使う言葉の一つです。とにかく、しらけは排除しなければ、と。
しかも当時は、作っても作っても新規事業がうまくいかない。そのことが、しらけの空気をさらに強めていました。売上が増えない。収益化しない。そうすると、その事業と遂行する人材とを選んだ経営陣に対する不満が噴出するんですね。
井上:当時、立ち上げた事業としてどのようなものがあったのでしょうか?
曽山:日本のファン向けにメジャーリーグのウェブサイトを開設するとか、自動車のネット販売とか・・・チャレンジしたことの一つひとつは面白いんですよ。そして皆、チャレンジすることの意義は理解している。ただ、説明が不十分で結果も出ていないから、組織全体としてそういうことに前のめりな感じが生まれない。大いなる自己矛盾ですよね。
で、今にして思えば、経営陣がこの“しらけ”を鋭敏に感じとって対処しなければならなかったのですが、それが十分にはできているとはいえなかったのかもしれません。しらけへの対処は理屈だけで云々できるものでもないので、人事や経営企画が“優等生”であるほど、かえって難しいのではないかなと思います。
井上:そうした悪循環、組織の閉塞感みたいなものを、どのように打破されてきたのですか?
新規事業に失敗した人材の流出、挑戦マインドの喪失。普通はそこで挑戦を止めてしまう
曽山:ビジョンの明確化からでした。当時、売上自体は伸びていたのですが、先行投資によりまだ赤字でしたので社内外からの批判に晒されていました。批判に影響されて辞めてしまう人も増えており、特に、会社として辞めてほしくないという人からいなくなっていく。その退職率の高止まりは致命傷だということで、役員合宿で議論をし、組織を今一度、束ね直すものとして2003年に「21世紀を代表する会社を創る」というビジョンが明示されたのです。またその後、2006年には行動規範となるミッションステートメントも出しています。
また、「maxims(マキシムズ)」という、我々が大切にしたい価値観も明確化し、小冊子として社員が持ち歩けるようにしました。

maxims(マキシムズ)
・オールウェイズ・ポジティブ ネバーギブ・アップ
・行動者の方が、カッコいい
・新しい産業を、自らの手で創るという誇り
・一流の人材がつくる、一流の会社
・挑戦した結果の敗者には、セカンドチャンスを
・最強のブランドをめざす
・常にチャレンジ、常に成長
・若い力とインターネットで日本を元気に
井上:ビジョンやミッションなど、自分たちがどこに向かうのか、長期的な視点を持てる共通のゴールを定めたことで、短期目線での目先の利益に束縛されるような意思決定が行われることを回避する素地ができたのでしょうね。ちなみに行動規範であるマキシムズのほうは、どのような経緯で作成することになったのでしょうか?
曽山:ビジョンが定められた役員合宿の後に、社内横断的に組織された「バージョンアップ委員会」というタスクフォースに取りまとめが委ねられました。委員会に社長の藤田は入らず、副社長主導のメンバーで自分たちが大切にしたいことを言葉にし、その草案に最後は藤田が手を入れるというスタイルで作りました。
私も委員の一人でしたが、ボトムアップで作り、最後はトップダウンで決める、というのは非常に良いプロセスだったと思っています。「社員みんなの声を聞きました」とボトムアップのみで作るのは一見すると民主的ですが、最後にトップが魂を込めなければ、決めた価値観を組織全体に本当に浸透させるところまでいかないと思うのです。
井上:バージョンアップ委員会というのは、マキシムズを作るためだけの時限的な組織だったのでしょうか?
曽山:いえ。ここでは、顕在化されていない社員の本音など、サイバーエージェントの“生の声”を拾うということに取り組んでいました。各事業部門のトップ7〜8名が、それぞれの現場でどんなことが言われているかを拾い、経営陣にぶつける役割を果たしたのです。そこで先ほど申し上げたような「新規事業に挑戦したいが、選ばれる基準が不透明で納得感に欠ける」とか、「中途採用にももっとチャンスがほしい」というような不満が可視化されていきました。
また例えば、新規事業がうまく行かず、撤退となったときに起きている人事的な課題も見えてきました。事業のクローズと同時に、「それは私たちに駄目出しということですね」と受け取った、立ち上げ要員として抜擢した社員が皆、辞めてしまうのです。5人が失敗すると、5人が辞める。とは言え、新規事業をやらせると辞める人が出るからと新規事業をやらなければ、会社を将来的に成長させる芽も生まれない。完全に衰退のサイクルですよね。
井上:負のスパイラルですね。
曽山:日本企業のほとんどが、このスパイラルに一度は入っていて、その結果として新規事業に臆するマインドができてしまっているように感じます。
でも、新しい事業を作るって、そんなに甘くないですよね。失敗は一定以上の比率で起きるわけで、それより問題は、失敗の結果として何かを学んだ人材を流出させてしまっているほうだ、と。人は同じ失敗はしませんから、次の挑戦ではそういう人材の成功確率はむしろ上がるはずなんです。
井上:おっしゃるとおりです。
曽山:だから僕らの場合は、むしろ恐れず、新規事業をどんどん作ってくぞということを決めた。そのための仕組みの一つが社員から新規事業のアイディアを公募する制度「ジギョつく」でした。
当初は様子見だった社員。今では5人に1人が新規事業立案に参加するように
井上:ジギョつくの始動は確か、ビジョンの再制定と同じ2003年ですよね。

曽山:2003年に決まって、2004年に第一回が開催されました。ほぼ10年前ですね。当初の応募は14件。過半の社員が様子見、という感じでした。それが2012年は800件にまで増えました。
井上:10年かけて、社員が挑戦する風土を定着させていった・・・
曽山:はい。それも単に公募制度を作って待っているだけではダメで、すごく大切なこととして、“失敗しても良いから思いっきり挑戦してほしい”という安心感の醸成があったと思います。マキシムズに明記されている“挑戦した結果の敗者には、セカンドチャンスを”が顕著ですが、がんばって失敗した人にはセカンドチャンスが用意されている、と会社から提示されたことは非常に勇気をもらえることだったと一社員としても思います。
そして制度面ですね。真に事業化まで持っていくためには、風土を変えるだけでは足りません。アイディアを実行に落とし込む上での障害を取り除くことも必要でした。例えば、人事異動等が典型ですが、経営のフォローがなければ書いたプランのエグゼキューション(実行)はできませんから。
井上:ジギョつくは、そうした意味からも大きな経営の転換を象徴する制度なわけですね。イノベーション生み出すために誰でも手を挙げられる場を作り、しかも単にアイディアコンテストに終わらせず、優勝者には「社長のイス」も用意して、本当に計画を実行する機会を与えた。これは大変な経営判断だと思います。
参加する社員の方々はビジョンを基軸にしつつ、自分自身がこれをやりたい!という想いを見つけ育む。しかも必死にやった結果であれば失敗も許される。そうしたことを経営が能書きとして言うだけでなく、本当に有言実行でやってくれることで、信頼が高まり、組織文化が変わり、また、個々人の固定概念や前提、常識に囚われないでゼロベースで何をするべきなのかを考え抜く力というのが高まっていったのではないでしょうか。
曽山:そうですね。応募数は10年間続ける中で徐々に増えてきた感じです。それまで一人で複数応募していいという制度だったものを、今年から一人一案にしたため、目先の応募数は350件と減りましたが、サイバーエージェント単体の社員数1500名に対してこの数ですから、5人に1人の社員が新規事業立案に挑戦してくれていることになります。
井上:すごい変化ですね。応募数を増やすために他に何か工夫はされたのでしょうか。
曽山:応募フォーマットを簡単にしました。エクセルに基本的なこと5項目を文字ベースで書くだけの体裁になっています。
今の日本企業のイノベーションを生む仕掛けって難しすぎるケースが多いと思うんですね。論理的にしっかりとまとまったきれいなパワーポイントの資料を提出させることが多いですが、それがイノベーションにつながるとは限らない。それと、現場は忙しいですから、社員にジギョつくにかかりっきりになってもらいたくないという意図もありました。書類審査とプレゼンまでの時間は2週間程度で、残念ながら受賞できなかった場合でも、すぐに切り替えて仕事に集中できるようにしています。
今年、一人一案までと決めたのと同時に、応募フォーマットはこれまでの5項目をなくし、パワーポイントに事業モデルを図式化するというものに変更しより提案内容をわかりやすくする改善をしています。
井上:変更のポイントも面白いですね。ルールブレイクシンキングという固定概念を打破する思考プロセスにおいては、発想を拡げて様々な要素を幅広く考えた上で、統合的に考えることが必要なんですね。その意味では新しいジギョつくの応募フォーマットにおいて「事業モデルの絵を描く」ということで統合的思考を求めていくということになっていると思います。それにしても、凄い数の応募ですよね。
曽山:はい。おそらく日本でいちばん、新規事業の案を出している会社になっているのではないかと思います(笑)。ただ過去を振り返ると、ジギョつくから事業としてのホームランが生み出せたかというとそうではないのです・・・
※応募数は増えたものの、グループの柱となるような事業を作るまでには至らなかったという「ジギョつく」。これを打開するためサイバーエージェントが打った次なる手は。本連載の最終回はこちら。






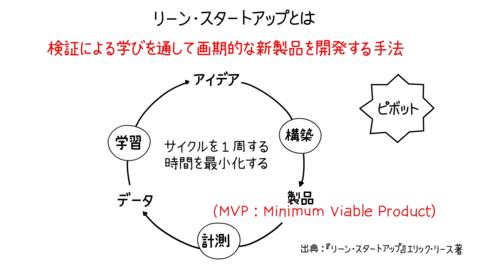































.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)
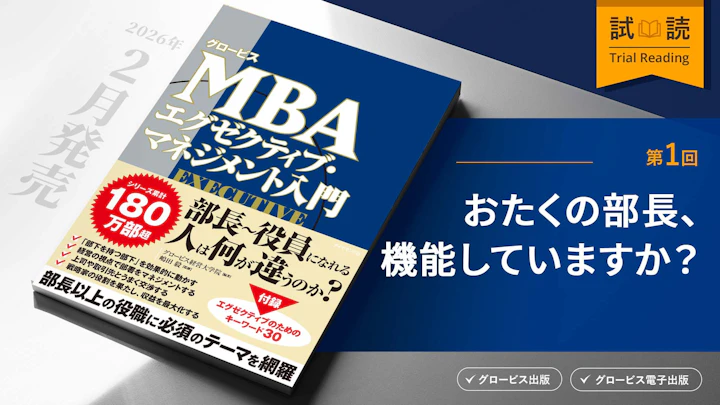
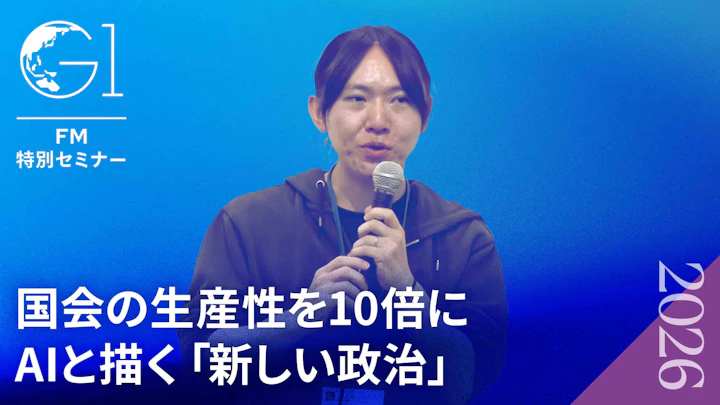


.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)
