
0:59:48
割引情報をチェック!

AI BUSINESS SHIFT 第8回 機能別戦略編:AI時代の営業現場のリアル
本コースは、リーダー・マネージャー層を対象に、AIのマネジメント活用・組織活用を体系的に学ぶ『AI BUSINESS SHIFTシリーズ(全12回)』の第8回です。 第8回「機能別戦略編:AI時代の営業現場のリアル」では、AIが営業現場にどのような変化をもたらしているのか、営業担当者・営業マネージャー・組織としての役割や戦略が、AIによってどう進化していくのかを、営業プロセスの分解や実際の現場事例を通じて学びます。 ■こんな方におすすめ ・AIを活用した営業活動の最新動向や現場のリアルを知りたい方 ・営業現場の変化に直面している営業マネージャー・現場リーダーの方 ・AI時代における営業戦略や営業マネジメントのあり方を学びたい方 ■AIシフトシリーズとは? 『AI BUSINESS SHIFTシリーズ』は以下の3部構成で設計された全12回のシリーズです。(順次公開) https://unlimited.globis.co.jp/ja/tags/AI%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E3%82%B7%E3%83%95%E3%83%88 ・基礎編(第1回〜3回):リーダーやマネージャーに求められる、AI時代の基礎的なリテラシーの強化を目的としたコース ・マネジメント編(第4回〜7回):AI時代のリーダーシップや組織変革を中心に学ぶコース ・機能別戦略編(第8回〜12回):AI時代における機能別での戦略のあり方を中心に学ぶコース より実践的なAIツールの活用法について学びたい方は『AI WORK SHIFTシリーズ』をご視聴ください。 https://unlimited.globis.co.jp/ja/search?tag=AI%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%95%E3%83%88 ※本コースは、AIのマネジメント活用を学ぶ「AIビジネスシフト」シリーズの一環として提供しています。 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2026年2月制作)
会員限定

マネジャーのための仕事の任せ方
「仕事を任せると失敗が怖い」「自分でやった方が早い」マネージャーとしてメンバーやチームの力を引き出しながら成果を上げるには、どのように仕事を任せていけば良いのでしょうか? 変化の激しい時代において、マネージャーとして成果を上げ続けるためには、メンバーの個性や特性を理解し、それに合わせた効果的な任せ方を身につけることが重要です。このコースでは、ソーシャルスタイル理論を活用してメンバーごとに最適なアプローチを学びます。「任せる力」を高めることで、チーム全体の成長を促進し、自身のリーダーシップを発揮できるようになっていきます。 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2024年12月制作)
会員限定

AI時代の個人力
AIが仕事や社会の前提を変え続ける今、最も求められるのは「他者に代替されない個としての力」“個人力”です。 本コースでは、澤円氏の著書『個人力』をもとに、AI時代をしなやかに生き抜くための「前向きな自己中戦略」を学びます。 テーマは、「Being(ありたい自分)」を中心に据え、自ら考え(Think)、変化し(Transform)、協働する(Collaborate)ことで、自分らしい価値を発揮していくこと。 リスキリングやAI活用が叫ばれる今こそ、スキルより先に“自分の軸”を問うことが重要です。 あなたは何を大切にし、どんな未来を描きたいのか? このコースは、あなたが“ありたい自分”として生き、キャリアをデザインしていくための思考と行動のガイドになります。 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2025年11月制作)
会員限定
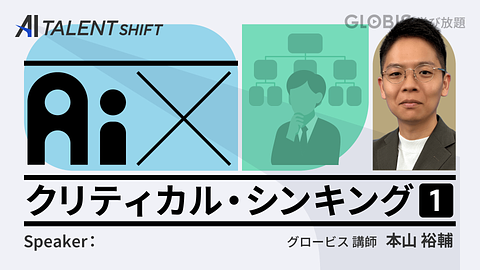
【AI×クリティカル・シンキング】①イシューと枠組みでプロンプトを磨く
生成AIから期待する回答を引き出せず、試行錯誤を重ねていませんか。 本コースでは、生成AI活用の質を高める鍵として、クリティカル・シンキングの視点からイシュー設定と枠組みを押さえる重要性を解説します。 目的に直結する問いの立て方や、プロンプトに落とし込む際の実践ポイントを具体例とともに学ぶことで、AIをより思考のパートナーとして活用できるようになります。 生成AIを業務で使い始めた方から、活用を一段深めたい方まで、再現性あるプロンプト設計を身につけたい方におすすめの内容です。 さらに学びを深めたい方は、こちらも合わせてご覧ください。 【AI×クリティカル・シンキング】②AIの弱点との向き合い方 https://unlimited.globis.co.jp/ja/courses/cdfe41e3/learn/steps/62198 ※本コースは、AI時代のビジネススキルを学ぶ「AIタレントシフト」シリーズの一環として提供しています。 https://unlimited.globis.co.jp/ja/tags/AI%E3%82%BF%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%B7%E3%83%95%E3%83%88 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2026年1月制作)
会員限定

リーダーの挑戦⑤ 藤田晋氏(サイバーエージェント代表取締役)
グロービス経営大学院学長の堀義人が、日本を代表するビジネスリーダーに5つの質問(能力開発/挑戦/試練/仲間/志)を投げかけ、その人生哲学を解き明かします。第5回目のゲストは、サイバーエージェント代表取締役の藤田晋氏。起業の理由、経営をどうやって学んだか、アメーバブログ・ABEMAの立ち上げ、経営チームづくりについてなど聞いていきます。(肩書きは2020年12月11日撮影当時のもの) 藤田 晋 サイバーエージェント 代表取締役 堀 義人 グロービス経営大学院 学長 グロービス・キャピタル・パートナーズ 代表パートナー
会員限定

ビジネスパーソンのための睡眠スキル ~問題解決編 前編 なぜ眠れないのか?~
「仕事が終わらないから睡眠時間を少し削ろう…」「業務時間中なかなか集中できない…」「毎日朝起きるのがつらい…」。 あなたはこのような経験をしたことはありませんか? 仕事やプライベートの時間をやりくりするために、真っ先に削りがちなのが「睡眠」時間。 実は今、日本社会は世界と比較して「最も眠らない国」だということもわかってきています。 慢性的な睡眠不足は、心身の健康に悪影響なだけでなく、仕事のパフォーマンスにも当然大きな影響を与え、社会全体の経済損失につながります。 このコースでは、基本的な睡眠リテラシーを学んだ後の「問題解決編」として、「なぜ多くのビジネスパーソンは眠れないのか?」について解説していきます。 ▼本コースで学べる主な内容 ・そもそも眠れないことは何が問題なのか? ・眠れなくなってしまう原因とは? 睡眠不足の原因は認知機能の問題にありました。 自身の睡眠不足に対し、正しく「気づき・理解し・行動を変える」第一歩を踏み出しましょう。 ▼関連コース ・ビジネスパーソンのための睡眠スキル ~リテラシー編~ https://unlimited.globis.co.jp/ja/courses/24575c03/learn/steps/53129 ・ビジネスパーソンのための睡眠スキル ~問題解決編 後編 どうしたら眠れるのか?~ https://unlimited.globis.co.jp/ja/courses/4ba981e9/learn/steps/62042 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2025年12月制作)
会員限定

大阿闍梨 塩沼亮潤が死の手前で見つけた「生き方」
あすか会議2018 第4部分科会B-1「極限の世界で見つけた人生の歩み方」 (2018年7月7日開催/国立京都国際会館) 1300年間で2人目となる大峯千日回峰行満行を果たした塩沼亮潤大阿闍梨。48キロの山道を1日16時間掛けて歩き、それを千日間に亘って続ける過酷な行の中で、どのような悟りを得たのか。そして、9日間、断食・断水・不眠・不臥を続ける四無行満行という極限の世界で何を見つけたのか。塩沼氏が「創造と変革の志士」へ贈る「人生の歩み方」とは。(肩書きは2018年7月7日登壇当時のもの) 塩沼 亮潤 慈眼寺 住職
無料
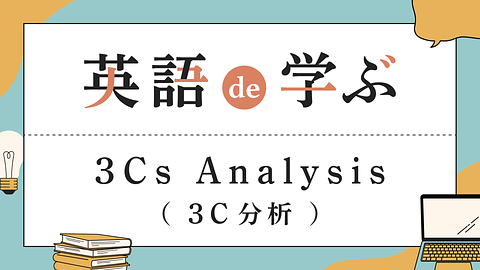
英語 de 学ぶ!3Cs Analysis(3C分析)
このコースでは、グロービス学び放題の英語版である『GLOBIS Unlimited』のコースの中から、ビジネスで役立つ頻出の英語表現をピックアップしています。英語ネイティブの方が実際に見ているコースなので、リアルなビジネス英語の表現を学ぶことができます。 今回のコースは「3Cs Analysis(3C分析)」です。一緒に『英語で』ビジネス知識を学んでいきましょう! ▼今回扱ったUnlimitedコース続きは下記からご覧いただけます 3Cs Analysis https://unlimited.globis.co.jp/en/courses/da5ca962/learn/steps/36362 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2025年12月制作)
会員限定
より理解を深め、他のユーザーとつながりましょう。
コメント218件
chiisai-kiba
Willについては、強い志があれば、CANとなりえると考えています。自分のWILLにCANが重なるように成長するという選択肢もアリだと考えます。勿論、その間に食べるためにNEEDも忘れてはなりません。(あまりにもNEEDがWILLとかけ離れていてストレスが大きければ、その時点で今の仕事を考え直すことも必要ですね。)
WILLとCANがある程度重なってきたら、次は今の仕事がWILLとどれだけ重なっているか、将来的に重なるのかを確認しましょう。
WILLと重ならないならば、マッチした仕事となるように環境を整える(あるいは探す/転職、起業)ことが、自分の大きな飛躍につながっていくと考えます。
私の場合、WILL をかなり早くから意識して、CANがついてこなかったことから、かなり回り道をしてしまいました。
WILLは、時を経ると変化していきます。時代の流れに抗うことがあるかもしれませんが、ピンであれば そのWILLでも市場価値はある筈です。
しっかりと磨きをかけ、WILLに、CANをさらにNEEDをも引き寄せることができれば、仕事はとても楽しくなります。
(NEEDを自分のほうに近づけるにはパワーと根気が必要で、少しは歩み寄りが必要です。そこはWILLを広げることで対応が可能かもしれません。)
sphsph
イメージとしてですが、まさにその通りと感じました。
NEEDで経験を積むことで、他の円も大きくなり、上手くバランスがとれるようになる気がしました。
あくまで前向きに!!
take_aya
WILL・CAN・NEEDで考えたことがなかったので自分のキャリアを考えるとき、子供や後輩が就職転職するときにヒントとして伝えたい。
sakumamasa
仕事のモチベーションを上げるためにも必要な考え方だと感じた。
araaraokinawa
自分のキャリアと現状のギャップを把握し、ギャップを克服するのは、個人の目標設定になる。人事評価における目標設定に活用できると思う。
asahisato
自分のキャリアに思い悩んでいます。
will,can,needの理論は非常にすんなりと頭に入ってきました。
CANの部分を広げられるよう自己研鑽してまいります。
watanabe_jiro
自分のキャリアアップを考える時に応用したい
miyukita92
育成に使えそうなのでこれをやる
tsukamotoya
業務に活かしていくよう努力していきます
reddragonfruit
これからのキャリアを考えていくのにためになりました。
aokiplayer
簡単なことではあるが、言語化するのは大事。
lb51seki
自分のキャリアについて考えてみたいと思います。
yoaoki
職場においても同じことが言えて、部下にはやりがいを感じてもらうことが大切.
その際の思考のフレームに、WILL・CAN・NEEDは大変良いと思いました.
pontaro-
重要なのは自分自身を知ること。これは意外と難しいものです。定期的に振り返り、フィードバックする習慣があると良いでしょう。Will,Can,Needのそれぞれの要素は大切ですが、まずはWillです。チャレンジなくして何も得られません。経験値を積み重ね、人生の設計を柔軟に立てていくのが良いでしょう。
konkon_
あらためて言語化するとこうなるんだな、と思いました。「生きるために働く」という事項においては断然、canやneedの方が圧倒的優位で、かつ、長く真摯に勤めればその2つの〇はある程度、勝手に膨らんでいくと個人的には思っているので、そこに合致するwillを自分の中から探して、ゆっくりでも紐づけていければより良いのかな、と思いました。
canもneedも関われない「不可侵のwill」が自身にはあるのだと気付きました。
koichi_mita
自分自身のキャリアを考える上でWiil, Can, Needに分けて考えて行きたい。
また部下のキャリア形成を考える上で、大いに役に立つ講義だった。
shin4205
リストラも当たり前になってきたので、このような考え方で日頃から自分のキャリアを整理しておき、自律的に行動することが重要だと感じた
izumity21
自身のキャリア形成に役立てたい
keroko_37
後輩や部下へのアドバイスに活用する
nb-take
Will,Can,Needのフレームワークを用いて今の仕事を振り返ってみることができ、良かったです。
himehin
上長、同僚、他部門との会話名の中で、will、can、needを意識し、情報収集したいと思います
sawa_6605
Needに追われてWillを見失うことがないように、折に触れて自身を見つめなおすことが重要だと感じました。
natsu_08
一度学んだことはあるが、再度考えるきっかけとなった。
shirokumao
ストーリーでは3年目の方が主人公だったが、社会人歴が長くなり、三つの意識が薄れている事、バランスが崩れている事に気づいた。意識してモチベーションを高く保ちたい。
fuhiro505
キャリア形成は柔軟に捉えて都度立ち止まって理想のキャリアを見直すことが重要と感じた。
will,can,needの円を大きくすることでより選択肢が広がることも改めて気付きとなった。
mochipi
WillもCanもNeedもわからないので、苦しいけれど現実と向き合いながら現状何が当てはまるのか考えてみる。
shun_358
NeedあってのWillとCanが生きてくるため自分よがりにならないように注意したい。
tatsuro-kochi
このフレームを活用して定期的に振り返ることで短期的な視点だけにとらわれず、中長期視点からのキャリアを考え、自律的に動いていくことができる。今考えているのが、WILLなのか、CANなのか、NEEDなのかの区別を意識してそれらを回していきたい
gantetsu013
よくわかりました。キャリアの形成は人生人生の道しるべを作るようなものだっていうことが理解でき
mofuowl
自分のやりたいことを明確にする、また「今何をやらなければならないか」を明確にするために良い視点の一つだと思った。
kbysr
キャリアは確定するものではない。will can needを定期的に見直し、自分の人生をよりよくする選択をしていきたい。
akira_shin
WILL・CAN・NEEDをもとに、これからの自分の人生観・働きがいを見つめなおしたい。
issei-adachi
キャリア形成をしていくためには、自身のやりたいこと、今現在できること、社会や組織から必要とされていること、を客観的に見る必要がある
tukiyush
自分をしっかりと見つめ直すいい考え方だと思う。
キャリアの形成だけでなくモチベーション向上にも繋がりそう
chi1bou
できることや必要とされているこを見つめなおしてキャリアを考えていきたいです。
tamu415819
業務に活用するにはキャリアの概念を知ることが大事
_kou_
他者評価という点においては上司の評価は会社の評価制度にあるので、
認識しつつ、業務に取り組んだりしますが、同僚とかそういう視点はなかったですね。
自身でも諦めてしまっているところもあったので、改めて考え直す機会をもらえた気がしました。
koichi_rose
私はこの概念を知る前から、自分のやりたいこと、向いてること、チャンスがある分野を考え、結果的に農業という道を選んだ。自分の考え方はwiicanneedに基づいていたことがわかった。
koderama
観点3つとも意識的に確認しておくことが大事だと思います。
kajitamu
今後のキャリアを考える際にwill can needで考えてみる。
okamo1480
今回のお話は、以前一緒に仕事をした仲間からも同じようなことを聞きました。その人は、WILL、CAN、MUSTと話していました。すごく尊敬できる仲間ですので、納得しながら聞いていました。私も50代ですが、次のステップを考えているので、まずは、もう一度自己理解からスタートしていきたいと思います。
shiba_momochan
今一度、自分の目指すキャリアを深く考える機会となった。
kakokoto
willcanneedがそろう仕事はなかなか現実には難しいかもしれないが、その中でもそういう観点から日々の仕事を見直すことは大事だと思った。
astk_0000
NEEDで経験を積むと、CANが広がり、WILLも見えてくるという好循環になるのではと思いました
higuchi_561
Will、Can、Needがそろうところがあるということは、大変市や幸せなことだと思う。
popo1227
自分のやりたいこと、できること、必要とされることを考えてみようと思いました。
できることを増やしやりたいことに向けて頑張ります。
yutoyohena
WILL CAN NEED の三つが重なる部分を探したい
やりたいことを明確にしたい
solato19109
自分のキャリアを考えるうえで、現状のWILL、CAN、NEEDを把握し、今後のキャリアを実現するために不足している部分を理解し補えるようにすることで理想のキャリアに近づける。
o--mi
自分のことを知るというのはわかりづらく難しいが、周りから情報収集などを行い、自己理解をしたいと思う。
okunaka_megumi
ウィル、キャン、ニードについて考えなきゃと思った
saku1111
やりたいこと、できることなど考えます
スキルアップしたいです
723tomato
これからのキャリアを考えるうえで、will.can.needをたくさん増やし
重り交わる部分を多くし
選択肢を増やしたい
nakamura0415
中途面接にて活用できそう。
特にパラリーガル未経験者の面接の際に、CANの深堀は必要そう。
業界や職種、時間軸を越えて発揮しやすい汎用的なスキルがどれだけあるか。
また現状とのギャップについて、求職者と話すことが出来れば、そのギャップを今回の転職で埋めることができそうか?を認識すり合わせ、よりマッチング度の高い採用を行うことが出来そう。
popororo
三つそろったところが重要と分かった
otukat777
Will can needが大事
特にWILLだが、それぞれの言語化、自己理解が弱いのでそこに努める
miki1524
WILL CAN NEED 自分を知ることから始めようと思いました。
ka0821
WILLばかりが強かったように思います、3つのバランスを意識してキャリアを考えていきたいです。
akiyoshi8
自分自身を分析し、理解することが必要と感じた
roji
Will Can Needを今後活用したいです
nakajima0729
部下にこの考え方を共有したさいに、転職や部署転換という選択肢を考えるきっかけになってしまうと考えた。個人の幸せを軸とすれば悪いことではないが、組織を預かる組織長として、組織の戦力DOWNは死活問題。潤沢なリソースを得られる会社の事例だと思ってしまう。
そのため、状況判断しながら、周囲への共有はすべきだと感じた。
ehime_403
自分自身のキャリアデザインをどのように考えたらよいか迷いがあったが、この3点を抑えることで、ポイントがわかりやすくなったと思う。
WILLは、県民の方の利便性を向上させること。
CANは、これまでのキャリアから土木分野。
NEEDは、土木分野の仕事は、これからも必要される仕事だと思う。
kentobigstar04
will/can/needでキャリアの再構築を進めたい
yuuutaa
Will:やりたいこと、Can:できること、Need:求められていること を把握するところから始めようと思う。具体的には、業務の言語化をすることでかなえられると思う。
rico0626
WILL、CAN、NEEDをまず一つずつ明確にしたいと思います。
jack-amano
will-can-needは自身の考え、年代や環境変化で大きく変わり
一度決めて進んだ場合でも、何かのきっかけ大きく変更余儀なくされる。
これもまた、選択肢や考えの変化で正しいと思う。
今の自身のwill-can-needが明日、変化・変更すると思い日々を活動する
28garden
Will
やりたいこと:情熱を持つ・好きなこと
CAN
やれること:得意なこと
need
必要とされること:仕事としての相当の価値
このみっつを考える→やりたいができるか?などがわかる
WiLL 自分の価値感をしる:体験思考の積み重ね
CAN 知識・スキルを考える:汎用的なものを磨く
NeeD 社会の機会や変化から考える
さらに充実したものは、このバランスを考える
スキルがない→CANにできるように変える
モチベーションがない
など、ないところがわかるので、そこを育てるとよい
キャリアを考えるは、人生設計でもある
何をするかを考えることが大切
自分の仕事観 時代観とあわせてみる
自己理解と自己評価 振り返る・フィードバックをとる
柔軟性と意識が大切
everest
自分やチームの意志・能力・役割を整理し的確に目標設定ができるようになると感じた。
noborufurukawa
よく理解できました。
nagano_ssc
自分がやりたいこと•できること•必要とされることを意識し、Will/Can/Needのバランスと
3つが重なる部分を満たしていることは何かを検討し、キャリアやライフデザインを構築していきたいです
tanaya1103
今後のキャリアを考える際に使えると思いました。
会社でもこの考え方が推奨されているので、実際に使ってみて検証したいと思います
kitazawa_m
定期的に、WILL,CAN,NEEDを考え直し、自分のキャリアについて考える必要があると感じた。
yama_kao
やりたいこととできることはなかなか噛み合わず、必要とされていることにもなかなかマッチしないこともある。needにwillとcanが合ってくるのが理想なのかなぁと感じました。
tanetsugu
自分自身では、will 自分の価値観、やりたいことの確立が重要で必要なことだと感じました。
問題点を洗い出し、明確な課題を創出することにより、現状と理想のギャップを埋めていきます。
okahama_0320
Will Can Needの3つのフレームで定期的に自分の進んでいくキャリアの方向性を明確にしていく
cmisaki
自分を知るのは難しい
ikumi_ya
我が社にも同じような言葉があったが、改めて説明されて何のためにあるものか分かった。
ただ理想を描いても意味がないので、今の「can」と今後の「will」を埋めるために何をしたらいいのかを考えながら、「will」が「need」とかけ離れていないか?その間を埋めるためにどうするのか?を考えながら仕事をしたいなと思った。
(そして、同じようなことを転職して2社目の今の職場の2年目研修で、この概念を知らずに発表したことを思い出した…)
akko_oo
自身の事業において、提供できるリソースを考える際にWILL CAN NEEDを使うと、理想に対し足りない知識やリソースが明らかになる為深める良いフレームワークとなるし、研修で企業の管理職研修で活用する場合、1番最初に参加者のキャリアを見直すきっかけとしてWILL CAN NEED を描いてもらうと、参加者それぞれのリーダーとしての理想の成長を明確に思い描くきっかけとなると感じました。
nacsan
理想のキャリアを体系化して学べました。
k-kikkawa
自分のキャリアプラン設計はもちろん、部下の話を聞く際にも有効な話ができると思った。
こういった考え方をもっておくことで、幅広くコミュニケーションがとれる
matutaka-1954
キャリアを考えるには3つの観点で考える事が重要だと分かった。
Will Can Needを忘れずに自分のキャリア形成を考えていく。
gosimakeizou
自分のやりたいこと、出来ることを優先してしまうと身勝手な行動に見えてしまうので一緒に仕事をしていると苦しく感じます。
maple5358
今後のキャリア形成に役立てたい。
takuma-o
自身のキャリアを当てはめて今後に生かしていきます。
watase-h
Will Need Can の観点でキャリアを考えていきたいと思います。
maru_hana
活用方法を教えてください
koshi888
自分のキャリアを考えるだけでなく後輩や部下のキャリア相談に応じるためにも活用したい。
konkonkon
キャリアの軸を改めて考えるきっかけになった。
自らのキャリアはもちろんだが、従業員教育にも活かしていきたいと感じた。
abwx
仕事で意識していこうと考えた。
shin0777
今回学んだ3つの観点を意識し、定期的に自らを振り返ることと、他者からの声を集めることを実践していきたいと思う。
atk_ando
Will、can、mustというセットでは聞いたことがあったが、needのほうが考えやすい。
needを前向きにとらえられるかどうか、Willを主体的に探せるかどうかで、canを増やすことができると思います。
kzm2929
10年前と自分のやりたいことは変わっている。今の会社で自分の力が分かり、更に上を目指せると思っているからだ。定期的な自己分析や目標設定はやった方が、高い意識で業務ができるかもしれない
ma_ni16
will can need、それぞれの円を自分に当てはめて考えると、何が足りないかが見えてくる。
needは自分で決められるものではないが、needを前向きにとらえられるかが今後の仕事の楽しさやりがいが変わってくる。
moveon-s
自分審はNEEDの必要とされているかという意識が強いです。 過去も現在もそうですが必要とされていないと考えてします。 NEEDばかりを意識を薄れてバランスを考えるよう思考をチェンジします。 そのことで安定しか思考になり自分らしい人生を向かえることができるのでは無いかと考えました。
o_ch
自己理解を進めることでキャリアのイメージを持つようにすると、仕事でも迷いなくやりがいをもてるようになると思いました。
円を大きくして可能性幅を広げたいと思いました。
cpasspa
キャリアを考える基礎を学びました。
fryfryfry
WILL、CAN、MUSTは聞いたことがあったが、NEEDは初めて聞いたので勉強になった。時代の変化も含めて市場環境に合わせてNEEDも変わるので、自分のWILLとCANだけにとらわれず大局的に考える必要があると感じた。WILLに関してはあまりないので、WILLの見つけ方を知りたい。
f_shimamoto
WILL・CAN・NEEDの考え方で、今一度、自分を見つめ直して、モチベーションの下がった後輩や指示待ちになっている社員に対して今回学んだ内容を活用して将来を考える機会を作っていきたいtと思いました。
nakatsugawa19
自分の理想を果たすために逆算することが大事だとわかった
katu7
wil、can、needの視点で自分のキャリア形成を考えるときの参考となった。
yamauchikohei
自分のキャリアを考えるうえで、「Will Can Need」の3つを考えて足りないものを補うように学んでいきたい。