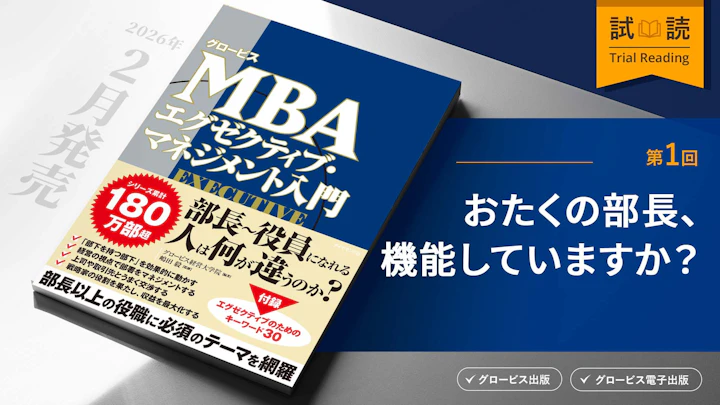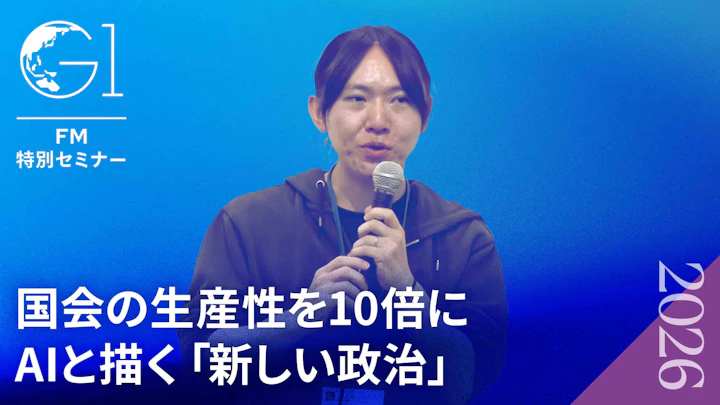本記事は、G1経営者会議2020「DX時代のデザイン×コミュニケーション」の内容を書き起こしたものです。(全2回 後編。前編はこちら)
365日のやりとりを経て、ユーザーがブランド・アンバサダーに
小佐野保氏(以下、敬称略):僕は田中さんに伺ってみたいことがあります。僕もCOHINAのインスタライブを観て、本当に可愛らしくて楽しそうだと思いましたが、それ以上に驚いたことがありました。今、フォロワーは数十万人いるんですよね。
田中絢子氏(以下、敬称略):今は15万人ですね。
小佐野:そうしたフォロワーの方々と、インスタライブで非常にマメなやりとりをしていらっしゃるんです。テクノロジーやDXといった話以前に、人間対人間のコミュニケーションを取っている感じが伝わってきて、そこがすごいと感じていました。何かの反応を戻すのも相当大変だと思うのですが、実はその部分が魅力になるというか。AI等々で自動的にコメントや問いかけを戻すのでなく、技術の上に生身の人間が乗ってやっているところがCOHINAさんの大きな魅力なのかなと、強く感じています。
田中:ありがとうございます。お客さんとのやりとりを365日続けていると、リアルでは見えないのですが、人間関係や信頼関係のようなものが生まれてきます。「あ、○○さん、今日も来てくれているんですね」とか、「□□さん、この前プロフィール写真変えましたよね」とか、そういうレベルで会話ができるようになる。フォロワー15万人ともなると、1人ひとりと1対1の会話はなかなかできませんが、それでも最初のきっかけがあると、お客さん同士がどんどん深く繋がっていくようになります。
たとえば、うちの場合はお客さん同士がインスタのDMを自由にやりとりしていて、今は、そこから派生してCOHINAの非公式LINEグループができたそうなんです。お客さん自身が繋がりたがって。しかも、なんと地方ではオフ会も開催されているらしくて(笑)。それぐらい、1度きっかけを作ってあげると、あとはユーザーさんがそれを深めてくれる部分があるから、私たちが全てを管理する必要はないんです。1人ひとり全員とコミュニケーションを取る必要もなくて、よく来てくださる方、あるいは特に愛情が強い人と、まずは向き合っていこう、と。
あと、先ほどコンテクストのお話がありましたが、管理できないというのはブランド側からすると結構怖いんですよね。「うちのブランド、どんな風に世の中に出ちゃうの?」と。実際、「それはミスブランディングじゃない?」という案件は、正直、日常的にあります。でも、そこでも全国のアンバサダーが発信してくれる。「いや、COHINAはこの前、こういう見解を出してましたよ? たぶんこっちなんじゃないですか?」と、そこでもユーザー同士がコミュニケーションを取ってくれます。そんな風にして、COHINAが言いたいことを皆さんが代わりに広めてくれる状況が今は生まれています。間違って解釈されることもぜんぜんあって、それはそれで仕方がないのですが、今は全国に仲間がいる状況で、ある程度は防ぐことができているのかなと感じています。
梅澤高明氏(以下、敬称略):それは、すべてのブランドホルダーがよだれを流すような状況ですよね。皆、コントロールできなかったり、一緒にブランドをつくってくれる人がいなかったりして悩んでいるわけで。
田川欣哉氏(以下、敬称略):その辺は、チャネル等をベースにしたような考え方とは少し違ってくるのだと思います。今までは「棚をどれぐらい確保するか」とか、ブランドが向いていた先はディストリビューターだったりしていた。でも、そこをぽんと飛び越えてユーザー側まで行くことができてしまっているのは大きいですよね。ShopifyでOKといった点も含めて。
梅澤:COHINAはユーザーに相当な余白を与えているブランドだと思います。ざっくりで結構ですが、「ユーザーが好きに解釈してくれてOK」というゾーンと、「これはブランド側からするとNG」というゾーンは、どのぐらいの割合になっていますか?
田中:(後者は)ほぼほぼないですね。たまにTwitterで少し悪く書かれているぐらいですかね。「COHINAってこういうブランドなんですよね」というものに関して、「違うものが広まっちゃってるなぁ」と思うのは、全体から見ると数%。結構きちんと伝わっていると感じます。
梅澤:嶋さんから「デジタル化の時代、どんどんコンビニエンス化、最適化、最速化していて、それはブランドに対するラブと相反している」との問題提起がありました。ストレートに言ってしまうと、COHINAというのは、言ってみれば最適化の極をいくようなブランドと言える気もします。
田中:目の前のお客さんと、互いに選び合って今ここにいるという感じですから。大々的に広告を打っていないし、うちに辿り着くお客さんは、だいたいインスタ経由でたまたま見つけて、「身長というコンセプトに惹かれて来ました」という方ですから。それでミスマッチが起こりづらいということもあって、今はやれているのかなと感じます。
DX時代のブランドに求められるのは、コントロールでなくマネージ
嶋浩一郎氏(以下、敬称略):スタンスの問題があると思っています。先ほど、梅澤さんは「すべてのブランドがコントロールしたい」といったお話をしていましたよね。僕はPRの業界に長くいたからよく分かりますが、広告業界とPR業界の人たちの間では、時々文化の違いによるコンフリクトが起きます。広告業界の人たちは、「メディアをどれだけコントロールできるか」といったことを、すぐおっしゃるんです。でも、デキるPRパーソンはコントロールという言葉を使いません。マネージという言葉を使います。コントロールなんてできないというのが前提なんですよね。

メディアにはそれぞれ人格があって、好きなことを、主義主張に基づいて書きます。それをコントロールしようとするとコンフリクトが起きる。でも、マネージする。それで、自分たちのブランドにとって適切な情報を提供するわけです。どこまでできるか分からないけれど、スタンスとして、コントロールとマネージはまったく違うと感じています。
梅澤:コンテクストデザインというのは、どちらかというとマネージに近い、と。
田川:難しいところですよね。「放し飼いなんだけど、一応OK」みたいな(笑)。
嶋:寿司原理主義者からしたら、「サーモンを使うのはOKか」とか、「アボカドを使うのはOKか」とか、いろいろ境界線はあります。でも、「これも寿司でいいや、寿司文化が広まるなら」という許容のマネージをどこまでできるか。でも、「コントロールするんだ」というブランドがあっても、その世界観でいいと思います。ただ、何によって文化が広まりやすいのかという考え方からすると、余白のあるブランドのほうがDX時代は仲間をたくさん作っていけるのではないかと感じています。
田川:あと、先ほどの「デジタルになればなるほど“人間”が出てくる」という話はすごい面白いなと思います。COHINAには、田中さんというマグネットがあるじゃないですか。でも、中心にそういう方がいなくて、「雇われて来ました」みたいなブランドマネージャー3~4人が合議で決めていたら、たぶんうまくいかない。
田中:そうです。「とりあえず、こいつに当てておけばいい」という熱量の高い人間が絶対に1人はいたほうがいいと思います。これからのブランドづくりでは共感できることや、誰が言っているかといった話が大事になるので。そうした文脈がないと人には刺さりづらいし、その意味でも「表舞台」に立つ人が1人いれば、どのブランドさんもかなりラクになるだろうなと思います。
田川:会場にいらっしゃる大手企業の皆さまのなかには、その辺について「難しいな」と感じている方も多いかと思います。スタートアップでは比較的、創業者が自明的にその役割を担うじゃないですか。でも、大きな組織だと、スターみたいに出てくるのがなかなか難しい。ブランドマネージャーが転属になったりして、その辺が担保できない難しさがありますよね。
嶋:寿司業界のように合議制がないような状態になればね。カリフォルニアロールは、もはや寿司として認識されているわけじゃないですか。それが認められる感じができるといいですよね。
コロナ禍で生まれた、「できなくなったこと」に対する問題解決
梅澤:それと、もう1つのテーマである「コロナで何が変わったか」という点についても議論したいと思います。
小佐野:コロナで変わったのは、「できなくなってしまったことをどうするか」という部分です。ただ、それまでも会社では「不可能を可能にするためにどうするか」という議論をずっとしていました。「どうすればできないことができるようになるか」という話と、「できなくなったことをどうするか」という話は、考えようによっては意外と親和性があると思うんですね。そこで、今まで寝かせていたネタのなかから、「じゃあ、今はこれをやれば問題解決できるかもしれない」と考えるわけです。
その1つが先ほどのデジタルロケーションですが、ほかにもトライしたことはありました。たとえば、うちはハリウッドの役者さんを起用しているコンテンツが多いんです。その場合、今は外国にも行けないので、シリーズもので次々提供するようなコンテンツが作れなくなってしまう。それで、「どうすればいいか」と、社内でいろいろ議論して出した答えがあります。世の中的にはあまり良い言葉ではないですが、「ディープフェイク」というものがありますよね。これは技術の名前でなくフェイクに使われているということの例ですが、つまりディープラーニングをさせて、存在しない人を存在させよう、と。ただ、それをゼロからやるのは大変です。ですから、ちょっと内緒の技術を使っていろいろなものを組み合わせ、その人がそこに存在して、しゃべって演技をしているような素材の開発をしてきました。そんな風にして今やっていることのなかでも、元を辿れば、「できなくなったことをどうするか」という発想から生まれたものがあります。
田中:私たちはコロナの前後で見ているKPIを変えています。コロナ後はNPS(Net Promoter Score)とリピート率をより重視するようになりました。今は選ばれることが一層重要になってきて、「指名買い」がすごく増えていると感じているので。1回のお買い物やお出かけ体験が人々にとってすごく重要になってきていて、そう簡単に消費できないわけですね。めったに出かけないから。だからこそ、「プチプラで済ませよう」とか、店頭にあったものをなんとなく手にとってみて「可愛かったから買おう」とか、そういう話にならず、「ここのブランドでこれが買いたい」と。そんな風に購買行動が変わってきていると感じます。
それで、そのブランドや企業をどれほど人に勧めたいかという指標であるNPSを見るようになり、業界平均でおそらくマイナス20前後のところを、私たちは今プラス20前後にしています。あと、リピート率も変わってきました。業界平均で20%だったとしたら、私たちは50~60%の水準を保とうとしています。そんな風に、とにかくユーザーからの愛着を測ることのできる指標を、より重視するようになりました。
梅澤:もともとそういうコンセプトでつくってきたブランドだけれども、コロナでユーザーの購買行動がなおさらシビアになったからということですかね。
田中:そうですね。シビアになったと感じます。
嶋:この問題も「コンビニエントとラブ」の話と同じぐらい重要だと思っています。平成時代に日本で何が起きたか。日本人は損したくない人になっちゃったと思うんです。集合知がすごく発達した結果、映画を観に行く前から評価を気にするし、レストランに行く前から点数を見るし、損したくないカルチャーが蔓延した30年だと思っています。もちろん、既存の選択基準に集合知が加わったことで、より便利になった面はあると思いますが、自分に言わせると“集合知野郎”が増え過ぎた感じがして(会場笑)。以前、ある仕事で高校生にインタビューをしたとき、「この音楽、使えるんですよね」と言われたことがあります。「え? 音楽で“使える”っていう形容詞を使うの?」って。音楽は「好きか嫌いか」という話じゃないのかと思うんですが、「いや、この音楽は使えるんです」と。「やばい、もう完全に損するかしないかで話してる」なんて思うわけですね。
選ばれるブランドになることを考えるとき、そうした集合知によって、あるいはデータの最適化によって、選ばれてしまっていいのかなと思います。それに対抗するブランディングがあって然るべきではないでしょうか、と。ブランドをつくる仕事をさせていただいているなかで、「集合知に勝てるブランディングって何?」というのは、自分は強く感じている今日この頃ですね。
いかにしてビジョンとアートを結託させるか
梅澤:では、会場から質問をいただきたいと思います。
会場質問者A:「アートは集合知でつくれない」との仮説を持っていますが、デザインはいかがでしょうか。アートとデザイン、または「つくりたい」という自身の願望と集合知との割合やバランスについて、どう考えていくべきですか?
会場質問者B:余白とは別に、変えてはいけない軸や、はみ出してはいけないフレームのようなものもあると考えていますが、その辺についてはどうお考えですか? また、余白はどの程度まで許していくべきものでしょうか。
会場質問者C:田中さんが思い描くCOHINAというブランドの将来像というか、「こんなブランドにしていきたい」というお考えがあればお聞かせください。
嶋:アートとデザインについてはずっと悩んでいて、結論は出ていません。ただ、訓練すればラブをつくることのできる技術は身につくのではないか、というのが今のところは僕の仮説です。集合知ではつくれないような、アーティスト的なものでしか発見できないような、今世の中に存在していない価値を見つけるスキル。あるいは、世の中で顕在化していない、皆が喜ぶ価値を見つけるスキル。ここはマーケターの仕事ですね。AIはすでに顕在化したものを見つけますが、顕在化する前の人間の欲望に気づく部分は、今のところ人間が勝っている気がします。人間は不器用だから自分の欲望を言語化できませんが、その前に行動には出てしまうかもしれない。そういう行動に出たファーストペンギンの動きを感知するセンサーのような部分は、意外と訓練で身につくように思います。「あの人、変なことをやっている」という違和感。でも、それが自分の欲望を体現する行動だということに、その人自身が気づいていないようなことを発見するスキルは、マーケターとして、ある程度身につけられると感じています。あまり答えになっていないかもしれませんが。
田川:アートとデザインの関係についてはアートスクールでもすごく議論になります。個人的には、アート、あるいはビジョナリーといったものは1人で考えるものだと思っています。アーティストはユーザーを観察しませんよね。まずは自分のなかに強烈なコンプレックスや生い立ち、あるいは課題意識といったものがあって、テーマが人間そのものや人類だったりするパターンが多いので。一方、デザインはユーザーと一緒につくっていくし、人工物を扱いますから、「ユーザーと一緒に」「ユーザー観察」といった言葉が出てきます。

先ほど、田中さんがデザイン経営の教科書のようなお話をなさっていました。僕は「真ん中にマグネットが必要」という風に言いましたが、COHINAは、おそらく田中さんの存在がアートなんですよね。「身長が低い方に」ということを普通におっしゃっていたし、「ユーザーを巻き込む」といったお話を聞いていると、デザインやテクノロジーの話に聞こえます。でも、その真ん中の課題解決のような部分に1本の軸が通っている。イーロン・マスクもそうです。真ん中にはアートやビジョンがあって、そこにデザイン等が結託している。ですから、ビジョンとデザインの結託をチームでどのようにセットアップできるかという話に尽きるのではないかと思っています。だから、僕らのようにデザインをやっている人たちはビジョナリーとの出会いをいつも求めている。一方、おそらくビジョナリーな人たちはデザインやテクノロジーの人たちとの出会いを求めればよくて、そこで結託してやっていくのがベストではないかと思っています。
COHINAは小さな共和国。グローバルでどこまでいけるか
田中:COHINAの今後についてお話しすると、目の前の試してみたいこととして、グローバルでこれが通用するのかという点に、ちょっとワクワクしています。最近、海外のお客さんからの問い合わせがすごく増えているんです。「YouTube観たんだけど海外に配送はできないの?」とか、「インスタライブ、私も小さいから観てる」とか。どうして観てくれているのか分からないんですが、「何を話しているか分からないけど楽しそうだね」とか(笑)。いずれにしても、海外の人たちが気にしているそぶりを結構感じています。ただ、私たちの今のビジネスモデルは、コミュニケーションがスムーズに取れることが大前提になっています。これが英語や中国語で、まったく違う文化になったとき、どこまで人の心を通わせるビジネスとして通用するのか。ここは、おそらく大きい会社だとやりづらいだろうなと感じているので、スタートアップとして頑張りたいなと思っています。
あと、うちも月に1度ぐらいの頻度でポップアップ・ストアをやっていますが、そこにいらっしゃるお客さんも、やはり大変な熱量を持っていらっしゃいます。うちの場合はスタッフにファンがつくような形式なので、スタッフのシフト変更が1日3回あるとしたら、3回いらして3回買っていくようなお客さんも結構います。そういう方々と、オフラインでも何か関係を築けるとしたら、どんな形式がベストなのか。その辺もこれから模索していきたいと思っています。
あと、余白とOBゾーンのような部分に関して申し上げると、私たちの感覚としては、自分たちを「小さな共和国」のように思っていて(笑)。「他国から侵害されるのは心外だけど、別に攻め入りもしません」と。私たちは私たちのルールで独自の文化をつくっていこうと思っているので、そこは私たちなりにやっていくということでいいのかなと考えています。まだ、それほど明確な法律がない状態なので、倫理観として「人を傷つける言葉は良くないよね」とか、そういう学校で習うような最低限のことがある程度です。ただ、いずれにせよ小国としてやっていきたいということは最近結構考えています。
梅澤:嶋さんはいかがですか? OBゾーンはありますよね。
嶋:もちろんあると思います。先ほど言った通り、スーパーストリクトに「これじゃなきゃだめ」という風にしたり、「うちは許容します」としたりするのは、もはやキャラの問題ですから。それ自体が愛されキャラになるかどうかという話でいいと思っています。
田中:うちはゆるキャラでやっています(笑)。
嶋:ただ、「完全にこれじゃなきゃ認めない」という経典主義の時代は終わって、今は余白とかぬり絵的なものがあったほうがいいのかな、と。結局、カルチャーは人とつくらなければいけないし、今何かをやろうと思ったら業際が崩れていきますよね。昔は同業の競合と戦う時代でしたが、今は異業種の人たちと一緒に1つの目標を叶える時代。ですから、企業と企業との関係性においても、「これじゃなきゃイヤだ」と言っている企業は、なかなか協業ができなくなってくると思います。そういう企業と企業のコラボを進めるうえでも、余白とか、「ここまで譲ります」という部分がないと、一緒に仕事はしづらい感じがしますね。
梅澤:特に大企業の方々は耳が痛いかもしれないですね。オープンイノベーションと言ってはいるけど、なんだか、やたらと厳しいガイダンスがあって、協業したいと思っている人たちもちょっと厭になってしまう、みたいな。そんなことがないかなというのはご注意いただきたいと思います。
「提供価値」は禁句。「体験価値」が何かを伝えよう
田川:1つ付け加えさせてください。別セッションで交わされていた議論のなかで、少し気になった言葉がありました。「提供価値」という表現を使っていらした方が多かったのですが、UXの世界だと、これは禁止ワードなんです。「それは提供者が考えている価値」を提供者の言葉で語っているだけなので。UXの専門家からすると、「いや、ユーザーに体験された価値しか、実際には存在してないのと同じですよ」と。ですから、体験価値が何かを会話のなかできちんと言うようにしないといけない。「これが提供価値です」というのは、なにかこう、それ自体がマスメディア的というか、提供者優位というか、一方的なので。
おそらく「体験価値が云々」という話は、先ほどの誤読(を許容する)というお話、あるいはCOHINAでやっていることと、根本的なスタンスの違いがあります。また、それはテクノロジーの話とも紐付いている気がします。おそらく昔は提供しないと棚に並ばず、ディストリビューションにならないという世界があったのだと思うんです。でも、今はそれが変わってきているし、昔できなかったことが今はできるようになったりしているので。その辺の微妙な差を、どういう風に理解して、解釈していくか。そういう違いが、経営者の方々、あるいはものを作っている方々が日常的に使う言葉の節々に染み出しているなということも今日は感じました。提供価値とか、コントロールとか、その辺は余白の話とも結構つながってくる気がします。
梅澤:時間になりましたので、今日私自身にとって学びになったポイントを簡単にまとめて終わりたいと思います。1つ目は、DXの時代は利便性をどんどん追求して最適化が進む時代ですが、田川さんから指摘があった通り、今はコロナを経てユーザーがどんどん変化をしている。だから、最適化するにしても、もう1度ユーザーのリアリティを見つめ直す必要があるというのが1点目です。2点目は、最適化の追求と、ある意味では対峙しがちなコンセプトですが、愛してもらえるブランドをどうつくるか。COHINAはその最たる事例だと思いますが、余白を相当つくって、その余白にファンを巻き込んで、文字通りファンと共創するというのが1つのアプローチになる、と。そうした点が、特にソーシャルメディアを駆使したブランディングという意味で参考になったかと思います。それからもう1つ、とても面白いなと思ったのが、そのなかでむちゃくちゃ頑張っているのは熱量の高い人というお話ですね。熱量の高い人が、ある意味ではブランドのメインコミュニケーターになって、そのプラットフォームを使いながら、人と人とのコミュニケーションのなかでファンをエンゲージしていくことが、本当に大事になる。そんなことを改めて確認できた1時間でした。今日は貴重な議論をありがとうございました(会場拍手)。





%20(16).png?fm=webp)

%20(19).png?fm=webp)



















.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)
.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)

.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)