本記事は、G1経営者会議2020「DX時代のデザイン×コミュニケーション」の内容を書き起こしたものです。(全2回 前編)
梅澤高明氏(以下、敬称略):申し上げるまでもなく、DX、製品とサービスのデザイン、そして事業のデザインといったものは、すべてつながっています。これはコロナ前からの話で、コミュニケーションの高度化も事業の高度化とセットで語られなければいけない時代になっていたと思います。そのうえで、新型コロナをきっかけに、現在は生活者の価値観やライフスタイル、あるいは消費行動がさらに変わってきました。そのなかで企業と個人のコミュニケーション、それからビジネス構築のアプローチも、再構築を迫られている会社が多いのではないかと思います。今日は、そうした変化の中身と、事業またはデザインやコミュニケーションのレベルで、どのような再構築が必要になるのかを議論したいと思っています。
壇上の小佐野さんと嶋さんは、コミュニケーションのプロ中のプロということで広告やPR、あるいは場づくりに取り組まれています。そして田川さんはデザイン分野の第1人者であり、COHINAというアパレル事業を立ち上げた田中さんはスタートアップということで、それぞれ異なるお立場から、今申し上げた論点で議論していただきたいと思っています。
効率化や最適化で乖離していく、ラブとコンビニエント
梅澤:大きなテーマは2つに絞ろうと思っています。1つ目は、そもそもコロナ前からの話として、デザインとコミュニケーションの役割や成功要件が、DXという流れのなかでどのように変化していたのか。2つ目は、今回のコロナを受けて、さらに新しい変化が生まれているのか、または既存の変化が加速しているのか。この2つを議論したのち、会場から質問をいただきたいと考えています。まずは、DX時代におけるコミュニケーションの役割と、その成功要件について。嶋さんからお願いします。
嶋浩一郎氏(以下、敬称略):たしかに、コロナによって非接触等がすごく大事になるので、DXは大きく進むと思います。コロナがあってもなくても5G化やIoT化は進んでいたし、デジタルを通じて企業等いろいろなプレイヤーが生活者と直接つながる流れは、もともとありました。でも、今までのマスメディアと違って新しいコミュニケーションインターフェースは情報の伝達だけでなくデータの取得もできるし、そこで直接サービスを提供してお金を取ることもできるようになると、そこでビジネスがすべてできてしまうわけですね。自動車メーカーがコネクテッド化によって、住宅メーカーがスマートホームによって、生活者と直接つながる。そういうことがどんどん起きるのだと思います。
ただ、僕はそこで、「うわ、これはどうなんだろう」と思うことがあります。生活者と企業がデジタルで繋がっていくと、効率が最も重視されるというか、コミュニケーションの最適化や最速化といった話が一番のプライオリティで語られる傾向があります。たとえば、わかりやすく言うとネットでポルシェのページを見ていることが分かったら、スポーツカーの広告をその人に一気に当てていくとか。そういうことが一番の最適化であるという考え方で、その手のサービスを追求していくわけです。たしかに、そうすれば多くの人にとって便利になるとは思います。「でも、それ、みんな好きなのかな」と思うんですね。コンビニエントになることと、ブランドが愛されることは、全く違うのではないか。そうしたコンビニエントとラブの乖離という問題が、今後はむちゃくちゃ出てくると思っています。これは結構重要で、デジタルで生活者と繋がっていく企業が考えないといけないことではないかと思っています。
梅澤:デジタルメディアやプラットフォームの発展によって進んでいった利便性の追求は、ある意味、ブランドに対する愛と相反するのではないか、と。
嶋:あるところまで一緒だと思いますが、完全に一致しないのが難しいところだと思っています。『BRUTUS』という雑誌で編集長をしている西田善太さんに、こういう話を聞いたことがあります。あるとき、マッチングアプリのエンジニアと話をしていたら、その方が、「うちのマッチングアプリは、釣りが好きな人同士を、キャンプが好きな人同士をマッチングさせます。だから、すごく仲良くなれるんです」と説明したそうです。それで西田さんは、「え、でも、まったくホラー映画を知らない女の子にホラー映画の楽しみを教えてあげたほうがモテると俺は思うよ?」と話したそうなんですね。これ、まさにラブとコンビニエントの違いを象徴している話だと思います。
撮影できなくなってしまった世界で、何によって映像を作るか
梅澤:そのあたり、またのちほど深堀りさせてください。では、続いて小佐野さん。
小佐野保氏(以下、敬称略):自分はギークピクチュアズというマルチメディアコンテンツの制作会社を経営しています。コンテンツのなかでも私たちは映像特化型。映像が自分のコミュニケーションのすべてというぐらいの勢いでやっています。映像といってもいろいろなジャンルが含まれていて、嶋さんともご一緒させていただいているTVコマーシャルだったり、映画だったり、ドラマだったり、動画だったり。とにかく、さまざまな映像を作りまくっている会社です。

一部の人の間では有名な話ですが、実は、私は子どもの頃から文字を読むのが大の苦手でした。学校の教科書を読んでいても文字がまったく目に入ってこないんです。ハリウッドには脚本を読めない役者さんがたくさんいて、それは1つの病気ということを大人になってから聞きまして、「あ、俺もそれなんだ。病気なんだ」と。そう自分で勝手に当てはめているだけなんですが。実際、映画の仕事で脚本を渡されて「どうでした?」と聞かれて、「いやあ、最高だったね」と話すものの、ほとんど頭に入っていません(会場笑)。では、どういう風に理解するかというと、周りの人たちに読んでもらって、その雰囲気を教えてもらって、音と雰囲気で理解していく、みたいな。
僕にとってコミュニケーションとは何か。何かの知識をそこから吸い上げていく、あるいは人に聞くというコミュニケーションもありますが、人から言われたことを自分のなかに吸収させるという部分が、自分はすごく限られた人間なのかなと思っています。そこをうまく埋めてくれるのが自分にとっての映像なんですね。「だからこそ、自分は今、映像の仕事をやっています」という風に言うと、周りの人たちが「なるほど」と言ってくれるので、今のところそれでずっと通しています。
梅澤:デジタル化の流れのなか、小佐野さんの仕事は大きく変わりましたか?
小佐野:実は、デジタル化というか映像制作のDXというのは、つい最近変化したというものでなく、緩やかに、この20~30年の中で何度か起きています。皆さんもご存知かと思うのはハリウッドの例ですね。昔はフィルムというもので撮っていましたが、それがビデオで撮るようになり、今はビデオすらありません。形のないもので映像を作る時代になりました。
それが最も大きなDXだと思いますが、コロナに関して言うと、自分たちの業界では本当に悲しい出来事が次々起きました。僕らの業界以外でもたくさん起きていた話かもしれませんが、僕らにとっては致命的なことで、今まで普通にできていたことがまったくできなくなってしまった。特筆すべきは、やはり撮影ですね。ものを撮影するという行為は僕らにとって絶対的に必要なものですが、それがまったくできなくなってしまった。これには、本当に皆ふさぎ込んでしまいました。
ただ、今は撮影ができなくなってしまった環境で何をすれば映像を作ることができるかというほうに頭をシフトして、いろいろなことがありました。ご覧になった方も多いと思いますが、ロックダウン中、ローリング・ストーンズが『Living in a Ghost Town』という新曲のMVを公開しました。映像は、誰もいない世界中の名所を撮っただけのもの。各国で、もうiPhoneで撮って送ってきたような映像を編集して当てただけのものですが、僕はそれを見て驚愕しました。「なるほど。誰もいない中でも、こういうコンテンツが作れるんだ」と。
そう感じたとき、思いついたことがあります。お天気コーナー等で渋谷の交差点を映した映像ってありますよね。ある時、そこに映っていた渋谷の交差点に誰もいなかったことがあって、それを見た時にちょっと思いついてしまって、すぐ会社でミーティングをしました。「今はチャンスだ」と。「誰もいない今のうちに、渋谷の街、もしくは日本中の、普段は撮影できないような場所を、点群データで撮りまくれ」と。建築の測量で使うデータの撮り方ですね。それをCGで再生して、撮影しなくても街並みを再生できるようなシステムを3ヶ月でつくりました。
これは数あるDX事例の1つですが、それで今は渋谷の街であれば中心地から500mぐらいは、裏路地に入っても横丁に入っても、そのお店のデータまで再現できるほどのデータが取れました。年明けまでには、スクランブル交差点の、表に立ったところから360度の部分は、すごくリアルな、実写と差を見出せないほどの条件で再現できるようになります。そんなことをしながら、実際の撮影ができなくてもリアルなハイクオリティ映像を再現できるというものに、今は渋谷以外でもトライしています。
梅澤:それは将来とても大きな資産になりますね。
小佐野:なると思います。普通なら面倒だし、「そんなバカなことはしないよね」ということが、今回、このタイミングでできたというのはありますね。
嶋:ある意味、立体的なGoogle Mapが将来的にすぐできるということですよね。
梅澤:かつ、将来は映像作品に使えるわけですよね。
小佐野:今はまだ発表できないのですが、とあるアイドルのミュージックビデオで今回初めて、渋谷の街をリアルに再現したものを使わせてもらっています。
梅澤:どんどん世界的な映像作品にそれを使っていただいて、日本のPRにも使っていただけたら嬉しいなと思います。
小佐野:そのつもりでいます。日本のデジタルロケーションを世界に、「販売」していくという言い方は変かもしれませんが、使ってもらうためのテストパターンという風にご理解いただければと思います。
コロナ禍を経てこれから現れる、僕らが知らないユーザーの姿
梅澤:続いて田川さん。デザインという視点からもう1度、DX時代を振り返って解説していただけますか?
田川欣哉氏(以下、敬称略):今回のG1経営者会議では、午前中の他セッションでもUXの話がずっと出ていました。それで、「ユーザー中心」「ユーザー理解」「顧客理解」といった言葉を多くの方々が使っていらして、G1でも今回はそういう話が最も多く出てきていると感じます。世界的な潮流としても、今はユーザーの変化が一気に加速していると思うんです。小佐野さんのお話は、事業をやっていらっしゃる方々がどんな風に自分たちを変えているかというお話であり、それにテクノロジーを使って取り組んでいらっしゃるということだと思いますが、おそらく、それはいち生活者のなかでも起きている。「買い物に行けない」「病院に行くのが怖い」と思っているユーザーさんが、あの手この手で自分たちの行動を変えているわけです。
デザインの世界にはユーザー理解の1つの公式というか、方程式があります。ユーザーは、いわゆる裸の状態でなく、服を着ていたり、靴を履いていたり、かばんやペンを使っていたり、スマホを持っていたりするわけですよね。つまり、ユーザーとは、ユーザーと人工物の集合体であると、僕らは理解したほうがいいという考え方があります。一方で、今はたくさんの事業者の方々が、「コロナ禍における行動抑制のなかで、どうすれば人間が人間らしい生活を送れるか」と、猛烈に開発をしています。では、来年頃にそれが世界中で解き放たれていったとき、どうなるか。人間が「人間+人工物」だとしたら、来年以降の人間やユーザーというのは、おそらく僕らが知らないユーザーになっていると、思ったほうがいいんです。
これは、おそらくすべての事業者に影響があります。マーケットはユーザーの集合体だと思いますが、その集合体を形成する一人ひとりの行動や持っているものが変わってくる。そういう環境変化が来ると、事業者の方々がどれほど感じているか。ライフルのスコープから見えていたところにユーザーがいたつもりになっていたけれど、スコープから目を逸した途端、いなくなっているという状態ですね。
たとえば、Zoomを使っている経営者と使っていない経営者では、おそらく質的に差が出ていて、その経営者が買うものも変わります。生活者もそう。PayPayを使う生活者と使わない生活者との間には、PayPayという事業をやっていらっしゃる方々にとっての違いがあるだけではないんですね。本や野菜を買うときも行動が違ってくると思います。そういうことができるという風に、ユーザーの理解が1度シフトしているので。強固なチャネルを持っていて、ビジネスモデルとして「ここが勝ち筋だ」と思っていらっしゃる方ほど、その辺の理解に注意を払わないといけない。そうでないと、知らない間にユーザーが今の場所からいなくなってしまっている可能性が、結構あると思っています。
その意味で何が大切になるかと言えば、何を作るか考える前に、とにかく顧客のところへ行って一緒に話をすること。デザインプロセスの最初は、顧客への共感や理解ですから。データの話もありますが、とにかくたくさん会話をする。1度、そういうことを20年ぶりぐらいに全社員でやってみる、みたいなことが大事になっている気がします。デザイン経営的な観点で言うと、デザインプロセスにおける最初の顧客理解が一旦リセットになった。ですから、ゼロから顧客理解を積み上げ直すタイミングが、ちょうどコロナで来たという感覚を持っています。今はそれとデジタル化が重なっている時期なのかなと思いますね。
空間を情報として認識できた時に起きる、リアルとネットの逆転
嶋:僕もそれを感じています。僕は8年前から都内下北沢で「B&B」というリアル書店を経営していますが、「なぜ、この時期にリアル書店なんか作るんだ?」と、当初はいろいろと言われたんですよ。しかも、出版社の人が「なぜ本屋を作るんだ」なんて言うからムカついたんですが(会場笑)。ただ、彼らは親切で言ってくれるわけです。「今どき、リアルとネットなら、ネットで買うだろう」と。たしかに、ネット書店は買いたい本が決まっているとき、めちゃくちゃ便利です。でも、リアルでは、買うつもりのなかった本を買っちゃう本屋が良い本屋。そこにセレンディピティがあるわけじゃないですか。
でも、それもいつか絶対デジタルに抜かれると思います。小佐野さんが先ほどおっしゃっていたことですね。空間を情報として認識し、見ることができる映像技術が本当にできたら、普通に本屋を歩いているような体験がネットの中でできるようになりますから。今は、そこがリアル本屋とネットの違いです。ネットで5分も調べたら、たとえばマダガスカルについて詳しくなることはできます。でも、街の本屋のなかを5分歩き回ったら、あらゆるものを見ることができる。本屋には、歴史、経営、宇宙、ガーデニング、ジャズ、野球の本から、ドロドロ恋愛小説まで、本屋には基本的には世界を構成するものがすべて詰め込まれています。街の本屋は30坪ぐらいだから5~6分で歩けるわけですね。その中で、いろいろなものを一気に見ることができる。これは、今のところネットではできません。
でも、小佐野さんのお話にあった通り、たとえば渋谷駅を中心とした空間認識が映像の中でできるようになるとどうなるか。「京都の恵文社さんっていう書店がいいと聞いたから行ってみたい」という人が、ネットで書店の空間を体験できるようになります。その中で、「あ、この本が欲しい」ということで買えるようになると、もうネットとリアルが一気に逆転するようになります。今までのコンシューマージャーニーみたいなものが一気に崩壊していくという感じがしています。
小佐野:おっしゃる通りで、ゲーム空間でのバーチャルは皆さんも経験していると思いますが、リアル空間ではなかなか無いと思うんです。でも、今僕らがやっているプロトタイプでは、渋谷の路地裏に行って、そこの本屋さんに入ることもできるぐらいのデータが取れます。だから、本当に、映画『レディ・プレイヤー1』のような世界が、もっとリアルなところで体験できるようになります。僕らの力だけでは無理だと思いますが、嶋さんがおっしゃるように、その可能性はあるという気がします。
声を拾い続けた先にある、顧客の言葉がCOHINAのブランド
梅澤:では、続いて田中さん。ここまでのお話とつながる内容も多いと思いますが、まずはCOHINAの事業をどのように組み立てたのかというお話をしていただくと、今日のお題につながるヒントが満載になると思います。
田中絢子氏(以下、敬称略):私はCOHINAという、身長155cm以下の、小柄な女性のためのアパレルブランドを運営しています。というのは、私自身も身長148cmで、先ほど壇上の椅子に座るときも緊張するぐらいには小柄で(笑)。シンプルな話、服が世の中に無いんです。皆さんからすると少し不思議な話かもしれません。ユニクロに行けば山のように服はあるし、ルミネにもさまざまな服があります。年齢も、ティーン・エイジャーから50代の方にまでぴったりの服まで、世の中にはあれほどたくさん服がある。「それなのに、“服が無い”って、どういうこと?」と思われるかもしれません。でも、本当に無いんです。
これは私自身が148cmだから気付いただけかもしれませんが、ぴったりサイズの服を着ようと思うと、キッズ服を見るしかないんですね。それで、「アラサーでキッズ服はちょっと痛いよな」なんて思ったり。XSサイズというのもありますが、あまりにも選択肢が少なく、自分のなりたい姿になれないというのが自分にとってはリアルな課題でした。周囲の小柄な女性に聞いてみても、やはり皆、「服が無い」と言います。それで、「世の中にはこれほど服があるのに、自分のための服が無いというのはどういうことだ」ということで、まずは小柄女性のための服を作ろうと決めました。

「では、服って本当に作ることができるのか」というところで、まずは壁にぶち当たりました。もともと私は文系大学を出たあとGoogleに新卒で入社したこともあって、キャリアにはアパレルのアの字もなかった。ですから、そこはITの力を借りまくりました。アパレル工場にツテもなかったので、中国アリババの2Bサイトで、「私たち、こんなブランドを立ち上げるのですが、作ってくれる工場さんはありませんか?」という募集をしました。すると、中国の工場が「はい、僕たちが作ります」という感じで応募してきてくれます。そこで、選んだ工場の方に「では、よろしくお願いします」ということで作りはじめました。
それで作ることができるのは分かりましたが、それをどう売るのか。私はエンジニアではないのでコーディング等はまったく分からないのですが、誰でも簡単にショップを作ることができるということで、ECサイトのShopifyというところに登録しました。ただ、「作ったはいいけれど、誰も私たちのことを知らないぞ」と。それで、アパレルやマーケティングの背景は一切なかったのですが、まずはInstagram等SNSの活用だろうということで、一気にSNS投稿をはじめていきました。
そこから、じわじわと、「私も小柄なんです」とか、「まだどんな商品があるのか分からないけれど、コンセプトだけでも応援したくなりました」と言ってくださる方が徐々に増えていきました。それで、商品を発売したその日から、もう「待ってました」という感じで、購入してくださる方がついてくださいました。そこからは、あれよあれよと、月商100万、500万、1,000万、5,000万、1億という感じで、どんどんファンの方が増えて、コミュニケーションも盛んになって今に至るという感じです。
梅澤:商品開発ではユーザーの声をどんな風に活かしているんですか?
田中:アパレルブランドのディレクターとしてあるまじき話なんですが、私は作りたい服というものが全くなくて。本当に、「可愛ければなんでもいいんじゃない?」というぐらいの感じでやっています。ただ、私たちのコンセプトとして、「お客さんの代弁者であろう」という考え方が根底にあるんですね。ですからお客さんに聞いています。たとえば、今(11月下旬)は来年1月ぐらいの服をつくっています。ですから、「1月は何が着たい?」とか、あるいは「コロナで実際に生活が変わったと思うけど、コロナ禍の冬って何が着たい?」とか。そういうことを、私たちはインスタライブをずっとやっているので、そこからダイレクトに声を拾って、「今回はこういう声が多かったから、じゃあ、次の企画に反映させよう」という風にして作っています。
梅澤:そこで、「次は何が欲しい?」とか、「こういうときは何を着てるの?」とか、「どんな色がいいの?」とか、次々聞いていくわけですね?
田中:そうです。ユーザーインサイトはユーザーに聞くしかないということで。私たちは1年365日、毎日インスタライブの配信をしていて、1日1時間は必ずユーザーの声が入ってくる時間があります。そこで商品の話に限らず、皆の生活スタイルとか、最近あったこととか(笑)、そんな話までしながら商品展開にも活かしているという感じです。
梅澤:そうすると、そもそも「ブランドディレクション」のような概念があまりない?
田中:そうですね。ブランディングというのは、おそらく「私たちはこういうブランドです」という風に発信することだと、この事業を始めるまでは私も考えていました。でも、私たちが何者かを決めてくれるのがお客さんなのかなと、今は思っています。自分たちでは定義せず、そこの判断もお客さんに任せてしまう。ただただユーザーの声を拾いまくって、形にして、最後にお客さんがなんて言うか。それがブランディングなのかなと、私たちは思ってやっています。
ブランドをつくるのは、誤読を許容する「ぬり絵」的コミュニケーション
嶋:このセッションがはじまる前、同じような話を田川さんとしていました。これからのブランディングは、経典みたいなテーゼを企業が発信するのでなく、生活者と一緒につくらなければいけなくなる、と。トヨタさんはモビリティカルチャーを皆と一緒につくる。協業する人たちとも一緒につくるし、生活者とも一緒につくるわけです。スノーピークさんはアウトドアカルチャーを一緒につくる。ただ、そんな風にしてカルチャーをつくるというのは、相当難しいことだと思うんですよね。
梅澤:スノーピークは、ある意味では1つのライフスタイルをものすごく強烈に出しているという気はします。
嶋:そうした強度の違いはあります。でも、たとえばTakramの渡邉浩一郎さんが「コンテクストデザイン」というものを提唱していますが、これからの企業はスタンスとして「誤読」を恐れないようにするという話ですね。コンテクストデザインとは何か。これは僕の解釈ですが、たとえば「お寿司を世界中に広めたい」という人が、お寿司の作り方をいろいろな人に教えたとします。すると、カリフォルニアの人が「分かった。寿司ってこういうことだね」と言って、アボカドを使って寿司を作っちゃう。それをサーモンと一緒にして「カリフォルニアロールです」というものができる。
寿司原理主義者からすると「これが寿司なのか?」という話になると思いますが、「寿司という文化が世界に広まるなら」ということで、そういう誤読みたいなものも許していく。そういう度量の広さがあると、カルチャーは一層広まっていくという感覚です。「こういうものである」というガチガチのテーゼよりは、「こういう楽しみ方やスタンスがあります」と発信したうえで、「あなたなら、どう解釈する?」みたいな。そんな風に、クリエイティビティの一部を受け手に託し、委ねるということですね。
僕はラジオが大好きですが、これはラジオ的コミュニケーションとも言えます。ラジオではリスナーがそれぞれ、「このパーソナリティは俺のために話している」と、勝手に想像しています。そうした、ぬり絵的な余白がある。聴き手が自由に解釈できて、カリフォルニアロールも「勝手に作っちゃっていいでしょ?」と。僕は、そういうコミュニケーションが今後は文化をつくると思っています。メジャー企業の人たちは、すごくインフルエンシャルな、「こういうものがいい」といったものを発信しています。でも、これからは誤読や誤配のようなものを許容する文化のある企業のほうが、ブランドをつくっていくことができるのではないかなと思っています。
梅澤:いつ頃からそういう流れがはっきりしてきたんですか?
田川:圧倒的に、Instagram等でコミュニケーションが双方向になって、皆がものを言えるようになってからだと思います。嶋さんがおっしゃる通りで、UXの世界におけるアカデミックな定義をご説明すると、コンテクストというのはデザイナーがデザインできないものなんですね。コンテクストというのはプロダクトとユーザーの背景にある。だから、企業等はプロダクトしかつくれないという話だったんです。でも、コンテクストの側を「雰囲気の良いもの」にすると、ユーザーとプロダクトとの間にあるインタラクションがすごく平和な感じになっていく。
ですから、「その背景側をどういう風にしようか」といった話が、コンテクストデザインでは結構あります。誤読といった考え方は超面白くて、『鬼滅の刃』でもそういうものが結構あります。ネットにはパロディ画像や映像みたいなものがたくさん流れていますよね。皆、それを作っているときにワクワクしたり、それを見た人たちが、おそらく原作者とは全く違うやり方で、『鬼滅の刃』を多面的に楽しんでいたりする。そういうものが全体的にコンテクストを作っていくのだと思っています。
ただ、企業側から見ると、マスコミュニケーションということでCMにてコミュニケーションをしても、「あちら側から吸い上がってこない」という話になったりします。あるいは、CMの更新も毎日は無理で四半期に1度しかできないといった話になると、誤読の先の副作用みたいなものが大きくなり過ぎてしまう。だから手前で制御しようとするのだと思うんです。でも、COHINAのように毎日やっていると、誤読や勘違いも受け取って、「いや、そこは違うんですよ」とか、「それ、面白いですね」なんていう風になる。それを365日やれる状況が担保されているので、ユーザーと一緒につくっていくことができるのかなと思っています。
嶋:産業がコネクテッド化すると常時接続の状態になります。メーカーとユーザーは毎日接続している状態になる。そういう生活者と企業との関係性も相まみえて、誤読の共有やコンテクストデザイン的な、ある程度受け手に判断を委ねる、「ぬり絵的コミュニケーション」が進捗していくのではないかなと思います。ただ、今までのコミュニケーション、たとえば15秒のCMで「うちはこういう会社です」という風にやってきた感覚からすると、企業はそれなりの許容量を持たなければいけないという話になります。(後編に続く)





%20(16).png?fm=webp)

%20(19).png?fm=webp)


















.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)
.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)

.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)

















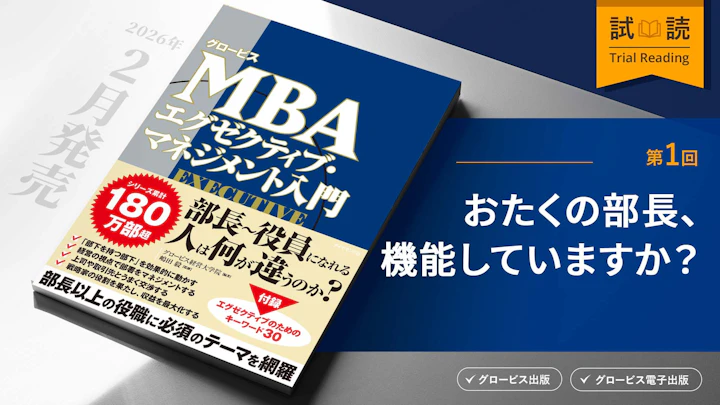
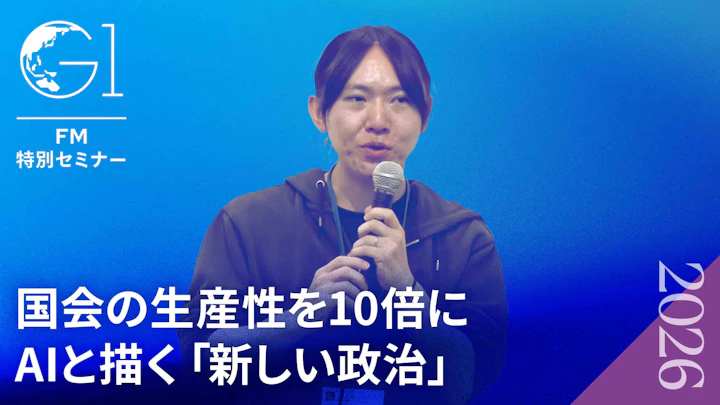


.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)
