本記事は、2018年7月7日に行われたあすか会議2018「競争優位を生み出すデザイン×クリエイティビティ」の内容を書き起こしたものです(全2回 前編、後編はこちら)
小笠原治氏(以下、敬称略):テーマには「競争優位」という言葉がありますけれども、壇上4人は「デザインで競争」といったことは、あまり考えていないと思います。ですから、テーマから少しズレていったらすみませんということは最初にお断りしておきます。
さて、田川さんは経産省のプロジェクトで、いわゆるデザイン経営について、「デザイン思考からデザイン経営へ」といったお話の取りまとめをなさっていますので、まずはそのあたりから。なぜ、国がそんなことを今言い出しているのか。実際の策定に関わったお立場から、デザイン経営とはどんなものであると委員会で考えていらっしゃるのか、といったお話からお願いします。
デザインシンキングからクリエイティブアクションへ

田川欣哉氏(以下、敬称略):「経産省 デザイン」で検索してみると、『「デザイン経営」宣言』というpdfのレポートが出てくるので、よかったらダウンロードして読んでみてください。これは去年から1年ほど続いていた特許庁と経産省の会議でつくられたものです。もともとの目標設定としては、日本の産業競争力を、たとえば技術の力ですとか、「〇〇の力」ということで、いろいろと高めていきたいという大命題がありました。そのなかで、「デザインも効くかもしれない」という仮説が最初に立てられていたんですね。それをハッキリさせるため、年に12回ほど行われた研究会の最終的なまとめが『「デザイン経営」宣言』になります。
これ、「デザイン」と「経営」という2つの言葉が入っています。「デザイン思考(Design Thinking)」というのは‘ing’だからhow toの部分ですよね。どのようにデザインのプロセスを走らせるかという話ですから、現場っぽい話が結構多いし、そこはなんとなく浸透しているところもあります。一方で、本当の意味で経営にデザインが入り込んだ形になったとき、どうすればいいのか。あるいは、そこで何がポイントになるのかという話もあります。また、それによってアウトカムとして何が出てくるのかといった疑問もあるわけですね。レポートでは、その3つの疑問に答えています。
小笠原:レポートを読ませていただいて、「デザインシンキングからクリエイティブアクションへ」という、「実践していこうぜ」という意思を感じました。その点、スマイルズはそれを自然に実践してきた会社というイメージがあります。スマイルズという会社、あるいはその経営のなかで、デザインはどのように位置づけられているのでしょうか。
アートはビジネスではないが、ビジネスはアートに似ている

遠山正道氏(以下、敬称略):私は最近、「アートとビジネス」といったテーマで登壇等に呼ばれることが多いんですね。そこで私は、「アートはビジネスではないが、ビジネスはアートに似ている」と言っています。私は三菱商事のサラリーマンだったとき、「このまま定年を迎えるのは嫌だな」と思って、なぜか絵の個展をやりました。そこからはじまって今日に続いているので、まさにアートのつもりなんです。スープストックトーキョーを会社に初めて提案したときの看板にも、絵画のキャンバスにマークを描いて提案しました。「これは作品です」ということで。(「スマイルズの五感」と呼んでいる)うちの5つの言葉のなかにも「作品性」という言葉があります。
これはどういうことかというと、アートにはコンテクストがあるんですね。世の中的に言うとコンセプトということだと思いますが、現代アートにはコンテクストがあって、「どうして?」というのが重要になる。我々のスープストックトーキョーにも理由はあるし、会社とか、他の各ブランドにも理由はあります。そして、それはすべて自分たちからの発信になっている。逆に言うと、外の理由に寄りません。だからマーケティングがないし、広告もやらない。自分たちが「これだ」と思ったものを提示して、「いいね」とか「ダメじゃん」とか言われながら進めています。ですから、逆に言えば軌道修正もできるし、ダメだったらダメという判断も自分たちでできる。
また、規模については、どちらかというと私は小さければ小さいほど面白いと、今は実感しています。たとえば、森岡書店というのをTakramさんと一緒にやらせていただいています。森岡君という人がいて、私が『やりたいことをやるというビジネスモデル: PASS THE BATONの軌跡』(弘文堂)という本の出版にあたってTakramさんでトークイベントをしたとき、彼が来ていたんです。そこで、「皆さんはどんなことがやりたいですか?」と聞いたら、彼が「1冊の本を売る本屋」ということを挙げてきた(編集注:参考動画「仕事をデザインする 世の中をデザインする」)。それで「おもしろいね」と言って、そこからスタートしました。これは5坪の店内で1冊の本を売るという書店ですが、おかげさまで今は海外を含めて引きが多い状態です。Takramさん経由だと思いますが、カルフールのフランス人役員が6人でインタビューに来たり。
小さければ小さいほどリスクも少ないから思い切ったことができて、そのぶん遠くまで届くという実感があります。だから、小さいほうが面白い。自分たちが作品だと思えば、むしろ小さいほうが、やりたいことがそのまま出るというか。もし森岡書店が150坪で5,000万かけていたら、今のような状態にはまったくなっていません。大きくなればなるほど甘くなっちゃうわけです。
もちろん、作品、あるいはビジネスならビジネスでもいいんですが、大きくなって連鎖していくようなことが必要なら、そういう選択肢もあると思います。たとえば私はこれから「The Chain Museum(ザ・チェーン・ミュージアム)」というものをやろうとしています。小さくてユニークなミュージアムを世界にたくさん、たとえば100箇所つくろうというものです。これはツーリズムのように巡るから、ある程度は数もあったほうが面白い。ただ、1つひとつは小さいです。とにかく今はそんな風に、ビジネスの起点、あるいは人事というか、1人ひとりのあり方のようなものも、すべて自分事になっています。
小笠原:自分ごとにできる適正な大きさってありますよね。僕らもDMM.makeというのを数年前につくりました。そこで目指しているものは、「大量生産から適量生産へ」という言い方をしています。欲しい人がどれほどいるかをしっかり見極め、本当に欲しい人に、その人たちが出せる金額で買っていただける適量を1回定めよう、と。
田川:そのあたり、水野さんも先ほど控室で話していらっしゃいましたが、今は「不特定多数から特定少数へ」といった流れがありますよね。特定少数がテクノロジーでようやく捕捉できるようになってきて。
小笠原:Cerevo(セレボ)という会社をやっていた岩佐琢磨は「グローバルニッチ」といった言い方をしていましたが、小さいものをつなげていくことで、ある程度持続的な経営・商売にしていける仕組みが、今はテクノロジーによって成立してきたのかなと感じます。
田川:先ほど水野さんが「江戸時代に戻っている」という風におっしゃっていて、面白い表現だなあ、と。
小笠原:そう、水野さんにはその辺も含めてお聞きしたいと思っていました。
江戸時代の経営では、経営者がデザインのこともしっかり考えていた

水野学氏(以下、敬称略):今、江戸時代なんですよ(会場笑)。皆さん、今は舶来物ばかり着ていますが、江戸時代だと思ったほうがいいんです。まず、商いの手法として、高度経済成長の前後50~60年、ここ100年ほどは、広告にすごく助けられた時代でした。マスメディアというものが登場して、テレビや新聞が一気に広がっていったわけですね。でも、今はそうしたマスメディアを通してモノを買うことがすごく減ってしまいました。たとえば「車が欲しいな」と考えたとき、最初に見るのが広告ではなくなってしまった。そういうことが当たり前の話になってきています。
では、今は何をもってして江戸時代と言っているのかというと、江戸時代の経営では、おそらく経営者がデザインのこともしっかり考えていたということです。店先の門構え、つまりファサードから、商品の並べ方から暖簾のデザインにいたるまで。もちろん暖簾屋さんと一緒にやっていたのかもしれませんが、店や商品、すべてにおいて見え方のコントロールを行っていた。僕はこの見え方のコントロールをブランドという風に申し上げています。
私は数年前に5年ほど、慶応SFCで「ブランディングデザイン」という授業を持っていました。ただ、当初、授業の名前をどうしようかと思い、「ブランディングデザイン」で検索をしてみると、当時はカタカナの「ブランディングデザイン」が5~6件しかヒットしなかったんです。7年前かな。でも、今は数え切れないほどヒットします。それほど、この7~8年でブランディングデザインまたはブランドというものに、企業あるいは多くの人々が興味を示すようになったということだと思っています。まさに、そういう経営スタイルこそ江戸時代の経営スタイルなのかなと思いますね。
小笠原:経営者がきちんとブランドコントロールをしていた、と。一方で、今世の中を見渡してみると、会場にいらしたら申し訳ないのですが、たとえば広告代理店さん経由で「こういうブランドをつくりましょう」と、ブランドをつくることに囚われてしまっているケースも多いように感じます。
遠山:私も、水野さんのお話とは少し別の意味で、「今後は江戸時代になっていくだろう」と言っていました。当時はきっと、農業も含めて商売人が8割で、奉行のような奉公人が2割ぐらい。それが高度成長期になってからは、奉公人であるサラリーマンや役所の人たちが8割で、商売人が2割ぐらいになった。で、これからはまた、フリーのライターとか、そういう人たちを含めて個人の単位が大きく増えて、むしろ「社員を6,000人抱えています」なんてことは企業としてやっていけないようなことになる、と。だから、むしろすごくやりがいがあると思います。江戸時代の感覚を持てば、今はそれを助けてくれるツールがインターネットやAI等いろいろありますから。それで、1人ひとりの感覚が生きる時代になっていくのかなという気がします。
小笠原:「デザインと経営」というと、今は見た目の話になることが多いと感じます。でも、もっと俯瞰したうえで、「どういう社会構造になるか」「企業体はどんな組織になるか」等、目に見えないデザインも考えていくと、究極的には今言われた江戸時代みたいな話になるのかなと感じました。
田川:デザイン的な感覚を持っている経営と、そうでない経営との、アウトプットレベルの質的な差というのは、1人のユーザーがきちんと見えているかどうかだと思います。マスコミュニケーションはn数が多めで、たとえば10万人にアクセスをして、そこで「購買の確率が◯%だから、価格はこういう風に設定します。すると、期待値はこうなります」と考えるわけですね。そのうえで、「いけ」とか「いくな」という話がメインになって、広告もそこにクリエイティブが入っていく。
一方で、今はおそらくクリエイティブのパワーが、先ほど水野さんがおっしゃっていたような、より本質的な形になってきた。提供するものについて、1人のお客さんがどう思うのか、かなり深いレベルで入っていく。で、それによって提供価値が口コミで伝播するから、パワーがそちらのほうに戻ってきているという感じがします。
「1人」の生活をドラマ化できるくらい絞り込んだものが「ターゲット」
水野:その辺についてお話をすると、僕は現場で、「『ターゲット』という言葉を簡単に使わないでください」と、よく言っています。「ターゲットはどうしますか?」と聞くと、「20代から30代の女性です」とか、簡単に言われるケースがあるんですね。ただ、20代から30代の女性は全員同じではないですから。だから、田川さんが言った通り、「1人」という言い方が正しいのかどうかは分からないけれども、本当に「こんな感じ」というのを“絵”に描いて、その人の生活について、たとえばドラマ化できるぐらいターゲットとして絞り込んでいく。そのうえで、どういう商品の届け方をするかというところまで見ていくことが今は求められているのだと思います。
遠山:ちなみに、ターゲットというのは、うちはないんです。アートだと思うと分かりやすい。アーティストが「来年絵の個展をやるんですけど」と言ってアンケートを取らないですよね。「それで返ってきた回答の上位3つを描いたんだけど、どうして買ってくれないんですか?」なんて、言わないですよね。「何を描くのか」「何を描きたいか」が大事なわけで、それが面白いところだから、そこを譲ってしまったらやる意味がないという。
小笠原:僕は今、京都造形芸術大学というところで「クロステックデザインコース」というコースを担当しています。こちらではアートだけでなく、テクノロジーや経営についても4年間で教えています。ただ、僕は高卒なので大学に行ったこともないんですが、今大学の現場に入ってみると、なにかこう、オペレーションをたくさん教えてしまっているようにも感じます。それで、デザインやアートと言いながら、下手をしたら今遠山さんが言われたような、「上位3つを描いてみました」というようなオペレーションしかできない人が本当に生まれそうで、怖いなと思っていたりします。
遠山:ターゲットについて、もう少しお話をすると、スープストックトーキョーでは(『スープのある一日』という)物語を書いていました。そこに「秋野つゆ」さんという人が出てきます。これは20年以上前に書いた物語ですが、たぶん「秋野つゆ」さんは「お客さんのペルソナ」と言われるものでもありません。というのも、日本で「ペルソナ」というと、たいていはターゲットを具現化するという意味になるわけですよね。でも、「秋野つゆ」はターゲットとは違っていて、自分のこと、つまりはブランド自身のことなんです。ただ、そこで「私が」と言うと、皆さん共感しづらいから「秋野つゆ」さんにしたという。
田川:遠山さんのことだったんですね。
遠山:言ってみれば、そうなんです。あと、うちのカミさんにもすごく似ている。「プールに行ったら首から上を出して平泳ぎするのではなく、いきなりクロールをする」とか。スープとは関係ないんですが、我々はスープ1つをつくるうえでも無数の意思決定を行うじゃないですか。それで、「装飾より機能を好む」とか「フォアグラよりレバーが好き」といったことまで、物語のなかでは書いていました。それならば、たとえば「猫脚みたいなノブではなくて、機能的なノブを付けたほうがいいのかな」という話にもなるわけです。そういうことを「秋野つゆ」さんという人を通して書いている。誰かのことではなくて自分たちのことなんです。
小笠原:すごく理解できます。僕は企画するとき、ペルソナというものを使うのが苦手で、言葉遊びになってしまっているかもしれませんが、キャラクターと言っています。「どんなキャラクターがどれぐらい出てきますか?」という風に、その人のキャラクターを深堀りするというか。自分たちで勝手に考えるだけなんですが、そのうえで「そういう人が来たら楽しい」とか、「そういう人が喜ぶものをつくろう」という風に考えています。
「自分は特別だ」と思っている全員に引っかかるような、もっと特別なものをつくらないと
遠山:うちはGINZA SIXというところで「刷毛じょうゆ 海苔弁 山登り」というお店をはじめて、おかげさまで好評をいただいています。8年ほど前から、「お弁当、気になるね」ということで、お弁当のワークショップをやったり本を出したりしていたんですね。で、いよいよお店を出したんですが、オープン1週間前、事業部長に「そうだ。銀座の真ん中でのり弁を出すと、どういう人が買ってくれて、どういう人が食べるんだっけ?」と聞いたんです。「丸の内ならなんとなく分かる。品川なら新幹線だと、なんとなく分かる。でも、銀座はどういう人だっけ?」と言ったら、事業部長も「いやあ、分かんないです」って(会場笑)。
要するに、自分たちがやれることを一生懸命やっているわけです。海苔は上位5%の、海苔屋さんには「え、これをのり弁で使うんですか?」なんて言われるほどの海苔を使ったりして、それを銀座ですべて手づくりしている。そこまではやるんです。ただ、そこから先はよく分からない、みたいな。だから最近は「ターゲットすらないのかな」と思いますね。100人いたら100人、それぞれ個性があるわけだし。
これは古い話ですが、「シーマン」というソフトがあったじゃないですか。20年前ですが、あれを開発した方の話を新聞で読んだことがあります。当時、あのプランを考えて仲間1人ひとりに見せたら、「俺は面白いと思うけど、これは売れないと思うよ?」って、全員に言われたそうなんですね。それで、「これはいける」と思った、と。要するに、20年前から“大衆”なんていう人はいなくて、1人ひとりが「自分は特別だ」と、全員思っていた。だから、特別だと思っている全員に引っかかるような、もっと特別なものをつくらないと。「ざっくりこんな感じ」では、ちょっと無理という感じです。
小笠原:オペレーションが得意になると、数字等、定量的なものに頼りたくなる気持ちも少し分かります。そこで脱オペレーションというか、きちんと考えてアクションを起こすということを、どこで教えていけばいいのか。これは今悩んでいるポイントですね。
デザインには「機能するデザイン」と「装飾として彩るデザイン」の2つがある

水野:僕は、デザインの意味は大きく2通りあると思っています。それは、装飾的なものと機能的なもの。機能するデザインと、装飾として彩るデザインという、その2つがきちんと理解できていないと、本当の意味でのデザインはできないのかなという気がします。その点、美術の大学ではどうしても装飾的なものが主導的になってしまうし、逆に美大でない大学だと機能デザインが優先されがちになります。でも、その両輪が回って初めてユーザーに届くデザインになるのかなという気がしています。その辺については、先ほどの経産省のpdfを見ていただけると。
田川:僕は水野さんと、それを肴にして一晩お酒を飲みたいぐらいです。そこを、人によっては「狭義のデザイン」「広義のデザイン」という風に分けたがるんですよね。「それは狭義のデザインの話ですよね」とか、「それは広義のデザインの話ですよね」なんていう風に。で、互いにポジションがあるから、そこで少し防御に入るような感じになる。でも、水野さんがおっしゃる通りで、本当に皆に受け入れられているプロダクトをつくっているところは、その両方をやっています。僕は「デザイン思考」が少し危険だなと思うのは、そういう風にラベリングされた、いわゆる「狭義のデザイン」を、結構低く見ている人たちも結構いるという点なんです。
水野:その通りですね。
田川:でも、たとえばアップルはDesign Thinkingというものをめちゃくちゃ使いますが、それを行うチームとは別に、ジョナサン・アイブがいる15人のプロダクトデザインチームもあります。ここは、鬼のようなクラシカルデザインのチームです。その2つがあるから成立している。テスラもそうです。あの、えもいわれぬスリークなフォルムとは別に、UXの体験みたいなものが両方揃っているからいい感じになっている。でも、教育を受ける順番等によっては、そのどちらかを通らなかったりすることもあるわけですね。
今日会場にいらしている方々はどちらかというと経営者候補だと思いますが、デザインというものを行う場合、その両方をやるということを覚えておいていただきたいと思っています。ひょっとすると、雇うデザイナーは、そのどちらかの人かもしれません。でも、どちらかだけはなく、その両方をやってバランスを取ることで会社のキャラクターができるのだと考えています。
水野:僕はそういうことをずっと言っていたし、経産省のレポートにも同じようなことが書かれていますよね。ほかにも、僕が言ってきていることとすごく似ていることがレポートに書かれているので、考えていることは一緒、というと失礼かもしれませんが、かなり近いのかな、と。
田川:水野さんと以前飲んだとき、水野さんが「俺さ、いいデザイナーって2種類しかいないと思っているんだよね」という話をされていました。1つは、新しい物事を、今までやっていなかった方法でつくってしまうタイプです。こちらはイノベ―ションに関わるほうですね。経産省のレポートでは「DESIGN for Innovation」と言っている部分です。で、もう1つは実際に多くの人々に受け入れてもらえるデザインをつくるタイプ。そちら側は「DESIGN for Branding」と言っていますが、たぶんその両方が必要なんです。
会社は「作品」であり、「私自身」でもある
小笠原:遠山さんがおっしゃるアートというのは、その両方をまとめていると感じます。
水野:そう。遠山さんが先ほど言っていたのは、もう会社が作品ということだと思うんです。経営者にも従業員にも、その意識が低い人は多いと思います。会社というのは利益を得るところだったり、社会に何か届けるものだったりするということは、なんとなく言われています。でも、自分が考えて考えて考えて、「こんなことがやりたい」「こんなのがあったら素晴らしい」という、自分の結晶や作品であるべきなんだ、と。その作品が頂点にあれば、機能デザインと装飾デザインというのは当然必要なことですし。アップルというのは、まさに会社自体が作品ですよね。そういう風になっていかないと、江戸時代においては簡単に見破られてしまう。
遠山:さらに分かりやすく言うと、作品だし、さらには私自身なわけです。だから、「恥ずかしいこととか、そういうのは無理」となる。ダサいと言われたくもないし。私は会社もブランドも、よく人にたとえています。「スープストックトーキョーさん」とか「スマイルズさん」とか。そう考えるとどうなるか。たとえば、誰にでも大事にしているものはいろいろあるわけですが、そのなかで「一番大事なものはお金です」と言う人がいたら、怖過ぎるじゃないですか。というか、たぶんそういう人はいないと思うんです。でも、なぜ企業だとそういう風になってしまうんですかね。それがすごく不思議で。もっと大事なものはほかにあって、それで4番目か5番目ぐらいにお金が来るんだと思います。もちろんお金がなければ食えないし、お金は必要ですけれども、「必要」というだけじゃないですか。
田川:たしかに。ほかの人と似たような話になったことがあります。旧来型のブランディング、マス広告的なブランディングというのは、「いつも赤い帽子をかぶっているおじさんだ」と。どこから見ても、同じようにきっちり帽子をかぶっているおじさん。遠くから見ても近くから見ても赤い帽子をかぶっていて、毎回同じことしか言わないおじさんがいたら、「友だちになりたくないよね」みたいな(笑)。昔は、企業とユーザーの距離が比較的離れていたし、関係が断続的だったから、それで良かったんです。でも、今はかなり密着していているから。
遠山:たとえば、「スマイルズさん」という人がやっているのは、スープやネクタイ、あるいはリサイクルとか、ホテルとか、本屋とか、のり弁とか。つまり赤い帽子ではなくて(笑)、そのとき気になることや好きなことをやっています。人であれば、飲食なら飲食だけということはたぶんなくて、映画も好きだし、夏は休みたいし、恋愛だってするわけですね。だから、そういう自分の気持ちや、今自分が得意だと思っていることや好きなこと、あるいは「出会っちゃった何か」とか、そういうことに対して忠実になればいい。でも、なにかこう、カテゴライズするんですよね。それが不思議だなと思っています。
小笠原:そうですよね。なぜ、皆それほどカテゴライズしたいのかというのは僕も分からないのですが、そうでない方法を取ったほうがうまくいくという。
遠山:たぶん、カテゴリーにしたりすると言語化しやすいんですよね。仕事は1人ではできなくて、巻き込まなければいけないので。仲間も銀行も。そういうとき、「どうして次がのり弁なんですか?」とか。そういうのはたしかにあります。あるんだけど、だからこそ、小さければ、リスクが少なければ、会社のなかでもこっそりできるという(笑)。
小笠原:カテゴライズなのかどうか分かりませんが、DMM.makeをつくるときは、「居場所のない人のための居場所をつくろう」と思っていました。つくりたいものはあるけれども、自分が勤めているメーカーではそういう仕事をさせてもらえないような人っているんだろうな、と。自分でつくったもので発表する場もなくて、つくっている過程を人と共有することもできず、みたいな。そういう人が結構いる筈だと思っていました。カテゴライズしていたのでなく、僕自身が知っている、そういうしんどそうな人を見て、「これ、たぶん日本中に1万人ぐらいはいるよな」と。そういう人が来る場所をつくろうと考えていました。カテゴライズとか、ターゲットとか、ペルソナとかではないけれども、「そこではない何か」というのが言語化できるともっといいなと思っています。
遠山:「作品」とか「自分事」という風に言うと聞こえはいいんですが、それをしている1つの理由は、そうしないとジャッジができなくなってしまうから。うちは、自慢ではないけれども、ぜんぜんビジネスがうまくいかないんですよ(笑)。売上や評価はいいんですが、利益は出ないというか。そういうとき、社内といえども、「これ、なんでやっているんだっけ?」という場面が何度も何度も出てくるわけです。そのときに「ペルソナが」とか「ターゲットが」とか「お客さんに言われたから」とか、そういうのだと、絶対に続かない。でも、そこで「誰が」「どうして」というのがあれば続く。「好きだ」という理由でもいいし、なんとか歯を食いしばって、粘ってやっているうちに、5~6年経ってようやく形になってきたということの繰り返しです。そういう根っこがないと無理だと感じます。
水野:おっしゃる通りです。遠山さんは経営者でもあるわけで、その辺のケツ拭きというか、自分がすべて責任を取るよというスタンスで裁量を社内に任せているから素晴らしいのだと思います。では、普通の企業はなぜそれができないのか。企業には内側からできていくパターンと外側からつくられてしまうパターン、大きく2つあると思うんですね。もしくは、その2つのタームを行ったり来たりしながら大きくなっていくと、僕は考えています。創業期は、基本的には内側からつくらざるを得ない。ただ、それで波に乗ってくると、すぐに収益性を考えるようになる。そのときに、中身はまだそれほど整っていないかもしれないけれども経済活動を優先して、自分達の思いよりも売れそうなほうに投資したり、早いリターンを狙って広告を打ちはじめたりするわけです。
これ、どちらが良いのか悪いのかという話でなく、その2つのバランスが崩れた状態が長く続くというのが良くないのではないかと思っています。外側からつくられる状態というのは、ユーザーがつくってくれるというのもあります。売れて、ファンができて、たくさん買ってもらったり。ミュージシャンなんて、まさにそうだと思います。あるいは、企業であれば広告を打つことで、たくさんのファンが一気に押し寄せてきたりすることもある。ただ、そこで自分たちが本当にやりたいことを見失わずにいられるかどうかが、今遠山さんがお話をなさったことにもつながるのかな、と。
その“イズム”が崩れなければ、どちらからやろうが、広告を打とうがブランディングをやろうが、どちらでもいいと思うんです。ただ、僕自身は「ブランディングデザイン」という言葉を世に広めてしまったと思っていて、それが早くも形骸化しているなと感じているんですね。ですから、今はブランドをつくることのできる経営者とデザイナーが、真に求められているという気がします。(後編に続く)



%20(16).png?fm=webp)
























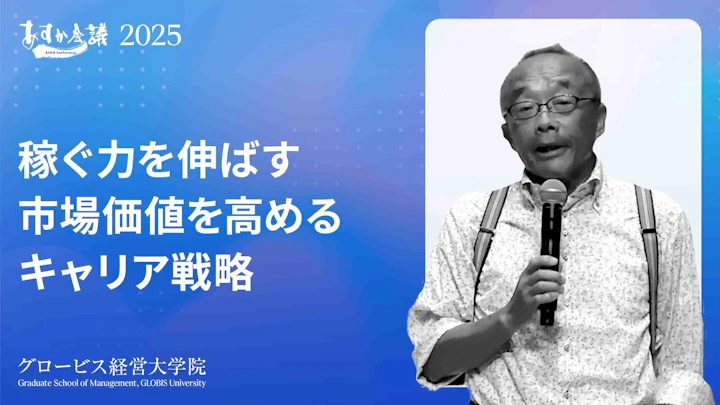






















.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)
