最近、メディアで見かける機会が圧倒的に増えたChatGPTの話題。前回はChatGPTとは何かを理解するための基本を解説しました。ではこうした基礎知識を踏まえて考えてみると、ChatGPTをはじめとした生成系AIの拡がりはどういったインパクトをもたらすのでしょうか。そしてビジネスパーソンは、どのように関わればよいのでしょうか。
言語モデルの軍拡競争
前回、モデルや言語データは大きければ大きいほど、言語モデルの予測精度は高くなるということを整理しました。
大きいことはいいことだ、とわかれば性能を上げるためにしなければならないことは見えています。そう、規模拡大の競争です。
次図は過去数年の言語モデルのモデルサイズ(パラメータ数、単位10億)の変遷を示したものです。OpenAIが先ほどの論文の結論に沿う形で、他社に先行してモデルサイズの拡張競争(GPT-3)に走り、他社もこれに追随したであろうことが読み取れます。

執筆時点(2月10日)、OpenAIに出資するMicrosoftのBingに搭載されたChatGPTはGPT-4と報道されており、正式には公開されていないものの、より大きなモデルサイズ、あるいはより大きな言語データで学習した言語モデルではないかと考えられます。
ChatGPTのインパクト
さて、ChatGPTの社会的なインパクトは何でしょうか?
今度はBingに搭載されたGPT-4ベース(?) の新しいChatGPTに聞いてみましょう。

あたかも有能なリサーチアシスタントのように、該当箇所に出典までつけて答えをまとめてくれています。
情報収集や制作のあり方の変化
同じ問いに対する答えをGoogleなどの従来の検索エンジンを使って書こうとすれば、検索して情報を収集し、自分で取捨選択と編集をすることが必要になります。しかし、対話的に問いに対する答えそのものが返ってくればその必要はなくなり、検索に比べて遥かに便利です。となると、現在支配的な地位を築いているGoogleの検索エンジン、さらに一蓮托生となっている大事な収入源の広告ビジネス(2022年の売上2,828億ドルのうち1,625億ドル)にとっては大きな脅威になりえます。
先述のように、当然Microsoftは自社の検索エンジンBingにChatGPTの搭載を開始しました。
また、すでにプログラムのコード作成分野では、傘下のソフトウェア開発プラットフォームであるGithub上で、GPT-3ベースのCopilotという名称のコード作成支援サービスが2022年に商用リリースされています。今後、WordやPowerPointをはじめとするMicrosoftの製品群にはChatGPTが当たり前のように搭載され、文章やプレゼン資料の作成支援に使われるようになることでしょう。
今回、ChatGPTはOpenAIが開発した言語モデルですが、名前に反して(?)コードやモデル自体は実はオープンソースにはなっていません。画像生成AIの分野ではStable Diffusionがオープンソースでコードや学習済みのモデルも公開しました。これにより、誰でもStable Diffusionを組み込んで新しいアプリを作ったり、また、例えばアニメデータを追加学習させてアニメに強いモデルを作ったりすることで、ユースケースが劇的に拡がりました。今後、こういった大規模言語モデル、言語生成AIがオープンソース化されればそのインパクトはさらに拡がることが予想されます。
人間に求められる力の変化
上記のような情報収集や制作を補助するツールの変化はわかりやすい一例にすぎません。イシュー(問い)を押さえ、仮説をもとに情報やデータを集めて分析し、それをもとに考えて問いに対する答えをまとめて資料を作成するといった、ホワイトカラーの価値の源泉となっている思考活動全般にChatGPTが与える潜在的なインパクトは極めて大きいものがあります。
問いを立てればとりあえずAIが仮の答えをつくってくれるのであれば、「問う力」がより重要になるでしょう。ただ、「問い」そのものを考える際もChatGPTとの対話を活用し、ChatGPTをあたかも思考のスパーリングパートナーとして自分の問いを磨く、といった形で使えそうです。
また、以上の話はあくまでAIが学習できる言語化された世界での話ですので、言語化しがたい世界を、身体を使って五感で体感し、いかに知覚するか、といった身体をもつ人間らしい知覚の重要性も高まりそうです。
そして私たちはどうすべきなのか
従来、グロービス経営大学院でも論理思考のクラス「クリティカル・シンキング」では、問題解決の際にはHowから考えず、何が課題か、イシュー(問い)なのかを最初に考えるよう、伝えています。これ自体は正しいのですが一方で、人は問いの設定をする際、「最初から解けそうもない問い」はなかなか設定しないものです。Howの知識の幅が問い自体の限界を規定しているといってもいいのかもしれません。
この20年近くの間にテクノロジーの進化によって大きく変わってきたのは、そもそものHowが大きく変化したことで、個別におススメを出すような、以前は解けなかったようなビジネスの課題設定、問いに対して答えが出せるようになったことです。同時に、AIが教えてくれるのであれば知識は不要なのではないか、という疑問も、そんなことはまったくありません。というのも、知らないことはそもそも知覚できない、からです。
AIが出してきてくれた答えの虚実を見極めるためという意味でも、課題設定の幅を広げるという意味でも、しっかりとした体系的な知識やHowの知識、体感値をあげていくことは重要になります。
だとすれば、答えはシンプルです。
まず使ってみましょう。
ピカソの言葉として伝わっているものに以下のものがあります。
“コンピュータは役に立たない。答えをくれるだけだから”
まさにビジネスの課題解決に向けてどのような問いを立てるのかが問われています。


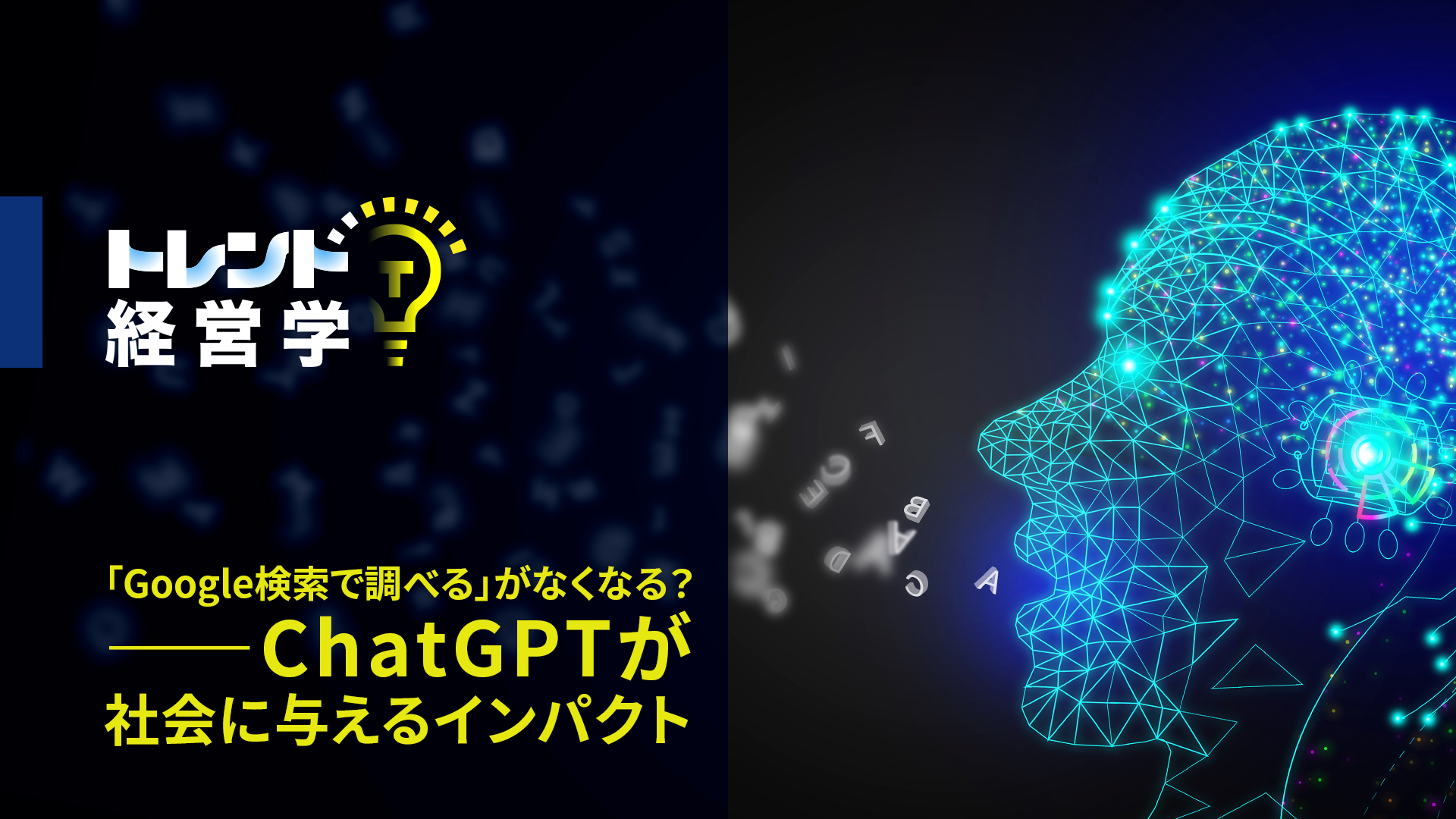










































.png?fm=webp&fit=clip&w=720)
.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)



