政府によってスタートアップ創出元年と位置付けられた2022年が終わろうとしている。取り組みの中で政府は大幅なスタートアップ支援策の拡充を発表したが、そもそも現在日本のスタートアップはどんな環境に置かれ、どういった課題を抱えているのだろうか。
次世代のイノベーターを育成してきた「始動」をはじめ、数々のスタートアップ支援プログラムの創設に携わる経済産業省の石井芳明氏をお招きしてのインタビュー。後編は、ユニコーンに成長し産業構造を変えていけるような企業・経営者のロールモデルを日本でうみだす方法について語る。(前後編、後編)(前編はこちら)
スタートアップを取り巻く環境は、変わりつつある
田村:シード期のアクセラレータープログラムであるG-STARTUPでは、若手の起業家、起業を志す学生の方と話す機会があります。会話をしていると、若年層にとって起業する、あるいはスタートアップで働くということへのイメージはここ数年で大きく変わり、当たり前の選択肢になってきていると感じます。
石井:日本のスタートアップを取り巻く環境はいま、変わりつつあります。最近は政府においても、以前はスタートアップとの関わりが薄かった省庁から「スタートアップ向けの支援策を強化したい」と僕ら新規事業創造推進室にお声がけを頂くことが増えてきました。
田村:世間一般としても、スタートアップが随分と身近な存在になってきた様に感じますね。
石井:2022年は『ユニコーンに乗って』というドラマが放送されていました。スタートアップの女性CEOが経営に奮闘する物語ですが、学生ビジネスコンテストを経ての起業やエンジニアの争奪戦、元金融機関の年上部下とのコミュニケーション、またEXITがM&Aだった点なども、リアルなスタートアップらしい題材が盛り込まれていましたね。これが地上波放送のTVドラマで話題になったというのは、今までにないことだと思います。
田村:私自身はいわゆる大企業のオープンイノベーションの取り組みの一環で社内起業家育成プロジェクトやアクセラレータープログラム・コーポレートベンチャーキャピタルの運営を通じ、会社を変えたり、ないところに立ち上げたりしてきました。アクセラという言葉が一部でしか知られていなかった2014年頃から取り組んできた身からすると、ここまで市場としても拡大して、認知度も増してきているのが嬉しい一方、信じられないような気持ちです(笑)
とはいえ、まだまだ解決すべき課題はあるかと思います。石井さんご自身としては、どういった点を注視されていますか。
石井:エコシステムの文脈で言えば、経団連のスタートアップ委員会がとても活発に活動していることが印象的です。大企業においてもこうした流れが来ているからこそ、リスクを取らないで安定的にやることばかりを重視する姿勢が残っている組織があるのならば、変えていってほしいと思います。始動のアルムナイをはじめ、尖ったチャレンジを実行する人材が大企業においても増えてきましたが、メインストリームになるのはこれから。頑張っていても苦労は多いであろう彼ら彼女らを、もっと所属する組織の方から後押ししてもらいたい。リスクを取らないこと自体が、今やリスクになりうるのですから。そこの理解が広まれば、より流れは大きくなっていくのではないかと思っています。
市場全体を伸ばす「集団出世主義」の考え方

田村:企業側あるいは市場側に求める点をお話し頂きましたが、スタートアップ側には何が必要だと思われますか。
石井:グロースするエクイティストーリーを現実に即して描けるメンバーは必要だと思っています。いま時価総額が数百億以上のスタートアップを見ると、ほぼ必ず投資銀行で大きなファイナンスを仕切っていた経験があるCFOやCOOを抱えています。また、テック系のスタートアップには成長の路線の中で知財の戦略やアライアンス戦略をどうするかまできちんと描けるCTOなどがいる。大きな夢を描けるCEOプラス、それを実現するための道筋が速い段階から明確に見える仲間、という組織構成です。
そういった組織を構築しようにも人員が足りないのであれば、外部から人を連れてくるという話にもなってきます。だからこそ先ほどお話ししたシリコンバレーへの派遣プログラムでは自身が成長するだけでなく、キーパーソンとの繋がりをつくってもらっています。
田村:先日シリコンバレーを訪問した際、始動を通じ親しくさせて頂いている琴さん(WiLパートナー:琴 章憲氏)とお会いしたのですが、「結局は脈々と続く、現地に根を張って世代ごとに続くネットワークにいかに入り込んで行けるか。日本の人は来もしないから、まずはとにかく来て、そこのネットワークを1つでも2つでも取りに行くことが重要」と仰っていたのが印象的でした。
石井:例えば始動の運営を担って頂いているWiLの伊佐山さん(General Partner & CEO:伊佐山元氏)も堀さんも、現地で密なネットワークをつくっていますね。今現在のキーパーソンとネットワークを作るのはもちろん、若い人同士でもネットワークを作っておいてもらいたい。当省の若手にも伝えているのですが、「今偉い人に会っていても、将来いろいろと仕掛けるときにその人がまだ偉いとは限らない。これからすごくなる人を見つけるよう幅広く交流するといい」という話をしているんです。
田村:それでいうと、グロービスに元々根付いていてG-STARTUPでも使っているコンセプトに、「集団出世主義」があります。各領域で頑張っている人たちが、自分が成功したら他の人を引き上げてあげるということをして、みんなで成長して出世していこうよという考え方です。これを実行していると将来的に、各セクターのリーダーの間でつながりが生まれ、社会変革の可能性も広がっていくんですよね。
石井:それは始動と相通じますね。実は始動では、毎年募集が始まると、アルムナイが自主的に応募者向けの説明セミナーを開催しているんです(笑) これはそういった、後輩を引き上げようとする連帯意識のあらわれだと思っています。
高い視座を持つ起業家とキャピタリストがユニコーンをつくる

田村:グロービスでは30年VC事業をやってきた実績を活かして、ユニコーンを目指して産業構造を変えていけるような企業・経営者のロールモデルを100社作ろうという目線を持っています。今後日本から成功するスタートアップを輩出していくために、起業家のすそ野を広げるという取り組みのほか、この「ロールモデルを作る」という面について、政府はどのような取り組みをしていますか。
石井:その点は経済産業省が推進するスタートアップの支援プログラム、J-Startupでまさに考えていることです。
スタートアップ政策の柱のうち、始動に並ぶもうひとつの柱がJ-Startupです。これはわかりやすく言えば、ある意味での「えこひいきをしよう」という取り組みです。
役所の政策は公平を原則としていますが、「世界で戦って勝つ」あるいは「勝つことによって新しい価値を提供できる人、企業を増やす」ということを意図するのであれば、それとは異なる尖ったやり方が必要です。そこで、とにかく世界で勝ってほしいスタートアップを「目利き」の方々にセレクションして頂き、集中支援しています。制度創設の時にはグロービスの堀さん(グロービス経営大学院 学長:堀 義人)にアドバイスを頂き、仮屋薗さん(グロービス・キャピタル・パートナーズ 共同創業パートナー:仮屋薗 聡一)にもご協力頂いています。
採択企業への支援の具体例としては、大臣の海外訪問時に同行してPRをしてもらったり、あるいは大臣が直接他国の大臣に電話をかけて特定の企業の後押しをしたり、国内外の展示会への出展支援、あるいは補助金の加点、入札の特例、規制緩和の検討などがあります。
こうした一気に成長を促し、ロールモデルを作っていく方法は、始動での取り組みを含め、有効な手段のひとつです。そんなロールモデルになりうる企業や、「自身こそがロールモデルになろう」といった視座を持てる起業家を増やす、という点は、G-STARTUPにも非常に期待しているところですね。
田村:2022年末から2023年始にかけ、G-STARTUPでは6th Batchの募集を行っています(募集要項はこちら)。選考の中で感じているのは、年々質が上がっていってるということです。今後も更に勢いを増していくであろうスタートアップへの期待について、最後に改めてお聞かせください。
石井:質が高まっていることは僕らも肌で感じています。先ほどお話しした社会の変化によって、自然体でスタートアップの世界に入って来てくれる方々が増えているからでしょう。だからこそ、いいコーチがつくとどんどん伸びるはず。そしてグローバルに出て行ってほしいですね。
田村:ユニコーンを目指すと言っても、国内マーケットだけでは幅が限られている。いかにDay1から海外のマーケットで戦える起業家を育成するかが重要ですが、そのためにはDay1からグローバルで戦える戦略を描き、コーチングできる支援家・ベンチャーキャピタリストも日本にはもっと必要です。だからこそ、起業家もキャピタリストも、海外に出て、修業して感覚を養うというのはひとつの手ですよね。
石井:現地のネットワークの中心に入り込んでいけるような人材を増やすためには、まず筋のいいところに入ることが大切です。始動ほかの施策拡充による派遣プログラムはそんな機会にしたいと思っていますし、他にも2023年は力を入れた政策を更に進めていくことになると思います。日本の市場全体を盛り上げていくために、あとにつづくスタートアップが「こうなりたい」と思える企業が増えていくといいですね。
始動やG-STARTUP、その他のネットワークを通じて、日本のスタートアップのエコシステムの好循環がうまれることを期待したいと思います。
田村:私も経産省の取り組みと足並みをそろえて、日本のスタートアップエコシステムの益々の向上に力を割いていきたいと思います。本日は貴重なお話をありがとうございました。


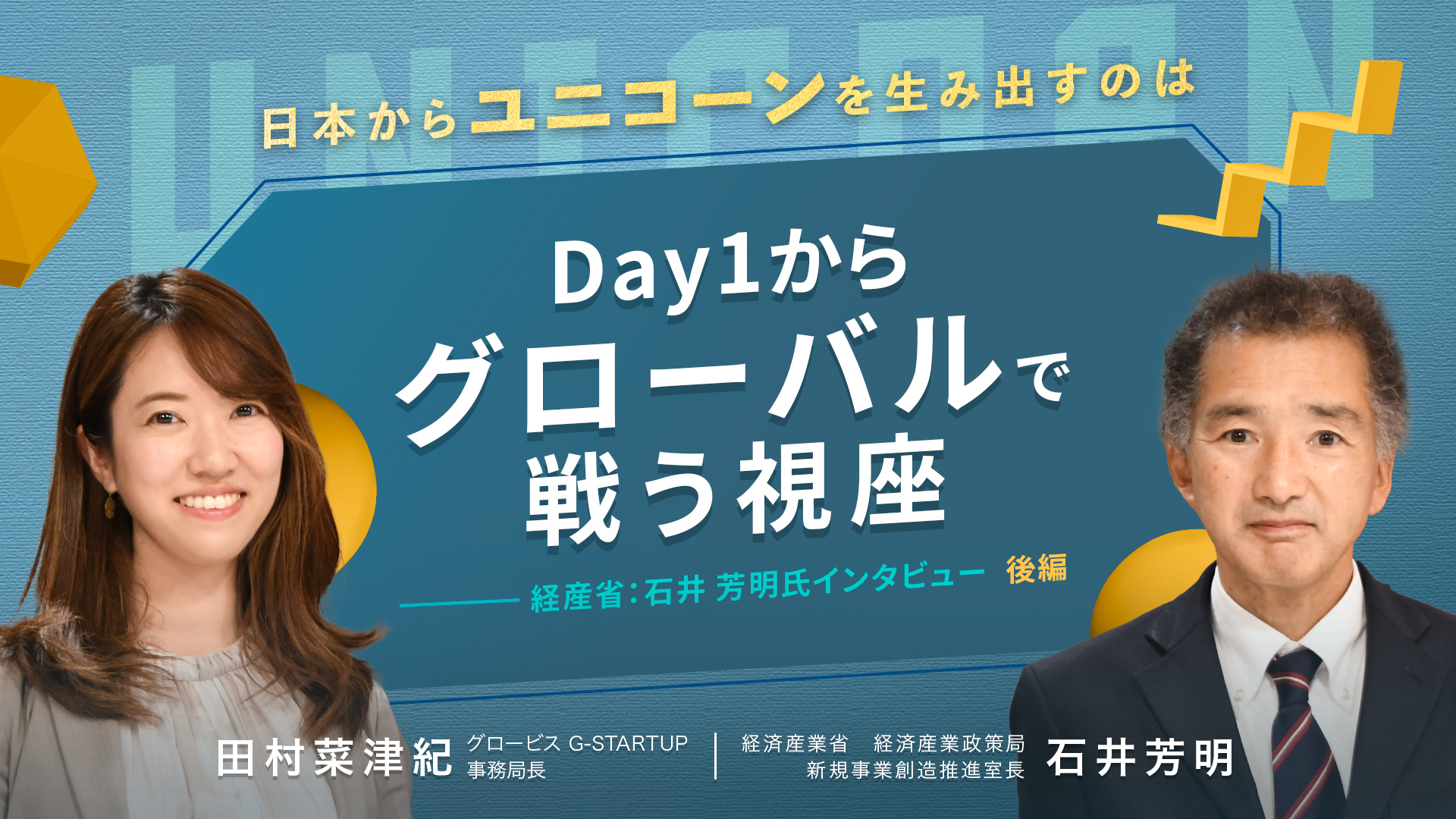




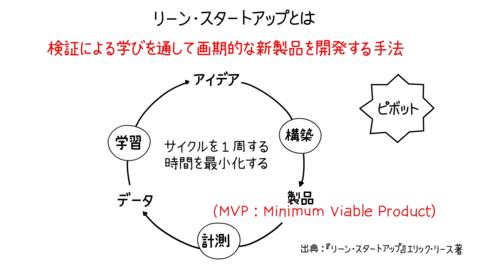































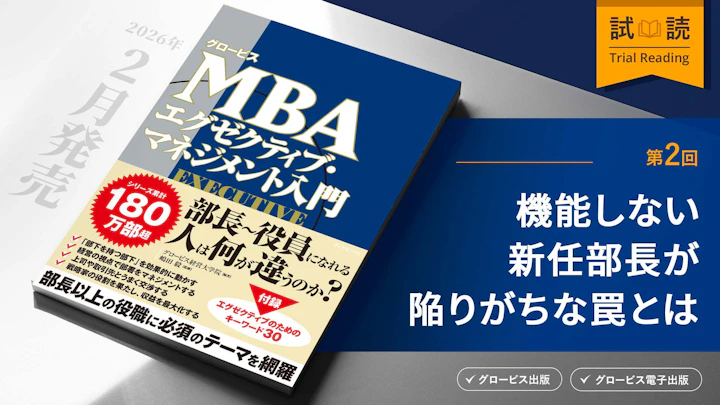




.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)
