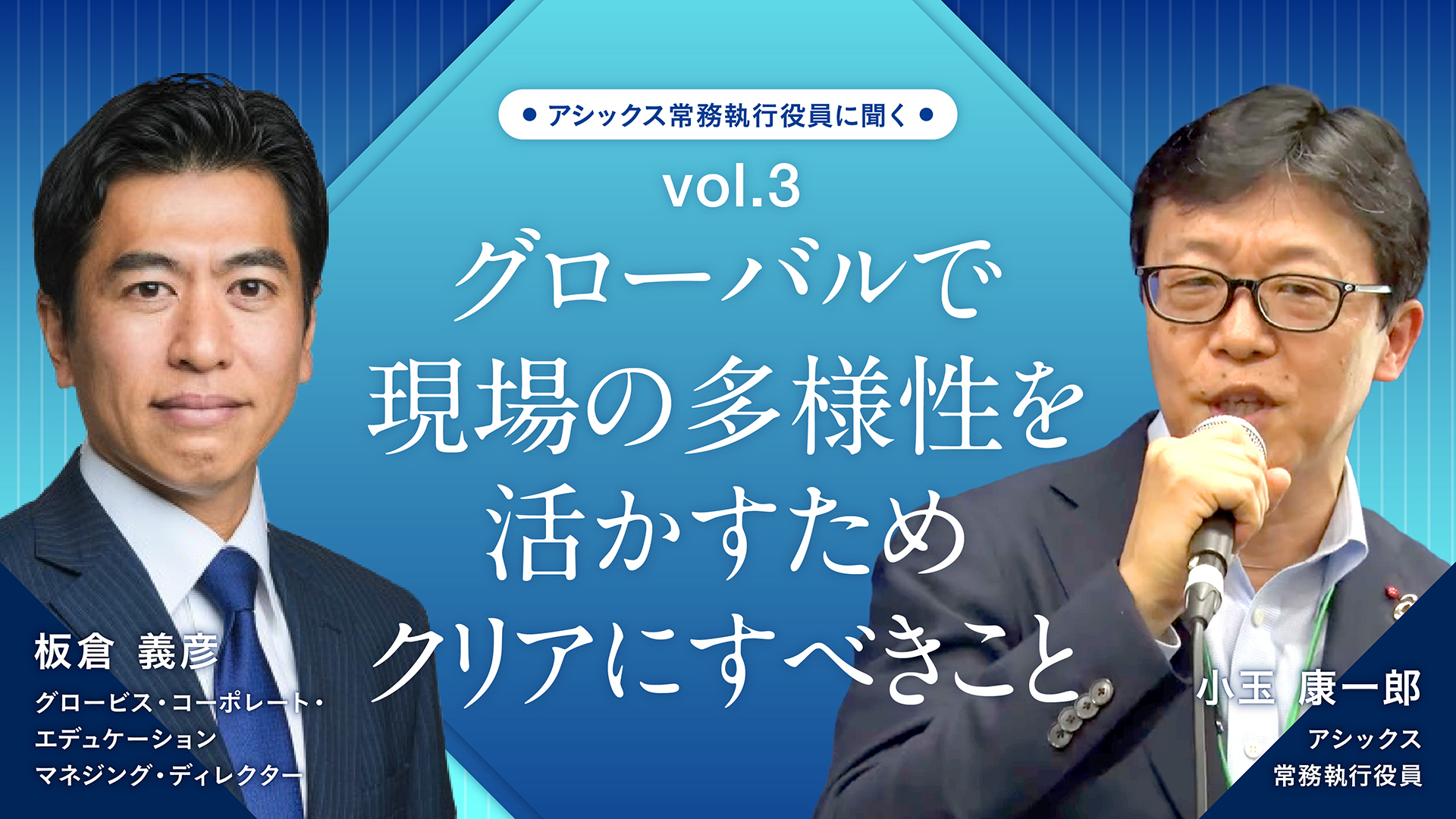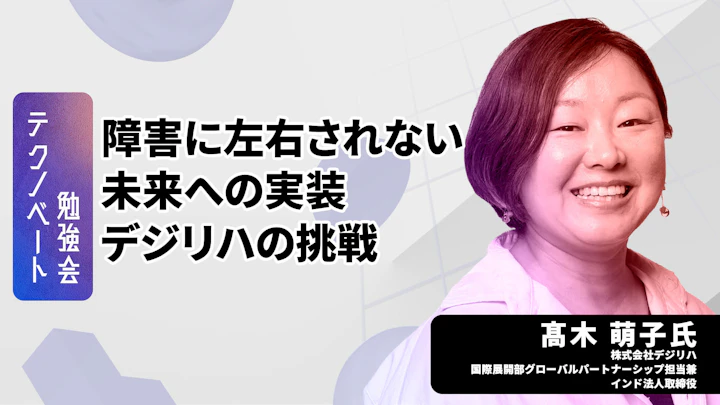グルジアとロシアの紛争。ソ連が崩壊して以来、ロシアが主権国家に侵攻したのはこれが初めてのこと。ロシアにとって1990年代はまさに失われた10年。1998年には経済的に崩壊しかかった。そのロシアが主権国家に軍を進めるほど自信をつけてきたということだ。
欧米諸国は一致してロシア非難に回っている。フランスがEU(欧州連合)議長国として調停案づくりに走ったのも、EUや米国の一致した支持があったからだ。
シナリオを描いたのはロシア?
今回の紛争はグルジア側が仕掛けた。親ロシアの南オセチア自治州にグルジア軍が侵攻したのがきっかけ。とはいえこのシナリオを描いたのはロシアというのが西欧の見方であるようだ。グルジア軍に仕掛けさせて、ロシア軍が平和維持軍としてグルジア領内に進駐するというのである。撤退条件に反して(ロシア軍は条件に違反していないと主張)、黒海に面した重要な港ポチに軍を配備しているのはその証拠かもしれない。
ロシアがそれだけ強気なのは、何といってもEUへのエネルギーの元栓を握っているからだ。かつてウクライナへの天然ガス供給を絞ったために、ヨーロッパへの天然ガスがストップしたことがあった。それ以来、EUはロシアを「潜在的脅威」と見なすようになっている。
ロシアがさらに自分たちの影響力を高めようと思えば、グルジアを自分たちの支配下に置きたいというのは論理的帰結である。カスピ海沿岸のバクーからグルジアの首都トビリシを通って、黒海へ抜ける石油のパイプラインがある。このパイプラインだけではなく、グルジアはカスピ海からの石油や天然ガスを西欧に運ぶ地政学的にきわめて重要な場所になっているからだ。
逆に言えば、グルジアにもし親ロシア政権が誕生したら、カスピ海からの原油や天然ガスは、ほとんどすべてロシアに元栓を握られてしまう。これはEU諸国としては何としても避けたいところだろう。
超大国としては力不足だけれど
もっとも、エコノミスト誌最新号(8月23日号)は、ロシアが超大国への復活をもくろんでいるとしても、それは「自信過剰」というものだと指摘している。
ロシアのGDP(国内総生産)は米国の10分の1にしかすぎず、ロシアの国防費は米国の7分の1でしかない。それに原油価格が下がってくれば、ロシア経済はすぐに転落することになる。紛争を引き起こすことはできても、世界のどこにでも軍を派遣する力もない。周辺諸国を脅せば、むしろそれらの国はロシアからの防衛に走る。ポーランドが米国のMD(ミサイル防衛)に協力することにしたのは、ロシア軍がグルジアに侵攻した直後のことだ。
しかしこのロシア・グルジア紛争で、ウクライナやグルジアがNATO(北大西洋条約機構)に加盟することはより難しくなる。これを強行すれば、ロシアがさらにいろいろな面で態度を硬化させるだろうし、場合によってはエネルギーをきわめて政治的に使うかもしれない。それではなくても金融危機とエネルギー価格の高騰が日米欧の先進国経済に影響を与えているだけに、ロシア発のエネルギー危機がもしあれば、先進国経済はかなり大きなダメージを受けることになるだろう。
もちろん、こうした事態になればロシアも大きな打撃を受けるが、エネルギーに関して言えば、元栓を握っている者が基本的には勝つのである。
▼「BusinessMedia誠」とは
インターネット専業のメディア企業・アイティメディアが運営する、Webで読む、新しいスタイルのビジネス誌。仕事への高い意欲を持つビジネスパーソンを対象に、「ニュースを考える、ビジネスモデルを知る」をコンセプトとして掲げ、Felica電子マネー、環境問題、自動車、携帯電話ビジネスなどの業界・企業動向や新サービス、フィナンシャルリテラシーの向上に役立つ情報を発信している。
Copyright(c)2008ITmedia,Inc.AllRightsReserved