前回は、地域で持続可能な社会を創出する事業創造の先駆者、小松洋介氏、立花貴氏、山内幸治氏から、ご自身たちの事業を具体的にお伺いしました。今回は、着想から実行プロセスまで、その試行錯誤の軌跡を具体的に語っていただきます。(第2回/全3回)
地域を変革する社会起業家に学ぶ事業構想と実行力[2]
村尾佳子氏(以下、敬称略):今回のテーマは「地域を変革する社会起業家に学ぶ事業構想と実行力」ですが、おそらく会場にお集まりの皆さまは、「ビジネスの現場でイノベーションを生み出すためのヒントが欲しい」「どうすれば地域の変革に貢献できるのか」等々、さまざまな課題意識をお持ちだと思う。まずは私からいくつか伺ってみたい。現在のお仕事や役割を担うにあたって、当初はどのようなきっかけや思いがあったのか。
小松洋介氏(以下、敬称略):リクルートで最初に配属されたのは出身地の仙台だった。「飛び込みに行って来い」と言われて新人時代に営業で走り回っていたエリアが仙台の沿岸部だ。だからよく知っていた場所だし、何かあれば帰ってきていたその場所で役に立ちたいという思いで、震災後にボランティアをはじめた。そして、その活動を通してどんどん気持ちが高まっていた頃、すでにリクルートを辞めていた周囲の悪いオトナたちに「今が辞めどきだ。挑戦しろ」とさんざん言われ(笑)、僕も「そうだな」と。それで思い切って辞めて飛び込んだという経緯になる。
村尾:生活のこと等、飛び込んだ先でいろいろと不安はあったと思うが。
社会起業家としての不安、その1「地元に溶け込めるかどうか」
小松:そういう不安がすごく大きかったから期限を決めていた。「半年動いて可能性が見えなければ、動き方を変えるか、もう1回(企業で)働こう」と。
実は、当初は入っていく場所も街も決めていなかった。いろいろな街を周るなかで「うちの街に来い」と言われた地域に、「あ、脈があるな」ということで入っていった状態だ。そして、そこで復興支援のお手伝いをしているうち、「もっと手伝え」と言われてさらに深く入り込んでいった。その結果、「このままじゃあいつが可哀想だからちゃんと仕事を出してやろう」という話に切り替わっていったという流れになる。当時の収入はたしかにリクルート時代に比べてすごく低かった。でも、そんな風に地域との関係をつくることができたとき、「ここでいろいろとチャレンジをすれば、収入を増やして生活していくことはできるんじゃないか」と。それで、もう半年、さらに半年、というふうに仕事を続けてきた。
「溶け込んでいけるかどうか」「ここで自分にできることは本当にあるのか」といった部分で答えを見出せたとき、女川に入っていく決心がついた、という感覚がある。
村尾:立花さんはどうだったのか。
立花貴氏(以下、敬称略):きっかけは本当に単なる家族の安否確認だった。だから「じゃあ、なんでそこまでやるんですか?」とよく聞かれるけれども、一言で表現すると「見ちゃったから」という感じになる。僕は学校を出たら故郷を出て東京で働くものだと思って育ったし、地元に戻る意識はなかった。でも安否確認をきっかけに戻って、それでふと見てみると、「あ、日本の地方行政ってこうなってたんだ」「学校教育ってこうなってたんだ」「一次産業ってこんな風に成り立ってたんだ」と。未来へ大きなツケを先送りにしているような、高コストな地域づくりになっているのを見て、そこに違和感を持った。
その点、民間企業で20年働いてきた経験と発想をもとに事業を通して解決できる課題があるんじゃないかと考えた。そうなると、「やはり持続可能な事業をつくって雇用を生み出すことが、結果的には地域を元気にすることにつながるんだろう」と。そんな思いで小さな事例を数多く積み上げるということに、これまでは注力してきた。
民間で働いていた時代から、地域や社会の課題についていろいろと考えていたかといえば、まったくそんなことはなかった。むしろ僕は、20年間、どちらかというとNPOやボランティアというアプローチを避けてきた人間だった。どうやって食べているのかも分からなくて。だから意識的に距離を置いていた。結果として今も昔も「どのように持続的事業にするか」という意識でやってはいるけれども、ある意味、目指すものは規模の面からみれば今と真逆だったと思う。
実際にやるにあたって、迷いや不安がなかったと言えば嘘になる。ただ、僕も一緒にやっている油井も、「できないという」という前提はなく、壁が高ければ高いほどそれを楽しんでしまうようなメンバーが周囲にたくさんいた。そして、本当に有難いことに応援してくださる企業や財団、あるいは企業に務めながら応援してくださるプロボノメンバー、ご支援くださる個人の方々、卒業生でもある浜の住人の方々など数多くの方々に支えられ、ここまでやってくることできた。
前職での経験も役に立った。僕は、商売で大切なことは2つしかないと思っている。1つは、飲食店や宿泊施設に来てくださった方、あるいは販売店で商品を買ってくださった方が、「もう1回来たい」「もう1回買いたい」と思ってくださるかどうか。そしてもう1つが、そんな風にて来てくださった方が「ほかの誰かを連れてきたい」と思ってくださるかどうか。その2点は事業が異なっても変わらないんじゃないかと思う。
村尾:続いて山内さん。学生時代からETIC.の立ち上げに関わっておられたが、そうしたキャリアを選ぶに至った価値観についてまずは伺いたい。
社会起業家としての不安、その2「自分が食べていけるか」
山内幸治氏(以下、敬称略):私の大学時代は、ちょうどバブルが弾けたあとの就職氷河期。一方、当時の私自身はというと海外の学生たちと交流するサークルにいたこともあって、目をキラキラ輝かせたアジアの学生たちが「国を背負ってやっていくんだ」なんていう話をする場面に触れる機会が多かった。振り返ってみて、当時の自分はそれほど高い意識を持って大学に入ったわけでもなかったとは思う。ただ、そうした海外の学生たちと交流するような環境にいて、「これからの社会ってどうなるんだろう」と、ある種の好奇心みたいなものがすごく出てくるようになっていた。
そんなとき、これもたまたまだけれども、当時の私はさまざまな経営者および起業家の方々とお話を聞かせていただく機会にも恵まれていた。そこで、ベンチャー経営者の方々が「こういう社会にしよう」というビジョンを語っていたところを数多く見てきている。ちょうど堀(義人氏:グロービス経営大学院大学学長/グロービス・キャピタル・パートナーズ代表パートナー)さんがグロービスを立ち上げたばかりの頃だ。実は当時、堀さんにもイベントでお話をしていただいたことがある。そんな風にして、たとえば堀さんがどういった問題意識で事業をはじめたのかといったことを聞いたりしていた。
当時、教育学部にいた私は、それまで起業という価値観をまったく持っていなかったし、将来についても「教師になろう」とか「メディアの世界に行きたい」とか、そういったことを考えている人間だった。でも、起業家の方々の生き様に触れていった結果、自分が起業するかどうかは別として、「社会をつくっていくことに関わる生き方にしたい」と。それが今の道を進むようになった原点というか、きっかけになる。
現在の路を進むことに不安はなかったかどうかに関しては、大学時代に限って言えば、社会起業をするためのハードルは低かった。家族を養うわけでもないので。ただ、自分のなかで決めていたことはある。大学時代、社会起業による私の初年度の年収は30万円。なので、当時は一人暮らしで仕送りもなかったから、生活費は夜勤バイトで稼いでいた。バイトに行けば無条件でお金が入ってきたわけだ。自分はETIC.で懸命に頑張っているつもりだったし、むしろETIC.における活動のほうに、より大きなエネルギーを使っていた。考える時間もETIC.での活動のほうが長かった。でも年収30万しか稼げない一方で、アルバイトに行くと必ず時給をもらえる。つまり、誰かがお客さん、ひいては社会にとって価値があることを回しているからこそ、そのなかで働いている自分にはお金が入ってきていたわけだ。
そう考えると、自分がやっているETIC.の仕事できちんとお金が回せないのは、誰かにとっての価値を残すことができていないからだと思った。だから、大学を卒業するまでに月20万ぐらいはもらえるような仕組みをつくれないなら止めようと思っていた。その結果どうなったか。最初に立ち上げたのはインターンシップの事業。スタートアップのベンチャーに、自分でも起業したいと思っているような大学生をマッチングさせる仕事だった。それがなんとか軌道に乗って、月20万ぐらいのお金はもらえそうだなというところまで行ったので、そのまま続けたという形だ。その意味では、ビジネスもNPOも、誰かに価値を提供しなければいけないという意味では変わりないように思う。
いろいろな社会起業家を見てきて、社会起業を目指す方には、大まかにいくつかの特徴があると思う。強烈な原体験をベースにしている人たちもいて、「震災があったから」というのもそうかもしれない。一方で、今はどちらかというと「こういう生き方をしていきたい」という意識が根底にある場合も増えている。また、課題解決型と価値創造型があるとしたら、未来のあり方や自分の暮らし方、あるいは周囲の人たちの暮らしのなかで、どのように幸せをつくっていくかという問題意識からはじまるケースも多いように思う。
社会起業家としての不安、その3「事業のお金を回していけるか」
村尾:続いて、「どうやってお金を回しているのか」という部分について、もう少し伺ってみたい。1対1の企業対顧客ならWIN-WINにするのは比較的容易だと思う。ただ、社会起業のセクターは1対1でなくトライアングルだったり、場合によってはさらに多くのステークホルダーがいたりする。そこでうまくシステムをつくるのは一般的な民間事業に比べて1段も2段も難しいのではないかと思う。そのあたり、小松さんと立花さんはどう感じておられるか。一般的なビジネスと比較して、特にここは難しいというポイントはあるか。
小松:最初に入ったときは、本当にとても難しかった(笑)。街づくりは、ある意味で社会づくりのようなもの。復興を経てどんな街や社会をつくっていくのか考える作業だ。そういう事業に入れていただいたわけだけれど、そこには行政の方もいれば、さまざまな産業界の方々も「俺たちの産業はこうなんだ」といった感じで入ってきている。だから各々の考え方がまったく違っていたりする。行政は公平性や平等性を大切にしたり、「行政がやることで民業を圧迫しちゃいけない」なんて考えたりもするわけだ。でも、民間とすれば「稼いでなんぼなんだ」という考えもある。そうした異なる意見を取りまとめながら、社会や街、あるいは仕組みづくりをしなければいけないという点では苦労した。
僕の場合は「聞く」ということは大切にしていた。被災地の人たちが何を求めているか、とにかく話を聞いていた。地方にうまくハマる人とハマらない人の差として、聞き上手かどうかということはあると思う。聞き上手な人はうまくハマる。一方で、「私はこれができます。これをやりましょう」と、現場の声を聞かずに話を進めようとすると結構入りづらくなったりする。だから、皆さんがどうしたいのかをよく聞いたうえでファシリテーションをする感覚だった。「それってこういうことですか?」という感じで提案を出して、「あ、結構、分かってるじゃん」と。そんな風にして距離を近づけたりしていった。
村尾:そのあたりは一般のビジネスと共通点がありそう。立花さんはどうか。
立花:資金も信用も人材もすべてがゼロからのスタートだった。民間企業における新規事業の負荷を1G(*重力の単位)だとすると、人口たった1000人で東京から500km離れていて、かつ公共交通機関もない雄勝町で持続的な雇用を生み出すための負荷は、もう10Gぐらいだと思う。逆に言えば、僕らのところへ来て新規事業を考えるのは民間企業の方にとって筋トレみたいなもの。「どのような価値を生み出せるのか」「企業のあり方はどうあるべきか」「20年後の自社商品・サービスはどうあるべきか」といったことを考えつつ、地域とともに新規事業開発を、大変な負荷がかかる環境下で行うので。そういう経験があると、民間へ戻ったときにすごくラクなんじゃないかと思う。その意味では人材育成にもつながると感じる。
そうした負荷を乗り越えるためには、もう「体感」してもらうしかないと思う。時間がかかるし、いろいろな方々が関わってくるので、それらを調整しつつ皆の話を聞くといった姿勢が求められるので。
僕の場合は、地元の方々に自身のコミットの強さを伝えたかったこともあって、すぐに住民票を移してしまった。それで、浜の漁師さんたちと一緒に会社をつくったり、漁師さんたちの息子さんや娘さんたちの学習支援や体験学習支援をするというところからはじめていた。繁忙期には漁師さんたちのお仕事を手伝わせていただいたりもしている。これは6年間続けているし、今でも行っている。「MORIUMIUS」のスタッフ全員、漁師さんの繁忙期には海に出る。夜中の12時半や1時ぐらいに出港したりして。そういうことを6年やってきた。そういうなかで信用の問題に関しては時間が解決してきたというか、馴染むことができるようになったのだと思う。
村尾:やはり人間関係がベースということかと思う。山内さんはどうか。
山内:ニーズがあって、ビジネスとして成立する条件が整っているなかでやるのなら、これはもう普通にビジネスとして株式会社でやったほうが早い。でも、そういうマーケットがないか、成立しづらい領域でやるのがソーシャルビジネスなのだと思う。そこでは、「目に見えない資本」という言い方がよくされるが、ボランタリーな経済をどれだけ回していけるかがカギになると思う。私たちはたくさんの方々に支援をいただきながら事業を進めている。目に見えないので分かりにくいけれども、そうしたボランタリーな力が背景にあるからこそ、事業を伸ばすことができているのだと思う。
では、どうすればそういうボランタリー経済が回るのか。そこで、先ほどから出ている「聞く力」といった部分がすごく大事になる。それは共感を集める力につながる。自分という人間に興味・共感してもらうためには、まずはこちら側が相手に興味を持ち共感して話を聞く必要があり、その意味で聞く力はとても重要だ。相手の話を聞いて共感していくことで関係が豊かになり、その結果として知恵を持つ人たちがいろいろ力を貸してくれる。その部分を回さないまま普通にビジネスだけで採算を合わせようとしてもうまくいかないケースが多いと思う。そこを回すことができるか否かが、ソーシャルビジネスで成功する人としない人を分ける大きなポイントになると思う。
たとえば、僕は小松さんのお話ですごく共感したことがある。震災直後、地域に入った小松さんは「ノート」を取っていた。そのノートというのは、住民の方々一人ひとりについて、どういう方なのかを詳細に書いたものだ。家族構成とか、「この方はどんなことに関心があるのか」といったことまで、すごく丁寧に書かれていた。これは、「右腕」として小松さんのところに派遣させていただいた当時の大学生に聞いた話だ。「小松さんに、『こういうことまで把握して地域に入っていかなきゃいけないんだ』ということを教わりました」と、当時「右腕」だった学生が話していた。
村尾:そこまでできるのは、やっぱり本気の思いがあったからということだと感じた。ただ、それでも今まで簡単な道のりではなかったと思うし、さまざまなご苦労のなか、「もう止めたい」「もう無理」と思われるようなこともあったと思う。そういったご経験等があれば、併せて伺いたい。
「もう無理」だと思った瞬間を乗り越えられたわけ
小松:仕事を始めてから1年が経つ前に、こういうことがあった。当時はまだ住民の方々についてもすべて把握していなかった頃で、ノートに「町内組織図」を描いて、「どなたとどなたがどういった関係でつながっているか」といったことを理解するようにしていた。「外から入ってきた人間として敬意を示さなきゃ」と思って、そういうことをやっていたわけだ。けれどもそのノートが完成する前、僕のこともまだ多くの方に伝えることができていない段階で、ある人から「お前は裏でお金をもらっているんじゃないかと思われてるぞ」と言われたことがある。
僕はボランタリーな気持ちで何かをやりたいと思っていたわけだけれど、そういう見方をされているのかと思った瞬間、なんというか、すごく嫌な気持ちになった。相当なショックで、それまでいろいろなことを丁寧に積み上げてはいたけれども、「もういいや」という気持ちになった。仕事をすべて投げ出して、仙台の自宅まで帰ってしまったことがある。そのときが一番しんどかった時期だけれど、ただそこから、どうすれば人の信頼を勝ち取れるのか、どうすれば共感してもらえるのか、ということもずっと考えるようになった。
私のそれへの答えは、まあ、すごくシンプルで、「やっぱり自分が動かなければ何も変わらない」と。だから自分のほうから動いたし、いろんな場に出ていった。地域ってすごく小さいし飲み屋も限定されるから、たとえば飲み屋へ行く。そこで、たまたま会ったフリをして「あ、こんばんは」なんて挨拶しつつ、話をしたりしていった。そこで「この人を紹介していただけないですか?」といったお願いをしたりして、地道に一つひとつ、信頼してもらえるよう努力していった。
その上で、一つひとつの目的をブレずに持ち続けることで、なんとか乗り越えてきた。たとえば、宿をつくるプロジェクトを進めていたら、まずはそれをやりきろうと。そうでなければギブアップしていたように思う。
村尾:「これは無理かも」と思うような経験について立花さんはどうか。
立花:正直、たくさんあります(笑)。結局は人のつながりでしかないから。まあ、自分も田舎の人間だけれども、田舎の人はモノをはっきり言う。ずけっと、オブラートに包まず。だから傷ついたりする。慣れていなくて。でも、はっきり言うのは家族、仲間だっていう意識があるからだ。狭い地域だし、情報が広がるのはLINEより速かったりする(会場笑)。僕が助手席に誰か知らない人を乗せて雄勝町に入ろうものなら、「誰か連れてきたぞ?」と、はるか先の浜にいる漁師さんから連絡が来たりするほど速い。そういうところでコミュニケーションを取っていくことが大事だった。だから、とにかく起きたことはなんでも話す。今日何を食べたとか、誰ソレとこういう話をしたとか、常に細かくコミュニケーションを取っていくのが大切なんだな、と。で、そういうことが分かったら、「あ、自分はそういうコミュニティのなかに入れてもらっているんだ」思えるようになってラクになった。
そんな風に消化できるまで、3年ほどかかった。当時、印象的だったことがある。あるとき浜で誰かがバーベキューをした跡が残っていた。漁師さんたちの大切な浜で。それで最初は僕らが嫌疑をかけられた。「外から来ていたあいつらの団体なんじゃないのか?」と。でも、そこで僕らを最初にかばってくれたのは漁師さんたちだった。「彼らがそんなことする筈はない。そんなことをしたらこの町にいられなくなるのを一番知っているのは彼らだ」と、役場の方をはじめ、いろいろな方に言ってくださった。実際、それは外から来た別の人たちがやっていたのだが、とにかく、そういうようなことを言ってもらえるようになるまで3年ぐらいかかった。
村尾:山内さんはいろいろな方を見てこられた中で、苦しい状況を乗り越える方と、途中で「もういいか」と止めてしまう方との間に、どのような差を感じられているか。
山内:一般的にベンチャーというのは3年以内になくなってしまうところのほうが多いけれども、私たちが10年以上続けている社会起業の創業支援では3年目以降も9割近くが事業を継続している。結局、非営利でも営利でも、きちんと価値を生み出すことのできる仕組みができれば事業は続くし、できなければ続かないというだけの話だと思う。皆がどんな部分で壁にぶち当たり、もがいているのか。いろいろな思いやアイディアがあって事業を興すものの、価値をきちんと生み出せない状態が最初の頃はどうしても続く。
おそらく震災後に東北でスタートした団体の多くは、今、それで苦しみはじめているという印象がある。当初は被災地ということもあって、寄付やサポートをしてもらっていたが、2年ほど前からはきちんと持続する事業モデルの構築に真剣に向き合わなければいけなくなってきた。そこで、きちんと価値を生み出せるモデルに磨き上げることが、今は求められているのだと思う。(第3回はこちら)
※この記事は、2017年2月20日にグロービス経営大学院 東京校で開催されたソーシャルナイトセミナー2017「地域を変革する社会起業家に学ぶ事業構想と実行力 」を元に編集しました


























.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)
.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)
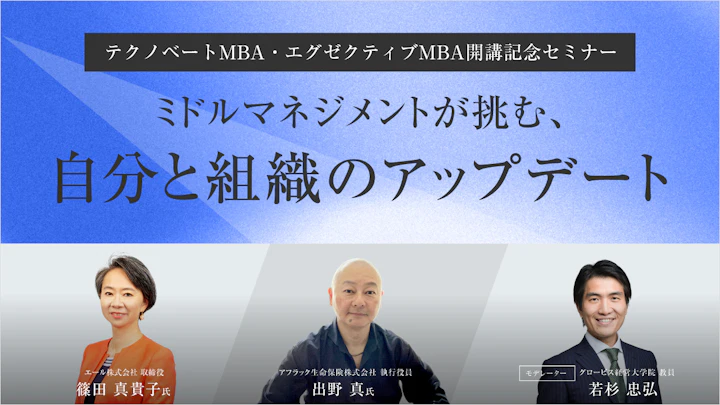
.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)


.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)

















.png?fm=webp&fit=clip&w=720)
.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)

