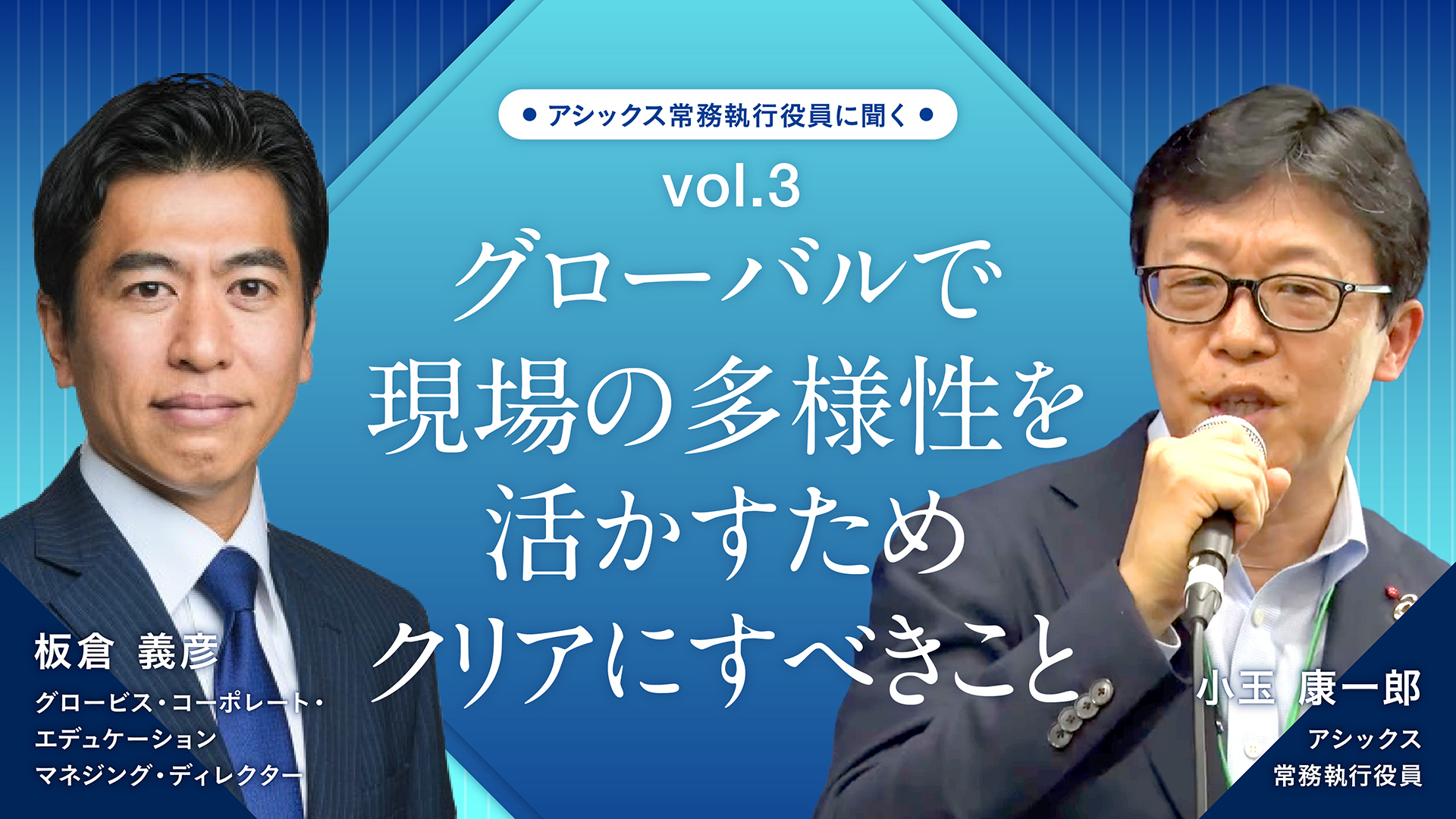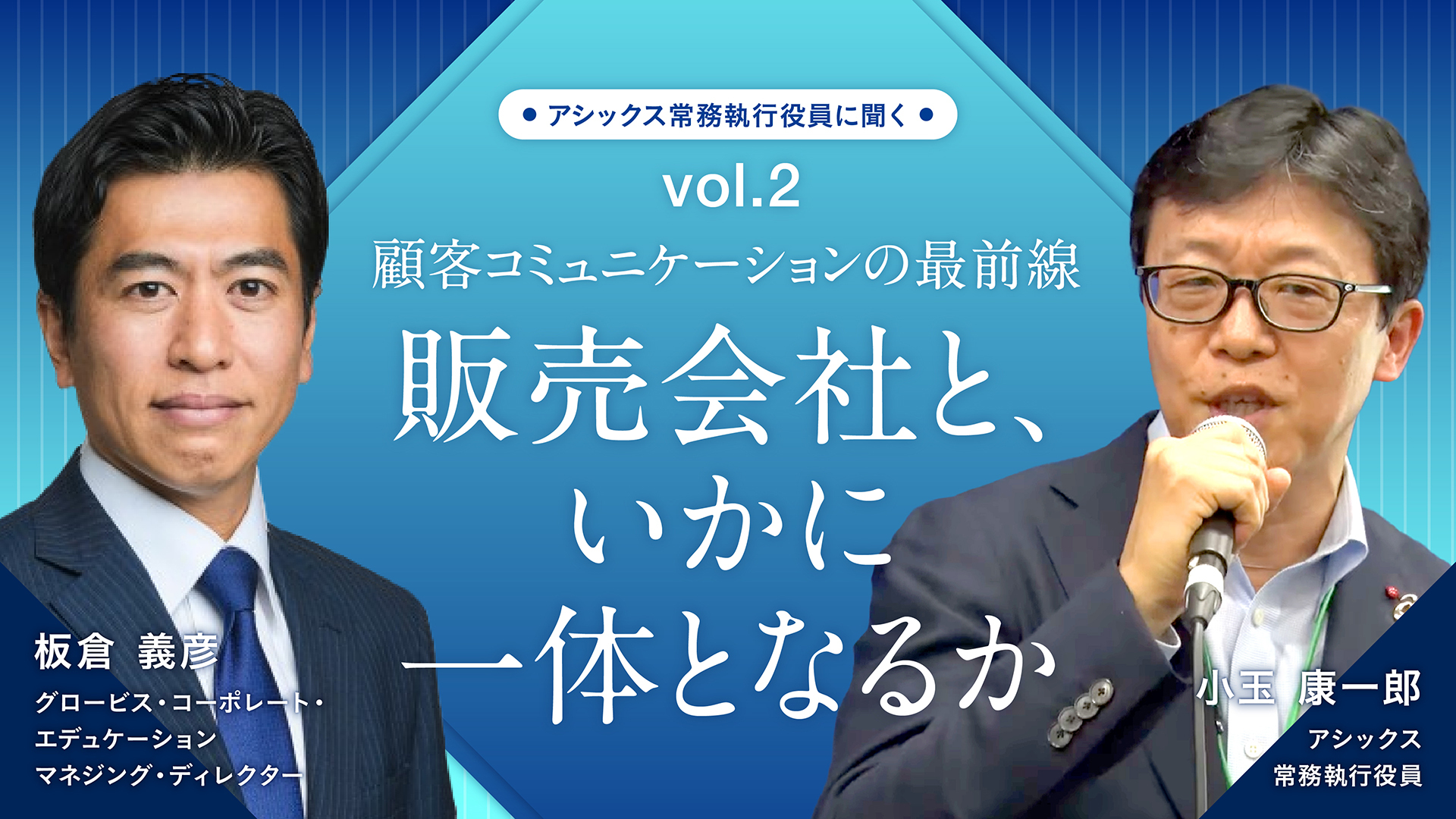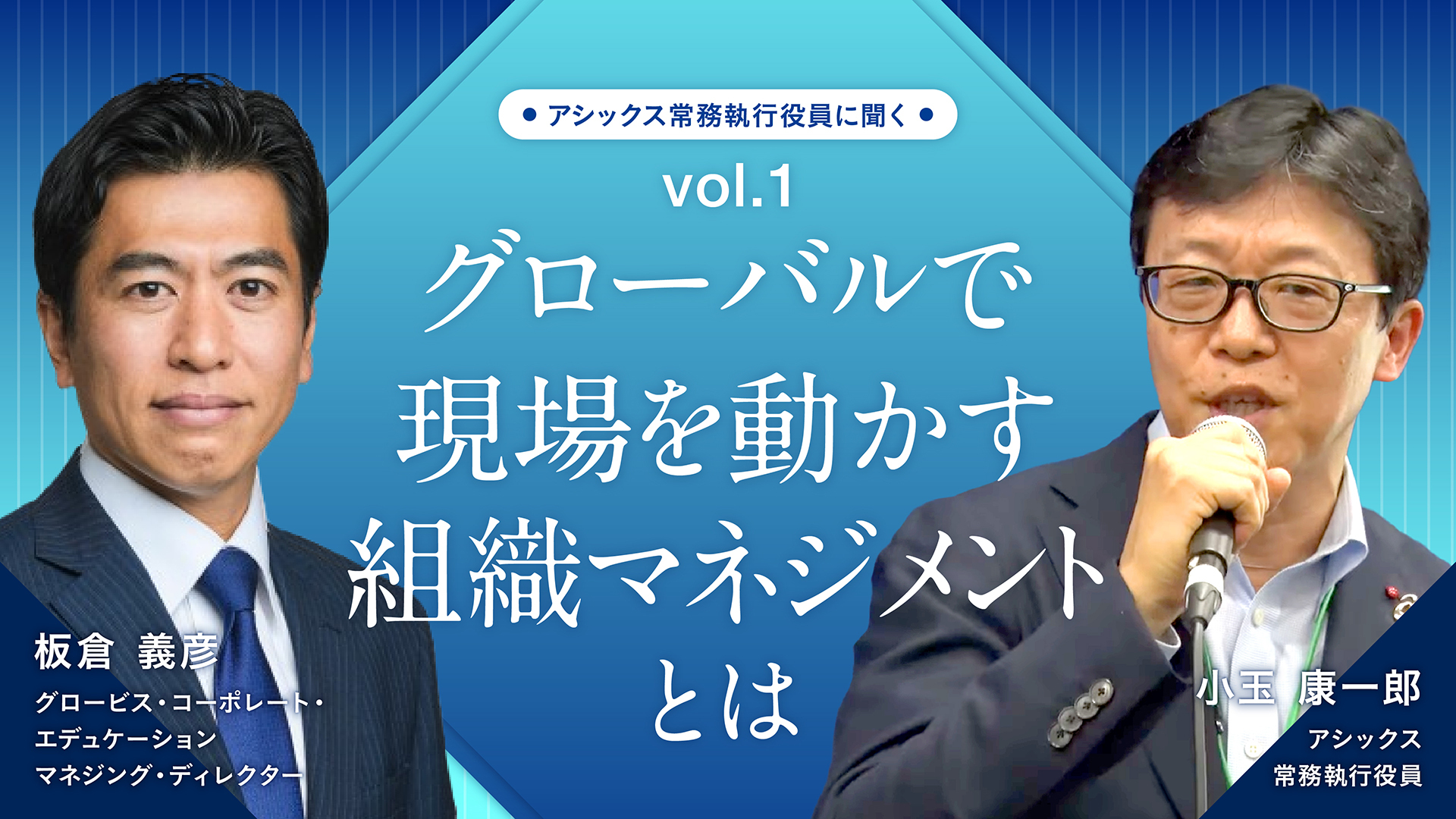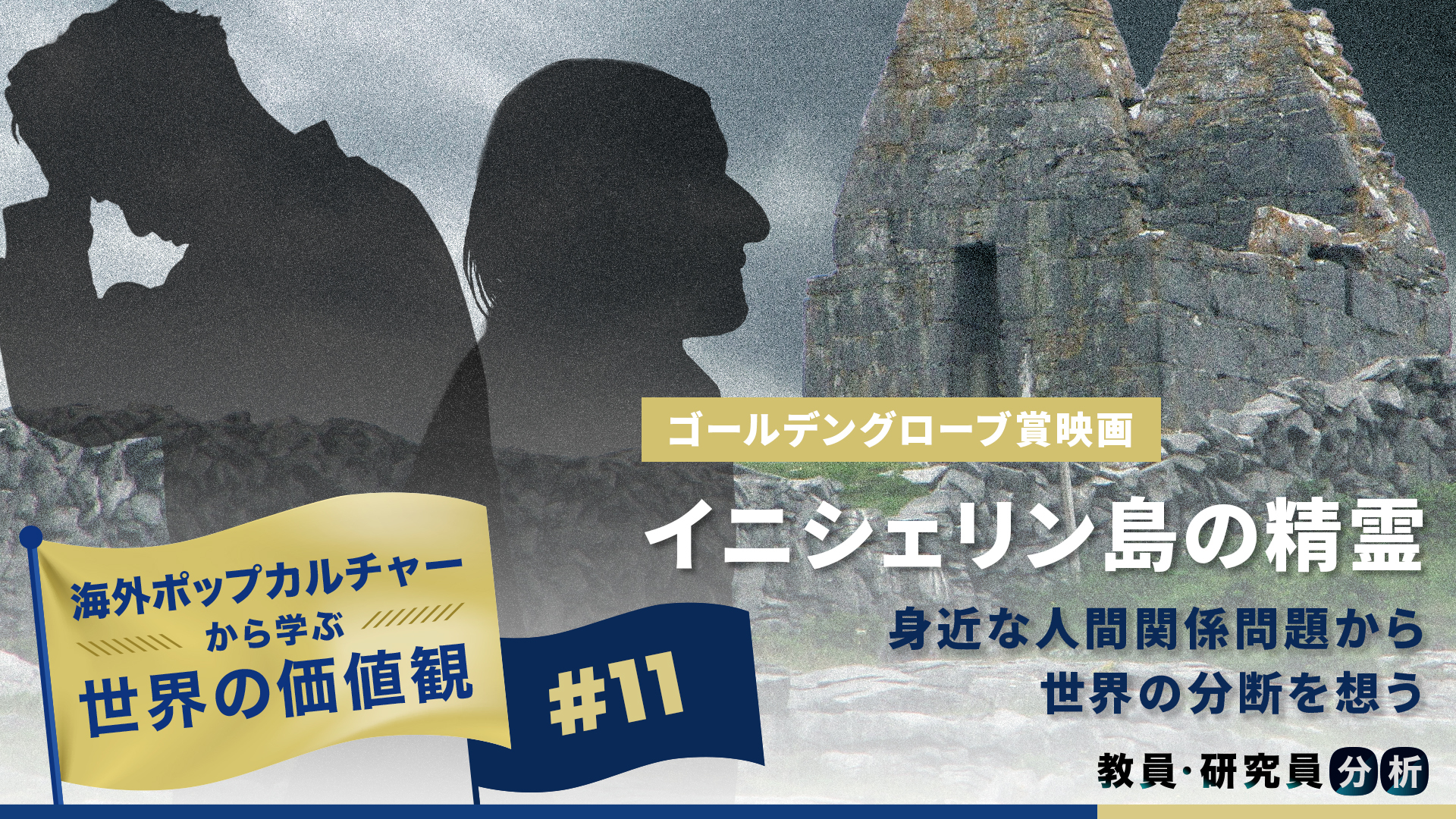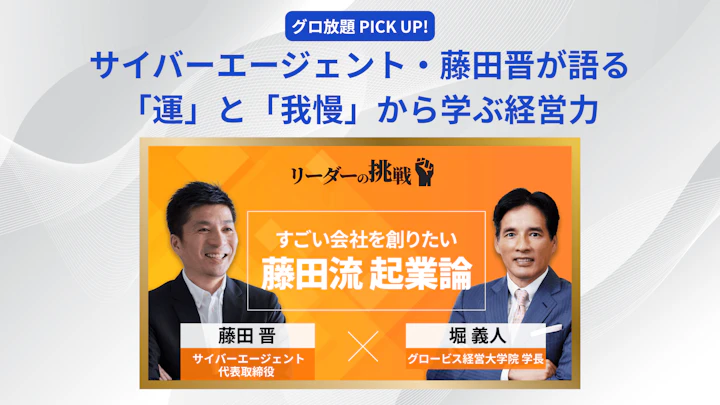日立金属タイランドの岸工場長(当時)のインタビューの冒頭で語られた、「日本人駐在員自らが襟を正して経営にあたる」という言葉。極めて当たり前の話であるにも関わらず、新鮮な響きとともに、背筋の伸びる思いをした読者も多いのではないか。日本人駐在員の給与までもオープンにして、正々堂々と自らの価値発揮に向き合ったことも潔い。岸氏をはじめ日立金属タイランドの経営陣のコミットメントの高さと「腹の括り」に敬意を表したい。うまく行っていない多くの企業においては、ここまでの「腹の括り」がないだけのかもしれない。案外単純なことに(しかし、実行となるとなかなか難しいところに)解があるように感じた。私自身も海外で事業運営を担う者として、感じ入るところが大変多いインタビューであった。
そのインタビューの中で、特に私が注目したのは、「現地化のプロセスにおいて、能力の差に着目するのではなく、習慣の差と捉えることが鍵」という点だ。この「習慣」というキーワード、海外の現場においては、異文化コミュニケーションというキーワードで外国人との関係について語られることが多い。しかし、私の現場感として、異文化コミュニケーションの考え方や方法論を学んでもあまり使えないという印象を持っていた。そこに、岸氏の「単に、持っている習慣の違いが組織での活動における難所になっている」という考えに、「的を得たり」という感覚を持った。海外の従業員の実行力が発揮されないのは「能力が違うのではなく、習慣が違うだけなのだ」という岸氏のメッセージを掘り下げてみたい。
人間の行動の4割は習慣によってなされる
全米でベストセラーになった『習慣の力』(チャールズ・デュヒッグ著)によれば、人間は自分の意志で行動を決めていると思っているが、実は全行動の4割は「習慣」によるものだという。つまり脳で考えることなく、無意識に身体を動かしているということだ。
この説が正しければ、企業の組織内の行動の半分近くは、習慣的に無意識に行われていることが多いということになるだろう。海外の現場や組織で、自社の仕事のやり方を説明し、論理的に仕組みを共有し、マニュアルを書き、行動を促しても、なかなかうまく行かないのは、「習慣」を変えるという発想がないからと言えまいか。一度身に付けた習慣を変えるのは簡単ではないにもかかわらず、従業員が新しい作業や行動をうまく取れないことを、得てして能力の問題と捉えてしまうところに問題があると、岸氏も看破している。習慣の問題を能力の問題と捉えてしまっては、対応策を誤るということだ。
組織にとって「良い習慣」を増やし、「悪い習慣」を減らすことができれば、理想的な組織作りがしやすくなり、人生は知らず知らずのうちに好転していくのだと。そのためには、「習慣」がどう作られるのかのメカニズムを知っておくことは有益だ。
「きっかけ」「ルーチン」「報酬」の三段階ループで習慣化される
既出の『習慣の力』によると、そもそもなぜ習慣が形成されるかと言えば、脳が常に楽をしようとするからで、脳は「いつ習慣に主導権を渡すか」「どの習慣を使うか」を常に決めている。従い、この脳の特性に従った三段階のループが習慣を強める。三段階のループとは
・「きっかけ」脳が自動作業モードになるように、そして、どの習慣を使うかを伝える引き金となるもの
・「ルーチン」きっかけに反応して起こる習慣的な行動や思考
・「報酬」具体的なループを将来のために記憶するかどうかを脳が判断する役にたつもの
この3つの要素を連動させ、「きっかけ」と「報酬」が相互につながると、強力な期待や欲求がうまれ、そこに一つの習慣が形成される。岸氏のインタビューの中で、何度も習慣化を促すには「気づく力」を鍛えることだという言葉が出てきたが、「気づき(=きっかけ)がなければ習慣化しない」という岸氏の言葉を裏付ける。
習慣を生み出す「力」とは
同書によると、習慣を生み出す力とは
1) シンプルで分かりやすい「きっかけ」を見つけること
2) 具体的な報酬を設定すること
だと言う。従い、2をどう設計するかも成功の鍵となる。岸氏のインタビューにも「お金のインセンティブ」に加えて、「心のインセンティブ」という言葉があったが、最終的に脳が「具体的なループを将来のために記憶するかどうかを判断する」ためには、脳を気持ちよくする必要があるのだ。
「習慣化」と「インセンティブによる仕組化」が現地化においての成功条件とまで言わないが、これがないと絶対にうまく行かないという必要条件だと考える、という岸氏の言葉を奇しくも裏付けるものとなった。日系企業の多くは、これまで得てして人の実行力を「能力」の違い、「文化」の違いとして捉えがちであったかと思うが、「習慣」の違いに着目して、組織運営や人材育成のあり方を見直してみてはいかがだろうか。