iPS細胞の未来 ~再生医療の実用化が世界に貢献する日~[2]
 世耕弘成氏
世耕弘成氏
世耕弘成氏(以下、敬称略):中学・高校とともに勉強した同級生だけれども、当時から勉強ではまったく敵わないし、スポーツでも敵わなかった。女の子にも彼のほうがもてていた。ただ、生徒会だけは私が会長で彼が副会長。当時から選挙だけは私のほうが強かった(会場笑)。今日は対談でなく、あくまでもフロアから質問を受ける係ということで、早速ご質問を受けたい。
会場(河野太郎氏:衆議院議員):今後、日本では社会保障費が伸びていく。で、年金はマクロ経済スライドで押さえ込んでいるから伸びるのは医療だ。となると、どこかで線を引いて「ここから上は自費でお願いします」としないと、今日お話しいただいたような新しい薬や治療法のすべてが保険収載になると予算でまかなえきれなくなると考えている。倫理的または現実的にそうせざるを得ないことについて、研究者のお立場ではどうお考えだろう。予算が多少増えてもいいからすべて保険収載すべきだとお考えだろうか。予算と医療の高度化についてご意見をお聞かせいただきたい。
山中:本当に切実な問題だ。アメリカの医療はまさにそういう状態だ。数多くの新薬が生まれている。たとえばC型肝炎。昔なら治せなかった病気が、インターフェロンができた今は経口投与で治せるようになった。ただ、それが1錠で10万円もするので治療に1000万円かかってしまう場合があり、それが飲めるかどうかで助かる人と助からない人が分かれてしまう。では、なぜそれほど高くなるかというと製薬会社の特許があるから。製薬会社でも開発費がかかっているからだ。
その点、日本が今まですべて保険にしていたのは良かったと思うし、できる限りそれを維持して欲しい。ただ、そのためには高額医療を減らすしかない。製薬会社の方もいらっしゃると思うから補足があればお願いしたいが、高額になる原因の一つは特許で、もう一つは治験。何千人という患者さんの治験に莫大な費用がかかる。
だから、まず特許に関して言うと、できるだけ国に研究費等を出していただいて、大学などの公的機関が主要な特許を押さえるようにする必要がある。また、何千人もの人間でいきなりやれば何百億もかかる。だからiPS等の方法によって、まず細胞レベルで対象を絞り込んでおく。効果が期待できない人に治験を行っても無駄なので。それで治験自体を現在の数10分の1に圧縮するといった面で、私たちとしては貢献したい。それによって馬鹿げているほど高価な先進医療を少しでも減らしたい。

会場(湯崎英彦氏:広島県知事):運営交付金と競争的資金の関係は本当に重要だ。現在、特に地方大学では競争的資金が増えて苦しくなっているところもあり、それで大学が地域をあまり見てくれず、お金が出てくる文科省ばかりを見てしまっているような面もある。だから、我々としても運営に使える安定的資金を産業界から集めることができないかと思っている。この点、京都大学で何か具体的に動いていらっしゃることや、「こんな仕組みがあれば」といったご提案があればぜひお聞きしたい。
山中:寄付活動は5年ほど前からものすごく力を入れていて、まずはファンドレイジングの担当者を雇用した。それで、「あなたのお給料はあなたが集めたお金から出ます」と。そういう言い方がいいのか悪いのか分からないけれども(笑)。これまで、大学の研究機関がそこまで懸命に寄付集めをすることがなかったが、私たちの研究所では年間5億という目標に去年も今年も到達している。ただ、アメリカで比べると大口の寄付額はまだはるかに小さいので、この点についていまだに悩みの種だ。
会場(山本雄士氏:株式会社ミナケア代表取締役):研究開発の重点分野はどのように決めていらっしゃるのだろう。社会保障費として大きなコストのかかる分野と、研究開発視点で魅力的な分野には、若干ズレがあると思う。たとえば人口透析は年間で一人およそ500万円かかる。で、透析を受ける方の平均寿命を10年とすると生涯で一人5000万かかるわけだ。それが、もしiPSによって1回の治療で済んで、しかもトータルコストが500万円で終わったら、これは社会コストが一人につき4500万円下がることになる。そのように社会コストを下げる視点で開発分野を選ぶということが、今はどれほどできているだろうか。あるいは、「まずは希少疾患・難病だ」「この分野なら日本が研究開発でリードできる」といったお考えが基準になるのだろうか。
会場(堀義人氏:グロービス経営大学院学長/グロービス・キャピタル・パートナーズ 代表パートナー):‘Welcome back to G1 Summit.’山中さんは5回目の参加だが、ノーベル賞を受賞してからは初めてのG1サミットになる。おめでとうございます(会場拍手)。iPS細胞研究で断トツとなるために、僕らが寄付以外でできることや、「こういうことをして欲しい」とお考えになっていることがあれば、ぜひお伺いしたい。
山中:重点分野の決め方というのは大変難しい問題だ。iPS細胞自体、10年前はどうなるかまったく分からなかったし、基礎研究の段階で多くの人から、「そんなのうまくいくわけない」と言われていた。ただ、そういう研究にも関わらず支援をいただけたので、たまたまというか、数多くあるリスキーなプロジェクトのなかからぽっと出てきた。従って、どうなるか分からないし成功率は低いかもしれないけれど、でも今までとは違う世界を生み出すかかもしれない分野で研究費を保証し、支援していくことも大事だと思う。ただ、一方では伸びてきた分野を見ながら選択と集中もしていくことも大切だ。だから、基礎的な部分は今後も文科省にきちんとやっていただけると思うが、選択と集中に関してはちょうど明日オープニングを迎えるAMED(エイメッド)という日本版NIHに期待している。選択と集中の司令塔になってもらえるのではないかなと思う。
それと、寄付…、以外ですよね(会場笑)。やはり人材面が大事だと思う。特に経営の部分。今は僕が所長をやっているけれども、経営者だった僕の父親は僕に、「お前は経営者になるな。向いていない」という言葉を残していた(会場笑)。その僕がなんのトレーニングも受けないままやっているわけで本当に危険だと思う。アメリカのほうでは、そうした部分でプロの素晴らしい経営者を雇っている。だから僕らは研究に専念できるわけで、日本もそのようになって欲しいと思う。会場にたくさんおられるような素晴らしい経営者の方々に…、給料は若干安いけれども、「大学の研究所経営や運営という点で、本気で力を貸してもらえたらな」ということはずっと思っていた。
会場(上月りょうすけ氏:参議院議員):iPS細胞に関して、今日ご提言があったようなことをやっていかなければいけないというのはよく分かる。ただ、今後は「第2、第3、第4の山中教授」と言えるような人材を輩出することも同様に重要だと思う。山中先生の研究を手伝ってくれる人でなく、山中先生のような人が次々と出てくるためには、どのような教育や環境が必要になるのだろうか。世耕先生に聞くほうが良いかもしれないが、教育におけるポイントのようなものあれば教えていただきたい。
山中:自分がどうだったかということだけを考えてみると、ある意味、すごく虐げられていたというか(笑)。人生を振り返ってみると、いろいろな意味で長らく、トップにはいなかった。だから偉い方のご加護みたいなこともほとんどなくて、なんでも自分でやらざるを得なかった。ただ、逆に言えばそれがすごく自由だったと思う。助けてもらえないけれど、何をしてもいいという感じで。だからアメリカにも勝手に行った。
そのうえで非常に運が良かったのは、37歳のとき、奈良先端科学技術大学院大学というところで、主任研究者として自分のラボを持たせてもらえた点だ。30代で独立できたのは本当に幸運だった。で、そのあとJST(独立行政法人科学技術振興機構)という文科省のファンディングで、年間5000~1億の研究費を5年間、iPS細胞の開発前となる2003年から支援いただいた。その二つだったと思う。JSTのお金は繰越もできたし相当使いやすかったというのもある。だからCiRAでは、自分がやってもらったことを今度はほかの人にしていきたいという思いもある。できるだけ30代の人を引っ張ってきて、基金の面も含めて彼らを精一杯応援していきたい。それで、実際に伸びてきてくれているので。ただ、30代の人を単に独立させるだけでなく、いろいろな面でサポートをしてあげる必要もあるなと思っている。

世耕:僕から見ていると、山中さんの研究のベースには中学・高校の影響も絶対にあったと思う。我々の学校には山中伸弥さんからオウム真理教の菊地直子までいろいろな人間がいたけれど(会場笑)、かなりユニークな教育だった。この辺については、ナイトセッションの席ででもまた二人でお話できたらと思う。いずれにせよ、第1回G1サミットの頃と比べると、iPS細胞もいよいよ実用化に向かってきたと感じる。G1の一つのプロジェクトということで、皆さまにもぜひ、山中さんの研究を今後とも応援していただきたい。今日はありがとうございました(会場拍手)。
→iPS細胞の未来 ~再生医療の実用化が世界に貢献する日~[1]
※開催日:2015年3月20日~22日
執筆:山本 兼司


























.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)
.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)
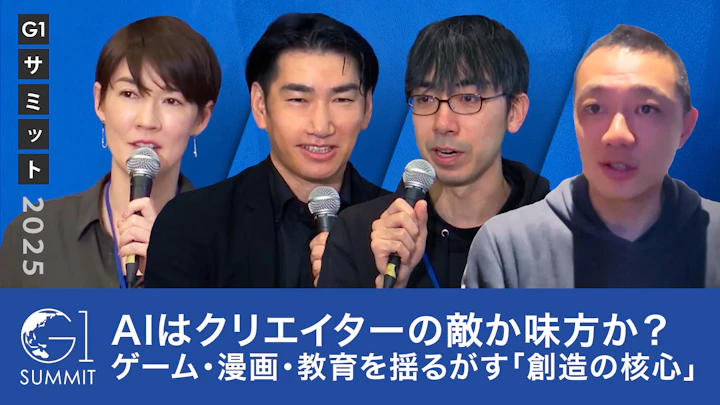
.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)
.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)











.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)


.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)




