「食の安全をわざわざ訴求するのは“このスピーカーは音の出るスピーカーです”と言うようなもの」(高島)
佐野友昭氏(以下、敬称略):福岡市とグロービスの共催による福岡ベンチャー・シリーズ。今回は記念すべき第1回ということでオイシックス高島社長とクロスエイジ藤野社長にお越しいただいた。起業の醍醐味を直にお伝えすることで、会場にいらっしゃる皆さまのなかから将来企業したいと考える人がひとりでも多く出たら思っている。まずはお二人が現在どんなビジネスをされているかというご説明からお願いしたい。
高島宏平氏(以下、敬称略):土曜日のこんな時間にベンチャーや農業あるいは流通といったテーマのセミナーに参加する人というのは変わった方が多いのだろうなと。グロービスの皆さまは相変わらず熱いというか、暑苦しい(会場笑)。楽しい感じです。今日は皆さまのお考えや視点も教えていただき、コミュニケーションしていかれたらと思う。
まずオイシックスについてご紹介したい。以前から当社をご存知であった方はどれほどいらっしゃるだろう(会場ほぼ全員挙手)、あ、ケーススタディで出ているのか。うっかり喜びそうになってしまった(会場笑)。ではオイシックスを通して何か召しあがった方は?(会場数名挙手)。…はい、きちんとアウェイであることが分かった(会場笑)。
僕らは食品の販売・宅配をメインにしている。いわゆる生鮮食品の販売だ。我々の業界は元々、「日本の農業を救おう」というところから出発した業界だが、農家に優しく消費者に少し厳しいサービスが多かった。しかし私たちは出来るだけ多くの人に消費者視点でサービスを提供したいと考えた。これは小売業やサービス業であれば極めて普通の考え方だが、農業や自然食品業では大変珍しい考え方でもあるのかなと思う。具体的には少し付加価値の高い無農薬野菜や有機野菜、あるいは添加物を使わない加工品等を販売している。
今は肉も魚もスイーツもお酒も惣菜もなんでもやっているが、農薬や添加物に関してはすごく細かいルールがある。その基本となる考え方は、「つくった人が自分の子供に食べさせることが出来るものだけを売る」というもの。その考え方をさまざまな農薬や添加物の基準に変換しながらやっている。食質監査委員会というものをつくり、加工食品に関して私たちが決めたルールと実際にやっていることが合致しているか、外部監査法人のような形で外部の先生方にチェックしていただいている。
その意味では食の安全担保が重要だと思っているが、それによって差別化していきたいと考えている訳ではない。食の安全性というフレーズは世の中で頻繁に使われるが、よくよく考えると極めて変わった言葉だなと思う。安全な食というのは、「食べていい食べ物」ということだと思う。しかし、「食べていい食べ物」が話題になるということは、きっと「食べてはいけない食べ物」や「食べないほうがいい食べ物」があるということで、「それってなんなんだ?」という感じがする。
他の分野ではあれば、たとえば「このスピーカーは音が出るスピーカーです」なんていうことをわざわざ言う人はいない。ところが食品に関しては食べられる否かをお客さまがスーパーで、パックの裏を見ながらなんとなく予測する。それで「食べられそうだな」、「食べないほうが良さそうだな」と考えながら食べていると。それが今の日本における食品流通業界の一般的な姿だ。しかし、「売るもの」が「つくった人が自分の子どもに食べさせることの出来るもの」というのは、食品小売業では差別化のポイントというよりも前提になるべきだと私たちは考えている。
ただ、その前提が世の中では一般的になっていない。そこに対してチャレンジしていきたい。従って、当たり前である食の安全性とともに、食本来の美味しさや楽しさといったものをいかに提供出来るか。そこで私たちはミシュランのシェフやメディアとともに、恐らく自然食品界で最もミーハーな取り組みを色々と行っている。で、小さなお子様のお母様というのが典型的なお客様のイメージだ。自分のことはもちろん家族に安全な食べ物を与えていきたいというニーズからオイシックスを利用される方が多い。それと、ビジネスモデルについてはなんでも良いかと思うが(笑)、非常にシンプル。基本的には仕入れて売るという小売の仕事になる。
最近は九州産品の取り扱いがすごく増えている。やはり震災の影響が大きい。私たちは震災にあたって恐らく日本で最も早く食品の放射能検査を行っており、検査を通ったもののみ販売している。検査をはじめた当初は、各所から怒られたり、励まされたり、いろんなことがあったが、今は僕らがはじめたやり方が一般的になっていると思う。
ただ、それでも西のものを召しあがりたいという方は多く、それで福岡市や熊本県との連携を今は行っている状態だ。自治体さんと組ませていただいて良かった点は、僕らだけではなかなか見つけられない、隠れた美味しいものをたくさん発見することが出来たこと。それで九州産品の取り扱いもここ1年で格段に増えた。いずれにせよ今はそんな風にして全国で1000軒以上の取扱先から仕入れている。
で、現在は売上145億に成長したが、我々の感覚としては13年もかかっているので極めてゆっくりとした歩みだと思っている。我々が扱っているような商材はニッチ市場で回している限り、恐らく私たちが存在する意味はない。しかし我々の事業が成長すれば幸せな食卓が増えるし、素晴らしい農業者様や漁業者様への経済的リターン拡大にも繋がる。だからもっともっと早く成長していきたい。と、いうことで会場に負けないよう無理して熱く語ってみた(会場笑)。とりあえず以上になる(会場拍手)。
佐野:今は実店舗も運営されているが、これまでは長らくインターネットに特化してきた。その理由を伺いたい。。
高島:これまでの自然食品のカタログ通販は、先にも触れたように、コンセプトとして農家さんに優しく消費者の方に少し我慢をしていただくようなサービスが多かった。たとえば何が届くか分からない野菜セットが毎週届くと。で、「入会金と年間費は農家義捐金として必要です。また、お届け時間はこちらで指定させていただきます」というのが従来のサービスだった訳だ。
私たちはそれがお客さまにとって結構なハードルになっており、継続した利用を難しくしていると考えた。そこで、一つひとつ選べる、入会金や年会費が不要、あるいはお届け時間もお客様で指定可能といったサービスにした。そこはやはりインターネットの力が大きかった。従来のカタログ印刷および配本のコスト、あるいは電話やファックスで受け付けた注文をデジタル変換する受注処理のコスト等を、インターネットで削減することが出来た。そこで生まれた余剰分を、今お話ししたような、普通であればコスト増や収入減に結びつくようなお客様の利便性向上に回していった形になる。
「自分でつくって自分で売る農業の実現により、農家を子どもたちが憧れる職業にしたい」(藤野)
佐野:藤野さんから見て、オイシックスのビジネスモデルで「ここがすごい」と思われる部分はあるか。
藤野直人氏(以下、敬称略):社長の前で言うのもおこがましいが、やはりオペレーションだと思う。こうしたコンセプトでやろうとしていたところは恐らく数多くあったと思う。ただ、オイシックスさんはそこでITによる効率化を実現し、物流の仕組みや受発注の正確性で群を抜いた状態になったからこそこれだけ広がってきたのかなと感じている。
佐野:農産物流通の分野ではオペレーションが大きな壁になるのか。
高島:立ち上げメンバーで農産物や流通をやっていた人間はほとんどいない。小松菜とほうれん草の区別もつかない若手男性もたくさんいた。ただそれでも、なんというか…、「これほど大変だとは思わなかったのでやっちゃった」というのが大きい。これは農業界や食品流通業界に限らないと思うが、業界に長くいる人は出来ない理由が簡単にたくさん思いつくのだと思う。僕らのビジネスモデルも、業界の方からすれば「本当によくやるね」というものだったと思う。ただ、僕らはその業界にいなかったから、それほど大変だと思わかった。やってみたら結構大変だったし、もしこれまでの13年間に渡る記憶が残ったまま20代の頃に戻ったらこのビジネスをやることはないかなと思うが(笑)。従って、一般的に大変だと言われるポイントはたくさんあったが、それらは解けない問題でもなかったのかなと思う。
佐野:では藤野さんにも伺っていきたい。中規模流通という言葉も使っていらっしゃるが、現在どんなビジネスをされているか、ご説明をお願いしたい。
藤野:その辺については著書を買っていただくと早いが(会場笑)、まず自己紹介からはじめたい。僕自身は農家の倅でもなんでもない。中学3年のときにたまたま観ていた「NHKドキュメント」で孫正義さんやビル・ゲイツさんを知って、「ああ、すごいな。この人たちは何をしているんだろう」と思ったことが起業を志したきっかけだ。その気持ちが実際に起業するまで変わらなかった。
で、元々は奈良県生まれだが、東京の大学と九州大学を受験し、そして東京のほうが落ちてしまった。それで九州にご縁があったのだろうなということで九州に来た。そして大学在学中、たまたまインターンシップでお世話になっていたコンサルティング会社が青果市場の経営再建に取り組んでいたという流れになる。
学生だった僕はそこで農家廻り、あるいは青果市場や仲卸さんやスーパーさんへのヒアリングを行い、3〜5年後の青果市場がどうあるべきかという絵を一緒につくったりしていた。プロジェクトが継続していたこともあり、そのまま大学卒業して4月から12月までそのインターンシップに行っていた会社にお世話になっていたが、「藤野君は来年どうする?」と聞かれ、「自分で会社を興したい」という話をした。そして年が明けた3月に立ちあげたのがクロスエイジという会社だ。
今日は同業界ではない方もたくさんいらしていると思うので、農業・青果物流通の魅力や面白さについてもお話ししたい。基本的に、僕としてはクロスエイジで農業を魅力的な産業・職業にしたいと考えている。農業の産業化だ。農業の産業化が何かと言えば、ひとつは自分でつくって自分で売る農業ということになる。やりがいも大きく、重要なことだと思っている。
そこで今は、農協に出荷する従来の形をとらず自分でつくって自分で売っているプレイヤーのお手伝いをしている。有限会社や株式会社で農業をやっているところは多いし、たとえば我々は「ネバリスター」という長芋をつくっている若手農家とも契約している。今はこうした若手農家、あるいは昔からこだわりをもってつくり、そして自ら売っている篤農家と言われる人たちに注目が集まっている。実際、今は夫婦や親子で法人を経営して1000万の所得を実現している方もいる。「農家は儲からない」というイメージをお持ちの方はいると思うが、売上ではなく所得が1000万レベルの農家が九州にはたくさんいる。その多くはテレビに出ているような有機農家等でなく、どちらかというと業務加工用の契約栽培や施設園芸等で大きな利益をあげている方々だ。
日本の農業が世界一になれるとしたら、やはり品質と生産性によるものとなるだろう。限られた面積で高い収量をあげ、少量のオペレーションで効率的にかつ高品質な産品をつくりだしていく。また、流通・加工のなかでひとつの素材からジュース等の加工品をつり、それを海外輸出までするという事例は海外でもなかなか見られない。現在はそうした領域で世界一を目指すような取り組みがあちこちで行われている。我々はそのお手伝いしながら、農業を小学生にとって憧れの職業にしていくといったようなことを経営理念としている。販路を基点としてその動きをどんどん促進させていきたい。
「マーケティング支援により、農協経由の大規模流通と自力で契約を取る小規模流通、その中間を実現する」(藤野)
藤野:そこで出てくるクロスエイジのコンセプトが中規模流通だ。最近はネット販売や直売所への出荷、あるいは地産地消に自ら取り組んでいる農家もあるが、それらは小規模な流通に留まってしまっている。また、その一方で九州には大規模農家が多く、農協市場流通において自分で価格を決めることが出来ない、あるいはこだわりが評価して貰えない農家も多い。現在はその二つしか選択肢がなく、その点が農家にとって辛いところだ。そこで我々は、前者を小規模流通、後者を大規模流通としたとき、その中間となる流通を手掛けたいと考えた。たとえば量販店さんや生協さんあるいはオイシックスさんのような全国的通販会社との契約、または業務加工用の契約によって、自分がつくる価値にふさわしい量を出荷するという流通だ。
我々はそこで生産でなくマーケティングを担っていく。たとえば農家とともに商品コンセプトを考えていく。我々はその辺について、「消費者目線を持った農家の味方」という表現をしている。重要なのは農家の情報を消費者目線で翻訳し、そのうえで商品コンセプトをつくることだ。また、生産と流通のコスト分析も行う。収量増加や生産コスト削減を行いながら、最終的には供給・販売企画という形で一つひとつの商品を世に送り出していく。たとえば農業生産法人でつくったトマトに関して、「アイコという品種で、色は三色でやりましょう」と。それをひとつのダンボールに18パック、6ケースで括り、宅急便対応で全国に出荷していきましょうと。そうした商品化企画を行っている。
また、我々は卸の事業も手掛けている。トマトであれば11月に出はじめるから、そこで全国規模の量販店やマミーズさん等の地元スーパーに販売を行う。農産物の難しいところは時期によって収量が変わる点にある。トマトは4〜6月に大変増えるから販売先を探さなければいけない。そこで、たとえば関西のライフという量販店さんに週間300ケースで仕入れていただいたりする形になる。
農産物で難しいのは、たとえばスーパー向けに「甘金時」「しっとり甘いも」といった商品名でサツマイモを出荷するのだが、サイズはMとSだけになる点だ。では他の2Lや2Sはどうするのか。我々は、「端から端まで売っていく」ということで、たとえば小さいものは自然解凍して食べる冷凍焼き芋に商品化している。そんな風にして加工にも携わりつつ取り組みながら、農業経営が良くなるよう販売方法や販路について考えると。その一方で消費者目線もきちんと考えるという流通をさせて貰っている。
それと業務加工用についてだが、この分野は非常に伸びている。たとえば畑で育てたネギに関して根っこから抜かずに出荷する部分だけを切って、その後再び伸びた部分をまた切る。それを繰り返しながら出荷するというつくり方で、コストを従来の半分から1/3まで落とせる。我々はそうして収穫したネギを、たとえば博多ラーメンの上に乗るネギとして、牛丼の味噌汁に入るネギとして出荷する。そうした業務用の大根や茄子やトマトも、九州中の農家と契約して全国に出荷をさせていただいている。
販路開拓は基本的に年に4〜5回の商談会で行っている。現在は80ほどの取引先がある状態だ。そこで農産物を並べて名刺交換したバイヤーさんと繋がり、商品を供給していく。大きく分けて、量販店さん、生協さん、通販会社さん販売、そして業務課効用の販売というのがメインになる。
我々としてはそうした中規模流通による卸がメインのビジネスとなっているが、農業コンサルという形で紹介されることも多い。たとえば中規模流通に対応していきたい産地があった場合、行政の委託を受ける。今年は福岡県から県産農産物の商品化ということで業務委託した。地産地や農協向け出荷でなく、商品化したうえで全国あるいは県内で売るという部分を請け負っている。また、復興庁さんの予算で東北における植物工場の農産物流通等も考えている。
それと、現在は「時や」という直営店舗でも自分たちが商品化した農産物を売っている。創業4年目に高宮で1号店を、同6年目に春日公園で2号店をオープンした。今月は渡辺通りの清川という商店街で3号店をオープンする。皆さん、10月19日は皆さん空けておいてください(会場笑)。そんな風にして中規模流通を軸にして卸とコンサルそして小売の事業を展開しているが、そのほかにも全国で仲間づくりを行っている。中規模流通を地域間で行うような地域商社の仲間づくりということで、全国にネットワークをつくったりもしている状態だ。そこでクロスエイジは事務局としてノウハウの交換や商品のやりとりを行っている。
売上についてはどうかというと、第1期は100万円だった。僕の役員報酬は20万円。どう考えても赤字だ。第1期は650万の赤字だった。ただ、2年目には売上900万円前後ということで収支トントンぐらいになり、3年目は売上4100万で390万円の利益が残った。ここまで一人でやっていた。3年ほど死に物狂いでやったらなんとなく光明が差してきたということになる。そして4期から6期にかけて24人採用しており、ここで第2の苦しみがはじまる。売上はその後2億にまで膨らんだものの、利益がなかなか残らなかった。そして第7期は震災の影響もあって売上も一旦下がっている。で、直近は3億近くにまでいっており、現在は3億7000万前後で推移している。
社員数はパートを0.5人換算すると今は12.5人ぐらい。労働生産性は845万円。一人当たりの稼ぎである労働生産性を常に指標としているが、これについては大企業の平均が910万前後と言われているのでそれに近い労働生産性を目指している。主に20代の若い社員たちが営業やコンサルをやっている会社だ。
今後のビジョンについては、まず我々は福岡市ステップアップ助成事業ということで平成20年度に100万円をいただいたり、24年度には福岡市創業者応援ファンドの第1号という形で支援いただいたりと、行政からも色々支援をいただいている。で、我々としては卸で10億、店舗で3億、コンサルで1億ということで、14億円の売上を目指している。また、地元の証券市場等への上場に加え、九州発であるこうした事業モデルを全国の仲間に広げていきたいということも考えている。そのなかで最終的には会社の経営理念である「販路を基点とした農業の産業化」を実現したい(会場拍手)。
佐野:お二人のお話で非常に面白いと感じたのが、ビジネスの原点というか、きっかけの部分だ。高島さんからは「安全な野菜を」というお話があった一方、藤野さんからは「農家が1000万円を稼ぐことの出来るように」というお話もあった。発想の基点はそれぞれ生産者側と消費者側にあった訳だが、結局のところは消費者と生産者を結びつけるということで、やはり両方のニーズを満たさなければいけないと感じる。高島さんから見て、藤野さんのビジネスで何かお感じになったことはあるだろうか。
高島:会社員と同様、農家にも良い農家とそうでない農家がいる。で、僕らは事業農家としてかなり上手くいっている農家さんと取引をしている訳だが、世の中全体で見ると、誤解を恐れずに言えば、弱い農家と言われる人たちが大多数を占めている。藤野さんはその中間に目をつけられた。すごく強い訳でもなく、けれどもやる気はあるという方々に着目された訳で、そこを伸ばしていくというアプローチは大変面白いと思った。
佐野:藤野さんが「中間」の農家に着目された背景には、どのような思いがあったのか。
藤野:「普通に農家をやって、それで普通に農業で食えたらいいな」と思っている。テレビでよく紹介される農家というのは特殊な事例だ。それをモデル化して全国展開するのは難しい。それよりも普通に、限られた面積で収量をあげ、きちんと野菜をつくり、かつコストもきちんと考えながらやっている農家のお手伝いをしたい。ただ、今までは販路の部分で農家がすべてのリスクを背負ったりして、そこが上手くいっていなかった。そこで我々が販路の再構築をしたいと思っている。
「『また合流しよう』と約束した仲間と、互いに知識・経験を積みんだ2年後、オイシックスを立ち上げた」(高島)
佐野:続いて起業のきっかけについても伺っていきたい。。まずは高島さん。
高島:僕が最初に会社をつくったのは22歳のときで、大学院在学中だ。インターネットが世に出てきた1996年頃だが、当時は大変な衝撃を受けて「インターネットが世の中を変えるプロセスのそばにいたい」と思った。で、大学時代はサークルを結構やっており、なにかこう…、「会社がいいかな」という感じで、学生だけで会社を立ちあげた。
で、それはインターネットの会社だったのだが、「会社をやりたい」と思って立ちあげた訳ではなかったので事業計画も何もなかった。また、色々やりたかったので、「一度やった仕事は二度やらない」という変わったルールもあった。初めての仕事はホームページの受託制作だったが、一度請けると2回目はないという(笑)。次は別の仕事をやらなければいけない。そんな、ノウハウもまったく溜まらない仕組みを自分たちに課した訳だが、それでも2年続いた。元々、ある意味ではノリでやっていた訳だが。
佐野:楽しみでやっていたということか。
高島:たまたま大学院へ行けることになったので、「好きなことをやりたいな」という気持ちから、インターネットというものが起こす変化の近くにいたいと思った。変化を起こす側に行きたいと。ただ、起業という選択肢は当時持っておらず、会社に関してはなんとなくつくったという感じだ。しかしやっているうちに「仲間と一緒に起業するというのは、いいかもね」と。また、「自分はそのなかで経営者というポジションをやるのがいいかもしれない」と感じるようになった。
ただ一方で、「このままでは“小成功”だけで終わりそうだな」という気持ちもあった。事業計画がなかったのだから当たり前だが、いきあたりばったりの繰り返しだったためだ。しかしやるからには大成功したい。ではどうしたか。当時、僕らのあいだで「サンクチュアリ」という漫画が流行っていた。主人公である幼馴染二人のうち、一人がやくざの組長になり、一人は衆議院議員になる。そして将来、二人は社会的地位を高めてから再び手を組み、ともに日本を変えていこうと考える。そういう、すごく漫画的な漫画だが、それを読んだ僕らは「これだな」と思った。それで一旦別れ、僕は経営の勉強をするためマッキンゼー・アンド・カンパニーに就職した。システムを勉強するためIBMに就職した人間もいるし、インターネットのことを勉強するため会社に残り事業を続けたメンバーもいる。そして「3年後に合流しようね」という話をしていた。
それで一旦別れたあとも毎週末集まって、どんなビジネスがいいかという議論をしていた。「インターネットで」というのは元々あったが、それで何をするか。当時は根っこの部分で、「世の中の役に立ちたい」という気持ちがすごく強かった。そんなことを言うと良い人のように聞こえるが、そういう訳ではない。「世の中の役に立つ自たちが好き」という感じだ(会場笑)。「俺たちがいる前の社会よりもいたあとの社会がより良くなっていたら、なんか気持ち良くない?」という感じで考えていた。
従って、医療や食品流通等、インターネットを使って本質的なところで世の中の役立つ領域での起業を考えていた。そしてそのなかで食品について考えてみると、偽装問題等さまざまな不安があったという訳だ。また、流通プロセスが極めて長いために生産者さんが搾取されているというか、収益がサスティナブルにならないような仕組みもあった。そこで、「これは改善の余地があるし世の中の役に立てそうだ」と考えた。それで結局は3年でなく2年で合流したのだが、とにかく食品事業をインターネットでやっていこうということでこの会社が生まれた。
佐野:一度別れたメンバーがまた2年後に戻ってくるというのはドラマチックだ。
高島:2年で戻ってきたメンバーもいれば5〜7年かかった人間もいるし(会場笑)、サラリーマンが楽しくなってしまってまだ戻ってきていない人間もいる(会場笑)。
佐野:藤野さんはいかがだろう。中学生の頃から志していたとのことだが。
藤野:中学から志していて、大学卒業後もそれが変わらずに起業したと。ただそれだけ。たとえば高校の頃から休み時間に樋口廣太郎の本を読んだりしていたし、大学時代を含めて実務書やMBA関連の本も色々と読んでいた。23歳で起業した訳だが準備や勉強をしていた期間は長かったと思う。
佐野:中学3年で起業したいと思ったのは何故か。。
藤野:たとえばサッカー選手やNASAの宇宙飛行士にも憧れたが、なにかこう…、崇高な技術者的世界よりもどろどろした世界のほうが面白そうだと感じた。「社長業って、何か色々なことが起こりそうだ」と。孫正義さんやビル・ゲイツさんをはじめとした経営者の自伝も色々読みながら、なんとなく、「自分のやりたい仕事は社長業だな」と、当時から感じていた。
佐野:中学3年でそこまでブレない決意を持っていたというのはすごい。起業したいと考える会場の皆さんにお二人から何かアドバイスはあるだろうか。
高島:まず、僕の場合は仲間をつくるというのがあった。レールを外れるときは結構な勇気がいる。僕は中高一貫で卒業したあと、東大へ行って東大の大学院まで進んでいる。だから、なにかこう…、起業することに関して“レールを外れてしまった感”が当時はすごくあった。これはきっと多かれ少なかれ起業する社会人に必ず付き纏う感覚だ。ただ、そのときの僕にとって大きかったのは、「仲間と約束しちゃったし」という背景だ。レールを外れることがあまり上手ではなかったからこそ、仲間の存在が起業の前も後も極めて重要だった。従って、皆さんは起業の話を聞くために今日お越しになった訳だが、もしかすると僕らでなく隣の人を見たほうが良いのかもしれない。隣の方と一緒に起業することだってあり得るし、ここはそういう場であるとも思う。
それともうひとつ。いきなり起業せず、小さな会社で経営幹部としてのキャリアを経てみるのも有りかなと思う。藤野さんはそんなことないが、僕はこういう場に来ると2割増ぐらいで喋るから良い話ばかりになる(会場笑)。けれども本当のところはそんな訳でもないと。その辺に関しては小さな会社の経営者とともに経営幹部として働くと「経営者ってこんなものなんだな」と、よく分かる。その経営者から盗むことが出来る要素もあれば、反面教師として学ぶこともたくさんあるだろう。それによって“やれる感”が身につくケースも多い。インターンでオイシックスに来る学生には卒業後就職せず、すぐに独立して会社を起こす人も多い。多分、「高島に出来るのなら俺にも出来るだろう」と皆が思うのだろう(笑)。ただ、小さな会社の経営幹部というワンクッションを2〜3年挟んでみるというのもひとつの有効な手段ではないかなとは思う。
佐野:藤野さんからもアドバイスをいただきたい。
藤野:社長になっても非常に大変だと思う。経済全体が右肩上がりだった20〜30年前と、必死に頑張ってやっと人並みに成長出来るかどうかという現在では大きな違いがある。ブラック企業が云々といった議論もあり、今は人の扱いに関しても色々難しい部分がある。まともに考えたら起業しないほうが良いと思う。けれども、まともではないほど年中仕事のことを考えているような人や使命感をきちんと持っている人あれば…、それで「やれる」という自信があればやってもいいのかなと思う。ただ、社長業というものは経験しない限り分からないという考え方も一方ではある。年齢に関係なく、大事なのは社長を何年務めたか。社長になっても3〜4年は初心者マークがついている状態で、5年が過ぎたあたりからそのマークも外れるかなといった感じになると思う。
そこで大事なのは理念だ。起業当初は理念も何もないかもしれないが、そこから1〜2年経ったら…、「このために人生を費やしても構わない」とまでは言わないが、それに近い思いを持つ必要があると思う。僕の場合はそれが農業の産業化だった。僕は坂本竜馬の「世の中に生を受けるは事を成すにあり」という言葉が好きだ。生まれた以上、この世に何か残したいと。それが会社の理念とリンクすることで生きた証が実際に残っていく。それほどの強い思いを持って経営していたら、日々色々なことはあっても「また頑張ろう」という気持ちになる。
僕は一人で起業した訳だが、他の人々は大学卒業後、皆、銀行や役所に就職していた。僕の感覚としては「皆ベンチャーをやりたいのだろうな」思っていたのだが、実際には完全にマイノリティーだった。「何故ベンチャーなんだ?」と。それでも実際に起業した訳だが、1〜2年目にきつかったのは暇だったことだ。仕事がなかったから。その辺も乗り越えつつ、スケジュールも頑張って埋めていった。そこで僕は思うのだが、天命といったような考え方が向いている人は、出会うべき人に出会うと思う。僕にとってはその出会うべき人の一人が宮崎の新福青果という有名な農業生産法人の社長だった。そちらの社長には、「誰と会うときでも俺の名前を使っていい」、「流通がきちんと整備されていないから農業をやろうと思っても食っていけない。だからお前は生産しないでいい。流通のほうをやれ」といったことを言っていただいていた。そこからの縁でさらに人の輪が広がったりしていった。そんな出会いがいくつもある。
後編はこちらから























.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)
.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)
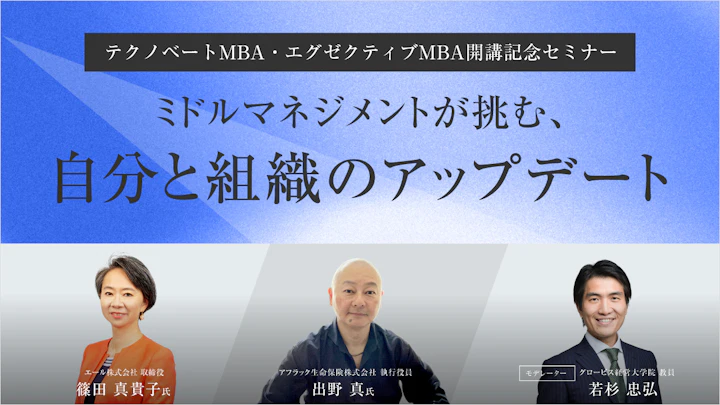
.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)


.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)

















.png?fm=webp&fit=clip&w=720)
.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)

