ITベンチャーを生み出すプラットフォームでは世界で最も恵まれている(夏野)
川上:本セッションでは、IT、エンタテインメントなどの領域で今後、日本がどのように存在感を高めていけるのか。そんな元気の出る話をしたいと考えています。議論を進めるにあたり、各登壇者から、まず自己紹介をいただきます。その際、本セッションのテーマとなっている「テクノロジー」、「ベンチャー」というキーワードに絡めてお話しください。
夏野:昨年、11年間、務めたNTTドコモを離れました。その前は、実はベンチャー企業の立ち上げをしており、その会社が倒産したために仕方なくドコモに入りました(会場笑)。ベンチャーで成功していたら、iモードは生まれなかったかもしれません。どちらが良かったのか、今となってはよく分かりませんが、給料だけを考えればベンチャーの方が良かった、と、私の妻などは考えているかもしれません(笑)。
本日のテーマは、「日本発テクノロジーベンチャー創出の可能性」ということですが、まず私にとっての「ベンチャー」を改めて定義したいと思います。本日、お話しするような、技術や発想を源泉に実業を興していくベンチャーは、いわば本当のベンチャーです。それに対して、ただ金儲け、個人が財産を築く手段としてのベンチャーというのも世の中には存在します。とりわけ、iモードというプラットフォームを作った2000年代前半に、そうしたベンチャーを数多く見てきました。誤解を恐れずに言うなら詐欺まがいの会社も山ほどあったと思います。
ここでいう詐欺は法律上の違反行為ではありませんから、誰かが逮捕をされるというわけではありません。けれど私は、金儲けを一義的な目的とするような、これらベンチャーには大きな違和感を覚えます。背景には、マザーズをはじめとする新興市場の上場基準が、あまりにいい加減だったこと、それを投資家もまた、理解できていなかったという側面があります。残念なのは、その反動によって、今度は本当に優秀なベンチャーまで、上場してもまったく資金を調達できない状況が生まれてしまったことです。
金儲けを目的に次々とベンチャーが生まれたステージは終わりました。私は、ベンチャーというのは本来、ゼロから何か価値を生み出すもののことだと思います。創業期の会社でCEOをやることがベンチャーだ、などと考えるのは、もうやめたほうがいいでしょう。大企業が、従来にない新しい発想の事業を創造するのもベンチャーです。最近では、創業時から、きちんと資金がついているベンチャーも目立ちます。個人でスタートするベンチャーは逆に、ほとんどありませんね。資金調達に向かうのがベンチャーではなく、あくまでお客が対価を払って買ってくれるような技術やサービスをゼロから生み出すことこそが、ベンチャーであると私は考えます。
「日本発」というキーワードにも少し触れたいと思います。日本は、ITベンチャーを生み出すプラットフォームと意味では世界で最も恵まれた部類に入ると思います。その理由の一つは、“目利き”の多さ。市場には目の肥えたコンシューマや企業が山ほど存在します。もう一つは、インフラの充実。低価格のブロードバンド環境が整備されており、モバイル普及率も圧倒的に高い。新しい技術やサービスを普及するうえで障害になる要素は、50歳代以上のオジサンが多いというぐらいではないでしょうか(会場笑)。
ガラパゴス化しがちな日本市場(内海)
内海:「ベンチャーとは?」というテーマを語るのに自分自身がふさわしいかは分かりませんが、エンタテインメントの領域でプロデューサーをしている立場から、残念に感じている側面はあります。日本には力強い個性や表現力を持ったクリエイターが数多くいて、夏野さんが言われるように環境も整っている。ユーザーも熱い思いを持った層が育っています。にもかかわらず、それがビジネスとしてアウトプットされたときに世界の中でガラパゴス(独自の進化を遂げた市場)化しがちであるということを私は残念に思っています。
例えば「マトリックス」という映画があります。あの映画を構成する魅力的な要素のほとんどは、もともとは日本のアニメから受けた影響を起点にしたものだと思います。でも、それを作品に仕上げ、配給やマーケティングのパッケージングで世界的なヒットとしたのはアメリカのエンタテインメント業界なんですね。「マトリックスは日本文化から影響を受けてできたんだよ」などと言い合うのも、それはそれで格好いいのですが、だからといってマトリックスのヒットで日本に何か益があるわけではない。尊敬はされるかもしれませんが。
私は、この状況を少し変えるだけでも業界が大きく成長する可能性があると信じています。ここで何か新しい価値を生み出すお手伝いをして、日本のクリエイターに利益を還元できるようになればいいなと。それがプロデューサーとして私の個人的なミッションだと思っているんですね。ベンチャーとは何かということを考えるというよりは、そんな視点で仕事をしています。
事業概要なども簡単にご紹介させてください。企業名は、Quest for the future entertainmentという当社のミッションから、キューエンタテインメントと名付けました。従業員は現在70人ほどです。
私自身はもともとソニーの本社で経営企画のようなことをやっていました。当時は良い時代で、会社が留学させてくれたんです。それでウォートン(米国ペンシルベニア大学ウォートン・スクール)に行きました。帰国後は、ソニーがアメリカの音楽会社と映画配給会社を買収したタイミングだったことから、エンタテインメント系の企画管理をする部署に配属されました。大賀典雄社長(当時)が「ハードとソフトが(ソニーという)車の両輪になる」と話し出した頃です。
その流れで出てきたプロジェクトの一つが、「コードネーム・プレイステーション」で、私は、会社(ソニー・コンピュータエンタテインメント)設立に関わったのですが、その際、「アメリカにも誰か必要だよね」ということで、同社の米国法人を作りました。そこでも本社機能のようなところに従事しましたが、3人しかいない部門でしたから、当初はソフト会社のサポートを得るために、開発キットを持って各社を廻る毎日でした。それまでコンピュータのことは全く分からなかったのですが、現場で勉強しながら最終的にはプロダクトも作れるようになっていました。
その後、あるきっかけでアメリカのセガに転職しまして、いきなりゲーム開発部門のトップを務めることになりました。そこではリストラをしたり、会社を買ったり・・・。私は、オペレーションの経験は、実はアメリカから始まっているんですね。当時は本当にアメリカ人になりきっちゃっていて、もう日系2世みたいに見えていたらしいです。髪型もポニーテールだし、変な格好でした(笑)。その後、アメリカから、ドリームキャストの立ち上げのために日本に帰って来たのですが、これが失敗。さらにディズニーに勤め、最終的に現在の会社を立ち上げるというキャリアになっています。
キューエンタテインメントにはクリエイティブ面を任せているパートナー、もう猪子さんそっくりの人物ですが、水口哲也というクリエイターがいます。彼もセガで働いていたのですが、当時から、「スペースチャンネル5」「Rez」といった割と尖ったゲームを作っていました。どちらかというと日本よりもアメリカで人気がありますね。
キューエンタテインメントで最初に発売したゲームはPSP向けの「ルミネス」というタイトルです。会社は設立当初は8人しかいなかったのですが、皆で最初は何をしようかと考えた結果、「テトリスみたいな音楽ゲームにしよう」と言って作ったゲーム。プレイをしながら音楽が流れていく、パズルと音楽を併せたゲームですね。これが日本ではぼちぼちだった一方、アメリカで非常に高い評価を受けました。
人気ゲームのランキングを発表するあるウェブサイトでは、すべてのPSP向けタイトルのなかで一番高い評価が付いたほどです。ラッキーだったのは当時PSPが世に発売されたとき、マスコミが大騒ぎしてくれたこと。彼らはハードのことを取り上げるにあたってソフトの記事も一緒に書いていて、そこでNewsweekやUSA Todayが、「PSPのソフトで一番面白いのはルミネス」と書いてくれていたんです。その結果、まったくブランディングの背景がなかったのに100万本近く売れました。経験上、プロダクトのローンチのときぐらいしか我々みたいな企業がブランド価値を高めるチャンスはないと感じていてはいましたが。ここまで皆が騒いでくれたのは計算外でしたね。
その後は、水口がある程度有名だったこともあり、マイクロソフトが新しいハードを立ち上げるタイミングに合わせて割とオーソドックスなゲームも作ったりしていました。ただ、最近のゲーム市場はクオリティが高いものだと制作費が一本あたり10億円ぐらいかかります。一本作るのに一年間以上の制作期間が必要になるんですね。もちろんそれはそれなりに大変ながらも面白いのですが、「これだけでうちはやっていけないな」という思いがありました。それで、私のほうはオンライン・ゲームの運営事業も始めたんです。「エンジェル戦記」というちょっとべたな名前のゲームですが、台湾や韓国にライセンスして日本で運営する事業を手掛けていきました。ビジネスモデルとしては基本プレイが無料で、アイテムによって課金していくパターン。普通にプレイするぶんには無料ですが、経験値をあげたり特別な剣を買ったりするためにお金が必要になるモデルですね。普通、アイテムはユーザー全体の10〜30%しか購入してくれません。でもそこで払ってくれるユーザーは大抵、毎月一万円以上払ってくれるのがこのビジネスの特徴でもあります。現在、ネットでは各社、特にモバイル系ではゲームを前面に出す事業者も多いのですが、当社はそのなかでも比較的課金しやすいビジネスモデルを構築できているのではないかと思っています。
また、モバイルでも「ガーディアンハーツ」というゲームを出しています。これはPCのモデルをモバイルに持ってきた本格的RPG。こちらも基本プレイが無料でアイテム課金です。こちらは始めたばかりですので、どこまでユーザーがつき、ARPU(加入者一人あたりの月間売上高)が上がるのか、まだ結果は出ていません。日本のゲーム環境は夏野さんがおっしゃったように進んでいます。今、海外のモバイル事情では何が旬かというと3Gではなく音楽携帯なんですよね。日本人からすると、何をいまさらという感じでしょう。だから、日本で実績をあげれば海外展開しやすい。コンテンツ会社にとっては本当に面白いエリアですし、当社としてもその点には大いに注意を払っています。
当社ではこのほか、「元気ロケッツ」という音楽プロジェクトも手掛けています。これはボーカルの「ルミ」がフロントアップを務めるコンセプチャルバンド。人類史上、初めて宇宙で生まれた人間で、30年後の17歳という設定で・・・、皆さん、ここ笑うところです(会場笑)。地球のあらゆるメディアやアーカイブにアクセスでき、地球に対する夢や憧れを持っている女の子という設定です。そのルミが歌うとしたらどんな曲になるか。そういう視点でストーリーが進んでいきます。それで最初に発売した曲は「Heavenly Star」という歌でした。あちこちで環境問題や紛争を抱える地球ではあっても、彼女にとっては天国のように美しい奇跡の星だと。そういう歌詞になっています。
この曲、もともとはゲームのBGMに使っていたもの。そのあと、「レコード会社から出すわけでもないし、どうしよう」と考えた結果、YouTubeにアップして展開していきました。これがウケた。最初に面白いと言ってくれたのは日本のDJたちです。もうクラブでかかりまくりですね。はっきり言って、これ知らないとクラブ好きな女の子には遅れていると言われますよ(笑)。で、さらにすごいのはこの後。2007年7月に世界7カ所で同時開催された「Live Earth」という巨大チャリティー・ライブで、他の会場に出演しているマドンナやビースティ・ボーイズに向こうをはって日本では元気ロケッツがフロントアップを務めたんです。ホログラムでの出演でアル・ゴアさんにも一緒に出演して貰いました。おかげさまでアルバムも「iTune Store」でトップになった。ただ、はっきり言って音楽は儲かりません。このまま行くと会社がやばいことになるので(笑)、今後はゲームと絡ませるなど、色々、展開を検討しています。
それから、最近は米国最大のゲーム会社エレクトロニック・アーツ(EA)と、日本の非常に優秀なデベロッパーであるグラスホッパー・マニファクチュアを結びつけ、15億円以上の規模となるプロジェクトを組成するサポート等もしました。昨今、ゲームの予算が映画並みに膨らんでいて、そもそも若いクリエイターが参入しづらいし、仮に製作しても日本の市場だけだと投資を回収できないんです。そこで、世界に流通網を持つEAのような会社と、日本のクリエイターを結びつけるために何か自分たちにできることはないかと尽力させていただいた。さらに、米国最大の映画業界のエージェントであるCAAを使用し、ファイナンス面でも色々とユニークな工夫をしています。15億円というと、ちょっとした日本映画よりも大きいプロジェクトです。
以上のような事業とともに我々が掲げている全社的ビジョンは、まずミュージックインタラクティブの領域で世界のトップスタジオになること。そしてフォーマットを超えたオンライン運営で確固たる地位を築くこと。そして、さらには世界中のクリエイティブ&ビジネス・セクションとコラボレートしていくということです。いちばんの目的はアジア、とりわけ日本のクリエイターを世界にどう進出させていくかということ。ですから、そういった領域ではぜひ皆さんにもご参加いただきたいと思っています。
川上:ありがとうございます。内海さんにはエンタテインメント系のお話をプロデューサー視点からしていただきましたが、今度はクリエイター視点ということで、猪子さんにお話を伺いたいと思います。
“やばい”ものを作れば人も集まるし、売れる(猪子)
猪子:当社はテクノロジー、デザイン、アートをやっている会社ですが、200人ほどいる社員は全員ブルーカラーです。ホワイトカラー禁止の会社です(笑)。
何をしているのかというと、たとえばテクノロジーでは、Google(グーグル)に対抗して「SAGOOL(サグール)」という検索エンジンを作ったりしています(会場笑)。Googleで「ドラえもん」を検索してみると、「ドラえもんチャンネル」や映画版ドラえもんのオフィシャルサイトなどが検索トップに表示されますが、SAGOOLで検索すると、おもろい順に表示するので、いきなり「ドラえもん最終回シリーズ」が検索順位トップで出てきたりします。独自に発明した“オモロ”アルゴリズムでコアな情報を探せるという「おもロジック」のおかげ。ノーベル賞を貰えると思って待っているのですが、いっこうに連絡がきません(笑)。
アートでは、たとえば去年12月にパリのルーブル宮殿で「感性kansei -Japan Design Exhibition」という“日本かっこいいだろう展”みたいなものが(ジェトロや経済産業省によって)開かれたのですが、そこの空間設計をやりました。展覧会自体は、日本のデザイン性に優れたプロダクト100点を持って行って見せるというものだったのですが、それだけでは美意識や思想の異なるフランスの人たちに感心を持ってもらうのは難しいだろう、と。それで高さ3メートルのディスプレイを20個並べまして、奥行き20メーターくらいになる作品に、書が描かれているというような、そういうものを作り、プロダクト自体はディスプレイの裏に並べていきました。
デザインで分かりやすい例というと、2007年に「au design project」に参加しました。これはおしゃれなケータイをデザインするというプロジェクト。で、当時iPhoneが発表されて、これからはインタフェイスがホットになるから、それを革新しよう、と。インタフェイスというのは、よくよく考えてみると、テクノロジーが未発達だから仕方なく存在するというところがあるんですね。電話したいと思った瞬間に電話できればいいけれど、それができないから仕方なくインタフェイスが存在する。ということは、おしゃれなケータイを作るということは、「おしゃれで、しょうがないもの」を作るということになってしまいます。人間で「おしゃれで、しょうがない奴」って最悪じゃないですか(会場笑)。だから、まず「しょうがある奴」「しょうがあるインタフェイス」を作ろうと。って、何を言っているか、よく分からないと思いますが(笑)、とにかく「使う」という行為に別な価値を付けようということを考えました。
たとえば皆さんは、「メールを書く」という目的のためにボタンを押すわけですよね。そのボタンを押すという行為に対して、僕らが勝手にリズムを加えていくんです。そのリズムに合わせて絵が描かれていったりする。本人は目的があってメールを打っているんですが、これに勝手なリズムやDJが付いていって、最後はメールを打っている本人も何か目的は忘れちゃった・・・みたいな(笑)。
それから、今の例は、瞬間々々の行為に別な価値を与えるというものですが、「携帯電話を長く使い続ける」という行為に別の価値を与えるインタフェイスも作りました。インタフェイスが町になっていて、携帯電話を使うことが、町をプレイすることにもなる、というものです。プレイの仕方によって町が変わっていくんですね。電話帳に登録された知り合いが町の住人になっていて、その人に電話をすると画面上でも本当にその人と話をしている感じになる。こういうインタフェイスにすると、たとえば仕事仲間とばかり電話していると町がだんだんオフィスになっていって、友達と遊びの電話ばかりしていると町が南洋リゾートみたいなことになっていく(笑)。で、プレイの仕方によっては町に事件が起きます。って言っても、本人は、ただ携帯を使っているだけなんですけど、あんまり不在着信が続くと怒って、町でテロが起きちゃうんですね。あと恋人からラブリーなメールが来ると嬉しくなっちゃったり、電波状況が悪いと町の住人が禿げちゃったりというように、一応、状況は可視化するんですが、基本的には何か目的がある合理的な存在としてではなく、インタフェイスそのものをコンテンツにしよう、と。僕は行為そのものを消費するのは日本の特異な文化だと思っていて、これを「コンテンツ・インタフェイス」と名付けました。
au design projectの例は目的に対してはあくまで愚直なままで、ということで作ったのですが、今度はこのコンテンツ・インタフェイスだけを切り出してサイトも作りました。これは、アイディーユープラスという都市開発の会社のホームページなんですが、そのままだと誰も見ないですよね。で、誰も見ないんで、やっぱ、落書きできるようにしたほうがいいなと思って(笑)、黄色い線を描くとキャラクターが跳ねるんですね、水色の線を描くと滑るんです。あと、スタンプを押すと、ちゃんと車とかプロペラとかが動き出したり。そんな感じで、テクノロジーとアートとデザインをキーワードに色々のことをしています。
アートとデザインというのは本来、全く異なるものなのですが、今の時代、色々な境界線が曖昧になってきました。そのなかで、僕としては「経営とは何か」といった話はどうでもいいと思っていて、とにかく“やばい”ものを作れば、人も集まるし、売れると思っています。ソリューションっていうのはやばいもの作ることだと考えながら企業に提供していて、今では売上も3倍、利益も赤字だったものが年間10億円程度、出るようになっています。
あとは、なぜベンチャーを興したかというと・・・就職できなかったからかな・・・。いや、電波が来たからです(笑)。
川上:ありがとうございます(笑)。では、ここから少し議論をしていきたいと思うのですが、先ほど内海さんも言われたように、日本には文化があるから、それを世界に発信していくと「日本ってかっこいいよね」と言われるし、すごく受ける。ここでお聞きしたいのは、その文化とテクノロジーやコンテンツというのが、どう関係していくのか、ということです。猪子さんはどう思われますか?
インターネットのテクノロジーでは絶対に勝てない、ただし文化は勝てる(猪子)
猪子:まず単純な答えとしては、テクノロジーだけでは絶対に勝てないと思っています。情報化社会は情報流通コストの差が理論上ほぼゼロだから、テクノロジーの差が絶対にゼロになるんですよね。すぐに共有できるから。チームラボは上海にもオフィスがありますけれど、上海と東京のエンジニアでどちらが優秀かなんて比べたくもありません。現実を知らないまま生きていこうと思っていますから(笑)。特にインターネットのテクノロジーでは絶対に勝てないと思いますね。ただし、文化は勝てる。テクノロジーは客観的だけど文化は客観的ではありませんから。どちらが優位かなんて分かりませんよね。インドと日本、どちらの文化が優位かなんて客観的に比べようがありません。だから単純に先進国が有利なんです。先に豊かになったほうが有利という意味で。そんなわけで、文化的なものをテクノロジーで再構築していくような領域でしか、日本には優位性がないような気がしています。
そういう意味では、任天堂なんて日本文化の塊のような会社だと思います。先ほどお話しした携帯電話のインタフェイスを作るときに、「日本文化の特徴って何だろう」って色々考えてみたんですが、その答えは行為そのものを消費する文化であるということでした。たとえば茶道。本来はおいしいお茶を淹れるための手段だったのに、そのお茶を入れる行為はいつしか「俺の淹れ方のほうが格好いい」とか「俺の淹れ方のほうが宇宙に繋がる」とか「哲学的だ」とか、わけのわからないことを色々言い出した挙げ句、おいしいかどうかという本来の目的を皆、忘れちゃった(笑)。おいしいだけなら、廻さないで飲んだほうが絶対、おいしいんですよ。同様に宮本茂さんが任天堂でマリオ作るとき、もともとはゲームというのは何かそれぞれに目的があったんですけれど、宮本さんは「目的がないものを作りたい。触わっているだけで楽しいものを作りたい」と言ったというんですね。それはある種、日本文化をソフトにしたということではないかと思うんです。
ハードとソフトでコラボすればさらなるJAPAN COOLは生まれる(内海)
内海:猪子さんの次に発言するのは大変で、まずは翻訳を求められている気分になりますが(笑)。私としては、日本はハードを付けてのグローバルな競争分野ではまだチャンスがあると思っています。その一方で、ソフトというか、サービスで打って出ていく場合にはかなり大変になると思いますね。なぜなら海外では皆、英語を使っているから。英語圏の人口は十五億人以上だし、中国語圏だって十億人以上ですよね。やはり生活に近いところで競争優位性を持つのは結構しんどい話だと思います。ただ、コンテンツでは競争優位も何も、そもそもの価値が「違い」なので、コンテンツ会社は比較的グローバルに活躍しやすいのかなと。もちろん、実際に受けるコンテンツには少なからずローカル色が反映されるので、それぞれのセクションに対するローカリゼーション、カルチャリゼーションは大切でしょうね。冒頭のマトリックスの例ではないですが、他のチームと上手にコラボしながら商業化していく努力も欠かせません。そこをどういう風に組んで上手に作っていくか。それが一つのテーマになると思いますね。
ITのソフトでは、やはり日本人が弱いかな。結局、この部屋(講演スペース)を見渡しても全員が日本人じゃないですか。おそらく海外で同じような状況はありませんよね。アメリカ企業でもすべてアメリカ人だけの部屋なんてありません。ヨーロッパの企業でも色々な国民がいるし、中国だって同様です。繰り返しますが、ハードウェアならたとえばアップルがやっているようなことはぎりぎり可能だと思います。なんで、iPhoneのようなものをソニーが作れなかったんだ?と皆さんも思われたでしょう。逆に言えば、そういうことを皆さん方、夏野さんのような方々が積極的にコラボレートして作って世界に出ていって欲しい。私からすればなぜPSPに電話が付いてないんだろうとか思うわけです。そういう領域で、本当はまだまだチャンスがある。そんなハードとソフトでコラボレートしたプラットフォームは増えて欲しいです。そうすれば、少し右寄りな物言いですが、さらなるJAPAN COOLが飛び出してくるようになると思います。
猪子:僕は少しそこに異論があります。プロダクトを作るときは文化の純度が深ければ深いほどいい。もちろん売るときは別です。売るときはグローバルで考えたほうがいいと思うのですが、作るときっていうのは、グローバルのことを考えちゃいけないと思う。トヨタなんて、もう気持ちが悪いぐらい日本的な純度が高いと感じるし、任天堂もそうだと思います。
内海:もちろん作るときはそうなんです。逆に言えば、それがいつもジレンマになる。商売人とクリエイターの間を取り持つのが本当につらくて(笑)。いや、本当にそうなんです。だってカルチャーが深いほうが作品としては深いということになるんです。ただ、黒澤明監督の作品とスターウォーズと、どちらが商業的に成功したかというと、やはりスターウォーズの方が売れている。
結局、最終的には個人のレベル次第でしょう。クリエイターがどんなバックグラウンドを持っていて、本当に作りたいものを作っているか・・・。さきほどの猪子さんの作品を見ていると“イっちゃってる”と皆さんは思うかもしれないけれど、本当にイっちゃってる人の作品はもう商品にできないぐらいすごい。しかし、それでもうまく肉付けをして売り出していくという人が世界にはいるんです。で、それは残念ながら日本人ではない。クリエイターの側の純度は充分に足りていて、ただ、そうした日本人が育ててきた日本文化の深さに対抗できるような日本人がビジネスサイドにも現れて、それをグローバルに商業化していって欲しいと思います。
新しいものを作るためにマーケティングセオリーは通用しない(夏野)
夏野:「日本文化って何?」ということは、きちんと突き詰めたほうがいいでしょうね。作っている人間が、たまたま日本人だから日本風になっているということでもあると思うんです。クリエイターが日本に住んでいるから日本文化になるわけだけれど、そのクリエイター自身は日本ということを意識していない。結局はクリエイター次第ということではないでしょうか。
今の時代の新しいものを作るために、グロービスで学ぶマーケティングセオリーは絶対に通用しない(笑)。グロービスに限らずMBA関連のすべてのセオリーが通用しないんです。なぜならマーケティングした時点で、中間程度のものしかできなくなるから。マーケティングした瞬間にヒット商品は出てこなくなるんですよ。マーケティングの本質は、「現在の皆さんの気持ちはどうですか」と聞くことなんだけれど、プロダクトを出すときには、気持ちも状況も何もかも変わっちゃっているわけですから。そうなると、拠りどころは作り手個人のセンスやフィロソフィーになるんですよね。
これは、チームとしての作業でも同じことが言えると思います。日本人が多いチームであればたしかにプロダクトは日本風になるかもしれないけれど、アメリカ人でも日本おたくの人々が作れば日本よりさらに日本風なものが仕上がることはある。日本風のテイストがもしあるとすれば、それはただ単にサービスやコンテンツをパッケージするときの拠りどころとして使っているというだけなんですよ。北欧デザインなんてまさにそうでしょう。それほど北欧に関係なくても、「日照が貴重な国に住んでいたら、とりあえずコントラストがはっきりした色合いを使わないといけないんだろう」みたいな(笑)感覚を拠りどころにして作っていくわけですから。
何を言いたいかというと、たとえばトヨタのある車種のデザインがまったく尖っていないことについてまで、「とりあえず日本風になっていればいいんじゃないか」という間違った結論に達するのは嫌なんです。もちろんトヨタは素晴らしい会社です。でもレクサスが1000万円を超えたら売れないと、私は思いますね。ポルシェは1700万円でも売れるのに。それはマーケティングをやり過ぎているからだと思うし、個人の思い入れも少ないからでしょう。そもそも日本の伝統的な芸能で人間国宝になるような方々は、それこそ思い入れだけで生きているわけですよね。そんな思い入れの部分に戻ろうよという意味で、日本文化に立ち返るお話ならば僕も賛成です。でも、それがいつもの「チームワークを大事にして、マーケティングをきちんとやって、平均値を高めて」みたいなことになってしまってはいけない。それこそ日本的な大企業病ですから。
川上:たしかに個人のセンスやフィロソフィーによってクリエイティビティを凝縮するのは大切ですね。ただその一方で、誰もかれもがばらばらの個人でいるわけでもなく、チームではないと作り出せないものも多くあります。そこで会社に「チームラボ」という名前を付けた猪子さんにお伺いしたいのですが、チームで向き合うクリエイティビティとはどんなものになるのでしょうか。あるいは、個人ではないチームでもクリエイティブにはなれるものなのですか?
チームでも文化的な純度が高ければユニークなものは出てくる(猪子)
猪子:そもそも僕らの基本思想として、情報化社会においては、極端な話、高度なブルーカラーしか、まともなものは考えられなくなるのではないかと思っているんです。「しか」っていうと、ちょっと言い過ぎかもしれませんが、つまりは、ありとあらゆる分野において、高度な専門分野を持った手を動かしている人、たとえばデザイナーだとかエンジニアだとかが、ものを考える時代だと思っていて、ただ、何もかもが凄いスピード感で動いているので、専門性の深さがただ事ではないものとなっている。そうなってくると、何か一つモノを作る際の領域全部を一人でカバーすることは、ほぼ不可能なわけです。
では、簡単に分業できるかというと、そういうわけでもない。以前であれば、デザイナーはプラスチック(のモックアップ)を作ればよくて、エンジニアはハードを作ればよくて、ソフトウェアエンジニアはソースを書ければいい、という感じだったのが、iPhoneなんかを見れば容易に理解できるように、境界線が物凄く曖昧になってきているんですね。どこからどこまでがデザイナーの仕事で、ソフトウェアエンジニアの仕事なのかということを規定できない。作っている本人たちですら説明できないと思うんですよ。なのに求められる専門性の深さは、どんどん高まっている。だから専門性の違う人たちが一つのチームを作って、共にものを考え、新しい価値を作っていこうと。それでチームラボと名付けたわけです。
ですから、チームラボでは、もはや一人で考えるということがほとんどありません。対話によって、ものを考えていく、という。まぁ、大昔からそうだったかもしれませんが。
僕がチームでもクリエイティブになれると思うのは、ユニークなプロダクトが、特別な個人から出てくるだけではなく、特殊な文化から生まれる部分があると思うからなんです。プリクラなんてまさにそうだし、「ニコニコ動画」もそう。「あれは、俺が作った」って人が、10人くらいいますよね(笑)。チームでも文化的な純度が高ければユニークなものは出てくるような気がします。
川上:個人かチームかっていうのとは関係ないということ?
猪子:文化となった瞬間、もうチーム、集団になっているんです。
夏野:個人、といったとき、それは必ずしも一人である必要はなくて、「俺はこうだ」という個人が集まればすごく楽しくなるんですよね。でも、何かこう・・・、まったく主張がなくて、とりあえず人数を揃えただけのような、どこかの会社の役員会みたいなものもあるでしょう(笑)。訳が分かっていないのにコンセンサスみたいなもの決めてしまうのが、日本人の悪いところなのかなと。
猪子:そうですね。僕も、個人のクリエイティビティを否定するわけではないんです。
クリエイターをマネジメントできない日本の問題(内海)
内海:そういう意味では、僕は個人に寄っているんですよね。日本の問題は、ある意味、天才を上手にマネジメントできないところにあると思うんです。プレステを作ったとされる久夛良木健さんがあれほど輝いた理由は何かというと、あの裏に丸山茂雄さんという元ソニーミュージックエンタテインメントの社長だった方がいらしたから。丸山さんが久夛良木さんをいい気持ちにさせながら、同時に周りからも守るという、編集長的な役割をこなしていたんです。プレステ事業のなかで、あるときアメリカサイドと日本サイドが喧嘩になって、もう社内のポリティカルバトルになってしまったことがある。アメリカサイドで「単なるエンジニアがなんで俺のマーケティングに文句を言うんだ」という話になったんです。そのとき、丸山さんはアメリカサイドに「健さんはマイケルジャクソンなんだ」と言った。彼はクリエイターで、強い思いがある。だからその通りにやっていれば上手くいくのだというんです。夏野さんの場合もそれと同じで、これほど尖った人なら周りにちゃんと良い気持ちにさせてくれる人がいれば、ドコモにいても結構ハッピーにやっていたはずなんですよ。
夏野:いや、あれは給料が安かったの(笑)
内海:それも含めて、きちんと天才に報いることを裏でやるとかいう人が必要だと思っているんです。例外はシステムがなかなか認めないし、男の嫉妬が一番怖いのも確かだから。でも、そこで才能をきちんと認めて良い気持ちにさせながら、かつ締めるとこは締める。そんなクリエイティブ・マネジメントのできるチームは、やっぱり強い。だって、最終的にこれが白であるべきか赤であるべきかなんて誰にも分からないじゃないですか。そこを決める人がいるかいないかの違いなんです。誰が強い思いを持ち、この色や形を決めるのか。そして、その熱さはユーザーに伝わるのか。そこに答えを出すのがプロデューサーや編集長という商売の難しい部分ではないでしょうか。もちろん売るという面で考えたときですが。
アートもエンタテイメントも“暇つぶし”(夏野)
川上:放っておくとお三方同士でどんどん進んでしまいそうです(笑)。何か皆さんの方からご質問はありますでしょうか。
会場:私は現在東京オリンピックの招致委員を務めているのですが、そのことと本日のお話のなかで関連していると感じた点について、ぜひ聞かせてください。オリンピックでは今後、テコンドーが正式種目になります。空手でなくテコンドーが正式種目になったのは、実は韓国がテコンドーの伝統や文化を捨てた側面があるためでした。彼らは伝統的なテコンドーの格式をあえて捨て、世界中の人々が勝てるテコンドーを普及させていく道を選びました。空手はそれをしなかった。その結果、空手がオリンピックの正式種目になる可能性は現在、非常に低いままとなってしまいました。個人的にはそれがとても残念です。私自身はそれが、グローバルに空手を広めていくためのプロデューサーが日本にいなかったせいだとも、ましてやインフラを揃えることができなかったせいだとも思っていません。欠如していたのは、「広めていくために何をするか」を考え抜く国家戦略ではなかったかと思っています。そこで夏野さんにお聞きしたいのですが、iモードを海外へ広めていこうとしたとき、官のサポートや国家的な戦略はあったのでしょうか?
夏野:結論から言うと、ありません。実は、まずiモードを国際的に広げるという話はマスコミが騒いでいたものだったのですが、それはNTTドコモとしては国際的な技術の標準化をめぐる防衛策にしか過ぎなかったんです。実際、その甲斐あってワイアレスインターネットにはほとんどiモードのプロトコルセットが採用されています。あまり知られていませんが、ほとんどiモードのTCP/IPが国際的にも標準化されているというのが真実なんですね。ですから、巷では海外でiモードが失敗したといった話にはなっていますが、実はそれほどコストすらかけてないし、そもそもビジネスモデル自体なかったんです。
会場:内海さんと猪子さんに質問させてください。ゲームやコンテンツを作るにあたって「これはウケるだろう」という感覚はまったく生まれないのでしょうか。プロダクトを作るとき、まずはクリエイターに強い思いが必要であることは理解できます。しかしグローバルに広げていこうとすれば、ユーザー側の視点というか、地域によって異なる感性や文化も大いに考慮する必要があると思うのですが。
猪子:僕は、いつだってウケたくて作っていますよ(笑)。常にターゲットに合わせて作っています。プロダクトを作るときは、基本的には自分がターゲットになりきるということなんです。自分がユーザーとしてこのプロダクトに触れたら「きっと興奮できる」とか「絶対人にも教えるだろうな」と思えるものを作っています。
内海:クリエイターは当然、自分の世界を持っていますが、基本的には皆、ウケたいと思っているんですよ。手を叩いて貰いたいと。すかしている人もいますが、本質的にはウケたいと思っている。ウケれば、それが次にも繋がりますから。
それで「これはウケるだろう」と思って作った結果、その通りになったものもあるし、ならなかったものもあります。ゲームは一部でコンシューマプロダクト的な存在になってきていますから。凄いマスプロダクトもあれば、マニアックなものもある。ゲームと言ったとき、それがインターネットと同じように広い世界を指す言葉になりつつあるんです。だからビジネスモデルがずいぶん変わってきて、ウケかた自体もずいぶん多様化してきているのかなという印象はあります。
会場:エンタテインメントとアートの違いについてどのようにお考えでしょうか。何がエンタテインメントであり、何がアートなのか。あるいはエンタテインメントとはどのあたりからを指すものなのか・・・。室町時代以前に日本文化の主流だった和歌には、もともとインタラクティブな要素がありました。ですからインタラクティブなエンタテインメントの要素を日本人はもともと持っていたと思えるのですが、この点を含めていかがお考えでしょうか。
内海:アートが昔、どうやって成り立っていたかと言えば、気に入った作家にパトロンがつき、強力にサポートをしていました。私たちがやっているのは、エンタテインメントですが、それでも、いくらかアート的な要素が融合されていなければ形にならないという気がしています。何をもってアートとするかが微妙なところではありますが、ただ、少なくともある尺度にもとづいた美しさが入っていて、それを生み出した作り手の思いのようなものが受け手の支持を引き出すという意味から考えれば、エンタテインメントとアートのコンビネーションは必要でしょう。
あと、インタラクティブという点ですが、ゲームはもともとインタラクティブなフォームですよね。私はそれに加えて、そもそもあらゆるエンタテインメントにインタラクティブな要素が含まれていると思っています。舞台一つとっても演者のストーリーだけでなく、観客を含めたインタラクティブな空間が存在していますし。たまたま直近の40〜50年、テレビやラジオから流れる一方的な「ストーリー」ばかりが強調されていたというところではないでしょうか。本質的にはエンタテインメントはインタラクティブなものだと思います。
猪子:僕の定義では、アートというのはアウトプット先のないものです。アート以外はすべてアウトプット先としてのジャンル、産業がありますよね。映画一つをとってもそうです。でも、たとえば社会問題を解決するヒントになるかもしれないもの、新しい表現、新しい美しさ、もっと大きく言えば、未来のヒントになるになるような表現なのだけれど、アウトプット先のないものを僕はアートと呼んでいます。本来のアートというのは、もっと保守的なもので、カテゴリーも色々あるけれど、正直、僕はそこは全く興味がないんですね。アウトプット先があるのであれば、産業に合わせればいいじゃないか、と思う。
ただ、社会にとってアートそのものは、もはやエンタテインメントになっています。エンタテインメントとアートの区切りはほとんど存在しない。なぜかというと簡単で、情報化社会の登場以前は情報流通チャネル自体が少なかったからです。テレビも新聞も数チャネル程度ですよね。インターネットになった瞬間、それが数兆〜数十兆になった。そうなると、社会にとって“勝てるものの定義”自体が変化するんです。たとえば「和田アキ子さんと初音ミク、どちらがコンテンツとして価値が高いと思いますか?」と質問されたら、ネット以前の社会では皆が自動的に和田アキ子さんと答えていた。だって、テレビ最強コンテンツですよね。紅白歌合戦のトリを務めるんですから。100人に訊いたら99人は和田さんと答えていたかもしれません。というか、99人は初音ミクを知らないし(笑)。そうすると、初音ミクの100倍程度の価値が和田さんにあったということになるんですよ。でもネット情報化社会になった瞬間、質問が変わるんです。「あなたの渇望は何ですか?」と。すると、今度は誰も和田アキ子さんとは答えなくなる。YouTubeでわざわざ和田アキ子の出ている動画ばかり検索して見る人なんていませんから。そして初音ミクと答える人が1人いる。そうすると初音ミクが和田さんの“無限倍”の価値を持っていることになる。つまり、価値が変わるんです。だから“イッちゃったもの”を作るんです。少ないコストで勝つためには普通のものを作っていても受けないし、流通しませんから。だからアートが最大のエンタテインメントになるんです。
そして、アートがエンタテインメントになるスパンが短くなっている。例えば何年か前にアートの世界で起きたヒットが、量産品のTシャツのデザインに採用されてウケたりする。ゲームの音楽をメディアアートの世界の人が評価したり、同時になっていることだってあります。
夏野:私としては「これが果たしてエンタテインメントなのか、アートなのか」と分けて考えることにそれほど意味はないと思っています。だって、どちらも“暇つぶし”じゃないですか。貴族が戦争をしなくても済むから始めたという豊かな遊びの話ですから。究極的には人生、皆、暇つぶしでしょう?
少し冒頭の話に戻したいのですが、とにかく日本人は世界にアート的なものを山ほど発信していて、世界的に著名な人も山ほどいます。それなのに、なぜテクノロジー的な領域ではグローバルに勝てないかという話になったとき、私は日本の行きすぎた分業に問題があると思います。たとえば建築家を理科系のように捉えるのは日本だけ。本来はアートなのに、日本人はすぐ構造計算の知識が必要とか、色々と言い出してしまう。分業し過ぎて自分の殻に閉じこもって、自分の領域にしかものを言わないから、全体でコンセンサスを作る段階で、ろくなものが出てこないんです。チームラボとかって分業じゃないんでしょう? お互い言いたいこと言い合っているんでしょう?
猪子:そうそう。
夏野:なのに、単に楽をするために分業してしまっているところも多くあると思います。さっき猪子さんの話を聞いて面白いなと思ったのですが、分業は同時に、能力のないホワイトカラーをたくさん雇うための仕組みでもあるんですね。だからこそ、そこで組織の壁を越えて何かをしようとすると怒られもする。でもそこで怯まず、良いと思ったら何にでも強い思いを持って口を出していくべきです。そういうこと含めて考えると、これはアートか、エンタテインメントか、という議論一つとっても、あまりそんなふうに色々分けて考えないほうがいいんじゃないかと思えてくるんですね。大事なのは「お金を払って良かった」とか「時間使って良かった」と思って貰えるような、そんな主観的な満足度を与えられるものが作れるかどうかに尽きるわけですから。そういう軸だけで考えたほうがいいんじゃないでしょうか。
川上:皆さん、ありがとうございます。特にオチはないんですが、今回のお話は、ぜひ皆さんのなかで自分なりに落とし込んで色々と考えてみていただければと思います。



























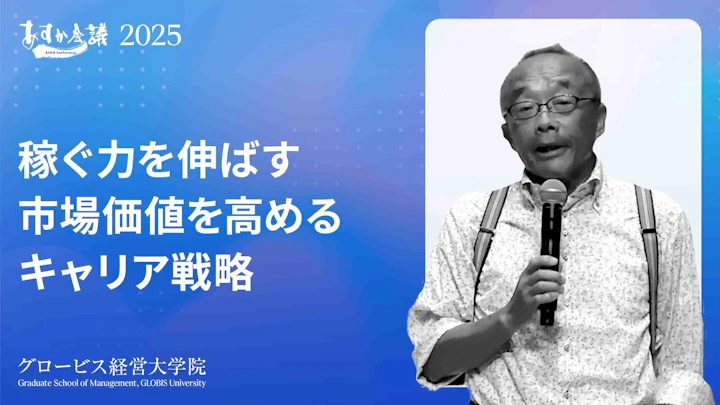

















.png?fm=webp&fit=clip&w=720)
.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)




