問題です
以下のAさんの考え方の問題点は何か。
Aさんはある飲料商品のマーケティングについて考えていた。
「この商品カテゴリーは、もう完全に成熟期から衰退期に入っている。事実、近年の市場規模は、毎年、わずかながら微減しており、全盛時の8割程度にまで低下している。人口は減るし、どんどん高齢化していくという要素もあるから、これ以上、国内市場が伸びることは期待できないな。やはり経済成長が見込める新興国市場でのマーケティング計画を早急に立てることが必要だ」

解答です
今回の落とし穴は、「無意識の限界」です。これは、本来、もっと大きくなる可能性があるかもしれないものに、「これ以上大きくなりようがない」と、無意識に「天井」や「限界」を設定してしまうものです。経営の世界では、「ユニバースを小さく見積もる」という言い方をすることもあります。往々にして、こうした「天井」「限界」を取り払い、ゼロベースで考えてみることで、「ユニバース」を拡大し、売上げなどを伸ばせる場合があります。
今回のケースでは、「人口は減るし、どんどん高齢化していく」というマクロ環境、そして実際に市場規模が減少しているという事実から、もう市場は頭打ちと決めてかかっています。実際の企業の会議でも、こうした議論は多いはずです。しかし、いつもこうした発想をしていては、ビジネスはどんどん手詰まりになってしまいます。その限界が本当に限界なのかを問い直し、真のユニバースを見極めることが求められるのです。
たとえば、昨年の話題として、ハイボールの復活、そしてウイスキーの消費増がありました。ウイスキーは、1983年をピークに市場が減少。国内市場が停滞している商品の典型でした。しかし、ウイスキーの最大メーカーであるサントリーは、「現在の市場が停滞しているのは、ウイスキーの美味しさを伝え切れていないから」と考え、美味しい飲み方さえ提案できれば、ウイスキーの需要はもっと伸びるはずと考えました。その1つがハイボールだったのです。結果として、2009年に市場は10年ぶりに拡大に転じ、2010年はさらなる伸長が予想されています。ちなみにこの発想は、個々の飲食店が様々な工夫をして売上げを維持しようとしているのを見た現場の声を経営陣が活かしたものです。
古くは、昭和30年代のホンダの米国オートバイ市場への参入の事例があります。当時、米国ではオートバイは粗野なイメージが強く、またハーレーが圧倒的に強かったことから、「オートバイに乗るのは限られた人で、市場はもう頭打ち。新規参入、ましてや海外メーカーの付け入る隙はない」と考えていました。
こうした中、ホンダは、性能の良い安価な小型バイクを中心に市場参入を果たし、また、広告を工夫して粗野なイメージを払拭することで、あっという間に米国のバイク市場を数倍(台数ベース)に広げてしまったのです。これも、当時のインサイダーが勝手に想定していた限界を打ち破った例と言えるでしょう。
限界を取り払う方法論にはいくつかの代表的なものがあります。1つは、他のベンチマーク(参考となる比較対象)と比較して、なぜその差異が生まれているのかを考え、その原因をつぶせないか考えるものです。
たとえば、「ビール(発泡酒なども含む)」の消費量は、大びん換算で日本人が1人当たり年間70本台であるのに対して、トップのチェコはおよそ250本と、3〜4倍の差がついています。言いかえれば、理論上は、日本人がチェコ人並みにビールを飲むようになれば、国内市場規模は3〜4倍になりえるということであり、まだまだユニバースは広がるということです。
現実にこの差を埋めるのは容易なことではないでしょう。しかし、食生活や文化の違い、あるいは人種的なアルコール許容量の差異などの要素を、つぶせそうなものからつぶしていくことで、現実に消費量を増やせる可能性はあるのです。その可能性を最初から捨ててしまうのはもったいないと言わざるをえません。
たとえば、もし日本人が体質的にアルコールに弱いという要素が大きいのであれば、アルコール(正確にはその分解途中で生じるアセトアルデヒド)の分解を早めるような安価で安全なサプリメントの探索がその解となるかもしれません。
もう1つ、限界を取り払う代表的な方法論として、別のモノと対比させて、「これがこれだけの規模あるなら、こちらもそれだけの規模があってもいいはずだ」と考える方法があります。
たとえば、トイレ用擬音装置は、(トイレ以外の用途はいったん無視するとしても)トイレの便器数と同じ数だけ売れてもいいはずです。そうならないのはなぜかと考えると、たとえば、「男性用には普及しない」「家庭では普通つけない」など、さまざまなギャップが見つかるはずです。そうしたギャップをつぶしていくことで、ユニバースは大きくなりえるのです。
多くの場合、人間は似たような発想をしますから、限界や天井、ユニバースについても、同じ発想をしがちです。だからこそ、競争相手が囚われている限界にいち早く気づき、そこをブレークして新しいユニバースを切り拓き、先行優位を築くことが、激しい競争時代を生きるビジネスリーダーに求められるのです。


















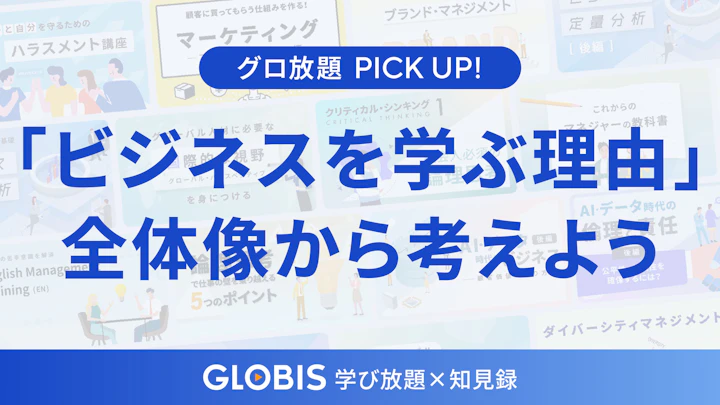











.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)

.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)


.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)


