
「たはむれに母を背負ひて そのあまり軽きに泣きて 三歩あゆまず」
(石川啄木)
ある母と息子の話を聞いた。シングルマザーだったその母親の「背中」が、息子にどのような影響を与えたのか、知りたかった。
この息子(K君)は山梨県で生まれた。生まれて間もなく両親は離婚し、母親はK君を連れて埼玉県に転居した。
その後に再婚。K君が小学校1年の時に、川崎市に転居してきた。
K君は明るく、学校でも人気者だった。母はいわゆる「教育ママ」だったのかもしれない。K君に公文と、プールと、習字を習わせていた。
中学校。バレー部に入り、全国大会に進んだ。
しかし表面上の明るい青春とは異なり、家庭内は複雑さを増していた。
家族で食卓を囲んだのは、小学校4年までだったと言う。母は外に働きに出て、23時頃まで帰ってこなくなった。
働きに出る母の姿を見送るK君の心は、寂しかった。それまで愛情たっぷりに感じられた母親の背中が、自分の届かないところに行ってしまう気がした。
サラリーマンだった父の帰りは、さらに遅かった。毎晩1時か、2時の帰宅だったのかもしれない。
消費者ローンの多重債務が家族を苦しめた。夫婦はたびたび父の実家に行って資金援助を乞い、祖母が父に罵声を浴びせる。それをK君は目の当たりにしていた。
両親の不和が、K君をさらに苦しめた。父は酒を飲んで暴れ、母に暴力をふるった。母は毎週のように、110番通報していたという。
K君は、眠れなかった。寝る前にCDを聞き、心を安らげる音楽を聞かなければ眠れなかった。
中学3年で、両親は離婚した。K君と弟は母親に引き取られた。
母は生命保険の営業の仕事をしていた。懸命に働いた。教育の力を信じていた。K君を進学塾に通わせた。
K君は良い成績を取り、高校受験に成功し、大学に進学した。
母は、恩着せがましいことを一切K君に言わなかった。生命保険の営業の仕事がつらいとこぼしたこともなかった。ただただ、猛烈に働いていた。その目的は自分だということにK君が気づくのは、ずっと後のことだった。
K君は大学で電気電子工学科に進んだ。が、勉強に熱心ではなかった。大学に行くのは週1回。K君が熱中したのは、アルバイト(20種類)、部活動(体操部で全国大会出場)、そして音楽活動だった。インディーズの事務所にスカウトされた。
大学3年の時に留年。就職活動は連戦連敗。
K君は就職活動をやめた。「1年だけ音楽に挑戦させてほしい」と母に頼みこんだ。独立したミュージシャンとして活動した。
経済的に自立できないK君を、母は責めなかった。
「人とわが身を比べるな」
「自分にしかできないことが、きっとあるはず」
何度も母が語ってくれた言葉を、K君は今でも忘れられない。
しかしK君の生活を支えることは容易ではなかったのだろう。生命保険の営業をしながら、自分自身の生命保険は全て解約していたという。
結局ミュージシャンとしては芽が出なかった。K君はベンチャー企業に就職した。
仕事は厳しかった。
「疲れた」
実家でこぼしたK君に、母は「疲れた」と言ってはいけないと言った。
「お母さんを見てごらん。私がこれまで、『疲れた』と家で言ったことがあったか」
母は愚痴をこぼさない人だった。夫の暴力を受けても、息子が留年しても、母の背中に疲れや悲しみや自己憐憫の色が見えたことは一切なかった。
K君が29歳の時、病院から電話が来た。母の病気のことを、伝えたいと言われた。
母はガンだった。全身に転移し、余命は1週間かもしれない。1カ月かもしれない。はたまた、1年かもしれず、先行きは全く分からない状態と言われた。
告知するかどうかは、君に任せる。医師はそう言った。
気丈な母。誇り高い母。告知せずに入院、治療させることはできない。K君は弟と相談し、母にガンを告知した。
母は「迷惑かけてごめんね」と言って涙を流した。自分の弱いところを初めて見せた母の姿に、K君と弟は衝撃を受けた。
医療費の支払いは厳しかった。K君と弟は、昼間は企業で勤務し、夜はアルバイトで医療費を稼いだ。K君は居酒屋で、弟はコンビニで深夜まで働いた。
自分が留年せず、母親に苦労をかけなければ、母はあれほど働いて、ガンになる必要もなかったかもしれない。そんな思いが、K君を苦しめた。疲労困憊にも関わらず、眠れない夜が続いた。
告知から2年が経った。
母は時々、病院帰りに蕎麦屋に行くことを楽しみにしていた。K君にとっても、母親を行きつけの田園調布の蕎麦屋に連れていくことは、ささやかな親孝行だった。それが、腸閉そくのため、食事を取ることが難しくなった。食べても全て、吐きもどしてしまう。
母は衰弱した。体重は30kgにまで落ちた。
しかし母が本当の強さを見せたのは、それからだった。
抗がん剤の治療は、ずっと続くわけではない。退院し、自宅で療養する時期もあった。そのたびに母は、栄養剤を肩から胃に注入する装置をリュックに入れ、リュックを背負って外出した。
外出先は、生命保険の営業だった。ガリガリに痩せても、営業活動を止めなかった。
リュックを背負った母の背中を、K君は痛切な思いで見送った。
この時期だっただろうか。息子達を決してほめることのなかった母が、こう呟いたことをK君は今も宝物のように胸の奥にしまっている。
「立派に育って良かった。なんでも好きなことができるでしょう。」
昼も夜もなく働く息子の姿を見てのことだろうか。K君にとって、涙が出るほど嬉しい言葉だった。

告知から4年が経過した。
最後の入院。母は「もうここから出られないのかもしれない」と、悟ったように言った。
食事は1年以上、全く取っていなかった。
しかしある日、夜20時頃、急に母からK君にメールが届いた。
「おなかがすいた」
「なにか食べたい」
K君は自宅の冷蔵庫を開けた。マンゴーがあった。
急いで切り分け病院に持っていった。
母は、タッパーに入ったマンゴーを、約1分で一気に食べた。
心から満足そうに、言った。
「ああ、おいしかった」
K君は、久しぶりの母の笑顔に安堵した。
しかし、結局全部吐きもどし、これが母が食べた最後の食事となった。
その数週間後、母からメールが来た。
「せなかさすって」
K君は病院に急いで行ったが、母の意識は混濁し、その身体は小さく縮こまっていた。
K君は、苦しそうな母の背中をさすった。母の背中は小さく、固くなっていた。背骨がゴツゴツと手に当たった。何度も何度も、背中をさすり続けた。
2009年9月8日、永眠。

その4年後。2013年3月31日。
K君…小尾勝吉の姿は、グロービス仙台校にあった。
震災後に夫婦で宮城県塩竈市に移住した小尾。24名のクラスメイトの前に立った。
自分のビジネスプランのプレゼンを始めた。
「母が亡くなった時、食べられなくなって、衰弱して、そして命を失った。」
クラスメイトたちは息を飲んだ。
小尾の目が強い光を放った。
そして強く言い切った。
「ご病気などで食に困っている方々が健やかに過ごせるよう、力になりたい。」
高齢者向けの弁当宅配事業「愛さんさん宅食」。サービスを開始したのは、その翌日、2013年4月1日のことだった。
オフィスの壁には、1枚の紙が貼ってあった。そこには経営理念として、「家族愛」という言葉が大きく書かれていた。

塩竈の海を見る小尾勝吉氏
【追記】 「愛さんさん宅食」は、KIBOW社会投資ファンドから1000万円の出資を受けて事業展開を加速しようとしている。
▶次の記事
ある牛飼いの覚悟
◀前の記事
ヨシエの居場所 ~リーダーシップの理由は何か


%20(3).png?fm=webp)


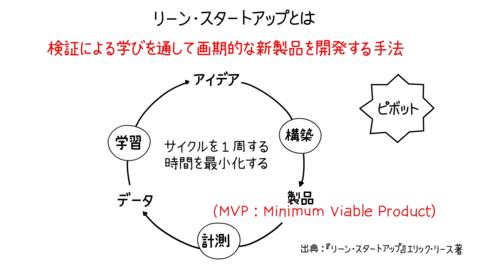


































.png?fm=webp&fit=clip&w=720)
.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)

