2025年は、AGIに向けた“ゴールドラッシュ”の号砲とともに幕を開けました。米国発のBigTechに寛容なトランプ政権の誕生と呼応して、OpenAIやNVIDIAから近未来を予感させる高度なAIサービスの発表が相次いでいます。彗星のごとく表れた中国発、大規模言語モデルDeepSheekからも目が離せません。
かつて産業革命が社会や経済の枠組みを大きく変えたように、このAIの急速な進展は、どのような機会と課題をもたらすのでしょうか。ここでは、まず前編で、営利企業へと舵を切ったOpenAIの動向を、後編では、AGIゴールドラッシュ時代を生き抜く日本企業の処方箋を探ります。
そもそもOpenAIはなぜ非営利だったのか?
OpenAIはみなさんがよくご存じの生成AI「ChatGPT」を開発した組織です。
同社は、“汎用人工知能(AGI)の開発を通じて、人類全体の利益を追求する ”という崇高な理念を掲げ、イーロン・マスクやピーター・ティール、サム・アルトマンなど、名だたる実業家や研究者たちによって2015年に設立されました。
AGIとは その魅力と脅威
AGIとは一般に、人間の知能を超越した認知能力を持ち、幅広い課題に対して学習・解決できる人工知能(AI)のことです。その可能性は、秘める魅力もさることながら人類の脅威となることへの懸念も相当なものです。そのため、当初のOpenAIは非営利団体として運営され、得られた研究成果は公知のものとされました。このアプローチは、技術の透明性を担保することでAGI開発の暴走を防ぎ、不毛な論争で疲弊することなく、AGI開発を加速させることを狙ったものだったと考えられます。
理念遂行と資金調達のバランスを模索
しかしながら、AGIのベースとなる大規模言語モデルを拡張するには、非常に高いコンピューティング能力と優秀な人材の確保が欠かせません。そのため同社は、早くも2019年に「OpenAI LP」という営利組織を非営利組織(OpenAI Nonprofit )の直下に設立し、創業のミッションと迅速な資金調達の一挙両得を狙う体制へと移行していました。営利組織:OpenAI LPは投資家や従業員が得る利益に上限を設ける「キャップド・プロフィット」を採用していて、一定のリターンを保証しつつも、利益の多くを非営利組織へ還流させ、研究開発や社会貢献に再投資する構造でした。このことはMicrosoftから10億ドルの 巨額投資を引き出すことに成功し、その後のOpenAIの技術開発と商業展開を大きく後押しすることとなりました。
生成AIの人気爆発で再び露呈した綻び
そして、創業7年目となる2022年に満を持してリリースされたのがChatGPTでした。ChatGPTに代表される生成AIは「対話型AI」とも呼ばれ、人間と自然な形で会話をする能力を持つのが特徴です。
瞬く間に世界へ浸透した生成AIは、人に代わってAIが対話相手となるカスタマーサポートや、語学学習のヴァーチャル教師など、さまざまなビジネス領域でその価値を発揮するようになりました。加えて、同社が開発した画像生成AIのDALL-Eや動画生成AIのSoraもまた、文章からリアルな画像や動画、アート作品までを瞬時に生成することから、クリエイターやデザイナーが新しい表現の可能性を探るなど、デザインやマーケティング領域においても人の創造的なプロセスに欠かせない存在となっています。
いったん生成AIの利便性に触れてしまった人類がその魅力から離れるのは容易ではありません。しかし、爆発的に増加する需要に応えるためのインフラコストは甚大です。大規模なサーバーやそれを設置するデータセンター、そしてそれらを動かす大量の電力などが必要というのが通説でした。AGIの実現を見据え、更なる技術進化を目指すとなれば言うまでもありません。現在の組織構造となってから3年、再び相当の資金が必要となった同社にとって、非営利の枠組みで営利組織を運営する体制では事業の継続が困難であることは明白でした。
営利化へ舵切るOpneAIに問題はないのか?
営利化の要請が高まるにつれて内部は混乱しました。2023年11月には経営方針を巡る対立でサム・アルトマン最高経営責任者(CEO)が理事会から解任され、数か月後に再び復帰する迷走ぶりを同社が見せたことは記憶に新しいところです。
設立から10年が迫った近年、大規模言語モデルあるいはAGIを目指す市場は、今や多くの競合がしのぎを削るレッドオーシャンとなりました。GoogleやMeta、さらにはオープンソースコミュニティも独自の生成AIモデルを開発しており、OpenAIのビジネスモデルはそれらとの価格競争や差別化戦略からの圧力を強く受けるようになりました。
そこで24年末に発表されたのが営利主体とする新体制への移行でした。 事業特性に応じて営利/非営利のベストな選択ができる状態を残しながらも、既存の営利組織を競合他社も採用する「Public Benefit Corporation(PBC)」へ転換することで経営の独立性を高め、競合と同条件での資金調達を可能にする狙いです。
では、この営利化によって問題はないのでしょうか?
収益モデルの確立はいまだ途上
営利化への試金石として、月額200ドルのChatGPT Proのプレミアムサービスを開始した同社ですが、既存の有償モデルの実に10倍の価格設定ながら「Proの有償モデルは赤字垂れ流しだ」とサムアルトマン本人がXに投稿して話題となりました。というのも、Proの契約者の多くは最上位モデル「o1」のヘビーユーザーか、リアルタイム処理に膨大な計算リソースを割く動画生成AI「Sora」目的である可能性が高く、ユーザー数が増えるほど運用コストが急増するからです。
電力需要の急増と地球環境への責任
先ほども触れたように、AGI開発を巡る競争には、電力消費という大きな代償が伴います。国際エネルギー機関(IEA)によると、Google検索の1クエリーが平均0.3Whのところ、22年版のGPT3の時点で平均2.9Whと実に10倍の消費電力がありました。高度な推論を行う現行のo1モデルやリリース直後のo3-miniはその数十倍~数百倍が示唆され、さらにその先のAGIに向けての電力消費は計り知れません。
OpenAIもこの問題を認識しており、TSMCやMicrosoftとの連携を通じて専用のAIチップの開発やデータセンターの構築に乗り出しており、効率的な電力利用を模索しています。 しかし、現時点では、AI技術の拡大が地球環境に与える影響について、十分な解決策は見つかっていません。
直近では、AGI開発に不可欠なクリーンエネルギーへの予算増強などを盛り込んだ米政府への提言書「OpenAI’s Economic Blueprint」を発表して話題となりました。
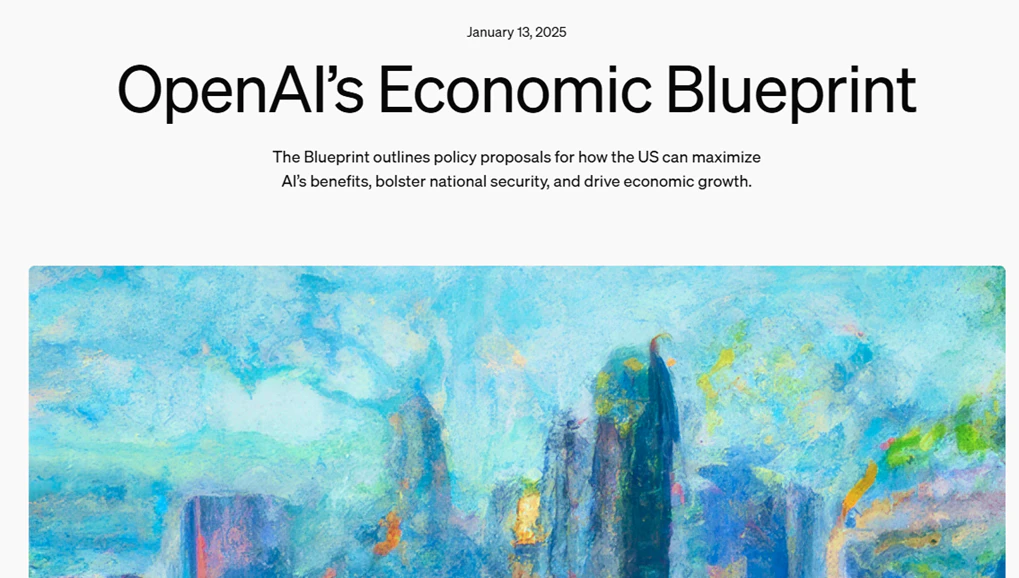
透明性や公平性が後退する可能性
さらに、透明性や公平性についてはどうでしょう。営利化が進む中で、OpenAIはモデルの仕様を非公開にしてきました。OpenAIは「すべての人類に利益をもたらす」という使命を掲げているものの、巨額の資金を投資する一部の資本家の利益が優先されることとなれば、生成AIに頼らざるを得なくなった多くの人々に対する優越的な地位の濫用に陥りかねず、社会的・経済的な格差が拡大する懸念があります。
また、技術がより高度になるほどに詐欺や偽情報の拡散の防止は困難になってきます。トランプ政権の誕生で、国際的な協調体制が築きにくくなる中、業界全体で技術の悪用を防ぐためのルール作りにも暗雲が立ち込めています。
問われる収益性と使命の両立に向けた挑戦
OpenAIは、収益性を高めつつも「社会的使命を遂行する」という困難な課題に取り組んでいます。急速な技術進化と市場競争の中で、どれだけ理念を守りながら収益を上げられるかが問われています。
というのも、今でも世界にはオープンソースで透明性高くAI開発を進める企業もたくさん存在するからです。このような課題を乗り越えられるかどうかが、人々の信頼に関わり、OpenAIがAGIゴールドラッシュ時代をリードし続ける鍵となる でしょう。
後編では、AGIゴールドラッシュに沸く世界と日本企業の処方箋について考えます。
<参考>


















.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)














.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)


