G1ベンチャー2025 第2部 分科会【AI】
「AI×科学領域へのスタートアップ×アカデミアのチャレンジ〜発明を加速するAI〜」岡野原大輔×奥野義人×川上英良×上野山勝也
(2025年6月8日開催/グロービス経営大学院 東京校)
AIが科学研究の加速装置となる時代が到来しつつある。創薬や物質探索、基礎科学等における未知の発見に、AIはどこまで貢献できるのか。研究現場とビジネスの最前線で挑戦を続けるアカデミア・スタートアップのリーダーたちが、AIによる科学革新の最前線を俯瞰し、日本から世界を変えるディープテックの未来を展望する。(肩書は登壇当時のもの)
※タイムスタンプは生成AIで作成しているため、一部誤りがある可能性があります。あらかじめご了承ください。
00:01 AI×科学セッション開始
AIが科学にもたらすインパクトについての議論の背景を説明。
01:32 AIによる科学研究の現状
研究者が論文調査や仮説生成など、研究の全分野でAIを活用。
02:15 材料開発を加速するAIシミュレーター
スパコンが必要だったシミュレーションをAIで高速化する事例。
05:42 実験を自動化するラボオートメーション
センサーとAIを活用し、実験データを取得・学習させる取り組み。
10:18 生物学・医学領域におけるAI活用の現在地
言語と繋がることで応用範囲が拡大する一方、データ取得が課題。
12:30 AIと研究者の協業「リサーチャー・イン・ザ・ループ」
AIと人間が協働する形態の模索と、生物学における実験標準化。
14:41 科学の近未来予測:今後5-10年で起こること
AIエージェントが発見を主導し、集合知を形成する未来像を議論。
16:46 論理で完結する分野でのAIの爆発的進化
数学やプログラミングなど、バーチャルで完結する領域の急進展。
21:42 現実世界との接続(グラウンディング)の重要性
シミュレーションで解けない問題は実験データが競争力を持つ。
24:07 アカデミアが目指す今後の方向性
基盤モデルの構築と、運に頼らない体系的な発見プロセスの確立。
26:43 AI時代に人間に残される「問いを立てる力」
AIにはできない、既存の定説を疑う異なる見方や問いの重要性。
29:40 科学の本質とエラーやノイズの価値
セレンディピティなど、偶発的な発見を仕組み化するAIの可能性。
32:08 Q&A:AIとロボティクス、知的財産
AIによる発明や、特許戦略の変化についての質疑応答。
41:32 Q&A:理論物理学、日本の勝ち筋、資本主義
AIによる物理学の進展や日本の産業、新しい社会システムを議論。
48:15 パネリストが描く未来とアクション
各登壇者が今後個人として、また組織として目指す方向性を表明。


%E5%B2%A1%E9%87%8E%E5%8E%9F%E6%A7%98.png?fm=webp)
.png?fm=webp)
.png?fm=webp)
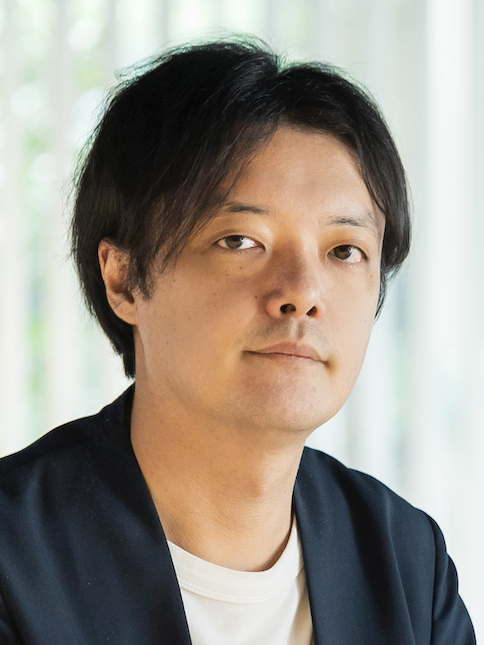




















.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)


.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)

.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)













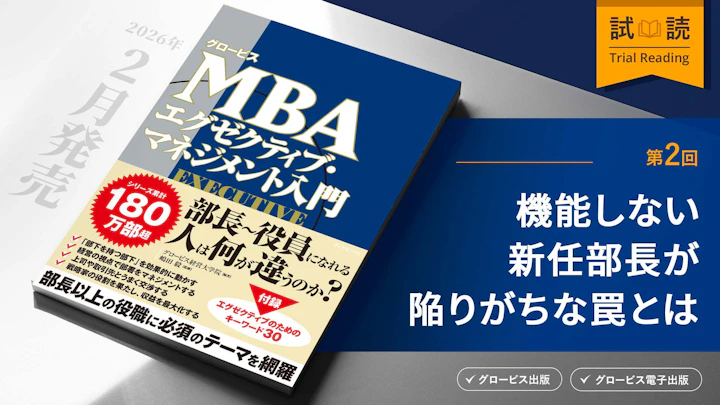




.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)
