本記事は、G1サミット2019「ネットメディアの行方」の内容を書き起こしたものです(全2回 後編)。

津田大介氏(以下、敬称略):私はメディアの機能を3つに分けるといいと思っています。まずはファクトファインディング。調査報道的なものが1つあります。で、2つ目は社会の需要に対して意見を言うオピニオン的な機能ですね。そして、おそらく3つ目としてジャーナリズムやメディアに必要なのがフォーラム機能です。議論の場をつくり、賛否両論があるような議論を整理する。その3つのなかで、今はそれぞれマスメディアとネットメディアの強みが分かれている状況だと思います。
そのうえで、まずファクトファインディングや調査報道については新聞やテレビといった従来のマスメディアが圧勝ですよ。人海戦術が必要ですし、記者がプロとしてトレーニングを受けていないとできないから。でも、オピニオンはネットの圧勝。拡散力もあるし、個人が強くなっていきますから。では、フォーラム機能はどうか。本来、インターネットが抱いていた理想はフォーラム機能です。いろいろな人が参加して、いろいろな意見を持って多事争論ができる筈だった。
でも、結局インターネットには質的コントロールが存在しない。司会者やモデレーターがいないから議論になりません。しかもTwitterなんか140字だから揚げ足だって永遠に取ることができるメディアになってしまい、匿名の参加者も増えました。それでネットの議論はほとんど破綻している状況です。ですから、マスメディアは強みがあるファクトファインディングとフォーラム機能で売っていくしかないというところがあります。

ここ10年ぐらいのなかで私がすごく面白いなと思ったのは、ウィキリークスをつくったジュリアン・アサンジが言っていたことです。彼は、双方向性ですとか、ネットの面白い部分をジャーナリズムに持ち込んだ人です。でも、のちに彼自身は、「匿名告発サイトをつくれば、いろいろなリーク情報が集まって、ネット、あるいは市井の人たちが情報の検証をしてくれると思った。でも、誰もやってくれなかった。結局、素人はできないんだ」と言っています。会計書類も読めないのですし。それでウィキリークスは今、メディアに対して先に情報を提供して検証してもらうようにしているわけです。
では、ソーシャルメディアをアサンジ氏はどう見ていたかというと、不確かな情報についてはプロが見るしかないけれども、「ソーシャルメディアにもいいところがある。ニュースに対して多様な視点を提供する点だ」と。オピニオンを多くの専門家に出してもらうことで、多様な視点が得られるということです。
あと、埋もれているニュースを拡散することもできる。これは「#MeToo」のような文脈もあると思います。かつてはなかなか拡散しなかったことに火をつける機能がある、と。で、さらにもう1つ。プロの取材者にとっては取材の情報源にもなります。そんな風に役割分担していくことが大事なんだと、アサンジ氏はすごくまともなことを言っていました。マスメディアもそうした特性を分かったうえで役割分担をしなければいけない。
ただ、そこで問題は、報道における3つの社会的価値を広告業界がどう捉えるかという点です。この3つに対して、「どれもなくてはならないよね」ということで、広告業界がお金を流さないといけない。2番には流れるようになりましたが、1番と3番にも流さないと、いろいろな言論空間が壊れていく。ですから、私はやはり広告業界が意識を変えない限り現状は変わらないと思います。
夏野剛氏(以下、敬称略):広告業界が新聞等のメディアを支えているというのは、結果として出来上がった世界じゃないですか。ただ、広告業界は広告効果で測るわけで、効果が出るならいくらでもお金は流すし、出ないなら止める。つまり、メディアを支えているという実感はゼロ。まったく思ってないんですよね。

関口和一氏(以下、敬称略): テレビはもともと広告モデルからスタートして、新聞は広告とサブスクリプションで半々だったわけです。でも、今は広告が少し弱っている。ですから我々は、もちろんネットもやりますが、購読料もきちんといただき、下部構造をしっかりさせるということをやっているわけです。
蜷川聡子氏(以下、敬称略): たとえば自動的に入ってくる運用型広告と言われるような広告は、メディアを支える意思があるものでもなく、個人の、ときには詐欺的なものも入ってきます。ですから、そこは「支えてもらいたい」という声がまったく届かず、変なものが入ってくるという。
夏野:パトロン的役割を広告に求めるのは無理という感じが私はしています。意思決定の主体が広告効果ですし、今はどんどん効果測定ができるようになってきているので。パトロン的にやるなら皆でクラウドファンディングをしないとダメなように感じます。
資本の論理が入り過ぎて、ジャーナリズムが壊れている
津田:広告業界が資本の論理に左右されるのは仕方がないんですが、それをすごく巨大にして推し進めたのはGoogleとFacebookですよね。では、その巨大なプラットフォーマーがどうやって儲けているのか。彼らは世界最大の広告代理店ですよ。アメリカのネット広告も、その2社だけで7~8割シェアを占められている。あそこがジャーナリズム等を考えなかった結果、フェイクニュースの問題とかトランプ大統領の誕生とか、いろいろなものにつながっていった。それで批判が大きくなったので今は対処をはじめていますが、焼け石に水ですよね。1番の問題は、広告業界による資本の論理が入り過ぎてしまったがゆえに、ジャーナリズムが壊れている点だと思います。
瀬尾傑氏(以下、敬称略):広告の仕組みとして、フェイクニュースができる構造というものがありますよね。たとえば、アメリカ大統領選でロシアが介入したというように、意図的にやっている人たちもいますが、一方ではビジネスとしてやっている人たちもいます。嘘のニュースを拡散しても広告は自動的に入って、それがビジネスになるので。そうすると、広告が、ある意味では社会を破壊することに加担しているわけです。
それともう1つ、効果測定に関しては、一見すればデータ的にすごく高い効果が出ているように見える一方、実はフェイクニュースについて回ることで、自分たちのブランドが毀損している面もあります。そうしたマイナスの広告効果みたいなものが今は測定されていませんが、こちらの問題も可視化できるようになるべきだと思います。
夏野:今は「出し手責任」みたいものが結構問われていますよね。テレビの世界では「この番組のスポンサーをしているこの企業はなんなんだ」といった話になることがありますよね。新聞等の紙メディアでも同様の話はあります。ただ、それはアドネットワークの世界にはまったくありません。だから、どこでネガティブな宣伝になって、どこでプラスの宣伝になっているのか、もうぜんぜん分からない。
社会問題を告発することで企業ブランド向上につなげる広告

瀬尾:そうですね。まったく違う例で言うと、以前、ニューヨーク・タイムズのチャレンジで話題になったことがあります。彼らは、女性刑務所のなかで起きている虐待問題みたいなものを、デジタルの広告記事としてつくった。で、その記事には広告がついていました。ネットフリックスによる女性刑務所のドラマの宣伝になっていたんです。アメリカにはそういうモデルがある。社会問題を告発することで企業ブランドの向上につなげているんですよね。日本のブランド企業でそういうことにチャレンジしているところは少ない。私もそうした広告にチャレンジしようと思ったことはありますし、そういう話をすると、現場では結構関心が持たれますが…。
夏野:それは本当のニュースやドキュメンタリーなんですか?
瀬尾:そう。広告であることもきちんと示して。
津田:それに貢献した企業もブランドがアップする、すごく質の高いネイティブアドということですよね。
瀬尾:そうです。だから、私もそういう社会問題告発広告みたいなものつくりたいと思ったんですが、日本企業に聞くと「うちは無理です。読者からクレームが来る」と言うわけですね。だから、「どれくらいクレームが来たらダメなんですか?」と聞いたら、「うちの場合、だいたい5件問い合わせが来たらダメです」と。
夏野:しきい値が低いですね。1人で5回電話できますから(会場笑)。ちなみに、フェイクニュースというのはネットメディアのあり方について根本に触れる部分だと思うので、その話もしてみたいと思います。
津田:そういうサイトがなぜできるのかと言えば、アドネットワークで容易にお金儲けができるから。これは、かつてのブログブームと密接に結びついています。ブログがたくさん生まれて、一時期アフィリエイトブログみたいなものが流行りました。いろいろな情報を、コピペも使って量産するわけです。そういうブログの運営者に話を聞いてみると、1人で50も100も200もサイトを運営しているわけです。
なぜ彼らの影響力が高くなるのかというと、いろいろなジャンルをやるから。芸能から政治まで。それで、いろいろやった結果、ネットでアクセスを集めやすく、しかもコピペで記事がつくりやすいものに最適化していくと、保守的な情報だとか、弱者叩きだとか、あるいは一番アクセスを集めるものとして、中国韓国叩きのようなものになる。右派系ブログも左派系ブログも両方運営しているけれども、アクセスは10倍ぐらい差があるらしい。それなら、そちらに特化しようということで、そういうのが増えてきた、と。ただ、ようやくそういう構造をマスメディアも追いかけはじめてきたというのが、背景としてあります。
夏野:つまりそれは、「ジャーナリズムなんかどうでもいいからアクセスを稼げればいい」ということですよね。
津田:結局、リスクもなければコストも低いから、そうしたブログ運営をしてしまう。だから、私は信用情報のようなものを設ければいいと思います。今お話ししたようなブログのほとんどは利用規約違反をしているわけです。で、違反への対処がほとんど履行されることはない。でも、必ずお金は振り込まなければいけないから、ある種、銀行の信用情報みたいに、問題を起こしたアカウントが新しいアカウントをつくれないようにする。広告業界の倫理として、そういう対応をしたほうがいいと思っています。
夏野:ただ、そういうものが溢れてくると、メディア的にやっているところも流されるじゃないですか。既存メディアできちんとやってきていても、そうしたブログ等がどんどんアクセスを持っていくようになると、(旧来のメディアも)表現も過激になったりして。
津田:だから、ネットにあるような、いわゆる「釣り」の見出しみたいになって。普通の新聞もそれをやっていたら自滅すると思いますが。
夏野:「〇〇か!?」みたいなやつですね。
読者のリテラシー向上を教育に組み込むべき
瀬尾:フェイクニュースに関しては、発信者側がフェイクニュースに気をつけるとか、広告を出稿する側も配慮するとか、キュレーションやポータルがアルゴリズム等で排除していくとか、そういう制度等は必要だとは思います。ただ、一方で読者のリテラシー向上も必要だと思うんですよ。フェイクニュースってどんどん難しくなっているけれども、「そもそも情報というのは疑うものだ」と。マスコミを疑うだけではなく、情報を疑って自分で確認する必要があることを、教育に組み込むべきだと私は思います。
日本の今の教育ではメディアリテラシーも高まりません。今の状態であれば、たとえば「新聞を教育に取り入れましょう」と言っても、「新聞を読んで勉強しましょう」なんて話になるじゃないですか。そうではなく、いろいろな情報を見て、「どういう情報が信頼できるのか」と。あるいは、「情報は一歩引いたうえで、左右をきちんと確認して見ることで交通事故を防ぎましょう」とか。そういったことをきっちり教育に入れるべきだと思います。私は、G1というマルチステークホルダーが集まる場所で、そういう運動やイニシアチブみたいなものもできればいいなと思います。
夏野:では、最後にメディアの行方について。日本経済新聞社から「新聞」が取れちゃう。フェイクニュースは増える。そして、どうなっちゃうんでしょうか。我々はどうやって生きていけばいいのでしょうか。
蜷川:当社としては、今後も新聞社や出版社がやっていないような幅の広い情報を、好奇心を持って出していきたいと思っています。で、こうしたディスカッションでは報道やジャーナリズムの話になりがちですが、ネットの読者からすると、情報やメディアというのはもっと幅広かったり、自分にとって身近な話だったりすると思うんですね。たとえば、当社は女性のお買い物とお出かけに関する情報サイトもやっています。で、たとえばGoogleニュースに聞いてみると、そうしたお買い物やセールの情報はニュースではありませんと言われる。ただ、女性にとってはすごく必要な情報だったりするわけです。ネットはそういうところに人が集まってくるので、そういう部分も含めて幅を広げたいと考えています。
あと、私は最近広告の部署をやっているのでアドフラウド問題にも重大な関心があります。NHKも「ネット広告の闇」として取り上げていました。そうした問題も解決しないと、きちんとしたメディアが真面目にやればやるほど、その穴をかいくぐって、おかしなところがどんどん稼ぐ結果になってしまうと思っています。ですから、そこを整理していくことできちんとした情報を皆さんが受け取れるようにしたいな、と。
夏野:でも、そんなの整理できないですよ。ネットワーク販売の広告とか、もうやばいじゃないですか。
蜷川:そうですね。いたちごっこで。ちなみに、すごく困っているのが、それを止めるために、またベンチャー等いろいろなところが技術を開発する点です。それにまたお金がつくんですよね。そんな風にして、「そういうのを防ぎましょう」という技術をどんどん中間に挟んでいくことで、実は最近、メディアが取るお金がすごく減ってきているなと思っています。広告代理店以外にも、中間にいろいろなところが入ってくるので。
新聞社が生き残るためにはアーカイブを個人に開放すべき
津田:ネットメディアの未来というのは、つまりはメディアの未来でもあるし、インターネットの未来でもあると思っています。インターネットが出てきたときは、世界中に個人が情報を届けることができるという、その可能性に私もワクワクしました。人類が情報や知を共有することで進歩していくことの面白さもあった。インターネットは、昔は今ほどファーストなものではなかったんですよね。もっとスローで、じっくりとじっくりと、ウィキペディアのように皆で知を共有しようとしていた。
でも、今はTwitterやFacebookといったSNSが普及して、情報も一瞬で消費され、午後になったら忘れられているような状態です。情報が流れては消えていく、その速度がテレビ以上になってきました。「でも、実はインターネットの本質はアーカイブではないの?」というところに立ち返る必要が、まずはあると思っています。
あと、G1にいらしている方は感じていると思いますが、今はGoogleが使い物にならなくなっているんですよね。かつては本当に、検索ワードを工夫すれば良い情報に辿り着けていた。でも、今はスパムブログによって、まさに資本の論理によって、Googleの情報がどんどん汚染されていて、なかなか欲しい情報が見つからない。15年前の情報とか、今は一番検索しづらいですよ。
では、そこでどうするべきか。私は今大学の教員でもあるので、新聞社のデータベースに入って、面を指定して、「このときにどういうことがあったか」ということを調べます。そうすると、もう5分で欲しい情報が見つかる。ですから、新聞社やマスコミが持っている膨大な情報のアーカイブを活用するべきだと思います。それが月1,000円や1,500円になっていけば「Googleで検索するより毎月の契約でアーカイブサービスを利用しよう」となる。そういう風になるよう、新聞社が解放していくべきだと思います。おそらく、それによって大きな情報格差が生まれます。Googleしか使わない人と、新聞社の有料サービス契約でアーカイブを使う人とのあいだに。ただ、いずれにせよ新聞社が生き残るためには、どのような形でアーカイブサービスを個人に開放していくのかが鍵になると思います。
夏野:それはなぜやらないんですか? 日経には「日経テレコン」がありますよね。
関口:「日経テレコン」という有料サービスは前からありましたし、今は購読料をお支払いいただければ、電子版のほうで遡って1年ぐらいは出すようにしていますが。
夏野:1年という話ではないですよね。
関口:もちろんです。
津田:過去すべての記事をやらなければ、おそらくダメだと思います。
関口:そこは別料金でやっています。ただ、金額は結構高いんですよね。
津田:それを月1,500円ぐらいで過去のものも全文検索できるようにしたほうが、新聞の未来になると、私は思います。
ジャーナリズムの構成要素として「記録機能」もある
関口:ネットの話は皆さんがしてくださったので、新聞あるいは日経新聞としての未来についてお話をさせてください。結局、今は国内のユーザーまたはカスタマーベースがどんどん減ってきているわけです。消費財等、他の産業もそうですが。
すると、どの会社さんもやっていることとして、やはり海外展開が出てくる。だから日経もFTを買収して海外に出ていく決断を、まずはしました。あとは、「もっとネットにシフトしていこう」と。これはFT買収と連携しています。海外のほうがネットへの移行が早かったので、そのビジネスモデルを勉強しようというのが買収の1つの大きな要素です。
だから、FTを買収して大きく変わった点があります。先ほど「ネット嫌い」という話がありましたが、カルチャーが変わりました。デジタルファーストということで、たとえば先日のカルロス・ゴーンの獄中取材もそうです。昔は翌日の一面にバーンと出すということで、それまで出さなかった。でも、今回はネットで先に出して、そのあとは夜にテレビでも喋って、そして翌朝の朝刊です。そういう、かつてはなかった形が出てきています。
それともう1つ。ジャーナリズムの構成要素として、私は記録機能もあると思っています。紙は、あとから改ざんができないので、アーカイブとしての需要も結構ある。ネットはあとからでも結構変えているんですよ。紙はそれができない。これはネットにない強みなので、そこは死守していきます。それと、日経新聞が特に他の大手新聞社さんと違うのは、たとえば役所で予算を申請したり会社で稟議を上げたりするとき、日経新聞のコピーがついていると通りやすいといった話がある点です。そういう機能もあるので、やはり紙は紙で残していくという形ですね。
夏野:それでは、会場の皆さんからのご質問にお答えしていきたいと思います。
Q1)、フェイクニュースに関して、AIで判定するシステムは作れないのか?
津田:フェイクニュースのフィルターは実際に開発されています。大統領選でもFacebookには大きな批判がありましたし、今はGoogleもFacebookも、ある程度はできます。ただ、これはイタチごっこのようなところがある。スパムフィルターのようなものを実装することと、その効果については別問題なんですよね。たとえば、「フェイク度が高いです」といったことも、Facebookはアメリカで一時期表示していました。ただ、ほとんど効果がなかった。なぜか。「フェイク度が高いぞ」というニュースほど、保守的なユーザーや極右的なユーザーはガンガンシェアしたそうです。
むしろ、「あ、このフィルターで高いスコアが出るということは、俺らにとっては重要なニュースだ」という風に思ったところもある。むしろ、それによって確証バイアスが強まるという結果が出てしまった。だからFacebookはその表示を止めたという残念な結果がありました。ですから、ある程度はできますが完全には難しいというか、とにかく表示しても意味がないということですよね。プラットフォームが先にフィルタリングまでしてしまえば意味はあるかもしれませんが、そうすると今度は表現の自由や検閲といった議論になるので、すごく難しい問題です。
夏野:あと、学習が結構難しいですよね。スパムフィルターの場合、発信と、それから何通出しているかといったことをすべて分析したうえでやっています。でも、フェイクニュースの場合、そういうパターン化する、つまりAIが学習する十分なフェイクニュースの特徴があまりないので。その都度いろんなアカウントから出たりするから、少し難しいかもしれない。
津田:そういう意味での応用はあります。FacebookでもTwitterでもGoogleでも、つまりヤバいユーザーを把握するというか。そういう情報を最も取ることができるのはプロフィール欄なんですね。そこに、事前にフラグみたいなものを立てることがある。その機械学習で、ヤバイことがあったらすぐ凍結するといった運用は、実ははじまっています。
Q2)、紙メディアの良い点は広げて見ることでまったく興味のない情報も目に入ってくる点だと思っていますが、そうした良い部分について何か取り組んだりしている試みはあるか?
瀬尾:紙メディアの一覧性についてはUI/UXで改善できる面もあると思いますが、もう1つ、デバイスが変わってくる可能性があると思います。今みたいなスマホではなくて、もっと大画面の、紙のようなデバイスができたり、ARで空中に浮かせたりできれば、フリップボードのようなものもできたりすると思いますので。
ただ、今回のような議論のなかで、いつもメディアから抜けていると私が思うのは本のことなんです。私たちは普段、ニュースばかり見ていて意識していませんが、人生に影響を与えるという意味では、本はメディアとしてすごく大きな影響力を持っている。ところが、そこはデジタルの世界から取り残されています。電子書籍にはなっていますが、なかなか新しい接点ができていない。とんでもない本もありますが、良質な本もたくさんあるわけですよね。ですから、そこを、もっとうまくつなげていけたら。新聞が新しいポータル等を使って読者を広げたのと同じように、本についても広げる場所が、アマゾンのレコメンド以外にも、もっともっと必要なんだと思います。
夏野:本のほうがフェイク本みたいのはたくさんありますよね。誰も検証しないから、結構ひどいことが書いてある。でも、読者が1000人ぐらいしかいないから分からなくて、それで炎上もしないという。
津田:フィルターバブルとかエコーチャンバーと言われる通り、今のネットは自分が興味・関心のある情報しか行かないですよね。だから私は実際の人間関係に注目するしかないと思います。ソーシャルグラフ的な意味で。自分が欲している情報をネットで探すと、自分好みの情報しか見つからない。でも、実際の人間関係はもう少し複雑じゃないですか。実際、私には右寄りの友人も数多くいます。で、そういう人たちとFacebookでつながっていたりするとき、普段自分が見ないような情報をどんどんプッシュするとか。そういった仕組みは必要だろうなと思います。
Q3)、動画とテキストの親和性については?
蜷川:動画とテキストの相性については、おそらくデバイスと、あとは音の問題があると思っています。基本、皆さんは電車内でスマホを見ていますから。動画で最近すごくよく見られているのは、写真と字幕だけのもの。個人の方々がコピペをしたような動画コンテンツがすごく読まれていて、広告的にもすごく儲かっているそうです。でも、おそらくテレビは音声ありきで映像をつくっていらっしゃいますよね。ですから、動画とネットとの相性は悪くないと思いますが、音声ありきという今の動画とはおそらく合わないので、それでテキストによる補足等が必要になってきてしまうのかな、と。あとは観ていられる時間の長さが違うという点もあると思います。
Q4)、フォーラム機能の可能性については?
津田:フォーラム機能というのは、この場のように、いろいろな人が出てきて、皆がつながるところにもあると思っています。インターネットには質的なコントロールが存在しないという問題がある。事実確認をしてくれる人の校閲、ファクトチェックの不在ですね。また、ネットの特性として、初めて聞くような話、あるいは確証のない断言のほうが、しっかりファクトチェックしたものよりも拡散しやすいという面もあります。これは、ある種、人間の弱さみたいなものでもあると思います。
また、議論で何かを断言したのち、あとで調べたら間違っていたという話もあったりします。ですから、フォーラムを適正に機能させるためにはリアルタイムできちんと場を仕切って、事実確認もできる人がすごく重要になる。ネットに可能性があるとするなら、そこですよね。それをリアルの場で、リアルタイムでやることには限界がありますが、ネットであれば不特定多数の人が参加して、そういうことができると思うので。そういう点で、今後もマスメディアが拾っていって技術開発等をしてもいいのではないかと思える点はたくさんあります。
関口:フォーラムの話と少し違うかもしれませんが、ここ10年ほどの傾向を見ていると、リアルのフォーラム、つまりカンファレンスというものを、新聞社が皆やるようになってきました。当社は特にそうですが、ダウ・ジョーンズやウォール・ストリート・ジャーナルもそうですし、FTも。カンファレンスでリアルタイムのやりとりをして、それを今度は記事化する等、コンテンツにしていくというのはありますよね。
Q5)、メディアのリテラシーという話もありますが、結局、誰がどう変わらなければいけないのか?
夏野:誰がどう変わっていくべきか。メディアというのは大衆の鏡だと私は思っています。テレビの編成でどんな情報を扱うか、なぜ不倫ネタがあれほど多いのかと言えば、それを見て喜ぶ視聴者がたくさんいるからですよね。だから、そこを教育するというのは広告モデルである限り無理だと思います。なので、「そんなもんなんだ」と。1つのバロメーターだと思って、仕方なくコメンテーターとして抵抗していくしかないというのが、我々の宿命だと思っています。
Q6)、メディアのマネタイズとして、サブスクか広告以外で何か最先端の話があれば
瀬尾:新しい収益に関しては、広告か課金かというだけではなく、いろいろな方法を考えることが大事だと思います。フォーラムもそうですし、コミュニティもあると思うんですね。私は先日、アメリカでいろいろとデジタルメディアの話を聞いてきましたが、そのなかで面白かったのが地方紙での成功例でした。アメリカの地方紙も経営は相当厳しいのですが、そのなかでもデジタルで成功しているのは、コミュニティをつくっていたところ。自分たちの記者については、今までやっていた事件取材等はすべて止めさせ、コミュニティの取材をさせているんです。で、そこからまた情報を上げるようにして、そのなかではメルカリのようにモノの売買もできる。その手数料でビジネスにするわけです。そこでコアになる取材は、コミュニティの取材と、あとは行政のウォッチドッグのような部分ですね。そこは普通の人になかなかできないので、特化したうえで差別化するというやり方をしていました。そんな風に、どこでエッジを立てるかという話だと思います。
夏野:あと、スポンサーを見つけてくるというビジネスモデルはありだと思います。今、ジェフ・ベゾスは『ワシントン・ポスト』のオーナーでしょ。 お金持ちが出してくれるじゃないですか。マーク・ベニオフが『タイム』を買ったり。言論ペーパーは、そういうパトロンに支えられてきた歴史もあると思うので、反権力を貫くためにはそういうパトロンも必要だと思います。
津田:もう1つ、広告モデルと課金モデルのほかに、第3のモデルとして今注目されているのが行動モデルと言われています。一番分かりやすいのは食べログです。もともとはアクセスを集めて広告を貼っていましたが、今、あちらの収益源は予約なんですよね。皆が利用して情報が集まっているので。今、食べログに掲載されているほとんどのお店には予約機能がついていて、予約による手数料を得るという形です。これは、おそらくマスメディアもできると私は思います。たとえば、取材をして「地方にこれだけ魅力的な旅館がありました」といった記事を読み終わったあとに1クリックで予約できたら、それはやりますよね。そこは利益相反の問題もあるのでジャーナリズムとの相性は悪いんですが、行動モデル自体にはいろいろな可能性があると思っています。ネットメディアの未来という話であれば、ジャーナリズムはそこを上手く使っていくのもいいのではないかなと思います。
夏野:時間が来てしまいました。素晴らしいパネラーの皆さんに語っていただきました。今日はどうもありがとうございました(会場拍手)。
<前編はこちら>





























.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)
.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)
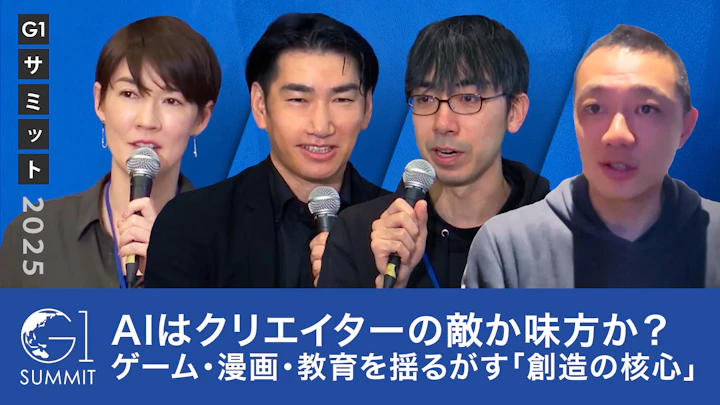
.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)
.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)














.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)


.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)

