本記事は、G1サミット2019「終末期〜人生における幸せとどう死ぬかを考える〜」の内容を書き起こしたものです。(全2回 後編) 前編はこちら>>
柳川:今は「提案がまとまりました。こうしましょう」と、我々がプレゼンしているわけでなく「イニシアティブがはじまりました。皆さんもぜひ議論を」という段階ですので。
藤沢:そうです。ですから「このポイントをもっと議論すべきだ」「こういう取り組みをイニシアティブで動かしてみてはどうか?」といったご提案があれば。
会場参加者1:今日の議論は精神論的要素が多く、実際、それが本論だとは思うんですが、せっかく経済学の先生もいらっしゃるので財政的な話もしてみたいと考えています。今は正確な数字を把握していないんですが、おそらく国民医療費の70~80%は75歳以上となる後期高齢者に注ぎ込まれている。たとえばICUのベッドでターミナルケアを受けている患者さんにかかる費用は、3日でおよそ1000万円と言われています。3日間、チューブなり人工呼吸器なりにつながっている患者さんを生かし続ける、その延命治療で1000万円。それが、もちろん日本中で起きている。
本当はその費用を赤ちゃんや若い世代につぎ込むほうが将来世代にとってはいいんですが、高齢者が有権者(の多数派)なので、どうしても政治が高齢者を向いた施策ばかりになっている。しかし、将来を考えるG1では終末期医療の財政的判断も必要ではないかと考えています。冷たい話ですし、誰もこんな話はしたくないと思うんですが、議論の場には論点として提示したいと思います。
藤沢:ありがとうございます。その議論はイニシアティブでも出ていました。ただ、これを言うと「お金のために殺すのか」みたいな話になって、公には議論しないでおこうという話になっていたのですが、たしかにおっしゃる通りだと思います。
会場参加者2:医療費亡国論というか、終末期医療に関して「死ぬ前の1ヶ月に大変なお金がかかる」という話は、とあるG1メンバー2人の議論が先日大炎上したことでご存知の方も多いと思います。ただ、いろいろと誤解もあります。「専門家の方によると」という受け売りですが、終末期医療にかかるお金は医療費全体の3%ほど。なので、そこをなんとかすれば大きな財源になるというお話ではありません。もちろん尊厳とコストは分けて考えるべきだと思いますし、お金のメリットもない以上、やはり切り離して議論するのがいいと思います。
会場参加者3:私が住んでいるスイスでは、先ほどの分類では医師による「自殺幇助」を選択しています。それを支援する団体があるんですね。で、本人の意思確認をして、各種基準もクリアした場合のみ、それを支援する医師が薬を提供します。また、これはいろいろの人が監視しているなかで行われるし、あとでビデオを警察に届けないといけない。そんな状況で自ら飲んで亡くなるというのがスイスのやり方で、私はこの方式をおすすめしたいと思います。キリスト教徒である私自身は絶対やりませんし、同じキリスト教徒の兄弟姉妹にもすすめません。しかし世界はキリスト教徒だけではありませんし、良い社会とは選択肢がある社会だと思っていますので。スイスのやり方は非常に頭が良いと思っています。
会場参加者4:死ぬときは結構忙しいので、たとえば余命3ヶ月の時点で何か選択できると考えないほうが良いと思います。特に、会場にいらっしゃるような皆さんは忙し過ぎて、そんなの絶対にできません。それに「死人に口無し」ではないですが、残されるのは医者と家族だけですし、「あまり心配しなくていいのでは?というのがまず1つ。
そのうえで、今のうちに何ができるか。面白いのが「入棺体験」です。棺に入ってみる。あの本物の箱に入るのは気持ちのうえでハードルが高いんですけれども、実際にやってみると「棺には何を入れてもらおうかな」「服は白装束じゃなくてこれがいい」となるんですね。それで家族も呼んで体験すれば本当に“死んだ感”が出て、そこではじめて「死んだらどうなりそうか」という話から逆算できるようになる。ですから、1度家族ぐるみで死ぬフリをしてから考えるのはとてもいいと思います。最近はそういうイベントもありますし、イニシアティブでそれをつくってもいいと思います。
藤沢:今度からG1で運動会でなく入棺体験を(会場笑)。ほかにはいかがですか?
会場参加者5:もちろん緩和ケアの技術は今後も高めていくべきだし、「それでも最期まで取り除けない場合は安楽死でも良いのでは」という議論はあると思います。ただ、国立がんセンターが昨年行った調査によると、いまだに半分ぐらいの人は痛みが消えないまま亡くなっているというんですね。ですから、そういう方々への配慮というか、そこの議論も同時進行で深めておくべきではないかなと思っています。
古川:そうですね。イエスかノーの2択ではないし、選択肢はあっていいと思います。ただ、僕も数多くの病院を見ているわけではないんですが、すべからく99%の痛みは取り除くことができるという先生もいれば、「そうでもない」という先生もいて、人によって差があるんだろうなと思っています。ですから、そのクオリティを高めましょうという試みをやってから、選択肢ができるといいのかなという意見になります。
会場参加者6:祖父が最期に体調を悪くしたとき、救急車を呼んだ私たちは、それが延命治療のボタンを押していることでもあると知りませんでした。「倒れたら救急車」と、条件反射で呼んでいた。ただ、即「チューブをつないで欲しい」という話ではなかったんです。「お医者さん、これは最期なんですか?」ということが知りたくて。ですから、たとえばナースコールにように「先生来てください」というボタンと、「しっかり医療の限界まで見てください」というボタンが別々にあれば、と思っています。延命治療を考えていない人まで医師法の絡み等で対応ががっちり進められたため、呼んだ人が驚いたという話は私もときどき聞きます。ですから、特に終末期には「救急車を呼ぶことがどういうことなのか」を伝える。もしくは、呼ばれたら「はい、お運びします」としたうえで、病院では一度落ち着いて、「では、どちらにしますか?」と伺うような2段階方式が現実的なのかなと感じています。
会場参加者7:今のお話にも関連しますが、リテラシーの問題があって、ご本人が病気で倒れたときに「延命治療は行いません」と言っても、もうだめなんですよね。ですから、子どもや兄弟を含めて家族が事前に同意したという同意書のようなものをつくっておく。で、先ほどの「消極的安楽死」を望む人はそれを持っておくべきだと思います。その辺があまり知られていないので、あとでいつでも止めることができるようにはしつつ、そこまでの準備はとりあえずしておくという話を広めていくのも大事だと思います。
藤沢:これは良いご提案だと思います。ご家族とそういうお話をしたことがある方はどれほどいらっしゃいますか?少数ですね。では、これも皆さん、それぞれご家族と一度お話をしていただいて、次につなげるのがいいかもしれないですね。
会場参加者8:あと、たとえばスイスはホスピスも大変充実しています。ですから普通の病院に入っていても、「もうこの人はもたない」と思ったら、延命治療ではなくて「ホスピスを紹介します」となる。それで私は親しい友人を3人ホスピスで亡くしていますが、皆、ハッピーに亡くなりましたし、そのご家族も満足して送っていたと感じています。
会場参加者9:その「もう、もたない」というのはどなたが判断しているんですか?そこが最もクリティカルな部分だと思います。
会場参加者8:そこは厳密に確認できていないんですが、ある種、ホスピスにいくのが普通のことと思われているので、何かの判断基準があるんだと思います。
藤沢:大切なポイントだと思います。私の父は、先生に「もうもたないからホスピスに行ってください」と言われ、ホスピスで亡くなりました。ただ、たしかに今はその基準もないですよね。さて、そろそろ時間になりましたので、最後に一言ずついただきたいと思います。
柳川:最後のご指摘は大切なポイントだと思います。いろいろな法制度化にあたっては、どういった基準でどのように進めるかを具体的に考える必要がある。ただ、その裏側では「ホスピスに行くのが当たり前」「医者は治すだけじゃない」といったお話のように皆のマインドを変えていくことも大事なので、イニシアティブでもそんな議論をしたいと思います。
津村:あらゆる議論にはそれぞれ時間軸があると思いますが、このテーマは会場の皆さんが今後20~30年、自分の生き方・死に方の時間軸で考えるテーマであり、社会でも同様の時間軸で議論が進むのだと思います。また、そこで私自身は最終的に先ほどの「積極的安楽死」まで行くべきではないかと思っていますが、20~30年、あるいは50年かけてそこにいくのかな、と。これだけ医療が発達し、これだけ人の生き方も多様になったわけで、最終的な答えはそこにあるのではないかと思います。今後も皆さんとともに考えていきたいと思います。
古川:日本では医療が空気のように当たり前のものとして、実際のところフリーアクセスで当たり前のものとして提供されていますが、実際にはそんな国は少ないですよね。これほどクオリティの高い医療が、限られた医療資源の分配で皆さまに提供されている。この価値を強く感じていただいたうえで、その先にある医療資源の有効活用という観点で、終末期医療を考えることが大事ではないかと思っています。どちらかというと医療提供サイドにいる私としては、今ある医療は決して悪ではない、と。世界水準で見ても非常にクオリティが高く、そして安価だということを強く呼びかけていきたいと考えています。
松山:私としては、平均寿命信仰を止めたほうがいいと考えています。長生きはいいことか。「健康寿命を伸ばす」というお話がありますが、健康寿命が長くなっても私は今と同じように考えると思います。ここは日本一の短命県である青森ですが、では青森の人が他の都道府県の方と比べて不幸せかというと、まったくそんなことはないと思うんです。たとえば健康で100歳まで生きても、お話を伺ってみると「早くお迎えにきて欲しい。誰からも望まれていない」と、すごく寂しそうな顔をするお年寄りがたくさんいるわけです。ですから、自分が大事にしているものは何かとか、生きるとは何かとか、そういうものを皆さんが認識して運命をきちんと消化して受け入れる。そういう体制を普段から取っておくのが一番重要なのかなと思います。
藤沢:このテーマは多様なステークホルダーがいるなかでの議論になるので、すぐに答えが出るものではないんですが、だからこそG1でやらなければいけないと思います。今後も引き続き議論していきたいと思いますし、イニシアティブは毎月第2水曜ぐらいに朝8時からやっております。ぜひスカイプでもいいので参加していただいたり、今日のようにご意見やアドバイスもどんどんいただきたいと考えています。G1の方々は皆前向きですから、どうしても前向きな声ばかりが聞こえてきますが(会場笑)、「いやいや、こんな問題もあるんだ」という声も絶賛募集中です。ぜひご参加いただいて、来年のG1では入棺体験を進めることができたらと思いますので(会場笑)、よろしくお願い致します。今日はありがとうございました(会場拍手)。
執筆:山本 兼司










.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)
.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)
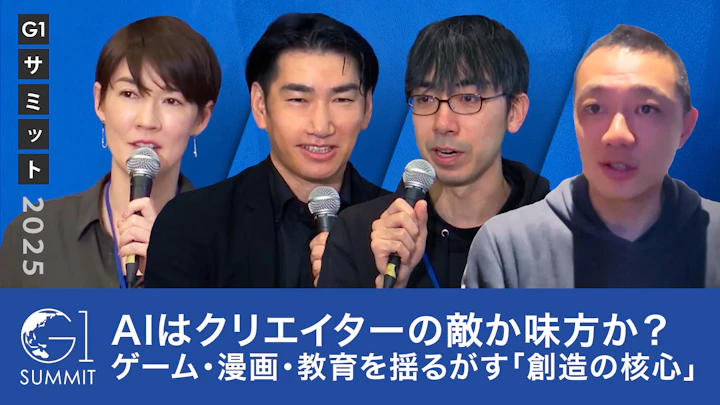
.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)
.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)




