長野県小布施町は人口1万1000人ながら、年間130万人もが訪れる観光の町である。葛飾北斎と栗菓子が有名だが、加えて土蔵や土壁、茅葺の民家、栗の木が敷き詰められた歩道など、生活感が溢れているのに昔の風情も残っている町並みが観光客を呼び込んでいるのは間違いない。国からの補助金に頼ることなく、住民主体でこの新旧建築物の調和する美しい町並みをつくった「町並み修景事業」の立役者が市村次夫氏だ。市村氏にどのような志を持って小布施町の町並み修景事業を推進したのか、話を聞いた。(全2話)
町並み修景事業、発想の原点

西村:町並み修景事業の発想の原点は。
市村:「自分の一生を大切にしよう」というところから来ています。従兄弟で仕事のパートナーが、私と同じ昭和23年の生まれなんです。自分たちが年取った時に暮らしやすい田舎町を思い浮かべて、まずは車からリタイヤしても暮らせるような町にしておきたいと考えた。
さらに言うと、「街並み保存」と言うのはどこか窮屈に感じる。時代は変わっているのに、「江戸時代のものが最高!」みたいな感じが多いでしょ。信念としては分かるけど無理がある。コーヒーショップ禁止、TVは隠せ、洗濯物は干すなとか…。そんなの町じゃないよと。
ドイツのロマンチック街道に、ローテンブルクという人口十数万人の観光地がある。実際は観光だけでは食えないから郊外に工業団地を作って企業誘致をしているけれど、交通の便が良くないから大した企業が来なくて、住民が食べて行くのに非常に苦労している。それなのに東京から来る先生方は「日本のローテンブルクになれ」と言う。私はもっとリアリティがある町の方がいいんじゃないかと思った。日本のお城を見ても分かる通り、建物だけじゃなくて地形や空間を上手く使っていく点は「買い」だから、それを徹底的にやって行こうよって思いますね。
西村:それが「街並み保存」という考えと「町並み修景」の違いなんですね。
市村:新しいものがあって、それも含めて町なんだと言いたい。古いものだけなら博物館だよと。
西村:年間どれくらいの人が訪れるのでしょうか。
市村:現在は、年間130万人くらい。平日も紅葉の時期は混みます。
もともと小布施は善光寺の市場町として1600年頃にできました。その頃は福島正則という戦国大名も町づくりを担っていて、その最たるものが町を分断している川の流れを変えるというもの。ここに流れている用水もその頃につくったものが未だに残っています。
小さな社会が地域の強み。完璧な被害者、加害者は存在しない
西村:地域に町おこしを主導するリーダーがいない場合はどうすればよいのでしょう。
市村:その場合は、地方の強みを生かします。地方は社会が小さいから、完璧な悪人もいなければ、完璧な善人もいないし、完璧な被害者もいなければ、完璧な加害者もいない。例えば、公共事業で山から砂利を持って行ってビルをつくるとする。「自然破壊だ」と主張する人がいても、一方で同じ地域内で恩恵を得ている人もいる訳で単純じゃない。
西村:受益者と被害者の関係が近いから、文句が言えなくなるということですね。
市村:善悪のレッテルを張るのは簡単だけど、それで解決できないことも多い。例えば、幕府の代官には悪役のイメージがありますが、個人の財産を削っても町のために尽くしている代官もいて、彼らほど良い仕事をしている人はいない。
小布施の3分の1ぐらいは昔、都住(つすみ)という村で、椎谷(しいや)藩の領地でしたが、税収の半分くらいを司る代官屋敷がありました。「こんな小さなところに住んでいたの?」って感じの代官屋敷ですよ。自分と足軽の2人しかいない。となると、一揆がおこった時に大刀を持って迎え撃つのは1人しかいないから、真っ先に殺される。つまり、地方では悪代官ってやりようがないから、お百姓と協力し合うしかなかったわけです。
信越化学での仕事の考え方が原点となった仕事観

西村:小布施は栗菓子が名物で、小布施堂の「朱雀」を遠くから食べに来る人も多いと聞きました。
市村:栗の時期の1か月だけの話ですけどね。小布施が栗の一次加工をやっていることを知って楽しんでもらいたいと思って、30年くらい前に「朱雀」の販売を始めた。ブレイクしたのは10年くらい前からですけどね。
西村:10年前、銀座で栗羊羹を配っているのを見かけました。その時に小布施=栗という認知ができたのですが、このような仕掛けをいつから意識されていたのでしょう。
市村:町並み修景を実施する頃から意識していました。コモディティ商品じゃないやり方をしないといけない。そう考えると、どういうところで誰が作っている、というのも商品の一部だって言うことですね。
商品の強さというのは売上以前に、2つ3つの商品が並んでいたときに「あ、これ小布施のやつだ」と認知した状態で選んでもらうこと。複数商品が並んでいる中で、結果的に何となく選ばれて売上は上がっているけど…という状態では強い企業と言えません。売上は結果であって、商品力は2つ並んだ時に勝てるかどうかということなんですよね。
西村:今のような商売に対する考え方を形作った原点は何ですか。
市村:以前勤めていた信越化学という会社が徹底的にそういう考えでした。200とか300種類の商品の売上を足した結果がどうであっても、ワールドワイドで考えたらほとんど意味がない。それよりも一つひとつの商品が世界の中でどのくらいのランキングなのかと言うことを考えないといけないと言われていた。
特にコモディティ商品は単品で世界トップシェアじゃないと意味がない。目指したのは1位ないし2位。3位以下は2位にするか止めるということを実施してきた結果、主要10品目のほとんどがトップシェアになった。売上規模はそれほど大きくなく2兆円くらい。でも純益が2000億くらいあるんですよ。その考え方が面白いなと思った。
多様性を受容してきた小布施だからこそ生まれるもの
西村:小布施ではUターン就職は多いのでしょうか。
市村:私は一度就職して外を見て勉強してから小布施にUターンして欲しいと思っているけど、ちょっと気がかりなのは外で就職しないでこっちで就職しちゃう人が増えている。小布施の居心地がよくなっているし。知名度が高いのが快適なのは分かるのですが、やっぱり外を見てきた方がいいのではないかと。
西村:その方が小布施の町自体にいろんなアイデアが生まれますしね。外の知恵も歓迎ですか。
市村:最初から狙っています。町長は「小布施町の得意技はアリ地獄ですから」とよく言われます(笑)。小布施は、葛飾北斎もそうだし、昭和初期にイギリス国教会のカナダ支部が日本に結核の療養施設を提供しようと全国に呼びかけたけどどこも嫌がって手を挙げなかった中、小布施は手を挙げた。もちろん反対派もいて流血騒ぎまであったけど、最後には推進派が勝って呼んできた。それが今の新生病院になっています。
西村:地域全体で異質なものを好意的に受け入れる文化は、どのように醸成しているのですか。
市村:小布施全体が異質なものを受け入れる文化という訳ではないと思う。小布施の中でこのあたりは町場といわれる。町場はシティだから異質なものを受け入れないといけない。両方あるから面白いって考え方なのですよ。こんなところに住んでいながら気分はニューヨーカー(笑)。喧嘩は絶えませんけど。
例えば、戦後日本は民主主義の象徴として地方に公民館活動を促進した。小布施の初代公民館長は、林柳波という「お馬の親子」などの童謡も書いている詩人で東京の人でした。それがうまく融和を促した。小布施の人は、自分たちでは力が不足していると自己認識していたから、よその才能の助けを借りることができた。それが歴史的に大事だった。
町づくりのアドバイスを求めてきた人へアドバイス
西村:もし強みが何もない町からアドバイスを求められたらどうしますか。
市村:強みが絶対ないってことはないと思いますね。極端なことを言えば、アドバイスを求めてきた人が凄く熱心な人であれば、あなたがいること自体が武器だろうって。
いかにコモディティ商品で沢山作るか。それが出来ない山間地は農業不適地だと思われがちですが、高級品はどうだと考えてみると、全く逆転するんですよ。生産効率は悪いけど、味の良さって言うのは山間部の水温の冷たいところの米がいいし、朝晩の気温の寒暖差の激しいところの果物がいい。
もうひとつ、日本の農政がこの土壌には何が合っているかと実験しているかというと、していない。それを突き詰めると絶対有利な作物はあるはず。そう考えて行くと、やることも考えることもいっぱいあるだろうとお伝えしたい。多様な視点で考えられるといいですね。
後編のファミリービジネスの歴史観編は3/6掲載予定です>>





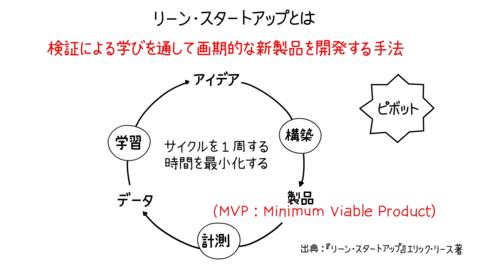




































.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)
