本記事は、GLOBIS知見録YouTubeにて公開している【特別シリーズ座談会】「キーワードから読み解く VUCA時代のリーダーとは」#1 VUCA時代に求められるリーダー像の内容を書き起こしたものです。
西:やらなければいけないことはそんなに変わらないと思うんですが、やらなければいけない内容や程度は結構変わると思っています。特に人々の共感をつくらなければいけないということに対するリーダーの役割とが、すごく大きくなったと思うんです。先ほどの多様であるとか、いろんな選択肢を働く人が持てるようになってきたことによって、働く人も働く場所、働くリーダーを選ぶという時代になっていると思うんですよね。そうしたときに、「このリーダーの話には共感できる」とか、ストーリーに対する共感ってすごく大事だと思っています。さっき言ったようにテクノロジーもすごく進化している、環境のことについても考えなきゃいけない、いろんな世界でいろんなことが起きている中で、「自分と会社ってどうしていきたいんだ」という点を定めていくのは難しいと思っています。かつ、それを自分の原体験に近い形で話せないと、その人らしさは伝わってこないんだろうなと。「いろんな多様なテーマを自分と紐づけて、ストーリーで語って共感をつくっていく力」というのはすごく難しいけれど、それができる人に、人々とか投資が集まってくるのかなと感じています。その点がすごく変わってきたところじゃないですかね。
嶋田:そこはさっきの論理思考力も出てきますし、当然ですけれどヒューマンスキル、あるいは俗にいう人間力とでもいうのか。「この人の言うことだったら、とりあえず付いて行っても大丈夫かな」と思えるぐらいの姿勢であるとか、その人の自己鍛錬の度合いだとか。そういったものがますます重要になってくる気はしますよね。
西:そうですね。働くモチベーションが「お金のために」とかじゃなくなってきているし、「自分の自己実現のため」になると余計そうなりますよね。
嶋田:やはり、そういう共感力っていうものがますます重要になってきそうですね。これからの時代、君島さんの論理思考力と同じで、ますますその重要度が増していくと。私も、人間力というとビッグワードではありますが、先ほども言いました、「この人だったら付いて行ってもいいかな」と思える、その人の原体験に根ざした未来に対する洞察であるとか。あるいは常日頃から積極的に情報にアンテナを張って、いろんなものを収集しているとか。あと、単純に打たれ強いとか、誠実だとか、何かあっても逃げないとか、そういったことがますますリーダーには求められる気はしますね。
では一方で、「ここは今までとは少し違って、変えていけばいい」っていう点は、どんな点を思いつかれますか。
君島:ひとつは、「自分とは違う人を相手にして話している」という前提が必要になるかなと思っています。先ほどの西さんの共感力という話で、共感したことを発信してみんなを引き寄せないと、リーダーとして誰も自分の組織に来てくれないかもしれないと考えると、きちんと自分が共感したことを発信できないといけない。発信するときに「相手は自分と同じことは考えていないかもしれない」という前提で、きちんと「自分はこういう体験があってこう思っているから、こう考えている」みたいなことが、これは論理性にも通じるんですけれど、整理して発信できないといけない。前提として「同じ体験があるんだ」とか「同じ世代として同じ背景を共有しているんだ」というのは、もう成り立たないのです。
時事問題の話題を出すと、最近オリンピック委員会の女性の話がありましたね。あれはおそらく、あの世代の方の価値観としてはまったく普通のことだったと思いますし、その世代で(平等に)女性が委員会に入っているなんていうことは、おそらくなかったわけですから、まったく不思議のない話だったのでしょう。でも、「もう聞き手はそういう世代ではなく、そういう世界に生きていない」ということを想像の上でしゃべらないと、「うーん、何でこういう話になったのかな」と、いらない不信を呼んでしまって、ぜんぜん違う文脈で理解されてしまうわけですよね。ぜんぜん違う人たち相手にきちんと通じる話をしなくてはいけない、その前提で話を組み立てなくてはいけないっていうところは、おそらくこれまで、日本の企業社会が同質的な人を前提に作ってあって、同質的な人を前提に発信してきたところから、大きく違っていくことだろうなと思っています。
嶋田:西さんはいかがですかね。変えていかなければいけない点。

西:変えていかなければいけないのは、リーダーとしての意識の部分。経営者がトップマネジメントとして最終責任を負いながらやっていて、他の人はどちらかというと「ついていく」。比較的、部門長、課長、部長などの形で、「役割を与えられているからやっています」「上から落ちてきた目標を頑張ります」という思想で働いていて問題なかったことが、従来は多かったと思います。これからは部長であっても「自分が経営者である」という意識で働いていくのがすごく大事になってきていて、人事制度も含めて、そういうふうになってきている。「権限は与えます。でも、結果をちゃんと出してほしい」、「自分がどういうことをしたいか、というプランがあれば、人的リソース、お金のリソースなど必要なリソースをいろいろ使っていいよ」と。でも、逆にプランがない人にはお金も人もついてこない時代になる。自分で経営する感覚でやっていって結果を出していく。経営者のつもりで仕事をする機会も増えてくるし、そういう人が、社会でより求められていく時代になってきたなと感じるので、マインドがそこから変わっていくというのは大事かもしれないですね。
嶋田:マインドを変えるためには、当然だけれど時間の配分も変えなきゃいけないし、日常からの言動も。ある意味形から入っていくという側面もあるでしょうし、そのあたりを変えていかないと新時代のリーダーにはなり得ない、という話ですね。
西:そうですね。昔はホールディングスがあって、ホールディングスの下にカンパニーをつくって、「この人たちが経営者だよね」ということだったと思うんですけれど、それがさらに細分化されて、事業部ごとに責任者=経営者として活動することが求められるイメージがありますね。
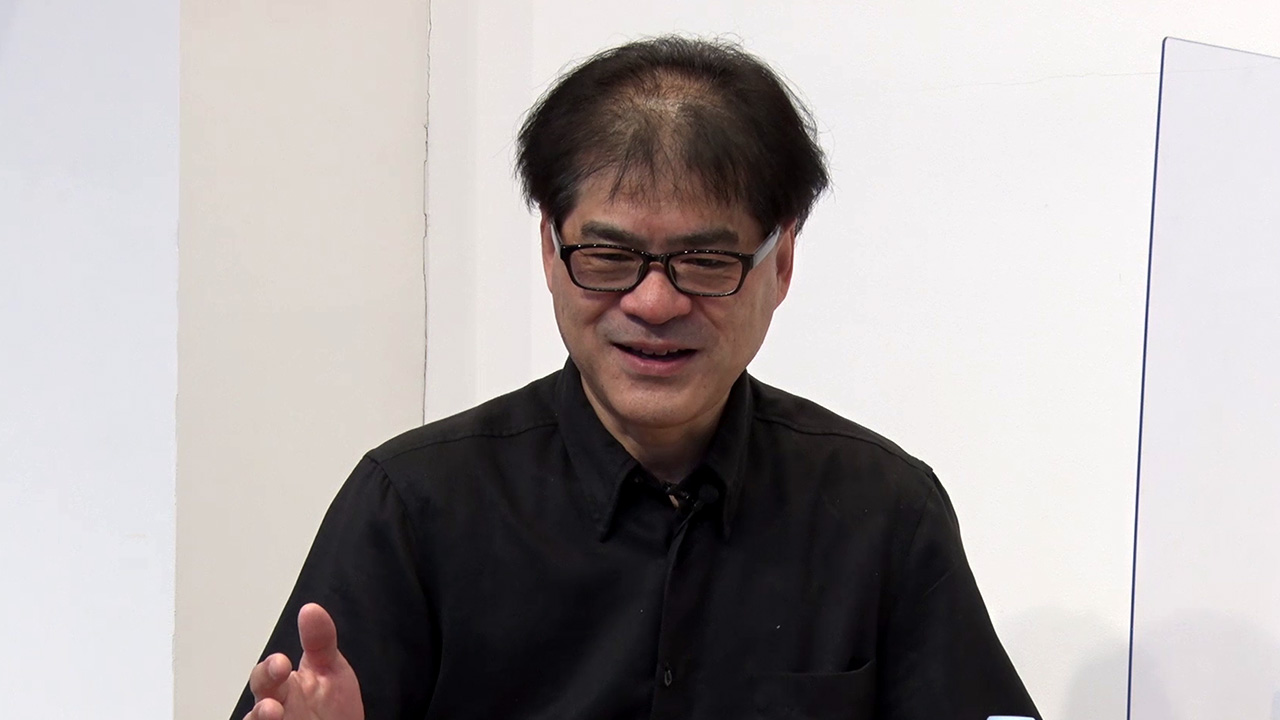 嶋田:そうですね。やはり、みんながさらにリーダー的な視点を持たなきゃいけなくなってくるというのでしょうか。マネジャーとリーダーは微妙な使い分けをされたりしますけれど、通常マネジャーと呼ばれる人でも、本当に組織のトップのリーダー的な振る舞いがより求められるようになっていく感じですよね。極端に言えば、昔は単純作業の監督みたいなことをしている人も多かったわけですけれど、さっきもあったように、単純作業の監督のような仕事はだいぶ付加価値が落ちていく。企画力であるとか、それまでなかった物事を生み出す力、あるいは、先ほどもあったように差異から何か富を生み出す力とか。いろんな情報なりに意味づけをするとか、そういったものをどんどんつくっていく。まあ、いままでももちろん重要だったのでしょうが、それこそがある意味、仕事の本質になっていくんじゃないかなという気がしています。
嶋田:そうですね。やはり、みんながさらにリーダー的な視点を持たなきゃいけなくなってくるというのでしょうか。マネジャーとリーダーは微妙な使い分けをされたりしますけれど、通常マネジャーと呼ばれる人でも、本当に組織のトップのリーダー的な振る舞いがより求められるようになっていく感じですよね。極端に言えば、昔は単純作業の監督みたいなことをしている人も多かったわけですけれど、さっきもあったように、単純作業の監督のような仕事はだいぶ付加価値が落ちていく。企画力であるとか、それまでなかった物事を生み出す力、あるいは、先ほどもあったように差異から何か富を生み出す力とか。いろんな情報なりに意味づけをするとか、そういったものをどんどんつくっていく。まあ、いままでももちろん重要だったのでしょうが、それこそがある意味、仕事の本質になっていくんじゃないかなという気がしています。
他にどうでしょう。変えていかなきゃいけない点、相変わらず強く持っておきたい点。
君島:どっちにあたるかなと思って考えていたんですけれど、多様なアイデアを出す力というか、いろんな意見を言う力。考える力もそうだし、言う力もそうですね、両方もっともっと必要になってくるかなと思っています。本当は今までも必要だったのかもしれないんですけれども、組織の中でいろんなことを言う人が重宝がられていたわけではないのでは、という気がします。そうすると、今後は必要になってくる。変えていくべき力のほうかもしれませんね。どんどんいろんなアイデアがないと、世の中が変わったときに何が受けるのか、何をしたら価値だと思ってもらえるのか。これらはどんどん変わるはずですよね。それにキャッチアップして、いろんなアイデアが組織の中で出てこないといけない。いろんなネタが出てきて、それが表明されなければいけないと思います。けれど現実、そんなにいろいろみんな思いつこうとしているか、思いついたらそれを会社で言おうとしているかというと、そうでもなくて。言われたこと、上から与えられたことをやっていくっていうのが仕事だという認識が多いかなと思います。そうじゃなくて、自分がアイデアを出して、それを表明してつくるんだという、西さんがおっしゃる「みんな経営者」というのに似ているかもしれませんね。そういう発想がもっともっと要るかなと思います。
 嶋田:そうですね。言われたからやるんじゃなくて、「やりたいからやる」とか「やるべきだからやる」とか、そういう発想を組織のてっぺんのリーダーだけではなくて、特にミドルのリーダーぐらいの人が持てる組織は強いなと思いますね。
嶋田:そうですね。言われたからやるんじゃなくて、「やりたいからやる」とか「やるべきだからやる」とか、そういう発想を組織のてっぺんのリーダーだけではなくて、特にミドルのリーダーぐらいの人が持てる組織は強いなと思いますね。
西:ベンチャーの経営者って自分がやりたいことを強烈に思って、形に落としていくじゃないですか。ビジネスパーソンとして働いていると、そういうことに対する意識はどんどん弱くなっていく。だけど、ここからは、「自分のやりたいことって本当は何だろう」とか「自分が成し遂げたいことは何だろう」っていうことがちゃんとあって、「それがこの会社でできるんだったら、自分はここで働きたい」と、発想が逆になっていく人のほうが強いと思います。そういうことができる人は、君島さんが言ったような世界観とか、嶋田さんが言ったような「そういう人がミドルにいると強いね」という。こういう育成って、日本企業ではまだ難しいなと感じていますが、そういうことにチャレンジできる会社は、もっともっと強くなる感じがします。
嶋田:グロービスの宣伝をするわけじゃないんですが、われわれはよく「志のMBA」と言っていて、「志」というものを非常に鍵に置いているわけですけれど。「世の中をこう変えたい」とか、自分が30年たったときに「あのとき、ああやってよかったな」みたいな、そういった志の高さというのを、ミドルの方であってもひとりのリーダーとして高く掲げることで、さっきもあった「人がついてくる」とか「その志に共感してくれる」とか、そんなことも起きるんじゃないかと思いますね。志というのもある意味、ある程度分解していけば、それを高く持つとこともスキル化できると思うので、ぜひ、そういったところも学んでいただければと思います。
本日、あっという間の短い時間ではあったんですが、このVUCAの時代、5つぐらい大きなトレンド、今日は触れきれなかったテーマもありますが、今後これに触れていきますので、そういった時代においてビジネスパーソンやリーダーがいかにあるべきか、今日はわれわれが話をしましたが、これは視聴されている皆様も、ぜひ自分ごととして、その中で自分はどういう生き方をこれからしていくべきなのか、何をすれば自分が生き残っていけるのか、そんなことをしっかり考え抜いていただければと思います。















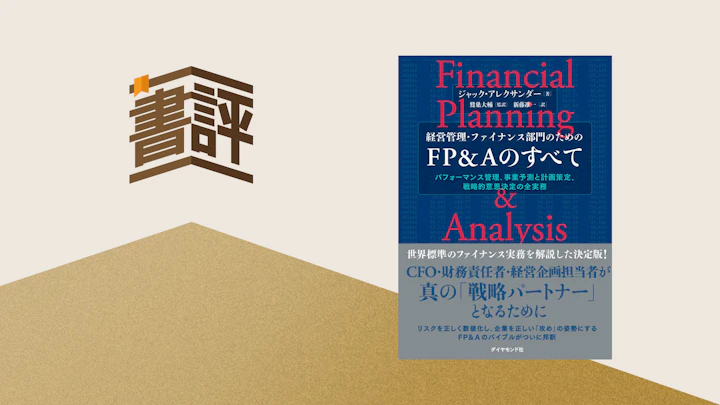


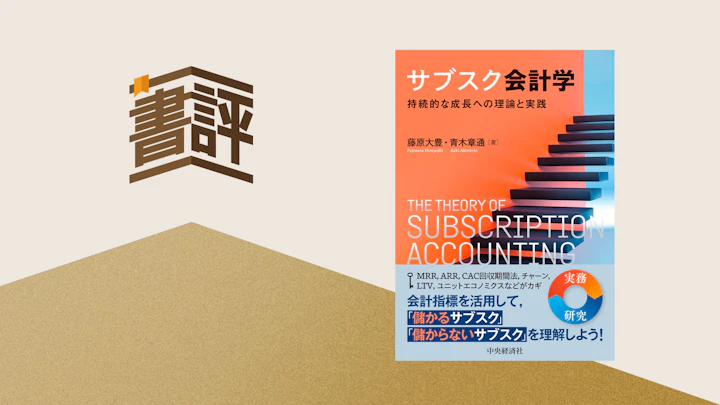



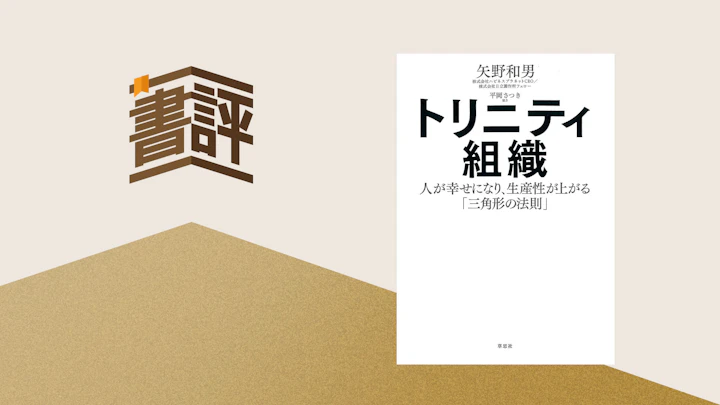












.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)






