G1ベンチャー2025 第4部 分科会【AI】
「AI×ヒューマノイドの可能性」青木俊介×尾形哲也×Shane Gu×島田太郎×川田忠裕
(2025年6月8日開催/グロービス経営大学院 東京校)
強化学習の非連続的進化により、米中欧で知能化ヒューマノイドが急速に実用化されつつある。そうした中で日本はどのように独自の強みを活かし、世界競争に挑むべきか。ヒューマノイド開発の社会実装や産業変革に向けた課題と可能性を議論し、技術革新の最前線から日本が取るべき戦略を展望する。(肩書は登壇当時のもの)
※タイムスタンプは生成AIで作成しているため、一部誤りがある可能性があります。あらかじめご了承ください。
05:00 ロボットの導入領域と可能性
通常のファクトリーオートメーションでは難しい領域へのロボット導入の可能性について議論する。
06:19 スタートアップの挑戦とヒューマノイド
スタートアップの立場からヒューマノイドの社会実装と挑戦について語る。
08:29 グローバルAI研究から見た状況
大規模言語モデル研究の最前線から見たAIとロボットの関係性を説明する
10:45 器用さの定義と実用性
ロボットの「器用さ」という言葉の定義と、実用性との関係を議論する。
15:53 スタートアップから見たロボット戦略
政府のロボット戦略とスタートアップへの支援について意見を述べる。
19:11 AIロボット協会の狙いと日本の強み
AIロボット協会の取り組みと、日本らしいロボット開発の方向性を語る。
20:45 中国・アメリカの蓄積と日本の課題
中国やアメリカのAI・ロボット分野の蓄積と日本の状況を比較する。
26:04 現場で感じる最大の壁
自動運転開発の現場で直面した最大の課題と解決策について話す。
28:10 AIとロボットコミュニティのギャップ
日本のロボットコミュニティにおけるAIとの価値観や認識のギャップについて語る。
30:08 ヒューマノイドの非技術的課題
ロボット普及における倫理や安全性などの非技術的課題を考察する。
33:30 日本の強みと今後の戦略
日本の強みである品質や感性を活かしたAI開発の可能性を議論する。
39:50 なぜ日本は社会実装に至らなかったのか
これまでの日本のロボット開発と、社会実装が難しかった理由を分析する
42:33 質疑応答と今後の展望
来場者からの質問に答え、熟練の技の転用やヒューマノイドの必要性について議論する。
44:59 質疑応答2:ロボットと宇宙の理解
言語モデルと身体性、宇宙全体の理解に必要な要素について議論する。
47:34 30億台のヒューマノイドは現実か
予測されるヒューマノイドの普及台数について、背景にある課題や日本の戦略を語る。
52:36 ヒューマノイドが解決すべきタスク
人型ロボットが最初に解決すべきタスクや、ブレイクスルーの可能性について議論する。
56:11 汎用性と社会的許容性
ロボットの汎用性と、それが社会に受け入れられるための条件について考察する。


%20(4).png?fm=webp)

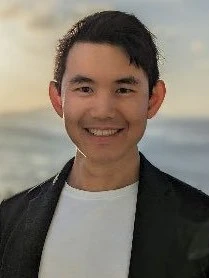
.png?fm=webp)





















.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)


.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)

.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)














.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)




