『異文化理解力——相手と自分の真意がわかる ビジネスパーソン必須の教養』を監訳した、グロービス経営大学院教員の田岡恵。ソニーの社員として1993年から20年にわたり9カ国に海外赴任し、『日本人が海外で最高の仕事をする方法——スキルよりも大切なもの』を執筆された糸木公廣氏。二人の対談を通して異文化マネジメントにおいて重要なポイントをお伝えしていきます。第3回は日本人海外赴任者が意識すべきことについて、具体的に語ります。(全4回)
多国籍企業に必要なのは共通のビジョン
田岡: 異文化への処しかたということで、我々日本を1としたときに、違う文化というのが百何十種類あるわけですよね。百何十カ国、世界にあって。例えば自分が日本人で、相手が全員アメリカ人ですという話であれば、日本対アメリカみたいな形で1対1の関係の物差しを使って相手に合わせてみるとか、1つの方法として処せると思うんです。けれど、多国籍の場合って、アメリカ人もいます、イギリス人もいます、ベトナム人もいます、中国人もいます、ハンガリー人もいますというところになると、誰がいったい、何に合わせるんだというのが悩ましい。物差しにプロットしてみてもみんな違う。実際、誰がどうしたらいいんだろうかというのが実務上の悩みだと思うんですよね。そういうコンテクストの中で言うと、特に自己開示って全ての文化の皆さんに一様に心を開く上で非常に効果的なのかなと。
糸木: そうですね。ただ程度問題は国によってあるような気がしますね。アジア圏ですと、非常に日本人のこの人に対して興味がある、家族まで含めて知りたいという感じはありますし、欧米ですと開示の仕方がそこまでいかなくてもいいような感じが。
田岡: トゥー・マッチ・インフォメーションみたいな。
糸木: なりますよね。
田岡: 多国籍チームでお仕事された経験で、1対1じゃない関係で、何かエピソードとかありますか?
糸木: これは、本当に苦労したことがありまして。ヨーロッパ本社のバイス・プレジデントという立場になって、あるプロジェクトを率いたときですけれども、12カ国のメンバーをまとめなくちゃならなかったんです。それもヨーロッパだけじゃなく、例えば東欧ですとか、チュニジアですとか、そういうところも入っていたんです。そうすると、1つの文化に対して理解をしてということを全部にするわけにはいきませんし、複雑なわけです。彼ら同士の対立関係だとか、エゴの張り合いというのがマトリックスのようにあるわけです。中には、「俺は日本人のボスにこれだけ言ってやったぞ」というのを誇りたいという気持ちもあったりするんです。
田岡: 例えば、どこの国の方ですか? 具体的に、言えればですが。
糸木: あれは、東欧の人だったかな。それは、一般化できないと思いますけど。
田岡: でも、日本でもよくありますよね。アメリカ人の上司に言ってやったみたいな。
糸木: 東ヨーロッパ人の場合、西ヨーロッパ人の前で、「俺はここまで言ったんだぞ」っていう形で、自分の株を上げたいという。
田岡: 東欧の方が、西欧の方に対して、言ってやったぞと。
糸木:ただ、一般化できるかどうか分かりませんけど。ですから、1対1の文化とか、人との向き合いだけじゃなくて、彼ら同士のものもあって、当初は上手くまとめられなかったんです。後半は上手くできるようになってきましたけど。
田岡: そうですね。例えば12カ国のメンバーがいて、1対1の関係で自分が全く違う対応の仕方、相手に合わせることを善意でやったにせよ、何となく八方美人に陥る。イコールこの人はいったいどういう人なんだという不信感に繋がるということもあり得ますよね。物差しの使い方で言うと、お互いの文化の違いや距離感を計るのに非常に便利な一方で、多国籍チームになると全く違う形で異文化に対してまとめていかざるを得ないと。その中で、糸木さんなりのご経験が何かありますか?
糸木: このままですと、多国籍チームはまとめるのが難しいというだけで終わってしまいますね。私がもう1つターニングポイントだなと思ったのは、やはり、ひとりひとりと個別に話し合ったり、オフでも付き合ったりする中で、個々を知っていくということから打ち解け始めましたね。そうなってきますと、彼らの態度が変わるのもそうなんだけど、打ち合わせの席なんかで出てくる意見の意味合い、重きというものが分かってくるんです。彼の発言はこういう意味合いで言っているんだなというのが分かってくる。それが1つですね。
もう1つ大事だったのは、当初、私が上手に示してなかったせいだと思いますけど、向かうべきビジョン、共通のビジョンというものをクリアにみんなの間で共有させるということだったと思います。それができたときに、ターニングポイントは始まったような気がします。
田岡: やっぱり、ビジョンの大切さというのは、異文化に関わらず日本の中でもありますよね。日本人同士でも認識の差、価値観の違いというのは、意外と異文化以上にあるという部分もなくもないので。国の文化が違うからこそ、その企業のビジョンであるとか企業文化で一つにまとめていくというのが、アプローチとしてはあるわけですね。なので、強烈な企業文化を持っている会社というのは、やっぱり海外に出て行く上で、すごい強みを持っているんじゃないかと。

私もグローバル企業の研修講師を担当させていただいていて。いろんな企業様からオーダーをいただいてマネジメント教育をさせていただいているんですが、特にグローバルに出ていこうとしている日本企業の現地のマネージャーの方のトレーニングを担当することが多いんです。実は、来週末からベトナムのホーチミンに行ってくるんですが、ホーチミンで教えるのは財務会計なんです。東南アジアに出ていらっしゃるリテールの企業様で、数年来担当させていただいていて。現地の店舗を管理されている、あるいは本部で管理業務に当たっている方々のトレーニングなんですけれども、財務会計なのに私の締めくくりはやっぱり企業文化の話になります。「皆さんはこの会社の方々だから、こういう価値観を持って、こういう意思決定をして、こういう結果を求めているんですよね。それは財務的な判断であっても同じですよね」と。
財務的な判断というのは、通常、戦略的判断に従うものですが、要はどういうふうに決断するかというのは、「あなたがこの会社の人だから、そういう決断をするんですね」と。すると、その場にいる10カ国くらいから来た方が「そうだ」と。自分たちはこの会社の人間だからそういう決断をする。これでいいんだと言って、納得して笑顔で終わると。多国籍企業になればなるほどそういった企業文化、それも紙に書いてあることだけではなくて、個人個人の心を掴むようなビジョンを持っています。それを聞くと自分の何かが震えるような、心にタッチするような何か、バリューを持った会社というのがグローバルでは強いなと思います。
糸木: 答えが難しいと思うのは、はっきりそれが出せる会社と、みんなシェアされている会社と、そうでないというのがあると思うんです。多分、いま田岡さんがご担当されている会社はそれがはっきりしていて、しかも現地レベルでもアプリカブル(適応できる)ということだったんですね。
田岡: すごくいいご指摘、ありがとうございます。なぜアプリカブルかというと、日本企業文化のコアって顧客主義なんですね。結局、自分が相対しているお客さんに対して、何が提供できるか、どうやって皆さんの生活を豊かに、幸せにできるかというところに紐づくので、結構どこの国の方も、顧客という接点でまとまれるというのが、日本企業文化の素晴らしいところかなと思うんです。
糸木: そういう場合であれば、それは素晴らしいと思います。ただ、必ずしも多くの会社で、日本の本社が抱えているビジョンなり理念というのが現地の人たちに理解しやすいかとか、あるいは、それを物差しにして果たして自分の行動基準を決められるかっていうと、必ずしもそうじゃないと思います。
本社の抱えている理念とかビジョンって、結構あいまいできれいごとだったりして、じゃあ現地人から見たらどうこれやっていいのという場合があるかと思うんです。だから、そこに赴任者の1つの役割があると思うんですけど、それを再解釈してあげるということだと思うんですね。そのハートの部分は理解しつつ、でも現場レベルでそれが生きなければ意味が無いし、それを再解釈して、自分なりのローカルビジョンというのを作ってあげることじゃないかと思いますね。
ビジョンもパーソナリティも可視化することが大切
田岡: そこで、今おっしゃったように企業文化が明示されているのか、されていないのかというところも、わりと日本文化のハイコンテクストな部分が尊ばれているところもあって、あえて言わないけれど、この一言で分かってほしいみたいな。あえて説明しないというのが結構ありますよね。
糸木: まさに、ここでおっしゃられているハイコンテクスト、ローコンテクストというのは、通常の個々のコミュニケーションだけじゃなくて、企業が発信している情報もやっぱりそうなんですね。日本の文化というのは、みんなが読んで、何となくイメージとして、いいでしょうと。でも現地の人には具体的に、それも言葉のレベルが具体的というだけじゃなくて、現地のマーケットとか状況で、本当にできるように、使えるように再解釈して伝えてあげるということがローコンテクストじゃないかと思います、クリアコンテクストというか。
田岡: 日本人のチャレンジの1つとして、ハイコンテクストなもの、我々が普段言わないことをあえて言っていくって大事ですよね。これは、日本の経営者の皆さんにとって賛否両論分かれるところかなと思うんですが。ハイレベルの経営というのは、言わなくても分かると。あうんの呼吸である。そこを察するところが実は経営力なんだとおっしゃる方もたくさんいらっしゃると思うのですが、『異文化理解力』を読み返しながら思ったのは、見えないもの、聞こえないものを見ろ、聞けというのは非常に酷な話であって、ローコンテクストの文化で育った方に対して、ほらあそこに、言外に見えるじゃないのって言っても見えないんですよね。それはもう、ほぼ意地悪に近い。確かに10年、20年その環境で過ごせば、いずれ見えてくるとは思いますが、グローバル化していく世の中では非常に一方的なリクエストであって。日本企業の明らかなチャレンジとしては、ハイコンテクストもローコンテクスト化していく、全部明示していく、これは怠っちゃいけないだろうなと。
糸木: おっしゃる通りだと思います。別な言葉でもう1つ補えば、やはり可視化ということだと思うんですね。見えるようにしてあげる。自己開示も可視化の1つですね。自分というパーソナリティを可視化してあげる。ビジョンをローカライズして、現地で分かるようにしてあげるのも、会社の企業理念の、ある意味では現場での可視化であるし。本社って、現地からずっと遠い存在なんです。だいたい、難しくてうるさいことって本社で始まって通達が来るんです、赴任者に。通常、郵便屋のようにそれを渡すということが多いと思います。本社がああ言ってる、やらなきゃいけない。でも、それじゃ現地の人は本当に理解してくれないし、納得してくれません。そうなると、それを再解釈して伝えるのも赴任者の役割だし、本社が言っているとしても、この部分はこの国では全然当てはまらない、その代わりこの部分はやろうという仕分けをするのも赴任者だと思うんです。
特に私が面白かった例というのは、本社で、ある販売会社に対する大きな変更があったときに私も呼ばれて。本社の大きい会議室で議論になるわけですね。帰ってきてその結果を伝えなきゃいけない。そのときに、決して皆さん真似しないでいただきたいと思いますけど、スマホで隠し撮りしたんです、会議の様子を。お偉いさん方がばーっと並んでいる。現地に戻って発表するときに、こんなことになったと。でも、これってすごく実はみんな悩みながら考えたと。その写真を出したら、こんな会議場に人がいて、この人はこういう意見を出して、実はこの人は反対したんだ、こうなってるんだ、そういう説明の仕方をしたら、みんなは割と受け入れてくれた。後からメールがきて、「ああいうところで決まってたんですね」と。赴任者や本社の人間はそれが当たり前だと思っているけど、現地の人から見たら遠い世界の出来事で、そこからいつも嫌な話とか、いい話もありますけど、来ると。なので、可視化するということはいろんな意味で大切だろうと思いましたね。

田岡: すごく共感します。私の仕事はビジネススクール、あるいは企業研修で教えることなんですが、日本人の方を対象にする場合と外国人の方の場合では、ちょっとやり方を変えています。
我々グロービスのMBAプログラムには、30カ国を超えるところからいらした学生さんが集まっているんです。なので、クラスの中でも少なくとも10くらいの国籍は常にある状況です。クラスでは先生というのはリーダーなんですけど、リーダーとしては、全員の意見を引き出して議論を深めなくてはいけない。日本人が対象のクラスと違って多国籍のクラスでまずやるのは、間違っていることを必ず「間違っている」と相手に明快に言うことです“What you said was wrong”というのを日本語で「あなたの言ったことは全然間違ってます」と言うと、多分、一生その日本人の生徒さんから許してもらえないと思うんですが、多国籍のクラスでは、曖昧に「うーん、そうですね」「そういう意見もあるかな」みたいなので受け止めてしまうと、「本当にあれであっているのか?」とみんなが途端に混乱してくるわけです。そうすると何が起こるかというと、リーダーである私に対する信頼が一気に失墜する。「この人は、間違っていることをこのままやり過ごすのか」と。議論はどこに行くのかと。放っておくと私の信頼が失墜するということで、多国籍の皆さんを相手にする私の仕事では、間違っていることがあったら、すかさずその場で、間違っているということが大切になります。
あと、結論に関してもかなりクリアに言う。私見であっても、要はこう思うということを結構文字に落としますね。見えるように。スライドの文字で見ると、みんなああそうかと。ちゃんと言うという責任を取ったことに対しては、割とリスペクトしてもらえる。他の文化では、ディスアグリー(同意しない)ということは悪いことじゃないんですね。「私は先生の意見とはアグリー(同意)はしないけれども、あなたがそれを言い切ったことに対して、あなたのプロフェッショナリズムを感じる。だから、あなたはいい先生だ」みたいな評価をされるんですね。なので、やはり多国籍チームを率いる中では、日本人としてはかなりローコンテクストにdecision(決断)のDというのを割ときっちりやることが、1つ自分の信頼を失わないという意味では非常に大事かなと思っています。
糸木: やっぱり、決断をするということが、自分なりに責任を取るということが、我々でもあると思うんで、それがやはり見えるということもあると思います。あと、決断の部分については、結論の決断と、手段の決断って2通りあると思うんですね。私がやったように、海外赴任で現地社員をまとめているときって、結論を先に見せてしまっていい場合と悪い場合があって、彼らに考えさせたり、彼らに参画させたほうが彼らの成長になったり、あるいは参画意識に繋がるということもある。その場合というのは、最初に結論の部分を決めないこともあるんです、あえて。ただし、手段を決めてあげるんです、はっきり言うと。
例えばちょっと面白い例で、韓国赴任中に若手社員がなかなか経営に参画しないということがありました。いろんな場面で、いろんなところにパーティシペイト(参加)させるようにしたんだけれど、地道にやっているだけじゃ、なかなかマインドセットって変わらないものなので、象徴と組み合わせたいと思っていたんです。そんなときに、たまたまオフィスの契約がもうすぐ切れる、新しいオフィスに移るということになったんです。通常、総務とマネジメントが一緒になって調べますね。6つくらい候補が決まった段階で、あとはだいたい条件をクリアしたから、この中から1つだけ選べばいいという状況だったんです。そのときに総務が「決めてください」って持ってきたんだけど、「これ、使えるな」と思ったんですね。これ、社員に決めてもらおうと思ったんです。
なぜかというと、彼らのほうが長く使うわけですよね、赴任者より。彼らのほうが、土地のプロファイルもよく知っているわけだし。何より、これこそ経営参画の1つを体験してもらえると思って。社員の代表を呼んで、「新しいオフィスに移りたいんだろう。これの中で、君たち決めて」と言ったら、「決められません」って最初言うんです。「自分たちがすることじゃない、そんなこと恐れ多くてできない」と。でも、「最終的な責任はどっちにしたって私なんだから、やってくれ」と言ったら、非常にその後は乗り気になって、全員でタスクフォースチーム作って非常にサイエンティフィック(科学的)に決めて、持ってきました。で、結論を持ってきて、やり方だけを聞いたら、こういうやり方で決めましたと。それは良かったので、「じゃあ、それでいいよ」と決めたことがあるんですね。こういうふうに、結論ありきの決め方だけじゃなくて、手段の部分を決めてあげるという決断の仕方もあるなと、そのときに非常に思いましたね。
田岡: 特に、韓国みたいに階層意識が高いところだと、普通は手段すら決められないというか。最後の決断はちょっと重すぎるけれども、途中のプロセスに関して関われる、決断に参加してもらうというのは非常に良いアプローチですね。
糸木: いずれの場合でも、どこかの部分で決断というのはしているということではありますし。
田岡: やっぱり、責任をきっちり取るということは、多文化でマネージするときの肝になりますよね。
糸木: みんな見てますよね。
田岡: 見られてますよね。リーダーとしてということですが。
※この記事は、2015年10月19日に行われた【英治出版×アカデミーヒルズ】『異文化理解力』出版記念トークイベントを元に編集したものです





















.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)
.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)
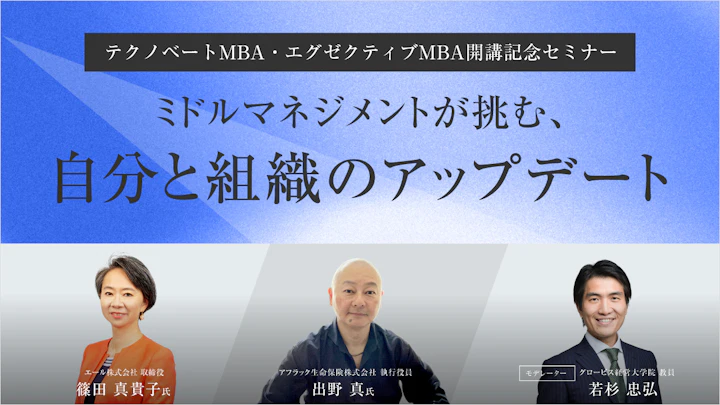
.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)


.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)

















.png?fm=webp&fit=clip&w=720)
.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)

