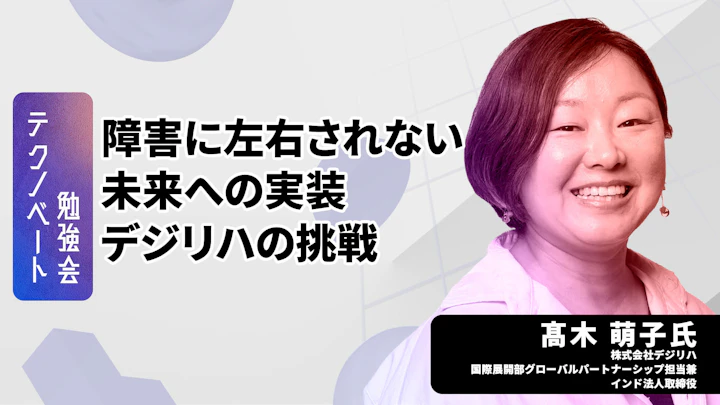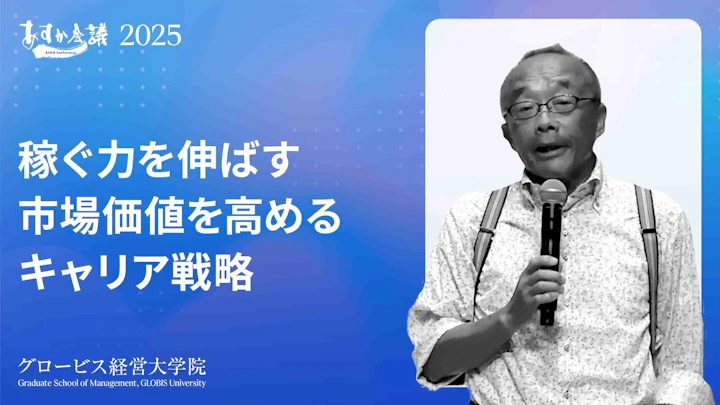G1地域会議2014 関西
第7部 分科会C 「世界を魅了する日本の食文化」Part2/3
2013年ユネスコ無形文化財に登録された和食。各地の個性溢れる風土が育んできた食文化を継承し、日本の生活文化として発信し、次世代に託していくために、何をするべきか。日本の食のキーパーソンたちが議論する(肩書は2014年10月19日登壇当時のもの。視聴時間24分10秒)。
辰巳 琢郎氏
俳優
徳岡 邦夫氏
株式会社京都吉兆
代表取締役社長
総料理長
原田 信男氏
国士舘大学21世紀アジア学部
教授
辻 芳樹氏(モデレーター)
学校法人辻料理学館 理事長
辻調理師専門学校 校長
【ポイント】
・味を決める基準はマーケット。こうしなければというものはなく、好きにやればいい。そこで淘汰されるものもある(徳岡氏)
・「本物」は時代と共に変わっていく(徳岡氏)
・中世までは、決まった時間に決まった場所で食べていたが、近世以降、料理屋が発達し、お金を出せば好きなときに食べられる自由な形になった(原田氏)
・武家の料理の作法は門外不出だったが、近世からは出版され、社会的に広まっていった(原田氏)
・江戸幕府により交通網が整備されて、コメを運搬するようになり、物資が動くようになった(原田氏)
・うなぎのかば焼きは「みりん」、寿司は「酢」のおかげで普及した。これらの工業化によって食文化が広がった(原田氏)
・成分の数値化を行い、おいしさを分析できるとがつくれると海外へのアピールも可能になる。加工して輸出して一次産業を活性化できる(徳岡氏)
・養殖技術を海外で再現できれば、ラスベガスで養殖ができ、輸送コストがかからず天然に近いお造りが食べられるようになる。それが日本の一次産業に還元されるといい(徳岡氏)
関連映像はこちらから
なぜ日本料理はコメ・魚が中心なのか 世界を魅了する日本の食文化 Part1/3
保守的かつ変わったものを望むのが食文化(原田氏) 世界を魅了する日本の食文化 Part3/3
























.png?fm=webp&fit=clip&w=720)


.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)