IOTが変えるスポーツ、家、ものづくり[1]
 佐々木紀彦氏
佐々木紀彦氏
佐々木紀彦氏(以下、敬称略):IoT(Internet of Things)はさまざまな分野に関わるので、本セッションでも幅広い視点で議論したい。ただ、今後は需要が爆発すると言われているIoTだけれども、そもそも何を表しているのか、今ひとつ分からない部分もあると思う。そこでまずは御三方にそれぞれ、IoTとはどういったもので、それらがビジネスをどのように変えていくと考えていらっしゃるのかを伺ってみたい。
小笠原治氏(以下、敬称略):以前から言ったり書いたりしているけれども、「モノのインターネット」という誤訳だけは止めて欲しいなと(笑)。僕は「物事のインターネット」だと思っている。物事とは、動作だったり、環境の変化だったり。で、それらのセンシングによるインプットを基にした、クラウドやアプリケーションのようなロジック層と、それをフィードバックするデバイスの組み合わせがIoTだ。そのロジックが継続的な商売になるから、今はインターネット側のプレイヤーが次々とIoTハードウェアの領域に入ってきているのだと思う。
 小笠原治氏
小笠原治氏
だから、根本的には「スマホのアプリ課金と何が違うの?」というのが正直ベースなところになる。ただ、昨今はハードウェアがつくりやすい環境になってきた。ここ5~10年でモジュール化が急速に進み、アリババやデジキーのように1個でもモジュールを買えるようになってきている。で、それが3Dプリンタ、あるいはキャッチ―なところで「メイカーズ」といった文脈と重なって、今はプレイヤーが増えている状態だ。この状況は15年ほど前のインターネットと似たような感じだと思う。
尾山基氏(以下、敬称略):企業の生い立ちを考えると扱ってきたものはラバーや繊維そのもので、ものづくりが中心。で、どうしてもITのあたりは弱いと感じていた。だからその点では大手とのアライアンスを考えている。そこで具体的には、たとえば下着状のウェアにセンサを入れることで、発汗状態をはじめとした身体の状態がすべて手元で、しかもリアルタイムで分かるようにする。これは医療関係にも転用できると思う。電波の飛ばし方次第だけれども、たとえば指にコードを差し込んでいなくても、センサによってすべて分かるようになるのではないか。
それともう一つ。お店で究極のパーソナル商品をつくることができるようになると思う。自動センサでスキャンをしたうえで、自分の体にあったサイズが手に入るようにしたい。現場はお店に商品でつくる機械まで置きたいと言っているが、スキャンデータを基にセントラルで商品をつくって3日後に配送というのもある。それで100%フィットした商品を提供することができるし、テンションをルーズにしたりハイテンションにしたりすることも可能だと思う。靴に関して、たとえばその人に合ったクッショニングのラバーをつくることだってできる。
 尾山基氏
尾山基氏
そんな風にしてITと製造を合わせたら、とてつもない、究極のパーソナル商品づくりができるのではないかなと思っている。それで一人ひとりにまったく別の商品を提供できたら、一種の産業革命だ。S・M・Lのサイズだけを大量生産して「それに体を合わせろ」と言っていたのに対して、一人ひとりの体に合わせてすべて異なる商品をつくるという、まったく反対のアプローチだ。そういう方向に行くと思う。
佐々木:どういうところとアライアンスを組んでいきたいとお考えなのだろう。
尾山:我々が弱いところは2つある。本体のIT部門はプログラムをつくる部隊だけれども、大事なのはその先にある最先端。こういうところにも一切出てこないような最先端を走る企業と、秘密保持契約を結んだうえでアライアンスを組みたい。あるいは、お互いに目的会社をつくり、そこでうちだけに製品をつくるとか。そういうことをして、なんとか最先端を取り込まなければいけないと感じている。
同時に、実はファンドを立ち上げてシリコンバレーに人を送ろうかとも考えている。ベンチャーの方に億単位で投資をしていこうかな、と。「それぐらいしないと情報は取れないんじゃないか?」と、ある弁護士事務所に言われて、「あ、そうだな」と(笑)。僕が昔アメリカへ行ったとき、シリコンバレーのベンチャー企業がプラスチックの補強材というものを提案してきたことがある。で、その打ち合わせでシリコンバレーにも数回行ったことがあるけれども、そういう新しいものが向こうにはたくさん転がっているんじゃないかと思う。そういうところから出てきたものを買うのでなく、ベンチャー投資もしながら一緒に先を取っていく。そうでないと、この世界では勝てない気がする。
佐々木:アシックスさんにはスポーツ工学研究所という歴史ある研究所もある。そうしたインハウスも大事にしつつ、オープンイノベーションも目指していく、と。
尾山:そこまでしないと情報が手に入らないと思う。そこで考えている投資先は2つ。一つはシリコンバレーで、もう一つは東京をはじめとした関東に絞りたい。まあ、メディカルのものは関西にあるし、そこもスポーツと健康の関係を考えると重要だから「どうしようかな」とは思っているけれども。ただ、とにかく我々としては、自分たちが疎いだけに最先端の情報が欲しいと考えてしまう(笑)。
 西條晋一氏
西條晋一氏
西條晋一氏(以下、敬称略):私は元々Wilというファンドに属していて、そこに出資いただいている大企業さんと、去年の夏前ぐらいから「オープンイノベーションを進めよう」という話になっていた。それに一番前のめりだったのがソニーさん。既存事業の改革を行いながら、新しいものもどんどん攻めるフェーズだったとのことで、今は一緒に取り組んでいる。
私としては、IoTは、ものづくりやソフトウェアやサービスをより有機的に連動させてくれるテクノロジーという風に捉えている。我々が今取り組んでいるスマートロックもそれにあたる。ただ、日本のIoTは恐らく、特に消費者向けコンシューマ領域ではアメリカから2年ほど遅れていると思う。アメリカのAmazonには‘Home Automation’というカテゴリに数千点の商品がある。でも、日本のAmazonや楽天には、そもそもそのカテゴリがないし、検索して出てくるものも大変少ない。
ただ、スマートロックについてはWilを一緒にやっている伊佐山(元氏:株式会社Wil Co-Founder&CEO)とアメリカのIoTを調べているときに知ったのだけれども、これにはもう一つ、別の背景がある。実は、僕は大家業みたいなことも少しやっていて、そこで空き部屋が出たとき、不動産業者さんの動きに無駄が多いと感じていた。また、内見情報が家主になかなか上がってこないこともあり、「これがあればすごく便利なのにな」と感じたことがスマートロックをやってみたいと思った背景だ。
そんな風にして、インターネットに何かデバイスがつながることで解決できる課題がある。僕も前職ではインターネット企業で、主にソフトウェアで課題を解決してきたけれども、IoTでさらにその可能性が広がるなと思ったし、それが面白いと感じた。恐らく多くのネット企業さんが、2年後ぐらいにはIoTデバイスを活用したサービスを当たり前のように展開しているのではないかと予想している。
佐々木:いろいろなIoT商品のなかでも、家やスマートロック関連が最も分かりやすいというか、IoTを広げるためのポイントになるとお考えだったのだろうか。
西條:家全体をインターネットにつなぐのは…、新築一戸建てならアリかと思うけれども、それ以外は少しずつやっていくのがいいのかなと思う。その意味でも鍵はすごく分かりやすいし、すでにニーズが顕在化しているところもある。実際、8月の発売予定だけれども現時点で4000人ほど買いたいという方がいる。そういう状況を考えると「家の中系」なら、たとえば監視カメラ、スマホでドアホンの応答ができるシステム、あるいはHEMS(Home Energy Management System)系とか、いろいろあると思う。
佐々木:お話を伺っていると、リアルとネット、ハードとソフト、あるいは人材面で、IoTによる融合が進むというイメージがある。また、今まで別々だった大企業とベンチャーが日本のなかでうまくつながって、世界にも広がっていく良いきっかけになるのかなとも思った。「DMM.make AKIBA」にもいろいろな人が来ていると伺っているが。
小笠原:そう思う。「DMM.make AKIBA」には、たとえば土日、自分で何かをつくりたいと思っている大手メーカーの方が若手起業家に会いに来ているような面もある。それで、僕のファンドでも出資させていただいている家電ベンチャーのCerevoという会社は、去年8月時点で13人だった従業員数が先月で53人になった。半年で採用されたその40人は全員大手メーカーさん出身の方々だ。スズキ、タカラトミー、パイオニア、ヤマハ等々、パナソニックとソニー以外からもいろいろな方が来ている。
そうした方々に共通しているのは一つ。「自分がつくったと言えるものをつくりたい。そういうものづくりに関わりたい」という願いだ。それで、平均では30%ほど年俸が下がっていると思うけれどもベンチャーに移ってきた。しかも、そういう方々は本当に優秀だ。40歳でR&Dしかやってきていない人もいる。大手メーカーの方は、実力はあるんだ。ただ、その研究にスポットが当たるか否かは半分運みたいなところもある。そういう状態から脱却して「小さな会社に移ってでもつくりたい」と。その意味では、大手メーカーにいなければ使えないかもしれない設備がシェアできるという利点が「DMM.make AKIBA」にはある。これも、たとえばインターネットのデータセンターができた頃と似ている。だから、どんどん人の流動化は進むだろうなと思う。
大企業はIoTでどう変わる?
佐々木:大企業にいる、特にハードウェアエンジニアの人はかなりフラストレーションが溜まっているものなのだろうか。
小笠原:溜まっているんじゃないですか? 所属しているあいだはなかなか言えないと思うけれども(笑)。辞める気80%ぐらいになったら文句をいっぱい言い出すか、品川あたりの居酒屋で文句を言うとか、どちらかじゃないかと(会場笑)。普通に考えて、ソニーに入ることのできる技術者の方って、すごいレベルだと思いません? 日本のいい大学に入って、いい研究室ですごい研究をして、それで大きな企業に入った優秀な人がモノを世に出せない。自分のつくったものを皆に使って欲しいからメーカーに入るのに。「それなら小さなところに行こう」と。特に、ソニーさんに関して言うと、自己満足欲求を満たせないことで辞めていく人が増えてきたと感じる。だからソニーから他の家電メーカーに行く人は少なくて、ベンチャーに移るケースが多いのかな、と。
佐々木:アシックスさんも西條さんのところも今はソニーとのコラボレーションで商品をつくっている。大きな企業とのコラボにはどんなメリットがあるのだろう。
尾山:2005年にSWATCHからコラボの話が来たとき、「ガーミンのようにGPSをつけて位置確認できないか」という話をした。で、我々の研究所ともいろいろ話をしたのだけれども、彼らはデバイスの会社は持っている一方、電波を遮断する技術はなかった。それで結局は止めたという経緯がある。それでガーミンとも話をしたのだけれども、彼らは「自分でやる」と。そのあとセイコーさんとランニングウォッチをやった。この辺に関して言うと、ナイキもアディダスも自前でやるということだけれども、当社はそこまでできないからアライアンスを組んでいく。たとえば、「MY ASICS」というサービスは2001年頃にオランダで開発したのだけれども、なかなか利用者が増えなかった。でも、需要はあるということで、いつの間にかソニーさんとコラボしていった。
ちなみに、ソニーの担当者は大変若い。オフィシャルパートナーを務めていた東京マラソンでマネージャーや店頭販売している方とお会いしたが、皆、若い。ソニーも昔とは違ってきているのかなと思う。あと、「MY ASICS」がソニーの「Smart B-Trainer」に入っているから分かるけれども、音は本当にクリアできれいだ。走らなくてもこれだけ聞いていればいいんじゃないかな、と(会場笑)。あと、彼らは若いけれども自信を持っている。ソニーは伝統的に大きなものを小さくする社風というか技術がある。それで、「こういうものができます」と言ってマイクロ化するところは、やっぱりソニーのDNAだなと思う。しかも、元々音楽に大変強いから音もきれい。だから、海外の企業ともやっていたけれどもソニーに戻ってきたという感じが、個人的にはしている。
佐々木:ソニー以外で注目していらっしゃるところはあるだろうか。
尾山:先ほど申し上げたたように、本当に先端の先端を行っているようなところと組みたい。とにかく、「どうですか?」ということで世に出てきたものを見てから考えるようなスピードでは勝てないという感覚がある。従って、一つにはファンドをつくってジョイベンをやっちゃおう、と。ファンドのオーナーという形でもいい。ある程度のデバイスをつくる企業とタイアップして、“もっと先”にあるものを取り込みたい。ソフトウェア系は当社も結構強いけれども、ITデバイスのエリアがすごく弱いので。そこで2~3人採用して強くするというぐらいなら、思い切ってBtoBで一気に組んだほうが早いんじゃないかなという気が、今はしている。
西條:去年は今回のアイディアを提案したのち、まずフィージビリティスタディという形で若手エンジニアの方に試作品をつくっていただいた。それで原理的にスマートフォンとハードウェアがきちんと連動して動作することを実証して、12月に平井CEOからOKをいただいた。それで正月明けぐらいから本格的に設計を行って今に至るので、スピード感はあると思う。これを自前でやっていたらもっと時間がかかっていたのではないか。少しずつ人材の流動化が進んでいるから大手メーカーさんを出た優秀な人材を採れるようになった。けれども、実施には採用だけでも1年かかるというか、下手をするとモノをつくるまでに1年半~2年かかっていたのではないかと思う。
それともう一つ。今は3Dプリンタもあるし、簡単に試作品をつくることができるような環境は整っている。ただ、量産化を視野に入れると状況が変わってくる。KickstarterやIndiegogoでお金を集めたプロダクトが出荷1年~2年待ちなんていう風に遅れてしまうのはなぜか。モノをつくっていると、やっぱり長年ものづくりをしてきた人だから気付く部分がすごくあるからだ。もしかしたら、そういうことがあるから若い技術者が下積みをするような構造になってしまっているのかなと思うが、いずれにせよ、ソニーさんに関していえば世界レベルでものづくりができる会社だ。
じゃあ、ソニーからどうして「GoPro」みたいなものがもっと早く出ないのか。理由はいろいろあると思うけれども、技術ではなく意思決定の問題がほとんどだと思う。「やるかどうか」と。ソニーさんと組む前、僕らは「カーブアウトして何かやりましょう」ということで、研究所へ行っていろいろなプロジェクトを見せていただいたことがある。すると、もう僕のようなモノが好きな素人が目をきらきらさせてしまうようなものばかりだった。シリコンバレーから今後出てくるだろうというような製品が、それこそ10年ぐらい前につくられていている。そういうモノがごろごろしている。
だから、「どうして出さないんだろう」と。ただ、ここ3~4年の話かどうかは分からないけれども、今は皆さんが思っている以上に、大企業はオープンイノベーションということを考えている。自社だけで進めるのでなく、外の力、しかもベンチャーを活用していこうといった動きがかなり出てきた。だからこそ、Wilも多くの大企業さんから出資いただけたのだと思う。だから、まずは門を叩いて、「こういう課題解決のためにハードウェアが必要なんです。一緒にやりましょう」と言うようなやり方が、スピード感を持ってプロダクトを世に出すという点では有効な手段だと思う。
佐々木:大企業もオープンイノベーションで取り込む戦略に変わってきた?
西條:ソニーさんは社内でも「アクセラレーションプログラム」という事業プランの社内コンテストみたいなことをしているし、外でも我々に限らずいろいろなところと取り組んでいる。オープンに進めようという意思を感じる。
佐々木:IoTで日本はアメリカに遅れているとのご指摘もあった。数十兆規模とも予測される同市場をリードするうえで、日本企業にはどんな課題があるのだろう。
尾山:西條さんがいいことをおっしゃったと思う。僕らとしては、たとえば60歳以上のエンジニアに、もっと生産ラインに入ってきてもらいたい。そうした人材へのニーズは急激に拡大しているし、当社では、たとえばOBで足らなければ生産に慣れた台湾の人材を採るように指示しているところだ。実際のところ、最近は生産ラインで不良が増えている。これは数量が増えているという理由もあるけれど、もう一つ、生産部門が中国から追い出されてアジア地区に移っていることも影響している。これは中国政府の意図だけれども、アジア地区は全般的に、中国と比べると“手”が下だ。
それともう一つ。今は若い人を次々採用しているけれども、本当に製造ラインを動かしたときになってミスが見つかることは多い。それで大量の不良品が、ロット単位でなく細かく出ている状態だ。これは過去に経験したことのない状況で、実はこの3年ほど、そうした状態に陥っている。従って、つくる前から熟練工を入れて、つくったときも彼らが現地の人を指導するとともにチェックも行うという、若い人と経験者のミックス型を今は試行している。若い人だけでは難しいところがあるし、やっぱり経験は重要。特に私たちのところはそうだ。いくらサンプルを3Dでつくっても…、うちも高い3Dプリンタを入れてはいるけれども、それが生産ラインに流れたとき、特にうちの場合はパーツが多いのでうまくできない場合が出てくる。
佐々木:世界3位のアシックスとして、先行するナイキやアディダスとはどのように戦っていこうとお考えだろう。特にIoTの部分でお考えを伺いたい。
尾山:今日はIRミーティングじゃないと思うんですけれども(会場笑)。最近はその点をよく聞かれるけれども、まあ、あそこまで大きな相手だと当面は難しい。ただ、いずれにしても同じようなことをしてはダメ。去年の秋に広島へ行ったとき、ある方に聞いたのだけれども、マツダの金井誠太会長は社長だった頃、「トヨタ、フォード、キャデラック、GEの車になるな」とおっしゃっていたそうだ。「あっ」と思った。だから、私も社内で「ナイキとアディダスの靴の真似をするな」と。言われたデザイナーは困ると思うけれども、それでデザインでも差別化したい。
あと、今はウェアが大変弱いのでM&A候補を探しているが、これは大変難しい。だから、人を採って自前でやっていこうかなと思っている。それでやっていけば2社にも近づくなという感じだ。で、そこから先はというと、重要なのはIT、製造の安定化、あるいはIoTだ。その辺はアメリカとのアライアンスで先へ進んだほうがいいと思う。やっぱり、アメリカをいかに日本へ取り込むかという発想のほうが、日本から出て行く発想よりもいいと思う。そのうえで、日本人の細かさとセンシビリティで勝負するという構造のほうがいいんじゃないかと考えている。

IoTにおける日本企業の課題は?日本の良さはどう活かせばいい?
佐々木:西條さんはIoTで日本企業にどんな課題があるとお考えだろう。
西條:IoTと言っても広いので産業用ビッグデータ等の話はちょっと置いておいて、デバイス系に関して私たちが取り組んでいることをベースにお話ししたい。ベンチャーの強みというのは、意思決定のスピードや小回りが効くマーケティング。ただ、ハードウェアに関しては大量生産することでコストが下がるという図式がある。たとえばゲームのアプリなら…、今はスマホゲームも高度化して大きなチームでつくるようになっているけれども、元々は1人でもつくることもできた。だから、アプリケーションに1人、サーバに1人、そしてデザインに1人の計3人であれば、立派な作品をつくることができるような感じだったわけだ。
ところが、ハードウェアでは話が違ってくる。たとえば、「Qrio Smart Lock」は1万5000円ほどで売り出そうとしているが、同じようなモノをつくっている国内の競合ベンチャーさんは値付けが倍ぐらい。通常なら、ある程度低い人件費とスピード感で、安いサービスを提供できることがベンチャーの強みになる。でも、そこにハードウェアが絡むと逆に高コストとなってしまう点がある。だから、アメリカのスマートロックもだいたい我々の製品より高い。「Qrio Smart Lock」は今一番安いぐらいだと思う。
従って、きちんとモノをつくることのできる仕組みをうまく活用すべきだと思う。特に日本企業のものづくりは世界一のクラスなので。で、そのほかに必要なのが、意思決定、アイディア、マーケティング、そして実行力だ。実行することができれば、とにかくモノをつくる能力は高いので世界にもかなり出すことができると思う。問題はやはり意思決定が遅い点。あと、いろいろな面でコストのかかるやり方を選んでしまっている部分もあると思う。最初から数十億~数百億の事業を前提にして、社内でも提案・意思決定がなされたりするので。でも、たとえば我々は、もうどうなるのか分からないような小さいニッチ市場から入る。でも、そうしたもののなかから、いくつかが化けていくこともあるわけだ。そんなことも踏まえて意思決定の方法を…、大部分はこれまで通りでいいと思うけれども、少なくとも一部は変えたほうがいいのではないかなと思う。
小笠原:IoTにおけるベンチャーやスタートアップの戦い方がインターネットビジネスと違う点として、価格勝負がしづらいというのはすごくあると思う。だから、たとえばCerevoは「グローバルニッチ」という言い方をしている。で、「20カ国で各国500個売れたらいい」ということで1万個つくる。そこは、たとえばハイ・アマチュアのように、高くても買ってもらえるゾーンだ。そうした、ゾーンが限られている代わりにスイートスポットはしっかりと開いているような領域を、いかに見つけるかが大事だ。そこで今言われた意思決定が重要になる。「ここを攻める。で、1万個だけつくるよ」と。「良いものを安く」ということでやっても、10万~100万個つくる領域では価格で勝てない。だから狙うところを間違えると死ぬという意味では、今までよりもリスクが高いと思いながらやってはいる。ただ、「一発、勝てる」というのは、倍率が上がっているような状態だから、僕としては結構面白いと思う。
佐々木:日本の良さはどのように活かすべきだろう。小笠原さんは「ものづくりの世界におけるエイベックスや吉本興業を目指す」といったお話をされているが。
小笠原:それでCerevoの岩佐(琢磨氏:同社代表取締役CEO)さんには「小室哲哉になってね」と(笑)。そういう人がいないと“次の安室奈美恵”が出ないから。だから、彼には盛大に成功するか失敗するか、どちらかにして欲しい。で、日本の良さに関して言うと、たとえば、元々絵を上手に描けない人が崩して描いた絵なんて、見れたものじゃない。けれども、ジャパンクオリティという壁は世界でも類を見ないほど高い。だから、ある程度はそれを崩して、そのぶん早く、あるいはターゲットに合わせたモノをつくったとしても、日本企業であれば一定のクオリティを担保できる筈だ。だから、大手企業でお金と時間がかかるつくり方をしてきた方々と、僕らみたいにインターネットで「えい」という感じでやってきた連中が混ざってはどうかと思う。そうした部分はアメリカより日本のほうがうまいと感じるから、その辺を強みにできたらいいなと思う。
尾山:2点ある。まず、ベンチャー的なスピリットをどう生かすか。私は海外にいた期間が長かったのと、ウォーキング部門で事業部長を10年やっていたこともあり、そのあいだ、ぐちゃぐちゃ言う人が上にいなかった。それで意思決定も商品決定もすべて自分でやっていたし、契約も自分で高島屋とか伊勢丹まで取りに行っていた。そういう経験があるから、社内で事業部をつくって上の人間にぐちゃぐちゃ言われるのなら別会社をつくる。そして10億の資本金を与えて、「これがゼロになったらアウトだよ」と。そこからインキュベーションさせてあげたほうがいいんじゃないかと僕は思う。そこに本体の取締役が2人ぐらい入っていれば、あとはぐちゃぐちゃ言わない。
とにかく僕は会社で保守本流を歩んでこなかったし、誰もぐじゃぐじゃ言ってくれなかったから(笑)、いろいろやれたし、ベンチャー的スピリットもよく分かるつもりだ。そうしてつくった別会社で、カルチャーも自分でつくればいい。よって、ベンチャーでしかできないことはないと思うし、その結果としてどこかの段階で統合してもいいとは思うけれども、走り出すときには別会社にしてあげるのがいいと思う。
それと、プライスについてもお話ししたい。当社は100ドル以上のランニングシューズで1位というか、かなりシェアが大きい。で、小笠原さんのお話を聞いていて思ったのだけれども、僕は40~60ドルの商品を出すことに恐怖心がある。そこの価格帯に落ちてしまうとブランドイメージも落ちてしまって、「拡販できたとして、それで何年間イケるの?」と。でも、100ドルで匠的につくり込んだシューズはシリアスランナーに受けるし、それはアメリカやドイツでも通じる。ただ、日本はというと、この20年間は「安いほうがいいだろう」ってな世界で、逆に勝負しにくいと個人的には感じていた。
従って、メーカーとしては、「数が少なくても高いもの」という世界から入っていったほうがやりやすいんじゃないかと思うし、その点で小笠原さんのお話に共鳴する。それでモノが良ければブランドイメージも自然と心に刻まれる。大きく宣伝しなくても、いい商品だということが心に入っていって、そこから横に広がっていく。それが、宣伝文句としては何も言わない、けれども商品が語るマーケティングだと思う。
→IOTが変えるスポーツ、家、ものづくり[2]は8/16公開予定
※開催日:2015年4月29日





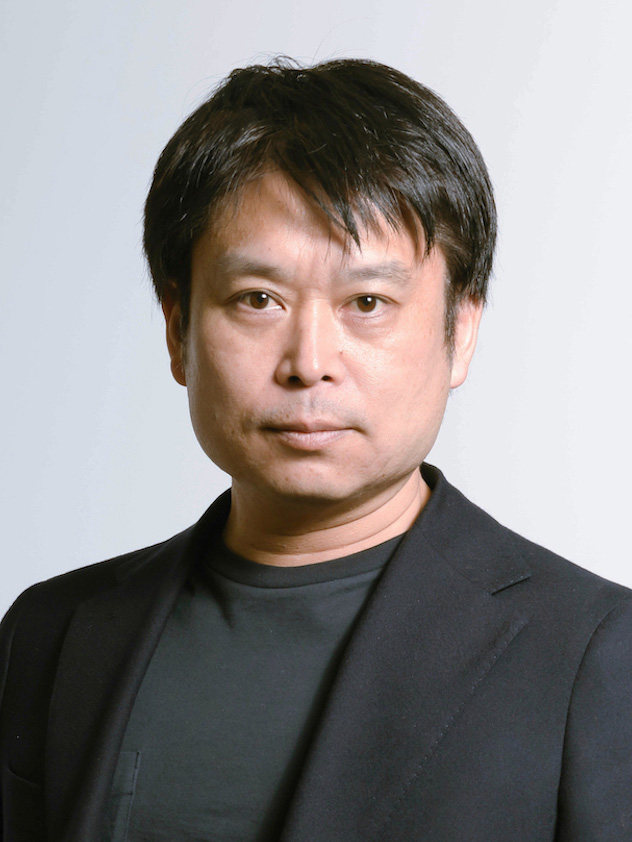





















.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)


.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)

.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)













.png?fm=webp&fit=clip&w=720)
.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)




