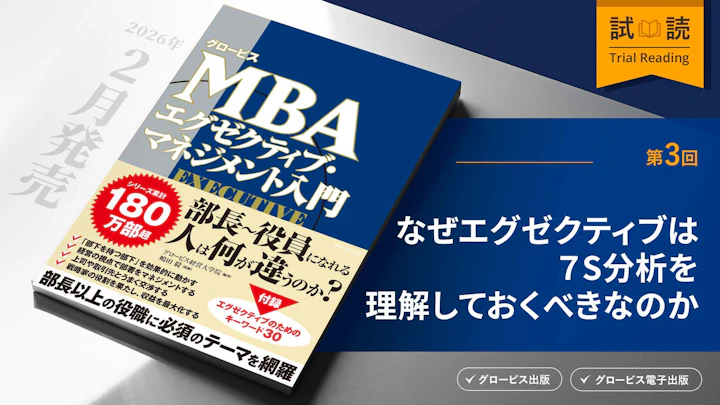世界を魅了する日本の食文化[2]
辻:では、次は江戸時代の革命を経て一気に現代へと話を進めたい。まず、江戸時代という260年続いた平和な時代、食はどのように変わっていったのか。特に、交通インフラの整備とテクノロジーの発展が大きな変化をもたらしたと思うが。
原田:日本における料理のあり方は中世以前と近世以降でだいぶ異なる。中世までの料理は、決まった時間に決まった場所で決まった人間が食べるものだった。しかし、近世になると料理屋が発達する。そこで、お金さえ出せば、予約は必要かもしれないけれども好きなときに食べられるという自由な形になっていった。また、本膳料理では武家の包丁流といったものができて、作法や料理法が書かれた料理書が成立していく。で、当初は門外不出であったそれらの料理書が江戸時代に入って出版されるようになり、お金さえ出せば料理の技術も分かるようになって社会的に広まった。
さらに、重要な変化としては交通網の整備がある。統一的な江戸幕府ができたため、輸送された米が大阪と江戸に集められるような交通網がつくられる。これは海舟だった。そして、やがて川舟も増え、毛細血管のように日本列島の各地へ入っていくシステムができていった。そしてもちろん五街道のインフラ整備も行われて、物資が活発に動いていくようになる。17世紀初頭に書かれた「毛吹草」という俳句の本には、全国各地の名産がすべて記され、情報としても分かるようになった。物も入ってきて、インフラの整備がなされていったわけだ。
また、工業的な生産も発達していった。たとえば鰻の蒲焼が一般化するためには、みりんが大量生産されなければならなかった。また、すしは元々米と魚を発酵させてつくるもので、これは東南アジアの稲作地帯であればどこにでもある。ただ、日本のすし文化がすごいのは、米に酢を合わせて寿司米をつくり、そのうえにネタ乗せて握りずしにした点だ。これも酢というものが全国で工場生産され、提供されていなければできなかった。もちろんお酒も同じ。そうした工業生産的な革命が江戸時代に進んで、江戸時代には庶民レベルまで食文化が広がっていった。その結果、さまざまな独自の食文化が展開していったと考えている。
辻:工場的な生産拡大が日本の食文化発展に大きく寄与していったのだと思う。ただ、その後は現代に到るまで、食品の工業化や交通インフラの整備が進めば進むほど、実は食の多様性や食文化の豊かさが衰退しているようにも見受けられる。
辰巳:食には本当にいろいろな切り口があって、本セッションの時間はあまりにも短いのだけれども、食文化というのは本来、人間が食いつなぐための対策から来ているというのが僕の理解だ。冬を越すために、秋に採れたものをどのように蓄えるか。大量に獲った魚を、不漁時に備えていかに保存するか。そういうことから来ていた。で、その心配が科学技術の発展によってなくなっていった。飢えとの戦いがある種の文化をつくってきたと考えるなら、その必要性が薄れたこと自体は仕方がないと思う。逆に、そういう部分とは違う文化が加わるんだろうなという感じがしている。その辺の文化というのはすごく幅が広いので、もう少し分けて考える必要があると思う。
辻:食文化の多様性を守るため、技術者としては何ができるとお考えだろう。
徳岡:基準みたいなものをつくることができないかなと思う。そこで科学者の方々とも連動して、たとえば成分やその含有量を数値化していく。それによって、なぜ美味しいのかを分析しながら基準を決めていく。我々はそこでお手伝いできると思う。数値に加えて経験値としてそこでコメントをさせていただくことができるのかな、と。
たとえばお米のランク。今はなんとなく雰囲気で「魚沼で誰々さんのつくったものがいい」という風になっているけれど、実際は天候条件等が毎年変わる。従って、毎年特定の同じ場所でつくられたこしひかりが日本で一番美味しいということはないと思っている。そこで理論的な数値まで考慮して、その基準をつくるのは一つの有効な手段だ。それで美味しさを理論的に説明できたら、海外の方々にもアピールもできると思う。僕自身はその基準づくりと、その一次産品を加工して流通に乗せる段階でお手伝いができると思う。技術を提供することで、一次産業の活性化に貢献したい。
そうすることで、日本中の、もしくは世界中の人々が欲するようなものを一次産業から生みだすことができると思う。それを、一次産業に従事する人たちとともに海外へ行って、新しく育てるというやり方もある。たとえば何も価値のないような土地を外国で買って、そこで高級食材を育てていく。それができたら不動産価値が上がるから、その不動産を再び、今度は栽培ノウハウごと買い取ってもらうという方法もある。
また、漁師さんを海外へ連れていって日本でしか食べることのできないぴちぴちした魚のお造りなんかを海外で普及させるというのもある。そこで技術者として…、もちろん漁師さんがいないとダメだけれど、海外では生の魚を食べる習慣が少ないから、それを各地のトップシェフたちに伝える。それで美味しく食べる技術を知った各地のトップシェフが生の魚を扱ってくれたら、その土地のセカンドあるいはサードシェフもその真似をするようになる。それで、魚を生で美味しく食べることが新しい価値観としてその地域で常識になっていく。そこで、ケミカルな理論的根拠とともに美味しさをプレゼンできれば新しい市場ができるし、漁師さんも海外で仕事ができる。
活躍できるのは漁師さんだけじゃない。今、日本国内では山のなか(の淡水)で高級魚やあわびを養殖できるような技術も発達している。養殖によって、たとえば砂漠で天然に近い状態のものを育てることができる。そこで水圧や日照条件を調整できるような養殖技術があれば、ラスベガスでも養殖所ができる。ラスベガスで大きな市場の横に養殖所ができたら輸送コストも掛からない。それで電話1本で締めて、ちょうどいい時間に、天然に近いマダイのお造りが食べられるようになるかもしれない。
その利益を、一次産業の現場に従事する日本人に還元できるような仕組みができたら、産業全体が活性化すると思うし、そういった仕事が憧れの仕事にもなると思う。そういったことの積み重ねで日本全体が元気になっていくのかなと思うし、私としてはその部分でお手伝いができると思っている。

辰巳:今のお話にあったような分野に投資することも大切だと思う。ただ、一般的な日本人は、たとえば東京にいる人も大阪にいる人も普段はそれほど美味しいものを食べているわけでもない。また、今は日本人の食生活や健康が乱れているし、米の消費も今は往時の半分にまで減っている。だから、そのあたりをもう少し整えてから外に出るべきかなという感じもしている。
地方の食を活性化させるためにはどうすればよい?
辻:江戸時代は地方が江戸を支えていたのか、それとも江戸が地方を支えていたのだろうか。また、今後は国が地方を支えていくような時代ではないだろうか。
原田:江戸時代も幕府によって社会が運営されていたけれど、経済の実態としてはむしろ生産者側が大変な努力をしていた。たとえば、江戸といえばそばとうどんが有名だし、当時から移動式の立ち食い屋台があった。そこで、武蔵野では米ができなかったために大量の蕎麦と小麦をつくって、大量の蕎麦を江戸に搬入していたわけだ。水車もつくったりして、現地で粉にしたうえで持ってくるという商人もいた。
また、江戸の周りには名物野菜が多かった。練馬大根や谷中生姜や小松菜といった作物は、江戸の市場を強く意識したものだ。農民たちが「これなら売れる」というものを開発し、村の名産として売り込んだ。そんな風に、むしろ下のほうから変えていった部分がある。さらに言えば、たとえば八尾善という有名な料理屋では旬の先取りをしていた。つまり促成栽培だ。障子に油を塗ってビニールハウスにして、そこで栽培したものを料理屋に売って儲けていた。江戸というニーズを見据え、江戸周囲の人々が下のほうから食というものを豊かに支えていたというのが現実だと思う。
辻:大都市近郊でも創意工夫によって価値を創出している人々はまだまだまだいらっしゃるのだろうか。
徳岡:たくさんいる。また、今は輸送の技術も冷凍技術も向上している。たとえば、アビーという会社はマイナス30度にしながら凍らない技術を開発しているし。凍らせてしまうと細胞内の水が膨張して細胞が割れてしまうのだけれども、その技術であれば凍らせないまま輸送できる。これは医療に採り入れることもできるだろうし、いろいろな可能性がまだまだあると思う。また、国内マーケットでもできることは多い。養殖技術がグレードアップすれば値段が下がるかもしれないし、コンビニでも食感が良く天然に近い状態の魚が買えるようになるかもしれない。
辻:今、国内には大きな問題がある。40数年後には多くの市町村がなくなっているという推計もある通り、人口減少問題は避けて通ることができない。人口が減少し、市町村が統合していくと、食文化や食の技術が失われてしまうのではないか。これは大変な課題だけれども、大都市への一極集中が進行する現代において、それは回避できるのだろうか。また、回避するためにはどうすべきだとお考えだろう。
辰巳:基本的には多様性が文化を豊かにしていく。しかし、たとえばミシュランもそうだけれども、食に点数をつけるというのは一方向の価値観で行われるものだ。レシピを分析して数値化するというのもそうだけれど、一方向性でやることに大きな危機感がある。食という官能的な要素のある分野では、ある程度は行うにしても、すべて同じベクトルで点数をつけるということ自体、まず止めるべきだと僕は思っている。
また、たとえば東京にいれば日本全国のものや世界のものが食べられるということが幸せなのかどうか、と。「本当にそこまでする必要あるの?」と思う。京野菜食べるなら京都に来ればいい。逆に「京都の野菜を表に出すな」というぐらいだ。イタリアはその辺が徹底している。僕はイタリア20州をすべて周ったけれども、パスタ一つとってもすべての地域で違う。それぞれ、独自の野菜やワインがある。そういうものが豊かさなんだという認識が必要だと思う。東京で金を出せばなんでも食えるというのは、実はすごく不幸だということを、僕はもっと言っていこうと思っている。
徳岡:たぶん両方必要なのだと思う。一方では教育したり伝えていったりするうえで、理解されやすい基準みたいものがベースとして必要だ。そういうこともあって、辻調理師専門学校も存在しているのだと思うけれども。もちろん、授業で教えていることが日本料理のすべてではない。ある程度の基準やベースがあるから多様化していくとうことだ。つまり、両方ないとダメなんだろうと思う。また、そのベースとなる部分の教科書自体も、多様性のなかで更新していかないといけない。同じ教科書のままではおかしくなってしまうと思う。あと、地方が消滅してしまうかもしれないという懸念については、「まあ、仕方ないかな」と思う部分がある(会場笑)。結局、守るべきなのかどうかを考えていく必要がある。ベースの部分があって、それを知ることができる環境をつくってあげれば…。
辰巳:それは本当に難しい問題だ。たとえば、今はいろいろな動物が絶滅している状況で、どんどんワシントン条約のレッドリストに載っていく。では、それらは守るべきものなのか、と。食文化でも同じ議論があると思う。
徳岡:それと、お金出して守るのではなく、自立できるように環境を整えてあげるということも必要じゃないかなと思っている。
原田:食文化の勉強をする前、私は村落史という村の歴史研究を専門にしていた。それで日本各地の村を訪れて歩いていた時期がある。そうして見てみると、やっぱり村ごとの特徴があるし、そこで育まれた文化がある。また、かつては地方のほうが文化的にも優れていた面がある。でも、明治以降は村にいた知識人が大学へ進むようになって、どんどん東京や京阪神に出て行ってしまった。で、その人々が帰ろうとしても、今度は地方に仕事がない。そういう流れが行き着くところまで進んだ結果、現在のような状況になっているのだと思う。
ただ、私がそのなかで最も強く印象に残っている村人の話がある。それは、「地球の中心はここなんだ」というものだ。自分が立っているところが地球の中心だ、と。その方は、そんな風にして郷土に誇りを持っていた。本来は、そういうところで文化が培われていくのだけれども、これは今辰巳さんがおっしゃった動物の話と同じだ。そういう環境で、どれだけキープして状況をつくっていくか。
これは政治レベルの問題でもあるし、いろいろなレベルで議論していく必要があると思う。企業レベルでも住民レベルでも、意識や取り組みが課題になっていく。で、国や地方自治体としては、それを保証するような政策を組み立てていかないと、本当に自治体が消滅することになりかねない。この問題についてはかなり強い意識と危機感を持って、官民両側面から取り組んでいく必要があるのではないか。そういう形で地方を守らないと、日本文化そのものがなくなってしまうと僕は思う。

日本の食をどのように海外へ発信していくべき?
辻:最後に、日本料理の海外発信についてコメントをいただきたい。「日本料理をどうやって世界に発信していくか」といったことは、僕も内閣府等でいろいろ聞かれる。それで、だいたいは「日本料理の枠組みを変えなきゃいけないね」といった、先ほどの話に戻るわけだ。では、どうすればその枠組みを変えていけるのだろう。
徳岡:先ほどワインに合う日本料理という話をしたけれども、今は世界的にもフレンチやイタリアンといったカテゴリがなくなりつつある。で、世界中で料理人個人の料理ということになって、いろいろな要素が入り混じってぐちゃぐちゃになっている。従って、マーケティングではないけれどもそこで差別化できるほうがいい。「ほかの料理とはまったく違うね」と、ぱっと見て分かってもらうのが得策ではないかなと思う。
その意味では、僕らは純粋な日本料理に見えるようなものをつくっている。たとえばバターを使ったりはするけれど、基準の話は抜きにして、ぱっと見て「あ、日本料理だな」と。そして食べてみて、「あ、日本料理って美味しいな」と思ってもらえるようなものを今はつくっているし、そうすることでお客さまも増えている。あと、海外出店は、今は考えていない。現時点でもある程度は世界で名前が知られているので、海外に出店する意味もあまりないし、それによって大きな利益を得られわけでもない。
それよりは、もっと手軽に文化的なものというか、本物を味わってもらえるよう、物販に力を入れていきたい。本物の醤油や出汁、もしくはそれを使ったお惣菜を、手軽に味わってもらえるような物販。そのノウハウが溜まった段階で海外に出店したいと思っている。たとえばナパバレーに出店して、当地の習慣も採り入れながらバランスの取れた商品を開発して、それをニューヨークで売るような仕組みをつくりたい。また、そこで日本の食材が必要になるので、農家さんや漁師さんと一緒に海外へ行く。料理店に対する提供でなく物販向けの食材ということなら、ある程度のロットもキープできるから、農家さんや漁師さんとしても仕事になるのではないかなと思う。
辰巳:クラシック音楽がなぜ最高級の音楽として世界に広がったかというと、楽譜があったから。世界中の音楽で楽譜があるのはクラシックだけだった。皆で賛美歌を歌うため、楽譜を発明した。五線譜のような分かりやすいものにして、全世界で使えるようにしたわけだ。そういう基準みたいなものが日本料理にも必要だと思う。いまだに呼び方や発音一つとってもばらばらだけれども、それをある程度整理して分かりやすくする。そして海外の誰が見ても理解できるようなものにして、世界へばらまく。そのための基準が必要だと思う。僕はやっぱり日本料理が一番美味しいと思うし、もっともっと発信すべきだと思っている。国家戦略としてもそれをきちんと後押しして欲しい。今は、誰もが理解できるような体系をきちんとつくって広めていくという努力があまりにも足りないのではないかなと思う。
原田:食文化の研究をしていると、食文化にはいくつかの特徴があると感じる。一つ顕著なのは、食文化というのはかなり保守性が強いという点だ。食べ物は急に変えられないという面があるから。ただ、その反面、革新性もある。急に変えられない一方で、変わったものを食べてみたいという、相反する気持ちも、個人の差はあっても皆が持っているから。そうであるなら、食がずっと同じということはあり得ない。冒頭でお話しした通りで、日本料理というものはかなり新しいものだし、歴史のなかでできあがってきたものだ。従って、今後も食文化はどんどん変わっていくと思う。
辻さんのハイブリッドというのはすごくうまい表現だと思う。そんな風にしていろいろな技術や素材を採り入れて、少しずつ変わっていけばいい。やはり慣れというものがあるから、外国の方々も食べているうち、だんだん美味しさが分かってくると思う。歴史の変化を踏まえたうえで、より新しく美味しいものを生み出す努力を続けていくことが大事なのではないか。
辻:では、会場との質疑応答に移りたい。
会場:海外での物販には大きな可能性があると感じた。物販によって海外の家庭でも広がっていく可能性があると思う。そこで、物販にしていくのは本格的な料理のほうだろうか、あるいはインスタントのような感じになるのだろうか。
徳岡:両方になる。本物だけを使った高級惣菜のようなものに加えて、ちょっとリーズナブルなものや90日間保存できるようなものもやろうとしている。それが海外でもできると思う。日本とまったく同じではないけれど、日本の要素を採り入れていくし、基本的には健康と美容というテーマがあれば海外の人は飛びついてくるので。富裕層の方々が健康のために日本まで来て食べているようなものが、海外で求められているように思う。我々としては、それに加えて先ほどお話しした基準を含め、「何が良いのか」ということも発信してく。それによって、より広がっていくと思う。また、そのベースがきることで、さらに上へと積み上げやすくなっていくと思う。
ただ、「日本料理が世界一になる」といったことではない。地域の人たちのニーズや文化も大事だ。それらと融合しながら、その国の食文化を一緒につくることができたらいいのではないかなと思う。そのなかで、日本の技術とか考え方、あるいは日本人気質みたいなものが世界で役に立てばと思っている。
会場:食を活用した地域の新しい活性化として、今後はどんな取り組みが考えられるだろう。地産地消とはよく言われるけれども、これはもう使い古されていて、当たり前という感覚がある。その次に来るような取り組みがあればお伺いしたい。
辰巳:B級グルメは一つの要素だと思う。B級グルメ自体の安さや旨さも大事だけれど、とにかく地元の食材を使っているものが多いので。そういう部分からやっていかないといけないのだと思う。今は学校給食で使われる食材の多くが中国産だったということがどこかの雑誌に出ていたりしていたけれども、食材のトレーサビリティみたいなことも分かりやすく打ち出していく必要がある。それが、地方できちんとこだわって食材をつくっている生産者の方々を守ることにもつながると感じる。

徳岡:コラボというのが一番早い。一次産品を加工して、広く楽しんでもらう。楽しんでもらうから、そこに行きたくなるわけなので。そういうことを一次産業の方々とも連携しながらやっていくのが一番早いと思っている。
会場:日本のワインをEUに輸出しようとしていたことがある。私たちはそこで「甲州」というブランド名で、アルファベット表記を含めて統一し、それを国際的ワイン機関に登録するところまでやっていった。そこで日本料理の定義について感じるのだが、「日本人がつくった海外にない料理」という定義に、海外でPRするためのポジティブな定義づけを加える必要があると思う。「天ぷら」や「すし」といった具体的料理名を列挙して、知らない人にも分かるよう、ポジティブな定義づけが必要ではないだろうか。
原田:たとえばカリフォルニアロールはどうなるのだろうという話になると、あれは、まあ、ベースは日本だけれども、つくっているのは向こうの人だ。だから準和食というようなことになるのかなと思うけれども、むしろ私が言いたいのはそれでがっちりと定義づけをしましょうということではない。それをベースにして広めていくような取り組みと、定義の問題は分けて考えていただいたほうがいいと思っている。
辻:時間になってきたので簡単にまとめさせていただきたい。日本食文化の問題点はあまりにも多岐に渡っているので、本セッションだけでは議論の時間も到底足りないと思う。ただ、たとえば京都の魅力も含めた日本食の文化は、国内または世界で、もっとしたたかに発信すべきだと思う。あまりにも真面目に「日本料理はこうあるべき」という風にせず、日本の食文化が持つポテンシャルや柔軟性をどんどん発揮して問題を解決していきたいと思う。今日はありがとうございました(会場拍手)。
※開催日:2014年10月18日、19日



































.png?fm=webp&fit=clip&w=720)
.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)