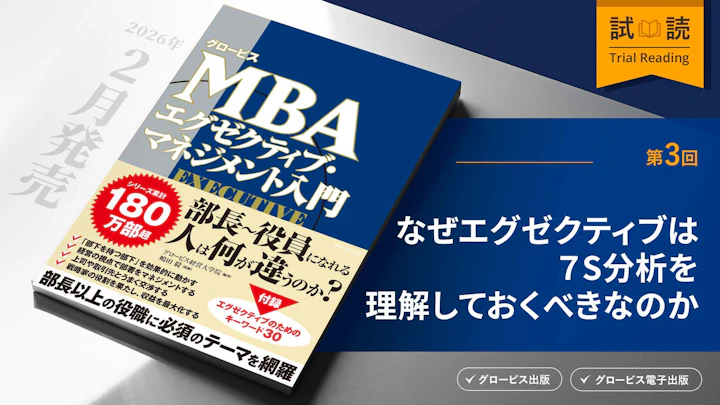世界を魅了する日本の食文化[1]

辻芳樹氏
辻芳樹氏(以下、敬称略):本分科会では日本食のパワーについて考えていく。まずは日本の食文化が持つ本質について、4つのパートに分けて議論しよう。そこで、それぞれ原田先生に歴史的な観点のお話を伺って、そこから現代に視点を戻して徳岡さんと辰巳さんにご発言いただく形にしたい。従って、過去と現代を行ったり来たりするような話になると思う。まず、パート1では日本の主食と言われる米について。そしてパート2では日本の食文化の歴史をハイブリッドという視点で、古代から中世そして近世にかけて一気に見ていきたい。また、パート3では現代の諸問題を考えるうえで、江戸時代をモデルとして見ていこう。そしてパート4はまとめということで、地方の再生をはじめとした各問題に関する皆さまの提言をいただきたい。
はじめに日本の食文化を歴史的な側面から見てみよう。まず、大陸からやってきた稲作文化が日本に定着し、中国の影響を受けながら宮廷料理として大饗料理が生まれた。その後、武家の料理として本膳料理が生まれ、さらに精進料理、そして禅の精神性も含む懐石料理が生まれていった。そうして室町時代には食事スタイルとしての日本料理が完成したと言われている。さらには江戸時代になると商人という新しいプレイヤーが参加して、多様性に溢れた食文化が育まれていった。今日は日本の食のパワーを考えるうえで、そうした日本の食体系や食事システムのユニークさがどこから来たのかということを議論していきたい。
まずはパート1ということで、米と、そして魚を中心とした日本の食事体系について原田先生にお話をしていただきたい。なぜ、米が精神的に日本の象徴のようになっていったのだろう。国家の経済や政治でも米が大きなテーマとなっていたことがある。その背景や、米に対する執念についてご解説いただきたいと思う。
日本の食文化はどう形作られた?

原田信男氏
原田信男氏(以下、敬称略):日本人の食生活というと、米と魚は頭から離れないというか、当然のものだと思われている。我々はその点を他国の食文化と比較しながら見ていく必要があると思う。まず、米ともう一つ、重要な主食として麦がある。ただ、小麦の文化と米の文化は、実は対照的で地域もきれいに分かれている。麦の栽培にはどちらかというと寒冷乾燥な地が適している。従ってユーラシア大陸を斜めに切って、その西北で小麦文化が発達した。また、小麦の文化には牧畜がくっつくから、ミルクと肉がセットになる。それが、今日我々が目にする西洋食にもつながっている。イスラムの地域も同じだ。そうした小麦とミルクと肉の文化がある。
で、その対極に米の文化がある。米は小麦とまったく逆の性質で、温暖湿潤な環境を好む植物だ。そのため、いわゆる東南アジアでアジア・モンスーン地帯と言われる、大量の雨の降る地域で米文化が発達していく。日本はその一番東の、離れのところに位置している。で、米の文化というと田んぼが最も象徴的だけれども、当然ながら水がなければいけない。そして、水があるところには魚がいる。だから米食地帯では米と魚が必ずセットになっている。カンボジアあたりでは田んぼの真ん中に大きな穴があって、そこに網が仕掛けてある。米をつくりながら魚を獲っているわけだ。似たようなものは日本にもある。
そこで魚を発酵させた魚醤という調味料もできた。それを大豆に変えたものが味噌・醤油だ。そのようにして、米と、魚醤もしくは穀醤という調味体系ができあがる。ただし、魚だけでは動物性たんぱくが少し足りないので、稲作地帯では必ずと言っていいほど豚を飼っていた。簡単に飼えるためだ。トイレで飼われることが多く、人間が輩出したものを食べてくれるから、あとは残飯みたいなものを放り込んでおけばだいたい育つ。だから稲作文化圏では米と魚と豚がセットで定着している。
この違いが一番分かりやすいのは中国だ。北のほうは小麦文化で南のほうは米文化。だから北京料理では饅頭や餃子や麺、そして羊や牛の肉が食される。一方、南の広東のほうは豚肉料理、鯉の丸揚げのような魚料理、あるいはチャーハンやお粥といった食文化になる。そんな風に、きれいな対象性がある。
で、日本には2000年前の弥生時代に稲作が入ってきたわけだけれど、そのときには豚も飼っていた。ただ、そこから少しずつ、「どうも動物を殺すと稲作がうまくいかなくなる」といった信仰が生まれ、それで古代律令国家の指導者たちは肉食を禁止していった。当然、そこには仏教の影響もある。ただ、私はそれ以上に、米をいかに育てるかが重要な問題として捉えられ、そのために肉食が禁止されたと考えている。それで豚が食生活から消え、そのぶん動物性たんぱくとして魚に集中していった。
なおかつ、我々は非常にデリケートな米のなかでも一際デリケートな温帯ジャポニカという米を選んで食べている。この米は、熱帯ジャポニカのような他の米よりもはるかにデリケートだ。田んぼをつくって水の管理をして、温度の管理までしないと育たない。農民たちはそういった点で常に心を配り、国家のほうも肉食を禁止してまでも米に集中してきた。育てるのが大変難しい米を、まさに愛着を込めてつくりあげてきた。ある意味、日本にはかなり特殊な米文化があると言えるのではないか。
辻:そうした歴史を経て水田耕作の技術が進み過ぎたため、現代の日本ではどの地方でもコシヒカリ一辺倒になって多様性が失われつつあるように思う。この点、徳岡さんはどうお感じだろう。

徳岡邦夫氏
徳岡邦夫氏(以下、敬称略):まあ、仕方がないんじゃないですかね(会場笑)。育てやすさもあるので。よく言っているのだけれども、何かが残るということは、その環境で必要とされているからだと思う。積極的に守ることで残るものあるけれど、特定の食生活や食文化は必要とされる環境で人気を得ていくのだと思う。
ただ、コシヒカリ一辺倒とは言っても、現状では気候の変化もあって…、温暖化が関係しているのかどうかは分からないけれども、たとえば北海道でもコシヒカリ以外のいろいろなブランドが出てきている。その意味では多様化しているし、値段や美味しさの競争を経て、残っていくものが残っていくという話だと思う。
辻:お米にはまだ多様性が残っていると。
徳岡:残っているし、これからいろいろ出てくると思う。
辻:辰巳さんにも同様の質問を、今度は野菜に関してしてみたい。地方色豊かな品種の多様性が、こちらも失われているように思うが。

辰巳琢郎氏
辰巳琢郎氏(以下、敬称略):食文化については、日常の食と文化としての食を分けて考えなければいけないと思っている。手のかかるものをつくったり、昔のものを発掘したり、あるいは歴史や文化を残していこうとするとコストが合わないことはある。でも、日本が豊かになってきたからこそ、コストが合わないこともできるようになってきた。それで地方色を出していくこともできる。日本には元々地産地消という概念もあったのだと思う。その食文化が、恐らくは戦後、アメリカナイズされて壊されていった。今はそれをようやく取り戻そうとし始めた時期じゃないかと僕は認識している。
で、多様性は、京野菜も含めて今もあると思う。ただ、問題は種だ。たとえば京野菜の種をアメリカでつくって日本でまた買ってくるという、そういうことがある。F1種とか、作物のそういう問題をもきちんと追及していくべきだと思う。やっぱり作物をつくって野菜をつくって、そこから種を自分でつくって、それを受け継いでいくというのが本来の農業だと思うので。でも、その形が崩れつつある。科学技術の進歩がそういうことを促しているような感じもするので、それは大いに憂慮すべきことだと思う。
日本の食はハイブリッド?
辻:続いて日本の食文化が持つハイブリッド性について議論してみたい。ハイブリッドという言葉は日本の食文化とはミスマッチだと感じるかもしれないが、日本の食文化はほとんどが中国と朝鮮から来ている。それが800年ほどの歴史を経て日本固有の食文化になっていたわけだ。まずはその歴史を原田先生に改めて伺いたい。
原田:そもそも米は中国大陸から朝鮮半島を通って日本に入ってきている。また、そうしたベースの食品だけでなく、料理の…、私は様式と呼んでいるが、時代ごとの儀式的な、正式な様式というかトップレベルの料理の流れもある。最も古いものは神饌料理という、神様に捧げる料理だ。それが、たとえば談山神社のようないくつかの神社に残っているけれども、あれも実は中国の影響を少し受けている。色つきの神饌(しんせん)を備えているのだけれど、それ、本当はおかしい。神社では色がつかないからだ。色をつけるのはお寺。中国の文化が神饌のなかに入ってきているということになる。
で、神饌料理を受けて、その次に大饗料理という貴族や天皇の宴会料理が出てくる。これは台盤というテーブルに全料理を並べるものだけれども、テーブルというのは中国の文化。禅にはない。また、そこに並ぶ料理の数は偶数だ。そして目の前には箸とスプーンが置かれる。これも中国文化の影響を強く受けていると言える。大饗料理の一つの特徴は、あんまり調理されていない点だ。生ものや干物が並ぶ。酢で締めたりはしているけれども、それが切って盛られているだけ。そして、手元には四種器という小さな4枚のお皿があって、そこに酒と塩と醤と酢という調味料4種が置かれている。そのなかから自分で味をつけて食べるのが元々の形になる。
そして大饗料理の次に出てくる精進料理も、道元のようなお坊さんが中国から学んできたものになる。ただ、そこで料理のイノベーションが起きる。つまり、食品そのものに味をつける。徹底して調味を行い、植物性の食材を使いながら肉に近いものを食べるわけだ。そういうハイテクノロジーの料理として精進料理が出てきた。そうして室町時代、大饗料理の儀式的な要素と精進料理が高度な技術がミックスして、いわゆる本膳料理ができあがる。その本膳料理が、ある意味では今日の日本料理の原型になっていると言える。
で、本膳料理は七五三膳という形であり、これは奇数。しかも膳で食べる。また、時系列的に料理が運ばれてくる。今日の日本料理の原型は、まさにこの本膳料理に至って完成した。また、かつおや昆布から…、当時からそれらも個別には食されていたけれど、かつおや昆布から出汁をとるということが始まるのも室町時代の、本膳料理がつくられた時期だ。そうして煮物や汁物が発達していく。
で、それがやがて茶の湯と結びつき、茶事の前にいただく懐石料理が成立する。もちろん精進料理のなかにも、もてなしの要素はあった。ただ、茶の湯には、もてなし、しつらえ、季節感、あるいは一期一会といった考え方がある。それで、いかに客が喜ぶ料理を出すかという点で最高の工夫がなされた。それが懐石料理になり、そしてそれが江戸時代には庶民的なレベルで展開する。ここで何が言いたいかというと、始めから日本料理というものがあったわけではないということだ。中国から朝鮮半島経由で入ってきたものを、日本的にアレンジしながら独自のものをつくりだしていった。で、それはたかだか室町時代の話で、14~15世紀の話に過ぎない。
辻:まさしくそれがハイブリッドという言葉につながるのだと思う。ただ、何百年もかけて自由自在に、海外の影響を受けながら変化し続けてきた日本料理が、今はなぜか、技術的にちょっと止まってしまっていると感じている。特に世界への発信という部分で、「これが伝統であるべきだ」「これは変わってはいけない」といったルールのようなものが増えたと思う。徳岡さんは京都で嵐山吉兆をやられていて、その創業者である祖父の湯木貞一さんは「世界の名物料理:日本料理」「革新こそ伝統である」とおっしゃっていた。そして、徳岡さんもまさに今、次から次へと懐石のなかで革新を起こしている。それを続けることのできる理由を教えて欲しい。また、そもそも日本料理というものは革新的に変化しなければいけないものとお考えだろうか。
徳岡:さっきの話に戻るけれども、環境のなかで必要なものが継続していくし、必要とされなければ淘汰されて消えていくしかない。今は、ある面では大阪も京都もあんまり変わらないような感じになっているし、ニューヨークと京都もあまり変わらないと思っている人はいると思う。そういう環境のなかで、求められるから変わっていっている。変わらないと必要とされなくなるので、淘汰されるしかないと思う。
たとえば2000年前後から5年ほど前までは、ワインと日本料理を合わせたいという人が多かった。海外からいらっしゃる方も、「ワインを飲みたいので、それに合った日本料理をつくってください」とおっしゃっていた。日本料理を知らないからワインに合ったものを考えて欲しいということで、そういうものが次々にできた。私たちとしてもかつおだしでなくフォンドボーを使ったり、キャビアもフォアグラも…、まあ、それは祖父の代から使っていたけれど、とにかく技術を駆使していろいろ対応していた。あるいは海外でイベントに参加した際、いろいろと情報を吸収しながらやったりしていた。
ただ、今は、うちではワインがあまり売れない。むしろ圧倒的に日本酒が出る。海外からいらっしゃる方も同じだ。2000年から2012年頃まではいろいろなイベントを行っていたしミシュランにも載っていたし、海外の方の比率は嵐山店で10%前後。それが、ここ2年ほどで30%を超えた。そうした海外の方々もほとんど日本酒を頼まれる。
辰巳:海外に行ったら海外のワインを飲みたい。イタリアでイタリア料理店に行ったらフランスワインを飲む必要がないし、日本でも日本のワインを飲むと思う。
徳岡:それも一つの考え方だと思う。
辰巳:そこら辺の感覚を、海外の人はだいぶ分かっている。日本に来たら日本のものを食べたいし、日本のお酒を飲みたい、と。でも、日本にあるほとんどの高級レストランや高級ホテルは日本のワインを置いていない。これは大問題だと、10年間、声を大にして言っている(会場笑)。吉兆は安いお酒は出さないかもしれないけど。
徳岡:出さないことはない。うちに来る人に求められていないので。
辰巳:ワインは高いものだと思っている人は多い。高いワインじゃないと美味しくないという先入観が、これまた日本における独特のワイン文化だと言える。

そもそも日本料理とは?
辻:徳岡さんには日本料理の基礎があるから、かえって柔軟にできるというか、革新に対する恐怖感もないのだと思う。でも、日本料理に携わる人たちのほとんどは、日本料理の伝統を崩すことに恐怖感を持っておられる。日本料理のフレームワークは環境に応じて変わっていかなければいけないと思うが、徳岡さんはその縛りやルールとして何を基準にしていらっしゃるのだろう。
徳岡:基本的にはマーケットが基準になる。求められるかどうか。たとえば京都の天ぷら屋さんに行っても、つきだしが出て、椀物が出て、お造りが出て、最後にちょろっと天ぷらが出るというところがある。京都ではそういうコースが定番というか、「京都に来たな」というイメージを演出できる。だから、天ぷら屋さんなのに京料理のコースを出すようなお店もある。それも分かる。求められているからだと思う。だから、どうしなきゃいけないということはなくて、好きにしたらいいと思う(笑)。そのなかで生き残るところは生き残るし、淘汰されるところは淘汰されるし、そこで何かを感じ取っているところが新しいことを次々やっていくのだと思う。
辻:本物かどうかというのはあまり気にされないと。
徳岡:本物か本物じゃないか…。なんというか、たとえば偽装はダメだし(笑)、そういうことをすれば潰れるしかない。船場吉兆さんもそれで潰れた。結局、本物とはどういうものかというのがポイントだと思うけれども。
辻:料理人の方々は、「これは本物じゃない」みたいなことをよくおっしゃる。
徳岡:本物というのも変わっていくと思う。たとえば湯木貞一がやっていたかつお一番だしと、現在のだしはぜんぜん違う。
辰巳:その前に、日本料理の定義が必要だと思う。ある料理人は「日本料理ではにんにくが使われない」と言っていた。それが日本料理の一つの定義だという風に、その有名な料理人の方は言っていた。定義というと難しいけれども、そのフレームワークというか、どういったものが本物の日本料理かということをきちんと定義する必要はあると思う。日本料理をこれから海外に発信していくうえでも。
原田:和食が世界無形文化遺産に登録されたわけだけれども、今後もそれを守っていかなければいけないということで、和食会議(一般社団法人和食文化国民会議)というものが立ち上げられた。そこでもう一度、和食とは何かをきちんと定義をしていこうということで、今は見直しがなされている。世界無形文化遺産に申請した際は、「基本的にはごはんと魚と野菜を中心にした一汁三菜で、だしのうまみをベースにしたものが日本料理である」としていた。また、食べるための空間のしつらえや、料理を出すときのもてなしを含め、和食の文化だという形で申請していたわけだ。ただ、「それなら、うどんや天ぷらはどうなんだ?」となる。
実は、すしも天ぷらも…、すしについてはまたあとでお話をしたいと思うけれども、江戸時代の新しい料理だ。それ以前はなかった。その意味では今の定義でも少し難しいところがある。それで私は…、めちゃくちゃ乱暴な言い方になるが、「日本人がつくった外国にない料理が和食だ」と。なぜなら、日本人がつくった料理ということは、いきなり生まれたわけじゃないから。そこに和食の伝統がある。ラーメンだって煮干しでだしを取ったり醤油を使ったりしている。カレーライスだってライスを生かしているし、カツ丼も同じだ。その意味では、やはり日本の食の歴史に基づいて、日本人がつくり出した外国にない料理という定義の仕方も、広義では当たっているのかなと思う。
辰巳:ハイブリッドという言葉が出ていたが、同じことだと思う。ハイブリッドでもあるし、模倣でもある。どんどん新しく日本の食のなかに入ってきて、変化している。
徳岡:その根本には日本人の「らしさ」や気質みたいなものある。
原田:歴史ですね。
徳岡:そう。歴史のなかで積み重ねたものがある。アニメも同じ。技術が高いとか絵がキレイといった話だけじゃない。そこに日本人のマインドみたいなものがあり、それが物語として展開されている。海外の方はそれに憧れているような気がする。
辻:無形文化遺産のお話があったが、たとえば「懐石とは何か」といった定義づけは提出書のなかで一切行われていない。書かれていたのは、心や自然の話がばかりだ。私としては、長い歴史のなかで到達していったものが懐石で、それは日本の技術の集大成みたいなものだと考えている。ただ、一方では庶民の料理も地方にそれぞれ根付いている。そうした大衆的な食事の研究も日本の食文化を研究するうえでは大切だと思うが、それらはどのように分けて考えればいいのだろう。
原田:大変難しい問題だ。我々は史料に基づいて過去を復元するが、地方の大衆的な食については史料がない。大饗料理や本膳料理の献立は残っていても、庶民が何を食べていたかがほぼ分からない。それで江戸時代の黄表紙や文芸を見て、断片のようなものをかき集めている。ただ、階層が上だった人たちの料理文化と庶民の料理文化は、やはり無関係ではない。どこかで連動している。素材は同じだし、「どこそこの何々が美味しい」といった情報も共通している。それらが流通した結果として大饗料理や本膳料理もある。だから両方を見るべきだけれど、なかなか大変だ。
辻:そこで懐石以外の地方食文化がなくなってしまう可能性はないだろうか。
徳岡:それはあり得ない。食材がなくては懐石も成り立たないし、それは地方にあるものの積み重ねのなかでできていったものなので二つは連動している。現代でも同じだ。普通の方というか、極端に言えばコンビニの食事だけで済ましている人もいるけれど、それも地方自治体との連携のなかの生産品として出てきているわけだから、関係なくはない。だから、どちらかだけが残るなんていうことはあり得ない。我々としても、どちらかだけを語っているのでなく、市場に求められているからそれをつくり出すというだけだと思う。結局、食にあまりお金をかけない人はコンビニの弁当を食べたりするし、食に重きを置いておられる方は高級レストランに行かれたりするのだろう。で、そこでたくさんの仲間をつくったりもする。どちらもそういう要望によって存在しているわけで、社会主義ですべて配給制にでもならないかぎりどちらもなくならないと思う。
辻:日本料理の将来に関して、あまり危惧する必要はないと。
徳岡:僕はそう思う。残るものは残るし、淘汰されるものは淘汰されていく。ダーウィンの進化論ではないけれど、環境に適応していったものが残るのだと思う。
辰巳:あと、日本料理を発信していくうえで、漢字等の読み方も重要だと思う。テレビでもナレーションが難しい。たとえば、「南高梅」と書いたら「なんこううめ」なのか「なんこうばい」なのか。本来は前者らしい。でも、どこのニュースでも「なんこうばい」と言っている。赤米と書いたら「アカゴメ」なのか「アカマイ」なのか。日本語的には訓読みで「アカゴメ」だ。そうした読み方も統一する必要がある。海外へ発信していく際、アルファベット表記がばらばらになったら困るので。国としてもきちんと、日本料理の枠組みや呼称を統一していくべきだと思う。これは提案になるけれども。
原田:言葉の問題は重要だ。概念として言葉を論理的にきちんと使わないと、文化の基礎が危うくなる。食文化でも言葉をきちんとしなければいけない。
→世界を魅了する日本の食文化[2]は6/23公開予定
※開催日:2014年10月18日、19日



































.png?fm=webp&fit=clip&w=720)
.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)