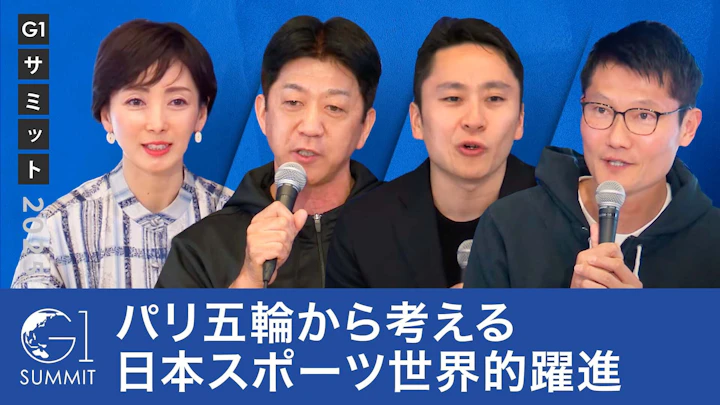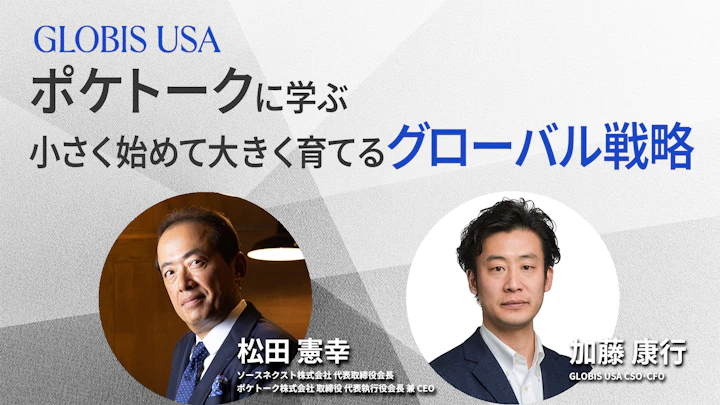大学入試改革と中等教育[2]
藤原:改めて漆さんに伺ってみたい。入試と高等教育に関わる部分で「これを変えて欲しい」と、強調しておきたい点は何かあるだろうか。
漆:「これ変えて欲しい」が、今はちょうど変わっているところなので。ただ、ゼロベースで考えたいのが学習指導要領だ。というのも、今はアダプティブラーニングということで、子ども一人ひとりに合わせた教材が次々出てきている。うちもリクルートさんにご協力いただいてiPadを一人一台提供するような実験をしているけれども、それで、家で予習してきてもらうといったことをしている。そういう時代に、学習指導要領という形で何を何時間学ぶかが決まっていて、しかも検定教科書がある、と。でも、うちの学校だけでも子ども一人ひとりは大きく違うわけで、彼らを一つの教科書等で勉強させるのは大変だ。以前はそれで未履修問題等、いろいろ起きた。従って、民主党のときに「大綱化」という言葉があったけれども、学習指導要領あきりでなく、大事なものだけに絞ってゼロベースで見直して欲しいと思う。
藤原:ゆとり教育のとき、「最低限に」ということで3割減らしたら、それで学力が下がったと言われてしまって、また3割増やしたことがある。そういう、ある意味では時代錯誤なことをやってしまったわけだけれど、小林さんはどうお考えだろう。

小林:なんのために学習指導要領を柔軟化するかという視点が大事だと思う。下村さんがおっしゃる通り、今はニーズが多様化しているし変化のスピードも大変早くなってきた。そこで、たとえば国のレベルで何年もかけて次の学習指導要領をつくり、それを降ろしていくという方法で、果たして多様化やスピードについていけるのかという問題意識は、たしかに私も共有している。
藤原:少なくとも8年や10年に一度変えるというのは無理ですね。
下村:ここは関係者が総論賛成各論反対になるところだ。今までの学力テスト一発勝負は、ある意味、公正で公平だった。点で合否が決まるわけだから。でも、面接や小論文で公正かつ公平な試験ができるのかという批判がある。それで国立大学協会からも、「総論賛成だけれどもできない」と言われた。だから文部科学省の役人が高大接続改革の説明にしに行く際、私が自ら国立大学学長会議に行って、なぜ必要なのかを改めてお話しした。そして優しく…、恫喝ではなく(会場笑)、「入学試験を変えるかどうかは各大学の判断です」と。「ただ、変える大学に対しては、その部分には財政的な支援をしっかり行います」と(会場笑)。で、改革をしないところについては、財政的支援は、その部分に限っては致しませんというお話をさせていただいた。
ある意味、今までの試験は最もシンプルだった。でも、面接や小論文で一人ひとりの成績をチェックするとなると相当な手間隙がかかる。そのためには教授だけでなく…、そもそも教授が入学試験をチェックしない大学のほうが海外は多いほどだけれど、アドミッションのプロを何人も何十人も確保する必要がある。また、大学によってはOBに協力してもらって面接試験をするという風にしないと、教授がやること自体そもそも難しい。だから、大学として経営力とともに明確な方針や核を持ってやらないとできないことだから、そこは国がしっかりと支援をする。私立大学だって、大きいところは10万人も受験するわけで、そこで今のようなことをすべてやるのは相当大変だ。従って入学試験も多様化しながらやっていくということなのだと思う。
一つ、象徴的なことを申しあげたい。先日、東京藝術大学の宮田亮平学長がいらしたとき、「東京芸大の入試をぜひ変えてください」というお話をしたことがある。すると、「東京芸大は入試に最も手間隙をかけている」と。たしかに作品等をつくらないといけないわけで、競争率は30~40倍だそうだ。だから大きなプライドがある。芸大にどうしても入りたいということで、「十浪」、10年間浪人する人もいるという。「5浪ぐらい普通だ。自分は2浪で入れたけれどもラッキーだった」とおっしゃっていた。
そこで私は率直に申し上げた。「そこで5年浪人することに、どんな意味があるんですか?」と。「あるいは10年浪人して、本当に音楽や美術で才能磨くことができるんですか? 人生の無駄になってしまっていませんか?」と申し上げた。芸大に入る学生にセンター試験が必要だろうか。数学とか英語とか物理とか…、知らないより知っているほうがいいに決まっている。ただ、それができなければ美術もできないというなら、それは落とすための試験だ。ダウン症の子どもや発達障害の子どものなかには美術の世界で、普通の子どもでは考えられないような煌く才能を持っている子がいる。けれども、彼らは今の日本の入学試験では絶対に受からない。でも、今求められているのは多様化だ。だから少なくとも美大や音大のようなところは、その子の能力を高めるという視点で言えば学習指導要領をぜんぶやらなくてもいいと思う。
とは言え学習指導要領自体は必要だと思う。それがなくなったらどんな教育されるか分からないから、基本的な最低限度の指導要領は必要だ。ただ、5教科7科目すべてでしなくてもいいと思うし、選択によって得意分野をさらに伸ばす形にすればいいと思う。で、何も知らないのも困るから、それなりの常識は大学でも教える必要があるけれど、すべてを試験で問う必要はないんじゃないかと思う。
藤原:今おっしゃったことを本当にやるのならアドミッションを行う事務方がビジネスマンとして優秀でなければいけない。事務長も、それこそ社長クラスの人材が必要だ。つまり、お金がかかる。人を抱えないといけないし、「学長よりも年収低くていいですか?」というわけにもいかなくなると思う。そういう予算は振り向ける?
下村:日本に世界の優秀な人材が集まらないのは、たとえば学長の給与よりも低い設定になっているから。国立大学の学長は1600~1700万ぐらいか。だからノーベル賞受賞者は日本の大学になんて来ない。桁が違うんだから。だから今度は年俸制にして、学長よりも高い給料を取れるような制度にした。

藤原:それは事務方も?
下村:とりあえず教授1万人を対象にしている。事務方はまだ年俸制になっていないけれども、そういう制度にしていかなくてはいけないと思う。
藤原:今朝、山中(伸弥氏:京都大学iPS細胞研究所所長)さんに面白いことを聞いた。仮に外国の優秀な方を日本で採用できるとしたら、それは奥さんが日本人の方だけだそうだ。分かりやすい。とにかく事務方やマネジメントにもお金を使わないと良い大学にはならない。ハーバードだって、資金の運用一つとっても一番能力の高いやつがやっている。そちらにもお金が廻るようにしないといけない。それともう一つ、先ほど大事なポイントが出た。指導要領を緩めるというか、最低限で…。
下村:緩めるというか、最低基準にする。
藤原:そう。最低基準にして、「特色ある子はそれをもっと伸ばせばいいじゃないか」と。これ、ゆとり教育のときに叫ばれていたことだ。でも、それが「学力だ学力だ」と、学力派に押し込まれ、結局は「ぜんぶやらなきゃダメだよ」ということで教科書も3割増えちゃった。それをもう一度戻すという意味で捉えていいのだろうか。
下村:そうでもない。ポイントは学校の先生だと思う。総合学習というのも、本来、発想としては素晴らしい。ただ、それをやりきれる先生が実際には1~2割しかいなかった。同様に、今回も学校現場にそれができるのかが問われている。
藤原:そこが一番大事なところです。
下村:だから、これから先生になる人はもちろん、現在の小学6年生から大学入試は変わるので、今現場にいる先生も授業の仕方を変えないといけない。今までの延長線上で、たとえば一方的に板書をするような形では自ら課題解決に取り組む能力なんてつくはずがない。だから、先生の研修も我々の取り組みに賛同してもらいながら変えていくというパッケージでないと、絵に描いた餅になってしまう。
藤原:その点、文部科学省で2月に人事で動きがあった。教育指導要領をつくる教育課程課の課長と、入試をやる大学振興課の課長に、すごく優秀な人間が就いた。それを見るだけでも本気だということが分かる。
漆:りんちゃんとも「ゆとり教育と同じにならないようにしないとね」という話をしていたけれども、下村さんがおっしゃる通り、今の改革理念とゆとりのときの理念はすごく似ている。で、総合学習というのも大変評判が悪いけれども、うちの学校はその総合学習の時間を最大限に活用して差別化している。で、その活用元になっているのが実は藤原さんの「よのなか科」だ。うちでも3教科やっていて、そのときに教員を研修していった。で、今はその教員が孫弟子みたいな人たちをどんどんつくっていて、今はアクティブラーニングが行える人は3割ぐらいになっている。
そこで思うのだけれど、たとえ研修をしても、教材があっても、藤原さんがやっていたことはほとんど広がっていない。なぜかと考えてみると、やっぱり仕組みが悪いのだと思う。校長に権限がないし、あと2年で任期を終える校長は挑戦をしない。そこでインセンティブとプレッシャーを校長に委ねる仕組みが必要なのだと思う。あとはりんちゃんが言っていたトラック。「校長になる人は経営の勉強をした人」という分け方が必要だ。とにかく研修だけだとまた同じことになってしまうという怖さがある。
→大学入試改革と中等教育[3]は6/10公開予定
※開催日:2015年3月20日~22日



.png?fm=webp)























.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)
.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)
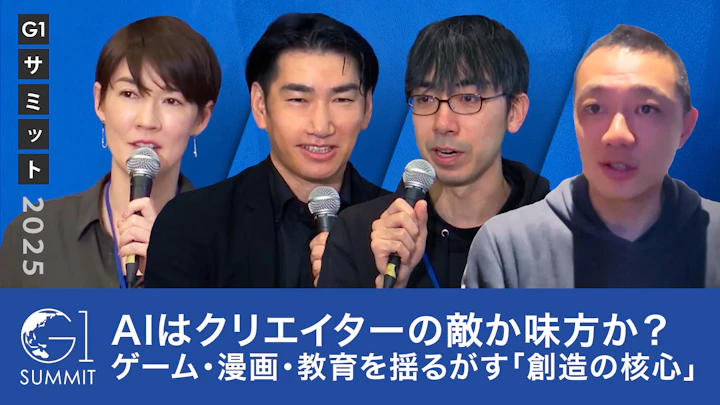
.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)
.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)