佐渡島庸平氏(以下、敬称略):企業の皆さまからすると、デザイナーはすごくセンスがある方々というイメージがあると思う。だから、そういう人たちに何かお仕事を頼むとなると、たとえば「修正の依頼もセンスのない自分は言えなのでは?」と、心配になる方もいるのではないか。デザイナーと企業のコラボ等は多いが、デザイナーの方々は普段どういったことを考えていているのか。また、実際にはどのような形で経営に携わっているのかといったことを最初に聞いていきたい。まず、経営に深く関わることが多い水野さん。いろいろな企業から依頼が来ると思うけれども、水野さんの会社ではどういったことをなさっているのだろう。(01:18)

水野学氏
水野学氏(以下、敬称略):社長の愚痴を聞くのが結構メインの仕事で(会場笑)、それを一通り聞き終えるとデザインの話になる。僕は、早い話がブランド構築をしている。では、ブランドとは何か。ほとんどの日本企業は技術持っているし、もっと言うと技術はお金で買うことができてしまう。ただ、どうすればそれを世の中にうまく発信できるかという点で皆が攻めあぐねている。たとえば伝統工芸。今は衰退しているけれど、元気なところもある。では、元気があるところとないところの違いは何かというと、見え方の違いだけ。つまり、僕はデザインを用いて見え方のコントロールをしている。時代劇を観ていると、なんの説明がなくても悪代官のような、悪そうな人間がすぐに分かる。見え方がうまくコントロールされているから悪役ということが分かるわけだ。(02:16)
企業も同じ。良い企業なのかどうかを、BtoBであってもBtoCであっても人々はすぐさま感じ取る。それでモノを買ったり、「この企業、いいな。入りたいな」と思ったりしている。つまりブランディングとは、すごく省略すると見え方のコントロール。「僕の仕事は見え方をコントロールすることです」といったご説明をすることが多い。(03:36)
佐渡島:一方、山中先生はプロダクト・デザイナーとして元々は日産で、今はフリーでお仕事をなさっている。現在はパナソニックをはじめいろいろな企業とプロダクトを開発されたりしているが、どういった立場でどんな仕事をなさっているのだろう。(04:10)

山中俊治氏
山中俊治氏(以下、敬称略):企業によって接し方が違うと言えば違う。パナソニックさんとは長い付き合いで、いろいろな提案をしてきた。実は13個ほどデザイン提案をしていて、ひとつもきちんと製品化されていない(笑)。ただ、パナソニックさんからはすごく感謝されていて、納めたものも大事にとっておいていただいている。(04:33)
たとえば15年ほど前、「クリーンスタイル」という、白とガラスの色だけで統一した白物家電のブランドをつくった。その頃の白物家電は白物と言いつつグレーとベージュしかなかったから。それを復活させたのは、実は僕の功績が大きい。「白い白物をつくろう」と、掃除機をはじめ真っ白なものをいくつか提案した。で、それらはそのまま製品化されたわけではなかったけれど、似たものが製品化されている。それが社内にも大きな影響を与えて、白いものをいっぱいつくる状況にもなった。その意味では、デザインは水野さんがおっしゃるように見え方だけれども、たったひとつの魅力ある商品をつくることがデザインではない。企業全体で商品の方向性をどのようにコントロールするかがすごく大事だということは、間違いなくある。(05:07)
佐渡島:なぜ社内にいるデザイナーにはそれができなかったのだろう。(06:27)
山中:いい質問で、それは「そもそもデザインとは何か」という話に関わる。工業デザインという仕事が成立したのは100年ほど前。当時はアメリカを中心に、最先端の技術を売るためにはどうすればいいかということが追求されていった結果、「形だけ変えても結構売れるね」という話になった。「新しい技術がないときは形だけ変えよう」と。逆に新しい技術ができたときは新しくないように見せることが、売れ行きを上げるためには案外大事だといった話になった。機能的には変り映えのしない冷蔵庫を飛行機のように見せたり、まったく新しく登場したテレビを昔からある木製家具のように見せたりすることが、すごく重要な技術だったという時代がある。(06:37)
デザインはその頃から職能として成立している。売るためにいろいろな形を与えていくという意味で、たしかに重要な役割を果たしていった。それは今でも十分大切な役割だ。ただ、多くの経営者にとって、デザインというものの認識がそこで止まってしまっているのはかなりの問題だ。実際、前世紀の終わり頃から、そのやり方でモノをつくってもうまくいかない事例がいくつか出てきた。それは、ひとつには成長の限界という問題がある。無闇につくるわけにいかなくなったというのが大きい。それとユーザビリティの問題。良かれと思ってつくっても誰も使えないということが、技術が複雑になってくると数多く出てきた。そこで、「もう少し丁寧に機能としてデザインを考えないとね」という時代が来たわけだ。ソフトウェアを含めた電子テクノロジーが技術をさらに複雑な状況にしたから、そうした考え方が必要になったわけだけれども。(07:39)
それともうひとつ、マイノリティの問題がある。昔は量産を謳歌する言葉として、たとえば「大統領もスラムの住民も同じコカ・コーラが飲める。素晴らしい世界が来たね」というのがコカ・コーラの初期の宣伝文句だった。しかし残念ながら、「ひとつのモノをつくって多くの人に配ると皆が幸せになって、皆から少しずつお金をもらえたらつくった人もハッピーになる」というユートピアは、マイノリティを見落としている。たとえば会場にいる方々全員に合う服をつくるとなれば、平均的な服をつくることになる。でも、その平均がぴったり合う人はたぶん会場に数名しかいない。で、ほかの皆にとっては小さかったり大きかったりする。量産とは、そもそもそういう問題を含んでいる。(08:38)
それで、前世紀の終わり頃から明らかになったことがある。デパートなどへ買い物に行くとさまざまな商品が山ほどあるのに、自分にはひとつもフィットしていない気がする消費者が増えてきた。それで、「もう少し、マイノリティや小さなマーケットのためにモノをつくらなきゃいけないのでは?」といったことが明らかになった。それが、デザインを変えなきゃいけないもうひとつの理由になる。ブランディング、機能とデザインの関わり、あるいは消費者とデザインとの非常に密接な関わりをきちんと見直していかなければいけなくなった。にも関わらず、「いいデザインにするとすごく売れるんじゃないか?」「変り映えさせないと売れないのでは?」といった旧来の価値観を多くの企業経営者が持っていることは、デザインの問題をかなり不幸にしていると思う。(09:36)
水野:今のお話、すごく面白いと思って伺っていた。経営者が何を目的にして仕事をしているかという話にもつながると思う。本セッションには思っていたよりも多くの方に来ていただいているけれど、空席はある。たぶん大西(洋氏:株式会社三越伊勢丹ホールディングス代表取締役社長執行役員)さんのお話なんかを聞きに行っている方が多いのかなと思う。ただ、大西さんは「僕の話を聞きたい」とおっしゃって僕を呼んでくださっている。(10:33)
で、今登壇している3人には共通項があると思っている。たとえば大きな会社の社長でも、ほかの会社で仕事をしたことがあまりないという方は多いと思う。社外取締役になっている方やいくつかの企業を渡り歩いている方もいらっしゃるのでは全員ではないけれど、大抵は自分の会社でしか働いたことがないと。でも、僕や山中さんや佐渡島さんはいろいろな会社の社長や取締役の方と膝を突き合わせて仕事をしてきている。それが最大の特徴だと思う。だから、デザインが経営にどうコミットしていくかということを、山中さんがお話ししていた洋服のサイズという側面だけを見ても日々突きつけられている。ただ、経営者の話も一側面だけを聞いて分かった気になって何かできるものじゃないと思うし、社会と経営の問題は密接に関わっていると感じた。(11:09)

佐渡島庸平氏
佐渡島:僕は講談社を辞める直前に雑誌をつくっていて、そこでお二人とも仕事をしていた。それで、辞める際は水野さんから「(新しい)名刺つくるの、俺だよね?」という携帯メールが来て(笑)、「はい、そうです!」と返したりして。ただ、水野さんに名刺をつくっていただいたとき、「ああ、デザイナーの仕事ってこういうことか」と思った。講談社で最後につくった雑誌は期間限定媒体で、ページをつくる際はデザインに関してもほぼ感覚的。「こういう風にしたほうが分かりやすいと思う」というような話に留まっていた。でも、水野さんとはコルクという会社の理念について話し合いを続けたし、その理念を体現したデザインになっているかも話し合った。だから理念に沿っていないならいくらでも直しができるけれど、「どちらがお洒落か」といった議論にはならない。僕が「こういう会社にしたいんです」と言うと、「それならこのデザインでこういう風に語れます」と。「こういう理由でコルクという会社にしたことが、このデザインから分かります」というストーリーを水野さんがお話ししてくれる。(12:45)
たとえば僕がリースリングのワインを好んでいるとしたら、リースリングのコルクはどうなのか。あるいはコルクというものがどこで採れてどんな価値や歴史を持っているか。それで、コルクの歴史と書体の歴史が結びつくといったお話をなさる。僕がこの会社を人に説明するとき、「あ、こう説明すれば一瞬で分かるんだな」というのを水野さんが先に表現してくれた。そこで、水野さんがお仕事をなさったほかの企業のお話も伺いたい。たとえば中川政七商店さんともお仕事をなさったけれど、どのような取り組みをして、どんな提案していったのだろう。(14:33)
水野:奈良の中川政七商店という、和雑貨を扱う業態のお店とお付き合いを始めたのが6~7年前になる。当時の年商は9億。それで1年半前まで僕が担当して、現在は40数億に成長した。つまり40数億にしようというデザインを施した。こちらは今も急成長を続けているし、今後もまだまだやっていく。ただ、当初はショッピングバッグをつくって欲しいとのご依頼だった。でも、ショッピングバッグのデザインは、変な言い方だけれども5分ほどでできる。さっとデザインしてマーク入れたら大抵は可愛らしいデザインになる。…ならないかもしれないけれど(会場笑)、少し工夫すると、なる。(15:26)
でも、僕としてはそういう装飾的なことは割りとどうでもよくて、なにかこう、いつも悩み出してしまう。そのショッピングバッグをつくるために僕は数十万なり数百万なりのお金をいただくわけだ。そのとき、「これでお金をもらっていいのかな」と。「この会社はショッピングバッグのリニューアルをしたいんじゃなく、そのリニューアルで売上を伸ばしたいんだよな」と、当たり前だけれども考える。ただ、そんな風にワンステップ先に行けるデザイナーが実は少ない。で、僕の場合は育ちが少し貧乏だったこともあって、「儲けなきゃ」という考えがすごく強くて、それで自分から提案し始めた。(16:37)
では、何を提案したか。まず、そのショッピングバッグの業態「遊中川」というブランドに関して、「どれほどの市場規模に持っていきたいですか?」という話をした。僕はこういうことを考えるとき、街や県にそれを取り扱うお店が何軒あればいいかといったことを考える。すると、当初は最大で40~60億ほどの規模になるだろうと思った。ということは、あと10年もすれば業態が行き詰る。市場規模が飽和すると思い、「違う業態もあったほうがいいのでは?」と。人の会社なのに(笑)、急にそう思い始めた。(17:23)
で、「遊中川」は出掛けるときに持つ和小物のような商品を扱う雑貨屋さんだったのだけれど、その頃は日本人がなんとなく和の暮らしに自信を持ち始めている気がしていた。それなのに当時は…、僕はそれを裏コンセプトで「和印良品」と呼んでいたけれど、そうした和印良品を売るお店が世の中にない。買おうとすると古ぼけた商店に行かなきゃいけない。「それなら、それを新しい業態としてつくってみては?」とご提案した。すると、社長の中川淳さんという方はすごく反応が早い方で、その場で「やります」とおっしゃる。それで仕事が始まり、6年ほど経った今はそちらの業態のほうが大きくなった。丸の内のKITTEにもショップがあって、そこでは月2000万円ほどの売り上げとなっている。この業態では珍しい売上で、爆発的なヒットを続けている最中だ。(18:10)
山中:水野さんはいつも自分からの提案型で、くまモンもそうなんだよね。(19:29)
水野:そうなんです。くまモンというキャラクターもつくったのだけれど、それも最初は「くまもとサプライズ」というプロジェクトのロゴをつくって欲しいとのご依頼だった。ただ、それがすぐできちゃった(会場笑)。で、「まあ、これでいいかな」と思ったけれど、「何かいたほうがいいな」と。そこで、当時はちょうど知事として活躍なさっていたか知事を退任なさっていたかというぎりぎりの頃だったと思うけれど、東国原前宮崎県知事のお仕事をモデルにした。ただ、当たり前だけれども人間は何か事件を起こしたりしそうだ。だから事件を起こさないモデルがいないかなと思ったとき、「あ、キャラクターだ」と。それでキャラクターをつくったという流れになる。(19:35)
佐渡島:それまではキャラクターをつくったことがなかったんですよね。(20:27)
水野:僕はキャラクターが大嫌いだったし、「安易につくったものが泣かず飛ばすになったら、キャラクターに失礼だ」といったことを言い続けていて、つくったことがなかった。でも、今お話ししたような流れでくまモンをつくったと。ただ、あれは僕がすごいのではなくて、県庁の方がその権利を開放するという、もう“現代アート”とも言えるようなことを展開したからあそこまで広がったのだと思っている。だから、「くまモンは望まれて生まれた子ではなかった」ということを言っている(会場笑)。(20:29)

佐渡島:一方、山中先生からはデザインが平均的ではないものに変わっていくといったお話があった。ただ、以前はSuicaのお仕事もなさっている。これは逆に圧倒的に平均的なものかなと思う。(21:07)
水野:そうですよ~。それはどう説明してくださるんですか(笑)。(21:31)
山中:(笑)。これはユーザビリティの問題になる。我々の周りに次々と、見たこともない魔法のようなテクノロジーが生まれてきたとき、どうなると人が使いやすくなるか。使いたくなるものにするだけでそれはだいぶ解決する。ただ、それ以前の問題として、形や色や信号や音のファンクションをきちんと整理する必要があると。これは1995年頃のプロジェクトだ。それまでもJRさんは非接触改札機の開発を長らく続けていた。これ、JRさんにとっては夢だ。投入するタイプの改札機はとても高価でメンテナンスも大変。だからJRさんはそうした精密機械じゃない、投入しないで済むマシンをつくりたいと思い続けていて、80年代から開発を続けていた。それで95年頃にやっと、ソニーさん東芝さんの協力を得て、今と同じようにカードを近くに持って行くと読み取って決済してくれる仕組みがほぼ完成した。(21:39)
ところが、実際にそれを数百人に使わせてみるとまったくうまくいかない。皆さん、今はなんらかのカードを当てる際、そもそも近くで当てないと反応しないことをよく知っている。「ピッ」という音がするまで一瞬の間があることも知っている。機器の近くを「サッ」と瞬間的に通すだけではたぶん反応しないことも、今は体感的に知っている。だから、少しあてがう。でも、そういう行為が常識としてまったくなかった時代に、「このカードがあれば投入しなくても通れるから使ってみてください」という以外は何も説明せずカードを渡すとどうなるか。アンテナを見つける人は多いけれど、縦にかざしたり、見せるだけで通ろうとしたり、振って反応させようとしたり(笑)。(23:04)
水野:(笑)。江戸時代の人に渡したような。(24:00)
山中:そう(笑)。そういうことがすごく多くて半分の人がまともに通れない。ただ、そこでJRさんのなかで、「これってデザインって解決できないですかね」と言ってきた人がいたのはなかなか…。(24:02)
水野:そこがすごい。(24:14)
山中:以前お付き合いのあった技術開発部の方が、「どうしたらいいと思いますか?」とおっしゃる。それですぐに答えを欲しがっていたのだけれど、僕は、「こういう問題ではデザイナーの直感がまずあてにならないから、僕がこれから言う答えはダメです」と。そのうえで、「やるべきことは精密な実験です。現場と同じ状況を再現し、いろいろな形を使わせてみてください」とお話しした。これはユーザビリティの基本だけれど、「少人数でも構わないから徹底的に人に使わせてみてください」とお話しした。(24:16)
で、その企画書を出した。当時はユーザビリティという言葉もなかった時代だけれど、デザインをしている友人たちがそういうことを研究していたりもして、僕はなんとなくそういうことを耳学問で知っていた。自分でやったことはなかったから、「ということ、らしいですよ?」というレポートにして渡した。ただ、その仕事自体をやるつもりはまったくなかった。すごく面倒くさそうだし。そうしたら「やってください」という依頼が返ってきて、「やるのかあ」と。そこから計画していろいろな形を試したんだけれど、もちろん、当時は勝算もまったくなかった。それで、「どうなるか分からないし、ぜんぜんダメかもしれないけれど、ダメなことがはっきりするだけでも意味があると思いますよ?」というようなことを言いながらやっていた。(24:53)
でも、それでいろいろな形を試しているうちに分かったことがある。人間、光るものには誘われるというのがひとつ(会場笑)。あと、あてがう面が自分の側を向いていると、なにか、あてがう(笑)。だから今は全国すべての駅で改札機のアンテナ面が13.5度手前に傾いていて、そして光る。その基本仕様を決めたのは僕だ。これをデザインと呼ぶのか。要は、僕はペンギンのデザインも緑色のデザインもしていない(笑)。今はPASMOのマークがついていたり、いろいろな色になっていたりするけれど、僕はそのどれひとつとして決めていない。ただ、人が人工物に接したときの基本的な作法はデザインした。そういうメタレベルのデザインが実はとても大切だし、それもデザインであるという認識自体がすごく大事だと思う。実際、それによって以前は5割しか通っていなかったものが1999年のテストで99%を超えた。それで、当時は頓挫しかかって「もう無理かも」という話になっていたそのプロジェクトだったけれど、当時のJR会長だった山之内秀一郎さんが「いけるね」と判断した。それでとても感謝されたけれど、結果として2001年から導入する形になった。(25:42)
佐渡島:デザインが必要だと思われていないところにデザインを入れることで、一気にビジネスの可能性が広がることもあると思う。人々がデザインに抱いている既存のイメージが、今は多くのデザイナーがやっていることとズレてきたとも感じる。(27:12)
山中:水野さんがお話ししていたブランディングの話と、僕が今お話しした認知科学に近いようなモノと形との関係って、あまりにも遠い。だから、「それもデザインなの? あれもデザインなの?」と、戸惑うと思う。ただ、僕は基本的には、人とモノとが接したときに起こるあらゆることをトータルに設計するのがデザインだと思っている。だから今申し上げたようなユーザビリティのレベルもあるし、愛着というレベルもあるし、ブランディングとしてそこに乗る文化的ストーリーをコントロールするレベルもある。いろいろあって、それらはすべてデザインなんだという認識が大事なのだと思う。(27:53)
佐渡島:水野さんは普段、「デザインはセンスでなく知識だ」とおっしゃっている。どういった知識を積み重ねていくと水野さんのデザインになるのだろう。(28:50)
水野:たとえば何か犯罪を起こした人間について、ニュース等でその特徴を言えないことってあると思う。髪の毛は短くもなく長くもなく、中肉中背で、なんらかの個性や趣味や趣向が入っていない。それが「ゼロポイント」だとすると、それを最適化するということがある。たとえば僕はEXILEの音楽は聴かないけれど、好きな人にとっては「EXILEはセンスがいい」という話になる。つまり、センスというのは良い悪いで語るべきことではなくて、最適化するものであると。実はこれ、企業がどこにターゲティングしているかという意味ですごく大事だ。それが明解でないとターゲットに刺さる筈はないから、最適化ができていないというのはすごく大きな問題だと思っている。(29:23)
それで先ほどのお話に戻るけれど、やっぱり多くの日本企業は行き詰っていると僕は感じている。特にIT企業は今までの伸びがすごかったぶん分、今は停滞しているように見える。有名だった企業もアップルやアマゾンやフェイスブック、あるいはツイッターに取って替わられているような状況だ。なぜ、取って替わられてしまったのか。デザインの力以外の何物でもないと、僕は思っている。(30:34)
昨日、LINEの森川(亮氏:株式会社LINE代表取締役社長)さんと少し立ち話をさせていただいた際、「LINEの成功事例ってなんですか?」と聞いてみた。すると森川さんは…、少し言葉は違うけれど、「あっと驚かせるようなことはしていません。皆がなんとなく欲しいと思っていたものをつくっただけです」とおっしゃっていた。僕が慶應で教えているのはまさにそれだ。僕も、「あっと驚かせてはいけない。驚くだけで終わっちゃうから」と言っている。で、僕が森川さんに、「LINEってすごくデザインがいいですよね」と言うと、「あ、そうなんですよ」とおっしゃる。だから認識はなさっていると思う。(31:13)
日本企業は圧倒的な機能デザインの力を持っているけれど、長く続いたものづくり信仰が装飾的に見えるデザインを軽視させてきた。でも、技術力が飽和した現代ではデザインで他の企業と差別化するしかない。ではどこからどこまでがデザインかと言えば、山中さんがおっしゃったように徹頭徹尾、すべて。だから僕は経営者のネクタイも選んだりする。そういうところまですべてブランディングで、デザインだ。だから山中さんとはお仕事の面で重なる部分もあると思う。僕はプロダクトができないからズレている部分もあるけれど、やっぱり同じことをやっていらっしゃるんだと感じた。(31:59)
佐渡島:アウトプットが違ってはいても、「あっと驚くことをするわけじゃない」という部分はお二人が共通しているところかなという気がする。(32:58)
山中:イノベーションというのはまた少し別のレベルにあって、それはあっと驚くものだけれども。水野さんはどちらかというと、「イノベーションにはすごいパワーがあるけれど、それだけに頼ってはいられない。だからブランディングで企業を底上げしておかないと」、というのがベースになっていると思う。(33:08)
水野:そうなんです。山中さんにはいつもそこで「違うよね」というアドバイスをいただく(笑)。(33:28)
山中:いやいや、違わない(笑)。(33:36)
水野:デザインには2つの役割がある。ひとつは売上を伸ばしていくことで、もうひとつは…、これは山中さんの言葉だけれども、世の中にプロトタイピングを出していくこと。たとえば、ロボットデザインのプロトタイピングをなさったのが手塚治虫さんじゃないかと僕は思っている。手塚さんがいなかったらロボットはもっと遅れていたんじゃないか。そういうものも山中さんは一方でつくっていらっしゃる。両方やっているから、それでたまに分からなくなる人がいるのかもしれない。(33:38)
後編はこちら




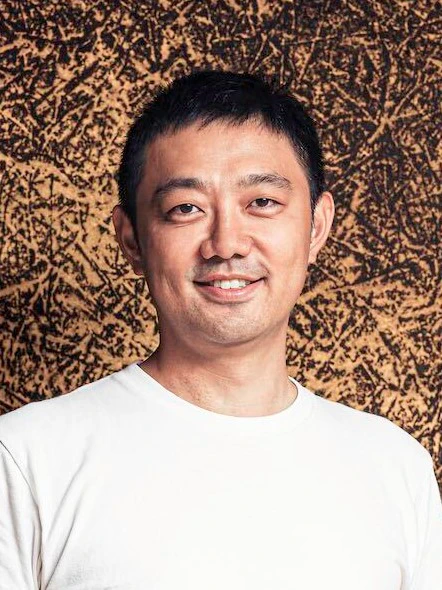























.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)
.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)













.png?fm=webp&fit=clip&w=720)
.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)


