「戦略コンサルタント」と聞いて、何を思い浮かべるだろうか。企業の参謀役。学生の人気就職先……。時に伝統的な日本企業とは相いれない「頭でっかちな存在」として否定的に語られることもあるが、今や、企業だけでなく、政府のシンクタンク役として、日本経済の行方、いや、日本そのものを動かしている。
ここに、憂国のコンサルタントがいる。経営コンサルティング会社A.T.カーニー日本代表を務める梅澤高明氏。自身を「国粋主義者」と表現するほど日本への強い愛着を持つ。日産自動車勤務、名門MITのビジネススクールを経て、A.T.カーニーの米国オフィスで経験を重ねた。だが、「日本企業が世界に打ってでるチャンスを手伝いたい」との想いから、帰国を決意。以来、数多くの企業の再生、グローバル化をサポートしてきた。
梅澤氏は語る。「欧州のメディアでここ1年、日本を表現するにあたって、『新興衰退国』なる言葉が使われています。日本は海外からそんな風に揶揄されるところまで来てしまった…」。統合の進む世界市場で勝ち残るべく、世界の企業が国境を越えて、合併や業界再編を繰り返している間に、日本は国内市場のシェア争いばかりに汲々とし、いつの間にか取り残されてしまっている…。
中途半端に国内市場が大きいがゆえに、短視眼的、近視眼的に陥っている日本企業が、本当にグローバル超競争を勝ち抜くためにはどのような方策をとればよいのか。
梅澤氏がグローバル超競争のリアリティーを語りながら、その方策を探る。
梅澤高明という平成の志士の想い
皆様こんばんは。今日は暑く天気も悪いなか、これだけ多くの方々にお集まりいただきまして本当に嬉しく思っております。これからの2時間が皆さんにとって意味あるセッションになるよう頑張りたいと思います。私の本職は経営コンサルタントですが、これまで10年程は、グロービス経営大学院で経営戦略を中心とした科目の教鞭をとる立場でもありました。
普段、私は大学院で優しい講師であるとの評判を頂いていますが(会場笑)、今日はA.T.カーニーのコンサルタントらしく、少し違った雰囲気でお話をさせていただこうかと思っております。
A.T.カーニーは外資系のコンサルティング会社ですが、「日本でビジネスをするのなら日本企業のお手伝いを」ということで、ここ10年間、クライアントも外資系企業から日系企業へとどんどんシフトしていきました。今ではもうクライアントの9割前後が日系企業です。特に我々がフォーカスしている日本を代表するようないくつかの産業で、それぞれTOP3に入るような会社を中心にお手伝いしています。世界には2000名強のコンサルタントがおりまして、東京にいるのはそのうち120人ぐらいですね。
私自身はアメリカで4年間コンサルタントをやっていまして、帰国したのは1999年になります。帰ってこようと思ったきっかけは、1997年にはじまった日本の経済危機でした。アメリカという対岸から、山一証券にせよ、日本長期信用銀行にせよ、あるいは私の古巣であった日産自動車にせよ、多くの企業が破綻、あるいはその寸前までいってしまった状況を目の当たりにしていたことがきっかけです。当時は米国企業のお手伝いをする日本人コンサルタントだった訳ですが、「このままの仕事では経済に対するインパクトも小さい」という気持ちがその頃から生まれていましたし、アメリカで4年間仕事をしてそれなりに鍛えてきたつもりでもありました。だから、「日本企業が再生するためのお手伝いを、何か出来るのではないか」と思いまして、帰国した次第です。
その後さまざまなクライアントと仕事をしていくなかで、「この会社の再生、あるいはグローバル成長に我々もここまで貢献出来た」といった風に、それなりに達成感を持つことが出来るようにはなりました。しかし、ご存知の通り2008年のリーマンショック以降、再び奈落の底に突き落とされる日本企業がたくさん出てきた。今でもどのように危機から這いあがり、もう一度世界へ挑戦していくかを模索し続けている企業はたくさんあります。早い企業は立ち上がってもう一度ジャンプをしようということで、特に今年に入ってからは積極果敢になっている企業も多い。今はそんなフェーズであるように感じています。
そんななかで色々と日本経済や日本企業のことを深く考えていった結果、1年半ぐらい前からでしょうか、社会に発信をしていこうという気持ちも強くなっていきました。それぞれの企業にそれぞれの提案をして個別に改革や成長のお手伝いをするだけでは、我々が日本経済に与えることの出来るインパクトもやはり限られてくるという思いがあったためです。1年半ぐらい前から、メディアを通して積極的に発信を行っていくようにもなりました。
この一年間、今まではあまり行ったことのなかった官庁や政治家のところにも通い、議論をする機会が増えました。「日本はこのままで良いのでしょうか」と。その結果、今年の春に経済産業省が発表した『産業構造ビジョン2010』において、いくつかコアとなる部分で戦略策定のお手伝いをするケースにも到っています。これは今年の6月に発表されたもので、現政権の新成長戦略における骨子となるものです。このなかで我々としては、どのようにインフラ産業を輸出していくか、あるいは日本の文化産業をどのように外貨獲得の手段にしていくか、こういった部分で戦略策定のお手伝いをしています。
今日のテーマはグローバル競争と日本ということですから、まずはマクロな視点で概論を述べるとともに、このグローバル競争をリードしている企業、特にABInBevというビール会社の事例を紹介していきます。そして最後に日本企業が現在どのような課題に直面しており、グローバル化を加速していくうえでどんな視座が必要になるのか。その点について、多少なりともヒントになるお話をしたいと考えています。
日本は世界唯一の新興衰退国?
まずはマクロな視点からです。ここではGoldmanSachsが比較的最近発表した指標で日本の地位を見ていきましょう。1990年、日本は名目GDPで世界の14%を占めていましたが、2007年には8%まで低下しています。そして2030年には4%、2050年にはさらにその半分となる2%までシェアを落としていくというのがGoldmanSachsの見立てです。
ちなみに2030年の4%という数字は1ドル100円ベースで換算するとちょうど510兆円になります。ここ15年の名目GDPは約500兆円前後ですから、GoldmanSachsは2030年まで日本経済が名目ベースでほとんど成長しない、あるいは一度成長するがまた縮小するのではないかと予測をしている訳です。それが真実かどうかはこれから20年間にわたる私たちの頑張り次第ということになると思いますが、とにかく外資系の金融機関はこう見立てていますよということです。
また、特に欧州のメディアは、日本を表現するにあたって、「新興衰退国(NewlyDecliningCountry:NDC)」なる言葉を使うようになりました。私はこの言葉を初めて目にしたとき、あることに気が付いて無性に腹が立った記憶があります。それは“NewlyDecliningCountry”という表現。単数形になっているんですよね。つまり日本一国だけということです。日本は海外からそんな風に揶揄されるところまできてしまった。これまで「失われた10年」と言っていたものが15年になり20年になり…、外から見るとそれだけ無策であったように見られているということだと思います。
もちろんこれは量の話です。たとえば中国があれだけの人口で、かつあれだけのスピードで成長していれば、いずれ量で抜かれるのは仕方がないだろうという捉えかたはあります。実際のところ、2010年には名目GDPで抜かれる訳ですから。ただ、問題は量の話だけでない。「質はいまだに世界一流だと、本当に胸を張って言えるのですか?」という問いかけが生まれているのだと思っています。
世界経済フォーラムが毎年発表している世界競争力指数を、バブルのピークであった1990年と足元の2009年で比較してみましょう。これを見てみると、シンガポールのような新興国がランキング外から入ってきている一方、先進国はずるずると順位を落としています。その分析自体はよくあることですが、米国の競争力は後退していませんよね。日本は残念ながら8位です。
ここでは併せて、同ランキングのなかで日本のどの分野が世界からいまだ評価されており、どこがだめだと思われているのかも詳しく見てみましょう。まずビジネスの先進度(businesssophistication)では、まだ1位です。自信をなくしている最近のビジネスマンからすると「何故こんなに高いのか?」と、少々違和感を持つと思います。しかし、日本には世界一厳しい消費者がいる訳ですし、その要求水準にしっかり応えて細かい差異化をしていくような戦いかたにおいては、日本企業はいまだに強いということです。その一面を見ればものすごく洗練されたビジネスが出来あがっている。これはある意味、BtoBの領域でも同じことが言えるでしょう。
イノベーションについても同様に高い評価を受けており、4位です。新しい技術の種も依然としてたくさん出てきているということですね。問題なのはその技術を活用するフェーズです。イノベーションは4位なのに技術活用は25位。これは何を意味しているか。せっかく良い技術があるのに、それで稼ぐことが出来ていない、あるいは産業として確立させることが出来ていないということです。なかなか世界は客観的に見ているなと思いますね。あと、個人的には高等教育および職業教育が23位、金融市場の成熟度が40位、政府が28位というのも大変気になるところです。
いずれにせよ我々が世界において一流国であり続けようとしたら、質の面でこのような低い評価を受けているという事実を放置しておくべきではありません。まずはこれを大きな問題提起にさせていただきたいと思います。ここまでがマクロです。次はミクロの視点からいくつかのデータを見ていきましょう。
電機業界とビール業界に見る日本の低迷
まず、リーマンショックまでは日本に外貨を稼いでくれる二本柱のひとつであったエレクトロニクス産業における、大手企業の業績と時価総額をそれぞれ見てみましょう。リーマンショック以降の混乱を避けるため、ここでは比較的事業環境が良好だった2007年までのデータを見ていきます。
キヤノンを例外として、日本企業は営業利益率も売上高成長率も総じて大変低いことが分かります。営業利益率で言えば勝ち組と言われる世界のグローバル企業は、この時期10%を超えて15%前後の水準を維持していますし、売上高成長率も海外競合のほうが高い。日本を支える産業であったはずですが、海外の競合には大きく見劣りしています。
さらに産業構造ビジョン2010の議論で用いられた経産省の分析も見てみましょう。まず主要な製品セグメントの世界市場が2001年から2007年までどのように伸びているかを見てみると、多くの製品カテゴリーで市場規模が3倍〜5倍に伸びていることが分かります。しかし日本メーカーの同じ製品カテゴリーにおけるシェアは、それに反比例するように右肩下がりとなっている。成長する世界市場に、日本企業はまったく同期出来ていない。そんな姿が見てとれます。
これは電機業界だけの話かというと、そんなことはまったくありません。次は食品業界における一大セグメントである酒類・飲料市場を見てみましょう。
2008年の世界ビール市場を見てみると、1位はベルギーのAnheuserBuschInBev(以下、ABInBev)。本日詳しくご紹介するビール会社です。ちなみにABInBevをご存知の方はどのぐらいいらっしゃいますか?…比較的少ないですね。InBevについて簡単にご紹介しておくと、2004年にベルギーとブラジルのビール会社が合併して誕生した企業で、本社はベルギーにあります。2008年には時価総額で当時世界3位だったアメリカのAnheuserBusch(アンハイザー・ブッシュ)を吸収合併しました。AnheuserBuschは「Budweiser」をつくっている会社です。こちらはご存知ですよね。たった4年間でこの3社が合体した結果、圧倒的な世界No.1の地位を獲得したという訳です。
2008年現在の2番手はSABMiller。こちらも聞いたことはないかもしれませんが、SABというのは「SouthAfricanBreweries」の略。もともとは南アフリカのビール会社でした。このSABがアメリカのMillerを買収して誕生したのがSABMillerです。そして3位、4位には、みなさんもよくご存知のHeineken、Carlsbergが続きます。業界構造が10年で大きく動いてきたのがビール業界の実情です。
各社の営業利益率を見てみると、ABInBevはなんと26%。また、売上高成長率は過去10年で年率20%です。年率ですよ。2位のSABMillerにしても年率20%というスピードで成長してきました。世界のトップ2社がこのように売上を伸ばし続けているなかで、日本の大手はというとキリンにしてもアサヒにしても営業利益率は10%弱で成長率はひと桁。これが2008年までの状況です。
こういった状況があるからこそ、ここ2年ほどはキリンやアサヒ、あるいはサントリーが色々な形で海外展開しているという現状に繋がっている訳です。危機感はそれぞれ持っているんですね。国内中心の事業展開を続けて、今のままの成長スピードで、果たして我々は生き残れるのかと。
寡占化が進む「グローバル超競争」
ここで今日最初のメインテーマとなる「グローバル超競争」についてさらにお話ししていきましょう。
1つ目は、顧客、サプライチェーン、そして資本市場という3つの面で世界市場の統合が進んでいるということ。それから2つ目は、東欧やBRICsといった新しい成長フロンティアにおける優位性が、グローバルでの規模の経済性に繋がるという点。新しい成長フロンティアにおける戦いが、グローバルレベルでの覇権争いの前線になるということです。そして3点目は、グローバル競争におけるメインプレイヤーには、欧州や米国、あるいは日本といった従来の先進国発企業に加え、中国、インド、ブラジルといった新興国のプレイヤーも含まれているというポイントです。
世界のグローバル市場では急速に寡占化が進んでいます。日経ビジネスは2008年1月、我々が提供した分析データをもとに特集記事を企画しましたが、これによると、ビール業界だけでなくたばこ業界でも急速に寡占化が進んでいることが分かります。ちなみに我々の言う世界寡占度の定義とは、グローバル市場におけるTOP3の合計シェアです。
このほかにもアルミニウム市場はTOP3社で世界シェアの約半分が抑えられていますし、鉄鉱石もTOP3社で市場の3分の1以上が占められています。この寡占度が2000年代以降、年とともに上昇しているのがグローバル競争の実情です。これは資源だけの話でもなければ、川下にある消費財だけの話でもありません。製紙や鉄鋼といった川中の業界でも同様なんです。自分がいる業界だけ見ていれば業種固有の現象に思えるかもしれませんが、実はグローバル競争のダイナミズムがもたらす、業界の垣根を超えた現象と考えるほうが正しいと思います。
グローバル産業の集中化というダイナミズムは何によってもたらされているのか。ここでは新旧の主要なファクターをご紹介します。
1つ目は、従来から続く流れとして、産業の経済性要因が挙げられます。規模の経済性がR&D、生産、マーケティングといった分野で働くということですね。また、要素コストや原材料の品質といった背景から、国による比較優位性も生まれます。国によって優位劣位があるのなら、当然のことながら、グローバル規模に事業を展開して優位なものを組み合わせる企業が強くなる。
たとえば製薬業界で考えてみましょう。同分野で基礎研究の蓄積量が圧倒的にあるのは米国または欧州の一部です。だいたい大学がある街ですね。米国で言えばボストンであり西海岸。そういった場所で基礎研究を行えば、当然優位性も高くなります。では開発はどうかというと、FDA(USFoodandDrugAdministration=アメリカ食品医薬品局)を通すのが一番大切な仕事になるのでアメリカだということになります。そして生産はというと、近年はインド。品質の高い薬を低コストで製造出来るからです。そしてマーケティングは世界全体で行うという構造になります。すると、たとえばアメリカ東海岸の開発センターとインドの生産拠点、そしてそれを世界にばらまく世界中の営業部隊、こういう組み合わせのリソースを持ったグローバル企業が世界でベストのコスト効率を持つことになります。この比較優位性がグローバリゼーションにおけるひとつの大きなファクターになるということですね。これに加えてGATTからWTO、あるいはNAFTAやFTAなど、さまざまな形で進んでいるブロック経済圏の確立もひとつの大きなドライバになっています。
この状況に、過去10年で何が新しいポイントとして加わったかというと、主に4点あります。1つ目は、新しい巨大市場が誕生したということ。その筆頭は拡大EUですね。ユーロが誕生したのは1999年ですから、過去10年ぐらいで新しく加わった事象ということになります。人口5億人、GDPで12兆ユーロ前後の巨大統一市場が、2000年以降に誕生しました。それからBRICs。この概念が世に出てきたのは04年頃ですから、現象として認識されはじめてからまだ10年にも満たないということです。
2つ目のポイントは、サプライチェーンのグローバル統合。これについてはトーマス・フリードマンが『フラット化する世界』のなかで述べています。それはすなわち、情報通信技術の発達と、アウトソーシングおよびオフショアリングの進展です。情報通信技術ということで特に大事なのは、ITもさることながら、通信の海底ケーブルが無尽蔵に敷設されたことで、ほぼゼロコストで通信出来るようになったという現象です。
ITバブルは1990年代末に起こりましたが、実は当時、通信バブルでもあった。そしてバブル崩壊後、世界中に海底ケーブルをひいていたケーブルオペレータたちは2000年代の前半に軒並み倒産していきました。その後、ケーブルオペレータはただ同然で売り払われていったのですが、買った人たちはただ同然でキャパシティを得ているから、やはりただ同然で企業ユーザーに貸し出します。そうなってくると、たとえばアメリカとインド、あるいは欧州と中国などで、無尽蔵のデータをほぼ無料で通信出来るようになった。これが実はグローバリゼーションにおけるひとつの大きなドライバにもなっているんです。
同様に「2000年問題」も大きなドライバになりました。皆さん覚えていますか?もう社会人になっていたと思いますが、2000年直前には世界中の大企業がパニック寸前の状況に陥っていました。2000年を迎えるタイミングでITシステムの多くが止まってしまったり、暴発してしまったりするという可能性に対し、膨大なデバッグ作業が発生していった。そこで1998〜99年、特に欧米の企業はこの作業の大半をインドのSEに任せていきました。これによってインドのSEたちは欧米企業のITシステムを2〜3年かけて熟知していくことになります。
そのあとインドのTataConsultancyServicesのような企業がアメリカの大企業に積極的な提案を行うようになりました。「我々は御社のITシステムをすべて理解しました。ですからITシステムを丸ごと我々に任せてくれませんか?」と。これがITアウトソーシングの流れです。で、ITアウトソーシングが進むと、実はビジネスプロセスもすべて分かってしまう。すると彼らは次にビジネスプロセスそのもののアウトソーシングを提案するようになった。それが海をまたいで行われるようになり、オフショアリングの潮流となりました。ともにITバブル崩壊と2000年問題を乗り越えたからこそ、2000年代に入って実現した、サプライチェーンにおけるもうひとつのグローバル統合です。
グローバル産業の集中化を生んだ3つ目の新しいポイントは、グローバル消費者の誕生です。“ネットによる情報武装”とか“かしこい消費者”なんていうキーワードはずいぶん前から存在していましたが、世界中の消費者が本当にインターネットへアクセスしたのは過去数年の話です。1997年、ほんの1億2000万人だった世界のネットアクセス人口は、10年後の2007年には13億人にまで膨れあがりました。
たとえば中国の消費者がネットで欧米や日本の情報に触れることで何が起きるか。あるとき、上海のネットアンケートで実施された自動車ブランドの人気調査結果を見て私は驚きました。当時はまだ上海に1台も走っていなかったトヨタの「レクサス」が、なんと2位に入っていたんです。実際には店舗もなく売られていないというのに、ブランドが出来あがっている。そいうことがネットの時代には起こり得る。ネットによって、グローバル消費者は強大なパワーを手にしました。
そして4つ目のポイントは、資本市場の発達とグローバル統合。これは言わずもがなだと思います。しかしこの世界のM&Aゲームについて言えば、金融技術の発達、ファンドの成長、新興国マネーの参入といったファクターが実情以上に光を浴びて語られることがこれまでは多かったと言えるでしょう。実際には、グローバルな産業集中化というのは、数多くのファクターが2000年代に効いてくるとともに発生してきた。つまり資本市場だけの話ではまったくないというのが、私の見方です。
こういった新旧のファクターに加えて、仮に自分の業界が無風だったとしても、隣の業界で何かが起こると一気に飛び火するような産業構造になったことも大きなファクターです。たとえば先程お話しした製鉄業界の寡占化が日本で最初に起きたのはどのタイミングだったか。世界中の自動車業界で“400万台クラブ”という神話が流布されていた時期です。「自動車メーカーは年間400万台を生産しないと規模で負けてしまう。だから業界再編が起こるだろう」と言われていたのが90年代末ですね。実際のところ、自動車業界にはいくつかの再編が起こりました。しかし、実は同じ時期に川上となる資源メジャーの寡占化も静かに進行していました。すると鉄鋼メーカーは、川上である資源業界の寡占化、そして川下最大ユーザーである自動車業界の寡占化に挟まれ、どんどん交渉力が弱くなっていきます。そうなると、「日本に製鉄会社が4社も5社もあったって、板を安く買い叩かれるだけ」という話になっていった。それで2グループに集約していったというのが、2000年代前半に起きた鉄鋼業界の再編劇です。
国内のシェア争いに経営資源をつぎ込む日本企業
こういったグローバル競争の大きな構図があるなかで、日本勢はなかなか勝利出来ていないことは、電機および食品業界の例で先程ご紹介した通りです。その理由の1つとして知っておいてほしいのが、それぞれの国が拠点としているホームマーケットの構造です。まず、縦軸に液晶テレビや原子力といった最近注目されている産業セクターを、横軸には日本、北米、欧州、アジアといった地域を並べてみましょう。ここでそれぞれのセルに主要プレイヤーを記していくと、たとえば液晶テレビは北米でVizio1社、欧州でPhilips1社、アジアでSamsungとLGと、数は限られてきます。しかし日本のセルにはプレイヤーの名前がたくさん入ってくる。さらにひどいのは鉄道ですね。実に多くのメーカーが1つのセルでしのぎを削っています。ちなみに世界の鉄道車両における日本のシェアはたかだか1割。1割しかとれていないのにこんなにたくさんの会社があるんです。最近注目を集めている水ビジネスでも同様です。
これは日本市場がそれなりに肥沃だったということもあるし、日本市場固有の要件に対応出来るのが日本メーカーだけだったという背景もあるでしょう。しかし日本市場が伸びている時代ならまだしも、これから先さまざまなセクターで市場が縮んでいく国内にあって、これほど多くの会社がシェア争いをしている状況で本当に問題ないのでしょうか。これについては我々も経産省と色々と議論しました。その結果として、産業構造ビジョン2010には、「国内の産業再編を進めるべし」という色合いが相当強く出ています。
ちなみに韓国と日本で、主要企業1社当たりのホームマーケットの規模を比べてみると、殆どの産業で韓国企業が日本企業のそれを上回っています。これは何を意味しているか。韓国企業は産業再編によって国内市場の寡占状態をつくりあげ、国内マーケットを“キャッシュフローを得る場”に位置付けているということです。そのキャッシュフローが新興国を中心としたグローバル展開の原資になっている。そういう循環を、韓国はIMF危機以降、国をあげてつくってきたんですね。しかし日本企業の多くは残念ながら、いまだ国内の市場競争が激しいので持てる経営資源の多くを国内シェア争いに投下している。国内で稼いだお金を海外に投下する好循環になかなか入ることが出来ていません。
シンガポールが象徴する苛烈な「Warfortalent」
以上、本日1つ目の大きな視点ということでグローバル超競争に関するお話をしました。ここからは、2つ目の問題提起に移りましょう。人材です。グローバル競争は市場や顧客をめぐる競争であると同時に、実は人材をめぐる企業または国家間の獲得競争でもあるということです。ここでは人材戦略という意味で長年トップランナーだったと私が考える、シンガポールの事例を見ていきましょう。
シンガポールの人材戦略は簡単に言うと、自国民を徹底的にアップグレードすることと、世界中の有能なタレントを一本釣りでどんどん連れてくることの2つで成り立っています。自国民のアップグレードという側面では、たとえば高学歴女性の出産奨励政策があります。これは平たく言えば、「子どもをたくさん産みたいのであれば高学歴になりなさい」という政策です。こういった政策は時期によって色々と変遷していますが、80年代以降で言えば大学院卒以上となる女性のご子息は優先的に初等教育受けることが出来るという政策がありました。減税の措置も受けられます。逆に学歴の低いカップルには、たとえば3人目の子どもから重税を課すなどの、過激な政策が実施されたこともありました。もちろんこれには「人道的にどうなのか」という声があるでしょう。日本で政治家がこんなことを言えば袋叩きになります。政治家でもない私だからこんな話も出来るのですが、とにかく自国の人材を強化するためにここまで徹底した政策を打っている国も世界にはあるということです。それとどう戦うかがまさにグローバル競争におけるひとつのポイントにもなっていきます。
それから国際人材プログラム。「manufacturing2000」と呼ばれていた90年代のシンガポール産業政策は、エレクトロニクスと化学を国策で育てようというものでした。この2つの産業を中心にして、シンガポールは90年代、国が企業団をひき連れて欧米のキャンパスにリクルーティングツアーを行っていました。そこでオファーを出した学生に対しては政府が入国、住居、渡航など諸々の便宜をはかり、その場でギャランティも出す。そんな力の入れようでした。
さらに2000年代に入ると、今度は世界中からノーベル賞級の頭脳を一本釣りでシンガポールへ連れていくという政策をとりはじめた。今年、堀(義人・グロービス経営大学院・学長)さんがやっているG1サミットに、日本を代表する科学者の方々も何人かいらしたので、そこで「海外からお誘いが来ていませんか?」と訊いてみたのですが、やはり多くの方々が、「あ、シンガポールから来たよ」と仰っていました。
世界はこうして激烈な人材獲得競争をしています。日本からノーベル賞級の先生が出ていくこと自体を悲しむ必要はないのかもしれませんが、とられる一方だったら日本は滅びます。人材も取り合いなんです。少なくとも取られるのと同じ数、あるいはそれ以上を日本に吸引出来るような研究環境を、国内に持つべきではないでしょうかという問いかけが生まれます。
ABInBevが象徴するグローバル超競争のリアリティー
ここで改めて個別企業の戦略に触れていきましょう。先程ご紹介したABInBevについて少し駆け足でお話したうえで、同社CEOであるCarlosBritoのインタビュービデオをご覧になっていただこうと思います。繰り返しになりますが、InBevは2004年当時、ベルギーのInterbrewが、ブラジルでシェア7割ぐらいを押さえていたAmBevを買収して誕生しました。AmBevは、2000年にブラジル国内で1位と2位のビール会社が合併した企業です。言ってみればアサヒとキリンが合併したようなものですからブラジルでは圧倒的にNo.1。ブラジル以外でも、アルゼンチン、チリ、ウルグアイ、パラグアイでNo.1でした。Inbevは続いて、2008年に「Budweiser」を擁するAnheuserBuschを買収し、ABInbevになった訳です。
買収に買収を重ねていた訳ですから当然ながら売上高はうなぎ登りですが、ここでさらに重要なのが営業利益率です。もともと10%強だったものが25%超まで上がっていきました。ではInterbrewを主語としたとき、彼らはどういったタイミングで世界展開をしていったか。2004年に合体したInterbrewとAmBevは、実に違ったキャラクターの2社でした。結果を見ると、この2社が本当にうまくハイブリッド化して世界最強のビール会社が誕生したように見えます。
まずInterbrewは欧州でプレミアムブランドのポートフォリオを持っており、一部新興国のローカルブランドも買収する。新興国市場が伸びてきたら、そこで買収したブランドの持つ流通網に、欧州発のプレミアムブランドを重ねていくという戦略を採っていました。
一方のAmBevは何が強みだったかというと、徹底した効率経営。業界No.1の効率であると当時から評価をされていました。親会社がInterbrewでAmBevを買収したという形ですが、そんな2社が合体することでAmBevが持っていた効率経営をInterbrewのオペレーションにも全面展開していったのが2004年以降です。グローバルでの標準化ということになりますね。
さらに2007年以降は標準化だけではなく、世界中で百数十に広がった生産拠点の統廃合をグローバル最適化という形で行っています。主に欧州の工場を閉めて新興国の工場を残すという方向でした。
それからもう1つ、日本のビール会社であれば、準コア事業になっているような清涼飲料事業やパブ事業を、ほぼすべて売却しました。儲かっているにも関わらず、です。そしてその売却益をビール事業におけるさらなる投資に向けていったという集中ぶりです。
AmBevのオペレーションエクセレンスということで、象徴的な施策も2つほどご紹介していきましょう。1つは、毎年のゼロベース予算をかなり真面目にやっているという点。どこの企業もそうですが、多くの品目について基本的には対前年で何%減らそうとか、そういったやりかたですよね。でもAmBevは毎年ゼロベースです。もう1つは、グローバルで工場オペレーションを標準化すること。こちらについては合併した翌2005年、世界の55工場にわたってオペレーション標準化の同時展開を実現していきました。そんなすさまじいスピード感で経営しているということです。当然社員だけでは出来ませんから、我々のような経営コンサルも大量に雇い、ひとつのメソドロジーのもと世界中で標準化を徹底していく。そんな戦略でグローバル効率化を推進していきました。
それを経営ビジョンレベルで表現すると「Shiftfrombiggesttobest」という言葉になります。これは2005年の経営ビジョンですね。「我々は合併によって最大のビール会社になったが、最大なだけではなく最高のビール会社になるのだ」と。ここでいう最高というのは最高効率という意味です。それぞれ異なる強みを持った2社が合併して、ブランドや地域市場を買収するという意味でさまざまなM&Aを繰り出し、その結果として世界シェアが大きくなる。しかもオペレーションの効率化を行うので利益率も上がり、時価総額も上昇するから投資家から見ても評判が良い。こんな好循環サイクルのなかで、凄まじい成長を約6年間続けてきた会社なんです。
ではこのABInBev、どんな経営陣が引っ張っているのでしょうか。現経営陣はブラジル人中心です。2004年の買収後、取締役会は2005年に当時のベルギー人CEOのクビを飛ばしました。そして買収先のAmBevで効率経営を引っ張っていたCarlosBritoという当時40代前半のCEOをベルギー本社まで連れてきた。そこでBritoは自分の右腕たちをベルギーに多数連れてきて、このベルギー+南米の世界帝国をマネジメントするチームが出来た。このあとAnheuserBuschも買収していますが、基本は同じチームでやっています。
そのCarlosBritoですが、CNBCTVで2009年秋に行われたインタビュー映像がありますので、こちらを一部ご紹介致します。
皆さん何を感じられましたか?これがグローバル競争で世界をリードしている会社のCEOです。
コア事業の成長を徹底追求するグローバル競争の覇者、事業領域を広げる日本企業
ここから先は、日本企業が直面している課題、あるいはグローバル化を加速するうえで何をしていくべきかということについて、ヒントというレベルに留まりますがいくつかお話をさせてください。
まず、ABInBevを含め、Samsung、Vodafone、Google…、そういったグローバル超競争の覇者は、「市場はグローバルだ」と考え、市場領域を広げているということです。海外である意味愚直なまでに市場をとっていく。しかしその一方で、事業領域はむやみに広げていきません。滲み出しはもちろんあるけれども、どちらかと言えばボリュームという縦軸を重視する戦いかたをしています。そのため、コア事業に必要な基盤や組織力を徹底的に強化していく。そんな戦いかたをしている企業が世界で強い。
これに対して日本企業は、もちろん外には出ていきますが、そこで少しばかり“やけど”をするとすぐに手を引っ込めてしまう。さらに一番の成長軸は事業領域という横軸でした。国内市場でどれだけ新しい製品カテゴリーをとることが出来るか。たとえばメーカーなら製品領域からサービス、さらには金融にまで事業領域を広げていき、事業モデルを高度化していく。
これは「何もしていない」という意味ではありません。知恵は、もしかしたらグローバル競合以上に使っているのかもしれない。けれどもその知恵の使いかたが国内での事業高度化や複雑化、あるいは事業領域の拡大という横軸に向いてしまっていた。これが少なくともリーマンショックまで、多くの業界における日本企業の戦い方だったように思います。そして国内大手の地位に、厳しく言えば「安住」し、中途半端な海外進出と撤退を繰り返している。もちろん自動車業界や建機といった例外はありますが、総合電機と言えどもこのパターンにはまっていた会社が多かったんですね。ましてやそれ以外の内需型産業は言うべくもありません。
では、縦軸で強烈にアクセルを踏んでいくという意味でのグローバル化が何故進まないのか。私はこんな問いを2005年ぐらいから日本の大企業に投げはじめていましたが、その頃からよく以下のような話をあちこちで聞かされました。
・大きな国内市場
・独自のニーズを持つ日本の顧客
・日本企業特有の風土、雇用慣行
・日本語の壁、国際化人材の欠如
・外国人のマネジメントの難しさ
もちろんこれらがすべて嘘という訳ではありません。ただ、私としては、「言い訳」と思います。日本企業が向き合うべき真の課題とは何でしょうか。
短期志向に陥った日本企業
まず戦略について。そもそも日本企業はいつの間にこれほど短期志向になってしまったのでしょうか。世界を見ていないだけでなく、「気が付いたらずいぶんと短期志向になっていませんでしたか?」というのが、ひとつ目の問いかけです。一昔前はアメリカから「日本の経営は長期志向だ」と称賛されていた。
「10〜20年先を考えた投資や人材育成をしている」と。ところが失われた10年〜15年を続けているあいだ、日本企業も背に腹が代えられなくなってきてしまった。とにかくこの3年でどう会社を立て直すかを追求した結果、2000年代前半のV字回復に繋がった。でも実はそのV字回復の成功体験が、成功の呪縛につながっている。「これから3年間で出来ることをコミットメントとして掲げ、それを徹底的にやるんだ」という経営から脱皮出来なくなってしまった会社が多かったように思えます。
そんな状態で海外展開を行うとどうなるか。10年先のインド市場を10年かけて開発しようなんていう発想にはならない訳です。今日本で持っている製品群を少々ファインチューンして中国に持って行けば、「中国の消費者は日本に近いから売れるよね」と。それで「3年以内にもしかしたら黒字転換出来る」と考え、日本と近い市場には出て行くけれど、日本と離れている市場にはいくら拡大すると分かっていても行かない。こんな戦い方になっていたように思います。
グローバル戦略というからには、グローバル市場全体を俯瞰して「ここが伸びる」、あるいは「ここで勝てる」という見立てをつくる必要があります。そこで勝てるからこそ、一気に資源を配分することも出来る訳です。もちろん、個別のマーケットごとに製品開発をしていたらコストがかさむので、可能な限りグローバルで共通製品を売りたい。だからどのように国外市場をクラスタリングして、グローバル共通商品“A群”や新興国ボリュームゾーン商品“B群”をつくり、それを世界全体でどう効率的に展開していくか考える。これがグローバル戦略です。
そういう意味で、グローバル化にはトップダウンによる長期ビジョン、または戦略の策定と提示が欠かせません。
自社のポジショニングを把握して、世界市場のどこを獲るかという戦略的フレームワークを作成すること。具体的には、もう見慣れたフレームワークですが、ひとつが地域軸で、もうひとつは製品セグメント軸ですね。このなかで「どのセルをどのように取っていきますか?」ということです。企業としてグローバル展開していくにあたり、どこで圧倒的に勝つかを明示出来ているか。皆さんもぜひご自分が勤める会社で確認してみてください。
ここで大事なのは、「そこにも、あそこにも」と全部を塗ることではなく、どこで圧倒的に勝つかを明示的に追求することです。どこでも勝てず、まんべんなく広がっている会社というのが一番危険です。
このほか、製品軸で戦おうということであればグローバルでプレミアム戦略を採るという戦い方や、あるレイヤーをひとりで総取りするというレイヤーマスターの戦略も考えられます。また、地域軸で戦おうということであれば、広域地域市場のドミナント戦略や新興国のボリュームゾーンを中心に攻めるといった戦略も考えられます。
しつこいようですが、もう一度お話しします。たとえば「我が社はアジアフォーカスだ」と、海外展開を掲げている企業は恐らく大企業の5〜6割以上にのぼると思います。しかしアジアフォーカスと言っている会社のなかで、本当にアジアNo.1になろうとしている会社はどれだけありますか?本当にアジアNo.1になる勢いでアクセルを踏んでいますか?そういう問いについて真剣に考えていただきたいと思っています。
となると、たとえば「中国市場が年率10%以上のペースで拡大しているから、我々も中国での売上高を年率10%で伸ばしています」では、戦略とは言えません。だってそれなら中国でもNo.1になれない訳でしょ?ましてやアジアNo.1になれる筈がない。そのままではいつまでたってもグローバル競合の背中が近くはなりません。遠くなることはあっても。
今や国対国の産業政策競争の時代に
最後になりますが、グローバル超競争では技術革新とともに、国対国の産業政策競争も進んでいます。日本は韓国との比較で見ていただいた通り、国内産業がばらばらであるためになかなか世界でうまく戦えていません。その状況を打破するひとつのきっかけとして有り得る話が、「生態系輸出」というストーリーです。たとえば原子力や火力発電設備に高圧の送電設備、さらには発電オペレーションをセットで売っていく戦略です。製造業とサービス業をセットで売っていくということであり、東芝や日立といった重電メーカーと東京電力やJ-POWERのような電力事業者がセットで海外の大型案件をとりに行く。そして発電所を納入する設備需要だけでなく、その先20年〜30年と続く発電オペレーションやメンテナンスの需要をとりにいくという戦い方です。
同じような戦略は鉄道や通信のインフラでも有り得ます。南米ではなんと8カ国が日本の地デジ規格を採用しましたが、その規格で映る薄型テレビを南米で誰が売っているかと言えば、SamsungとLGです。もったいない話ですよね。
さらに言えばEVのエコシティ。最近では「スマートシティ」とか「スマートコミュニティ」とか、色々な呼びかたをされていますが、不動産開発の領域から街のコンセプトを考え、分散型発電を行うエコタウンをつくるという事業です。ここにマイクログリッドやスマートメーター、あるいは充電ポストといった関連サービスを組み合わせたら、相当大きなプロジェクトになりますよ。しかも日本はそれら分野ですべて技術要素を持っています。それを組み合わせて大きく売りましょうというのが生態系輸出ですね。冒頭でお話しした経産省のインフラ輸出戦略でも同じような見方がなされています。
そんな形で、本日は多岐に渡るお話をさせていただきました。私のプレゼンテーションは一旦これで終わりたいと思います。


%20(19).png?fm=webp)


















.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)
.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)
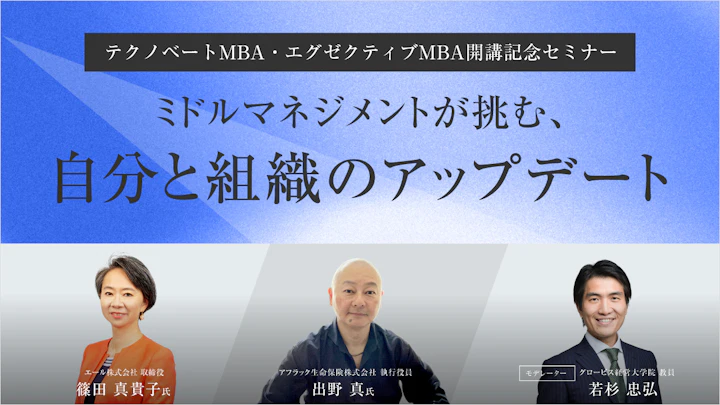
.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)


.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)

















.png?fm=webp&fit=clip&w=720)
.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)

