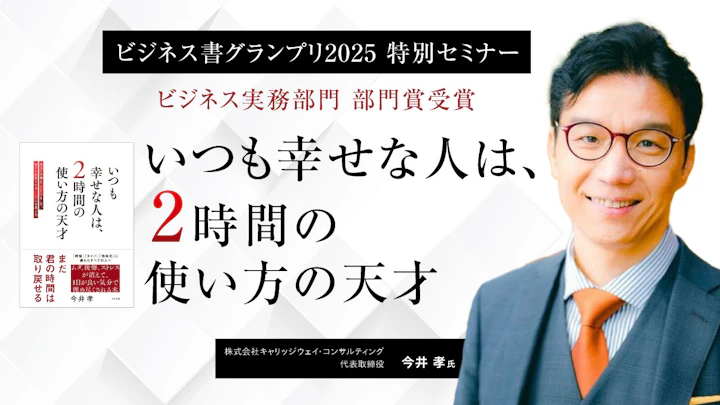鎌田:皆さんこんにちは。ご覧の通り本日はとても良い天気で、思わず外に見えるプールで泳ぎたくなってしまう感じです。しかし今日はそこをぐっと堪えながら真面目に、一方では楽しく議論していきましょう。
まず議論の前に少々構えますと、日本の産業人材がこれからの日本をどう構築していくのかという点が、今回お集まりいただいた皆さんにとっての大義かと思っています。その中で、業種や企業の垣根を超え、まず我々自身が当事者としてどうあるべきか。このあたりに視座を置きましょう。
本会議の目的を再度確認しますと、少々きざですが“Shaping the future of leadership” つまり、将来におけるリーダーシップのあり方を考えていこうじゃないかという問いかけが、大きなメッセージになると思っています。アジェンダは企業を支えているミドル層・・・、間違いなく次代のリーダーになっていくミドル層の、今後に向けたあるべき姿を模索することです。そして、そのような次代を担う人材が力強く輩出されていくために我々が何をすべきか。ここにゴールを設定しつつ議論していきましょう。
人口減少、国際競争力の低下…今、我々が考えるべきは何か(鎌田)

鎌田英治
議論を始めるに際し、皆さんの視界または風景も合わせておきたいと思います。各々の問題意識という意味合いでは事前にご協力いただいたアンケートの集計結果をお手元に配布しました。併せてマクロ環境の現状、グローバルなビジネス環境において日本の地位がどうなっているかについても確認しておきましょう。資料には表題を「量と質の両面における地位の低下?」と、末尾にあえて疑問符をつけましたが、これは地位低下であってはいけないという気持ちがあるからです。量とは人口動態であり、質というのは競争力、ここではスイスのビジネススクール、IMDの報告書からデータを引いています。
まずは量について見ていきます。日本の人口減少という大きな流れはなかなか抗しがたい動きかと思います。日本経済研究センターは世界における日本の人口シェアが2050年には20位になると予測していますね。1950年は5位で全世界の3.3%を占めていましたが、2005年には2%、2050年には1%まで縮小するとされています。購買力平価ベースのGDPも2005年には世界4位だったものが2030年に5位となり、1位との相対比は0.15%に低下すると予測されています。
一方、質の面はどうでしょうか。IMDが発表した「世界競争力報告書」によると、2010年現在、日本の国際競争力は27位となっています。全般的にアジア諸国が右肩上がりであるのに対し、日本の競争力は低下を続けており、なかなか厳しい状況です。欧州の成熟国も総じて日本と同様に右肩下がりの基調を示しています。先進国ではアメリカだけがランキング上位を維持しています。それにしても1993年には日本はなんと1位でした。これをどう考えていくべきか。もちろんIMDのランキング自体はひとつの見方ですから、すべて鵜呑みにする必要はないと思います。これは企業経営者がどう思っているかという認識をベースとしたようなアンケートである点も、また事実として押さえておかなくてはいけません。ただ、こういったいくつかのデータが我々に何を投げかけているのかは、ご一緒に考えていきたいと思います。
皆さんからのアンケート集計結果も見てみましょう。まず、経営のなかでグローバル化への対応をどのように位置づけていますか、という設問については、約8割が「重要課題」(最重要課題43%、重要課題の一つ38%)と認識、また、会社を取り巻く現在および5年以内の競争環境をどのように認識しているか、という設問については、9割が「有事である」と回答されています。
他に定性コメントも多数いただいていますが、これらが何を意味するのか。端的に言えば、「我々がこれから考えるべきことは、普通のレベルではだめなんだ」ということです。思考の次元や考える基準をぐいぐい上げて、「そんな程度のものではないんじゃないんでしょうか?」といったディスカッションにしていく必要があると思っています。従ってこの先の議論は、「視野と発想を広げること」「網羅ではなく、焦点の絞り込みをすること」「問題分析ではなく、どうしたら解決出来るかを考えること」「悩み抜かなければいけない側面と向き合い、考え抜くこと」などを流儀として揃えたいと思います。
今回のCLO会議は2日間3部構成となっており、冒頭はパネル討議を通じて「今、日本企業に求められるリーダーとは」ということを主に経営視点から議論します。その後、実在のビジネスパーソン4人を題材としたケース討議を通じ、主に40歳代のリーダーがどのような成長課題にぶち当たっているのかを現場視点から理解します。この経営視点と現場視点のギャップを意識しながら、ではどのようにしたら、そのギャップを埋められるかを考えるのが最終セッションとなります。
早速、最初のセッションを始められればと思いますが、ここではまず、島本パートナーズ代表取締役の安永雄彦さんと、カルチュア・コンビニエンス・クラブ(以下、CCC)の前代表取締役COO柴田励司さんにそれぞれ、先ほどのアンケート項目にも挙げた「グローバル化への対応」「有事における経営」といったことを切り口に、こうした環境下におけるリーダーの要件について、お話しいただきます。そのうえで会場の皆さんともインタラクティブに対話し、「今の日本企業には何が欠けているのか」という“WHAT”を絞り込むとともに、なぜ、それが育まれていないのかという“WHY”を浮き彫りにしていきましょう。では早速、安永さんから、主にグローバル化を切り口にプレゼンテーションをよろしくお願いいたします。
20数年前の私は言わば日本企業のグローバル化の尖兵だった(安永)

安永 雄彦氏
安永:ご紹介ありがとうございます。私は、エグゼクティブ・サーチと言って、経営者や経営幹部を企業の依頼にもとづいて探す、いわゆるヘッドハンティングを本業としています。その傍ら、グロービスで人材マネジメントや組織行動学といった科目の講義も持っています。
いただいたテーマは主にグローバル対応に関連したところということで、まずは私が過去、海外でどんなことを考えてきたのかを、最近の日本企業に関する問題意識も交えながらお話しさせてください。
私の職業人生は銀行員からスタートしました。約22年間を、現在では東京三菱UFJ銀行に統合された旧・三和銀行で過ごしました。大阪で8年勤務したのちにロンドンに赴任し、帰国してからは東京、名古屋、そして改めて東京で勤務しています。そんな経歴のなかでも、私自身、非常に学ぶところが多かったと思うのはロンドン支店にいた時代です。1987年のその当時、邦銀の格付けは皆AAAで、世界の上位10行のうち9行を邦銀が占めるという時代でした。ですから当時は「海外で儲けよう」というドライブが強くかかっていまして、国内の人材も大量に海外へ動員されていた。私もそのひとりとして、当時は英語がまったく出来なかったにもかかわらず、ロンドンへ赴任することとなりました。英語の研修も留学も一切なし。で、非日系営業チームでただひとりの日本人行員として、イギリス人シニアマネージャーの後を継いでくれと言われ、言葉、仕事、文化すべてに障壁のある中で働き始めました。20年前のこととなりますので、いわば日本企業のグローバル化の尖兵として働いたと言っていいのではないかと思います。
そこで4年間勤務したのち、上から突然「ケンブリッジの博士課程でちょっと勉強していらっしゃい」と言われて留学することになりました。その後、日本に戻ってからも色々なことをやった訳ですが、主に本部でグローバル戦略の策定、それまでのグローバル展開に関する反省、あるいは中長期計画の立案といった仕事を担当するようになりました。
それまでの海外展開の結果は実際のところどうだったかというと、1992年の時点では、殆どの投資が累積収支採算ベースで失敗していました。同じお金を英国債ファンドに投資していたらどちらが得だったかを計算すると、明らかに何もせず英国債を買っていたほうが儲かっていたという数字が出たんです。その数字をもとに次の中期計画を策定していった訳ですが、この結果にはショックを受けましたね。三和銀行のグローバル戦略に関する当時のキャッチフレーズは「世界のベストユニバーサルバンクを目指す」というものでしたが、「どこがベストだって言うんだ」と感じたことをよく覚えています。
その後、私自身はJR東日本へ出向になりました。そこで新規事業の企画担当課長となりましたが、ここでも色々と新しい経験をしました。担当した新事業の結果を見ると成功と失敗が半分ずつぐらいですが、いずれも私にとっては大きな経験になった。銀行カルチャーの外へ飛び出し、異文化のなかでまったく違う視点を身に付けることが出来たのではないかと思っています。
そして改めて銀行に戻ってからは支店長をやったり、再度、企画職に就いたりしていましたが、行員時代最後の仕事として、消費者金融のモビットという合弁会社の立ちあげに参加しました。これもまた異文化の衝突ですね。カルチャーのまるで異なるプロミスという会社と、ほぼ毎日のようにお互い掴みあわんばかりの喧嘩をしながら新会社を立ちあげていった。ここで私は、自信を持っていた銀行員としてのものの見方や常識が、いかに違う業態では意味を成さないのかということを学びました。
その後は時代の流れとともに銀行も左前になり、自分が再度踏み出したいと思っていたグローバルな舞台がどんどん売却されてしまった。それで銀行からは離れ、独自の道を歩むことにしました。46歳のときです。まずは米国系の会社で4年、そして今の会社に移って6年。足掛け10年間、エグゼグティブ・サーチの世界で学んでおります。最初の2〜3年はITバブルの際の残り香もあったため、外資系の仕事が中心となりました。2000〜2001年頃ですね。しかし9.11以降はそれもなくなり、日本企業の仕事を中心とするようになって現在に至ります。
経営者選出プロセスは日本式、欧米式で大きく異なる(安永)
これら経歴を踏まえ、グローバル化や有事対応といった今回のテーマに関わる私なりの問題意識の一つは、経営者、経営幹部選出のプロセスにあります。
基本的に、未知の領域に踏み出していこうというとき、多くの会社は「(社内で)最も優秀な人を充てれば何とかしてくれるに違いない」と考えます。しかしそれが殆どの確率で失敗する。たとえば、「日本の銀行が海外の銀行を買う」というぐらいの展開の仕方であれば、それで成功するように思うでしょう? しかし私が行員だった当時、海外にたくさんの日本人行員を送り込み、日本人が頭取となって進めていった三和銀行の海外戦略は、殆どが儲かっていなかったのです。ここに、どんな落とし穴があったのか——。
ヘッドハンティングを生業とする私が言うのも変ですが、会社の外から、誰かが探してきた経営者がやって来るというのは、不幸な事態ではありますよね。内部には経営者や経営幹部として適格な人材がいないということですから。
それでも私としては、グローバル化して欧米の企業と真っ向から戦っていくためには、外部から取るという選択肢も含めた、欧米型のプロフェッショナルな経営者選出への移行が必要ではないかと考えています。無論、そういうプロフェッショナルを内部で育てていくためのプロセスも、今後さらに重要性を帯びてくると思っています。私自身、そういう見方をするようになったのは、銀行を離れ、大企業を離れ、ヘッドハンティングをするようになってからですね。組織の内側にいて、組織のためにと働いている頃には、どうしても持てない視点であったと思っています。
トップを外部から選抜せざるを得ないというのは、確かに不幸なことではありますが、英米などではボードメンバーからなる指名委員会が、社内外双方の人間を並べて選ぶプロセスが一般的です。なぜかと言えば会社にとってベストな人材を選ぶことが当然の前提だから。こういう発想は日本ではまだ一般的ではありませんね。たとえば皆さんもよくご存じの事例で言うと、IBMは1993年のCEO決定にあたり、内部と外部、両方の候補者を並べています。外部からの候補者については我々のようなヘッドハンティング企業2社が関わり、有力な候補者を挙げていきました。求められていたのは上場企業におけるCEO経験、経営戦略の策定や実行に関する経験とスキル、さらに経営再建の経験とスキルといった条件です。そのなかから、皆さんご存じのルイス・ガースナーが選ばれた。当時彼は51歳でした。ハーバードでMBAを取得後にマッキンゼー・アンド・カンパニーのディレクターを経て、アメリカン・エキスプレスとRJRナビスコのトップを歴任していたので、51歳でも既に3回目のCEO就任です。
同様の事例は日本にもあります。我々がエグゼクティブ・サーチとして参加した、ある流通・飲食企業の案件をご紹介しましょう。売上は1500億〜1600億円ぐらいでした。その際の候補者の条件は、50歳代半ばでコンサル出身、かつ経営トップの経験がある人といったものです。最初に89人のロングリストをつくり、そのなかから35人にインタビューを行いました。そして有力候補者を8人に絞り、最後にそのなかからCEOが選ばれた。このように選んでいくのがエグゼグティブ・サーチの実態です。
かたや旧来型の日本式CEO選抜はというと、多くの場合、現社長が後継者を決めていきます。社長は自分と相性の良い人物を指名し、自身は会長として残って実権をはなさない。そんなケースがよく見受けられますね。ただ、今はそういうことをやっていて良い時代ではない。より高い危機感を持った、有事のCEO選びこそ日本企業に求められている大きな課題の一つだと思っています。
社長選抜における欧米式と日本式の違いは、明らかです。前者の決定基準は企業価値を長期的に増加させられるか否かですが、後者は現社長との相性とか、人格とか、はたまた「彼はこれまで良くやっていたから」とか、そんな要素で決まってしまいます。しかも選考プロセスは密室内に閉ざされ、ある日、突然に決まります。逆に、急にクビにされてしまうことだってあり得る。皆さんの会社がそうかどうかは分からないのですが、多くの企業で起きていることとして、この違いはまず認識しておいたほうが良いように思います。
“今”の延長線上に変革型リーダーはいないかもしれない(安永)
ここでちょっと別な角度からも考えてみましょう。グロービスの授業でもよく話すことですが、視点の重要性についてです。
そもそも私たち一人ひとりの頭のなかには、物事のありのままの姿やあるべき姿を、自分なりに描いたさまざまな“地図”がある。自分の経験はすべて、頭のなかにあるその地図に照らして解釈するわけです。しかしその地図が正確なのかどうかに疑問を抱くことは滅多になく、そんな地図が自分のなかにあることすら気づいていない人もいる。自身のフィルターを通った絵姿であるにも関わらず、それが物事のありのままの姿、あるべき姿そのものでもあると思い込んでいるケースがかなり多いのではないでしょうか。
ですからここで皆さんに提議したいのは、仮に皆さんが現在の日本的経営のあり方を、「○○をもっとブラッシュアアップすれば将来のグローバル化や有事対応の出来る人材輩出につながるのではないか」などと暗黙の前提のように考えてしまっているとしたら、まずその前提から疑ってみませんか、ということです。もしかしたら、現在、積み上げているものの延長線上には新しい変革型リーダーは出て来ないのかもしれない。そんなことを私は思うのです。
それならどうすれば良いか。我々の企業を救ってくれる次代のリーダーとは、少なくとも、今あるものを壊す発想や気概を持った人材ではないかと私は考えています。現実や課題を直視する姿勢と視点の多様性を持ち、国内だけで通用する考え方ではなく、より広い考え方から立案を行う。そして何より、変革にコミットし、実行に伴うリスクを取る覚悟がある人材であるということ。失敗すればクビという厳しさを受け入れられる人ですね。もちろん、異文化を許容したうえでマネジメントするスキルと行動力を持つ人材であることも大切です。日本固有の良さも大事ですが、日本的なものというのはグローバル環境のなかでは異質に捉えられています。ですから中国にあってもインドにあってもアメリカにあっても欧州にあっても…、まずは異文化をきちんと受容できることが、次代を担う変革型リーダーには不可欠ではないかと思います。
では現状、変革型経営人材を選出あるいは育成していくために何をすべきか。これは明日議論する予定の“HOW”にもつながりますが、第一に、経営者選抜において外部人材の導入に躊躇するのは、そろそろ終わりにすべきと、私は思っています。内部選抜型人材と外部人材を多様性のなかでうまく受け止めたうえで、企業の成長を図るべきではないでしょうか。
二番目に、これはある意味当たり前ですが、経営者の積極的な世代交代を進めるできです。50代で“若手社長”と言うのは、グローバルで戦うにはちょっと厳しいのではないかと思います。40代のリーダーが経営のトップになり、10年、20年をかけて変革を推進していく。そんな欧米型の人材登用に出来るだけ早く辿りつくべきだと考えています。
そして三番目。そのために経営責任を明確化して、出来たか出来ないかに関する信賞必罰を明確にすべきだと思っています。コミットメントを達成したらそれだけの報酬を受け取り、ダメなら潔く退場。そんな、曖昧さというものとは逆に位置づけられるマネジメントを実現しないとグローバルな競争環境では、とてもライバルに太刀打ち出来ない。最後は少々急ぎ足になりましたが、プレゼンテーションは以上で終わりたいと思います。
鎌田:ありがとうございました。今挙げていただきました課題についてはのちほど改めて整理したうえで議論につなげたいと思いますが、その前に、柴田さんから、こちらは主に有事対応を軸にプレゼンテーションをお願いします。
CCCでは88社を実質1社にまで絞り込んだ(柴田)

柴田 励司氏
柴田:ありがとうございます。本日は、10年来のお付き合いである安永さんより知己を得て、こちらに伺いました。私自身、過去に「そろそろ次の進路を考えてみようか」というタイミングになると、なぜか安永さんの顔がほわんと浮かんでくる。そういう関係ですので、こうして皆さんの前で並んでお話をしているのは少々不思議な心地がします。
簡単に自分の経歴を申し上げると、私は、この6月まではカルチュア・コンビニエンス・クラブ(以下、CCC)の代表取締役COOを務めていました。CCCで3年ぐらいかけてやろうと言っていたミッションが2年4カ月で終わりました。「まあ早く終わる分には良いだろう」ということで、任期満了として退任し、現在は自分の会社Indigo Blueの経営をしています。
これまでの職業人生を振り返り、様々な仕事をしてきましたが、一番長かったのはアメリカのマーサーというコンサル会社にいた13年間です。このうち7年は日本法人の社長を務めておりました。最期の2年はアジアパシフィックの上級副社長とグローバルリーダーシップチームのメンバーも務めておりました。このときはニューヨーク、シンガポール、そして東京にオフィスがあるようなムチャクチャな生活でした。飛行機で日付変更線を一週間に2回も3回もまたいでいるとロクなことがありません。飛行機の中で髪の毛がだんだん白くなっていくのがわかります。今、髪の毛が抜けているのは別の要因ですが(笑)。
マーサージャパンでは7年間社長を務めた後に辞任しました。、ひとりの人間が長いことトップをやるとろくなことがありません。私の専門は組織の活性化ですが、だいたい「組織がうまくいっていない」とか「新しいアイデアが出ない」という状況を診断すると、100社中99社ぐらい、一人が長く社長を務め過ぎていることがわかりました。その理由を細かくお話しすると3時間ぐらいかかってしまうので割愛しますが、要は、社長が誰よりも仕事が分かっているという感覚に陥ってしまうんです。そんなトップがいると、どうしても社員がお客様や社会に目を向けず、トップを見て仕事をするようになってしまう。これはどの国でも同じでした。ですから私の持論は6年以上トップをやってはいけないということ。その話を色々な場所で言ってまわっていたのですが、某知事にその話をしたら翌週に辞任されそうになって驚きました(会場笑)。でも、気づいたら私自身も7年やっていた。残念ながら他社と同じような現象が起きつつあった。それで、「これはまずい」ということで辞任することにしたのです。
その時点で私はちょうど100社のコンサルティングをしていました。お客様は、グローバルカンパニーとか、日本の大企業とか、大手の公共団体とか、すべて大きな組織だったんです。だから課題があると言っても、お金はあるし、それなりの人もいる。でも、世の中の多くの企業は違います。課題があってお金はないし人もいない。それでも成長していかなければいけないわけです。私としては、「そういう企業のお手伝いが出来ないならプロフェッショナルとは言えんな」と思いまして、出来るだけ厳しい状況にあるところに行こうと決めて、破綻した会社の社長をやりました。ここはもう人にも言えないような状況に陥ったITベンチャーでしたが、奇跡的に1年半ぐらいで再生することが出来ました。その後、CCCに入ったというわけです。
CCCで何をやったかというと、会社を統合して過去の膿を出す仕事です。皆さんご存じのように、組織というのは基本的には集中と分散を繰り返しながら成長していきます。しかし成長の過程で分散させ過ぎたり、逆に集中させ過ぎてしまうケースがあります。CCCの場合は前者でした。
私が入ったときにはグループ会社が合計100社ぐらいありまして、全体としてみると、「結局、何をやっているんだか、よく分からない」という状況になっていました。これを「“オールCCC”にしよう」ということで、88社を4社、実質的には1社に集約しました。会社を売ったり、統合したり…、色々な施策を打ったのですが、結構大変な作業でした。同時に税効果会計を考えながら進めていきましたので、昨年度は過去最高益を出すことができました。会社も一つになりました。そんな訳で、「ミッション終了。もう良いかな」とCCCを退きました。今は自分の会社に戻っております。Indigo Blueという会社です。
人口減少に伴い、個人にレバレッジをかけねば生産性は上がらない(柴田)
本題に入ります。今日は、まずは問題提起から。まずは、この「70万」という数字から考えていきたいと思います。今や毎年70万もの人が日本からいなくなっています。。毎年、島根県ぐらいの人口がボンッとなくなっていることになります。皆さんもよくご存じの人口動態グラフを見てみると、2030年にはピラミッドどころかツチノコのような形になっていくのが日本の状況です。少子高齢化が進み、平均年齢が上がるとともに人の数も減っていく。この状況を単純に考えると、今後、広義の国力を維持していくことは大変難しいという事態に向き合うこととなります。
つまり今後は高い付加価値を創出できる人なり、組織が世の中に出てこないと、少なくとも現在と同じ国力を維持するのは難しいことになります。生物の習わしとして、子孫の世代はより豊かに(豊かさの定義は色々あるものの)より豊かになって欲しいと願うものです。ならば何が必要かと言えば、ゼロから1を生む人、あるいはその1をn倍化していく人が出てこなければいけないと考えています。1を素晴らしい1のまま継続させること自体は否定しませんが、それだけではこのどうしようもない人口減少を見る限り追いつかないと思います。
高い付加価値をつくるにはどうすれば良いのか。私は仕事というのはインプットとスループット、そしてアウトプットの組み合わせだと思っています。アウトプットを出すには自分のなかでの分析や構造化といったスループットが必要になりますよね。で、それをやっていくためにはさまざまなインプットが必要になる。安永さんのお話にあった地図にあたるものがインプットだと思います。やはりインプットがないとアウトプットは出ません。そしてインプットが固まってしまうと固まったアウトプットしか出ない。人材育成という点からすると、これが大きな問題になっているのではないかと考えています。

ただ、だからと言って、なんでもかんでも整備して簡単にインプットできるようにする、という論調になるのは賛成できません。私は、今回のような人材育成系の勉強会に出るのは久しぶりです。以前、某研究会に呼ばれてディスカッションした際、「あまりに、マニュアル化の議論が多く、あ、いかん」と思ったからなんです。こんなことをしているから人が育たなくなるんだと思い、「もうこの手の会議には絶対出ない」と。しかし今回は大変な熱血漢かつナイスガイの鎌田さんに口説かれまして…、私はこの手の熱い人には弱いので、「じゃあ行こうか」と来た次第です(会場笑)。
たとえば今日お集まりの皆さんの顔ぶれを拝見すると、私と同年代か少し上ぐらいですよね。私は48歳の“アラフィー”です。で、同世代であればお分かりになると思いますが、我々には、現在に至るためのマニュアルなんてなかった。しっかりと教えて貰った経験はないし、ましてや人材育成のプラットフォームだなんてありませんでした。決められた道がない状況で、それぞれ痛い思いをしながら、ときには派手に転びながらやってきたわけです。
ただ、世の中ではそれでは非効率だという話になってきた。だからマニュアルを作って教えてやろうという話にもなる。でもそんな道を整備すればするほど、教わる側のユニバース(世界観)は狭くなってしまうんですよね。それなのに某研究会は「整備をどんどん進めましょう」なんていう話ばかりしていたので、「それは違う」と大ゲンカをした末、帰る羽目になってしまった。今日はそうならなければいいなと思いつつお話をしていますが(会場笑)。いずれにせよ、私としては「大事なのは道なき道を飛ぶことなんだ」という気がしてなりません。もちろん、按配はすごく難しい。本当に何ひとつない道で良いのかというと、たとえば倫理的な事柄だとか基本的な事柄を教えないで良いのかという疑問が出てきますから。私はそのさじ加減を調整するのが皆さんのようなCLO(Chief Learning Officer)と言われる方々であり、経営者ではないかと思っています。

良質なインプットを集めようというとき、自分から取りにいくのはもちろんですが、これだけ世の中が変わって色々なことが起きる中では、情報が自然と集まってくる形を各々が設えていくのが望ましいと思います。この点について、私はずいぶんと色々な人にお会いしてきたなかで、あるキーワードを意識するようになりました。それは“好感度×高感度”です。別に駄洒落を言おうとしているわけではないのですが(会場笑)、要は好かれるということです。人から好かれ、なおかつ感度が高い人。そんな人のところには良いインプットがたくさん集まってくるのではないかと思うのです。
リーダーシップスタイルは求心力型から遠心力型に変わってきている(柴田)
“好感度”について若干、補足します。人間というのは不思議なもので、「こいつはいいな」、「好きだな」と感じる人から聞く話については、たとえそれが眉つばもののストーリーでも「なかなか良いんじゃないか」と思ったりします。反対に「こいつは駄目だ」と思う人からどれだけ立派なプレゼンテーションを受けても、どうも怪しいと感じてしまう。皆さんもそんなご経験、ありますよね。だから好感度なんです。「あの人と仕事がしたい」、「あの人にこれを伝えたい」と思われる人であることが、とても重要だと考えています。
なおかつ人が良いだけでは駄目で、さまざまな空気の流れですとか、ちょっとした先のことが分かる人。そういうアンテナが立っている人が良いのではないかと思います。そんな要素を踏まえたうえでリーダーシップを捉えて見ると、自分だけではなく周りの人間もエナジャイズ(energize、精力を与える、激励する)出来る人であること。エナジャイズにも色々な定義があるかとは思いますが、その人がいることで周囲が元気になるといった要素がリーダーシップには不可欠だと思っています。特にミドルマネジメントには非常に重要ではないでしょうか。
ここで少しアカデミックな話をすると、ここ数年でリーダーシップのスタイルは求心力型から遠心力型に変わってきていると感じます。変わらざるを得ない状況にあるも思っています。求心力型のマネジメントは「俺の言ったことをやれ」と、同じことを繰り返すタイプ。指示をするし、統制をするし、場合によっては手とり足とり教えるタイプですね。これに対して遠心力型のマネジメントというのは、顧客との接点に近い個々の社員が思い切り働けるための環境をつくっていけるタイプです。このように、リーダーシップのベースがこれまでとまったく変わってきているという気がするわけです。
これについて私は、5年程前に本を書いたときには、「(リーダーとは)周囲に良い影響を与えて組織を動かす人材」と表現していましたが、最近ではもっと分かりやすく「飲み会の幹事」と言っています(会場笑)。
飲み会の幹事ってなかなか大変ですよね。店の選定からして「あの店だとちょっと…」とか、色々なことを言う人間が出てくるわけですから。あれこれ言われるなかで折り合いを付けていく。「今回は5000円ずつ出してください」と言えば、「それは高いよ」という人もいれば「5000円じゃ何も出来ない」と文句を言う人もいるでしょう。で、たとえば50人で予約したのに当日は20人しか来なかったとなれば幹事はクビをくくる世界です(会場笑)。そうなると、ある程度の人数には来て貰わなければいけないから、周知徹底しないといけない。そして、いざ飲み会がはじまったら「飯がまずい」とか「酒が足りない」なんて言わせないようにしないといけないし、セクハラ系のオヤジがいたら抑えないといけない(笑)。その結果として、お開きの際に「良い飲み会だったね。明日からがんばろう」と言われる。リーダーってまさにこれだなと思います。
これが“俺様系”の求心力型リーダーなら「俺に酒を持ってこい」とか「俺が頼んだんだからいいだろう」みたいなことになります。でも、そんな飲み会は誰も出たくありませんよね。だから良い飲み会を実現できる幹事のようなタイプこそ現代のリーダーシップとしてはふさわしいんじゃないかと、最近は思っています。同時にベースにあるのは周囲をケアする気持ちです。「俺が言ったことをやれ」ではなく、周りの人を大切にしていく努力でもあります。
僕の好きな言葉に「結果よりも原因を追究しなさい」というものがあります。結果は色々な局面で生まれるし、良い結果にせよ悪い結果にせよ、偶然によるものもあるでしょう。一方、その結果を生じた原因、メカニズムのほうを把握していれば、安定的に結果を測ることができる。
これを組織や人間関係に置き換えると、同様の状態というのは、お互いがお互いのことをよく知っていること。気心が知れている状態だと思いますね。そうした関係性を構築するには、一定の時間を共有しなくてはいけない。これを「絶対時間比例の法則」と私は呼んでいますが、リーダーはメンバーとなるべく長い時間を共有できるような場をつくり、人と人をつないでいく必要があると思っています。
ところが、残念ながら至るところで“集団皿回し”のような状況に陥っている組織を見かけます。。統計をとったら本当にそうなっていました。どういうことかというと、1995年から2008年ぐらいまでの日本の法人統計を見てみると、売上高の伸びはフラットでも粗利のような要素にはかなりブレがある。この背景にあったのは、
(1)10人でやる仕事を「8人でやってみろ」と言われて、何とかやりぬく。
(2)「8人で出来たのなら7人でも出来るでしょ」と言われる。
(3)7人でやっているうちに誰かが辞めたりする。
(4)6人になると、もうリーダー自身も輪に入って一緒に皿を回しはじめる。
(5)「結婚することになった」と言ってひとり辞める。しないのに(笑)。

結局こんな流れから、同じ仕事を同じやり方で、半分の人数でこなすようになってしまった。こうなると、リーダーも自分の皿回しで手一杯になりますから、新しいことをやろうとしても手が動かせない。倒れそうな人を助けたくても、自分の皿が落っこちてしまうから助けに行けません。新しい人が来てもケア出来ない。集団皿回しとはそんな状況のことです。こんな状態では何をやってもダメなので、必要になってくるのは「まず何かをやめる」という決断となります。
私自身、CCCにいた際には、「こんなことをやりたい」という提案を数多く受けましたが、そのたびに、こんなふうに返答していました。「それは素晴らしい、是非やりましょう。で、代わりに何を止めましょうか?」と。新しい仕事をひとつ始めるなら、何かひとつ、他のことを止めろということです。でなければ皿回しの状況がさらに悪化してしまいますから。
まとめます。高付加価値人材を育成するためにはインプットがとても大切になります。このインプットが固まってしまうと、決まりきった道を歩んでしまうことになります。そうではなく、道なき道を飛ぶようにして行く。インプットの質を高めるためには好かれる人材でなければならない。だから好感度の高い人間であって欲しい。また、色々なアンテナが立っているハイセンシビリティという意味での高感度であったほうが良い。その“好感度×高感度”で周囲をエナジャイズしていく。リーダーは偉い人ということでなく飲み会の幹事のようなもの。人と人をつないで時間を共有させるのがその役割。集団皿回しのような状態に陥った場合には思い切って何かを止める判断をする。それがリーダーの仕事。。以上が私からの問題提起となります。
鎌田:ありがとうございました。足りないものが何かという“WHAT”、何故足りないのかという“WHY”、そしてどうすれば良いのかという“HOW”。これらに対してひとつの大きな網がかかるお話だったのように思います。
自分を飾れない状況に追い込むことで発露するものもある(柴田)
鎌田:ここからはグローバルと有事、二つの論点でお話を続けていきましょう。柴田さんには有事を軸に伺っていきます。
先のお話では、マーサーの後の最初の会社では破綻から再生へ、CCCでは分散から統合へという流れがありました。どちらも力技の面があったかと思いますが、その文脈のなかでも高い付加価値をつくる人が足りないという実感はあったのでしょうか。経営視点で考えたとき、柴田さんを支えてくれる当時のリーダー陣に足りないと思っていたことはどのような要素だったのか。手触り感のある話として、当時、物事を動かすうえで「こんな奴らがいればな」とお感じになったことがあれば、お聞かせください。
柴田:最初の会社は再生会社で、事実上破綻して債務超過でした。その状況が明らかになったときから一気に貸し剥がしも起こりました。一方、人材もいない。感じたのはまともなトレーニングを受けてきた人がいなかったということです。特定事業のなかでしか育ってこなかった人ばかり。でも破綻しているからお金もなく、安永さんにお願いする訳にもいかない(笑)。だからとにかく、当時いた人材でやるしかなかった。その点、CCCは最初に4400人いましたから、リーダーとなる人材はこのなかに必ずいるはずだと感じていました。その違いは象徴的だったと思っています。
必要とした人材像は共通していました。今までやってきたことを止め、しがらみを乗り越え、周囲を巻き込んで動ける存在、つまりマグネットのような人材であるということでした。特にそうなってもらわなければならなかったのは、私の直属となる経営幹部ではなく、顧客接点に近いミドルマネジメント以下の人々でした。現場の状況を即時に把握しながら、色々な人を巻き込んで物事を進めていかれる人材が必要でした。再生会社の場合は残念ながらその絶対量が足りなかったので、私自身も現場でその役割を担いました。100人ぐらいの企業でしたから、私がトップもやりながらミドルもやるという形です。CCCは人がたくさんいたのでそういう人材を見つけていきました。「柴田塾」と呼ぶ塾を開催し、そのなかで人材を見つけ、彼・彼女らに影響を与えて動いて貰おうとしていました。この際のキーワードが先ほど申し上げたエナジャイズ・・・周囲を元気にしながら進めていく、でした。
鎌田:なるほど。今のお話は、いずれもターンアラウンドと言いますか、厳しい状況から普通の状態に持っていく、マイナスからゼロに引き戻すステージでのことですよね。どちらかというと再生会社ではトップのリーダーシップである程度ぐいぐい引っ張っていったのかなという気もするし、1年半という短い時間で勝負をつけるという意味でも、危機感が共有されていたからそれなりに出来たのかなと。ここでさらにお伺いしてみたいのは“その次の有事”における人材要件です。ゼロの状態から付加価値を高めていくステージでも、人材に対する枯渇感は出てくるのかなと感じています。
柴田:そうですね。少なかったと思います。
鎌田:そういう人たちが育まれない背景とはどういったものなのでしょうか。
柴田:そこはとてもアイロニカルで、地図やインプットの話と一緒です。同じインプットが続くと固まってしまう。同じ会社で同じ仕事を長く続ければ続けるほど、インプットの配分が固まってしまう。それを広げていくのが大変です。それなりにスループット、アウトプットが出来る人間であっても、インプットを固めてしまうような人事配置や育て方をしてしまっていると、なかなか期待しているような人材に育たない。そこは強く感じました。
鎌田:となると冒頭のプレゼンにも戻ってきますね。つまり、何をロックインしてしまうと爆発力を阻害してしまうのか。とりわけ育成の観点からすると、何を心掛けられたのでしょうか。
柴田:絶対解はないのですが、私自身がCCCで何をしたかというと、「R2」と呼ぶ施策を実行しました。R2は「Reset(リセット)」と「Re-entry(リエントリー)」の略。普通、会社の人事異動は組織の必要性から生まれるケースがおよそ8〜9割、自己申告で動くのが1〜2割ぐらいですよね。これを逆転させてしまったのがR2です。要は、3年以上を同じ仕事をしてはいかんと。3年以上同じ仕事をした人全員に手を上げさせて再配置するようにしました。その際に改めて驚いたのは、3年以上同じ仕事をしている人が86%もいたことです。ビジネスモデルが固まっていればいるほどやること(インプット)が固まってしまいがちという実例です。
なぜそうなっていたかというと、やはり「今こいつを動かすと回らなくなる」という現場の声があるためです。しかし誰かが現在と将来との按配を全体的に見てコントロールしないと、組織は知らないうちに硬直してしまう。ですからCCCの場合は少々荒療治でしたが、そういうことをやりました。
鎌田:非常に参考になるお話だと思いますし、皆さんのなかにも同じことをおやりになっているかたがいらっしゃるかもしれません。意味合いとしては環境を変え、見える風景を変えることで成長を促そうというアプローチだと思います。見えている風景を変えることで固定観念を揺さぶるということですよね。
柴田:そうですね。インタンジブルアセットというか、組織的な事柄や人間関係といった目に見えない要素が仕事をしていくうえでかなり大きな比重を占めます。同じ仕事をしていたとしても場所や人間関係が変化すれば大きく変わる。それを比較的、短いスパンで回転させることが、恐らく固まらないという結果にも繋がるんじゃないかと思います。
鎌田:なるほど。ただ、価値観を常に揺さぶることが、自分自身のないノンポリを生んでいっては困るわけですよね。自分なりの価値観は持って貰わなければいけないと思うのですが、そこに対する工夫や発見はありましたでしょうか。
柴田:そうですね。ただ、そこはあえてコントロールしないようにしようと思っていました。優秀な人というか、しっかりとした自己を持つ人というのは、別に会社がフォローしなくとも自分自身で方向性を見出していきますから。
鎌田:なるほど。場合によっては転職もよしとするという。
柴田:もちろん転職されてしまうと、先ほどお話ししたような目に見えない要素をすべて作り直さないといけないし、会社としても損失です。だから、なおさらCCCグループで色々な仕事が出来るようにしようと思ったんですね。
CCCでの仕事には第二段階がありました。TSUTAYAというのは95%がフランチャイズで、300社以上のフランチャイジーがありました。だいたいが中小企業でしたが、この場合、同じ仕事を3年どころか10数年やっている人もたくさんいたわけです。キャリアパスもありません。そこで私が実施したのは、同じ地域で同じTSUTAYAなら、Aという加盟店とBという加盟店で人をスワップしようというようなことです。フランチャイズ企業自体もまた揺さぶっていきました。
鎌田:なるほど。とにかく有事という文脈のなかで、普通ではないやりかたを選んでいったということですね。国全体の人口も減るわけだから、1人当たりが創出する付加価値を高めないといけない。では、この、高い付加価値を出せる人材を、もう少し具体化しようとすると、どのような要件が考えられそうでしょうか。
柴田:先に「ゼロから1を生む人」という言い方をしましたが、ここで言う1は完全なゼロから生まれるものでなく、色々なものの組み合わせて生みだすという意味です。もうひとつの1をn倍化する人材というのはその1を1で終わらせず、商売として広げていくデベロップメントのできる人間だと思います。
鎌田:ゼロから何かを生み出すクリエイティビティと、それを組み合わせて広げていくデベロップメント。すると統合力というか、色々なネットワークを束ねる力も資質として挙げられるわけでしょうか。それを育むため、一点目として「揺さぶる」という作業があった訳ですが、一方の中心概念が“好感度×高感度”とエナジャイズであると。これは非常に分かりやすい言葉であると同時に、根っこの部分では似たような事柄なのかなという気も少ししています。では、そうした能力はどうすれば育めるのか、或いは極めて先天的なものであって育めないものなのか——。
柴田:ここは本当に難しいところで、たしかに遺伝的な要素や生まれ育った環境によるところは、もちろんあると思います。だから全員がそのような人材になれるかというと、疑問符はつきます。ただ、社会に出てからも人は変化し続けるわけですから、うまい具合に環境を変えることで、それまで発露していなかったその人本来の良さが出てくるということもあると思います。
鎌田:なるほど。「柴田塾」には、そんな狙いもあったものと思いますが、具体的にはどんなことを行っていたのですか?
柴田: 2泊3日、毎日8時から27時まで語り合うような…(笑)。そこで延々議論していると、飾っていられなくなるんですね。ロールプレイひとつやるにしても実際にクレーマーだとか外国人が入ってきて、やいのやいの言われたりする。そんな状況になって初めて皮がむけたという人間が2割ぐらいいました。
鎌田:今のお話はもう少し聞いてみたいですね。もう素っ裸にして一段次元を上げると。その2割前後という人たちのなかでは何が起きていたんでしょうか。
柴田:「これはやっちゃいけないんだ」というセオリーが破れるんです。お行儀良くしていられなくなりますから。
鎌田:どういう環境を設定するとその状態が現れるんでしょうか。
柴田:長時間泊まり込みでぐいぐい議論を続けていると、小さくまとめられなくなっていきますね。
鎌田:囚われていたものから解放されることで、もともと持っていた何かが光りはじめ、それがエナジャイズや“好感度×高感度”の種になっていく。そんなイメージでしょうか。大変勉強になりました。
ではここで時間の関係もありますが、再度、有事における論点を整理してみましょう。有事はイコール再建という話だけではなく、新しい付加価値を次々と生み出さなければいけない状況でもあります。その価値を生み出すべき人材育成には、インプットが固まらないポジションをつくることが大事であると。一方で、好感度、高感度やエナジャイズという話は、これは資質かもしれないが、持っている人は何割かはいる。ならばそれを発露されるような環境をどのように用意していくか。そういったことが、柴田さんが取り組んで来られたお仕事だったと思います。
それでは会場からご質問、あるいはご意見でも結構です。いかがでしょうか。
配置転換や組み合わせの変更で動脈硬化を阻害する(柴田)
会場:お話を伺っていると、取り組まれたことの中心は、どちらかというと“育てる”というより“見出す”と言えるような気がしました。自社内から…、状況次第では自社でなくても構わないのですが、芽のある人材を見出して殻を破らせていく。ただ、そこで疑問もあります。今すぐにリーダーシップを発揮できる人材が欲しいとなったとき、何らかのミッションを与えて果たしてそれが続いていくものなのでしょうか。たとえば10〜20年先を考えたとき、4000人のなかに見出されるべき人材がいつまでも居続けるものなのか。彼らが要職に就いたのち、さらにその次を探しそうとしても残りの3950人のなかからはもう出てこないという可能性もありますよね。人材を、果たして見出し続けられるかという点についてはどのようにお考えでしょうか。
鎌田:ご自身としては続かないのではないかと思っているということですね?
会場:母集団が決まっていれば難しいと思っています。
鎌田:なるほど。ちなみに、その状態となった今は何をやっておられますか?
会場:局面ごとに、芽のある人材を外部から採ってくるということをしています。
鎌田:続かないのなら補給するということですね。
会場:そうですね。しかし即戦力となる人材を採るというのは、それなりのコストがかかり大変なこともあるので、まずは殻を破れそうなポテンシャルのある人を選びます。ここは非常に難しいところですから、場合によってはプロの力を借りたりもします。ただ、先ほどのお話にもあったように、柴田塾で殻を“破れるであろう”人などについては、どうやって常に置いておけるのかをお伺いしたいと思いました。
柴田:いきなり痛いところを突かれた気がします(笑)。たとえばCCCでは、これまで新卒採用は毎年それなりのボリュームでやっていまして、入社時の配置から将来に繋がっていくよう、3年間は会社預かりで色々な部署をぐるぐる廻らせることにしていました。初期の段階から揺さぶりつつ、CCC全体を見ていく人材の母集団をつくっていくためですね。また、これは今年も続けているかどうか、離れてしまったから分かりませんが、昨年やったこととして、幹部候補生15〜16人を集めて、半年ぐらい増田(宗昭)CEOや私のカバン持ちをさせたりするような選抜組をつくります。その一方で、その15〜16人と同じ数のMBAインターンを世界中から呼んできて、それぞれペアリングして3カ月間仕事をさせるということをやりました。
これも要は取り繕えない状況を作る施策の一つです。MBAインターンといっても、英語圏の人ばかりではなく、色々な国の人がいて、とにかく互いに言葉が分からない。でも一緒に仕事をしなくてはならない。そんな環境だと、最初は「なんじゃこりゃ」という感じになりますが、終わってみると一番感謝されたプログラムでした。手を変え品を変え断続的に埋め込んでいかないと、ご質問にあったような状態にするのは恐らく難しいと思います。ただ、嬉しかったのは私がCCCを離れたあとも、塾生たちが自分たちで柴田塾を続けていることです。これはこれで繋がっているので、長い時間議論をしていくDNAはとりあえず埋め込むことが出来たのかなと思っています。そんな施策のなかから何らかのパイプラインが出来ればと感じていますね。
鎌田:MBAインターン15人とカバン持ち15人のペアリングということで、やっぱりこれも飾らない状態になっちゃうということなんですね。
柴田:そうですね。今時分、日本にインターンでやってくる外国人にはそれなりにアグレッシブな人間が多い。そういう連中が日本語もよく分からないまま絶えず隣にいれば、これはもう英文法なんて気にしていられない。とにかく伝えなくちゃいけないから。これは本当に殻が破れる環境になると思いますね。
鎌田:今の議論からは、見出すアプローチ中にも育むという側面が存在するということが垣間見えます。今のお話にかぶせていただいても結構ですし、他のトピックでも結構です。他に何かご質問などいかがでしょうか。
会場:見出すというお話は、違う論点で言うと「人はいるはずだ」ということにもなるかと思います。並み以上の人材は揃っているはずだと。それなのに、力が発揮されていないというケースでは、見出す前に何かがそれを潰してしまっているのではないかと思えます。たとえば本部長が強すぎるから事業部長がへたっているんじゃないかとか、さらにその状況を目にした若い人材がダメになっているんじゃないかとか…。ですから“いるはず”の人材を育てるのも大事ですが、育てる環境を壊すような組織風土を排除するというのも、きっと大事なんだろうと感じています。若干、感想じみてしまいましたが。
鎌田:ありがとうございます。阻害要因の除去はたしかに大事だと思います。そのためにご自身がおやりになっていることは何かありますか?
会場:私としてはそれぞれのつかさつかさで、人材に思いの丈を語らせる場というのをつくっていきたいと思っています。
鎌田:思いを素直に語れる環境をつくることで、「そういうことを言っても良いんだ」と、皆が思うということですか?
会場:はい。たとえば企業コンプライアンス(法令遵守)が非常にクリアな例になると思います。私が勤めている化学会社は最近、何かあればすぐに119番します。一昔前なら事業所長が消防署に言うべきか否かをじっと考える。それで通報が15分遅れ、消防署からめちゃくちゃに怒られるというような状況になっていました。でも今はすぐに報告するんですね。すると下のほうが、「所長はどんなことも包み隠さず上に言うんだ」と理解して、ミドルやさらに下の層も「あ、上には何でも言っていいんだ」という文化が生まれます。そのサイクルとともに情報の流れのさらさら感といったものが生まれるような気がします。
鎌田:なるほど。今のご意見に対して柴田さんのほうからも何かコメントがあれば、お願いします。
柴田:組織的な阻害要因を解消していくのは、人事担当者や経営者にとって本当に大きな仕事です。組織というのは本当に不思議なもので、悪くしようと思っている人は一人としていないはずなのに、それが集団になった瞬間、色々な場面で動脈硬化みたいなものが発生してしまうことが多々あります。ただ、動脈硬化というのは大抵が組み合わせによるものが多い。だから、ここも配置をうまく変えていくことで対応できます。「これはこうなっているから、あなたも気づきなさい」と口で言われて「はい、わかりました」と変わるくらいなら、誰も苦労しないですよね。ですからそこは、気づいてもらえるよう配置や組み合わせを変えるといった施策が重要になるのではないかと思います。
鎌田:クリエイティビティの芽を摘まない組織や風土をつくるため、配置を変え、組み合せを変えるということですね。皆さん、他にはいかがでしょうか。
経営者の哲学、心構えが浅いと、事は“もぐら叩き”に終始する(鎌田)
会場:柴田さんのお話を聞いて、ガツーンと頭を殴られたような気がしています。会社というのはやはりトップで決まるのかなと。トップの価値観や思いといったものが組織を変え、人を育てるんだなとつくづく感じました。私も今の会社で人材育成の責任者ではあるのですが、会社のトップは柴田さんのような人材育成に対する思いはあるものの、自らが動くということはしていません。そういうトップにどうやって揺さぶりをかけていけば良いのかと、私としては長いこと悩んでいます。色々と手は打っているのですが、旧勢力の人たちに「そんなことをやる必要はないんじゃないのか?」と言われるようなしがらみもあり、なかなか前に進まない。そういった状況に切り込んでいく際のヒントをいただけたらと思っています。
鎌田:これは大きな課題ですね。柴田さんいかがでしょうか。
柴田:たしかにそれは皆さんも共通して悩んでおられることかと思います。人材育成については、特にトップの層にいる人たち、あるいは幹部一人ひとりに聞くと、たしかに「人材育成をしたほうが良い」とまでは必ず言いますよね。
ところが集団になったとき、色々な思惑が働いて前に進まなくなることがある。そこで私がどうしたかというと…、本来なら人材育成の責任者が間に入ってファシリテートすれば良いと思うのですが、幹部が10人いるとしたら、10人全員と1対1の関係をつくります。そこで「あなたの人材育成に対する考え方を、私はよく理解しました」と伝えます。で、次に10人全員を呼びます。基本的に皆さんが一致しているところとそうでないところがあるわけですから、そこではまず一致しているところを確認しつつ、少しずつ少しずつ埋めていってしまう。それで7割ぐらいの共有が出来たら「じゃあやりましょう」と、全員の前で話してしまうんです。同じタイミングで。これはパワーファシリテーションですが、そういう場で認識させていくことを、どなたかがおやりになると良いのではないかなという考えがひとつあります。
あと、経営トップがそれを出来れば一番良いのですが、なかなかそういうわけにはいかない。それならトップにはスポンサーになって貰うんです。つまり、ハシゴを外すようなことをしないでくれと。たとえば人材育成の責任者が「こういうことをやりますよ」という場面で、トップには横に座っていてうなずいて貰うんです。「何も言わないで結構です。ただ、私が足を踏んだときにうなずいてくださいね」と(笑)。そのぐらいのことをやれば暗黙的に「トップも一緒に動いている案件なんだな」と思われ、若干、動きやすくなります。
鎌田:なるほど。では続いてご質問またはご意見を募っていきましょう。
会場:私が在籍している会社は事業展開の範囲が国内に限られており、グローバルにライバルとどう戦っていくかに関する危機意識が薄いように感じています。そういう企業で人事を担当している人間として、先ほどのお話にあった「R2」についてご質問というか、壁を超えるためのヒントをいただきたいと思っています。
3年間、同じ仕事をしている人間は否応なく動かすということでしたが、私もある部署にとって「彼を抜かれるとやばい」と思われるような人間をピックアップすることはあります。その際、同部門のトップと膝を突き合わせ、会社全体の利益を見据えて全体最適の人事を考えるという話をするのですが、「そんな悠長なことを言っていられるか。こっちのパワーダウンはどうしてくれるんだ」と言われ、なかなか前に進まないケースが多々あります。新しいところで本人の力をさらに引き出したいという理屈で話を進めてみても、当該責任者からすると力を削がれることになる。その抵抗に対して、会社に対してどれだけの還元が時間軸的に発生するのかという観点を含め、説得力や納得性をもって話が出来るようにするにはどうしたら良いとお考えでしょうか。
柴田:そういう話は必ず出てきますよね。でもCCCの場合は一部の幹部や執行役員クラス以外は全員を対象にしました。全員が動く。そのときに「貴方は行かないでね」なんていう抱きかかえみたいなことは出来ない仕組みを目指しました。もちろん異動の話をすれば現場を預かっている幹部はは心配して色々なことを言ってきますよ。「こいつ抜けたらとんでもないダメージだ」と。私はそこで、「そうですね。でも他から優秀な人がきっと来ますよ、このビジネスが魅力的であれば」といった話をします。で、「来ないということは相対的に魅力がないということですよね」なんていう話を役員たちにもしていました。
実質的に全社員の3割以上を動かすような形で進めると、混乱のほうが大きくなってしまう可能性は確かにあります。でも3割未満であれば懸念されるほどの影響は出ません。1〜2日ぐらいはあるかもしれませんが、それも実施するタイミング次第。たとえば大きな営業上の狼煙が上がるときにはやらないとか、季節性を考えて設定すればそれ程ダメージはありません。それでも言われるなら、どれぐらいの損失が発生するかを金額に置き換えて言ってくれと、私は話していました。それで、「そのぶんはあなたの責任にならない」という話を個別にしていましたね。
鎌田:説明責任の果たしかたや納得のつくりかたという意味ではその通りだなと思う反面、これは経営哲学の話にもなるのではないでしょうか。柴田さんの主張は、「人は固定した瞬間にクリエイティビティを失う。それが良いのかどうなのか」という重大な問いかけでもありますよね。ですから個別のパフォーマンスの手前にあるポリシーというか、「こういう経営のあり方を実現するんだ」という心構えの問題という次元で考える側面もないと、いつまでも“もぐらたたき”が続いてしまうのではないかという気がします。
会場:クリエイティビティやデベロップメントという言葉は弊社の場合、「部長以上が考えれば良いんだ」となっていて、それ以外は兵隊のような見方をしているのかなと感じるときがあります。トップ層としては「自分たちのクリエイティブな仕事を完結するために、実務能力が優れた人材を留めておきたい」。そんな気持ちが透けて見えるときがあるんですね。一方で、私自身は、どんどん権限を移譲し、若い人間にチャンスを与えたいと考えています。人事担当が考えることと、営業部隊などフロント側が考えることが相反するのは所与としつつも、いかに彼らのリスクにまで踏み込んでいかれるか。それが最終的には会社全体の利益になるよう実現の方向性を考えていきたいと思っています。
鎌田:ありがとうございます。議論のなかでも“HOW”の話が少し出てきましたが、どんな人材が有事において必要か。環境の違いにより、どのような人材が輩出されるのか。そのあたりの“WHAT”をしっかりと言葉にしなければ、課題はやっつけられないように思います。
会場:問題提起に対する解になるかどうかは分かりませんが、今のお話の背景には危機感が必要だという認識が、私にはあります。たとえば私どもの会社は製薬会社で、現在はすごく安定しています。営業利益も26%ぐらいで、私としては正直、「もう利益が出ているんだからいいじゃん」といった気持ちもあります。そこで変革ですとか付加価値を高めるといったことをいくらトップが言っても、そもそも危機感がない状態ではなかなか社員の意識も高まらないのかなと感じています。そこと紐づけたうえで柴田さんにお伺いしたいのですが、はじめに入った2つの会社というのは、まさに危機感のただなかにあったと思うのですが、CCCはそこまで社員の方々に危機感はなかったのではないでしょうか。真の危機感を持っていることが次代のリーダーを自発的に導き出すベースにあるのではないかという印象を持っていますが、そのあたりについて何かコメントをいただければと思っています。
柴田:おっしゃる通りですね。私としては危機感と焦りは違うと、自分のなかで整理しています。危機感というのは常に持っていなくてはいけない。現場では優秀な人であればあるほど、それを持っているんですね。TSUTAYAの場合は映像レンタルのシェアが1位ですし、本の売上チェーンとしても全国1位。そういう意味では危機感が生まれにくい環境ではありました。ただ、柴田塾では大きなテーマとして「5〜10年後のTSUTAYAはどうあるべきか」という議論をしていました。その際に世の中の環境変化を具体的に見せていくと、「あ、さすがにこれはやばいね」という話になった。「数年後は配信が主流になり、映像レンタル店には誰も来なくなるんじゃないの?」と、感覚的には何となく思っている人間も、普段からそれを危機感として持っているわけではありません。ところが「あるお店でこういう事態が起こっている」ということを事実として見せたうえで議論すると、「あ、そこまで来ちゃっているの?」となります。実例を基に議論をしていくことで、焦ることなく危機感を覚えて貰うという癖づけをやっていったんですね。長い時間議論出来るという何らかの場に、そのようにして自社の重要なテーマを置くのは良いことではないかと思っています。
鎌田:分かりました。今日の議論に関して、対象層のイメージを含め、再度視界を揃えておきたいのですが、まずはミドル層を中心とするリーダーの今後に向けたあるべき姿を探るというのが大きなテーマになります。次代を背負う人材は現在現場を支えているミドル層から確実に出てきます。そんなミドル層が経営を担うにあたり、どうあって欲しいかのという議論を改めて共通認識にしていきましょう。
今こそ我々の内なる意識のグローバル化が必要とされている(安永)
そろそろお時間となってきましたので、次はグローバル化の流れにおける人材要件という観点から安永さんとも対話をしていきたいと思います。冒頭ではご自身の海外経験、そしてモビットへのご出向経験などを通じた、いわば異文化とのせめぎ合いから生まれた成功と失敗というお話がありました。そういったご自身の体験をベースに、これからの日本企業を背負う人材がどう選ばれていくべきなのか。まさにヘッドハンターの目線から生まれた、欧米のプラクティスと日本のあり方に対する問題提起だったのかなと思います。
ただ、安永さんはヘッドハンターではありつつも、単に足りない人材は外から補充すれば良いと言われたわけではありませんよね。日本における人材育成のプロセスをいかに構築するかというテーマも、論点として掲げていただいています。そのなかで徹底した若返りですとか、腹を括る覚悟や信賞必罰といった、非常に重要な概念についても言及がありました。そういうところを少しリマインドしつつ、安永さんにお聞きしていきましょう。
まずはクライアントから人材参謀として色々な相談を受けてらっしゃる安永さんに、昨今のグローバル人材を巡る論調についてお聞きしたいと思います。結局のところ、クライアントとなっている企業としてはどういう人材がいないから外にグローバル人材を求めているのでしょうか。そもそもグローバル対応が出来る人というのはどんな人なのかという話も含めて、実感に基づいたお話を伺いたいと思っています。
安永:一口にグローバルと言いますが、その言葉の意味するところについて、まずお話しさせてください。日本企業が見たグローバルと欧米などの多国籍企業が見たグローバルには、結構な落差があるんですね。コングロマリットとして長い歴史のなかで各地に根をおろして活動している会社には、そもそもグローバルという言葉自体が存在しないんです。あらゆる国で営業しているのが当たり前だから。当然、人材も多様化しているし、女性の活用も当然のこととなっています。日本企業のなかでそこまでグローバル化している会社があるのかなとじっくり目を凝らして見ると、残念ながら、ほとんどないですよね。
私がイギリスにいた25〜26年前には、シェルやインペリアル・ケミカル・インダストリーズといったコングロマリットとかなり深いディスカッションを度重ねてしていました。私がそこで大変驚いたのは、彼らはイギリスの片田舎にある本社にいながらも、パキスタンだとかインドネシアだとか日本だとかいった子会社も含む、非常にグローバルな視点で経営を考えていることでした。経営を論じる際、本社のストラテジーがあり、エリアのストラテジーがあり、それを支えるオペレーションがあり、人がいて、そしてファイナンスがある。そんな暗黙の前提にきちんと立ったうえでものを考えているんです。どうしてそんな人材が育ってくるのかという疑問は、私にとって長い間、基本的な問題意識でした。かたや日系企業はイギリスやアメリカの子会社だろうが東京の企画担当の重役だろうが、誰と話をしていてもそういう発想が出てこない。まず日本があり、海外があるというだけですから。
また、日本企業にとって海外部門というのは長らくメインストリームではありませんでした。私自身も長いこと海外人材と目されてきましたが、常に保守本流である国内の人材からは敵視されていたんです。典型的な例は妬み。私が海外でまだ平社員だった時代のことですが、私は日本人と交わらずに現地の人々と交わろうと決めていたので、日本人が誰も住んでいない地域に家を借りました。ロンドンの駅から急行電車で30分ぐらいですから、東京で言えば小田原ぐらいでしょうか。そこで広い家を構えていました。庭はテニスコートがふたつ入るぐらいの広さでした。また、車については前社長の奥さんが日本に帰る際、彼女の車を安く譲ってくれたため、その大きなものに乗っていました。すると私が、“ヒラのくせに”郊外の大きな家に住んで、でかい車を乗り回しているといったことが東京の国際本部で噂になりました。「ロンドンにいった安永というやつは生意気で大変なやつらしい」と、私と会ったこともない人が言うわけです。まさに妬みの構造ですよね。
日本企業には海外部門に対するそのようなネガティブイメージがずっとあって、いまだに解消されていないのではないかと思います。すると当然、そういう伝統を経営者も引きずります。そんな保守的な文化によって、本当に内部から人材がいなくなってしまったんですね。だから最近の傾向として保守本流に経営人材がいないので、子会社にいた人が引き上げられて本体の社長になるというケースがかなり見受けられます。グローバルな経験や子会社における事業再生の経験が買われ、本社の社長に復帰するケースが続いているということです。
だからこそ私は、今こそ我々の内なる意識のグローバル化が必要とされてきているのではないかと思えてなりません。「海外ってなんかこわいよね」といった自分のなかにある差別感情の集積が、おそらくは日本企業の経営に深く沁み込んでしまっている実態があるのではないかと。まずはそのあたりを皆さん自身が認識すること。また、単にグローバルと口にするだけでは、外国勢の競合には既に大きく水を開けられていますから、そこをどう超えていくか。これが哲学的な問題として大切になるのではないかと思っています。
ただ、そうは言うけれども、「克服出来たとして、それでグローバル経営者が本当に出てくるものなのですか?」という疑問は残りますよね。これは事業再生の経営者人材についても同様の疑問が成り立ちますが、私は素質のある人材はたくさんいると思っています。何故そう言えるか。我々には戦後の高度成長期を経て今日に至った歴史のなかで、築きあげてきた経営管理、生産管理、財務管理のノウハウがあるからです。スキルやメソドロジーで彼らに負けることはほとんどないんですよ。問題はもっと手前のところです。どう世界を捉えるか。冒頭のプレゼンでも触れましたが、どんな風にグローバルな世界を見ながら問題解決に向けた課題を設定していくのか。そんな訓練こそ、今求められている要素だと思います。しかしその訓練をあまりにも受けていない。
柴田さんのお話にあった「3年以上経って変えられた」という人は、立場が変わることで見方も変わります。それを意図的につくり出していくことは、私も大変重要だと思っています。だから資質があってスキルもある程度身に付いた人を、そういう場に追い込むことがグローバル人材の養成に向けた鍵になるのではないでしょうか。私がかつて“マルドメ”の人材だったのが、急に引きあげられて海外に行ったのと同じように、です。
私は昭和54年入社ですが、150人いた同期うち50人が何らかの形で海外勤務を経験させられました。もの凄く多いですよね。でも、残念ながらそういった人材は帰国してから企業がなくなってしまったということで、皆、リテールの人材になってしまった。支店長として投資信託の営業をやるといった状況になってしまったんです。もちろんそこには環境変化に伴った致し方ない事情もありました。しかし150人のうち50人も海外赴任した経験があると、そのなかではお互いの“言語”が通じるようになります。「イギリスではどうだった」、「イタリアではこうだった」と、共通言語で語れるようになるんです。それが企業のグローバル化には大きな影響を及ぼします。皆さんも色々な業種の企業に勤めていらっしゃるとは思いますが、どういった業種であってもそのような機会を、ときには強制的につくることが大事になるのではないでしょうか。
「伝えよう」という気持ちが基点。異文化間で「伝える」共通言語はロジック(鎌田)
で、ここで改めてヘッドハンターの視点からグローバル人材の養成についてお話ししてみます。たしかに昨今、グローバル人材へのニーズは非常に顕著です。行く先々で「中国人材が欲しい」とか「グローバルに子会社を買おうと思っているが、その会社の社長が欲しい」といった要請を受けています。その一方、海外で営業本部長が出来る人材、あるいは海外現地法人で経営管理が出来て、なおかつ国内の営業本部長たちと1対1でコミュニケーションをとることが出来る人材への要求も強い。これは国内で売れているものを海外に売ったり、逆に海外で売れているものを国内に売ったりするための人事ですね。これはマルチカルチュアルな能力がある人でないといけません。「外国人だとちょっと難しいので、そういう国内人材を探せるだろうか」と、ひしひしとしたニーズに基づいたご相談をあちこちで受けています。当然、我々はお請けしたうえで人材を探します。そんな人はいないのではないかと思われるかもしれませんが、いるんです。必ず見つけることが出来ます。自分たちが育ててきた視野のなかではいないというだけ。そうやって外部人材を入れるとともに、社内でも選抜型の人材育成を行う。そして多様性を導き出し、社内にグローバルな環境をつくる。今はそういったことに挑戦する時代なんだという思いを深くしています。
鎌田:なるほど。今のお話における大きな論点のひとつに、経験というものがあるのかなと感じました。分からないものは考えられないという話です。また、環境設定の“HOW”としては自覚的にパイプラインをつくっておくという話でもあったと思いますが、それは柴田さんとの議論と同様、環境をつくるという意味で非常に大事なことだと思います。ただ、先ほどのお話しにもあったように89人のロングリストから最終的に選ばれる人と選ばれない人がいるということは、同じ環境のなかでもよりグローバル化に適応できる人とそうでない人がいるということですよね。形式的に海外経験があるか否かといったところ以外にも、何らかの見極め材料があるということなのでしょうか。あるとすれば、それは一体どんな要素になるのかなと思っています。グローバル化に関わる基準なのか、あるいはグローバル化と関連しない経営基準なのか…。
安永:グローバルという言葉から想起することは各々異なると思いますが、ひとつの私の経験を申しあげます。行員時代、国際本部に海外のゼネラルマネージャーやその下のクラスを一同に集めて研修をやったことがありました。当時の私は講師経験などなく、しかも英語で準備をしなければならなかった。上からは「研修では会社の戦略から考え方まですべて説明して欲しい」と言われました。面白いことに、当時の国際本部セクションのなかで英語が出来る人間は私しかいなかったんです。で、結局私が全部やることになり、まる一日講師を担当しました。その後フィードバックをとってディスカッションした際、とても明確にあることが理解出来ました。研修ではたとえば「世界のベストユニバーサルバンクになる」とか何とかいう会社の戦略書を翻訳して説明したのですが、ほとんどの人は意味が分からないと言う。戦略書がロジカルではなかったからです。環境分析とか色々書いてはいるけれども、要点がなんだか分からない。どうしてそんなことが出来るのかというプロセスが書いていないんです。しかし、そんな彼らにも三和銀行のPDCAに則った方針管理のほうは極めてクリアに伝わりました。分からないという人は誰もいなかった。逆に「どうしてこういう問題解決のメソドロジーを使って、全体戦略をリファインしないんだ?」と聞かれましたね。この出来事から分かったのは、曖昧模糊とした日本的経営の精神論と、きちっとした問題解決の体系である方針管理などの日本のロジックが、ひょっとしたら単に日本企業のなかできちんと結びついていないケースが多いのではないかということです。だとすると、我々自身が日頃から業務を通してロジカルに考えながらきちんと実行している問題解決のメソッドは、十分、グローバルでも通用する要素と言えるのではないかと感じています。
鎌田:異なる環境や文化を持った方々にしっかりと物事を伝えるための共通言語は、あくまでロジックであるという話ですね。ただロジックを駆使出来ているとしても、まず「伝えよう」という気持ちがなければ伝わりませんよね。伝えようという気持ちでやる人とそうでない人がいたとすると、そこにはどういった違いがあるのでしょうか。グローバルで働く仲間たちにも「要するに背景はこうなんだ」と、滔々と語る人がいる一方、ロジカルな能力がないわけじゃないけれどもやらない人がいるとしたら、その違いを知りたいと感じます。
安永:後者は同じ環境や文化のなかにどっぷり浸かっている人ということかもしれないですね。もの凄くラクなんですよ。たとえば東京本社のカルチャーで10〜20年過ごしていると、そこではほとんど言葉を交わさなくても意味が通じるようになります。皆さんの会社でも“本社族”、“現場を廻る族”、あるいは“海外をずっと廻る族”などで縦割の状況があるかもしれません。これだと同じ会社でも部署が異なればなかなか言語が通じません。だから常に新しい環境にチャレンジしながら異分子を自分のなかに入れること。そこでコミュニケーションしていかざるを得ないような状況をつくることが出来るか否かによって、大きく変わってくるのではないかと私自身は思っています。
鎌田:やはりここでも環境づくりと。そうせざるを得ないような環境をどれだけつくっていけるかという話ですね。分かりました。
それではここで会場からもお話を受けてみたいと思います。グローバル経営へのニーズが高い会社も多いかと思いますが、今までの話、あるいはそれ以外でも結構です。ご質問やご意見を募っていきます。
会場:私はフランス人がCEOを務めるメーカーにおり、人材面も含め、グローバル化は相当に進んでいると自覚しています。先ほどは「日本人のスキルは決して劣っていない」というお話もあり、とても勇気づけられました。ただ一方で、私の上司は今年の3月までCEOのオフィスにいたのですが、欧州人であるCEOと日本人である彼のあいだには決定的な違いがあると言うのですね。それはとても単純なのですが、仕事に対するどん欲さや「のし上がってやろう」という気概だと。それだけの事例で、日本と欧州を区別するのは短絡的かもしれないけれど、どうも差があるように感じてしまうと彼は話していました。ああいう人たちとまともに対抗できる日本人っているのだろうかと(会場笑)。結局は個人の資質だと思うのですが、程度の違いこそあれ、この差はやはり存在するのでしょうか。
鎌田:これは会場からもうなずきがありましたね。結局のところ、グローバルはエネルギーレベルの問題だという話が大きな論点かもしれません。柴田さんのお話にもあったエナジャイズに通じると思いますが、他人をエナジャイズするならまず自分がエナジャイズされていなければいけない。エネルギーレベルというか、どん欲さという表現について安永さんはどうお考えですか?
安永:良い意味での野心や大望、これは我々も同じように持っていると思います。ただ高度成長のなかで、そういったものがかなり埋もれてしまった面はあると思いますね。今、新入社員にアンケートをとると社長になってやろうという人が殆どいないそうです。「上にいくとかえって面倒だ」と。私が銀行に入った30数年前は同期の中に頭取になろうという人間が3〜4割はいました。結局、出ませんでしたが(笑)。それは環境のなかにあって野心が刺激されるかどうかということだと思います。日本企業の環境でも、昔はかなり刺激的な競争がありましたよね。誰が手柄を立てて早く偉くなるかということについて緊張感があった。でも今は野心を刺激するような装置もなくなってしまったし、運動会でも順位を付けないような教育を受けてきた人たちが大勢になってきていますから、ある程度は教育の影響もあるでしょう。海外企業によく見られるような、コミットメントを達成したかしないかでまったく結果が異なる信賞必罰な世界がなくなってきているのではないかという気はします。
で、欧米人はどうか。これはもの凄く明確です。やる人とやらない人とではおそらく100対1ぐらい違う。欧米ではやらない人たちが大体9割で、本当の競争に参加する人たちはほんの数%です。その人たちは人一倍勉強し、努力をし、頭が良く、日本に赴任してきたら日本のことを何でも理解しようとしてもの凄く勉強します。勝てないですよね。私のお客さんでそういう外国人マネージャーが何人もいますが、彼らの殆どは30歳代で日本のゼネラルマネージャーをやっています。35とか36とかですよ。「こんなに若いの?」と、会ってびっくりすることも多いです。そして当然、もの凄く頭が良い。私たちがそれほど得意でもない英語で話をしても、1を言うと10ぐらい理解する。ヘッドハンターですから優秀な人たちにはたくさん会っていますが、日本人で同じように頭の良い人というのは、そんなにいないですよ。たとえば柴田さんに1言えば10ぐらい理解して、20ぐらい返ってきますが、そういう日本人は稀です。ただ、外国から日本のCEOオフィスに来るような人たちはマネージャーを経験するプログラムなどを経て、選ばれて日本に来た人たちですから、すぐさま欧米と日本との差であるという解釈をする必要はあまりないと思っています。
人材・組織の活性には凝り固まらない環境と良質な刺激は不可欠(鎌田)
鎌田:今の議論を、柴田さんとの議論とちょっと対比させてみましょう。教育というインプットが固定することでクリエイティビティが阻害される一方、我々はもともと競争心を刺激するシステムを持っていて、それによって大望や野心を育んできた。ということは、システムがエネルギーの源泉を育んできた側面と、システムがクリエイティビティの芽を摘んでしまう側面があると。こういった、ある意味では対比するような議論が成り立つのかもしれません。
それからもうひとつ。欧米では数%がスーパー…、しゃれではありませんが(笑)、数%のスーパーエリートが企業を引っ張っているというモデルが回っているのだとしたら、日本企業が果たしてそれを追従すべきなのかという議論も出てきますよね。我々ミドルを中心とする次のリーダーたちは、どういう形でエナジーを積み、どういう形でクリエイティビティを育むのかという問いが生まれてくるような気がします。では引き続き質問またはご意見を募りましょう。
会場:お二方のお話で共通していたのが、しがらみや“固まる”といったものの見方に対するお考えであると感じました。私はそれを価値観という風に捉えています。この価値観が固定されてしまうと成長も阻害されてしまう。能力を自由に引き出すことも出来なくなりますし、知識を使うことも出来なくなるし、やる気も起きなくなってしまう。ですから成長するためには、ものの見方や考え方を個人がどう鍛えていくのかが重要になると思います。当然、人というのは一人で生きているわけではなく、会社のなかであれば環境と仕事のなかで生きています。だからその環境をどう変えていくか。ものの見方や考え方が固定しないよう環境をどんどん変えていく。あるいは接する人をどんどん変えるといったことをすれば、人はある程度成長すると思っています。このような考え方についてご意見を聞かせていただけないでしょうか。
鎌田:わかりました。ちょっと時間の関係もありますので、もうひとつ質問を受けてから、お二方にそれぞれ話を伺っていきましょう。
会場:本日お話を伺いまして、「インプットが固まっている」、「3年以上同じところにいる」、「“マルドメ”である」等、すべて私に当てはまります(笑)。これはつぶやきに近いのですが、私としては国内で研修などをやっているなかで手詰まり感を覚える局面が、正直、あります。柴田さんのお話にありました危機感にも繋がってくるのですが、それは今までにない刺激を与えないと変化していかないという手詰まり感なんです。その突破口のひとつとしてグローバルという概念がひとつのキーになってくるのかもしれないという期待を持っています。とにかく人を還流させる。安永さんのお話にもありましたように、当時帰国してから良い思いをすることが出来なかった先輩方もたくさんいらっしゃるので、同じ失敗を繰り返してはいけないと感じました。
鎌田:わかりました。ではここで一度議論を収斂させますが、環境を変えていくことによってものの見方や考え方の固定化から解き放たれる。これは言い方を変えれば、後半のご質問にあった「これまでにない刺激を与える」ことにもなると思います。いずれにせよ我々は組織のなかにいて、人に対して凝り固まらないような環境と良質な刺激を提供していかなければいけない。これによって成長を促すことが可能ではないかということですね。さらに言えば、ものの考え方や見方はスキルとは違う。価値観という解釈でも宜しいですか?
会場:価値観とも言えますし、同じ物事であってもどう捉えるかという考え方とも言えます。
鎌田:そこには「より前向きに捉えて欲しい」というニュアンスもあるのでしょうか。
会場:はい。それも含まれます。
鎌田:分かりました。そういったものの捉え方は果たして鍛えられるかということですが、それぞれ一言いただけますでしょうか。では安永さんから。
安永:私はグローバル人材について考えるとき、いつも思い起こすことがあります。私は1987年にロンドンに赴任してから、お客さんとしてコングロマリットの財務担当者などと会って話すといつもびっくりしていたんですね。今まで、そのレベルの職階にいる方々と日本で話をしていたときは、その方が会社で担当している分野の話ばかりになっていたんです。ところが英国人…、なかには英国人ではない人も当然いましたが、その人たちは常に「会社全体のなかではこうだからこうすべき」というような前提を置いていた。出発点が違っていたんです。とても不思議な印象を抱いて、「どうしてそんな見方が出来るのか」と思っていました。で、今はどうかわかりませんが、当時はイギリスの上場企業のCEO、あるいは社長と言われている人たちの8割強がファイナンス畑の出身者だったんです。典型的な例は公認会計士の免許を所得してから2〜3年は大きな会計事務所で修業して、それで会計士として経理課の係長ぐらいで入り、課長になり、部長になり、役員になり、そして社長になる。恐らく今でも欧米の大きなコングロマリットではファイナンス出身の社長が多いと思います。なぜ生産や営業の人たちが社長にならないのか。これはまさにご質問にもありました、ものの見方に起因するものなんですね。その人たちは、数字やファイナンスといったツールを使いながら徹底して会社全体のバランスを考えて「こういう風に考えないといけない」と思考するよう、若いときから鍛えられているんです。決して営業や生産管理が出来ないという訳ではなく、あくまでそのファイナンスをツールとしたものの見方を鍛えているので、結果的にCEOになっていくんですね。ですから今後は、同じようなことが日本企業でも起こってくるんじゃないかと考えています。
鎌田:分かりました。それでは柴田さん。
柴田:かなり難しいというか、深い問題を議論しているなと思って聞いていました。冒頭でマーサーでの最後の2年はニューヨークとシンガポールと東京を行き来していたと言いました。そのときに私がやっていた仕事はグローバルトランジションといって、世界中から選抜された5人がマーサーそのものを変えていくタスクフォースでした。そのときに感じたのは色々な環境要因はもちろんのこと、言語の問題や表現方法、あるいは思考パターンが違うというだけであって、彼らと私のあいだでは何ら本質は変わらないなという結論でした。たとえばグローバルカンパニーで電話会議なんかをやると、アメリカ人とか英語圏の人たちは電話会議が得意だから、“わらわらわら〜”と喋ります。でも、どんどんズレていく(笑)。それは何故だろうと思っていたのですが、英語は主語の次に動詞が来るじゃないですか。“I like this water. 〜 私はこの水が好きです”なら“I like”でもう分かっちゃう。だからその後を聞かないんです。日本語だと「この水は、私としては、好きじゃないかもしれないけれど…」とか(笑)、最期まで聞かないと分からない。そんなこともあってか、我々は小さいころから「人の話は最後まで聞きなさい」と言われてきました。だからよく聞くわけです。英語や中国語は文法的にすぐ結論が分かってしまうから、どんどん話を重ねていくし、しかも人の話をお互いに聞いていない。英語圏の人々は人の話を2割ぐらいしか聞いていないんじゃないですかね。わーっと話しているうちに、私やドイツ人やスウェーデン人や韓国人が、「ちょっとズレてるよ? そもそもこういうことじゃないの?」と言うと、「おお、そうだ」となる(笑)。ですから卑下することはまったくありません。彼らはアバウトですから、「ぜんぜん話が違うじゃん」と、あるときから思うようになります。さすがに夜中12時までワインを飲んでメシを食って騒いで翌朝6時に起きて「おい走るぞ」とか言われると、参りますが(笑)。そういうパワーはともかくとして、他にそれ程の差はありません。ただ慣れていないことと、我々は英語を“勉強”してきちゃっているので、気持ちのうえで少々の引け目を感じるだけなのかなと思いますね。ものの見方だの何だのにはそれ程の違いはありませんから、皆さんも自信を持ってどんどん進んで頂きたいと、私としては考えています。
鎌田:ありがとうございます。話はまだまだ尽きませんが、一旦ここでラップアアップしましょう。有事とグローバル。今日は二つの論点を掘り下げていったわけですが、ともに共通していたのは環境が固定化しないようにすること。そして良質な刺激を与え続けることでした。それからも多様性というキーワードもありましたね。そもそもこれは多様性なのか、それともちょっとした慣れの問題なのか。そのような投げかけが最後の一節だったんだろうと思います。
皆さんのなかにもまだまだ論点があろうかと思いますが、ここで一度ブレイクを入れ、次のディスカッションに向かっていきましょう。ではまずは一旦、パネリストのお二方に盛大な拍手をお願い致します(会場拍手)。





















.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)
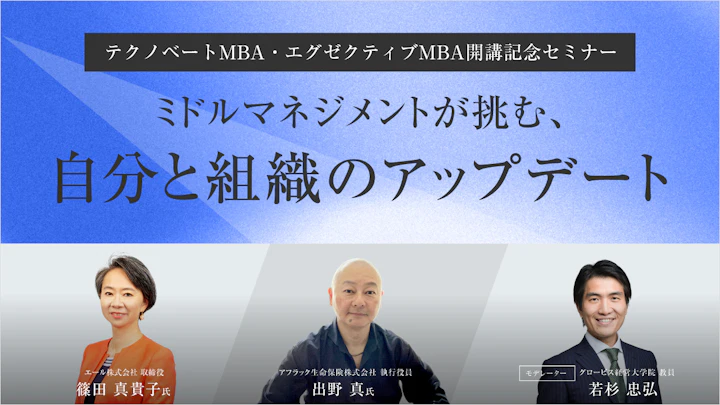
.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)


.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)