
「リーダーの育成に尽力しなければ、次代には日本の国際競争力は地に落ちる」――。40を超える企業の再生から見えた日本の景色と将来像を、元・産業再生機構代表取締役専務で、現在は経営共創基盤代表取締役CEOを務める冨山和彦氏が語った。SILC 2007 autumn初日の基調講演「再生の修羅場から見えてくる日本の課題」より詳報する(文中敬称略)。
企業破綻の病因は「経営」に帰着する

産業再生機構では、カネボウ、ダイエーのような大企業から地方の中小企業まで、40を超える企業の再生に携わりました。そこは決してきれいごとでは済まされぬ修羅場でした。切なく悲しい物語も目の当たりにしました。企業を倒壊する原因の多くは人間の「業」に起因するものです。つまり、全ては誰の身にも起こりうる物語なのです。人間は成功よりも失敗から学ぶものが多い。だから今日は、再生の現場から私が学び取ったものを少しでもお届けできればと思います。
産業再生機構は小泉(純一郎)政権の経済政策の中枢に据えられ、発足しました。有用な経営資源を保持しながら、他方に過剰な債務を抱えた企業を健常な状態とする手助けをすることで、日本の産業再生を加速させる狙いがそこにはありました。個人、企業、国が互いに連環していることは言うまでもありませんが、国の政策を通じて企業や人間の業を俯瞰することで気づいたことは多く、そうしたお話もできればと思っています。
産業再生機構で企業再生のためにとった手法は、(銀行側・債権者側から見ると)「金融と産業の一体再生」と呼べます。(企業側・債務者側から見ると)「財務と事業の一体再生」とも呼べるでしょう。
自力再生の難しくなった企業のバランスシートは多くが、実質の企業価値(バランスシートの左側)に対し、債務(バランスシートの右側)が過剰になっています。借金を返すのに100年はかかるだろうと思われるような会社に良い人材は就職せず、債務超過の状態では設備投資も適わないため事業価値も高められません。結果として、破綻への一途を辿るほかないのです。この悪循環を断ち切ることが「再生」につながります。つまり、金融工学的な手法を用いて過剰債務を切り崩し(バランスシートの右側を小さくし)、同時に経営課題を明確にして新しい戦略を打ち出し企業価値を高めていく(バランスシートの左側を大きくする)。これを両輪で回すことでバランスを整え、企業の健常化を図るわけです。
「なぜ、そんな状態になるまで放っておいたのか」――。企業規模の大小、業界・業態や地域に関わらず、企業破綻の病因は結局のところ、「経営」に帰着します。経済環境の悪化など環境要因を持ち出す人もありますが、それではダイエーがダメになった一方でイオンやイトーヨーカドーが躍進した理由が説明できない。
経営がダメになるということは、経営者がダメになるということです。現代の日本企業が抱える問題の大半は人材の問題であると私は考えています。
40年前、小売業のおける最強・最高の経営者は(ダイエー創業者の)中内功でした。しかし、その彼ですら最後には自ら興した企業を荒廃に導いてしまう。同様に、経営でいえば、ビジネススクールなどで多角化の好例として褒めそやされてきたのが繊維から興り、化粧品や食品に展開したカネボウのペンタゴン経営と呼ばれる手法でした。しかし、これも崩壊します。
元から問題があったわけではなく、優秀と言われる経営者、他社をして見倣わせる経営であっても、どこからか道を誤る。つまり、カネボウやダイエーが踏んだ轍は、誰もが踏みうるものなのです。
経営に係る病は今も進行しています。とりわけ経営を担うマネジメント人材、そして企業統治を担うガバナンス人材が圧倒的に脆弱化している。現場の人材はまだ良いのです。日本人元来の生真面目な気質などが支えとなって、企業のなかで堅牢な基礎構造を築いています。
平和と豊かさが人的競争力の低下を招くパラドックス

では、なぜマネジメント人材、ガバナンス人材、即ちリーダーが脆弱化するのか。一つは、この国が平和で豊かな良い国だからでしょう。例えば中国などに目をやると、経営者や官僚などトップに登りつめるためには、あの強大な人口構造のなかで勝ち抜かなければならない。しかも、その戦いは命を賭すほどに厳しい。中国政府の権力闘争では何か一つ間違えば命をとられることもあると聞きます。かたや日本の政界では反旗を翻しても、せいぜい所属の党から除名される程度で、総理大臣が変われば復党もできてしまう緩いものです。
日本も戦後の復興期は厳しかったのです。中内(功)さんにせよ、(ソニー創業者の)盛田(昭夫)さんにせよ、焼け野原の何もないところから世界と互角に戦う企業を興してきました。当時は、日本円が世界で全く通じず、また持ち出せる外貨の額も制限されていました。そんな時代に、私の父親は商社マンとしてオーストラリアに駐在し、鉄鉱石の輸入に取り組みました。その頃、オーストラリアでは、鉄鉱石は戦略的金融物資であり、輸出が禁じられていました。また、当時は対日感情の悪い国も多く外を歩けば石を投げられたり、刃物で刺されたりするようなところもあった時代です。そんな悪条件に歯を食いしばって耐え、輸出禁止を解除させてみせた日本人がいたからこそ、以降の日本の鉄鋼産業は発展したのです。
世界には、当時の日本人と同じような決意を持って戦いに臨んでいる人たちが多くいます。私たちは、そうした人たちと競争し続けなければいけないということを、忘れてはなりません。
こういうことを言うと、「サービス業は国内産業だから関係ない」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、(観光業などを考えてみても分かるように)潜在的には常に世界と競争しているのです。日本という小さな国のなかで“お山の大将”になって満足するのではなく、いつ外資と直接対決になっても勝ち抜けるよう、自分たちの企業の水準をどこまで高めるかは、常に世界を意識して考えていくべきと思います。
リーダーが脆弱化している理由として、もう一つ、日本的な学歴エリートの存在を挙げさせてください。私自身、東大の出身ですが、大学受験での結果などというものはリーダー選抜においては全く無意味です。ペーパテストで他人が用意した回答に従順に辿りつきさえすれば、東大には合格できます。かたや海外の大学では課外活動におけるリーダーシップの経験など、多面的に評価して合格者を選抜します。
結果として何が起きているか――。試しに東証1部上場企業における成長性・収益性と、経営役員に占める東大出身役員の比率をグラフ化してみたところ、ご覧のとおり(とグラフを提示)、非常に顕著な結果が見られました(会場笑)。日本の官僚、一流企業のトップには未だ東大卒が多くいますが、「高学歴だから」というだけでその実力を過信せず、リーダーとしての資質を公正に評価し、人材育成と人材配置の最適化を図ってください。
また、世襲オーナー企業の経営継承モデルの持続性にも疑問符をつけたいと思います。創業者が苦労のすえ築いた楼閣に、自動的に座る2代目が経営者として弱いのは当たり前のことで、圧倒的に修羅場に立った経験が不足しているのです。帝王学は機能していないと言わざるを得ません。
さらに、それを支える“番頭”陣も弱体化しています。かつては、貧しい家庭に育った優秀な子供は高等教育を受けることは諦め、中卒・高卒で地方の優良企業に就職しました。そのため地方のオーナー企業には大概、有能な番頭が揃い、彼らが“殿様”を支えたのです。しかし近年は、貧富の差が縮まり、優秀な子供は都会の大学に進み、大企業に就職するなど、都市部に偏在するようになりました。つまり、少し油断すると、頼りない2代目の殿様と足軽だけの会社となってしまう。オーナー企業(とりわけ地方の)というのは、そうしたリスクに晒されているのです。
こうしたオーナー企業が倒れる典型的なパターンがあります。凡庸な2代目に経営が軸足を移すと、社内に親戚縁者が増えてきます。出来の悪い子供を「入れてくれ」と頼まれると、断り切れないのです。情実採用を繰り返すと、他の社員は「やっていられない」と感じます。そうして組織が崩壊していきます。また地方では、「酒は同級生のAの会社から仕入れ、石油は幼馴染のBの会社から仕入れ・・・」というように、相見積もりも取らずに仲間同士で支え合う構造が散見され、結果として数字にルーズな経営となっていきます。
ここで親戚を切れるか。友達を切れるか。それだけの強い人間になれるか。自分は経営者としての冷酷無比さを発揮できたとしても、例えば次代の経営者となる自分の子供を冷徹に育てたいか。そう問われると、私も即答はできません。
産業再生機構を通じて私が携わったオーナー企業の2代目、3代目のなかに、“放蕩息子”は一人もいませんでした。皆、真面目で優しい。そしてその優しさが経営破綻につながってしまったのです。
ヒトの論理とカネの論理の正反合一を取るのが経営者の務め

では、どのような経営、どのようなリーダーが求められているのか。
経営コンサルタントの私が言うのも何ですが、世に数多ある経営論のなかで役に立つものなどほとんどありません。経営の基本原則は、「売り上げ−コスト=利益」であり、この利益がゼロより大きくなければならない。ただ、それだけです。この絶対的な方程式からは、いかなる経営者も逃れられない。だから、カネの論理(財務)に対しては冷徹でいなければならない。
しかし一方で、この方程式を成り立たせるのがヒトの論理(事業)であるのも、また事実です。売り上げを作り出すのも、コストとなるのも、冷徹な合理だけでは決して動かぬヒトであり、これをコントロールしない限り、プラスの利益は創出できないのです。
この合理と情理、カネの論理とヒトの論理という正反合一を高い次元で成し遂げるのが「経営」であると、私は考えます。
過去に「ヒトの心はカネで買える」といった若者がいましたが、経営の原則から考えれば、ヒトの心は買うべきではないし、簡単に買えるなら人望で買ったほうがいい。そのほうが安上がりで、利益につながるからです。
しかし、残念ながらヒトというのは、それほど単純なものではない。良いことをすれば悪いこともする。善意から悪事を働く矛盾を見せることも少なくない。例えばコンプライアンス(法の遵守)を人間の善悪だけを捉えて議論すると必ず失敗します。なぜなら、ヒトは理屈やルールだけで動くものではないからです。たとえJ-SOX法(日本版企業改革法)が早くから施行されていてもカネボウの粉飾決算は起きたと私は断言できます。彼らは自らの懐を膨らませるためではなく、会社という村社会を守るため、家族や仲間の生活を守るため、それがより大事な正義であると信じて不正を働いたのです。株主の論理だとか、法律だとか、そんなものは関係なかった。そこにコンプライアンスの難しさがあります。
日本で起きる犯罪に、絵に描いたような悪人というのは、ほとんど見られません。心の弱い善良な市民が、ルールではなく、自らの正義に従ったために犯すケースが大半ではないでしょうか。他方、米国型の犯罪というのは、『スター・ウォーズ』や『指輪物語』に見られるように、善意の欠片も見られない強大な悪人の存在が前提となっています。スター・ウォーズの『ジェダイの復讐』で、ダースベーダーを倒せば世界平和が訪れる、といった具合にです。しかし日本はそうではありません。トップを倒しても何も変わらないのです。事務次官が捕まろうが、総理大臣が代わろうが、政治は変わらない。なぜなら、問題の根幹がトップにはないからです。
サービス業は、とりわけ、ヒトあってこそのビジネスです。人間の弱さや、喜び、悲しみ、そうした数値には置き換えられない難しさを洞察する努力を失わないようにしてください。
ヒトの意思、感情に対する洞察の重要性に加えて、もう一つ、強く申し上げたいのが、マネジメントにはゴールがないということです。
長く経営に携わっていると、かつてできていたことが、できなくなります。なぜならヒトは変わるから。そして周囲も変わるからです。私たちは日々、老い、子供たちが大人へと成長します。顧客の望むものは毎日のように変容し、経済環境も自然環境も、一つところに留まることはありません。
周囲が変わる以上、同じことを繰り返すだけではダメなのです。ヒトは過去の出来事を美化する動物ですが、愚直にPDCA(Plan Do Check Action)のサイクルをまわし、常に過去を否定し、自己革新を続けなければ荒廃を招きます。「あのころは良かった」と過去を美化する発言が増えたり、飲み屋での会話が過去の自慢話ばかりになったら、経営者を辞めたほうが(あるいは辞めさせたほうが)いいでしょう。産業再生機構で扱った会社の経営者の99%は、過去の栄光にしがみついていました。
また、マネジメントには正解もありません。経営学の世界で、「成果主義をとるべきか、年功序列をとるべきか」というように、AかBかという議論をする学者が散見されますが、これは大きな間違いと言わざるを得ません。厳格な儒教社会では例えば年功序列が機能するでしょうし、成果主義がより機能する社会もあるでしょう。リーダーの登用にしても同じことです。これまで産業再生機構で41人の社長を選んできましたが、そのポイントは千差万別でした。年齢を重視した場面もあれば、成果だけを見て選んだ場面もあります。カネボウ化粧品のケースでは、経験の多い年齢の高い人を登用したほうがカルチャーフィットが良いかとも考えましたが、最終的には40歳代の知識(賢治)さんを登用しました。経営判断というのは常に、「A or B」ではなく、「A vs B=C(創造)」なのです。
そして、経営において最も大切なもの。それはやはり哲学や理念です。何のために会社を経営するのか、何のために経営者をやっているのか。その哲学や理念を本当に大切と思うのであれば、ほかのことは泡(あぶく)と感じるはず。犠牲にできるはずです。
日本という国は、嫉妬の文化に裏打ちされた社会です。大衆の想いとマスコミの意図と政治の思惑が一つになると、どんな人でも犯罪者として祭り上げる可能性があると思っておいた方がいい。この嫉妬の文化は100年たっても変わらないでしょう。変わらないものには、どう対峙するかを考えるほうが健全です。例えばビジネスのなかには、大衆の嫉妬を買うことがマイナスに作用するビジネスと、ブランド品のように大衆の嫉妬がプラスに働くビジネスがあります。嫉妬がマイナスに作用するビジネスを営んでいる人は、自身の豪勢な生活が大衆の目にどう映るか、それを想像してみなければいけない。私自身、産業再生機構で企業再生に当たっている期間は、銀座のバーやゴルフ場などには行きませんでした。それは「美学」などというレベルの話ではなく、ヒトの感情の構造や権力抗争の存在など、自分をとりまく環境を構造的に把握し、そこでのあるべき価値判断を自らの哲学に照らして考えてほしいと思っているのです。
人的競争力の向上が国際優位を守り抜く最後の砦となる

あと少し、マクロ的な観点からお話をさせてください。
日本の一人当たりGDP(国内総生産)は、かつて名目ベースで世界で1、2位だったこともありますが、実質ベースでは、バブル経済頂点の1992年の6位が最高値です。それが、現在は18位にまで落ちています。
言い換えれば、これは、日本人一人当たりの国際競争力がどんどん低下しているということです。オーストラリアでは、物価は上がっているが所得も増えているので、国民は物価が高いとは感じていません。逆に日本はどんどん貧しくなっているのです。皆さんも海外出張などに行くと、それがどこであっても「以前よりも物価が高いな」と感じるはずです。
日本は天然資源に乏しく、今も食糧の6割以上、エネルギーの大半を国外に頼っています。戦後の国際的な競争優位は人的資源のみによって保ってきました。その人的競争力を失ったら、すぐに飢えてしまう国なのです。
農業を振興し、食料自給率を高めようという議論はありますが、日本の稲作は石油がなくなると維持ができないものです。これまでは国際的な競争力があったので(石油などの天然資源保有国が)こぞって売ってくれていましたが、競争力を失った小国を誰が相手にしようと考えるでしょうか。例えば今、日本と中国を引き比べたら資源保有国は、どちらとパイプを太くしたいと考えるでしょう。競争優位の源泉であった人的資源の質が落ちてきていることを私たちはもっと深刻に捉えなければなりません。
ですから皆さんも積極的にヒトづくりに取り組んでください。「最近の若い人はすぐ辞めてしまうから」と、人材教育を疎かにするのは間違いです。20歳代の若者を育てるのは、企業の社会的責任なのです。国の成長を担保する公共財を作っていると考え、労を惜しまないでください。
俯瞰して考えれば、人材の流動性はもっと高まったほうが良いぐらいです。大企業のなかには非生産的な仕事をしている高学歴の社員が山ほどいます。官と民、産と学などに高くそびえる壁を取り払い、人的資源の配置を最適化していくべきです。壁は厚く、最初はビクともしないかもしれない。けれど、諦めずに叩き続けたいと思います。改革とは、そういうものです。ベルリンの壁も、そうして崩れました。
あらゆる場面で構造改革をやり抜かねば、近い将来、日本は世界のGDPの上位リストから消えてしまいます。今後、世界で勝ち残るのはヒトを大切にしている国か、希少な天然資源を持っている国のいずれかでしかあり得ません。国の経済政策に頼るのではなく、民間から改革を興すのが本来の自由主義経済の姿です。そこを一緒に目指していきましょう。
[対談]冨山和彦氏V.S.グロービス経営大学院学長 堀義人

堀:中内功さんのように最強・最高の経営者であっても、自己変革を続けられずに組織を誤った方向に導くことはある、というお話がありました。どうすれば良い経営者でい続けられるのでしょうか。
冨山:本人は自分がダメになっていることに気づけないんですね。権力・組織というのは恐ろしいもので、本人にそうと気づかせない状況を自動的に作り出してしまうのです。アドルフ・ヒトラーの著書などにもありますが、(例えば中内さんのような)専制君主がいる組織では、彼に全ての意思決定を委ね、余計なことを考えずに済むほうが心地いいと思う人が自然と拡大再生産されます。気づけない経営者だけが悪いわけではないのです。リーダーが自分のクビを途中で討たせるための何か仕組みのようなものが必要なのかもしれません。
堀:批判されて心地いいと感じる人は少ないですから、自分の意に添う部下ばかりを周りにおいてしまう、ということも往々にしてあります。どのようにして自分を律し、組織の正常性を担保し続ければよいのか。例えば松下幸之助さんは自身への批判を積極的に言ってもらうようにしていた、という話を聞いたことがあります。
冨山:難しい質問です。そこに一般解はなく、個別解になるのでしょう。進言役は友人でも誰でもいいと思いますが、その相手を尊敬していない限り、真摯には受け止められないというのが現実ではないでしょうか。かつては銀行がその役割を一部、果たしていました。銀行から資金を引き上げられたら企業は立ち行かなくなるため、効力がありました。悲しいかな、人間は弱い生き物なので何らか強制力とセットになっていることが必要なのかもしれません。
改革を遂げるには命を賭する覚悟が必要

堀:私は社外取締役にその役割をお願いしています。
会場:社外取締役に意見を求めても、例えばサービスや技術の細部まで理解していてはもらえず、意思決定にブレが生じるのでは?という不安があります。
冨山:社外取締役がビジネスのディテールを知らないのは当たり前です。でも、私はそれでいいと思っています。究極な話、社外取締役は平時のときは寝てもらっていても構わない。「この経営者はダメだな」と思ったとき、迷わずクビを切ってさえくれればいいと考えています。それがガバナンスの本質ではないでしょうか。
私自身、自分の会社(経営共創基盤)には経営諮問委員会を設置しており、その唯一の権限は私に引導を渡せるということです。いざとなったら本気でクビを切ってもらわなければならないので、他のパートナーには株も均等に持っていただいています。そこだけは最初から仕組み化しておく必要があると考えました。
堀:良いリーダーの指標としては、最近、AQ(逆行指数)に注目しています。一番高いレベルのリーダーは、「試練を楽しんでマネージする」のだそうです。人を育てる意味でも、自分を鍛える意味でも、もっと試練が来ないかな、などと思います。
冨山:経営の質を高めるためには、経営者が修羅場に身を置き、苦労することが大切です。従って、部下から悪いニュースが上がってくることを苦とするようになったら黄色信号です。経営者は良いニュースを退屈に思い、悪いニュースに目がキラキラと輝くようでなければいけない。良いニュースなどというのは、単なる部下の自慢話。悪いニュースのときこそ、経営者の出番です。そこでアドレナリンが出るか出ないか。どうしたら、そういう経営者になれるかという解は残念ながらないのですが。
堀:お話のなかで、「親戚を切れるか」「友人を切れるか」という厳しい問いかけがありました。
冨山:ズルイ知恵ではありますが、合理の観点から冷徹なことを行う場合には、外部の力を使うというのも一案です。歴史を振り返っても、日本は、聖徳太子の時代から、大きな構造改革が必要な場面では外圧を上手に利用してきました。
例えばカネボウが、(繊維事業の出身者が役員の半数以上を占めていた当時の)経営会議で自ら、繊維事業の撤退を決めるなどということは、どれだけ待ってもありえなかったと思います。これは、外圧(としての産業再生機構)があったからできたのです。また、カネボウ化粧品のときには、その役割を(当時、産業再生機構の執行役員でカネボウの会長兼最高経営責任者(CEO)を務めていた)余語邦彦さんが担いました。余語さんというのは、大変に優秀な方であるのと同時に、人から嫌われることを苦にせずに合理に徹することができる日本人としては稀有な意志力の持ち主なのです。知識さんには長期間、経営を続けてもらわなければなりませんでしたので、余語さんに悪役を務めてもらいました。
堀:改革の必要な場面では、常にそれに抵抗する勢力が出てきます。古い因習を打ち破ろうと出てきた新しい力は往々にして潰されてしまう。その繰り返しのなかで、「我こそは!」と思う人の減ってしまうことが心配です。
冨山:社会やその時点の常識に逆らおうとするのであれば、それ相応の覚悟が必要なのだと思います。日本だけが、既得権益を持った人に優しいわけではなく、権力闘争においては攻められる側も必死なのです。だから、本気で改革をしようと思ったら、脇を固め、死する覚悟で臨むほかありません。小泉さんも竹中さんも功名を立てようなどとは考えず、一心に取り組んだから構造改革をあそこまで進めることができた。私が産業再生機構で4年間やり遂げられたのも、本当に自分の社会的使命を全うしたいと思っていたからです。ほんの少しでも「自民党から国会議員になろう」とか、「国から勲章をもらおう」とか考えていたら、経済産業省などとあそこまでは戦えませんでした。
あれもこれもと望む人は、チキンレースで最後にブレーキを踏むのです。一つに決めていなければ、本当の強さは出せません。ほかの全てを犠牲にする勇気がなければ信念などというものは貫けないのです。
ですから経営者は胆力を持たねばなりません。本気で改革をしようと思ったら、何度も厳しい局面に身を置かされます。その際、胆力がなければ下血してしまいます。産業再生機構で携わった経営者の多くも血を吐き、流すようなつらい場面を乗り越えました。経営者の真価は、そうした厳しい局面でこそ、問われるのです。



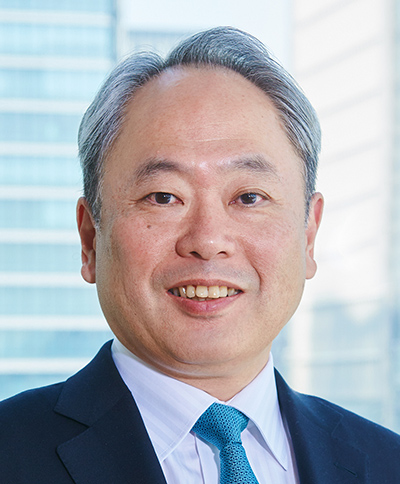



















.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)
.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)
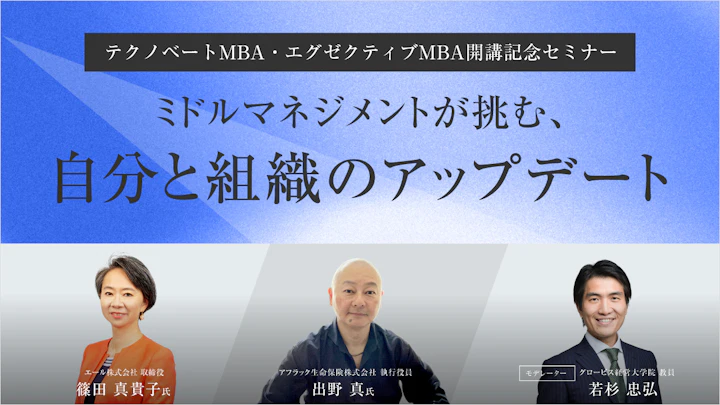
.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)


.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)

















.png?fm=webp&fit=clip&w=720)
.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)

