今回のテーマは「リーダー力を高める」ということで、これまでの経験などを基に、今、求められるリーダー像について、お話ししていきます。
私は、産業再生機構で4年間、41案件を管理してきました。そこで感じたのは、日本の企業において、現場はきちんとしているということ。現場が駄目になっているケースもたまにありますが、それは経営側が現場を駄目にしている、あるいは現場で働く個々人のモラール低下を招くようなことをしてしまっているのが原因であることが、ほとんどです。経営状態の悪化をバブルのせいにする経営者も散見されますが、結局はそのときどきの指導者や指導層の質が良くなかったとしか言いようがありません。
裏返して言うならば、残念ながら、日本の社会や企業、おそらく政治などでも、リーダーの力が総体的に低下しているのです。経済の病の根源がリーダー力の劣化ということであれば、そこに何らかのメスを入れない限り、本質的な企業再生は成し得ません。それには、今いるリーダーを良いリーダーに変えること、持続的に良いリーダーが作られる、あるいは選ばれる仕組みを構築することの2点が重要と、私は考えています。本日はそのために私が産業再生機構で何を考え、どのような努力をしてきたかを中心にお話しします。
済の本質的再生にはリーダーを鍛える仕組みが不可欠
「企業再生」を簡単に説明すると、その方法論は、企業側に立ち、「債務を減らしてください」と銀行にお願いすること、銀行側に立ち、企業の自助努力を促し、その価値を高めることに大別できます。企業価値というのは、その会社がきちんと利益を生み出しているかに収れんされますから、つまりは事業そのものを改善しなければなりません。
債務低減と企業価値向上、その2つを同時に行うのが企業再生あるいは事業再生ではありますが、特に労力を要するのは企業価値の向上です。事業の収益性を高いレベルに引き戻し、大幅マイナス状態のキャッシュフローをプラスに転換させるわけです。売り上げを増やすことと、コストを低減することを、コツコツと、しかし同時並行で達成していきます。経営者から現場に至るまで一丸となって、血のにじむような努力をしない限り、企業体質を改善することはできません。
産業再生機構が扱った41案件には、実に様々な業種がありました。どの企業も、それぞれ異なる理由で業績を落としてはいましたが、問題の根底には常に経営者の力量不足がありました。
再生案件では、経営者に辞職を求めるところからプロジェクトが本格始動するのですが、しかし、100人に聞いて99人は「辞めたくない」と言います。「会社の経営を悪化させたのは、自分ではない」「自分がいなくなったら、会社が回らなくなる」などと言い張るのです。しかし、デューデリジェンス(詳細な調査に基づく評価)をすると、意思が弱く、経営にはまるで向いていないことが確認されたりします。人間の本性というのは、修羅場になるほど、明るみに出るものです。
経営者も、最終的に「弱い人間」であることにかわりはありません。しかし、普通の人と同じくらい弱い人がリーダーを務めることは、リードされる側にとっては悲劇です。本来、経営者はより強い人間が務めなければならないのですから。あるいは経営者に育ち行く過程で、強い人間へと鍛え抜かれていなければなりません。
現在、経済状況は少し持ち直したかに見えますが、経営層は依然、脆弱なままであり、経済は砂上の楼閣に置かれているようなものです。
ではなぜ、強いリーダーの不在に至ったのでしょうか。その理由の一つに、彼らが現場の最前線にいた頃に置かれていた環境や動機付けのあり方が挙げられます。彼らが若い頃には、上司に逆らうことは自ら昇進の芽を摘むことにつながりかねませんでした。「上司の言うことは間違っているような気もするけれど、彼の期待通りに答えておこう」というように従順であることが期待され、強い意思に基づき、時には上司に逆らってでも行動すること、すなわち、強いリーダーになろうとすることは、むしろ不利と認識される風潮にあったのです。これが引いては、組織全体の誤った舵取りを是正する力の劣化へとつながりました。
人間は怠惰な生き物ですから、競争環境に置かれ、強いプレッシャーがかからない限り、あえて組織に逆らうような動きはしないものです。アメとムチがなければ、真の意味で一生懸命にはなりません。ここでいうアメとムチは、もちろん、報酬などの経済的なインセンティブではなく、おそらく、自己実現の意欲や、好き嫌いのような感情であると考えられます。
地方企業再生はフェアな人事制度の導入から
日本経済再生の鍵は、昭和20年代まではおそらく存在した、勝ち負けのフィールドで個人を鍛え、リーダーを輩出する仕組みを取り戻すことにあると、私は考えます。競争が格差を生むという論がありますが、競争の敗者は競争によってしか救えません。競争の敗者を社会主義的に救済しようとすれば、今度は敗者が弱者になってしまいます。産業の歴史を振り返り、政府が保護した産業で世界的競争力に勝ち得たものは一つもありません。典型例が繊維業界です。東レも帝人も、政府が救済措置を廃してから再興したのです。
ところで、地方経済は大変だとよく言われますが、産業再生機構で30件ほど地方の案件に取り込んでみて気づいたことがあります。
地方企業の経営が駄目になっている理由は、誤解を恐れずに言えば、名門企業のオーナーが、創業から3代目、4代目の代を迎えたことにあります。地方企業の経営者は、創業期や戦後復興期には苦労を重ね、鍛えられていたのですが、代を重ねるにつれ、緩くて頼りない“殿様”と化してしまいました。
彼らを支える家臣団が脆弱になっていることも、課題です。多くの地方企業は創業から3代目ぐらいに当たりますが、創業期は地域の優秀な人材が経営者を支えていました。しかし現代では、地方出身の有能な人材は大学入学を機に大都会に出てしまい、田舎には帰りません。
創業一族の後継者であっても、都会に出たきり戻ってこないケースは見られます。総領家の長子は仕方なく事業を継承することが多いですが、優秀な人であれば、都会でゼロからの挑戦をしたりしています。結果として出戻ってくるのは、あまり優秀ではない人材。彼らをオーナー一族だからということで管理職に奉りたてた結果、企業としての舵取りができなくなっていく、というわけです。
では、なぜ優秀な人間は都会に行ってしまうのか——。端的に言えば、都会のほうがフェアな舞台が用意されていることが多いからです。組織運営の成否を分かつのは、人事の公正さにあります。制度として、年功序列制を取るか、成果主義を取るかといったことは、さしたる問題ではありません。大切なのは、関係者がアンフェアだと思わないような仕組みとすることです。
これは逆に言えば、地方企業は公正な人事制度を導入するだけで見違えて良くなる、ということでもあります。病巣がはっきり分かっているので、そこさえ切除すれば急速に回復するのです。むしろ、カネボウとかダイエーのような大企業のほうが、問題が生活習慣病的になっているので治癒に時間を要します。
日本は今、中国やインドといった国々に経済面で追い上げられています。相手は死ぬ気に競争していますから、富はそちらに流れていきます。どちらの国も、それぞれ日本の10倍の人口がいますから、私たち日本人の平均が、インドや中国の上位10%の人材と競争していることを、これからは意識しなければなりません。
経営者に求められるのは、大人の心と青年の体
経営というのは、弱い人間の集団をして一つの目的に向かって組織的に行動をとらせることです。つまり、人間というものを分かっていなければ為しえないことであり、“子供”にできる仕事ではありません。例えば、老いることの悲しさや、従業員の家族の人生にまで責任を負わなければいけない苦しさが、“子供”には分かりません。私自身も、20歳代前半の頃は分かってはいませんでした。
また、年を重ねるとお金では買えない大事なものが分かります。“子供”の経営者は、これを解さないため、「人の心はお金で買える」などと言ってしまったりします。しかし、人の心をお金で買うほど効率の悪い経営はないですね。なぜならば、人望があれば、お金など払わずとも人の心は手に入れられるからです。
人間に対する理解は、10年、20年、30年・・・と、年数を重ねるうちに蓄積されていきます。ですから、基本的に経営というのは、40歳過ぎの人がするべき仕事であると私は考えています。
ただ、40歳を過ぎれば、経営者としての質の差異はさほどはないと私は考えています。心・技・体の総合力から言えば、40歳代も60歳代も大きな違いは見られません。なぜなら、年齢を重ねるに従い経験値が上がる一方で、体力が衰えていくからです。
経営者は、極限までシビアな状況で、シビアな問題と対峙することが求められます。年齢がゆえに体力負けしてしまうと、冷静な判断ができなくなり、本来の目的と外れた結果に会社を導いてしまう恐れがあります。
年齢の話をしますと、グロービスで経営学を学んだ知識賢治氏をカネボウ化粧品の社長に抜擢したとき、彼は41歳でした。カネボウは伝統があり保守的な会社ですから、猛烈な反対に遭いました。日本の組織を分かっていないと言われましたが、こちらは日本の組織を多く見てきた結果として、41歳の彼を敢えて社長に選んだのです。
カネボウ化粧品を本当に支えているのは、社員9000人いる中の7000人に当たる若い美容部員です。停滞したカネボウの中で、若い女性からみて誰が一番社長になってほしいかというと、それが、みんながよく知っており、「20年後には社長」と思っていたプロパー社員の知識氏でした。そこで彼を社長にしたのです。
経営者の適性には、年齢も学歴も性別も関係ありません。大切なのは、従業員、ひいては組織を動機づけし、進むべき方向に導いていかれるか、ということなのです。
マネジメントということで言えば、時代時代でいろんな理論が流行しますね。ただ、流行り廃りがあるということは、逆を返せば、それが普遍的な本質ではないということです。
では、普遍的な本質はどこにあるかというと、古今東西、昔から言われている法則に尽きます。簡単に言えば、「売り上げからコストを引いたものが利益である」ということです。プラスの利益を上げ続けない限り、企業の存続はあり得ず、この法則からは、いかなる経営者も逃れることはできません。
では、利益を上げない事業を簡単に切り捨てることはできるでしょうか。冷徹な経済合理に従うか、従わないかは、人間の意思と感情にかかっており、法則通りにマネジメントをし続けられるか、というのは、実際問題としては、とても難しいものです。
また、合理だけで企業活動を永続させることはできません。なぜなら、社員一人ひとりを動機付ける理由は一様ではなく、その基となる人間の情理を理解しない限り、組織を動かすことは不可能だからです。
従って、経営者は経済合理性を求める合理と、人を動かす情理のぶつかり合いに日々さらされることとなります。経営とは本質的に、そうした自己矛盾と葛藤を抱え続けるものなのです。情理と合理は両立を必要とするものであり、合理に逃げ込む人も、情理に流される人も、いずれは足下をすくわれます。
良い会社というのは、自分達が普段していることを疑い、改善を続けられる会社です。けれどこれは、人間の本性には反します。人間というのは、見たいものだけを見る生き物であり、自己の過ちといった見たくないものからは目を背ける生き物だからです。
戦略などというものは十中八九、あてが外れます。経営の差異を分けるのは、見込みを誤り上手くいかなかったとき、どこまで自分の傷口に塩をもみこむように冷静に客観的に見つめられるかにかかっています。そして、分析結果をできるだけ早くフィードバックし、軌道修正した人たちが勝者として残ります。例えば太平洋戦争のとき、真珠湾攻撃で一番学んだのは米軍でした。彼らはその後、航空母艦と飛行機ばかりを作り、結局は戦争に勝ちました。
人間の生来の性質に反することを続けるのは、しんどいものです。自己革新は自己否定から始まりますから、勝ち続けるためには、常にしんどい思いをし続けなければならない。飲み屋の話題が半分以上、昔の自慢話になったらやめたほうがいいですよ、経営者は。
将棋の駒と指し手の両方の視点を持って経営にあたれ
経営において、AかBかという議論はナンセンスで、常にAでもありBでもあると思ってください。例えば、成果主義も年功主義も、ある場合においては正しいし、ある場合においては間違っている。ただ、それだけの話です。そこで働く人たちの思いや動機付けと整合していればうまくいくわけです。
トップダウンもボトムアップも同様です。企業経営というのは重い歯車を回すようなものであり、上から下に向かう力と、下から上に向かう力の両方が同時に働かない限りは、動きません。経営者にとって大事ことは全体として、その歯車が本当に回っているかどうかをマネージすることです。
将棋に例えれば、指し手と駒の両方の視点で勝負の行方を見つめる技量が求められます。
トップダウンとボトムアップの均衡を取るわけです。
指し手の視点を持ち続けることは、孤独感との戦いでもあります。駒としての自分には盤上に多数の仲間がいますが、将棋を指すのは経営者ただ一人ですから。そう考えると、経営者には孤独に耐える強さと、勝負を乗り切る胆力が求められることが、想像いただけるでしょうか。
経営者というのは本来、明確に自分で「なる」という意思を持って、なるべきものです。では、どうやってそこまでいくかというと、二つの要素があります。一つは実践です。実践するなかで失敗をし、学ぶのです。失敗を通じてしか知識は肉体化しません。ですからグロービスで勉強して得た知識も、実践で試して痛い目に遭わなければ、肉体化しません。
もちろん、知識があることも重要です。弾の撃ち方くらいは知ってから戦場に臨まないと上陸する前に撃たれてしまいますから。失敗を無駄にしないためにも、経営に関する知識は持っていたいものです。
繰り返しとなりますが、今、日本ではリーダーが足りなくなってきています。本当の意味でのリーダーを目指す人がこの社会に増えてくるか、その人達が正しい努力と正しい道筋で自分自身を鍛えていくか。あるいは鍛えていきたい人が増えたときに、彼らに社会が場を用意できるか——そういったことを組み合わせて、リーダーの育成を考えていきたいと思います。
皆さんも是非、自らの胆力の鍛錬を続けてください。鍛錬をする人が今の従来の倍数となれば、社会の上部構造が変わってきます。そうすると、現場は依然として強いですから、まだまだ日本経済は成長できるし、少子高齢化をいろんな意味でスムーズに乗り切るベースになると思います。
リーダーは真のエリート商売です。エリートとは、他人の人生に、良くも悪くも影響を与えます。経営者が失敗をすると、他人の人生を壊してしまいます。社会に対して持つインパクト、個人として負わねばならない責任の重さがあります。例えば、産業再生機構のトップとして多くの会社の再生に関わるなかで、当然リストラに踏み切る場面もありました。すると、社員の家族、特に全く責めを負わない子供の将来にまで関わってしまうわけです。時間的にも空間的にも、周りの人にそれだけの影響を与えます。それが実はエリートの本質だと私は思います。今日のこと、1週間後のことから、10年後、100年後のことまで、どれだけ全部同時にマネジメントできるかが重要です。経営者は、権限、権力を持っているわけですから、それだけの責任を持つのです。
リーダーにとって最も大事なのは志です。その人の人間性、哲学、世界観、歴史観です。なぜなら、一番難しい局面での意思決定は、ほとんど情報がなく不確定な要素が多い状況で求められるものだからです。周りの反応も想定しづらいでしょう。そのなかで右か左か舵取りを決めるのです。そういう状況でよすがとするのは、自分の志です。それがない人間はそこで迷い、タイタニックで言えば目の前の氷山に突っ込んでいってしまいます。
なお、私自身が使っていた一つのメルクマールは、自分の子供が成人してビジネスパーソンとなったときに、難しい言い訳をしなくて済むようなものを意思決定として選ぶということした。結果がうまくいったものであっても、そうでなくても、です。そういった志といえるものを、是非とも、日々のいろんな苦労のなかから作り上げていってください。
<対談>経営共創基盤代表取締役冨山和彦氏×グロービス経営大学院研究科長田崎正巳
田崎:冨山さんの話を聞いて、会場の人は「リーダーになるのは難しい」と感じているようですが、いかがですか。
冨山:産業再生機構では、41の案件で41人の社長を選んだのですが、その経験から「リーダーの間口は意外と広い」と思っています。トップとして機能した人を分析すると、一番大切なのは、肝が据わっていることです。
再生機構では、中小企業を自分で経営して会社を潰して自己破産した経緯のある人物を雇いました。なぜなら、彼らは失敗する会社の気持ちをよくわかっているからです。会社が失敗しても命を取られるわけではないとわかっていて、物事を前向きに考えられる人——というと、実はそんなに間口はそんなに狭くない気がします。
田崎:先ほど、修羅場で本性が出るみたいな話がありましたね。社長になって初めて修羅場を経験するのではなく、どこかで免疫をつけたほうがいいですよね。
冨山:大変な場面に身をおくと、自分のことがよくわかります。そうした状況の中で、自分はトップに向いているのか、胆力のあるトップの補佐につくとよいのかが。胆力が必要な仕事はトップでしかできません。戦略策定能力とか分析力というのは多くの人が出来ることです。
私自身、先輩と共につくったCDI(コーポレートディレクション)という会社が、92年にバブルが崩壊して潰れかかり、修羅場的展開になった経験があります。今は再建して良い会社になりましたが、当時、発見した“自分”はたくさんありました。どんな場面で自分が情に流されるか流されないか、誰に対して強く出られるのか出られないのか。初めて自分の本性がわかるんですよ。
困った上司についた時など、苦境がリーダー力を伸ばす
田崎:ここに来ている人をはじめ、普通のビジネスパーソンにとって、修羅場を経験することはなかなかないのではないでしょうか。
冨山:例えば、出来の悪い上司についたときなんて、良いですね。無能な上司の下にいるというのはとても勉強になります。うまく仕事を任せて結果を出させてくれる上司は、必ずしも良い上司ではないんですよ。そういう上司は、実は部下に仕事を任せていなくて、勝ち戦のシナリオに部下を乗せるのが上手なわけですから。
むしろ、うまくいかなかったら全部部下のせいにする上司がいますよね。そういうのが実は良い経験になります。結局、自分がトップになったら、全部自分の責任ですから。困った上司の下にいる時期は、結果は出せないかもしれないけど、自分のリーダー力を伸ばすチャンスですよ。
田崎:冨山さんの話で、いつも印象に残るのが「合意と情理」。浪花節の人に見えながら、あるところは厳しくそろばんを弾く、というある意味、正反合一な部分は、どうやって身に付けるのですか?
冨山:板ばさみで苦しんだ経験がどれだけあるかでしょう。苦しんだ経験のデジャヴがあれば、困難な状況でも最適解にたどり着く確率が高いですから。
あとはもう言い古された言葉ですが、相手の立場に立って物を考える能力、想像力ですね。合理ばかり見ていると、大抵、情理の部分で足をすくわれます。以前、ある製薬メーカーであった話ですが、社員を集めてパッパッと紙を配って早期退職を勧告した人がいました。その紙に書かれていたのは、冷静に読めばみんな納得するような内容でしたが、いちいち説明するのが面倒くさいからバーッと配ったという……。結局、早期退職を勧告したその人はクビになりました。現実の社会での政治に負けたら、どんなに正論を述べても通用しませんから、情理に背を向けてもいけないのです。
田崎:「コイツは使えそうだな」というのは、どこを見て判断されますか?
冨山:自分が目指している理念とか志を、貫き通す意志力があるかどうか、という点があります。経営というのは上に行けば行くほど“変える”ことが仕事になります。すると社内では当然、抵抗が起きるわけで、それにめげずに頑張れるかどうかが重要です。
カネボウ社長の知識さんは、意外と老獪な人です。なぜそうかというと、彼は社内ベンチャーを成功させた経験があるんですよ。社内ベンチャーのように画期的なことをやろうとすると、邪魔する人間が出て、社内の資源を使おうとしても使わせまいとしますが、相当上手に老獪に社内の政治をかいくぐって振舞わないとなりません。それができたということは、彼は意思の強さに加えてマキャベリズムも持ち合わせていたということでしょう。
どのような“エリート”を目指すかは、自分の人生への賭け
田崎:ここで聴講しているビジネスパーソンの中には、それぞれの会社なりにエリートである人が結構いるかもしれません。その人達はそれでいいのか、それともその会社なりのエリートを否定したほうがいいのか。どのように判断されますか?
冨山:ここは賭けになるのですが、どっちにベット(賭け)するかですね。ずっといけそうだと当分は大丈夫だということにベットするのであれば出世コースに乗っておとなしくしているのも1つの選択肢です。自分が偉くなる頃に状況が変わって、波乱が起きるのではないかと思うのであれば、自分の人生を自分でコントロールできる方向を目指す道もあります。どちらもあっていいのですよ。
30年後の未来は誰にもわからない、20年後もひょっとすると怪しい——。私が就職したときには興銀も長銀も日債銀もありましたから。それが今や、みずほといったらただの都市銀行で、日債銀、長銀は破綻してなくなりましたから。
ただ、エリートだという自信があってそれだけのギフトをもらっている自覚があるのであれば、社会とか神様に対する責任として、本物のエリートになる努力をしたほうが良い気がします。
田崎:最近ある記事を読んで、これからのリーダーは大変だなと思いました。何を読んだかというと、高校生の意識調査で、日本では「偉くなりたい」という回答が少なかったというものです。これまで、会社という組織内での向上心があるという前提で指導していたのに、それがなくなったら、リーダーとしてどうしたらいいですかね。
冨山:そもそも論として、マネジメントをする側とされる側では、される側のほうが常に多いわけです。みんながみんな経営者になりたかったらチームが成り立たないわけですから、おっしゃる話題はあまり大きな問題ではないと思っています。あるいは、若い人にとってロールモデルとなるリーダーが、周りにいないのだと思いますよ。
それに、職務権限規定と指揮命令系統だけで部下が動いてくれたらこんな楽なことはないわけで、それを超えて組織をエンカレッジすることが、経営そのものなのです。


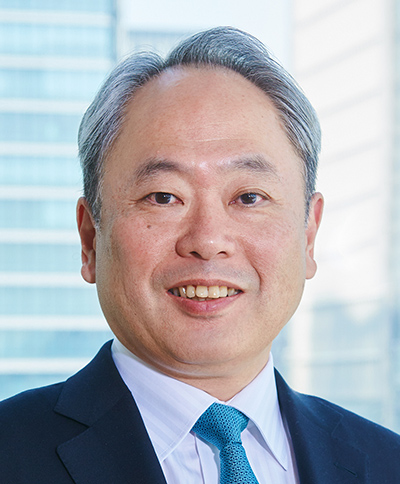


















.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)
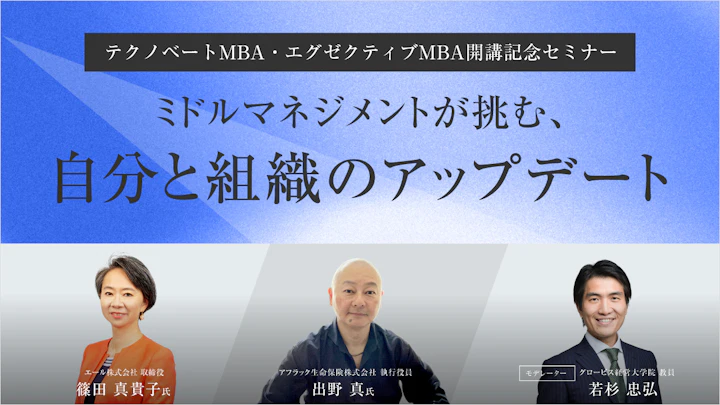
.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)


.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)

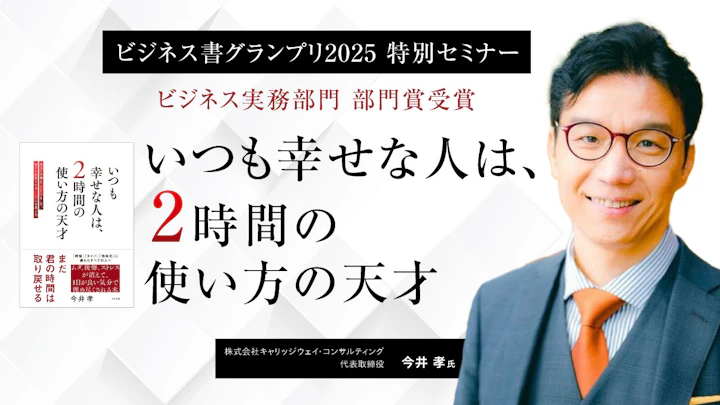















.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)



