
会員限定
プロジェクトマネジメント入門② 原理・原則編/スチュワードシップ・チーム・ステークホルダー
プロジェクトマネジメントについて、ビジネスパーソンが知っておくべき基礎知識を体系的に解説するシリーズです。プロジェクトマネジメントのガイドラインであるPMBOK®(ピンボック)では行動や意思決定の指針として12個の原理原則を定めています。この動画では、そのうち「スチュワードシップ」「チーム」「ステークホルダー」について解説します。
割引情報をチェック!
すべての動画をフルで見よう!
初回登録なら7日間無料! いつでも解約OK
いますぐ無料体験へ
・組織を正しい方向に導くためのルールを作りたい方
・ルール運用のヒントを知りたい方
・業界のルールを変えるヒントを得たい方
ルールのすり抜けとは、「ルール本来の目的や意図に沿った行動ではなく、都合の良い行動をとって成果を出そうとする人間の性質」のことを指します。他方でこれが業界ルールを変えるきっかけとなることもあります。よくある事例を通して、ルールのすり抜けが生じる背景を理解し、効果的なルールの策定と運用方法について学んでいきましょう。

会員限定
プロジェクトマネジメント入門② 原理・原則編/スチュワードシップ・チーム・ステークホルダー
プロジェクトマネジメントについて、ビジネスパーソンが知っておくべき基礎知識を体系的に解説するシリーズです。プロジェクトマネジメントのガイドラインであるPMBOK®(ピンボック)では行動や意思決定の指針として12個の原理原則を定めています。この動画では、そのうち「スチュワードシップ」「チーム」「ステークホルダー」について解説します。

会員限定
フォースフィールド分析 ~人々の心に作用している見えない力を可視化する~
フォースフィールド分析とは、人々の心に働く、推進力と抵抗力を分析する手法です。 推進力とは前に進めようとする力であり、抵抗力とはそれを妨げる力です。これらは人々の心に作用している見えない力ですが、この分析を使えば、プロジェクトや計画がうまくいっていない場合などに、その原因を推進力と抵抗力に分けて捉え可視化することができます。 フォースフィールド分析によって、「心に働いている力」を可視化し、チームを前に進めていきましょう。

会員限定
プロジェクトマネジメント入門③ 原理・原則編/価値・システム思考・リーダーシップ
プロジェクトマネジメントについて、ビジネスパーソンが知っておくべき基礎知識を体系的に解説するシリーズです。プロジェクトマネジメントのガイドラインであるPMBOK®(ピンボック)では行動や意思決定の指針として12個の原理原則を定めています。この動画では、そのうち「価値」「システム思考」「リーダーシップ」について解説します。

会員限定
共有地の悲劇 ~個別最適ではなく、全体最適を考える~
「共有地の悲劇」とは、メンバー全員が協調的行動をとっていれば皆に恩恵がもたらされる状況だったにも関わらず、各自が合理的判断の下に個別行動した結果、皆にとって好ましくない結果がもたらされる現象を指す言葉です。 サステイナビリティ(持続可能性)への視点や取り組みが企業にとって不可欠なものとなった現代において、個別最適が全体に望ましくない結果をもたらすという考え方が注目されています。このコースでは、日常の場面や国際的な取り組みなどの事例を通じて、「共有地の悲劇」という現象に対する理解を深めていきます。
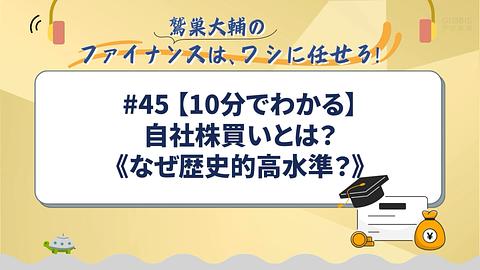
01月27日まで無料
【10分でわかる】自社株買いとは?《なぜ歴史的高水準?》/鷲巣大輔の「ファイナンスは、ワシに任せろ!」
多くのビジネスパーソンが苦手意識を持っているが、今さら聞けないと思っているファイナンス知識を簡単に楽しく学べるコース。グロービス経営大学院でファイナンスクラスの講師を務める“ワッシー先生”こと、鷲巣大輔氏が解説します。本コースは日本最大のビジネススクール グロービス経営大学院による、ビジネスパーソンが予測不能な時代であっても活躍のチャンスを掴み続けるヒントをお伝えするVoicyチャンネルからの転載コンテンツです。 Voicyチャンネルはこちら https://voicy.jp/channel/880 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2026年01月公開)

無料
みんなの学習図鑑 ~新人育成・オンボーディング編~
グロ放題をうまく活用したいと思ってはいるけれど、他の人がどう学んでいるのか気になりませんか? このシリーズは、ユーザーのみなさんの“超リアル”なグロ放題の活用法をまとめた学習図鑑です。 シナリオ作成も撮影も、実際のユーザーさんご自身に行っていただきました。 ぜひ自分に合った学習スタイルを見つけて、グロ放題ライフを楽しんでください!応援しています! ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2026年1月制作)

無料
みんなの学習図鑑 ~グロ放題に聞いてみよう!編~
グロ放題をうまく活用したいと思ってはいるけれど、他の人がどう学んでいるのか気になりませんか? このシリーズは、ユーザーのみなさんの“超リアル”なグロ放題の活用法をまとめた学習図鑑です。 シナリオ作成も撮影も、実際のユーザーさんご自身に行っていただきました。 ぜひ自分に合った学習スタイルを見つけて、グロ放題ライフを楽しんでください!応援しています! ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2026年1月制作)
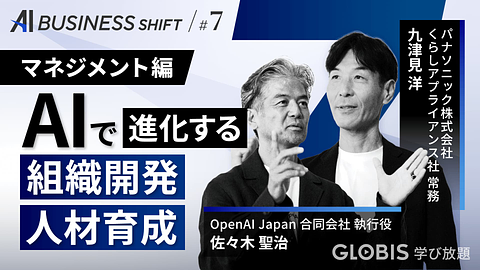
01月27日まで無料
AI BUSINESS SHIFT 第7回 マネジメント編:AIで進化する組織開発・人材育成
本コースは、リーダー・マネージャー層を対象に、AIのマネジメント活用・組織活用を体系的に学ぶ『AI BUSINESS SHIFTシリーズ(全12回)』の第7回です。 第7回「AIで進化する組織開発・人材育成」では、AIは人や組織にどのような影響を与えるのか、人や組織はAIと共にどのように進化していくべきかについて学びます。 ■こんな方におすすめ ・AI時代の組織開発や人材育成のポイントを学びたい方 ・組織開発や人材育成を担う人事担当者や現場リーダーの方 ・OpenAIやパナソニックHDの取り組みを参考にしたい方 ■AIシフトシリーズとは? 『AI BUSINESS SHIFTシリーズ』は以下の3部構成で設計された全12回のシリーズです。(順次公開) https://unlimited.globis.co.jp/ja/tags/AI%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E3%82%B7%E3%83%95%E3%83%88 ・基礎編(第1回〜3回):リーダーやマネージャーに求められる、AI時代の基礎的なリテラシーの強化を目的としたコース ・マネジメント編(第4回〜7回):AI時代のリーダーシップや組織変革を中心に学ぶコース ・機能別戦略編(第8回〜12回):AI時代における機能別での戦略のあり方を中心に学ぶコース より実践的なAIツールの活用法について学びたい方は『AI WORK SHIFTシリーズ』をご視聴ください。 https://unlimited.globis.co.jp/ja/search?tag=AI%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%95%E3%83%88 ※本コースは、AIのマネジメント活用を学ぶ「AIビジネスシフト」シリーズの一環として提供しています。 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2025年12月制作)

会員限定
ロジックツリー ~物事を把握する「分解」の考え方~
ロジック・ツリーとは、モレなくダブりなく(MECE)を意識して上位概念を下位の概念に分解していく際に用いられる思考ツールです。 問題解決で、本質的な問題がどこにあるのかを絞り込む場面や本質的な課題に対して解決策を考える場面で活用できます。 ※2020年3月30日、動画内のビジュアル、表現を一部リニューアルしました。 理解度確認テストや修了には影響ございません。

会員限定
MECE ~抜け漏れなく分解・構造化して考える~
MECEとは、ある物事を「モレなくダブりなく」切り分けた状態のことです。例えば年代別など、全ての人がその切り分けのどこかに属するようにします。MECEは論理思考の基本で、物事を分解し、構造化する際に役立つ考え方です。 例えば、状況を調べて問題箇所を特定する必要がある場合に、いくつかのポイントに分解して考えることが重要になります。その際に、モレやダブリなく分解することができれば、分析や問題解決の効率性が高まります。 ロジックツリーやマトリックス、あるいはその他のフレームワークなどにも応用できる基本となるコンセプトであるMECEを理解しましょう。 ※2018年2月15日にコース内容を一部リニューアルいたしました。 リニューアルに伴い、コース動画一覧は全て未視聴の状態となります。 なお、リニューアル前に当コースを修了している方は、コース修了済のステータスに変更は発生いたしません。

会員限定
貸借対照表 ~企業の財務活動と投資活動を読み解く~
財務諸表の要の1つである貸借対照表(B/S)は、ある時点(決算期末時点)での企業の資産内容を表します。継続的な経済活動を行っている企業の一瞬の姿をとらえたスナップ写真ともいえる貸借対照表を理解し、企業の財務活動と投資活動の結果を読み解く力を身につけましょう。 ☆関連情報 フレームワークでニュースを読み解く、日経電子版の記事もぜひご覧ください。 「米SPAC上場ブーム、引き金はコロナ禍の失業対策」 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC27E130X20C21A4000000/?n_cid=DSPRM5277

会員限定
リーダーシップとマネジメントの違い ~違いと使い方を理解する~
リーダーシップとマネジメントの違いとは、主にそれぞれ異なる特性と役割にあります。リーダーシップは人と組織を動かし変革を推し進める機能、マネジメントは定められた戦略やルールに基づき効率的に組織を運営する機能とそれぞれ定義されています。このコースでは、リーダーシップとマネジメントの違いについて詳しく学んでいきます。2つの違いと意味を理解し、日頃の業務やコミュニケーションに役立てていきましょう。 ☆関連情報 フレームワークでニュースを読み解く、こちらの記事もぜひご覧ください。 「吉本興業のこれからに必要なのはどっち?リーダーシップ、それともマネジメント?」 https://globis.jp/article/7224 「日本電産の永守氏にみる有事のリーダーシップ」 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58614190Y0A420C2X12000/?n_cid=DSPRM5277

会員限定
クリティカル・シンキング(論理思考編)
業種、職種、役職を問わずビジネスパーソンが業務のスピードとクオリティを効率よく高めるために必要不可欠な論理思考力。 論理思考のベースとなる考え方を学び、実務で陥りやすい注意点を理解することで、実践で活用する能力を養います。 論理思考の基本を身につけ、コミュニケーションや業務の進行に役立てましょう。 論理思考を初めて学ぶ方は、以下の関連コースを事前に視聴することをお薦めします。 ・論理思考で仕事の壁を乗り越える5つのポイント ・MECE ・ロジックツリー ・ピラミッド構造 ・演繹的/帰納的思考 ・イシューと枠組み ※2019年10月31日、動画内のビジュアルを一部リニューアルしました。 内容に変更はなく、理解度確認テストや修了には影響ございません。

会員限定
ロジックツリー ~物事を把握する「分解」の考え方~
ロジック・ツリーとは、モレなくダブりなく(MECE)を意識して上位概念を下位の概念に分解していく際に用いられる思考ツールです。 問題解決で、本質的な問題がどこにあるのかを絞り込む場面や本質的な課題に対して解決策を考える場面で活用できます。 ※2020年3月30日、動画内のビジュアル、表現を一部リニューアルしました。 理解度確認テストや修了には影響ございません。

会員限定
論理思考で仕事の壁を乗り越える5つのポイント
伝えたいことがうまく相手に伝わらない。仕事がなかなかスムーズに進まない。 仕事をしていると、そんな場面に直面することもあるのではないでしょうか。 そんな方に役に立つのが「論理思考」です。 物事を論理的に考えられるようになると、仕事の効率が格段にアップします。 このコースでは、論理思考のコツを5つに絞って説明していきます。 ビジネスパーソンにとって必須のスキルである「論理思考」をいち早く身につけましょう。 「クリティカル・シンキング」をまだ見ていない方にもお勧めのコースです。

会員限定
MECE ~抜け漏れなく分解・構造化して考える~
MECEとは、ある物事を「モレなくダブりなく」切り分けた状態のことです。例えば年代別など、全ての人がその切り分けのどこかに属するようにします。MECEは論理思考の基本で、物事を分解し、構造化する際に役立つ考え方です。 例えば、状況を調べて問題箇所を特定する必要がある場合に、いくつかのポイントに分解して考えることが重要になります。その際に、モレやダブリなく分解することができれば、分析や問題解決の効率性が高まります。 ロジックツリーやマトリックス、あるいはその他のフレームワークなどにも応用できる基本となるコンセプトであるMECEを理解しましょう。 ※2018年2月15日にコース内容を一部リニューアルいたしました。 リニューアルに伴い、コース動画一覧は全て未視聴の状態となります。 なお、リニューアル前に当コースを修了している方は、コース修了済のステータスに変更は発生いたしません。

会員限定
MECE ~抜け漏れなく分解・構造化して考える~
MECEとは、ある物事を「モレなくダブりなく」切り分けた状態のことです。例えば年代別など、全ての人がその切り分けのどこかに属するようにします。MECEは論理思考の基本で、物事を分解し、構造化する際に役立つ考え方です。 例えば、状況を調べて問題箇所を特定する必要がある場合に、いくつかのポイントに分解して考えることが重要になります。その際に、モレやダブリなく分解することができれば、分析や問題解決の効率性が高まります。 ロジックツリーやマトリックス、あるいはその他のフレームワークなどにも応用できる基本となるコンセプトであるMECEを理解しましょう。 ※2018年2月15日にコース内容を一部リニューアルいたしました。 リニューアルに伴い、コース動画一覧は全て未視聴の状態となります。 なお、リニューアル前に当コースを修了している方は、コース修了済のステータスに変更は発生いたしません。

会員限定
ロジックツリー ~物事を把握する「分解」の考え方~
ロジック・ツリーとは、モレなくダブりなく(MECE)を意識して上位概念を下位の概念に分解していく際に用いられる思考ツールです。 問題解決で、本質的な問題がどこにあるのかを絞り込む場面や本質的な課題に対して解決策を考える場面で活用できます。 ※2020年3月30日、動画内のビジュアル、表現を一部リニューアルしました。 理解度確認テストや修了には影響ございません。

会員限定
リーダーシップとマネジメントの違い ~違いと使い方を理解する~
リーダーシップとマネジメントの違いとは、主にそれぞれ異なる特性と役割にあります。リーダーシップは人と組織を動かし変革を推し進める機能、マネジメントは定められた戦略やルールに基づき効率的に組織を運営する機能とそれぞれ定義されています。このコースでは、リーダーシップとマネジメントの違いについて詳しく学んでいきます。2つの違いと意味を理解し、日頃の業務やコミュニケーションに役立てていきましょう。 ☆関連情報 フレームワークでニュースを読み解く、こちらの記事もぜひご覧ください。 「吉本興業のこれからに必要なのはどっち?リーダーシップ、それともマネジメント?」 https://globis.jp/article/7224 「日本電産の永守氏にみる有事のリーダーシップ」 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58614190Y0A420C2X12000/?n_cid=DSPRM5277

会員限定
因果関係 ~原因と結果の関連を理解する~
因果関係とは、あるものごとが「原因」と「結果」の関係でつながっていることです。「因果関係」という言葉は様々な場面で使われますが、ビジネスにおいても、因果関係の把握は問題解決などの場面でとても重要な思考技術の一つです。 因果関係を把握し、因果関係を明らかにすることのメリットやコツを身につけましょう。
より理解を深め、他のユーザーとつながりましょう。
100+人の振り返り
ar87531
販売・サービス・事務
最後のテスト問題も気を付けないと訪問することが目的となるリスクもあると思う
koedon
人事・労務・法務
ルールだけで社員の行動は管理できないという点については非常によくわかります。
ルールのすり抜けが具体的にどういうことかよく理解できませんでした。ルール違反とは違うのか?ルールが形骸化しているのではないか?
ルールすり抜けとは組織がうまくまわっていないことを示すと思います。対応が短絡的過ぎてなんか違うような気がする。
a_7636
人事・労務・法務
ルールのすり抜けは、本人の意識だけの問題ではないのでは?
例えば上司が「すり抜けか、否か」を見極める目をもって、ルールの趣旨に沿った行動をしている人を正当に評価することで、「ルールのすり抜け」の発生はだいぶ減ると思います。
あと、そもそもルール自体をむやみに増やさないのもコツかも。
ミスを防ぐためのルールを積み重ねれば、工数がかさむだけで形骸化まっしぐらです。
ozawa_h
IT・WEB・エンジニア
ルールのすれ抜けはよくあります。特に目標が正しく設定されていない場合は自分に好都合のような方法を選びます。
目標とその理由を明確にしてコミュニケーションを取るようにします。
trd-ty
その他
忙しすぎる場合に発生しやすいのは分かる
yyacupun
人事・労務・法務
ルールのすり抜けという言葉を初めて聞きました。
今までルールどうり進まない理由わかりました。
sphsph
メーカー技術・研究・開発
手段の目的化。
そうなってしまいます。説明しても難しい。正しいKPIの設定かと思います。
yosshi--
営業
そもそもの目的が何だったのに振り返ることや、風土の醸成の重要性を実感しました。
saaya-ryu
営業
ルールを作るだけでなく、人を動かす為の行動が必要であることを学んだ。
500nozomi
その他
ルールは、その形式よりも意味するところが重要であり、浸透のために十分なコミュニケーションを心がけたい。
gouda0922
経営・経営企画
KPIの目的を説明して理解させていきます
kawakami
金融・不動産 関連職
本来の目的を見失わないようにしたい
0402_nyy
IT・WEB・エンジニア
ルールのすり抜け
・楽をしたい
・プレッシャー回避
・タックスヘイブン ルールの裏をかく
会社にあけるルールを作る 業界ルールを変えるヒントを得る
chimo_s
資材・購買・物流
購買業務はルールを作り、守ってもらう立場です。
ペナルティによる抑止も必要なこともありますが、日常の中でどのように従業員へのサービス向上が図れるかという観点で、今回学んだ観点を活かそうと考えています。
asami-m
人事・労務・法務
目標を達成するためには結果だけを重視するのではなく過程を楽しむポイントを持つことも重要
適切に過程を行うことができれば適切な結果
が付いてくると思いました
33tiger
人事・労務・法務
成果だけでなくプロセスを評価する場合に申告ベースとするには一定のルールやペナルティを設定しがちだが、エビデンスのないものは性善説に依存し過ぎないよう注意が必要
tsuchida_94
営業
ルールのすり抜けという言葉を初めて知りました。自分でも事実やっていることが非常に多いと思います。
maki4878
その他
ルールのすり抜けを上司に提案すると「それは正当化だ」と言われてあしらわれることがあった。
動画の内容より、
・達成される目的を踏まえていること
・楽な方法を取りたいだけではないこと
以上2点を踏まえてしっかりと説明することが必要だと思った。
genta-
営業
必要最低限で済ます事があるが、そのことを言っている
lanian
その他
身近に起きがちだとつくづく実感。本来の目的をしっかり伝えることと、コミュニケーションをしっかいとることが
重要。
hisashi_a_77
メーカー技術・研究・開発
組織メンバーが目的を理解し、腹落ちしていないと、ルールのすり抜けが発生するのだと感じました。それを念頭に置いて設定し、kpiを達成したくなる文化を目指します。
osaru3
専門職
すり抜けを改善に実施していく
tomotanino
その他
ルールのすり抜けは明らかな悪意があってのもののように思われるため、実際の現場ではそのようなことはほとんどない。ただ、このルールの解釈の相違、拡大解釈のようなものはあるので、実際の運用上、ルールを明らかに逸脱しない範囲で、関係者でコミュニケーションを取りながら進めていくことが重要になると考えられる。
bad
建設・土木 関連職
ルールのすり抜けにならないようにコミュニケーションの取り方が重要であることがわかりました
職場で生かしていきたい
h_nishimura
その他
そのルールの必要性を理解すること、させること。理解できない、させられないのであれば、そのルールは変えるべき時期である。
touto
営業
ルールのすり抜けが起こらないよう目的をしっかり腹落ちさせる事が必要かと思う。
また守れないルールは作らない方が良い。他のルールも含めルールがルールでなくなる。
s_atmimi
メーカー技術・研究・開発
・最後の問題の解説は、どう見たらいいのでしょうか。
・人間の性質を理解した上で、ルールを設定することが重要ですね。
t-ishiza
販売・サービス・事務
ルールのすり抜けは、コミュニケーション不足が発生している組織では、難しいと思いました。
70sp1208
その他
我社の製造部門では、ネジ締めを確実に行うために作業後に占めたネジにフエルトペンでチェックを入れることになっている。しかし、形骸化しチェックを入れるのが目的となったためか、まとめてチェックを入れ、チェックが入っているのにも関わらず、ネジの緩みがあったとという事象があった。今思えば、作業者にルールの設定の目的が伝わっていなかったと反省している。今回の講義を教訓にそういった組織文化をなくしていきたい。
teruhiko800
営業
組織運営を考える上で必要な考え方である。
意図しない動きにならないような絶妙な設計を模索していきたい。
shonen_3340
その他
普段仕事をしている時でも、意識しないと時おり目的と手段が置き換わりかける場合があるため意識して仕事の振り返りをおこないます。
goanai
IT・WEB・エンジニア
業務の必須事項をシステムへ落とし込む場合のUXの設計
reikou
IT・WEB・エンジニア
ルールのすり抜け やってしまいがちかもしれません
bobo_matsu
IT・WEB・エンジニア
ルールを作る際にすり抜けを防止する発想を持って考えてること、すり抜けを防止するためのコミュニケーションの重要性を理解した
if_1980
営業
ルールが適切か、抜けることができるかを意識する
mika-1016
専門職
テストも理解できない
ot-take
メーカー技術・研究・開発
ルールのすり抜けは起こってしまう可能性がいつでもある、やりづらい・めんどくさいなど。
ルールを守った人を褒める、ルールの意図を説明する、ルールを意図に沿って改善する、それらが大切だと思いました。
mitsuyamaguchi
メーカー技術・研究・開発
罰則を規定するのには問題がありそうだが、最終的には評価で対応することになるのではないか?
kuta_41
IT・WEB・エンジニア
実務でばりばり生かせそうである。
14001
資材・購買・物流
ルールやマナー・条例・法律などを作る事は必要だが、あまりに多すぎたり、守るのが難しすぎたりすると必ずどこかで抜け道を探そうとしてしまう。雁字搦めのルールや条例・法律などは表現の自由を委縮させ、イノベーションの妨げになるので公務員や警察の仕事が増えるだけなのでそのようなルールや条例・法律などは廃止していく必要があると思いました。
nobu79358
IT・WEB・エンジニア
設定されたKPIを形だけ達成するといったルールのすり抜けは、本質的な成果には結びつかないので、ルールが設定されている「真の目的」を理解して行動することが重要。
また、自分がルールを設定する側の場合は、KPIの数値を単純に評価するのではなく、その背景にも目配りするコミュニケーションを行うことで、ルールのすり抜けを抑止していきたい。
d_yamanaka
IT・WEB・エンジニア
ルールを守らない社員の行動を正す為に教育による意識改革に取り組んでいますが、なかなか成果が上がらずに困っています。
say-go
メディカル 関連職
人間は本来弱いものと思っている。ルールのすり抜けを応用して、新たな業界の発想に繋がるという視点は学びになった。
riko0315
資材・購買・物流
自身が直面している課題と合っており、非常に学びの効果があると感じた。応用して活用したい。
ma48458
金融・不動産 関連職
自分も知らないうちにルールのすり抜けをしていたかも…
ルールが設定された意義をしっかり認識し、ルールがプレッシャーになりすぎないようにすることが大事だと思いました。
y-shiraki
販売・サービス・事務
従業員のルールのすり抜けの心理を考えて、ルールや規定を考える必要がある。
状況を見て見直しも必要。
評価制度の目標設定にも、すり抜けに注意が必要。
kankita
営業
副作用報告回数の多い人の行動面や内容にフォーカスする
kazu56209
営業
これは非常に難しい問題ですね。ルールのすり抜け=マンネリ化ともいう。
ある程度のコミュニケーションなども重要なのですね
mamisan
専門職
日頃のコミュニケーションが重要だと感じました
gosimakeizou
営業
都合がいいのと効率的とは違う、安全性がおろそかになったり周りの人が不愉快になります。
75475
メーカー技術・研究・開発
ルールのすり抜けは避けることも活かすこともできると考える。必要により使い分けて効率的、かつ、有効に仕事ができるようになるヒントになると思う。
ftomo
人事・労務・法務
ルールを設定するにあたり、まずその組織の理念を定め、仲間全員で共有したうえで、理念に向かう上で必要なルールを作る。その上で、ルールから外れるものがいれば、強く正すのではなく、コミュニケーションをしっかりとって、腹落ちさせる努力をする。
shiopipippi
人事・労務・法務
ルールのすり抜けは、目的と手段の混合だと感じました。
atlanticflight
メーカー技術・研究・開発
ルールのすり抜けが起きることを前提に組織のルール作りに当たるよう心がける。ルールのすり抜けを厳しく責めるのではなく、なぜそのような行動が起きるのか、ルールを守りやすくするためにはどうしたらよいか、また、そのルールの目的は何かを組織全員に理解してもらえるようコミュニケーションをとっていく。
ys-ishi
営業
ぱにっぱに、ぱにっぱに、ぱにぱにぱにっく!?
kam519
営業
ルールの作り方に難しさを感じた。
platon
メーカー技術・研究・開発
ルールを破った人に皆が納得する適切なルールを考えさせるルールを作っては
okuchann
営業
楽な行動に走るのではなく、自らの仕事の本来の意義は何なのかをとことん考え、周りの評価だけを気にするのではなく、自分自身の納得性、意義を感じながら仕事をしたいと感じました。
naoyasu_adachi
専門職
ルールのすり抜けは、ルールが効果を発揮しない場合の1つの理由として考慮する必要があるものと理解した。
環境変化に対応できていないことや、机上の空論で作られたルールによる、ルールの形骸化なども考慮した上で、目標達成に適した方法(ルールはその一つ)を節制する必要性を感じた。
katsuoga
経営・経営企画
結果を数字だけで管理しているとルールのすり抜けが起こりやすいと感じています。目的に沿った成果を出せる人の思考や行動を共有してあげるようなフォローも大切ですね。
o_s_
その他
ルールのすり抜けがあるなら見直すとよい?
sakiyam2
IT・WEB・エンジニア
人間誰でも楽な方に流れるというのはよくわかる。過度に負担を増やすことなく、関わる人が納得できるようなルールにすることが重要だと感じた。
alpina_b3s
販売・サービス・事務
ルールのすり抜けというワードを認識していませんでしたが、人間がもつ本来の楽をしたい、要領よく結果を出したいと考えがちです。
それを抑止するには、コミュニケーションとのバランスやインセンティブなどがあれば組織やチームが纏まりやすくなることを学びました。
mo_o
その他
消費者が望んでいるからという大義名分で楽な方法ね解決し、本来望んでいるのか疑問に思われる例はとても多い。
例えば食品の賞味期限。本来は安全のために定められているルールなのに、賞味期限が長い商品が喜ばれるといい、添加物まみれの商品がスーパーやコンビニに並ぶ。
社会全体で安全な食品について学ぶ必要がある。
ksk_aiko
販売・サービス・事務
自分の都合>ルール
で考えてしまうことがないように、
・ルールの目的を常に掴んでおく
・ルールの範囲内でどう解決するか考える
・ルール自体を適切な方法で変えてみる(変えようとしてみる)
これらを実践していきたい。
tsuki_y
販売・サービス・事務
ルールのすり抜けは往々にして起きることだと理解し、すり抜けをする人に丁寧に本来の目的を説明して結果を出せるようにしたい。
makiko-yama
販売・サービス・事務
取り組みの目的を粘り強く説明する。
toshiyukimaki
経営・経営企画
目標設定について、手段の目的化について留意する必要がある。そのためには本来の目的を理解し、行動してもらうまで十分にコミュニケーションする必要がある。
izapon1976
その他
ルールのすり抜けを防ぐために、所属メンバーとの丁寧なコミュニケーションが必要だとわかりました。
残念ながら、現職場ではルールのすり抜けが見受けられますが、少しでも減らせるように行動します。
ankoromochichi
人事・労務・法務
ルールのすり抜けとは、その業務における目的が理解されていない場合に起こるため、目標設定等を行う場合には、コミュニケーションなどを通じて、業務における目的理解を進めることが重要。
nishihira
経理・財務
ルールのすり抜けが習慣化すると、自ら考え自ら行動しなくなる。ルールに依存しているのだが、そのルールを重荷に感じるとすり抜けようとしてしまう。チームでルールを作成する際には、トップダウン式だけではなく、ボトムアップでメンバーが自らルールについて意見を出せる場にすることが解決策の一つではないかと感じた。楽することより行動することに対するやりがいを如何に見出すか。これもリーダーの役割であると内省。
bononomaru
販売・サービス・事務
ルールのみでは行動を管理できないというところが印象にのこりました。ルールをきめても本来通りに守らない、形骸化するということは経験上良くあることだなと思いました。そのことを踏まえたうえで運用するのが大事とおもいました。具体的に良くコミニュケーションする対策が大事というのが心にのこりました。
x0888
メーカー技術・研究・開発
プレッシャーで抑制するのでなく建設的な対策で対処する。
yasukei
金融・不動産 関連職
ルールを作る際には、そのもの自体が義務感や負担にならぬよう状況を見ながら考案することが大切であると思った。
atago08
金融・不動産 関連職
ルールは時に人の行動を制限してしまい、抜け道を探すことを考え新たな問題が出てきてしまうこともあるので、適宜見直しを行い、ルールの改善を行っていきたい。
hiraiwa_kenji
販売・サービス・事務
ルールのすりぬけについてどんなものがあるか、意識して業務にあたります。
buffalo_oshima
経営・経営企画
ルールが形骸化した場合には、さらなるルールを追加するのではなく、目的達成のために効果的な手段は何かを考える必要がある。基本的にルールは破られる(すり抜ける)ことを認識しておく必要がある。
takehito_otsuka
経営・経営企画
無意識でやってしまっていたり、そんな気はなくても、やらなければとストレスを感じれば誰しもがやってしまう事だと思いました。本来の目的を明確にし、成果に囚われすぎない事が重要だと思います。
celt
クリエイティブ
悪意はなくても楽をしたいという心理は誰しもあると思う。
怠慢による成果の低下を防ぐために定めたルールが、すり抜けによってルールが形骸化するだけでなく、本当の意味での成果につながらない活動に重きを置くようになってしまうことは皮肉なものです。
ひとを管理するにはルールを作るだけではダメなのだという言葉は心に残りました。ルールとコミュニケーションのバランスが大事ですね。
redpine
IT・WEB・エンジニア
常に目的が何であるか? を問いながら行動をすることで自身の勝手な解釈は抑制可能と考える。一方、自身が守れば良いだけでなく、組織メンバー全員が守らないと意味がない為、組織メンバーにも目的は定期的に伝えながら、意識統一を図る必要がある。聞く耳を持たないメンバーもいる場合、聞く耳を持たないメンバーに対して、影響力のある人の力を借りるなど、打てる手を打つことも必要と考える。
6151
マーケティング
ルールのすり抜けに加えて、正常性バイアスも考慮すると、管理者としては部下と密なコミュニケーションをとることで相手の思考がより分かりやすくなり、訴求ポイントが把握しやすくなるので、結果的に管理者と部下の双方にウィンウィンの関係が生まれる。このことから、本来の目的と目的に沿った方法を正攻法で伝えるようなコミュニケーションを日頃から心がけることでルールのすり抜けを極力減らすことが管理者に求められている。
it_tm
IT・WEB・エンジニア
ルールに込められた目的を理解してもらうことが重要
too_much
営業
評価者がルールのすり抜けを是正するように、ルールの目的をしっかりと理解し、判断、チェックスキルを上げねばならない。
kenji1209
メーカー技術・研究・開発
とくにございません。
ab0110
専門職
本来の目的が達成できるようルールを適宜見直す。
yujihoshi
経営・経営企画
自分のやっていることだけが正しいと思ってるリーダーが、ありたい姿も描かずレポートやミーティングなどをすると、参加するスタッフたちはその場を凌ぐだけのレポートやミーティングになってしまう
muramatsu-a
人事・労務・法務
目的の理解を深める事、設定したルールの本来の意味を理解出来る様に根気強く説明する事。プレッシャーではなく、寄り添ったアドバイスや称賛などによるマネジメントを推進しようと思いました。
suikinchikamo9
その他
こういう人はどこでもいる。成果のプロセスも含めて評価する必要があると思う
shimoosako
人事・労務・法務
業務改善活動(チーム制)の定期報告に対し、報告内容ではなく報告することに目的が移ってしまっている。改めて目的は何かを確認し本来の目指すゴールに導きたいです。
hagisho
資材・購買・物流
結局得したい、楽をしたいという気持ちをいかに抑えさせるかは難しい
nk1225tk
営業
KGI設定においては、目的を明確にし適切なKPIを設定し評価する仕組みをつくる。
ben3369
その他
ルールを軽視する人の行動心理に迫るようなコミュニケーションを意識したい。当事者を非難するのではなく、客観的に何故そのような行動になるのか、具体的には労働災害や環境トラブルにおける人為的ミスに関連して。
uchujinho
営業
ルールのすり抜けを抑制するためには罰則ではなくコミュニケーションが必要。
y_su
人事・労務・法務
ルールを破る人が出れば出るほどルールが厳しくなるが、また新たなすり抜けが起こる。
最低限のルールで教育に力を入れるべきと考える。
uta0612
人事・労務・法務
ルールのすり抜けはなんとなくわかっていることでしたが、人間の本質ということでクリアになりました。ルールのすり抜けにならないようなルール作りを心掛けたいと思います。
summner
金融・不動産 関連職
部下には目的と手段をしっかり理解させるよう説明を尽くしたい。
yuko625830
営業
営業業務に活用できると感じた。
ymh
その他
ルールだけで社員の行動は管理できないという点については非常によくわかります。
shinano777
人事・労務・法務
従業員に対して、KGIに向かうためのKPI設定をしています。KPIの数値を定量的な行動評価としていますが、KPIの数値を追うことが目的にならないよう、その意図であったり目的をしっかりつたえることが必要だと感じました。
miyagawa-toru
販売・サービス・事務
ありがとうございます