パレート分析とは
パレート分析とは、構成要素を大きい順に並べた棒グラフと、その累積量を示す折れ線グラフを組み合わせて、「少数の重要な要因が全体の大部分を占めている」ことを明らかにする分析手法です。
この分析法の最大の特徴は、一目で「何が本当に重要なのか」を判断できることです。たとえば、100人の顧客がいても、実際には上位20人の顧客で売上の80%を占めているといった「80対20の法則」が多くの場面で確認できます。
名前の由来は、イタリアの経済学者ヴィルフレド・パレートが発見した法則から来ています。ビジネスの現場では、限られた時間と資源の中で最大の成果を上げるために、この分析法が重宝されています。
なぜパレート分析が重要なのか - 成果を最大化する鍵
パレート分析が現代のビジネスパーソンにとって欠かせないツールである理由は、「選択と集中」の判断を科学的に行えることにあります。
①限られた資源を最も効果的に活用できる
どんな企業でも時間、人材、予算は限られています。パレート分析を使うことで、「どこに力を入れれば最大の効果が得られるか」が明確になります。例えば、営業活動において、すべての見込み客に同じ時間をかけるのではなく、成約確率の高い上位20%の見込み客に80%の時間を投資する方が、結果として売上は向上するでしょう。
②無駄な作業を減らし生産性を向上させる
多くの人が陥りがちなのが、「すべてを完璧にしようとする」ことです。しかし、パレート分析を行うと、実際には少数の要因が結果の大部分を決めていることが分かります。この気づきにより、重要度の低い作業に時間を費やすことを避け、本当に成果につながる活動に集中できるようになります。
パレート分析の詳しい解説 - 実践で使える分析のコツ
パレート分析を効果的に活用するためには、その仕組みと作成方法を正しく理解することが大切です。
①グラフの読み方と作成手順
パレート図は、左側の縦軸に各項目の数値、右側の縦軸に累積比率(パーセント)を示します。棒グラフで各項目の大きさを、折れ線グラフで累積比率を表現します。
作成手順は次の通りです。まず、分析したい項目のデータを収集し、数値の大きい順に並べ替えます。次に、各項目の全体に占める割合と累積比率を計算します。最後に、棒グラフと折れ線グラフを組み合わせたパレート図を作成します。
重要なのは、累積比率が80%に達するまでの項目数を確認することです。これにより、「全体の何%の要因が、結果の80%を占めているか」が明確になります。
②ABC分析との関係と使い分け
パレート分析は、以前は「ABC分析」と呼ばれていました。これは、重要度に応じて項目をA(最重要)、B(重要)、C(普通)の3つのグループに分類する手法です。
現在では、コスト管理の分野で「Activity Based Costing(活動基準原価計算)」という別のABC分析が登場したため、混同を避けるために「パレート分析」という名称が使われるようになりました。
使い分けのポイントは、詳細な分類が必要な場合はABC分析を、視覚的な理解と意思決定のスピードを重視する場合はパレート分析を選ぶことです。
③80対20の法則が生まれる理由
なぜ多くの現象で80対20の比率が見られるのでしょうか。これは、自然界や社会現象において「べき乗則」と呼ばれる法則が働いているためです。
例えば、顧客の購買行動では、収入の多い顧客ほど多くの商品を購入し、その差が累積されて大きな格差となります。また、商品の品質問題では、少数の根本的な原因が多くの不具合を引き起こすことが多いのです。
この法則を理解することで、ビジネスの様々な場面で「重要な少数」を見つけ出し、効果的な対策を立てることができます。
パレート分析を実務で活かす方法 - 具体的な活用シーンとコツ
パレート分析は、業種や職種を問わず幅広い場面で活用できる実践的なツールです。
①営業・マーケティング分野での活用
営業部門では、顧客別売上分析が最も一般的な活用方法です。例えば、100社の顧客を売上高の順に並べてパレート分析を行うと、上位20社で全売上の80%を占めているケースがよくあります。
この分析結果を基に、優良顧客への営業活動に重点を置いたり、上位顧客向けの特別なサービスを開発したりする戦略を立てることができます。また、下位顧客については、コスト対効果を考慮して取引を継続するか検討する材料にもなります。
商品別の売上分析でも同様の効果が期待できます。売れ筋商品に経営資源を集中させることで、在庫管理の効率化や利益率の向上が可能になります。
②業務改善・品質管理での実践的な使い方
製造業では、不良品の原因分析にパレート分析が威力を発揮します。発生した不良品を原因別に分類し、パレート図を作成することで、最も影響の大きい問題から優先的に対策を講じることができます。
例えば、10種類の不良原因のうち、上位3つの原因で全不良品の75%を占めている場合、まずはこの3つの原因に集中して改善活動を行うことで、効率的に品質向上を図れます。
事務部門でも、問い合わせ内容の分析やクレーム対応の優先順位付けに活用できます。お客様からの問い合わせを内容別に分類し、パレート分析を行うことで、FAQ の充実や業務手順の見直しにつなげることができます。
この分析を継続的に行うことで、改善活動の効果を測定し、さらなる改善点を見つけ出すことも可能になります。重要なのは、一度分析して終わりではなく、定期的に分析を更新し、変化する状況に対応することです。
参考ページ
MBA経営辞書「パレート分析」|GLOBIS学び放題×知見録



















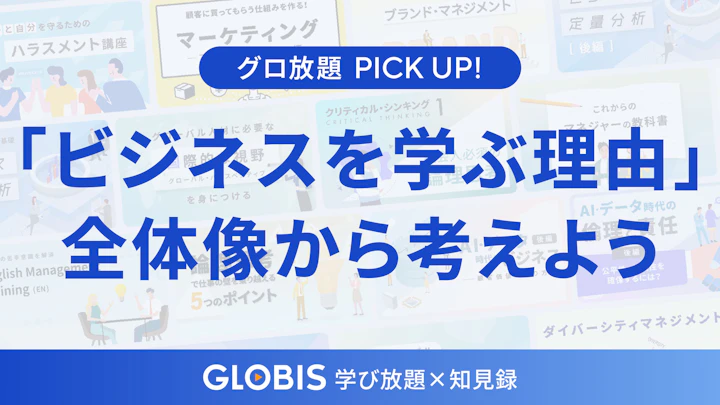











.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)


.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)



.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)
