今年8月発売の『KPI大全–重要経営指標100の読み方&使い方』から「066 1人当たりの人材開発投資」を紹介します。
どのような企業であれ、最後は「人」、特に従業員のスキルややる気が最も重要になることについて異論のある方は少ないでしょう。それゆえ、企業はOJTやOff-JTを通じ、従業員の能力開発に努めるのです。また同時に彼らのモチベーションを高めるべく、魅力的な経営ビジョンを開発・共有したり、適切な評価報奨システムを構築する努力をします。一方で、特に能力開発についていえば、お金をかけたからといって、それがダイレクトに企業の競争力につながるかは微妙なところがあります。もちろん、お金をかけないよりはかけた方がいいのでしょうが、質が伴っていないと、非効率な投資になってしまいます。「1人当たりの人材開発投資」というKPIは、従業員の声を愚直に聞き、その質(効果性など)を同時並行で見る必要性の高いKPIの代表ともいえるでしょう。
(このシリーズは、グロービス経営大学院で教科書や副読本として使われている書籍から、東洋経済新報社のご厚意により、厳選した項目を抜粋・転載するワンポイント学びコーナーです)
1人当たりの人材開発投資
その企業が従業員の能力向上にどのくらいの投資を行ったかの指標。投資としては一般的に研修費用や教材(デジタルのものも含む)費用などが含まれる
KPIの設定例
それほど大きな環境変化もなければ新規採用の人数も少ないので、今年も1人当たりの人材開発投資は昨年並みの25万円が妥当だろう
数値の取り方/計算式
基本的に社内情報より計算する。他社の数字を取るのは難しいが、定性的な評判を取得することはできる
主な対象者
経営者、人事責任者
概要
従業員一人ひとりをいかに教育し、戦力化するかは、企業にとって永遠の課題です。この数値が大きいほど、従業員の能力やパフォーマンスを向上させるための人材開発投資を積極的に行っていることを意味し、人材開発に熱心な企業といえるでしょう。
KPIの見方
この数字が全くないのは大問題ですが、大きければいいというものでもありません。例えば研修ばかりやっていて本業に割く時間が減り、売上げが下がって見た目の1人当たりの人材開発投資が増しても本末転倒だからです。
また、内容面でのブレークダウンも必要です。例えば、新卒採用者向けと中途採用者向けの研修や、若手社員向けと管理職向けの研修とでは、その目的や内容などは当然異なってくるでしょう。新人や非管理職層には手厚い一方、課長以上については自己責任に任せるというのではバランスが悪いといえます。
難しいのは、業務外のいわゆるオフジェイティ(Off-JT)の研修などの費用はわかりやすい反面、オンザジョブ(OJT)の人材開発については、その投資額も効果も測定しにくいという点です。また、オフジェイテイにせよオンザジョブにせよ、本来は費やした時問などの機会費用(その時間があれば生み出せた別の成果)についても考慮する必要があるのですが、その測定は容易ではありません。
KPIの使い方
この数字を気にするのは通常は人事部や経営陣です。絶対的にこれが正しいという数値を設定するのは難しいものの、過去の経験などを参考に目標設定することが多いようです。
また、人事部は他社の人事部と横でのつながりが意外とあり、研修業者に関する情報共有なども結構なされています。そこで得た情報なども参考に、目標数字を極端にオーバーしない範囲で、さまざまな取り組みを行っています。例えば、かつては課長や部長など階層別に一律に研修を行うことが多かったのですが、最近では、計画的に将来の経営幹部候補を選抜して研修を受けさせる企業が増えています。
この数字が高いことは、人材採用の際の武器にもなります。特に論理的思考力やコミュニケーション、マーケティングやアカウンティングなどに代表されるマネジメントスキルは、ポータブルスキル(企業が変わっても持ち運べるスキル)の代表です。企業を選ぶ人間にとって、そうしたスキルを会社のお金で身に付けることができるのは非常に魅力的なのです。
補足・注意点
より厳密にいえば、人事部の育成部門スタッフの人件費といった間接費も人材開発投資の一環ともいえます。時系列比較などを行う際には、どこまでの数字を含めるかをしっかり定義したうえで実施する必要があります。
なお、人材開発投資は、マネジャーやリーダーの育成、さらには業績に効いてくることが理想ですが、必ずしもそうならないという難しさは常に付きまといます。例えばゼネラル・エレクトリック(GE)は人材開発に大きく投資する企業として知られ、実際に一時は時価総額世界一になりましたが、ここ数年間は株価も低迷し、業績は冴えません。優秀な人材育成のためにはお金や手間は必須ですが、それは必ずしも企業としての成功を約束しないのです。
関連KPI
社外研修比率














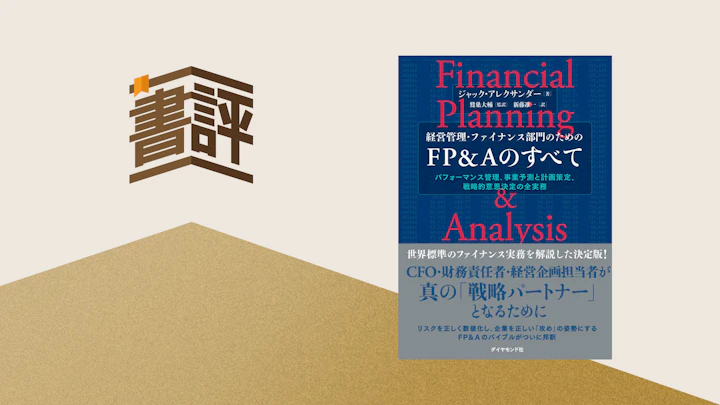


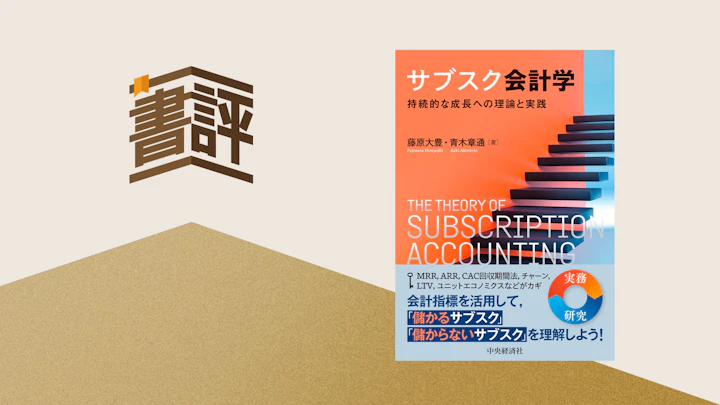













.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)




.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)


