今年8月発売の『KPI大全–重要経営指標100の読み方&使い方』から「046 商品ロス率」を紹介します。
本来売上げにつながるはずだった商品が売れずに、万引きや廃棄といった理由でロスになってしまうのは、ビジネス上、大変困ったことです。特にBtoCの店舗ビジネスなどは、こうしたロスをいかに下げるかという工夫の歴史だったといえます。たとえば世界最大のリアル小売りチェーンであるウォルマートはかつて、店舗ごとに、万引きの減少によってもたらされる利益の半分を従業員に還元することで、従業員の努力を促し、万引きによるロス率を半減しました。ただ、近年はこのような人の力と工夫に頼るのではなく、ITの力を活用する企業が植えています。たとえば本文中に紹介するスシローは、それまで職人が経験で判断していた新しい寿司を出すタイミングをAIなどを活用することで最適化し、劇的に廃棄ロスを減らしました。今後はあらゆるビジネスで廃棄ロスを減らすためにITが活用されると予想されています。このような箇所にもDXは浸透していくのです。
(このシリーズは、グロービス経営大学院で教科書や副読本として使われている書籍から、東洋経済新報社のご厚意により、厳選した項目を抜粋・転載するワンポイント学びコーナーです)
商品ロス率
本来売上げにつながりうる商品が何らかの理由でロスになった比率
KPIの設定例
うちの店は管理が弱いせいで廃棄ロスが多すぎる。せめて3年以内に業界平均並みにまでこの数字を改善しよう
数値の取り方/計算式
「KPIの使い方」を参照
主な対象者
事業責任者、オペレーション責任者、サプライチェーンマネジメント責任者
概要
この数字は一般には低い方がいいといえます。気をつけたいのは、業界によってロスの主な理由が異なる点です。製造業であれば出荷後の事故による破損(その意味で不良品とは異なります)や物流過程での紛失や盗難、小売業であれば廃棄や万引き、飲食業では廃棄がその主要な要因になります。
KPIの見方
業界による差異はありますが、ここでは小売業を例にとりましょう。小売業のタイプにもよりますが、概ね1%から3%程度がロス率の1つの目安とされます。小売業界では大きく「廃棄」と「その他」に分け、さらに「その他」を「外部要因(万引きなど)」「内部要因(従業員不正)」「不明」などとして分類します。
ロスの原因は商材による差異が大きく反映されます。例えば書店は委託販売(売れない書籍や雑誌は取次に返品できる)という制度の関係で廃棄ロスは少ないですが、万引きの被害が多くなっています。特にコミックのカテゴリーでは高いとされます。ドラッグストアなども万引き被害の大きな業界です。一時期のマツモトキヨシのように「万引き上等」ともいえる陳列で顧客を集めた例もありますが、やはり例外です。一方、生鮮食品を扱っている商店などでは、やはり賞味期限切れによる廃棄ロスの比率が増えます。
KPIの使い方
先述の通り、業界や商材などで原因は大きく異なってくるため、単にロス率という合計で見るだけではなく、商材別や重要なロスの原因別など、細分化して測定・管理する必要があります。
この数字の設定に当たっては、過去のトレンドや業界で平均とされる数値をまずは参照します。例えばスーパーでは青果の廃棄率は平均で3.5%程度、総菜は10%程度とされていますので、まずはそれを意識します。
多店舗展開している小売店や飲食店の場合、店舗間でのロス率の比較も非常に重要です。例えばある店舗で明らかに廃棄ロスが多い場合、発注見込みの甘さや陳列の不徹底(賞味期限の早いものほど前に出して並べるという基本を怠っている)などが考えられますので、店長や売り場責任者にしかるべく指導することが必要となります。一方で、廃棄ロスを恐れるあまり在庫を持つことを躊躇しすぎると、今度は販売機会ロスが生じ、全体の売上げを減らすことにもつながりますので、適切な範囲の数字を模索することも必要です。
補足・注意点
ロスの削減はいつまでも人手に頼ると人件費がかさんだり、店舗ごとのばらつきが出るという問題があります。例えば万引きであれば、昨今はデバイスの価格も下がっていますので、チップの埋め込みとアラーム機器で対応するなど、全社的に取り組む方が効果も出やすく、店長に対する心理的プレッシャーを低減することにもつながります。顧客からしても「ちょっとカバンの中を見せてください」などと勘違いしていわれるより、機械の誤作動の方が印象は悪くないものです(もちろん程度問題ではあります)。
回転寿司チェーンのスシローは、ベルトコンベアに流す寿司について、ビッグデータとAIを用いた需要予測システムを使用しています。回転寿司の皿にICチップをつけて単品管理し、過去の膨大なデータも活用して1分後と15分後に必要なネタと数量を予測します。それを見て職人が寿司を握るのです。これにより、従前の経験に頼る方法に比べ、寿司の廃棄量を75%カットすることができたといいます。適切な機械化は非常に大きな恩恵をもたらすといえるでしょう。
関連KPI
廃棄囗ス率、万引き数(金額)















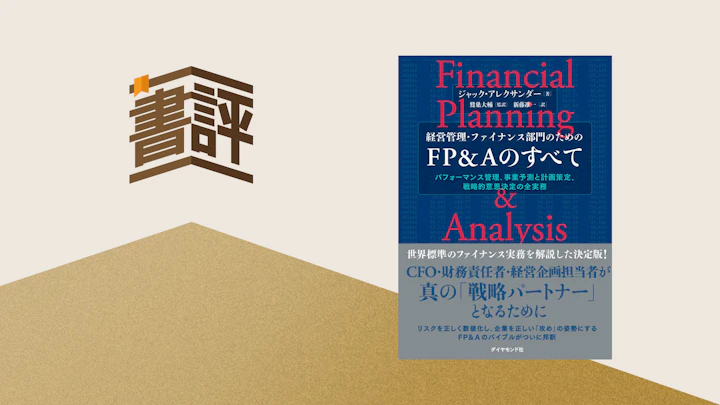


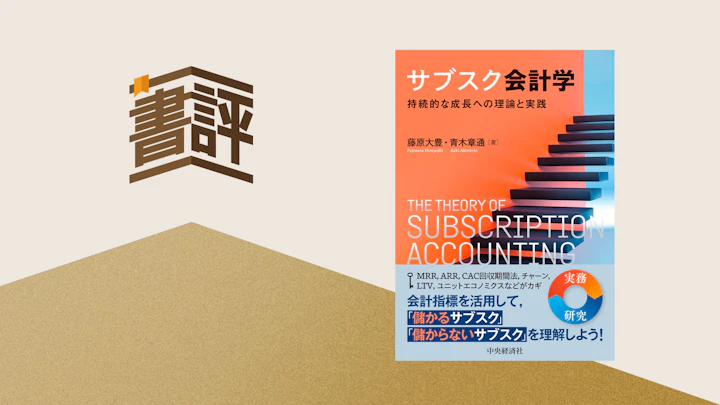













.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)




.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)


