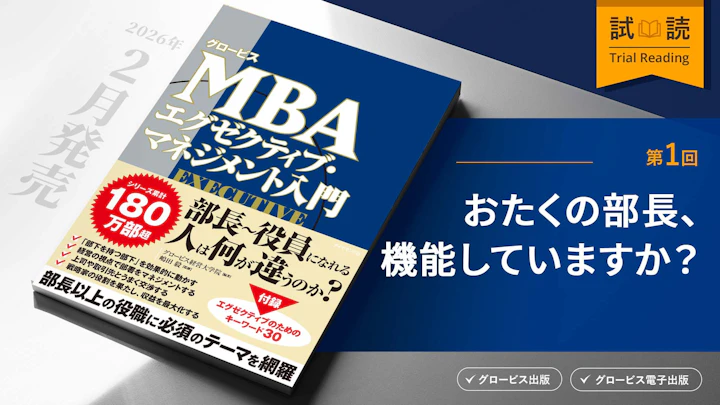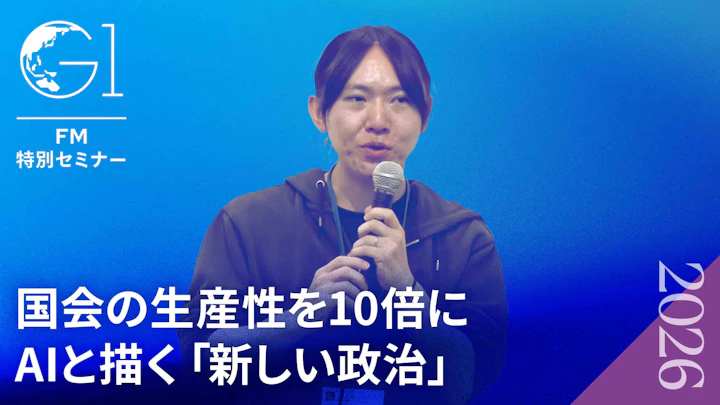本記事は、G1ベンチャー2019「エンタメ・スポーツで稼ぐ〜日本のエンタメ・スポーツ産業が世界で勝つための戦略〜」の内容を書き起こしたものです。(全2回 前編)

久志尚太郎氏(以下、敬称略):僕はメデイア・広告事業を運営していて、最近はスポーツとエンタメの業界が儲かりまくっているという噂をよく聞くんですが、本セッションでは大きく3つのテーマを設けたいと思います。1つ目は、オリンピックもありますので「2020年とスポーツビジネス」。2つ目はスポーツとエンタメによる掛け算のような側面がある「eスポーツ」について。そして3つ目は2025年の「カジノ以降」ですね。2024年から2025年にかけて日本でもカジノが誕生しますけれども、その界隈もすごくざわついていて、いろいろな動きがあります。では、まず2020年とスポーツおよびその周辺の可能性について、次原さんからお願いします。
スポーツ事業で世界に打って出るなら「ASEAN」が狙い目
次原悦子氏(以下、敬称略):2020年、いよいよこの街にオリンピック・パラリンピック(以下、オリパラ)がやって来ます。2016年の東京招致活動を含めると10年ほど、私もオリパラ招致では体を張って頑張ってきました。オリパラのビジネスというと皆さんはオフィシャルの部分しか想像しづらいかもしれませんが、短期的にはその周囲で、はるかに大きなビジネスが生まれます。オリパラが開催される数週間は、たとえば各国のオフィシャルスポンサーがその街でプロモーションイベントを開催したりパビリオンをつくったりするんですね。国としても同じです。日本が「JAPAN HOUSE」を開設したように、次にオリンピック開催を狙う国もパビリオンを出したりします。そんな風に、もう街全体がまさに万博状態になります。
そのうえで、2020年は過去のオリパラと比べても、とてつもない視聴率になると言われています。1964年の東京五輪ではテレビ1台にたくさんの人がかじりついていましたが、2020年は時差も少ないアジア各国の人々が大勢観ることになります。また、デバイスの発展によってアジアの方々が街頭テレビを飛び越え、1人1台で競技を観るようになることまで考えると、とてつもなく多くの方々が観るオリパラになるんだと思います。
一方、私が経営しているのは基本的にはPR会社ですが、スポーツ事業に携わることも多いということで、私自身は世界のスポーツシーンの裏表をいろいろと見させてもらいました。そこで最近思うことがあります。我々はオリパラで盛り上がっていますが、世界を見渡してみると、たとえばミャンマーやカンボジア、あるいはラオスといったASEANの国々は6~7人しか参加していなかったりするんですよね。それでメダルもまだ獲得したことがない。ですから、もし日本の皆さまがスポーツ事業で今後世界に打って出ていきたいとお考えになるなら、オリパラのようなレッドオーシャンに飛び込むより、経済的に大きく成長しているASEANあたりを狙うというのもアリかなと思っています。そうした国々ではスポーツビジネスも必ず盛りあがっていくので。
久志:「ここはイケるんじゃないか」という領域は何かありますか?

次原:たとえばASEANの人たちは「SEA Games(東南アジア競技大会)」という大会でオリパラ以上に盛り上がります。11カ国が参加する大会で、とてつもない視聴率を叩き出しているんですね。また、eスポーツが正式種目になったことでも注目されていますけれども、とにかく我々が想像もしていないような競技がある。「チンロン」って、知らないですよね。ミャンマーの蹴鞠のような競技ですが、競技人口は意外に多いんです。
久志:マススポーツというより「スモールマス」的なスポーツがたくさんある、と。
次原:そう。今その辺は議論のテーブルにも乗らないけれど、大枚をはたいて大きな大会を持ってくるだけではなくて、人口が大きな国や地域で人気ながら、まだ誰も手がけていないような競技を手がけるということにも大きなチャンスがあるんじゃないかなと思います。
たとえば私は昨年、仏リヨンで毎年開催されている「Equita Lyon」という、馬に関する競技および展示会の総合イベントを訪れました。5日間で16万人がリヨンを訪れるイベントです。馬というと「え?」なんて思うかもしれませんが、馬術、競馬、ロデオ等々、馬にまつわるあらゆる競技大会や展示会が開催されます。で、そちらに昨年訪れた際は主催者から「アジアで開催できないか?」という相談もありました。2020年のオリパラ招致にどれほどお金が使われたかは分かりませんが、意外と知らないだけで、外を見渡すと「え?これもスポーツ?」と思うようなものでも、かなり集客力のある競技はあるんですよね。
久志:ありがとうございます。続いて守安さん。DeNAはリアルなマススポーツ×インターネットといった領域で事業をやっていらっしゃいますが、今、日本のスポーツビジネスはどうなっていて、そこでDeNAはどのように事業を進めていらっしゃるんでしょうか。
プロスポーツ経営は知名度効果以上に「面白み」がある

守安功氏(以下、敬称略):我々はもともとインターネットの会社としてeコマースやゲームをやっていたわけですが、スポーツに目をつけた当初は、実はそのビジネス自体でなくブランディング効果を狙っていたんですね。プロ野球は国民の誰もが知るコンテンツですから、そういう部分に期待して、2011年に横浜ベイスターズを買収する形で参入しました。当時のベイスターズは年間の赤字額が30億ぐらい。それほどの赤字を出しても球団の名前を、当時は「モバゲーベイスターズ」にしようかなんて話もあって、今はDeNAベイスターズにしておいて良かったと思いますけれども(会場笑)、とにかく知名度を高めるという効果を期待していました。ただ、当然その効果もあったんですが、実際に手掛けてみるとビジネスとしてもすごく面白みがあるなと、少しずつ感じるようになっていきました。
たとえば横浜スタジアムには2万8000人ほど入りますけれども、当時の観客数は1試合平均で1万人ちょっと。それで、当初は「弱いからお客さんも入らないんだ」なんて考えていました。いつもだいたいビリで、弱かったのは事実ですし。ただ、我々としても当然強くなったほうがいいんですが、あまり勝敗に左右されず、弱くても球場に来ていただいて、それで楽しんでもらえたら再び来ていただけるんじゃないかと考えるようになったんですね。それで、野球観戦に加えてお酒を飲んだり、お料理をいろいろ食べるといった体験も含めて楽しんでもらおう、と。そんな風にして、5~6年が経った今は球場もほぼ満員になりましたし、そういうところまでは持ってくることができたのかなと思っています。
久志:そのなかで、DeNAとしてテクノロジーとの掛け算をしたことは何かありますか?
守安:テクノロジーも活用しましたけれども、実際には手を替え、品を替えながら、あれこれとリアルでトライしていたというのが実情です。たとえば球場でイニング間にどんなイベントを催したら喜んでもらえるのか、と。リアルな場でお客さんの反応を見ながら、ときにはやり方を変えていったり。チケットも、ただ販売するのではなく何かの特典をつけるような企画を打ち出したり。そうしたことをいろいろやってきたという感じです。
久志:もう1つ質問させてください。僕は小学校4年生の息子がいるんですが、eスポーツで友だちをつくったり、世界中のYouTuberを観たりしているんですね。もちろんフィジカルなスポーツの楽しさも知ってはいるんですが、今はサイバー空間でもeスポーツのようなゲームを通して、今までのゲームとは違う感覚で世界を広げている。守安さんはeスポーツを事業としてどのように捉えていらっしゃいますか?
守安:僕も少し囲碁をやりますが、今までは囲碁、将棋、麻雀、ポーカーといった伝統的なゲームにはプロがいて、ビデオゲームにはいませんでした。今、その後者でプロが出はじめてきたという意味ではそれほど違和感もありません。ただ、それでお金を稼ぐことに対して「どうなんだ」といった声はまだありますし、親からすると「野球やサッカーならまだしも、ずっとゲームというのは良くないのでは」なんて感覚があって、なかなか市民権は得ていない状態ですよね。ですから、熱中してスキルを高めて、それによって将来きちんとお金を稼ぐことができるようになるというエコシステムができるにはもう少し時間がかかるんだろうなと思います。少なくともそういう方向に流れてはいくと思いますが。
久志:日本でも新しいeスポーツ市場は立ち上がっていると思いますが、海外と比較すると規模は小さく、今のお話の通り「ゲームなんて」と、なかなか市民権を得ることもできないように思います。そのあたり、中川さんはどのようにお感じですか?
eスポーツが市民権を得るためには「圧倒的なスター」が必要

中川悠介氏(以下、敬称略):eスポーツでスターが生まれていないというのはすごく大きいんじゃないかなと思います。YouTuberもそうだったと思いますが、圧倒的なスターが生まれたら皆がそれを認める。HIKAKINさんが出てきたら「YouTuberってすごいよね」となるじゃないですか。eスポーツはそこまでいっていない気がします。海外のように、たとえばNinjaのような著名なストリーマーが出てきたりすると、子どもたちもそれを真似しようという風になりますが、今はゲームをやっていること自体の真似になってしまっているので。日本では、お茶の間にスターとして出てきたときに初めて認めてもらえるといった空気を感じます。
次原:イケてるスターに誕生して欲しいですよね。「いわゆる」っていう感じではなくて。
久志:芸能事務所の人たちがゲームをやりまくったら変わりますか?
中川:そういうわけでもなくて。実際、知名度のある人がやると少し変わるから、今は「eスポーツに参加してください」みたいな案件もすごく多いんですね。それで参加すれば報酬はいただけます。ただ、それってウソじゃないですか。そういう風に、普段やってはいないけれどもお金をもらってやっているというようなケースが今は多いけれども、それを乗り越えたらスターが生まれるのかなと感じます。
「IR(統合型リゾート)」誕生によってエンタメ産業は盛り上がるか?
久志: さて、次の質問に移りたいと思います。たとえば中川さんがいらっしゃるエンタメ業界の方々は、オリパラではまったく儲かりません。なぜなら手弁当だから。クリエイターの方々は基本的に手弁当で、国のための祭典ということで参加しているんですね。一方、エンタメ業界のクリエイターたちが今最も注目しているのは2024~2025年頃にできるカジノ。IR(統合型リゾート)における日本のカジノの営業区域の床面積はIR全体の3%以下と決まっていて、残りの97%はカジノに使えません。そこでエンターテインメントが出てくるわけですね。ですから、カジノができることによって2025年以降は日本のエンタメ産業に海外からも含め大きな投資が入ってくる。そのタイミングで日本のエンタメ産業は大きく伸びたり変わっていったりすると言われていますが、その辺について中川さんに伺ってみたいと思っています。
中川:芸能界というのは少し絡みづらいと思われている業界ですし、今回のG1ベンチャーにも芸能事務所から参加しているのは僕だけだと思いますが、僕らのようにコンテンツをゼロからつくる立場からするとカジノは大きなチャンスだと思います。オリンピックはどうかというと、リオのときもそうでしたが、協力させていただいて、名誉をいただいて、テレビを観て感動して、でもそれで終わっちゃって、あとは何も起こらなかったという感想があるんです。そういうことを経験した立場から申し上げても、やはりカジノは大きなチャンスだな、と。ただし、私たちもラスベガスに行けばショーやクラブに行きたいと思うし、行けばそこでしか体験できないものがあるじゃないですか。それと同じように、日本でカジノ(を含むIR)をつくるなら日本独自のエンタメをきちんとつくることが大切になると、強く思います。
今、日本ではライブエンタメが儲かっています。ライブ会場は足りていないし、アーティストのコンサートは常にチケット完売。今はファンに対するビジネスで成り立っているんですね。横浜アリーナでも東京ドームでも一般発売と同時にチケットはほぼソールドアウトになって、コアファンでない方が「誰々のライブに行きたい」と思ってもチケットはもう買えないということが多い。これはたしかに儲かります。ただ、一方では会場が土日しか使えなかったり、平日は人が入らなかったりと、いろいろと課題もあります。その点でも、カジノができると曜日に関係なく世界中から人が集まると思いますし、すごく大きなチャンスになると感じます。
それともう1つ。カジノができると今までのファンに対するビジネスからもう1歩先へ進めるのかな、と。たとえば我々は今年4月、京都の四條南座で改築記念の公演を松竹さんと一緒にやらせていただきました。で、そのときは「南座をライブハウスにしよう」と。新しい南座は座席を取り外せるので、DJブースをつくったりしてライブにするという企画にしました。それで、うちのきゃりーぱみゅぱみゅと松竹さんのコラボによる『きゃりーかぶきかぶき』という公演をしたんです。片岡愛之助さんに監修していただき、ライブと併せて公演しました。そうしたら、きゃりーのコアファンじゃない方々も外国からいらした方々も、すごく楽しんでいらしたということがありまして。今後はそういうチャンスがすごく増えるのかなと思っています。
今まではファンを呼ぶことでビジネスをしていましたが、今後はカジノとともに生まれた場所で、皆さまと一緒にコンテンツをつくることができるのかな、と。たとえばG1にいらしているようなITやTech業界の方々と組んで、新しくゼロイチで何かをつくり、さらにはそれを広げていくようなチャンスが今はすごく増えていると感じます。たとえば、今はきゃりーが「ライブはバーチャルでやります」と言っても、たぶん許してもらえないと思うんですよね。でも、それを何かコンテンツ化したら、どこかIRのシアターで毎日バーチャルライブをやっているという状態でも受け入れてもらえるんじゃないかな、とか。そういう可能性を感じています。
久志:中川さんは今、新しいクラブもつくっているんですよね。
中川:はい。ナイトタイムエコノミーには大きなチャンスがあるし、今は法律が変わっていろいろな方が参入を考えていると思います。僕らは昔からクラブでイベントをやっていて、それが会社の前身ということで、アソビシステムとしてのイベントと、協業している銀座のPLUSTOKYOでのイベントで年間100本ほどやっています。多いときは月に20本ぐらいイベントを手掛けていました。ただ、クラブというのは今までは遊ぶ場所ではあったけれどもオフィシャルではなかったから、遊びにくい場所だった。でも、法律が変わってからは遊びやすい場所になってきましたから。
さらに言うと、海外では年齢に関係なく、ご飯を食べたあとは「クラブで一杯飲もう」なんていう風になります。「誰々がDJだから」なんていうことに関係なくクラブへ遊びにいく文化がある。そんな形を目指して銀座にお店を出したんですが、まだ今はいろいろ試行錯誤しているところです。いずれにせよ、日本人は「誰々が来る」という風に、何かが起こらないとクラブに来ません。それを、海外のように常日頃遊ぶというカルチャーにまで持っていけたら勝てるようになるのかなと思います。
日本のテクノロジーとエンタメを組み合わせた「見たことないコンテンツ」が求められている
久志:実際、今の日本にはデジタルとリアルの双方を行き来できるようなエンタメコンテンツが少なく、そこに皆が注目していると感じます。その辺も踏まえつつ、悦子さんは日本のスポーツやエンタメ、いわゆるコンテンツの魅力や可能性をどう見ていらっしゃいますか?
次原:今さらだけど、歌舞伎町の「ロボットレストラン」ってすごいじゃない。海外の人たちは皆、日本を訪れたら行かなくちゃいけないようになっていますよね。日本テレビの土屋敏男氏さんも短期だけれども大阪で新しいコンテンツをつくっていますよね。入場時にお客さまを3Dで撮影して、1時間半のコンテンツのなかにお客さま自身が参加できるというような。日本のテクノロジーとエンターテインメントを組み合わせた、今まで見たことのないようなコンテンツの計画を発表していました。今はまさにそういうコンテンツが求められていますよね。
久志:最近、『アフターデジタル オフラインのない時代に生き残る』(著:藤井 保文、尾原 和啓)という本が話題になって、日本でもOMO(Online-Merge-Offline)みたいな考え方が広がってきました。これまでの「オフラインをオンラインへつなぐ」というO2Oが、オンラインがリアルを飲み込んでリアルのUXを変えていくという話になってきた。いかにして、デジタルのなかでリアルなコンテンツを消費して広げていくかということが、日本でもすごく考えられるようになってきました。そんな風にして設計されたコンテンツが僕らの知らないところで海外に出ているというのは、すごく面白いなと感じます。スポーツはどうですか?日本の野球ってすごいじゃないですか。守安さんは、テクノロジーやインターネットも活用しつつ、日本の野球コンテンツをどのように海外へ広げ、ビジネス化しようと考えていらっしゃいますか?
「広島カープ」の人気が上がると「横浜DeNA」も儲かる
守安:スポーツのビジネス構造って、我々がやってきたゲームとまったく違っていて面白いんです。ゲーム業界ならゲーム会社同士はライバルじゃないですか。事業でもライバル同士。でもスポーツ業界はというと、プロ野球12球団はチームの勝敗という点では当然ライバルですが、事業では食い合わないんですね。商圏が違うから。我々は横浜に球場があって、基本的には横浜の周辺か東京ぐらいまでのローカル商圏で成り立ちます。
で、今は広島カープの人気がすごいじゃないですか。2011年頃は横浜スタジアムでカープ戦をやってもお客さんがほとんど入らなかったんです。我々もカープも人気がなかったから。でも今はジャイアンツ戦やタイガース戦以上に、カープ戦のほうがアウェイのお客さんが横浜スタジアムに足を運びます。そんな風に、広島カープが人気になってくれると我々も儲かるといった構造があるから、リーグ全体で盛り上げていくことが重要になります。ですから我々としては、今は横浜でお客さんに来るようになってもらったということでフェーズ1。ただ、広島のMAZDAスタジアムでDeNA戦をやっても、面白いぐらいに我々のファンはいないんです(会場笑)。まだ全国レベルにはなっていない。カープはそこまで行ったし、ジャイアンツもずっとそうです。その意味では、横浜の商圏以外にもファンをつくって、それでグッズが売れたり放映権が高くなったりするというのがフェーズ2ですね。
その次が海外リーグとの戦いです。日本のプロ野球ビジネスも伸びていますが、メジャーリーグの伸び方ってぜんぜん違う。だからこそ、当然ですけれども日本人選手もトップの層は皆メジャーに行っちゃうじゃないですか。で、事業規模がでかいから、そのぶん選手に大きなお金を払うこともできるし、日本人だってその試合を観たくなるから放映権が海外でも高く売れる。そんな風にしてさらに商圏を広げている。ですから、我々としても海外の人たちに日本のプロ野球を観てもらうとか、あるいはどこか海外のリーグと一緒に新しいリーグをつくるとか、そういったところまで行くと世界のなかで戦うということになるんだと思います。
久志:「日本のプロ野球を海外へ」といった動きについては誰がリードしていて、今どんな状態なっているんですか?
守安:リーグとしてNPBがリードしています。放映権の売り方にしても、リーグが管理するのと各球団が売るのとではいろいろ違ってきますから。たとえばJリーグは数年前、DAZNと10年間で2000億という放映権契約を結びましたけれども、あれはリーグがまとまって交渉するからこそ交渉力も高まったわけで。
久志:インターネットを通じてビジネスを成長させるために、今リーグとしてどんなことをやるべきだとお考えですか?
守安:リーグがコントロールしてやるべきところと、各球団がやるべきところは分かれるので、そこがきちんと噛み合っていけば、まだまだ伸びていくんじゃないかと思います。そのうえで、たとえば放映権に関してはBリーグがソフトバンクさんから相当な放映権料をもらっていますよね。今のプロ野球と比べて観ている人はそこまで多くないんですが、それでも一定の放映権料がつくのは、やっぱりリーグがまとまったからなのかなと思います。 後編に続く>>





.png?fm=webp)




















.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)


.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)

.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)














.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)