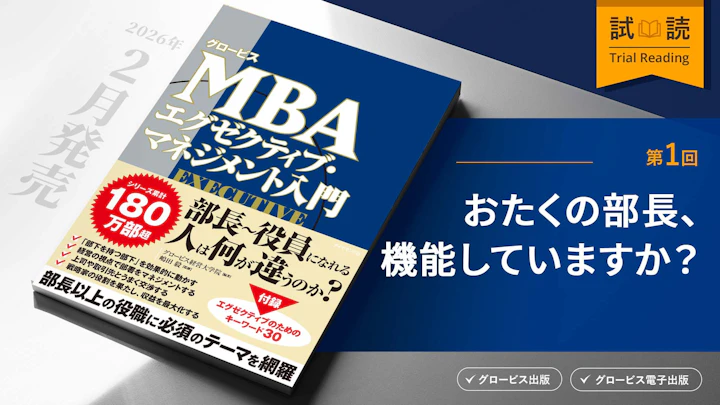大きな成功を収めたリーダーは、社会的な評価や期待、自分の役割などをめぐる葛藤とどう向き合っているのか――若新雄純が元フェンシング選手・銀メダリストであり、現日本フェンシング協会会長の太田雄貴氏に問う。

若新: 今日は、人の社会的な期待や役割について、太田さんと話せればと思っています。
僕は専門がコミュニケーションで、「社会的な存在」である人間がどうつくられていくか研究しています。最近感じるのが、インターネットが登場していろんな人が何でも言えるようになったことで、社会的な評価やポジションを持つ人への過剰な期待が可視化され、窮屈さを感じる人が増えているのではないかと。そんな中で、上手に自分の立場や役割をつくれる人と、そうでない人に分かれているなぁと。
太田: 僕は滋賀の山奥で生まれ、そもそも土地的に不利なエリアで育ちました。滋賀にフェンシングクラブはなかったから。だけど僕にとって有利だったのが、父親が僕のフェンシングに対して熱心だったこと。送り迎えに熱を出してくれ、フェンシングの世界で勝つためにいろんな大人に会わせてくれた。大人の中でどう振る舞うとかわいがってもらえるかということも、そうした経験から感じることができたと思う。
ちっちゃい頃からメダルを目標にしていたけれど、それはフェンシング選手が自分という人間を社会的に認めてもらうためには、オリンピックでメダルを獲るしかなかったから。僕らにとってのオリンピックは目標であり手段でした。
サッカー、テニス、ゴルフ、バスケといった競技からすると、オリンピックの価値はそこまで高くないかもしれないですが、そうじゃない競技は自分たちでブランディングができないから、そこの「社会的価値」の部分をオリンピックにゆだねていた状態なんです。
若新: 自分が人生をかける「フェンシング」というものを日本で根付かせ、その社会的な評価を上げるためにどうすればよいか、早い段階から考えていたんですね。
太田: はい。就職を1回見送ってオリンピックに一点賭けした後、2008年から森永製菓に入って、セミプロ状態で勝つことを仕事にしました。実は、ロンドンが終わって1回引退したんです。2012年から13年まで1年間休んで、東京オリンピックの招致活動をしました。
その最大の理由は、そういう国際的な場面にフェンシングの選手が全アスリートの代表として立てれば、親がお子さんにフェンシングを始めさせるきっかけになるんじゃないかなと思ったから。そして、そこで僕がキャリアを終えても活躍するロールモデルを見せることができれば、「フェンシングそのもので飯は食えないけど、こういう社会的インセンティブが発生するんだね」と、競技をやらせる親御さんが増えると思うんです。例えばヨーロッパの競技だから多言語を習得できる確率が高くなる、進学で有利になるとか、なんだっていいんです。
自ら社会の中の役割をつくりだす

若新: メダリストになったことで、自分の次の新しい役割ができてきたってことですね。僕は今、役割の格差が世の中に生まれていると思っています。お金の格差や生活環境の格差の方が問題になりがちですが、実は多くの人たちが直面している問題は、自分に社会の中での役割がどれくらいあるかっていう格差から生じているのではないかと。
太田: なるほど。日本のフェンシング界では、そもそも決められた役割が何もなかった。何をしていいのか分からないから、僕がやるしかなかった。草むしりからアスファルトをまいて道路の舗装するところまで全部やって、さらに自分で走るみたいな状態を続ける中で、いろんな変化を全部見られた。
若新: 多くの人は、もともと用意された役割を獲得しにいくわけですが、太田さんの場合はどんな役割でも新たにつくれる状態だったし、つくるしかなかったってことですよね。
太田:最初の1人だったので、ものすごく苦しい戦いでしたが、入ったらブルーオーシャンなので、逆に好き勝手やっていい状態でした。その代わり、ここには必ず責任が発生します。若い子たちは僕を見て育つので、僕の立ち振る舞いが今後フェンシングの指標になる。
若新: いつ頃からフェンシングの認知度を上げようと考えていたんですか?
太田: 小学生のとき、サントリーのウィスキー工場がある山崎の麓にフェンシングのメッカみたいな場所があって、そこで週2回練習していたのですが、たまたま読売新聞の取材が来て僕の写真が使われたんです。
学校でも「新聞出ていたね」と言われたんですけど、同時に「フェンシングって何?」とも言われる。その後、野球の強い学校に進学したんですが、同じ全国大会出場でも向こうは学校を挙げて応援するけれど、僕らはインターハイで優勝しても彼らの全国出場より評価が低いわけです。
これはなんとかならないかなって思ったときに、もうオリンピックしかないと思ったんですよね。世界で勝てば話は変わる、フェンシングを世の中の人に知ってもらうには、もうオリンピックでメダルを獲るしかないだろうと。
若新: 既にみんなが知っている競技のほうがよいと思わなかったんですか?
太田: それは1度も思ったことはないです。なぜならば、どんなに競技人口が少なかろうが、同じ1番は1番だっていう頭でいたので。鶏口牛後じゃないけど、大きいマーケットの真ん中にいるぐらいだったら、小さくてもトップになったほうがいい。上には上に立ってないと見えない景色があるから。だとすると、どんなに小さくてもいいから1番になるしかないって思ったんです。
ちなみに、フェンシングの場合、強い選手が必ず優勝するとは限らないんです。2008年から2017年までの世界選手権とオリンピック、過去10大会のうち10人とも優勝者が違うんです。それぐらい勝つのが難しい競技なので、どうしても確率論に落ち着く。そこで、本当は右に突きにいったほうがよかったんじゃないか、左に突きにいったほうがよかったんじゃないかって振り返りをして、議論をします。それが僕に「考える癖」を付けてくれました。
問い続けることで強くなる
若新: ビジネスの世界においても、絶対に勝てる、という戦法はないと思うんですよね。社会にはたまたまのことが要因としてたくさんあるので、努力によってたまたまの中で勝ち抜くための確率を上げるしかない。そう考えると、人生を捧げてやっている仕事は、その役割を通して見えるものから何かを考え、哲学することに価値があるのかもしれない。
太田さんは、フェンシングでメダルを目指す人生の中で、「日本とは?」「競技とは?」「戦うとは?」といった問いを早い段階から立てていたんじゃないですか?
太田: はい。オリンピックのメダルは、東大の学位に近いと僕は思っています。東大がそもそもゴールなのか、東大に入るための努力のプロセスを自信に変えられるのかにはものすごく差があるって思っていて。
フェンシングに捧げてきた人生であっても、体力とか筋力は練習を休めば落ちます。僕は約22年間、フェンシングに時間と労力を投資し続けて、でも今は、体力的にはもう全く何もないわけです。
だけど僕はフェンシングを通していろんなこと学んだし、いろんな人と出会えた。こうした自分の財産について、立ち返らずに次のキャリアにいこうとすると、セカンドキャリア問題が出てしまうと思うんです。スポーツ選手に限らず、自分はどういう人生を歩んでいきたいのか、どんな人生だったらワクワクするんだろうか、自分はこのままでいいのかって常に自分に問いかけることは必要なんじゃないかと。
若新: 「問い」があることが、1つの節目を迎えたり、限界に到達したり、変えなきゃいけないっていうときに、そこに強く居続けられるきっかけになるのかもしれませんね。
太田: 問うと、勝つまでにでも時間はかかりますけどね。
若新: まずは結果を出してから先のことを考えればいいって、よく学校の先生に言われたんですが、それにはちょっと納得いってないんです。そのセリフ通りにしていると、結果が出たときにはまだ問いを持つ能力を持ってないわけですよね。ステージが変わった瞬間に、その次どう対応していくかを考えなきゃいけないのに、その力が備わってないと。つまり、そこがゴールで終わってしまう。
問うことから役割が生まれる

太田: 両親が小学校の先生だったので、末っ子で知りたい坊やだった僕の「なんで?」っていう問いを、ちゃんと聞いて答えてくれた。一方で、「なんで?」と問う姿勢も求められた。
若新:僕も両親が学校の先生だったんですよ!でも、僕の場合は「こうあるべきだ」って教育受けてきたので、いちいち問うことを面倒くさがられましたが。
太田:例えば、フェンシングをしていると月8回で8,000円、僕は2つクラブを掛け持ちしていたのでその2倍の月謝がかかった。だから親父から、「必ず元を取って来い」って言われたんです。
元のとり方だけは教えてくれて、個人レッスンを受けろと。なぜならば、コーチの考え方とかを独り占めできるから1番費用対効果がいいと。それを受けて、必ず2個か3個質問してこい、疑問を疑問のまま家に持って帰るなって言われて。親父がずっと上で練習を見ているから、それをやらないとめちゃくちゃ怒られるんですよね。だから物事を問うクセが付いた。
「なんでこういう仕組みになっているんだろう」と気になった最大の延長が、オリンピックの招致だった。この年齢でメダルのプレゼンターをすることができたのは、先回りして自分で問いまくって、その仕組みが分かったからだと思う。
若新: 太田さんの場合は、メダルを獲ったからといって、代々のメダリストの流れでいくと次はここ目指して、その次はあそこを目指して、そうすれば最年少理事になれるよなんていうルートがなかったわけですよね。
最年少でいろんなポジションを得てきたルートについて、多くの人はそれに向かってがむしゃらに真っ直ぐ走って到達したんだって思っているかもしれないけど、そうじゃない。わざわざ、いちいち問うことで、ルートそのものをつくってきたわけですね。
誰も体験したことがないステージに立つと、次の目標設定も難しいから、常に疑問を持つとか、常に問う、そして今できることは何かと、そしてなぜ僕はここにいるのかっていう問いを続ける。そのことが結果的に、自分にとって価値のある役割を引きよせるものなんだと。
会社の上場にしてもオリンピックのメダルにしても、なぜそれを目指しているのか問わなくても、そこにいくまでのルートやステージは用意されている。だけどそこに一旦到達する、もしくは全然違う変化が起きたときに僕らが崩れてしまう理由は、普段から「問う」ということをしていないからかもしれない。
余計なことを考えよ

太田: オリンピックに関しては、明らかに最短で行ったほうがいい。距離と自分を正確に把握し、何年までにオリンピックへ行くという時間軸を設定して、やるべきことを明確にさせることを、中高生には徹底させています。
一方で引退したあとは、次の目標がなかなか見つからないわけですよね。次にやりたいことを見つけるまでのほうが実は大変で。
そんな中で取り組んでいるのが、スピード感は今までより落ちるけど、5個とか10個同時にガーっとやってあとで振り返ること。振り返ったらここがすごく効いてきたなとか、マルチタスクに何個か同時に進んでいくことに慣れていかないといけない。そういう自分を許容するのも結構大事だと思います。
若新: なるほど、「最短ではない自分」を許すということですね。チープな言葉でいえば、燃え尽き症候群の本質みたいな話ですよね。1本のときって分かりやすくて、ある1つのために合理化された1日のプログラムって、大変かもしれないけど組みやすい。
太田:そうなんです。「太田さん今何やっているの?」って聞かれて「これとこれとこれとこれ」って言ったら、みんな1本に絞ってほしいって言う。
世界で僕が市民権を得た日だって僕が思っているのは、2015年の世界選手権で優勝したとき。僕があのとき意識してよかったなって思っていることがあります。世界チャンピオンになると、誰もが最後の1点を獲った瞬間に、マスクを投げる、剣を投げるで、コーチと抱き合ったり大騒ぎして、「うわー」ってなります。
お客さんもそれ見て盛り上がるんですけど、僕は当時、全世界の選手会長だったんです。僕の立ち振る舞いを子供から大人まで見ているんだっていうのを最後の1点獲った瞬間にふと思い出し、今どういう振る舞いをしなきゃいけないのかを考えて、ガッツポーズをぐっとこらえた。
それによって世界のフェンシングを考えているという姿勢を見せることができたので、今でも世界の選手たちとも仲がいいし、太田雄貴としての立ち位置や価値があると思うんです。
若新:それは、余計なことを考える余地が自分の中にないとできないですよね。普通は、勝つことに夢中になりすぎて、その瞬間どう振る舞うべきかなんてまで意識がいきません。
太田:もっと悪い言葉で言うと、集中してないって言われるんですよ(笑)。
若新: そのことだけに集中して練習しなきゃいけないときにも、もしこの結果こうなったときに、俺はこう振る舞うぞとか、俺はこうありたいみたいなことをどこかで思う「余計さ」が大切ってことですよね。その余計な瞬間、集中していない瞬間にこそ、その人が自分の新しい役割や価値をつくるきっかけがあるのかもしれない。
太田: 僕は、頑張っている人が応援される社会だったらより素敵だなって常々思っています。協会の理事職なんて時間ばっかり取られて…と思う反面、次の世代が成長して、それこそメダルを獲った瞬間に、彼らの発言がよりインパクトのあるような舞台をつくってあげることが、僕の仕事だと思っているんです。
スポーツは選手じゃなきゃ意味ない、と考える人が多い中、僕がスパッと去年のリオで辞める決断ができた。なぜかと言うと、試合会場がガラガラで、このことに疑問を持ったんです。会場がパンパンだったら、選手はもっといいプレイができるし、もっと興奮するのになと。
若新:この前、ある生物学者からおもしろい話を聞いたんです。生物には生存していくための3つの能力があって、それは万物共通だと。1つは「競争力」で、より枝を伸ばして日光を浴びるといった戦いに勝つ。もう1つは「忍耐力」で、寒かったり暑かったり日差しが強くても耐えると。3つ目が、駄目だったら場所を変えて諦めるっていう「柔軟性」。この場所は向いてないから変えよう、場所を変えるなら形を変えようってどんどん変化していくと。
本当なら、「俺はこうあるべきだ」っていつまでも固執するっていうことは、生物が生きていく上ではすごく不利なことで、環境が変わったら、柔軟に変えてかなきゃいけない。何もアスリートの世界だけでなく、僕らは常に受験があり就職があり、会社の中で売上目標があり…という中で、競争をして、忍耐をしている。そして、ある結果を得たときに、仮にうまくいったんだとしても、柔軟に「次はどうすべきか」を問わないと生き抜いていけない。
太田さんはそれをずっと小さいときから問い続け、その柔軟性が、引退してさらに活躍を続ける今の太田さんをつくっているのだと思います。



.jpg?fm=webp)