これまで、仮説を持つことの意義や、そもそもビジネスにおける「良い仮説」とは、どのようなものか、ということを議論してきました。今回からは、そうした「良い仮説」を作るコツについて考えていきます。その第1回として今回は、仮説を作るという作業について少しブレークダウンしてみましょう。その上で、知識の幅を広げ、深く耕すということについて説明します(なおこれは、前回説明した、「FACT(事実)に基づいて考えること」と「経営の知識を押さえていること」に、強く関わってきます)。
仮説は、複数の事象や事柄を組み合わせ、意味づけることで生まれる
よく、天才の自伝などを読んでいると、まったく新しいアイデアが忽然と天から降ってきた、などというシーンが紹介されていることがあります。天才の例をひかずとも、我々自身、何かの拍子にパッと面白いアイデアや仮説がひらめくことは多いものです。
しかし、こうした新しいアイデアは、何もない「無」からいきなり生じるものではありません。むしろ、さまざまな事柄について徹底的に考え抜いたあげく、ふとそこに新しい情報や刺激が加わったときに、新しいアイデアや仮説が生まれることが多いものです。たとえば、物理学者のニュートンは、よく、リンゴが木から落ちるのを見て重力を発見したといわれていますが、これは彼の物語の一部に過ぎません。ニュートンはそれに先立って、月を初めとする天体が、なぜあのような挙動をとるのかずっと考えていました。月であれば、なぜあれだけ大きな天体が地球の周りをグルグル回るのかということです。
その一方でニュートンは、リンゴだけではなく、地球のさまざまなものが上から下に落ちる、あるいは上に投げたものも下に落ちてくるという事象も当然観察していました。「いろいろなものは地上に落ちてくるのに、なぜ月は落ちてこないのか。逆に、月は地球の周りを回るのに、なぜ他のものは地球をぐるぐる回ったりしないのか」。ニュートンはずっと考えていたはずです。そしてある日、彼はリンゴが木から落ちるのを見ます。実際に彼の頭の中でどのように思考回路が作動したかは分かりませんが、ここで彼はあの有名な仮説をひらめきます。「物と物はお互いに引き合うのではないだろうか。地球とリンゴも引き合うし、地球と月も引き合っている。引き合う力は、お互いの質量の積を距離の二乗で割った値に比例する。そう考えれば、月が地球を等速円運動で回ることも、リンゴなどが地面に落ちてくることも説明できる!」
ここで重要なのは、ニュートンがこの仮説提示に至った背景には、さまざまな数学的素養や、常日頃の観察、そして天体の挙動などに関する豊富な知識があったということです。これらが1つでも欠けていたら、ニュートンがこの仮説に至ることはなかったでしょう。
これはビジネスパーソンにも当てはまります。仮説は、ある事象や事柄に触れたときに、そこに「意味づけ」をすることで生まれてきます。そして意味づけの際に効いてくるのが、他の情報との組み合わせです。たとえば、ある新種の植物が、従来種に比べ、CO2の吸収率・固定率が数倍高いということが発見されたとします。もし30年前であれば、このニュースを聞いても、多くの人は、「フーン」で終わったことでしょう。しかし、現代であれば、「CO2が地球温暖化を加速している」「CO2の排出量を減らすことが重要な世界的課題だ」ということを知っている人は少なくありません。そうした人々は、この情報と組み合わせることで、「その植物を利用して効果的なCO2固定化システムが作れるのではないか」という仮説を持つでしょう。さらに、排出権取引や、各国の国情や農業政策などについて詳しく知っている人であれば、「某国で農地開発をしてその植物を大量に栽培すれば非常に大きなリターンをもたらすだろう」といった仮説を持つかもしれません。
知識を耕し、雑学をアクティブな情報へと昇華させる
このように、まずは知識の「幅」を広げておくことが、組み合わせの可能性を増すため、良い仮説構築の可能性を高めることになります。ただし、知識を幅広く持つだけでは、雑学にとどまってしまってビジネスにつながりません。雑学クイズに強くなるだけでしょう。幅広い知識を雑学にとどめず、ビジネスにおける仮説やアイデア創出の「引き出し」とするためには、その知識について、ある程度深く考え、情報を立体化しておく必要があります。「耕す」とは、そういう意味です。「情報をアクティブ化しておく」と言い換えてもいいかもしれません。
具体的には、以下のようなことを常日頃から意識してみるといいでしょう(なお、ここに挙げたものは一例であり、他にも耕す方法はたくさんあります)
・「なぜそんなことが起こったんだろう」と考えたり調べたりしてみる
・別の観点から見たときにどのように見えるか考えてみる
・時系列で展開を追うことで、動的な把握をしてみる
・「ということは、今後こんなふうになるのかな」など、思考実験的に将来予測をしてみる
・類似の事象や、反対の事象とセットで考えてみる
たとえば、最近であればブランド米として有名なコシヒカリでさえ、キロあたり2000円の維持が難しい、あるいはスーパーで特売の対象になったり、売れ残ったりするというニュースがありました。これをニュースとして知っておくだけではなく、まずは「なぜ?」と考えてみたり、「それはどのような効果をもたらすのか?」と考えてみるといいでしょう。一方で、小麦の価格が高騰し、加工食品に転嫁されるというニュースもありました。この一見相反するように見えるニュースは何を意味しているのでしょうか? 日常の限られた時間の中であまりギリギリ考え込む必要はありませんが、ある程度は頭の中で「転がし」たり、「揉んで」みる癖をつけておくことが、知識を表層的なものにとどめず、真に使えるものにする役に立つのです。少なくとも、自分のビジネスにかかわる可能性が高い情報については、この「耕す」度合いを高めておくことが求められます。
■次の記事
第8回 カルティベーション
■前の記事
第6回 良い仮説とは(後編)




















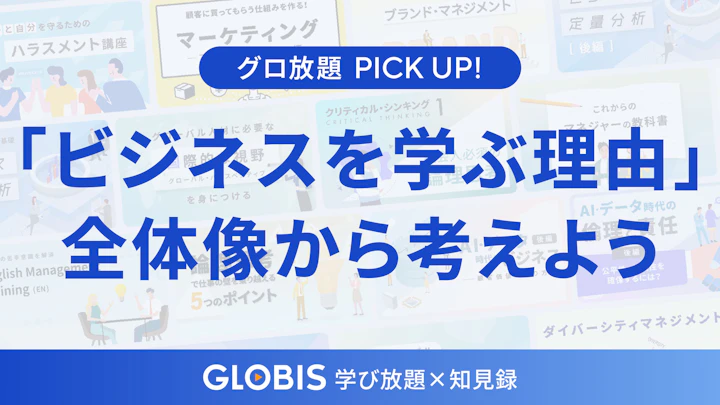














.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)



