前回は、「ビジネスを良い方向に推進する仮説」の条件として、(1)新規性・独自性がある、(2)ビジネスへの活用が可能である、(3)アクションオリエンテッドである、という三つの特性を指摘し、最初の二つについて詳説しました。これに引き続き今回は、三つめの「アクションオリエンテッドである」について説明します。
アクションにつながる仮説を立てる
さて、仮説によってビジネスを推進するには、仮説自体が最終的には具体的なアクションにつながることが必須です。ビジネスは、アクションを伴って初めて結果が出る、言い換えれば、アクションにつながらなければ、何かを考えても考えなかったのとあまり差がないからです。
例えば、「これから2、3年でCO2排出への意識が個人レベルで急拡大するだろう」という仮説があったとします。これはこれでもっともな仮説・予想であり、社会科学者やジャーナリストであれば十分な研究テーマになるでしょう。しかし、ビジネスの現場では、これだけでは漠然としすぎて「だから何?」という疑問を招くだけです。しかし、もう一歩踏み込んで、たとえば「消費者の意識は、これから数年の間に、CO2削減に対してプレミアム価格を支払うように変容するだろう」とすると、より具体的なアクションがイメージできるようになります。
一般の消費財メーカーであれば、パッケージや広告でCO2削減、ひいては「地球に優しい」を差別化要素として打ち出すことで、高価格を実現できるかもしれません。あるいは宅配便業者であれば、「電気自動車(EV)車両による宅配は20円の追加料金が発生します」というような、投資を一部の問題意識の高い顧客に負担してもらうような差別価格の設定が可能となるかもしれません。情報がない段階であまり具体的に最終アクションを決め打ちしてしまうのはちょっと問題ですが、ある程度アクション案が見える程度には仮説を発展させることが必要なのです。
自分の置かれた立場、役割を意識する
さて、アクションにつながる仮説を引き出す際には、自分や聞き手の置かれた立場や役割を踏まえたうえで、「意味のある」仮説を立てる必要があります。
これを説明する有名な例に、「空は青い。だから何?(Sky is blue. So What?)」というものがあります。「空が青い」は事実ですから、これを繰り返すだけでは仮説になりません。かといって、自分にとってまったく意味のない仮説を引き出しても仕方ありません。
例えば、「空が青い」という事実から、「紫外線が強いだろう」と仮説を引き出したとします。これは、日焼けを気にする若い女性にとっては、「日傘を持っていこう」「日焼けクリームを塗ろう」のようなアクションにつながるため、非常に有用な仮説です。一方で、日焼けをまったく気にしない一人暮らしの男子学生にとっては、この仮説はそれほど意味がありません。彼にとっては、「空は青い」という同じ事実に基づく仮説であっても、「今日は雨が降らないだろう」という仮説の方が意味がありそうです。この仮説であれば、「洗濯物をまとめて乾そう」あるいは「バイクで、ひとっ走りしよう」などのアクション案につながります。
つまり、同じ事実を見ていても、そこで抱くべき仮説は、立場や役割によって違うのです。自分の期待される役割や、相手(特に顧客や上司)の関心をしっかり把握しておくことが望まれます。
ビジネスの世界では、最初にチャンスを見出して実際に行動したものが成功する可能性が高まります。是非、アクションをイメージした仮説を立てましょう。
ここで、もう一度良い仮説の三つの条件を確認しておきます。
(1)新規性のある仮説で皆をハッとさせ/競合の先を行き
↓
(2)検証できることで「なるほど」と思わせ
↓
(3)具体的なアクションにつなげていく
この三つの要素を強く意識することで、仮説を検証しつつ、相手に強く影響を与え、周りを動かすことができるのです。
「良い仮説」を支える「FACT」と「経営知識」
さて、仮説の立て方についてはまた別途述べるとして、ここでは、上記の条件を満たす仮説を立てるために必要な条件を考えてみましょう。切り口によってさまざまな必要要件が考えられるでしょうが、本稿では二つの基本的条件について述べておきます。それは、「FACT(事実)に基づいて考えること」と「経営の知識を押さえていること」です。
一つめの条件である「FACTに基づいて考えること」は、説得力のある主張やアクション案を導くためにも不可欠の要因です。どれだけ論理展開が正しくても、その論理展開に用いられている情報が事実、もしくは誰もが疑わない価値観(「人殺しは良くない」「政治には民意を反映させるべき」)でなければ、それは単なる思い込みや当てずっぽうと言われても仕方ありません。
例えば、ある小売店の店主が、「集客力が落ちている」と感じていたとします。これが事実であれば、「品揃えが悪くなってきているのではないか」「顧客への情報提供がうまくできていないのではないか」など、さまざまな(原因の)仮説が生まれてきます。しかし、実際には集客力自体はほとんど変わっていないのだとしたら、そこから先の仮説やアクション案はすべて的を射ないものになってしまいます。
しかし、こうした例は意外に多いものです。典型的なパターンとしては以下のような状況があります。
・たまたま目に付いた印象的な事象(最近の事件など)に引っ張られる
・声の大きな人の意見に引っ張られる
・KPI(重要業績手法)の補足がされていないため、客観的な事実が分からない
・情報自体は決して間違ってはいないが、古かったり、収集方法が不適切だったりするため、仮説構築の役に立たない
先の例であれば、最低限でも店舗周辺の通行人数と、実際に店の中に入った人数を客観的に押さえておきたいところです。可能であれば、数年、数カ月にわたる時系列比較があるといいでしょう。なお、こうした数字は、集めようと思い立ったからといって、日ごろからシステマチックに測定していないと、なかなかすぐには集まりません。経営上(あるいは自分の仕事上)重要な数値については、常日頃意識して数字をとっておくことをお勧めします。
次に、ビジネスにおいて良い仮説を導き出すには、やはりある程度は、ビジネスの作法とも言える「経営の知識」が必要です。これがないと、まったくトンチンカンな仮説を出してしまうかもしれませんし、「そんなの昔からある。全然、新鮮じゃない」などと言われかねません。「ローリスク・ハイリターンな商品だけで作った金融商品は人気が出るに違いない」という仮説を説明しても、専門家からすると「・・・」となってしまうでしょう。
もっとも、ここで難しいのは、ビジネスの常識にとらわれすぎると、新しい発想が阻害されてしまいかねない、という点です。たとえば近年、ネット書店のamazonに刺激され、「ロングテール」で稼ぐ、というビジネスモデルがいくつか提示されました。こうしたモデルは、それまでのパレートの法則(20-80のルール)を妄信しすぎていると、生まれてきません(なお、「ロングテール」も、条件や見方を変えると結局はパレートの法則に従っている、という議論もあります)。経営の知識や常識は、素養としては知っておきながら、どこかでそれを疑い、それが成り立つ前提条件までさかのぼって理解しておくことが望ましいのでしょう。
経営のセオリーは押さえながら、枠にはまりすぎない――そうしたバランス感覚に基づく仮説こそが、時代をリードしていくのです。
■次の記事
第7回 仮説を作るコツ(1): 知識の幅を広げ、深く耕しておく
■前の記事
第5回 良い仮説とは(前編)















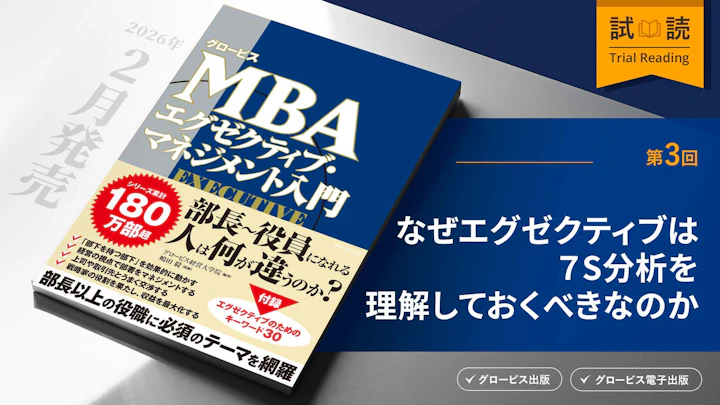

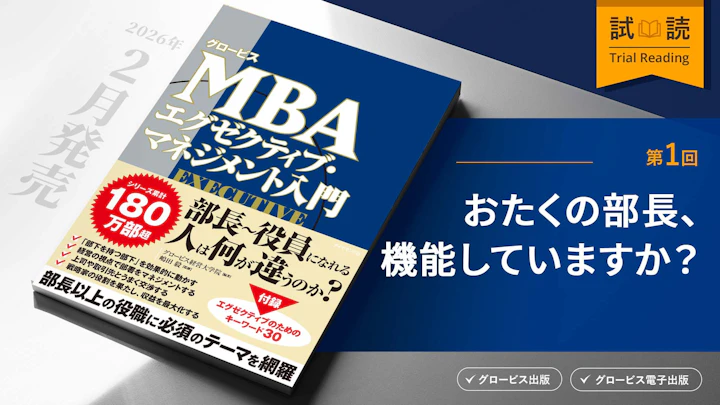















.png?fm=webp&fit=clip&w=720)
.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)




