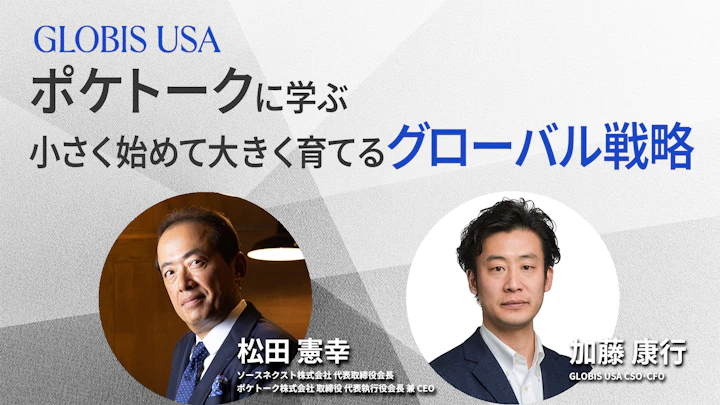堀義人氏(以下、敬称略):この最終セッションのテーマは「リーダーとしての使命と自覚」だ。G1には「批判よりも提案を」「思想から行動へ」「リーダーとしての自覚を」という3つの理念がある。その理念とともにG1中国・四国から各種イニシアティブを起こし、会場の皆さんがそれぞれハブとなって連携しよう、と。では、そのために我々はリーダーとしてどんな自覚を持つべきなのか。それを考えるにあたって今回も素晴らしい御二方にご登壇いただいた。林さんは先週まで農林水産大臣としてTPPを含むさまざまな農政をまとめていた方だ。ご多忙のなかお越しいただき大変嬉しく思う。
堀義人氏(以下、敬称略):この最終セッションのテーマは「リーダーとしての使命と自覚」だ。G1には「批判よりも提案を」「思想から行動へ」「リーダーとしての自覚を」という3つの理念がある。その理念とともにG1中国・四国から各種イニシアティブを起こし、会場の皆さんがそれぞれハブとなって連携しよう、と。では、そのために我々はリーダーとしてどんな自覚を持つべきなのか。それを考えるにあたって今回も素晴らしい御二方にご登壇いただいた。林さんは先週まで農林水産大臣としてTPPを含むさまざまな農政をまとめていた方だ。ご多忙のなかお越しいただき大変嬉しく思う。
 林芳正氏(以下、敬称略):今は暇でございます(会場笑)。
林芳正氏(以下、敬称略):今は暇でございます(会場笑)。
堀:(笑)林さんは当初からG1サミットにご参加いただいている。そして田坂さんはG1関西に続く最後セッションご登壇だ。本サミットにも最初からご参加いただいているので、まずは最初の15分間、田坂さんにお話しいただきたいと思う。本会議の感想とともに、使命と自覚というテーマに関して田坂さんのお考えを伺いたい。そのあと林さんに同じテーマで、大臣そして政治家としてのお考えを、大臣時代の体験談と併せてお聞きしたいと思う。で、そのあと会場の皆さまにもご発言いただこう。
田坂広志氏(以下、敬称略):このような場で再びお話をさせていただけること、心よりお礼申しあげたい。私のような人間がこれほどの場に登壇して良いのかなという思いはあるが、せっかくのご縁だ。私なりの思いをお伝えしたい。まず、やはり「思想よりも行動を」と掲げるG1だ。皆さまのお話を伺っていて強く感じたのは、行動する人間の言葉の力だった。私はそれを「言霊」と呼んでいる。単に本で読んだり頭で解釈した知識を語るのでなく、現実を前に悪戦苦闘しながら言葉を語られる皆さまのような方々がいる。そうした方々の言葉の重みを改めて、しみじみ感じた2日間だった。
実際、どなたも目の前の現実を1mmでも変えようという覚悟で取り組まれている方々ばかりだ。私は64になるが、その点では歳も関係ない。皆さんが発する言葉から多くのことを学ばせていただいたし、そのことに改めてお礼を申しあげる。そのうえで、堀さんにいただいた深いテーマについてお話をさせていただきたいと思う。「使命」と「自覚」。いつもながらのメッセージにはなるけれども、このような宗教的な場だからこそ語ることのできる使命論と自覚論を今日はお話ししたいと思う。
 まず、リーダーは使命という言葉の意味をしっかり見つめてみるべきだと思う。この言葉は日本語で指導者と訳されることが多い。「人々を導く立場である」と。企業では部下や社員、政治の世界では国民の方々を導く立場というわけだ。そうしたリーダーが持つべきは、「自分自身が導かれている」という思いだと言える。その思いを持てるか否かがリーダーを分けると私は考えているし、それがないと非常に危ない。「自分が人々を導いているんだ」という思いだけなら、実に簡単に、小さなエゴから生まれたエゴトリップに陥ってしまう。私も含めて人の心にはエゴがある。多くの人々を導く立場になると、そのエゴが喜ぶ。
まず、リーダーは使命という言葉の意味をしっかり見つめてみるべきだと思う。この言葉は日本語で指導者と訳されることが多い。「人々を導く立場である」と。企業では部下や社員、政治の世界では国民の方々を導く立場というわけだ。そうしたリーダーが持つべきは、「自分自身が導かれている」という思いだと言える。その思いを持てるか否かがリーダーを分けると私は考えているし、それがないと非常に危ない。「自分が人々を導いているんだ」という思いだけなら、実に簡単に、小さなエゴから生まれたエゴトリップに陥ってしまう。私も含めて人の心にはエゴがある。多くの人々を導く立場になると、そのエゴが喜ぶ。
それを戒める意味もあって、日本ではリーダー論として「大いなるものに導かれている感覚をまずは持つべし」と、昔から教えていたのだと思う。まさにリーダーである皆さんにも伺いたい。今までの人生や仕事のなかで、皆さまは何か大いなるものに導かれて進んでこられたのではないだろうか。安っぽい意味でなく、「リーダーは大いなるものに導かれて何事かを成し遂げる」という、この宗教的情操が日本では昔から教えられていた。
堀さんを例に挙げたい。もちろん素晴らしい才能と意思を持って歩んでこられた方だ。ただ、振り返ってみると何か不思議なものに導かれて今までの人生を歩んでこられたのではないだろうか。そして、気が付けば今は多くの方が堀さんと一緒に何かしようと考えてくださっている。私自身も同じだ。いつも思う。「どうしてこれほど優秀な方が私のような人間と一緒に歩んでくれるのかな」という思いを持つことが多い。
日本のリーダー論は欧米のリーダー論とまったく違う。日本では、「千人の頭(かしら)となる人物は、千人に頭(こうべ)を垂れることができなければならぬ」と、よく言われる。これは世界に誇るべきリーダー論だと思う。私もダボス会議等の場でささやかながらそうしたことを申しあげている。もし千人を率いる立場にいたら、心の深くで「自分のような人間と歩んでくださるこの方々が有り難い」と考える。日本のリーダー論では、そうした感謝の思いや拝むような思いを持つよう教えてくれている。
堀さんについても、やはり「「吾人の任務―MBAに学び、MBAを創る」(東洋経済新報社)」という本を書かれた瞬間から、大いなる何かが「この人物を導こう」という大きな流れが生まれたような気がする。私自身、ささやかながらそうした導きのなかで今日まで歩むことが出来た。皆さんも同じだ。気が付けば、何か不思議な「あの方とのご縁」「この事業との出会い」「こういう世の中の展開」が、素晴らしい使命の道を歩ませてくださったという思いがあるのではないか。それが私の考える使命論になる。
それともうひとつ。「もしかして、何か大いなるものが自分を通じて何か成し遂げようとしているのでは?」という思いもある。私自身、64にもなると「これほど未熟なひとりの人間を育てながら、大いなるものが何かを成し遂げようとしている」との思いに導かれる。会場にもそんな思いに至った方は多いのではないか。「我が業(わざ)は我が為すにあらず。大いなる天の成す業」という覚悟も日本の使命論だと思う。
挫折を乗り越えてリーダーになる
そんなお話をしたうえで、続いては自覚の醸成に関してお話ししたい。これもまた導かれるものだと私は思う。この言葉、普段は「しっかり自覚しろ」「部下にもっと自覚を持たせろ」といった意味で使われる。でも、リーダーとしての自覚の、心への刻み方はたったひとつ。誤解を恐れず申しあげると、素晴らしいリーダーは挫折を知っている。何かを成し遂げるリーダーは、実は若き日、あるいは歳を重ねたあとでも挫折を経験して、そこでリーダーとして本当の自覚を持たれている。政治家の方でも経営者の方でも、そうした例がほとんどであることに我々は気付くべきだと思う。これは本を10~100冊読めば深まるとか高まるといった生易しいものではない。天がひとりの経営者や政治家を育てようとするとき、そこで挫折を与えることも真実だと思う。
実は今この国を率いている方も、何年か前に大変な挫折を経験なさって、そして今戻ってこられたと思う。個別の政策に関する議論を超えて、そのように感じる。ひとりの政治家がひとつの道を歩むとき、天が挫折を与えることがある。そうして何年もの歳月を歩んだのち、「ああ、あの挫折があったからこそ」との思いになるわけだ。
それは決してこの国のリーダーだけの話ではない。皆さんの誰もが、たとえば経営の世界を歩みながらそうした挫折を乗り越えてこられたのではないか。そこで3~5年前の挫折に関して、「あんなことがあったせいで今の俺は」なんてネガティブに捉えている方はいないと思う。挫折した瞬間は心が挫けそうになるときもある。辛い日々を送ることもある。でも、それらを乗り越えた素晴らしいリーダーは必ず、こういう話が口をついて出てくるようになる。「辛かったよ。あの数ヶ月、あの数年。でも、そのおかげで自分は大切な何かを掴んだ。だからこそ今日がある」と。真っ当な人物ならそうなる筈だし、そういうことを語ることのできる方こそ本当のリーダーだと思う。
なぜ、そうしたリーダーの姿が必要なのか。皆さんもお分かりだと思う。皆さんが経営者として率いる社員や部下の方々、あるいは国家のリーダーとして率いる国民の方々だって、皆が苦しい人生を歩まれている。苦労や困難、失敗や敗北や挫折、あるいは大切な肉親を失う喪失。そうした悲しみや苦しみのなかでも立ちあがって歩んでいくのが人生だ。そうした人々を率いるリーダー…、率いるという言葉すら本当は使いたくないが、ともに歩ませていただくリーダーは、その後ろ姿に社員や国民の方々が勇気や希望を感じるような歩みをすべきだと思う。挫折から再び立ちあがって未来を見つめるリーダーは、「あれがあったからこそ」と言えるようになる。「起こることはすべて良きことである」と。実は最近、「人生で起こること すべて良きこと」(PHP研究所)というタイトルの本を書いた。そうしたことを堂々と語ることのできる姿こそ、リーダーの姿ではないか。

最近、政権は「1億総活躍社会」と言っている。私はこの言葉に異議を申しあげる立場ではない。ただ、私としてはしばらく前に発せられていた「再チャレンジが許される社会」という言葉のほうが、むしろ胸を打っていた。なぜか。それを語るリーダー自身がまさに挫折から戻ってきて再びチャレンジを行い、ひとつの道を歩みはじめたからだ。だからこそ言葉に言霊が宿るし、「その通りだ」と頷くことができる。これは単なるレトリックではない。結局、リーダーが何を語るにしても、部下や社員や国民の多くは、「そのリーダーがどのような人生を歩んできたか」を見ている。そしてそこに無言の説得力があるなら、リーダーとして堂々たる歩みを見せる資格が生まれるのだと思う。
また、宗教的な深い叡智が問われるこの素晴らしい場で「自覚の醸成」というテーマをいただいたわけだから、あえて申しあげたい。先ほどの「大いなるものに導かれる」というのは、自覚の情勢についても言えることだ。つまり天が導く。今、大きな壁に突き当たっている方がいらしたら、私は心のなかで手を合わせてこう申しあげたい。「それはお辛いでしょう。でも、今は大いなる何かが皆さんをリーダーとして育てようとしているんです。天が大いなる使命を与えようとしているからです」と。
私も32年前、生きるか死ぬかの大病を患ったことがある。当時はどん底の日々だった。でも、今振り返ると、あの日々がこの未熟な人間をどれほど鍛え、育ててくれたか。そして人生における大切な叡智をどれほど与えてくれたかと思う。では、その叡智とは何か。「使命」と書いて「命を使う」と、私には読める。あのどん底にあった日々、もう長くないと医者に言われた命を、気付けばもう32年も与えていただいた。私はあの頃から「あと1日生かしていただきたい」と思いながら、そして長くないと言われていた命を「何に使おうか」と思いながら歩んできた。それが私の使命観だった。
今振り返ると、「あと3ヶ月の命」と医者に言われたとしても、「あと30年の命」と天に言われたとしても、どちらもかけがえのない一瞬の人生だと思える。それに気付いたとき、使命という言葉の真の意味に我々は気付くのだと思う。そんなことを申しあげて最初のメッセージとさせていただきたい。ありがとうございます(会場拍手)。
→日本を変革するリーダーとしての使命と自覚 ~G1中国・四国を契機に~[2]は1/23公開予定
※開催日:2015年10月16日~17日



























.png?fm=webp&fit=clip&w=720)


.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)








.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)