「そもそも、組織って何だろう?」
リーダーであれば、一度は思い浮かぶ問いではないでしょうか。
プロジェクトの方向を決めるとき。制度を見直すとき。あるいは、部下から退職の意向を告げられたとき。重大な判断や転換点に直面するたびに、私たちはこの根源的な問いと向き合うことになります。
この問いに対して、本書はバーナード、サイモン、ワイクら組織論の巨人たちの古典をひも解きながら道筋を示してくれます。
組織論は「現場の悩み」とつながっている
組織論というと難解な学問のように思われがちですが、実は「現場の悩み」と地続きです。
学問としての組織論が本格化したのは20世紀初頭。軍隊や工場が巨大化し、「いかに効率的に組織をまとめあげるか」が社会的な課題となった時代です。
このとき登場した手法のひとつが、フレデリック・テイラーの「科学的管理法」です。これは、作業を客観的に分析し、最も効率的な手順を標準化することで、生産性を最大化しようとした手法です。
のちに「標準作業」「マニュアル化」などにもつながる考え方でもありますが、なぜこの手法が生まれるに至ったのでしょうか。
当時の工場では、労働者が意図的に作業を抑える「怠業」が問題になっていました。これは、単なる怠け心によるものだけではなく、集団が引き起こす「組織的怠業」もあったとされます。
背景には、こんな組織の力学が働いています。
当時、工員は出来高に応じて賃金を得ていました。この仕組みでは、熟練すれば生産量も上がり、賃金も増えていきます。
ところが、賃金の引き上げにも限界があります。そのため、人件費の高騰を嫌った経営側は、どこかで単価を引き下げてしまいます。すると、労働者の間では「なんだ、頑張るだけ損をしてしまうじゃないか」という心理が働きます。
もちろん、一人だけがサボっても、そこまで影響はありません。しかし、皆が足並みを揃えてサボれば、全体として生産が抑えられてしまいます。実際、こうした「組織的」な怠業が起こってしまったのです。
テイラーの科学的管理法は、この現象への処方箋として登場しました。
つまり組織論とは、現場の悩みに応える知恵であるということです。
巨人たちの理論を今にどう生かすか
こうした視点で読むと、組織論は単なる理屈の積み上げではなく、時代ごとの切実な課題に応えるために編み出された実践知であったことが見えてきます。
本書は、この実践知としての組織論を「10年ごとのマイルストーン」に整理し、その流れを形づくった5冊の古典を取り上げます。
『経営者の役割』(チェスター・バーナード)
『経営行動』(ハーバート・A・サイモン)
『オーガニゼーションズ』(ジェームズ・G・マーチ & ハーバート・A・サイモン)
『オーガニゼーション・イン・アクション』(ジェームズ・D・トンプソン)
『組織化の社会心理学』(カール・E・ワイク)
例えば、バーナードは、組織を上下関係の集合ではなく、人々が力を合わせて成り立つ「協働のシステム」と捉えました。トップの指示だけではなく、メンバーの協力がなければ組織は動かない──これは、現代のリーダーにも突きつけられる現実です。
サイモンは、人の意思決定は必ずしも合理的ではなく、情報や時間の制約の中で下される「限定合理性」に基づいていると指摘しました。制度やルールの設計がなぜ重要かを示した発想です。
マーチ=サイモンは、この意思決定を「情報処理のプロセス」として捉え直し、組織を『意思決定のシステム』として位置づけました。サイモンが提唱した「限定合理性」を前提にすれば、組織とは、人間の認知の限界を補い、より良い判断を導くための装置だとみなすことができます。この発想は、人の判断や記憶を支援し、意思決定の質を高めることが期待されるDXやAI活用にも通じます。
トンプソンは、 「不確実性こそが組織の本質」と喝破し、環境変化にどう備え、柔軟に構造を組み替えるかを描きました。VUCAの時代を生きる現代の企業にも直結するテーマです。
ワイクはさらに一歩踏み込み、組織を「意味づけ」のプロセスとして捉えました。人は出来事に意味を与え、共有し合うことで組織をつくり続ける。リーダーの言葉や物語がなぜ重みを持つのかを理論的に説明したのです。
こうして読み解くと、巨人たちの理論をたどることは、単なる歴史の振り返りではありません。むしろ、現代の私たちが組織課題に向き合う際、「どこから手をつけ、どう考え抜くべきか」を導いてくれるヒントに満ちているのです。
「どう解くか」より前に、「組織とは何か」を問え
「組織とは何か」という根源的な問いは、プロジェクトの停滞、制度改革の議論、メンバーのキャリアの岐路など、私たちが日々直面するあらゆる場面で立ちはだかります。
しかし、この問いに向き合わないまま目の前の課題に追われていると、つい「どう解くか」ばかりを探してしまいがちです。その結果、表面的な対応に終始し、問題の本質には届かないままになることも少なくありません。
だからこそ、解法に飛びつく前に、まず「組織そのもの」を理解すること。それがリーダーに求められる第一歩だと考えます。
読後にはきっと、自分が率いる組織の姿が、これまでとは違った輪郭で浮かび上がってくるはずです。
『組織の思想史 知的探求のマイルストーン』
著:高橋伸夫 発行日:2025/1/18 価格:3080円 発行元:日経BP 日本経済新聞出版


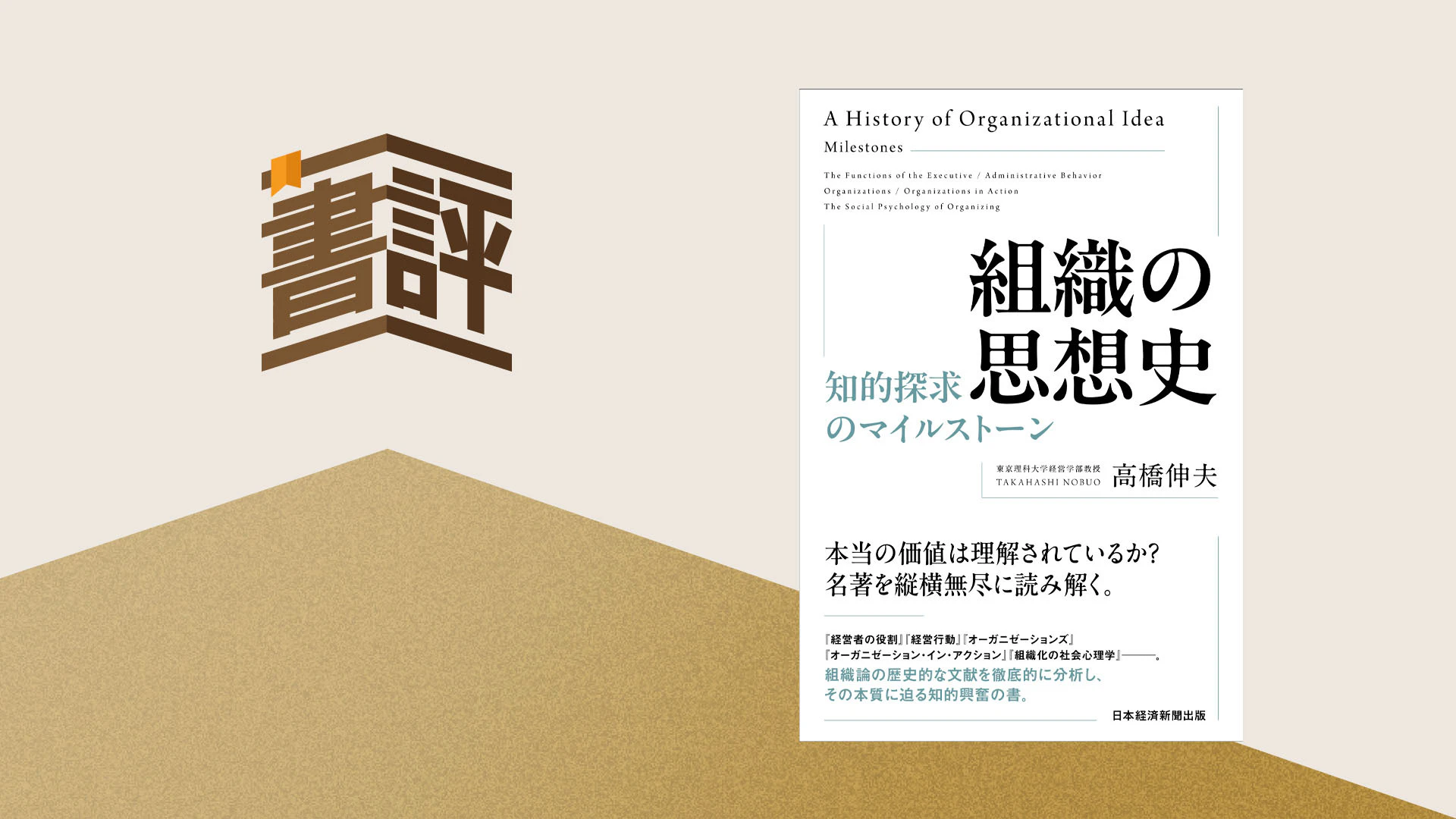













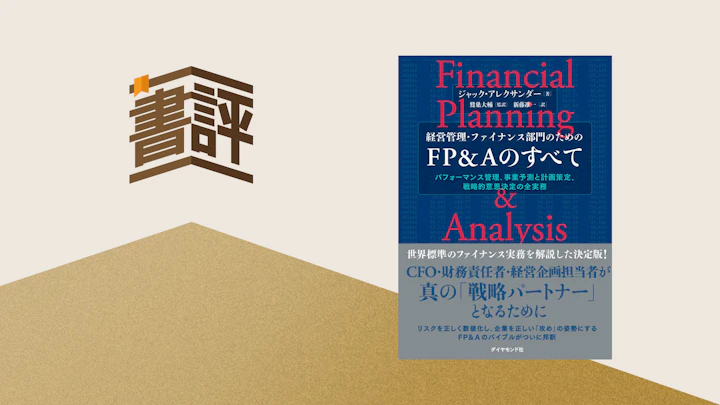


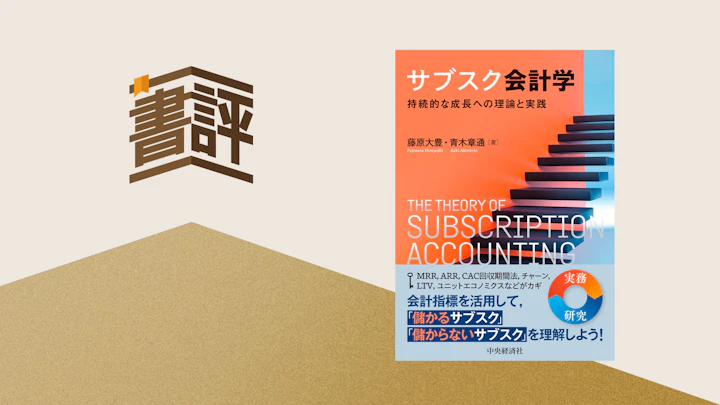













.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)

.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)

.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)

