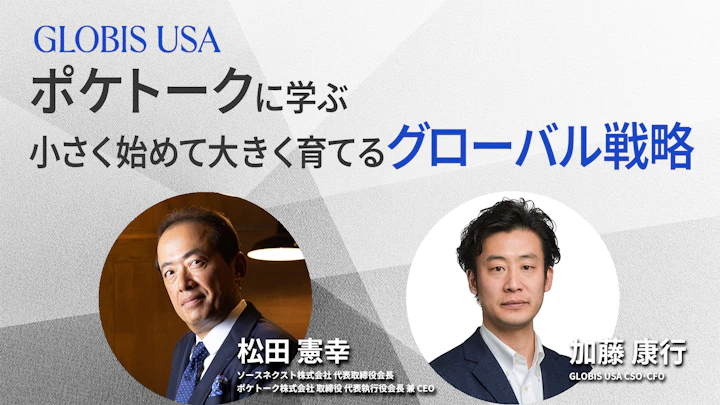地域発ベンチャー大国・日本をつくる[4]
高野:アベノミクス第3の矢では地方創生とベンチャーが大きな主軸になる。それで…、実は私のメインの仕事はエンジェル投資家という面があるのだけれど、最近はそれでいろいろな案件がくるし、東京は結構動いているイメージがある。実際にベンチャーを経営している岩田さんと谷井さんから見るとどうだろう。関西と差があるとすれば、その違いがどこから来るのかという点も併せて伺ってみたい。

谷井:たしかに今の東京はすごくホットだ。言い方を変えると、「じゃぶじゃぶ」だと思う。これは僕の経験に基づく感覚だけれども、日本の証券市場とVCマーケットの時間軸は同期していると思う。日本のIPOマーケットが大変好調だから資金が集まっている。恐らくそれだけの話ではないかな、と。だから、正直、「長くても2年ほどでパチンコの花びらはもう一度締まるのだろう」と。だから、調達するなら一刻も早いほうがいいと思っている。
一方で大阪はどうかというと、そういう盛り上がりには欠けている。なぜか。ぶっちゃけて言うと、優秀な起業家が少な過ぎると思う。自分に対する反省も込めて(会場笑)。僕はそれが悔しい。会場の皆さまも感じていらっしゃると思うけれど、皆が東京へ行ってしまう。なんとなく形になってくると東京へ行ってしまう。創業前に東京へ行ってしまう人もいるし、学生生活は大阪だったのに就職で東京へ行ったのをきっかけに、そのまま東京へ住み着く人もいる。実際、東京で創業する西日本の人間はすごく多い。悔しいじゃないですか。たぶん大阪や関西から人材が流出してしまっているだけだ。これはもったいないし、「なんとかせな」という問題意識がある。
僕は少なくとも東京に本社を移そうと考えたことがない。どこでやっても一緒やと思う。たとえばコカコーラがアメリカの会社というのは分かるけれど、アメリカのなかのどこかは、僕は知らない。ベンチャーの意識の高さはそういうところに出ると思う。本社が大阪なのか京都なのか神戸なのか、はたまた東京なのかは、あまり関係がない。どこでやろうが勝つのがベンチャーだ。「便利だし情報も集まるから東京に行ったほうがうまくいく」というわけでもないだろう。むしろ、基礎体力の差のほうがずっと大きいので、どこでやっても勝つやつは勝つと思っている。「だから大阪や京都や神戸でやればいいやん」と僕は思うけれど、今はそうなっていない。
高野:厳しい言い方をすれば情報の差が言い訳になっている、と?
谷井:なっていると思う。情報の差は実際にあるし、その量がディシジョンを分けてしまうときはある。とはいえ、大阪から東京はたった2時間半だ。それなら行けばいいと思う。本社が大阪や京都にある企業でも、経営者の方は普段から東京へ行っている筈だ。海外にだってビジネスで普通に行っているわけだし、そういう距離の差というのをあまり言い訳にしてはいかんと考えている。
岩田:東京がどうかというと、谷井さんがおっしゃる通りで2年後ぐらいにパチンコの花びらが締まる感じかな、と(笑)。今回は当社もIPOしたけれど、IPO時の企業評価軸と未上場時の企業評価軸がずれていて、それによって誰かが不幸になるということがあるように思う。そう考えると、近い将来、上場バブルのようなことも終わるのかなと思っている。あと、西日本に関してはまったく盛り上がっていない。我々も今回上場したし、関西のベンチャーに投資をしながら関西連合みたいな形でベンチャーを育てることができたら格好いいなと思っている。で、そのためにはVCと一緒に支援していくといったやり方のほうが効率的だと思って、某大手VCに「今はITでどこを推していますか?」と聞いてみた。すると、向こう3~5年はITで上場しそうなところがほぼないといった話だった。だから東京とは状況が違うし、かなり厳しいと思う。
で、その原因については谷井さんと少し認識が異なる。エコシステムについてざっくり言うと、築地のすし屋みたいなものだと思う。東京には、たとえば「すきやばし次郎」のようなすごいすし屋がある。なぜそういうお店ができたかというと、近くに築地があって、築地のおっちゃんと毎日話をして信頼関係ができているから。「このマグロがいい」と教えてもらって、毎日お店に卸してもらって、米も全国で一番良い米を出してもらっている。当然、職人もいるし、それに伴って客もいる。それらがすべて揃っていてエコシステムなのだと思う。それとまったく環境が異なる大阪の端っこで、「すきやばし次郎」レベルの寿司を出せるかというと、正直、厳しいと思う。
そうしたエコシステムという土壌のうえでこそ、大きな会社は育つのだと僕は考えている。だから東京が強い。当然、それは業界によって違う。寿司は築地だろうし、ITは東京。それをいきなり変えるのは難しい。ただ、業界が変わって築地のネットワークみたいなものを大阪にもう一度つくるといったことはできると思う。
吉川:まさにそういうことで、「ITだけなら東京に行ったらええんちゃう?」と僕は思っている。「IT×ものづくり」とか、「IT×農業」とか、ハードウェアとの掛け算等を見せないと大阪では無理だと思う。だから、OIHでも最初から「IT×ものづくりでないとあかん」と言っている。そこから「Moff」というバンドが生まれた。1年半前のハッカソンで高萩(昭範氏:株式会社Moff代表取締役)さんという人らがグループをつくり、現在のものとは違うインターフェースをつくった。で、我々が主催するシリコンバレーツアーに参加して、シードアクセラレーターで「私たちはこういうものをつくりました」というプレゼンテーションをした。それで、「うーん…、なんかよう分からんけどおもろいな」みたいなことを言ってもらったのが一つの励みになった。それで帰国後もユーザー調査をして、現在のような形になったわけだ。それで今はキックスターターというクラウドファウンディングで800万ほどを集め、現在のものを上梓している。
これはおもちゃと一緒に遊ぶものだ。振ると音が出る。たとえば飛行機を飛ばすと、その音がスマートフォンから出てくる。従来のおもちゃ屋さんは飛行機をめちゃくちゃ精巧に、格好良くつくるのが仕事だった。でも、これからのおもちゃは効果音を出さないといけないようになる。とすると、効果音を出すプラットフォームは「Moff」がスマートフォン上で展開しているものに依存しなきゃいけなくなる。で、ユーザーは年齢や右利きか左利きかといった属性を入れないといけない。そうしたデータがすべて「Moff」に流れる仕組みだ。つまり、彼らはITを用いることで従来のおもちゃ屋さんをオーガニゼーションするというか、囲い込むようなビジネスをするわけだ。
だから、おもちゃ屋さんにとってはめちゃくちゃ脅威だし、IT屋さんにとっては大きな機会という感じがする。大阪ではそういった形で、「IT×ものづくり」等、ITに何かを掛け合わせた形で頑張らないといけない。大阪の特徴として中小企業のものづくりの集積というもの一つある。また、小売等の面積は東京よりも大きい。密度が高い。さらに技術シードということで言うと、学生の集積率というか人口密度が関東圏とほぼ一緒だ。1000人中29人ほどが学生になる。背景には起業家の集団がいて技術もあるわけで、それを生かさない手はない。イノベーションやエコシステムを生み出すパーツはあるのだから、分野を絞ってリンクさせていけばエコシステムは生まれるという確信を僕は持っている。とにかく分野を選ばないといけない。

高野:Q&Aに入る前のまとめとして、関西にイノベーションのエコシステムをつくるための具体的提案として何かあれば伺ってみたいと思う。
岩田:これはシリコンバレーに対する日本の強みでもあると思うことだけれど、良くも悪くも最初から資金調達があまりできない。ある程度の規模になってから資金調達をしていく。だからオーナーが結構株を持っている。これはかなりの強みだと思う。だから、社会全体のエコシステムをつくる前に、社内のエコシステムをつくることが日本企業ならできるのではないかと思う。
たとえば、ファミリービジネスであれば2000~3000人規模の会社でオーナーがほとんどの株を持ち、それで事業をどんどん変えたり新規事業を進めたりすることができる。これ、シリコンバレーではあり得ない。ビジネスモデルをピボットするのは大変だ。その前にどこかの会社へバイアウトするのが王道というか基本になる。でも、日本ではそこでビジネスモデルを変えることができる。これは最強のモデルだ。だから、良くも悪くもお金は集まらないから、しっかりと地道にビジネスをつくりながら社員を育てていける。家族的経営ということを我々も標榜しているけれど、そうした密な組織でやっていけるのだと思う。そのうえで、いざというタイミングが来たときに社長が「この事業をやる」と言えば、次の日からでも50~100人をアサインできる体制をつくれるのか。その辺が重要なポイントなのかなと、個人的には思っている。
谷井:先ほどのお話とまったく違う観点のお話をしたい。先ほどは関西起業家の人たちの悪く言っちゃったので(会場笑)、「ほかのところも悪く言っておかないとあかんかな」と(笑)。関西全域で見ても、いろいろな形でベンチャー支援の取り組みは行われていると思う。京都でも大阪でも神戸でも滋賀でも、たくさんある。それで、僕のところにも数多くの話が来る。ただ、たとえば「学生の起業家意識を高めるため、こんな活動をしてます」と来て、その3日後にまったく別のところが、「学生の起業家意識を高めるため、こんなイベントを打ちます」と言ってくる。「あれ? どっかで聞いたな」みたいな。「この前、夢見たかな?」みたいな話が山ほど来る(会場笑)。
こういったものについて連絡会のようなものをつくってはどうか。そこで、「うちはこんな活動をしています」「うちはこんな場を用意しています」と、とりあえず足並みを揃えるだけでかなり使えるものになると思う。情報についても同じだ。各社に入ってくる情報には抜け漏れがあるというか、すべての情報が入ってきているわけではない。そこで何か連絡会的に情報共有をしていただいて、どこか一つのところから情報が手に入るような仕組みにしていく。それだけで、たぶんベンチャー側で使えるものや我々が協力できるもの、あるいはアクセラレートできるものがあると思う。
高野:いいですね。これ、G1関西における関西ベンチャーの具体的アクションということで、谷井さんが幹事でよろしいだろうか(会場拍手)。
吉川:大企業さんとコラボをする機会を増やして欲しい。具体的には、たとえば大企業さんが従業員さんに対して、15%ほどの…、20%でも構わないけれども、その時間を使ってグーグルのように新規事業を考えてもらう。で、「そのためにOHIへ行ってきてもいいよ」という風にしていただくとすごくいいかなと思っている。
OIHのようなところに来ると脳が活性化すると思う。以前シリコンバレーツアーに連れて行った学生のなかにも、そのツアーを契機に「もう就職辞めます」となった学生がいた。「シリコンバレーでお金を出してくれる人がおりますねん」と。バイタリティある男だからエンジェルに気に入られて、「俺のアイディアを渡すから開発しろ」と言われたそうだ。で、その彼が久しぶりに日本へ帰ってきたときに話をしたのだけれど、「ソフトの開発は新潟県にある某ソフト会社の部長さんにお願いしています」と言う。企業の方々が5時以降や土日にボランティアでやってくれるそうだ。その人たちは普段から、「今後はスマートフォンのスキルを身に付けなければ」ということで勉強をしていたり、自分のアプリをappストアに上げたりしているという。で、彼はappストアでいろいろとアプリやその開発者情報を見て、「あ、この人、ええな」と思った人に直接メールをする。それで、あとはスカイプで話をして助けてもらうという。
結局、その彼は就職したこともないわけだけれど、ソフトウェアや仕様の書き方はその新潟にいる部長さんに教わるらしい。「お前、こんな書き方してたらあかんわ」と言われるそうだ。そういうワーキングスタイルってすごいと思う。だから私は企業の枠を超えた新しいワーキングスタイルが広がってくると思う。G1関西だってある意味ではそれを目指しているわけでしょ? リーダー同士がコラボや横連携をするためのプラットフォームだと思う。そういうことが毎日起きるようになればエコシステムと言われる。たぶん、そういう状態になると思う。会社の寿命は30年だけれども職業時間は50年。「その差の20年はどうするか?」と、ドラッカーだって言っている。だから、基本的にはプロフェッショナルというかナレッジワーカーとしてその人を育ててあげないと、その人にとっても企業にとってもアンハッピーだと思う。
これから、企業の枠を超えた横コラボを行う時代は確実にやってくる。全員がなるわけじゃないけれども、力のある人ほどそうなる。そういう人たちが横連携しながら一つの事業をつくっていく時代が来るということを、僕はOIHでも感じている。「Moff」だってOIHでグループがつくられてから生まれているんだから。なんというか、今までの縦社会にあった壁がどんどん希薄になってきている。シリコンバレーでは以前からそうだった。そうしたエコシステムの一部は、このG1サミットがどんどん大きくなれば関西でも絶対にできると思う。だから提言としては、そういった未来を踏まえつつ、大手企業さんには20%でも15%でもいいから人件費をリリースするようなコミットをお願いしたいと思う。
→地域発ベンチャー大国・日本をつくる[5]は5/15公開予定
































.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)