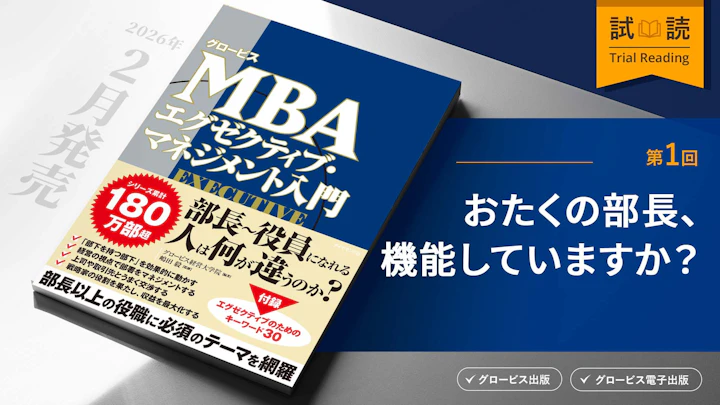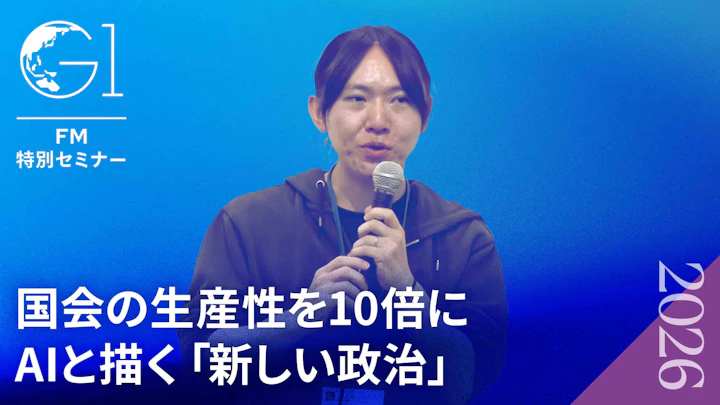「環境変化と偶然に押し出されるようにして新興国へ展開していった」(山田)
梅澤:私自身、これまでコンサルタントとして色々な企業のお手伝いをしてきたが、リーマン・ショック前までは「グローバル成長の加速」というものが経営アジェンダのトップに上がっていない企業のほうが多かったと感じる。しかしリーマン・ショックと3.11を経て、それが消費財メーカーや消費サービスを手掛ける企業でも上位になってきた。そこには少子化や高齢化、あるいは長引くデフレによって国内市場になかなか伸びる余地が生まれてきていないという背景がある。一方で世界経済全体は成長をしており、特に新興国では相当の伸び率を期待出来る。それでここ5年ぐらいのあいだ、日本の消費財関連企業がグローバル、特にアジアでの成長に大きく舵をきってきた。本セッションではそういった消費財のグローバル展開で長い経験を持つ企業からお越しいただいたお三方と議論を進めていきたい。(1:36)
山田:ロート製薬は創業110年の会社だが、私が経営に携わるようになった20年ほど前は、苦境というほどではなかったにせよ、見通しはかなり暗い状況だった。目薬や胃腸薬の「パンシロン」など我々はいわゆる一般薬しかやっていないが、その市場は当時から右肩下がりだったためだ。ある程度のシェアはあったが成長性は非常に乏しかった。当時は100%国内向けの企業だったこともあり、「ここから先、一体どうしていけば良いのか」というのが1985〜1990年あたりの状況だった。大きな背景まで含めると、そういった厳しい状態にあったことが海外展開の原動力になっていたのではないかと、今振り返ってみると感じる。(5:34)
ただし、そのきっかけには偶然の要素も重なっている。当時は米国企業の製品であった「メンソレータム」という軟膏のライセンスを持っていたのだが、こちらの会社オーナーが「自社を売りたい」ということで、1988年、M&Aで傘下に入って貰った。それで海外ビジネスしなければいけない状況に突然追い込まれてしまったという背景が事実としてあったのだ。海外経験が殆どなかったため、実際、5年ほどは相当苦労した。メンソレータムは“身売り”しようかと言っていたほどの企業だから収益もあまり上がっておらず、それでも「とにかくアジアで力を入れてみよう」という話になった。で、当時は中国で改革開放が、ベトナムではドイモイ政策が打ち出されていたため、同地域が行けそうだと考えた。ただし我々が扱っているような商品では、現地で製造し、それを日本へ持ってきてコストメリットを得るというモデルが成り立ちにくい。商品ひとつひとつが小さくて安い割に生産しようとすると意外と大きな設備投資が必要になるためだ。それでまずは「消費マーケットとしてアジア市場を見ていこう」と考えた。本当に一からのスタートだったが、1990〜1996年にかけて、ベトナム、インドネシア、そして中国へ進出していった。昨今はミャンマーでも本格的に展開していこうかと考えている。また、東アジアと南アジアから進めていった訳だが、その次ということでバングラデシュに2年ほど前から、そしてモンゴルでも昨年から薬を売りはじめている。(7:45)
結果、数字は順調に伸びた。中国市場といっても先行投資で進めている企業さんは多いと思うが、我々は現地生産・現地販売で完結させ、営業利益率は10%前後。海外でも実際に稼ぎ、現地で回すことが出来ている状態だ。連結売上高1200億円のうち、海外比率はまだ40%に届かないぐらいだが、それでも成長率は海外、とりわけアジアが高い。これからも着実に上がってくると思う。(13:12)
「南米には“移民でお世話になったから”と進出した。今も海外展開は分析より縁を大事にしている」(角田)
角田:公文式という学習法および教育サービスを世界で展開している。会社創業は1958年。そこからの推移を見てみると、創立当初は300人だった学習者が現在は436万人にまでなった。グローバル展開も比較的早い時期にはじめている。まず1974年にニューヨークで教室をつくり、その2年後に台湾、さらにその2年後にブラジルのサンパウロ、それからドイツということで展開していった。(14:51)
これには、創立4年目の1962年、創始者が事業に関する将来の夢を盛り込んだ10項目のメモのなかに、「公文式を海外展開する」という項目を入れていたことも影響している。1962年といえば国内でもまだ学習者は2500名程度。公文式の名も知られておらず海外進出など夢の夢だった。しかし当時の将来像が今でも浸透しており、グローバル展開についても色々考えず、とにかく打って出て行けるような社風になっているのだと思う。現在は47の国と地域で学習して貰っており、学習者の内訳では国内が34%、海外が66%になっている。売上、利益の構成比もほぼこれと同じと考えていただいていい。(16:18)
海外展開に関してひとつ象徴的なことをお話しすると、たとえば南米には34年前に進出しているが、こちらは日本から最も遠い地域だし当時は交通事情も今と違っていた。だから創始者が展開先に南米を選んだ理由が当初は分らなかったが、後日、「日本は移民で南米に大変お世話になっている。だからその恩返しだ」と言っているのを聞いた。こういった考え方は今も海外へ出て行くにあたってひとつの基調だ。きちんとした市場調査やマーケティングの上でというケースは比較的少なく、むしろ“縁”といったところで始めて、そこで育てている。(18:17)
ちなみに教室内の風景は日本も海外も同じ。公文式学習法には「個人別」という冠がつくが、教室にいる子供たちの学年や年齢は皆違うし、それぞれ異なる教材で勉強している。江戸時代の寺子屋がイメージしやすいと思う。昔は「手習いそろばん」と言われていたが、公文は「読み書き計算」。それ以外はやらない。これが海外で受け入れられているひとつの要因だと思う。教育は国づくりの根幹だから専門性の部分は国によって違う。我々がやっているのは、その一歩前となる読み書き計算という基礎学力の土台づくりだ。その先は国ごとにそれぞれのやり方でやって貰ったら良いのではないかと考えている。従い、言語は当然、翻訳するが、算数・数学など設問は同じ。日本でもインドネシアでもカタールでも南アフリカでもアメリカでも同じ教材・同じ指導法をとっている。(18:17)
その一方で、教室などのハードにはあまりこだわっていない。フランチャイズビジネスではハードの統一がよく言われるが、公文はショッピングセンターの中や、独立の建物や、多少シャビーなところや、色々だ。ソフトである教材は世界共通でも、ハードはそれぞれお国事情に合わせている。インストラクターもスタッフも現地の方々だ。海外で働いている社員およそ2000人のうち、日本からの駐在は40人だけ。教育ということもあるので、やはり現地を愛し、その文化が根づいている方々に中心メンバーとしてやって貰っている。それによって現地で雇用も創造しつつ、それぞれの国で教育の土台づくりをお手伝いするという形だ。(22:00)
理念に関して言えば、たとえば「436万人の学習者と指導者が地球上に散らばっている」という考え方になる。年齢や学年ではなくその子の学力がどうか。国籍も関係なく、「その子は掛け算が出来るか否か」といったことをまず考える。アメリカのジョンちゃん、日本の太郎ちゃんを横に並べて考える。それが個人別の概念であって、それぞれの国の教科書に合わせるという話ではない。で、そんな風に考えていくと、ひとつの理念を共有出来る。不易流行という言葉があるが、我々は不易の部分は絶対に外したくない。それは日本でも大事にしてきたことで、具体的には、「個人別」、「自学自習」、「子どもは可能性を持っている」といった考え方だ。国によって「そういうのはちょっと違うのでは?」という気質もあるが、その辺は変えない。(22:23)
一方で、個別具体的なやり方についてはそれぞれの国に合わせていく。たとえば中東にはラマダンがあったりして休みが長く、日本のような休みをとっている国とは勝手が異なる。しかしそこで日本のやり方を押し付けても上手くはいかない。だからその国のなかで良い方法を探していくのだが、そのなかで創意工夫が生まれる。それは100点ではないにせよ、日本だけでやっていたら生まれなかったような工夫だ。海外展開を進めていく大きな意味のひとつがそこにある。もちろん確信を持って学習してくれる人が増える喜びもあるが、海外へ行くことで創意工夫がなされ、公文式が磨かれていくと我々は感じているためだ。もちろん不易の部分が崩れたら公文式ではなくなってしまうから、そこは絶対に崩さない。それ以外のやり方について、状況に合わせつつ「皆で知恵を出し合いましょう」と。そこで生まれる創意工夫は小さいようにも見えるが、私たちにとっては大きなイノベーションだと考えている。(26:25)
「アジアのスキンケア、欧州の香水、北米のメイクアップ。個別のビジネス体を拡げながら一つに束ねてきた」(フィッシャー)
フィッシャー:資生堂の売上をグローバルに見ると、15年前にはおよそ11%だった海外売上比率は2012年におよそ44%にまで高まっている。まずはそのような現在に至るまでの流れをもう少し遡ってみたいのだが、そもそも「資生堂は日本の伝統的企業」というイメージがあると思う。しかし我々のDNAは非常にグローバルだ。オリジンは「日本初の洋風調剤薬局」であり、1897年に日本で初めて西洋の薬理学を採り入れた化粧品を発売したのも資生堂だし、初代社長の福原信三や2代目の松本昇はそれぞれコロンビア大学とニューヨーク大学で薬学を勉強していた。そういう意味でも西洋と東洋のハイブリッドカルチャーを持っていると思う。(27:20)
しかし、1970〜1980年代頃にどうなっていたかというと、特に1970年代、国内市場が急激に伸びていったため、高級商材からマスマーケットまで広く手を出し、かたや海外展開は減速していた。それで2000年ぐらいまで、特に海外ではほぼ高級化粧品だけを展開していたのに対し、国内では中低価格商品の販売が中心となり、両者の戦略がどんどん乖離していったという経緯がある。そこで改めて2005年、「少なくともアジアでは合わせていこう」ということで、アジアではマステージマーケティングを展開していった。一方でグローバル市場、特に欧米市場では高級化粧品を展開していったという流れになる。(29:23)
現在は製品カテゴリー別の3つのプラットフォームでグローバル展開を強化している。まず「スキンケア」。これは今までアジアを中心としていたが、現在は約90カ国で展開している。次に「香水」。資生堂はBPI(Beauty Prestige International)という独立した香水部門を持っており、こちらは世界最大の香水市場である欧州をメインにしつつ、やはり展開自体はグローバルに107カ国で行っている。そして「メイクアップ」ブランド。Bare EscentualsやNARSといった企業を買収し、こちらは北米市場をメインにしつつ、少しずつアジア、欧州に向けて展開しようとしている。(31:04)
日本・アジアを中心にしたスキンケア製品の輸出型ビジネス、欧州を中心にした香水の独立型ビジネス、そして北米を中心にしたメイクアップの買収ブランドのビジネス。おのおののビジネス体の展開地域を広げてきた結果として、数字上でも海外比率は確かに1997年の11%から現在の40%台まで高まっているが、重要なのは中身が大きく変わったことと我々は考えている。2005年まではほぼ輸出ビジネスが中心だった。販社がつくっても、トップラインとボトムラインだけで管理していた状態だった訳だ。しかし現在は、それぞれの販社が独立し、ほぼホールディングカンパニーのような形になった。2006年から、プロセス、組織、あるいは人材をすべて統合していった結果、たとえば海外比率の44%というものがひとつのブロックになったと言える。それまでは30数%あってもばらばらな形だったが、今はそれが合算されたことで、初めてスケールメリットが生まれている。(32:22)
「現地の自由度を可能な限り高めることで、スタッフのモチベーションを引きだした」(山田)
梅澤:おのおの違ったやり方で成功を収めてきた結果や経緯について伺えたところで、戦略についてもう少し踏み込んで聞きたい。まずロート製薬の戦略だが、これはまさにアジアンボリュームゾーンにおける大成功例でもあると思う。アイケア、リップクリーム、日焼け止めなど、その国のシェアNo.1を取られているものも多い。これらアジア新興国市場は具体的に、どのように攻めてきたのか。(33:37)
山田:中国やインドネシア、あるいはベトナムのマーケットが動きだすタイミングに合わせて、我々も出て行くことが出来たというのがひとつあると思う。また、日本で作って現地に輸出するでも、現地で作って日本に輸入するでもなく、現地でつくって現地で売ることを海外展開の柱としていたことも大きかった。また、アジアの人々が持つ価値観や生活様式が日本人のそれに大変近いと感じていたこともある。日本人が歩んだ道をアジアの人々もまた歩もうとしていることから、ニーズなどを考えたときに日本での経験が生きると思っていた。(34:16)
細かく言えば気候も色彩感覚も香りの好みなども違う訳で、やはり現地向けの仕様は不可欠になってくる。さらに言えば、我々は「成功して当然」というような立場にいた訳でなく、突然、手探りではじめたわけで、だから、たとえば人材にしても、「分からないことだらけだが現地で出会った人となんとか上手くやろう」という状態だった。そこで現地のスタッフがどれぐらいやる気になってくれるかが鍵になった。そうなると、ベースには日本での経験を生かしたいという気持ちもあったが、やはり「現地の方による“自分たちの商品で自分たちのマーケティングをしたい”という気持ちを上手に生かすべきではないか」と。そういう考えもあり、ブランドはさすがに同じだが、商品のプレゼンテーションなどは地域ごとにバラバラ。ある意味では、ワンセットで新しく会社を興すぐらいの気持ちで、現地での自由度を高めた。その結果として現地スタッフが思った以上に活躍してくれたことが、奏功したと思う。(35:33)
梅澤:公文の場合、新市場に入るときはまずパイロット展開を行っていると伺っていたのだが、その辺はどうか。(38:58)
角田:教育サービスの価値は目に見える形で表れない。従って、形の見えないものをどのように知っていただくかが大きな課題になると考えている。さらに言えば、形のある商品であればお金を出して手に入れたたとき、商品としての価値も手に入る。しかし教育サービスは違う。本当に良いと感じることが出来るのは学習を続けて力がついたときだ。要するに商品価値…、我々は学習効果と言っているが、これは最前線の現場にいる学習者と指導者のあいだにしか生まれない。これは我々にとって、ある意味では大きな可能性だが、ある意味ではやはり大変なことだと言える。(39:45)
だから新しく展開する国で学習効果を感じて貰うため、数は非常に少ないがパイロットの教室を最初につくるということにしている。そこで指導していくことにより、不易の部分は変えず、かつそれぞれの気質や文化を合わせたやり方を見つけていく。そうすると何が起きるか。そこで公文式が子どもを伸ばしていけるという成果が出てきたら、展開の決定をした我々も現地スタッフも、商品について確信を持つことが出来る。そうなると必ず公文のファンが増えてくれる。そこから、「通いたいのですが近くにないのですか?」という声に応えて、教室の数を増やしていくという形になる。(40:47)
それ以外にも、新しい地域で展開するときに我々が大事にしている考え方がある。それは創始者が残した、「悪いのは子どもではない」という考えと、そして「子どもから学ぶ」という考えだ。前者は我々にとって大きな制約であるとともに、強い気持ちで前へ進んでいける力にもなっている。たとえばなんらかの指導をした子どもが思ったように伸びなかったとき、教室も家庭も「子どもが悪い」とよく考えてしまう。しかし、「本当はそこで与えた教材の質や量に原因があるのではないか」と。だから提供者側を見直すというのが、「悪いのは子どもではない」という言葉の意味だ。一方、「子どもから学ぶ」というのはどういうことかというと、たとえば子どもを見ていると教材をすらすら解いているときと、なんだか考え込みながらやっているときでは様子が違う。そういう部分を注意深く見ながらプログラムや教材が適切なのかどうかを常に考え、ときには改定していくというのが「子どもから学ぶ」という言葉の意味になる。(41:56)
梅澤:資生堂はどうか。新しいマーケットに入っていくときのアプローチは、恐らく“シティ・コンセプト”といったものになると思うが。(43:40)
フィッシャー:世界全体ではGDP成長の60%が、世界の上位600都市で占められている。従って資生堂は海外展開において、基本的には都市という部分を軸にしている。たとえばロシアであればモスクワやサンクトペテルブルグに出店してブランドを打ち立てることで、そのブランド効果を全土に波及させていく。高級品市場ではとりわけこの戦略が有効だ。有力な空港内の免税店などに商品を展開していくことでも同様の優位性を築くことが出来ると考えている。(43:50)
「統合とダイバーシティ。ある種、二律背反するものを同時に進めながらグローバル展開をしている」(フィッシャー)
梅澤:グローバル化を進めていく上での課題はどうか。イノベーションを起こし、それを相互共有していくためのアプローチも伺っていきたい。(46:10)
角田:同じ教材と指導法でやっていることがイノベーションを可能にしている。それによって各地域でやっていること、そしてこれまで段階的にやってきたことのすべてが学びの材料になる。我々はアメリカ、そして次はブラジルという風に、これまで段階的に海外展開してきたが、そのキャリアとともに見えてきた課題は基本的にはどの国でも同様だった。そうなると、たとえば20年前に日本で認識され、かつすでに解決した問題が、今まさに別の国で出ているということにもなる。そこに過去の知恵をすぐに持っていける訳だ。そんな風にして接点が広がれば広がるほど新しい知恵や創意工夫が生まれてくるし、それを皆で学ぶことも出来るようになる。具体的には、グループ内国際会議という形式で、IT、広報、教材開発といった領域別の事例共有の場を設定している。指導者についても同じで、日常的には地域ごとに指導者同士が集まる勉強会を持ち、更に国ごとの研究大会、全世界の研究大会といった格好で、2008年には1万3000人の指導者が東京ドームに集まる事例共有会を設けた。さらに言えば、こうした営みを繰り返していくことで価値観の共有も出来る。課題解決する際の意思決定の基準を考えれば、当然、「公文式の理念とは何か」というところに必ず戻ってくるからだ。(46:51)
山田:グローバリゼーションが持つひとつの意味は、地域の壁を越えることだと思う。ただ、それ以上に重要なのが、我々を囚われの身にしている色々な壁をいかに壊すか。その分かりやすい壁が地域を越えたグローバリゼーションというだけの話なのかなと考えている。我々としてはそこでさらに一歩を踏み出して、事業領域という壁を越える、即ち製薬というか薬屋という“ムラ”を出たいと思っており、だから資生堂の領域に“お邪魔”して化粧品をやったりもしている。とにかく、大きな意味で言うとやはり日本企業は業界や慣習、あるいは伝統といったものに囚われている部分が多いので、それを越えていきたい。イノベーションというのはその殻を破る部分にあるのではないかと思っている。(50:44)
また、今日は角田さんとフィッシャーさんのお話を伺って改めて、「皆、それぞれ特色もポジションも違うのだな」と感じていたが、それで良いと思う。公文とロート製薬の共通点を探すのでなく、いかに違うかを認識すべきだ。もっと言えば、日本中の企業がそんな風にそれぞれ違う行動をとれば、素晴らしい力が発揮されるのではないか。ところが、なぜか皆が同じ行動をとる方向に行ってしまう。これだと良いときは皆良いのだが、悪いときは皆が悪くなってしまう。そうではなく、いかに他社と異なる企業になるかということについてもっと考えるべきだし、それはグローバリゼーションについても同様だと思う。外へ出ていけば何か見えてくるし、それはロートだけの話ではない。「良い商品や技術を持っている企業は多いのに、なぜもっと出ていかないのかな」と、私としては思う。国内も大事だが、ほかにもやることはたくさんある。多くの会社は意外と内部留保も技術も持っており、人材もいる。最近よく耳にする“社内失業”なんていうのをしているぐらいなら、どうしてアフリカに行かないのかなという…、まあ、せっかくの機会なので今日は、そんな主張もさせていただければ、と。(52:09)
とにかくそういう風に考えていくと、国境を越えていくのは大したイノベーションでもないと思えるが、心理的にはいまだぶ厚いバリアになってしまっているのではないか。しかしやろうと思えば出来る程度のイノベーションなのだから「もっとやりましょう」とぜひ申し上げたい。そうすることで日本の潜在力はさらに花咲いていくと思う。今年出て来年、というのはさすがに無理だけれど、5年10年もしたら、必ず咲くはずだ。(54:15)
梅澤:ここでセッションを終えても良いほどの貴重なメッセージをいただいた(会場笑)。資生堂のほうはどうか。異なる地域でブランドあるいはヘッドクォーターがグローバルに広がる組織を、どのように管理しているのか。(54:53)
フィッシャー:鍵になるのはシステムやプロセスの「統合」、そして「ダイバーシティ」だ。まず世界100カ国以上で展開しているので、特定のスタンダードとなるフォーマットによって、それぞれの市場が持つ特性データおよびP/Lを現在統合している。また、マーケットに関するナレッジを各ブランドのマネージャーで共有しているほか、世界共通のブランド管理におけるKPI(Key Performance Indicator)も定義した。それらを見ながら、各ブランドのパフォーマンスをセンターでも比較しながら管理出来るようにしたという仕組みが統合のひとつだ。そしてもうひとつ重要なのがダイバーシティ。現在、管理職の半分以上は女性だし、全世界でみると半分以上のマネジメント人材が日本人以外で占められている。我々としては現在、そういったダイバーシティの受け入れをスムーズにしていくために世界中で基幹職のローテーションも行っている。(55:20)
質疑応答
・ロート製薬は各国でかなり独立性の高い経営をさせているようだが、そのときの資本構成はどうなっているのか。現地にもかなり持たせているのだろうか。(59:42)
・たとえば中国事業部やインドネシア事業部であれば、その事業部の人間が社長に直接レポートすることで本社の組織構造もフラットになるし、取締役会の外国人比率も高まっていくと思う。この辺について皆さんのお考えは。(1:01:31)
・グローバル化が進んでいくその先について議論したい。グローバリゼーションが行き着く先々で、それでも日本企業であり続けることの意味があるのか否かを敢えて伺えれば。(1:08:40)





%20(19).png?fm=webp)



















.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)
.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)

.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)