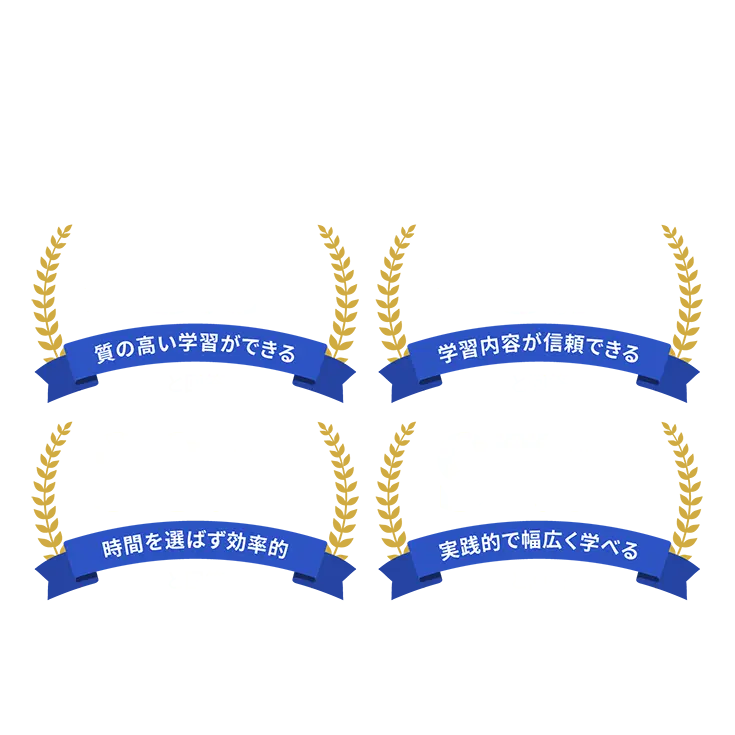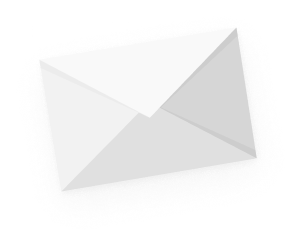OJTを機能させるためのアプローチとは?
成人の能力開発の7割以上は実際の仕事上の経験によるものだと言われるように、育成の成否の鍵はOJTにあると言ってよいだろう。かつて日本企業はOJTが得意だったと言われる。本当に部下指導のスキルが優れていたのかどうかは議論の余地があるが、少なくとも現場の上司に人を育てるマインドが旺盛だったことは事実だろう。現在でも企業組織の現場の要となるミドルリーダーの多くが、仕事を通じて人間的に成長することを重視する勤労観を持っているというのが筆者の実感値だ。人材育成を推進する上で、このマインド面でのアドバンテージを生かさない手はない。その一方で、失われた20年の間に劣化してしまった育成スキル面を強化していくことが、現実的なアプローチだろう。

部下育成スキルをインプットさせる
OJTが機能不全を起こしている原因の一つは、上司側の指導力の問題だ。何のサポートもないままに、我流で悩みながら部下の育成に当たっている管理職は少なくない。そうした上司の側に育成スキルをインプットすることは大きな助けになる。
NHKの人気番組「プロフェッショナル仕事の流儀」で、先日「育ての流儀スペシャル」という特集があった。登場したのは、一流のアスリートを鍛えるスポーツコーチ、伝統技能を伝承する宮大工の師匠、学級崩壊したクラスを立て直す小学校教員といった各分野の育成の達人だ。興味深かったのは、ダルビッシュ有や田中将大らを育てた楽天のピッチングコーチ佐藤義則氏と、北島康介をはじめオリンピック日本競泳陣を支える競泳コーチの平井伯昌氏の指導に相通じる部分があったことだ。何よりも選手の「納得」を重視する佐藤コーチは、選手の横に立ち、1球ごとによいか悪かをはっきりと伝えていく。どんなときにいい球を放れているのか、関節の動き一つひとつまで目に焼き付け、それぞれの選手のよさを伸ばすようにフォーム修正を指導する。一方、平井コーチもむやみに褒めることはせず、率直に厳しい現実を伝え、その上で選手に具体的な改善の手だてを示していく。共通するのはフィードバックが具体的なことだ。何がよくて何が悪いか、ポイントを具体的かつ簡潔に指摘している。
「支援型のリーダーシップ」の型を知る
精神的にも未熟な若手選手の指導法は、職場の若手育成にも通じる。ある企業で入社5年目までの若手社員を対象にアンケートを行い、「上司に望むことは何か」を聞いたところ、一番多かった回答が「具体的なフィードバックがほしい」だった。具体的なフィードバックをするためには、普段から上司は部下を丁寧に見ている必要がある。メンバーに適切な業務を付与し、業務遂行のプロセスをフォローし、しっかりフィードバックし、さらなるチャレンジの機会を与える。このように仕事を任せながらフィードバックを絶やさず育成を図る「支援型のリーダーシップ」の型を知っているか知らないかで、上司の育成力は大きく変わる。
業務の種類と部下のレベルに応じ、働き掛け方を変えていく方がより幅の広い場面で有効なリーダーシップを発揮できるという考え方は、「シチュエーショナル・リーダーシップ」あるいは「エンパワーメント・リーダーシップ」として日本でも名前は知られている。しかし、企業内で管理職がマスターしている度合いは濃淡があるのが実態だろう。我流で部下に命令し、やらせっぱなしにしたまま結果オーライとしている例も少なくない。欧米のグローバル企業のリーダーたちの中で、こうした技を駆使してチームマネジメントするのが常識になっているのとは対照的だ。エンパワーメント・リーダーシップ、コーチング、ファシリテーション等は、ミドルマネージャーの必須スキルとしてインプットしておいて損はない。
■経験機会を効果的に付与する
OJTを機能させるためにもう一つ大切なのは、「どんな経験をどんな順番で付与するか」という視点だ。かつて右肩上がりの成長の時代、経験を積む機会が豊富にあったことはOJTを行いやすくしていた大きな要因だった。しかし、必ずしもそうしたチャレンジの機会が十分にあるわけではない現在では、限られた経験をいかに成長につなげていけるかが問われる。この時に大切なのは、いかに達成実感を伴いながら経験の階段を上っていけるかだ。心理学の研究では、自己効力感(やればできると思えること)が高いほど学習効果が上がると言われている。同じことを、『「日本で最も人材を育成する会社」のテキスト』(光文社新書)の著者・酒井穣氏は、「勝ちぐせをつける」と言っている。いきなり難易度の高いエベレストに登るようなまねをするのではなく、比較的小さな登りやすい山から始め、山を登りきる喜び(成功体験)を積み重ねられるよう業務付与の仕方を工夫せよということだ。
「勝ちぐせをつける」ために、より具体的に推奨しているのが「バックワード・チェイニング」という考え方だ。業務の流れを鎖の連結(チェイニング)に見立て、その連鎖の中のどの部分をどんな順番で経験するとより「勝ちぐせ」がつきやすいかを意識して業務付与していく。例えば、研修会社の営業の仕事の場合、「1. 顧客とのアポ取り」「2. 自社の説明 」「3. リードの獲得」「4. 社内関係者と企画立案」「5. 顧客への提案」「6. クロージング」「7. 詳細計画の詰め」「8. 契約書面取り交わし」といった行動の流れが考えられる。これを1から順番に業務の流れに沿って行動を連結させていくのが、「フォワード・チェイニング」だ。経験の乏しい若手の営業マンにとって、「1. 顧客とのアポ取り」から「3. リードの獲得」に至るフェーズは相当ハードルが高いので、数多くの失敗を乗り越えながらの成長を強いられることになる。それに対し、8から業務の流れと逆に連結させていくことを「バックワード・チェイニング」と呼ぶ。1から7はベテランの先輩が進め、8の契約手続きだけを若手に任せると、最後のゴールでの達成感を味わうことができる。次は7と8を、その次は6、7、8というように任せていく領域を広げていくことで、常に「最後までやり抜いた」達成感を伴った経験を繰り返せるのが「バックワード・チェイニング」のポイントだ。
重要なのは、意図を持って「経験をデザインする」スタンスを取ることにある。これまでのOJTは、いわば「ランダム・チェイニング」とでも呼べそうな現場の成り行き任せの状態だったのではないだろうか。限られた経験の機会で育成の歩留まりを上げていくためには、個々のメンバーそれぞれについて、どのタイミングで、どんな順番で、どんな経験を踏んでいくのがよいか、丁寧に「経験をデザインする」ことが肝要だ。
■「教えるべきこと」と「学びに委ねること」の切り分け
OJTに関しもう一つの重要な視点は、「何を教えるか」ということだ。業務上必要な知識や技術といった表面的なものから、具体的な業務の手順、関係者との調整方法、さらにその底流にある仕事へのこだわり、価値観、DNAといった深層レベルまでさまざまなものが含まれる。表面的なものは環境変化に伴って変わっていくのが必然であり、教える側の持っている知見は時間がたつにつれ陳腐化してしまう宿命にある。逆に言えば、こうした部分は教えるのではなく、最も高い感度で最前線にいる本人が自ら学び取れるような環境を整えることのほうが必要な支援と言えよう。
一方で「教えるべき」なのは、自社ならではの仕事の仕方、そのベースにある仕事へのこだわり、価値観のほうだろう。これはマニュアル的に伝えられるものではなく、共通体験やエピソードなどを通じて共有される暗黙知だ。伝える場面もさまざまだ。フォーマルな会議よりも、インフォーマルな飲み会で披露される武勇伝に込められることもある。
ただし、どんな場面でも教える側の「伝えたい」という意志が不可欠だ。「人事部門主導の画一的な育成」から、「現場主導で個々に応じた学習の促進」という大きな流れがある中で、企業として「教えるべきこと」と個々人が「学び取ること」を峻別しておくことが必要だ。「ダイバーシティ・マネジメト」でも触れたとおり、その企業として「譲れないこだわり」が明確にあってこそ、それ以外の「多様性」を尊重できるからだ。
※労政時報に掲載された内容をGLOBIS知見録の読者向けに再掲載したものです。