
0:59:48
割引情報をチェック!

AI BUSINESS SHIFT 第8回 機能別戦略編:AI時代の営業現場のリアル
本コースは、リーダー・マネージャー層を対象に、AIのマネジメント活用・組織活用を体系的に学ぶ『AI BUSINESS SHIFTシリーズ(全12回)』の第8回です。 第8回「機能別戦略編:AI時代の営業現場のリアル」では、AIが営業現場にどのような変化をもたらしているのか、営業担当者・営業マネージャー・組織としての役割や戦略が、AIによってどう進化していくのかを、営業プロセスの分解や実際の現場事例を通じて学びます。 ■こんな方におすすめ ・AIを活用した営業活動の最新動向や現場のリアルを知りたい方 ・営業現場の変化に直面している営業マネージャー・現場リーダーの方 ・AI時代における営業戦略や営業マネジメントのあり方を学びたい方 ■AIシフトシリーズとは? 『AI BUSINESS SHIFTシリーズ』は以下の3部構成で設計された全12回のシリーズです。(順次公開) https://unlimited.globis.co.jp/ja/tags/AI%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E3%82%B7%E3%83%95%E3%83%88 ・基礎編(第1回〜3回):リーダーやマネージャーに求められる、AI時代の基礎的なリテラシーの強化を目的としたコース ・マネジメント編(第4回〜7回):AI時代のリーダーシップや組織変革を中心に学ぶコース ・機能別戦略編(第8回〜12回):AI時代における機能別での戦略のあり方を中心に学ぶコース より実践的なAIツールの活用法について学びたい方は『AI WORK SHIFTシリーズ』をご視聴ください。 https://unlimited.globis.co.jp/ja/search?tag=AI%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%95%E3%83%88 ※本コースは、AIのマネジメント活用を学ぶ「AIビジネスシフト」シリーズの一環として提供しています。 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2026年2月制作)
会員限定

マネジャーのための仕事の任せ方
「仕事を任せると失敗が怖い」「自分でやった方が早い」マネージャーとしてメンバーやチームの力を引き出しながら成果を上げるには、どのように仕事を任せていけば良いのでしょうか? 変化の激しい時代において、マネージャーとして成果を上げ続けるためには、メンバーの個性や特性を理解し、それに合わせた効果的な任せ方を身につけることが重要です。このコースでは、ソーシャルスタイル理論を活用してメンバーごとに最適なアプローチを学びます。「任せる力」を高めることで、チーム全体の成長を促進し、自身のリーダーシップを発揮できるようになっていきます。 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2024年12月制作)
会員限定

AI時代の個人力
AIが仕事や社会の前提を変え続ける今、最も求められるのは「他者に代替されない個としての力」“個人力”です。 本コースでは、澤円氏の著書『個人力』をもとに、AI時代をしなやかに生き抜くための「前向きな自己中戦略」を学びます。 テーマは、「Being(ありたい自分)」を中心に据え、自ら考え(Think)、変化し(Transform)、協働する(Collaborate)ことで、自分らしい価値を発揮していくこと。 リスキリングやAI活用が叫ばれる今こそ、スキルより先に“自分の軸”を問うことが重要です。 あなたは何を大切にし、どんな未来を描きたいのか? このコースは、あなたが“ありたい自分”として生き、キャリアをデザインしていくための思考と行動のガイドになります。 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2025年11月制作)
会員限定
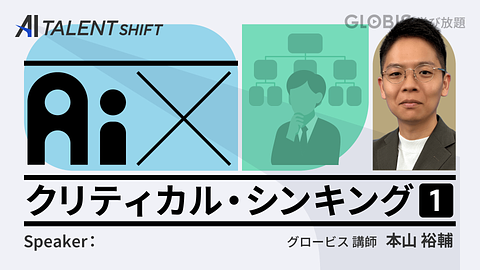
【AI×クリティカル・シンキング】①イシューと枠組みでプロンプトを磨く
生成AIから期待する回答を引き出せず、試行錯誤を重ねていませんか。 本コースでは、生成AI活用の質を高める鍵として、クリティカル・シンキングの視点からイシュー設定と枠組みを押さえる重要性を解説します。 目的に直結する問いの立て方や、プロンプトに落とし込む際の実践ポイントを具体例とともに学ぶことで、AIをより思考のパートナーとして活用できるようになります。 生成AIを業務で使い始めた方から、活用を一段深めたい方まで、再現性あるプロンプト設計を身につけたい方におすすめの内容です。 さらに学びを深めたい方は、こちらも合わせてご覧ください。 【AI×クリティカル・シンキング】②AIの弱点との向き合い方 https://unlimited.globis.co.jp/ja/courses/cdfe41e3/learn/steps/62198 ※本コースは、AI時代のビジネススキルを学ぶ「AIタレントシフト」シリーズの一環として提供しています。 https://unlimited.globis.co.jp/ja/tags/AI%E3%82%BF%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%B7%E3%83%95%E3%83%88 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2026年1月制作)
会員限定

リーダーの挑戦⑤ 藤田晋氏(サイバーエージェント代表取締役)
グロービス経営大学院学長の堀義人が、日本を代表するビジネスリーダーに5つの質問(能力開発/挑戦/試練/仲間/志)を投げかけ、その人生哲学を解き明かします。第5回目のゲストは、サイバーエージェント代表取締役の藤田晋氏。起業の理由、経営をどうやって学んだか、アメーバブログ・ABEMAの立ち上げ、経営チームづくりについてなど聞いていきます。(肩書きは2020年12月11日撮影当時のもの) 藤田 晋 サイバーエージェント 代表取締役 堀 義人 グロービス経営大学院 学長 グロービス・キャピタル・パートナーズ 代表パートナー
会員限定

ビジネスパーソンのための睡眠スキル ~問題解決編 前編 なぜ眠れないのか?~
「仕事が終わらないから睡眠時間を少し削ろう…」「業務時間中なかなか集中できない…」「毎日朝起きるのがつらい…」。 あなたはこのような経験をしたことはありませんか? 仕事やプライベートの時間をやりくりするために、真っ先に削りがちなのが「睡眠」時間。 実は今、日本社会は世界と比較して「最も眠らない国」だということもわかってきています。 慢性的な睡眠不足は、心身の健康に悪影響なだけでなく、仕事のパフォーマンスにも当然大きな影響を与え、社会全体の経済損失につながります。 このコースでは、基本的な睡眠リテラシーを学んだ後の「問題解決編」として、「なぜ多くのビジネスパーソンは眠れないのか?」について解説していきます。 ▼本コースで学べる主な内容 ・そもそも眠れないことは何が問題なのか? ・眠れなくなってしまう原因とは? 睡眠不足の原因は認知機能の問題にありました。 自身の睡眠不足に対し、正しく「気づき・理解し・行動を変える」第一歩を踏み出しましょう。 ▼関連コース ・ビジネスパーソンのための睡眠スキル ~リテラシー編~ https://unlimited.globis.co.jp/ja/courses/24575c03/learn/steps/53129 ・ビジネスパーソンのための睡眠スキル ~問題解決編 後編 どうしたら眠れるのか?~ https://unlimited.globis.co.jp/ja/courses/4ba981e9/learn/steps/62042 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2025年12月制作)
会員限定

大阿闍梨 塩沼亮潤が死の手前で見つけた「生き方」
あすか会議2018 第4部分科会B-1「極限の世界で見つけた人生の歩み方」 (2018年7月7日開催/国立京都国際会館) 1300年間で2人目となる大峯千日回峰行満行を果たした塩沼亮潤大阿闍梨。48キロの山道を1日16時間掛けて歩き、それを千日間に亘って続ける過酷な行の中で、どのような悟りを得たのか。そして、9日間、断食・断水・不眠・不臥を続ける四無行満行という極限の世界で何を見つけたのか。塩沼氏が「創造と変革の志士」へ贈る「人生の歩み方」とは。(肩書きは2018年7月7日登壇当時のもの) 塩沼 亮潤 慈眼寺 住職
無料
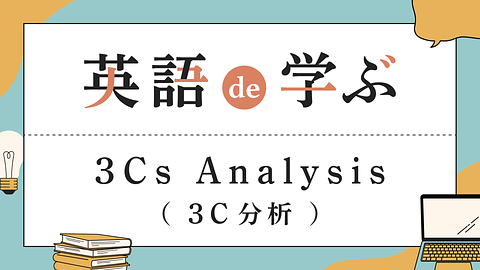
英語 de 学ぶ!3Cs Analysis(3C分析)
このコースでは、グロービス学び放題の英語版である『GLOBIS Unlimited』のコースの中から、ビジネスで役立つ頻出の英語表現をピックアップしています。英語ネイティブの方が実際に見ているコースなので、リアルなビジネス英語の表現を学ぶことができます。 今回のコースは「3Cs Analysis(3C分析)」です。一緒に『英語で』ビジネス知識を学んでいきましょう! ▼今回扱ったUnlimitedコース続きは下記からご覧いただけます 3Cs Analysis https://unlimited.globis.co.jp/en/courses/da5ca962/learn/steps/36362 ※本動画は、制作時点の情報に基づき作成したものです(2025年12月制作)
会員限定
より理解を深め、他のユーザーとつながりましょう。
コメント5643件
keiko_biz
上司が、まったく真逆の1 on 1をするので困っています。来月までにこれができるようになれと一方的に押し付けられ、私のダメなのところ、できなかなったこと、反省点のリストを聞かされる苦痛の1時間になっています。日々の業務でも、できていないと見つけ出して注意され、生きた心地がしません。評価に響くのではと気になって思いきった行動はできなくなりました。当然、モチベーションは下がります。このままではお互いに時間を無駄にしているだけなので、違う方法を一緒に検討しませんか?と持ち掛けましたが却下されました。傾聴、共感、承認は、部下を持つ人が身につけるべきスキルなのだと実感しています。
zac51
4月から在宅勤務に移行し、コミュニケーションの機会が減ったことから週1回の1on1ミーティングを継続実施しています。本講座の内容は抑えておりましたが、つい自分の話をしたくなる衝動に駆られる事があるので、意識してコーチング・傾聴を心がけて続けていきたいと思います。
講座にもありましたが部下の成長を支援する事が目的であるため、今年度のキャリアプランを話題の1つに掲げて実施しています。常に相手の言葉に耳を傾け、自分の経験などはわずかな参考情報としつつ、部下が自ら答えを導き出せるよう、黒子となり相互成長を狙っていきます!
wkiymbk
思えば、昭和・平成前期は飲みニケーション・喫煙室でこういうことをやっていたのではないでしょうか。
業務時間内に、ちゃんとした仕事として素面でやるようになったことは素晴らしいと思います。
ただ、いきなり「さぁ話せ」では面喰います。
コミュニケーションスキル研修をセットでやる必要があるのでは、と思います。
ryoma_sakamoto
部下側にも、1on1のねらいや期待効果を理解してもらい、この時間を有効活用しようと意識してもらうことが大切だと思う。
両者が目的意識をもって実施すれば、部下の成長に大変役に立つと思う。
sarah1207
基本週1で上司とおこなっていますが、業務の進捗報告にほぼなっています。上司から話を広げることもないため本来の目的とはかなりずれている気もするし、正直ストレスです。
noyo1
採用してほしい。飲み会不要。
nobonobo17
テレーワークになって、部下との時間が必要と感じてミーティングを実施していたが、自分が話しすぎていた気づきになった。
gojiro
自社では年2回、半期ごとの評価について機会を設けてます。Yahooの週1回の頻度に驚きました。実際にどういう対話をして、どういう成果があがっているのか知りたい。
naka_09
1on1は、始めることがまずは大事。ただそのままバラバラで進めるのではなく、社内で進め方を共有し、標準化・進化させていくことが必要と感じます。
takechansan
1on1は上司もスキルを身に着けないと、間違った1on1になりがちだと思いました。
rakado
「部下が活躍する舞台をつくるのが上司の仕事である」という言葉に同感です。1on1では、部下に関心を寄せて、成長(部下にとってのメリット)を促すことで、部下を動かすということだと理解しました。
keisuke0614
上司の対話スキルがないとそもそもやる効果が、極めて薄くなる。
tomousa
私のチームでは月1回1時間を定期予定として確保しています。
時間は確保しているのでその時間をどれだけ部下の成長、モチベーションupに繋げられるか、
リーダー側の責任、スキルはとても重要だと思いました。
特に成長が思わしくない部下こそ、1on1を活用したモチベーションupが有効だと気付きました。
1番身近な応援団の位置付けになれるように取り組んでいこうと思います。
hiro_yoshioka
1on1 推します。上司と部下以外でも信頼構築のために意図的に活用したい。
単に雑談するのではなく、双方とも1on1をする 目的を意識することが大事ですね。
部下は、承認欲求が満たされ、やる気が高まり、
上司はコーチングの練習になってよいと思いました。
実際にやるには、時間の課題はあるので、適度に取り入れるのがよいと思います。
comedo_0930
部下の立場で視聴したが、こちらから投げかけるテーマが見つかったような気がする。
hayase_tomoharu
メンバーとの信頼関係を気付くために、1on1を活用したいと思った。
今年度から、新たなミッションを持つ組織を任されており、かつ、メンバーがこれまであまり接点がなかった方々なので、まずは相互理解し、その上で、モチベーションを高められるように働きかけていきたいと思う。
kuta_41
実際のミーティングにおいて、理想と現実が違う可能性があると私は思いました。
kzhr2358301
メンバーが考えていることを理解するためにも定期的に行うことが必要だと思っています。
メンバーの中には自分を知ってほしいとは思っていないメンバーもいるので丁寧に説明して実施したく思いました。
masarukanno
上司の役割の大切さをあらためて学べました。
k-man
テレワークを導入した組織では、どうすれば生産性を高めることができるかを解決することが課題の一つである。すべての人が自立的に行動し結果を残すという性善説を前提とした場合、高い確率で運用するためには仕掛けがいると思う。それが、1on1なのかもしれないと感じた。実践してみたい。
aqueous
1on1はビジネスだけでなく、普段のコミュニケーションにもいかせることだと思った。
mihoshimada_123
どうしても「効果的な問いとは?」「テーマは?」と、なりがちなところですが、まずは「聞くこと」からはじまると考えます。他人の話に耳を傾けて、うけとめるように聞くことは、一見簡単そうにみえて、実はだれもトレーニングを受けたことがないのではないでしょうか。また、聞き方に対してフィードバックをすること、フィードバックされることも、めったにありません(話し方にはあっても)
「聞く」ということは、まず立派なスキルであると認識し、練習や実践をしながら、少しずつでもこの「聞くレベル」みんなで上げていこうと思います。
hashitak
1on1をより有効に活用するためには、日ごろの信頼関係が必要であることが分かった。一方、ソリが合わない人同士はどう対処すれば良いのだろう?という悩みはある。
s_s___
話を聞いてくれ、フォローしてくれる上司だったら、部下も頑張るでしょうね。
実際は、できないことを指摘し叱るだけの上司や、報告や連絡だけの上司や、やる気アピールのためにその場で決意表明する様に誘導したりする上司がほとんどでは?
たいていの部下は、すでにそこそこ活躍している場合、さらなる活躍を要求され、十分に回ってるからいいでしょ?とは言えないでしょうし。こうしたいこうなりたいと言ったところで、自力で実現させろなだけで、実現できる様にフォローしてくれる上司なんてそうそういない。
だから、上司に本音は言わずしれっと退職したり、言われたことだけやる様になるのがほとんどでは?
rie0114
採り入れる企業も増えよく聞くワードになってきましたが、効果があるのかどうかは正直微妙なところでしょう。
上司の傾聴力次第。
takuya-koi
既に対応中です。参考にします
crystalucas1110
全ては部下の成長のためにという基本スタンスを忘れないようにする。
sealegend
部下の立場でも1on1の意味合いをきちんと理解して活用したいと思います。
hkoke
形だけ取り入れるのではなく、ここで述べられているような1on1を導入する意義を理解した上での適切なアプローチが必要。ただ、マンネリ化したり慣れてくると原点を忘れないような意思が難しいかもしれない。
marimon1105
働き方の多様化、部下のモチベーションアップへの対応、成長を促すなど、結局は上司と部下の間の信頼関係が大事なのだと思う。
話す内容を間違う、やり方を間違うとこじれてしまいそうですが、上手にこのシステムを活用できれば、チーム全体の雰囲気も良くなりモチベーションアップにつながると感じました。
tak-9710
1on1ミーティングは、上司の考えをさらに強く伝えてしまう誤ったやり方にもなり兼ねないので十分注意する必要があると感じました。
como23
上司から部下への伝達の場ではないことを強く理解し、部下のサポートの場だと考えて1on1を行うことを心掛けようと強く感じた。
gantetsu
リモートワークで部下の様子が見えないので、活用を検討したい
yosi_
1one1 を実施する為に必要なスキルを持ち
部下がミーティングを必要と思える位にする必要がある
kameco
所属部署では全く機能していないのは何故かを考えます。
saito-yoshitaka
日常で気にしていなかった内容でも 部下からの意見を引き出す可能性が出てくる。
satopon1
組織の生産性の向上、部下の能力・スキルアップ、上司・部下間の信頼関係の構築などのためにも、上司と部下が定期的に対話を行う必要性があることを理解しました。
kaki_077
対話が極端に少ない部署もあるので、制度としての1on1を推進していきたいと思いました。
harunosuke
より良い1on1になるように、創意工夫をしていきたいと思います。
mei_papa
大変
参考になりました。
maruka0094
常に上司、部下共に意見を言い合いお互いの考え等を理解することによりより良い職場環境が構築され仕事の効率化に繋がる。
a_momoka
1オン1とは何なのか?と思いながら受けていました。(部下として)
部署が変わった際には、1オン1をするとき、改めて目的の共有をした方が良いと思いました。
s-bm
1on1ミーティングの手法をこれからも活用しようと思います!
gotou_daisuke
部下とのコミュニケーションの一つとして1on1を取り入れることによって、より良い理解が得られると考えさせられました。
yusuketoda
モチベーション向上は大切であると思われる
k-toru
上司だけではなく、部下も1on1の意義を理解したうえで取り組むとより効果的になると思う。
takumi3331
チーム内でも実施してみようと感じた。
tomo-tom
効果的に出来ればよいが、開催側が意図を間違えて実施するとただの説教時間になって本末転倒となる。そんな事例が社内に蔓延しています。
shishima
すでに1on1は全社的に導入され、その目的や留意点については理解をしているので復習になった。成長段階にある若手社員や異動したての社員には1on1の実施頻度を高めて、信頼関係の構築や成長支援のために積極的に話を傾聴して本人の気づきを引き出す問を発していきたい。ベテラン層については実施頻度は多くなくてもよい方が多いので、1・2か月に1回程度、健康状態や職場の課題についてベテラン層として気になっている点を質問する場として活用したい。
inada-makoto
体験はしたことはないが、モチベーション低下の理由が退職を考えているなど、最悪を想定して挑むようにしたい
自分が心を開かないと相手も開かないので話題を考える
初回は自分もそうだが相手も身構えるため、継続して信頼感を得ることが大事
相手により話す内容を変えることが出来るぐらいのコミュニケーションスキルを日ごろの業務で身に着けるようにする
7291
部下からの立場でしたが上長視点も知ることができて、1on1ミーティングに対する考え方を学べた
moririn-yukirin
1on1は傾聴を主体とし、相手の想いを聴ききる事から始まると思う。伝える事よりも、相手の話を共感的に聴き、その上で相手の関心事に関心を寄せつつ関わっていきたい。
t_iino
1on1をどのように行うかも重要だと感じる。個室でやることで堅苦しさを感じる人もいれば、個室でやることを好む人もいる。相手の希望を極力くみとりながら、バランスを意識した対応を心がけたい。
tosan103
上司側は日頃からの行動や言動に注意が必要 !! 『この人に聞いて貰っても』と部下から思われている場合はやる意味がない。
emori415
会社が変わらないと何も意味を持たない。
本当に実施されているのかなど、意味があったのかなどを追跡して欲しい。
fukumura25
<部下の成長支援とスキルアップ
キャリアプランの相談: 部下の長期的なキャリア目標や、現在興味を持っている分野について話し合います。上司は、その目標達成に必要なスキルや経験を特定し、具体的な学習機会やプロジェクト参加を提案できます。例えば、「〇〇さんの目指すリーダー像に近づくために、まずはこのプロジェクトで〇〇のスキルを強化するのはどうでしょう?」といった対話が考えられます。
強みの特定と育成: 部下が自身の強みを認識し、それを業務でどう活かしていくかを話し合います。上司は、部下の隠れた才能や潜在能力を発見し、それを伸ばすための具体的な機会を提供できます。例えば、「〇〇さんは分析力に長けているから、次の市場調査プロジェクトではデータ分析のリードをお願いできないかな?」といった形で、具体的な業務と結びつけられます。
課題克服とフィードバック: 部下が直面している業務上の課題や、スキル面での改善点について話し合います。上司は、建設的なフィードバックを提供し、具体的な改善策を一緒に検討します。例えば、「この資料のロジックは素晴らしいけど、もう少しターゲット層に合わせた言葉遣いを意識すると、もっと伝わりやすくなるよ」といった具体的なアドバイスが可能です。
tsuyoshi_ueoka
業務を任せきりでなくフォローすることで仕事がやりやすくなる
mikami0121
部下が話したいことを決めるといっても迷いや心配があると思われ、上司から何か話題を振らざるを得ない。そうするといきなり具体的な業務の進捗を聞いてしまうということになりがち。上司がさまざまな話題を提供することが大事と思う。
noga-
業務に関する報連相とは別枠で時間を確保することの大切さを感じた。
tokumaruo
1on1を取り入れる準備として傾聴スキルやそもそも1on1をきちんと理解することから
始めたい
s_n_0726
定期的な1on1を実施することで、リモート環境下でもメンバーのメンタル面などのサポートができるようになりたい。
sayuchi
このミーティングは業務において必要と感じました。離職率を低減させることにも有効だと思います
tamurahidehiko
人事評価のギャップを埋めるための手段として活用したいと考えています。信頼関係の構築は生産性やモチベーションを高める上で重要であり、1on1ミーティングを定期的におこなえる環境づくりからスタートします
principe_ny
現状、自部署では導入はしていないが、状況に応じて、部下の話を聞く機会として実施した際に、基本的な考え方や進め方を知ることができた。つい自分の考えや話をしてしまいがちなので、部下の考えを引き出すべく、傾聴とコーチングの姿勢を常に意識したいと思います。
o-kataoka
1on1を引き続き行い、部下のモチベーションを高めれるようしたい。
また、部下との信頼関係をしっかり築いてチームの生産性を高めたい。
lc_saito
1on1ミーティングでダメ出しをしてしまう機会が何度かあったので、より深く意見を傾聴しようと思います。
bluesky_tr2002
自身のパフォーマンスアップの為に、上司以外にも聞いてもらいたいと思った。
a_ak
部下のモチベーションアップのため、個別の事を話す。
kn_tm
〇積極的な声掛け、コミュニケーションをとることを意識的に図っていきたい。
takesheest
部下の生産性向上を図るため、相手の心理や健康面での状況把握と、コミュニケーション向上のために有効な手段であると理解した。
ccudjr
日々行っている1on1の目的、メリットを再認識できた より効果的な1on1を実施できるよう活かしたい
kzstn
上司側のコーチングスキルが重要だと感じました。上司による工程管理の場となり下がらず、成長志向で時間を使うことが大切だと思います。
taiga_fujiwara
経営層から意識改革を行う事が大切と思った。
noxalvelt
1on1をどのように実施するか、する意味があるかは再度検討が必要と考える。
shura1975
部下との1on1時の雰囲気づくりに注意したいと思う。
私は業務などにおいて、厳しいというイメージをもたれているので、まずはリラックスして話ができる雰囲気づくりを行おうと思う。
1-3-7
社員が話しやすい環境作りや自身の表情を心掛け、多様な働き方に対応できるよう信頼関係を築いていきたい。
baseball_boy
部下が上司に積極的に話せる状態を構築するのは、職場の環境やルール整備、意識の共有を職場単位で解決することができ働きやすい環境だけではなく業績向上効果につながることを学びました。私の職場は、定型業務が主となっているので不満など我慢することで業務は成り立ちますが組織力向上がなかなか図れません。このことはモチベーションが上がらない原因となりますので1on1を通じ組織力向上に生かしていきたい。定型業務が多いことはマンネリ化しやすい環境といえますので頻度等にも気をつかいながら進めていきたいと思います。
masaomi-s
部下の成長のために行うという目的を理解して取り組むことが大事だと改めて認識することができた。
kawakami4
1 on 1についてこれまでに認識していた内容と大きな違いはなく、目的や取り組む姿勢を再認識する機会となった。
ただし、実際に行うのは簡単ではなく、経験を積み重ねたりノウハウを学習する必要があると感じている。
itomasa57
1on1の導入おいては、Yahooの事例の通り、事前準備がまずは重要と考えます。
会社全体の認識を合わせることから始める。
そして、導入以前の観点として、上司の役割は部下を育てること。人材育成が大きな役割であることを理解してもらうことが重要。
人への興味関心、寄り添いを大事にして日頃からの部下に対する伴走を心掛けるような社風を築き上げていければと思います。
ashken
メンバーと1対1で話をする機会はよくありますが、話しを最後まで聞けないこともあるので、気を付けようと思います。
1257822
まずは1on1を始めて見て部下と1対1で話してみることが大事だと思った。
miyagi1216
仕事は1人では出来ない,周りの協力があって成立する。普段からのコミュニケーションが大事。人間関係及び仕事が円滑で出来るよう,1on1を上手く活用したい。
---hide---
on1は、まず始めること。話過ぎないこと。共感すること。
kei-hori
定期的に1on1ミーティングを実施する様に心掛けたい。その際は部下の管理ではなく、支援の場という事を忘れずに取り組む
yujim1211
余りプライベートすぎる対話も、多様な価値観の時代に何が地雷になるかわからない。かといって仕事の話が中心になると、部下が身構えてします。バランスが本当に難しい。
mochizukiyusuke
上司から質問をしたり、会社の方針を一方的に伝えるのではなく、まずは部下の意見を最後まで聞く機会だということを学ぶことができました。「特に話す話題がない」と言う部下についても、話しやすい空気や話題作りを心がけることでコミュニケーションをしっかりとりたいと思いました。
kykjbn-2525
1on1は導入していたが、部下の話を最後まで聴く、話しやすい環境を作る、といったことはできていなかった。部下の話を徹底して聞くことを意識し、モチベーションアップ、方針の共有、成長支援の場としたい。
tadaharu
1on1により上司との信頼性が築け、部下とのコニュニケーションが構築される。日常では、妻との会話を聞くのと同じ考えで、その日にあった出来事や悩んでいる事を真摯に受け止める。自分の意見は、言わずに最後まで話を聞くように心掛けること。と同様に考え、例えば、家族の体調不良により早退する可能性があることを伝えたり、後輩とのコミュニケーションが上手くいかないのでどうしたらいいのか相談したり、職場にいてもいつも孤立しているような気がしている等、心身的な悩みや家庭環境の状況を話す事により少しでも解決策が見出されれば良いと思う。
marigoto
1on1の目的を再認識しました。定期的に実施するようします。
nanamioki
上司への相談だけでなく、信頼関係を築く場として利用して良いことが判った。
pupula
1on1を行うことで、部下の考え方や困っていることを聞き、よりよい方向に成長するための助けになればと思う。
takanoma91
部下側にも、1on1のねらいや期待効果を理解してもらい、この時間を有効活用しようと意識してもらうことが大切だと思う。
両者が目的意識をもって実施すれば、部下の成長に大変役に立つと思う。
kou_ko
説明内容が、1on1を行えばメンバーがやる気を出す、問いトーンで構成されている。本来は、どこに違和感を持っているかや、長期間気になっている事、最近初めて見たこと、などから、当人の経験や知識を整理し、特性や才能を自覚するところにつなげなければいけない。
このイメージでは、1on1と上司部下でやっても、効果が出ず、時間の無駄になりかねない。
後は個別に考える、というものでもない。
章区切って詳しく解説する構成が望ましい。
mamo1227
1on1は使分けが必要,傾聴のスキルが大事,ついつい上司が話し込んではダメ
n_sakamoto216
部下とのコミュニケーションは非常に大事と考えているので部下と二人きりになったら、意識して声掛けを心掛けている。
tgnw9774
上司は、1on1の進行を重視しようとしてしゃべりすぎない。
hasobe
私自身も上司が話しやすい環境を作っていきたいと考えた。
atsuchi_tg
1on1を実施する意味を説明できるようになる
yasuhiro-nukaga
正しく運用出来れば効果がある
形だけ整っていても部下の説教部屋になっては逆効果
上司の資質が問われる